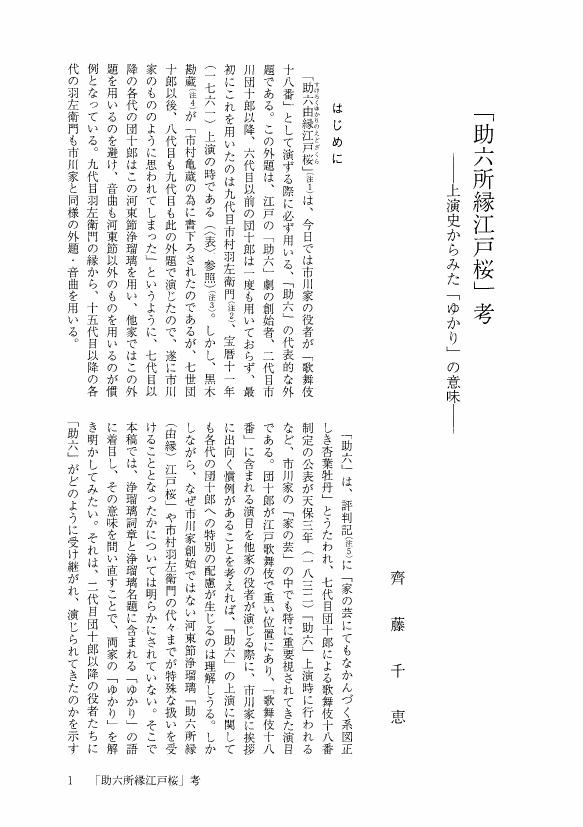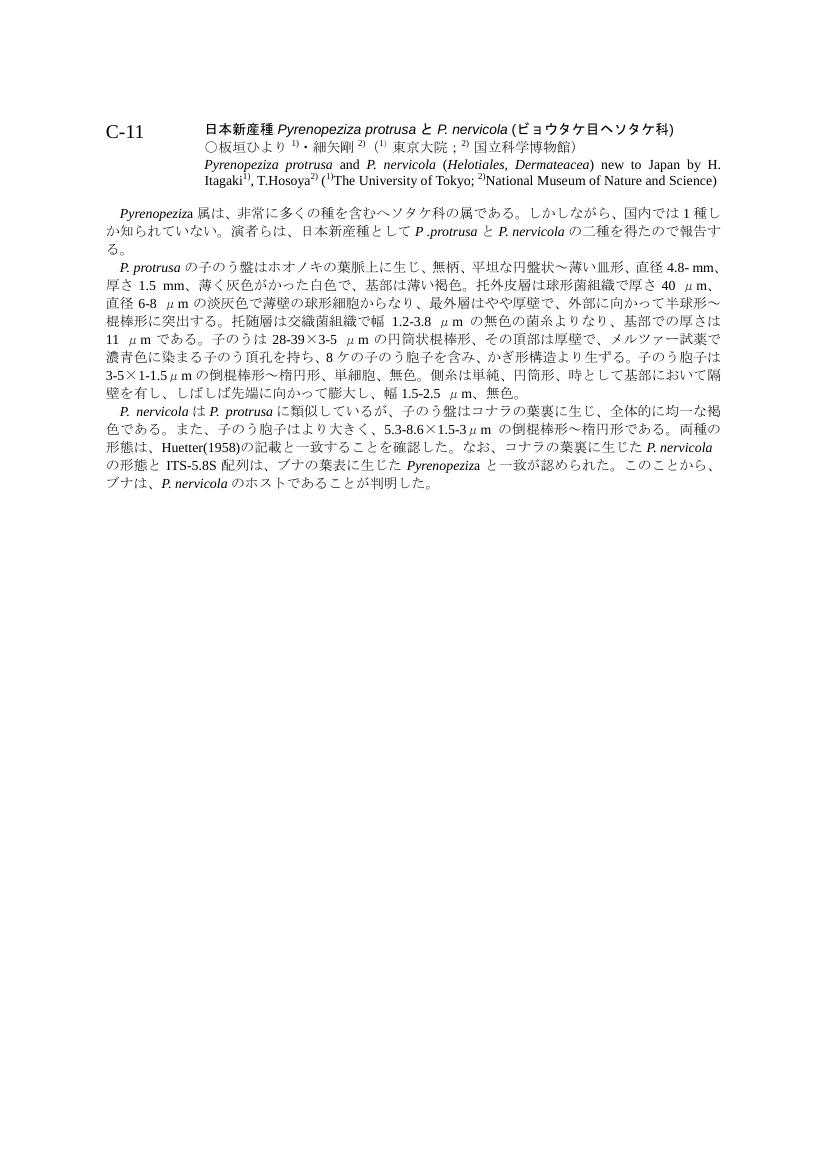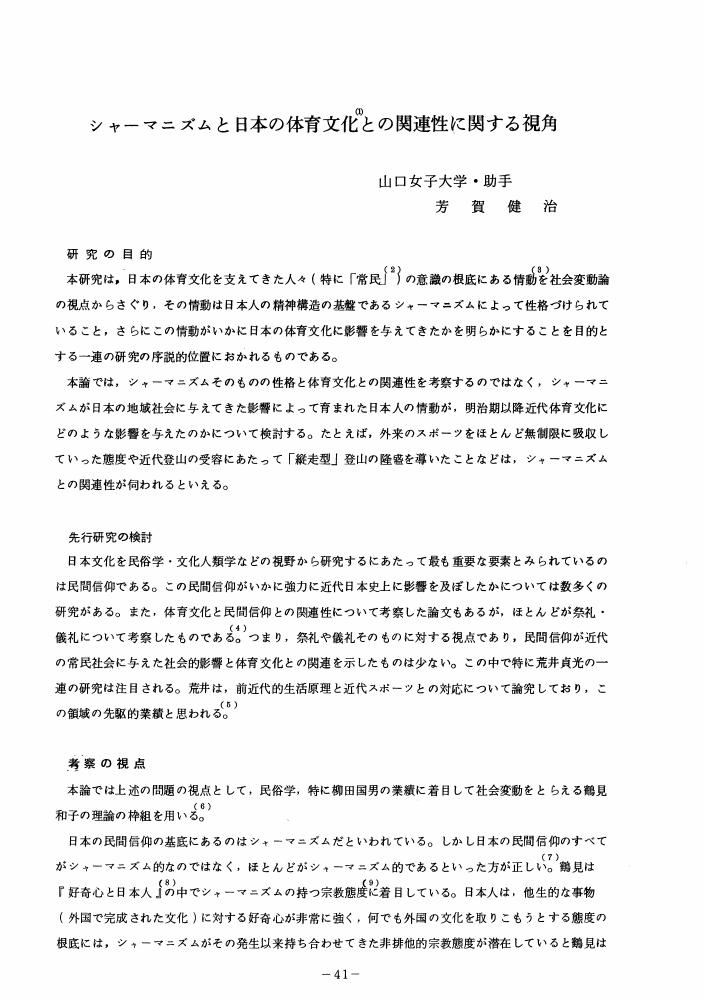1 0 0 0 OA 内頚静脈直接穿刺法によって長期間血液透析を継続した1例
- 著者
- 三宅 範明 宮本 忠幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.114, 2007 (Released:2007-12-01)
<緒言> 慢性血液透析を実施するにはバスキュラーアクセス(VA)が不可欠である。標準的内シャント(橈骨動脈-橈側 皮静脈間の皮下動静脈瘻)作製が自己血管の荒廃のため困難な症例が増加している。そのような症例では人工血管の使用、動脈表在化などによりVAを確保するという方法もある。しかし、いずれの方法でもVAを作製し得ない場合には血流量の多い静脈を毎回、直接穿刺する方法が選択される症例が出て来る。大腿静脈を直接穿刺する報告は散見されるが内頚静脈の直接穿刺の報告は少ない。今回我々は内頚静脈を直接穿刺し長期間血液透析を実施した症例を経験したので報告する。 <症例提示>: 症例: 80歳、女性 現病歴; 2000年3月、多発生嚢胞腎に起因する腎機能低下のため近医より紹介となる。同年11月21日、左手関節近傍で内シャント作製するもシャント血管の成長は不良であった。2001年4月10日、血液透析開始(BUN109,Cr 8.02)したが数日で内シャント閉塞のため4月18日に右手関節近傍で内シャント再建術を実施した。この内シャントは同年8月まで使用可能であったがシャント血管の狭窄、血流低下を生じ閉塞に至った。この時期より右内頚静脈の直接穿刺を開始した。以後、両側肘関節部、上腕部での自己血管による内シャント再建術、人工血管植え込み術、動脈表在化など(合計6回の手術)行ったがいずれも長期間はVAとして機能しなかった。2004年6月より左肘関節部での上腕動脈直接穿刺法と内頚静脈直接穿刺法を併用したが2006年10月からは内頚静脈直接穿刺法のみで血液透析を行っている。返血には外頚静脈を主に用いている。 <考察> 慢性腎不全の維持血液透析患者にとってVAは文字通り命の綱であり、必須のものである。近年、慢性血液透析の新規導入症例に占める糖尿病性症例の頻度は増加している。そのような症例では動静脈ともに標準的内シャント作製に不適である場合が多い。すなわち動脈硬化や長期間、採血のために穿刺を繰り返したことに起因する静脈の荒廃などによって内シャント作製そのものが困難であったり、作製し得てもシャント血管の発育が不良である症例が少なくない。 自己血管による内シャント作製が困難である場合、1)人工血管植え込み術、2)動脈表在化、3)長期留置型カテーテルの中心静脈への挿入留置、などが対応策として考慮される。 1)、2)は動静脈に問題を有する症例が多いため必ずしもVA確保に成功するとは言い難い。3)には血栓によるカテーテルの閉塞、カテーテル先端部が血管壁に密着することに起因する脱血不良、カテーテル感染などの危険性がある。 大腿静脈の直接穿刺により血液透析を長期間続行しえたとの報告は散見されるが、我々の調べ得た範囲では長期間、内頚静脈を使用したとの報告は無い。内頚静脈穿刺は大腿静脈穿刺に比し患者さんの羞恥心が軽減されるという利点がある。内頚静脈穿刺の合併症として大腿静脈穿刺と同様、動脈の誤穿刺があるが適切な圧迫止血で対応可能である。VAが自己血管や人工血管を用いても作製しえない症例にとって本法は選択肢の一つとなりうると思われる。 <結論> 諸般の事情により自己血管あるいは人工血管によるVAが作製できない場合には内頚静脈直接穿刺により血液透析を続行するという方法は1つの選択肢になりうると思われる。
1 0 0 0 航空用距離測定装置のインテグリティ保証のためのマルチパス解析
- 著者
- 毛塚 敦 齊藤 真二
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 C (ISSN:13452827)
- 巻号頁・発行日
- vol.J105-C, no.5, pp.139-148, 2022-05-01
航空機のナビゲーションにはGNSSが主に利用されているが,GNSS信号は微弱であり,脆弱性を有する.GNSSに障害が発生した際にも航空機の安全と効率を維持できるように代替測位システム(APNT)を構築することがICAO(国際民間航空機関)での課題となっている.そこで,現在配置・運用されている航空用距離測定装置(DME)を2局用いたDME/DME測位の機能・性能を向上させて短期的なAPNTとすることが検討されており,欧州で標準化が開始された.GNSSのみ航法装置として認められる経路にDME/DME測位を適用するためには新たにインテグリティの保証が必要となるが,山岳地形が多い日本国内では特にマルチパスによる誤差がインテグリティの脅威となる.現在運用中のDME/DMEのインテグリティ保証のためには,飛行検査において発生するマルチパス誤差を抽出し,その原因を特定するとともにインテグリティへのインパクトを評価することが有効である.そこで本論文では,シミュレーションによりマルチパス発生位置を推定する手法を提案し,更にその誤差量のインテグリティへのインパクトを定量的に評価する一連の手法を示す.
1 0 0 0 OA 「助六所縁江戸桜」考 ―上演史からみた「ゆかり」の意味―
- 著者
- 齊藤 千恵
- 出版者
- 日本近世文学会
- 雑誌
- 近世文藝 (ISSN:03873412)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, pp.1-14, 2012 (Released:2017-04-28)
1 0 0 0 OA ロボットの概念的変遷
- 著者
- 村上 陽一郎
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.6-7, 1998-01-15 (Released:2010-08-25)
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA なじまぁ 12号
- 出版者
- 立教大学アジア地域研究所
- 雑誌
- なじまぁ (ISSN:21888213)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-27, 2022-03-31
1 0 0 0 OA 大学生における「ひとりの時間」の検討および自我同一性との関連
- 著者
- 増淵(海野) 裕子
- 出版者
- 日本青年心理学会
- 雑誌
- 青年心理学研究 (ISSN:09153349)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.105-123, 2014-02-10 (Released:2017-05-22)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
This study had four purposes: (1) to create two scales related to the time spent alone by undergraduate students; (2) to examine the relationship between how the students spent their time alone, and their thoughts and assessments about spending time alone; (3) to examine what types of groups with what characteristics were observable, specifically as to how the subjects spent time alone and what their thoughts and assessments were about spending time alone, and (4) to examine the relationship between ego identity and how the subjects spent their time alone and their thoughts and assessments about spending time alone.An investigation was carried out using a questionnaire given to 347 undergraduate students. The results revealed the following. (1) Their thoughts and assessments about spending time alone could be described, using four subscales: loneliness/anxiety, desire for independence, fulfillment/satisfaction, and desire for isolation. (2) How the subjects spent their time alone also comprised four subscales: self-introspection, self-liberation, immersion in personal activities, and release from stress. (3) A cluster analysis identified five different cluster groups: the Anxious-When-Alone Group, the High-Desire-for-Independence Group, the Moderate Group, the Feeling-One’s-Way Group, and the Desire-for-Isolation Group. (4) A path analysis found that the way in which students spent their time alone, and their thoughts and assessments about spending time alone, had an influence on ego identity.
- 著者
- 江原 康生
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.14-16, 2022-03-31 (Released:2022-05-10)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 松江藩の郷校について――新史料「郷校取調巡郷日記十五」(桃文之助)を中心として――
- 著者
- 磯辺 武雄
- 出版者
- 国士舘大学文学部人文学会
- 雑誌
- 国士舘大学文学部人文学会紀要 (ISSN:03865118)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, 1988-01
1 0 0 0 OA 知的障害児教育の教育養成課程における知的障害児の心理・生理・病理に関する一考察
- 著者
- 河合 高鋭 中尾 健太郎
- 出版者
- 鶴見大学
- 雑誌
- 鶴見大学紀要. 第3部, 保育・歯科衛生編 = The bulletin of Tsurumi University. Pt. 3, Studies in infant education and dental hygiene (ISSN:03898024)
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.1-6, 2022-02
1 0 0 0 OA 2010年における学齢期のフッ化物配合歯磨剤の使用状況
- 著者
- 山本 龍生 阿部 智 大田 順子 安藤 雄一 相田 潤 平田 幸夫 新井 誠四郎
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.410-417, 2012-07-30 (Released:2018-04-06)
- 参考文献数
- 12
「健康日本21」の歯の健康に関する目標値「学齢期におけるフッ化物配合歯磨剤(F歯磨剤)使用者の割合を90%以上にする」の達成状況を調査した. 2005年実施のF歯磨剤使用状況調査対象校のうち,協力の得られた18小学校(対象者:8,490 名)と17中学校(対象者:8,214名)に対して,調査票を2010年に送付し,小学生の保護者と中学生自身に無記名で回答を依頼した.回収できた調査票から回答が有効な12,963名(小学生:6,789名,中学生:6,174名)分を集計に用いた. F歯磨剤の使用者割合は89.1%(95%信頼区間:88.6〜89.7%)(小学生:90.0%,中学生:88.1%,男子:88.0%,女子:90.2%)であった.歯磨剤使用者に限るとF歯磨剤使用者割合は92.6%(小学生:94.9%,中学生:90.2%)であった.F歯磨剤使用者の中で,歯磨剤選択理由にフッ化物を挙げた小学生(保護者),中学生は,それぞれ47.9%,15.8%であった.歯磨剤を使わない者の約3〜4割は味が悪いことを使わない理由に挙げていた. 以上の結果から,学齢期におけるF歯磨剤の使用状況は,2005年(88.1%)からほとんど変化がなく,「健康日本21」の目標値達成には至らなかった.今後はF歯磨剤の市場占有率の向上,歯磨剤を使わない者への対応等,F歯磨剤使用者の割合を増加させる取り組みが求められる.
- 著者
- 藤崎 亜由子 廣瀬 聡弥
- 出版者
- 奈良教育大学次世代教員養成センター
- 雑誌
- 次世代教員養成センター研究紀要 = Bulletin of Teacher Education Center for the Future Generation (ISSN:21893039)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.85-94, 2022-03-31
本論では、保育内容の領域「環境」の中で身近な自然(動植物)との関わりに焦点を当て、特に自然と関わる際にその促進要因とも阻害要因ともなる虫に注目した。まず、幼稚園教育要領等に示された「幼児教育において育みたい資質・能力」と領域「環境」の「ねらい」を踏まえて、保育者を目指す学生及び保育者が身に着けてほしい知識、技能及び態度を明らかにした。その上で、虫に注目する意義やその教育的活用の方法について整理し、虫との関わりを通して自然や生命の豊かさを実感し、生物多様性への関心と関わりを醸成する保育を目指し、その担い手となる学生に伝えるべき内容を含んだ実践プログラムを提案した。最後に提案した実践プログラムを授業として実施した上で、受講生からの感想を質的に分析し今後の課題を探った。
- 著者
- 板垣 ひより 細矢 剛
- 出版者
- 日本菌学会
- 雑誌
- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第62回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.58, 2018 (Released:2019-04-17)
- 著者
- 松本 健太郎
- 出版者
- 観光学術学会
- 雑誌
- 観光学評論 (ISSN:21876649)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.109-116, 2018 (Released:2020-03-25)
ポケモンGOはそのリリース直後、都市の意味空間を規定するレイヤーを多層化させ、われわれが認知するリアリティをより錯綜したものへと変質させた。実際それは物理空間と仮想空間の領域区分を越境しながら多くの社会問題を引き起こし、われわれが生きる意味世界に「分断」(それをプレイする人とそうでない人のあいだのそれ)をもたらす存在として報道されるに至った。本論考ではプレイヤー/非プレイヤーのあいだの「軋轢」、あるいは、そこから派生した社会的な「分断」を視野にいれつつ、複数の領域にまたがる理論的言説を参照しながら、また、それを前提に「ゲーミフィケーション」概念を再考するなどしながら、デジタル・テクノロジーが現代の記号世界にもたらしつつあるものを考察の俎上に載せてみたい。
1 0 0 0 OA 沖縄県における駐留軍等労働者の経済効果について
- 著者
- 楠山 大暁
- 出版者
- 日本公共政策学会
- 雑誌
- 公共政策研究 (ISSN:21865868)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.128-140, 2012-12-17 (Released:2019-06-08)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
日本には,日米安全保障条約に基づいて米軍が駐留している。米軍の駐留に資するため,在日米軍基地では,駐留軍等労働者と呼ばれる民間人従業員が,米軍の指揮・監督下で労務に服している。本稿の目的は,駐留軍等労働者とはいかなる存在なのかを,根拠条約に基づき明らかにする。その上で,産業連関分析の手法を用いて,駐留軍等労働者が沖縄県経済にもたらしている経済効果を計算することにある。沖縄県における2006年度の軍雇用者所得524億円の総効果は,1,100億円92百万円となった。これは,中間投入を含む2005年の県内生産額5兆7,668億円の約1.9%にあたる。このように,失業率が全国平均を上回る沖縄県経済にとって,米軍基地は貴里な雇用の場になっている。その反面,普天間基地返還を含む米軍再編により大規模に返還される駐留軍用地跡地を活用することにより,現米軍基地を上回る経済効果がもたらされることも期待されている。そこで,本稿の後半では,米軍再編を概観し,基地返還により逸失される駐留軍等労働者の経済効果を計算する。その上で,跡地利用の先行事例や今後沖縄が発展させるべき新たな産業を検証することにより,基地が返還された後でも,駐留軍等労働者に新たな雇用の場を提供できる条件を議論する。本稿の貢献は,沖縄県の基地問題に係る議論に対し,駐留軍等労働者という側面から定量的な視点を提供できたことにある。
1 0 0 0 OA シャーマニズムと日本の体育文化との関連性に関する視角
- 著者
- 芳賀 健治
- 出版者
- 日本体育・スポーツ哲学会
- 雑誌
- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.41-50, 1981 (Released:2010-04-30)
1 0 0 0 OA エレクトロニックアートとしてのCG
- 著者
- 上瀬 千春
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.18, pp.13-15, 1987 (Released:2017-10-06)
1 0 0 0 OA 磁性ビーズを用いたアセトアミノフェンの鎮痛機序の解明
アセトアミノフェンは副作用の少ない解熱鎮痛薬として使用されている薬剤である.しかしその作用機序は未だに不明である。そこでアセトアミノフェンの薬剤標的タンパクを網羅的に探索し作用機序解明を目指した.アセトアミノフェン合成物とHela細胞破砕液を結合反応させ,磁性分離によりタンパクを抽出しアセトアミノフェンと結合するタンパクを同定した.得られた標的タンパクは体温の恒常性に関与するGSK-3βであった.そこで発熱モデルを用いてアセトアミノフェンの解熱効果を確認した結果,アセトアミノフェンはGSK-3βを抑制することで解熱作用を発揮する可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 「泳道」 : 初めて津軽海峡を泳いで渡った男・中島正一譚
- 著者
- 宇田 快
- 出版者
- 国士舘
- 雑誌
- 楓厡 : 国士舘史研究年報 (ISSN:18849334)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.117-132, 2018-03-13