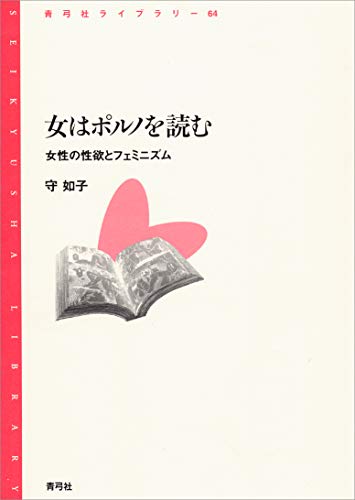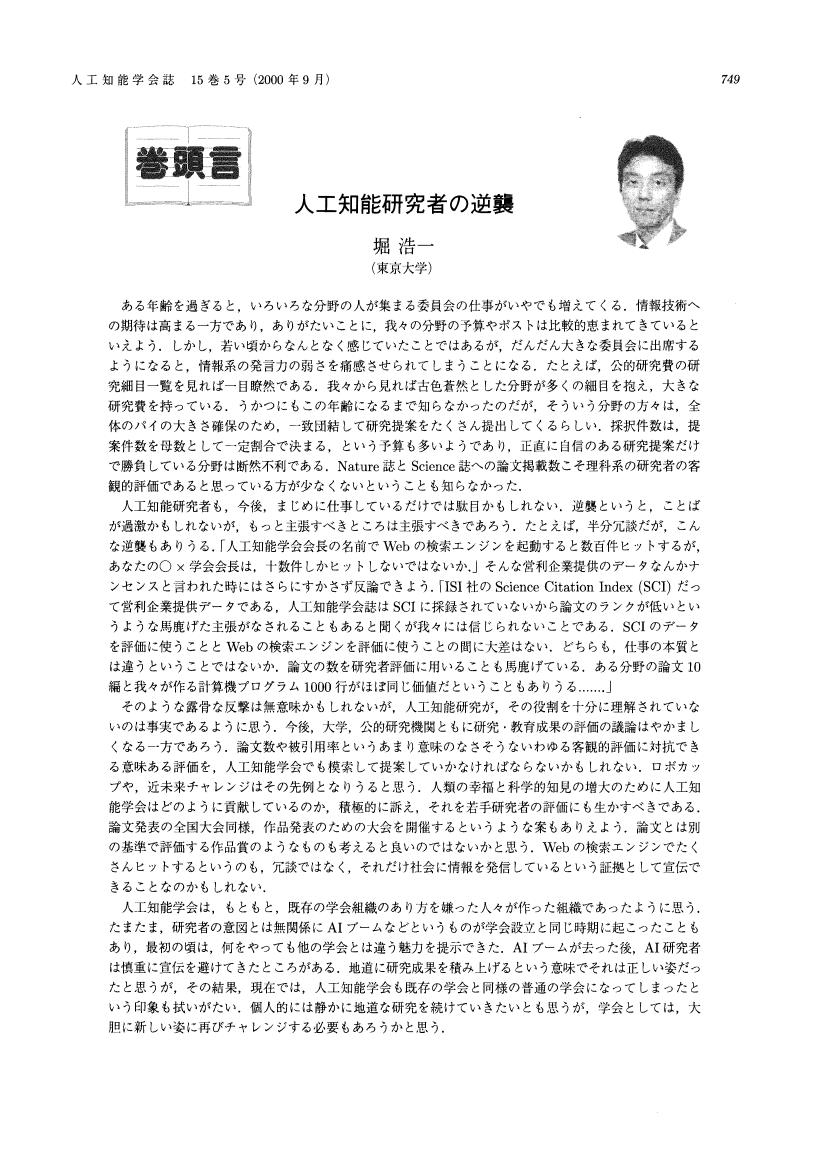1 0 0 0 OA 岐阜県可児市大森奥山湿地群に生息するハッチョウトンボ個体群の遺伝的多様性評価
- 著者
- 飯田 貴天 村上 哲生 南 基泰 藤井 太一
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- pp.2115, (Released:2022-04-28)
- 参考文献数
- 56
ハッチョウトンボ Nannophya pygmaeaが生息している岐阜県可児市大森の湧水湿地群は、太陽光発電施設建設予定地となった段階で開発業者と地域住民らの事前協議によって湧水湿地群を保存することになった。本研究では、 8つの湧水湿地に生息するハッチョウトンボ個体群の遺伝的多様性まで考慮した保全のために、ミトコンドリア cytochrome c oxidase subunit I遺伝子部分領域( 658 bp)を用いて、各湧水湿地に生息する個体群の遺伝的多様性及び遺伝的分化について解析した。 294頭から 8つのハプロタイプが確認され、各湧水湿地に生息する個体群のハプロタイプ多様度は、生息している湧水湿地の面積および傾斜角度、湧水湿地表層水の pHおよび電気電導度、湧水湿地周辺部の植生高と有意な相関関係は認められなかった(ピアソンの積率相関分析, p > 0.01)。また、 8個体群間の遺伝的分化係数( pairwise Fst)を算出した結果、有意な遺伝的分化は全ての個体群間で認められなかった( 10,000回の Permutation test,p > 0.01)。これらの結果から、本湧水湿地群のハッチョウトンボ個体群は、各湧水湿地間を遺伝的交流の制限なく移動している同一個体群であると考えられた。本湧水湿地群のハッチョウトンボ個体群の遺伝的多様性維持のためには、各湧水湿地間の遺伝的交流の制限となる生息地適性の低下や湧水湿地の消失を防ぐ必要がある。現在、市民によって実施されている湧水湿地の水質のモニタリング、湧水湿地内への土砂流入・堆積のモニタリング・除去、周辺から湧水湿地内に侵入した植物の除去を今後も継続し、定期的にハッチョウトンボ個体群の遺伝的多様性についても評価していく予定である。
1 0 0 0 OA 次世代の歯髄保存療法を目指したペプチド覆髄材
- 著者
- 高橋 雄介
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.115-119, 2022-04-30 (Released:2022-04-30)
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 OA 身分を秘匿してなした法律行為と詐欺罪 : 暴力団員のゴルフ場利用をめぐって
- 著者
- 四條 北斗
- 出版者
- 桐蔭法学会
- 雑誌
- 桐蔭法学 = Toin law review (ISSN:13413791)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.75-102, 2014-05
1 0 0 0 OA ネット言論のインパクト : ネット言論との接触は、若者をどう変えるのか
- 著者
- 南 宏幸
- 出版者
- 法政大学多摩論集編集委員会
- 雑誌
- 法政大学多摩論集 = TAMA BULLETIN (ISSN:09112030)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.115-185, 2022-03
- 著者
- 高橋 純一 福井 順治 椿 宜高
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.73-79, 2009-05-30 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 41
絶滅危惧種であるベッコウトンボの羽化殻を用いたRAPD解析によって、ベッコウトンボの集団に直接影響を与えることなく、遺伝的多様性を明らかにした。静岡県磐田市桶ヶ谷沼地域の3つの発生地で採集した60個体に対して80種類のプライマーを使用しRAPD解析を行った。17種のプライマーから20個の遺伝子座で多型が検出され、12種のDNA型が見つかった。そのうち集団特異的なDNA型が合計4つ検出された。遺伝子多様度は平均0.317、遺伝子分化係数は平均0.07となり、集団間の多様性は小さかった。AMOVA分析によっても集団間の分化は検出できなかった。また3集団から見出された変異は98.7%が集団内の個体間変異に、集団間では1.3%となった。クラスター分析からも集団間は非常に類縁関係が高いことが明らかになった。
1 0 0 0 OA 素朴な自由意志信念尺度の開発
- 著者
- 渡辺 匠 唐沢 かおり
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- pp.2012, (Released:2022-05-03)
- 参考文献数
- 36
自由記述方式の質問をもちいた過去の研究では,人々にとって自由意志は「何ものにも制約を受けず,自分の心理状態にそって行動を選択する」ということを基本的に意味すると示唆されている。しかしながら,人々の自由意志信念に関する既存の尺度は,人々の素朴な自由意志概念ではなく,研究者の理論的な自由意志概念にもとづいて作成されてきた。そこで著者らは他行為可能性,行為者性,制約からの自由の3つの因子から構成された,人々の素朴な自由意志信念を測定するための新たな尺度を作成した。本論文では,3つの研究で約4,000人の回答者(大学生および一般成人)が分析にふくまれている。その結果,予測されていた因子構造や尺度の信頼性が確認された。それにくわえて,他行為可能性と行為者性の得点は,道徳的な責任帰属の得点と正の相関関係をもつことが明らかになった。これらの知見は,心理学および哲学の文献と照らし合わせて議論されている。
- 著者
- 浜崎 智仁 奥山 治美 大櫛 陽一 浜 六郎
- 出版者
- 日本脂質栄養学会
- 雑誌
- 脂質栄養学 (ISSN:13434594)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.69-76, 2013 (Released:2013-05-01)
On September 8, 2012, the panel discussion “The Rethinking of Cholesterol Issues” was held in Sagamihara City, Japan. This paper is the summary of that panel discussion. Four discussants expressed their skeptical views against the cholesterol hypothesis. The whole discussion will be freely seen on the net. Also a similar editorial written by the four discussants will be published in English (Ann Nutr Metab 2013;62:32-36, a free PDF file is already available on the internet). Because Japan Atherosclerosis Society Guidelines for Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Diseases 2012 (JASG 2012) has recently been published, the main part of this paper is focused on serious flaws found in JASG 2012. Dr Harumi Okuyama discusses the differences between JASG 2012 and our guidelines indicating that high cholesterol levels are a good index of longevity; the most important point is that the statin trials that have been performed after 2004, when the new EU law regulating clinical trials became in effect, are all negative. Dr Yoichi Ogushi claims that JASG 2012 intentionally omits some good aspects of cholesterol; cholesterol is a negative risk factor of stroke. His own data also show that cholesterol is good for stroke. He also claims that to properly treat patients with diabetes, we need to reject the cholesterol hypothesis and to reduce carbohydrate rather than cholesterol. Dr Tomohito Hamazaki points out unforgivable flaws in JASG 2012. It does not disclose any COI. It does not contain any relationship between cholesterol levels and all-cause mortality in Japan. Pharmaceutical companies spend 600 billion yen (7 billion US$) per year for advertisement in Japan. This works as “devil’s insurance” (withdrawal of advertisement is a real threat to the mass media). The last discussant, Dr Rokuro Hama, explains the mistake made by JAS (liver disease causes both death and depression of cholesterol levels, and low cholesterol levels are not the cause of death). Hepatitis C virus (HCV) enters hepatic cells via LDL receptors, and low cholesterol levels are one of the major risk factors of HCV infection and chronic hepatitis. Hence, death from liver disease could be the result of low cholesterol levels.
1 0 0 0 女はポルノを読む : 女性の性欲とフェミニズム
1 0 0 0 OA 十一面觀音の表現に就いて
- 著者
- 佐和 隆研
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教研究 (ISSN:18843441)
- 巻号頁・発行日
- vol.1943, no.84, pp.57-79, 1943-03-10 (Released:2010-03-12)
- 著者
- 川嶋 正志
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 開智国際大学紀要 (ISSN:24334618)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.15-24, 2022 (Released:2022-04-28)
社会の中で「コミュニケーション能力」という言葉が多様化し、強い力を持つようになった。社会学の視点から「コミュニケーション能力」について考えると、コミュニケーションの高度化と個人化という状況が見えてくる。同様の問題は国語科教育でも起きており、過剰な「メタ認知」への注目によって求められる知識や技能が高度化していく事態を招いている。従来の国語科教育の理論的基盤はハーバーマスの理論であったが、これまでもその理論の不十分さが指摘されてきた。そこで、本論ではハーバーマスと論争を繰り広げていたN.ルーマンに注目する。高度化していく「コミュニケーション能力」とは別の視座を得るため、ルーマンのコミュニケーション理論に注目し、「コミュニケーション・システム」という新たな捉え方を提案する。 ルーマンのコミュニケーション理論の特徴として注目した点は①「移転」というメタファーからの脱却、②「三重の選択」、③「二重の偶発性」の3点である。まだ課題は山積しているが、わかりあえないことを前提とした新たなコミュニケーション観には可能性があるように考えられる。
1 0 0 0 OA 自己修復機械の設計(<特集>「バイオメカニズムと設計」)
- 著者
- 中野 馨
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.18-24, 1985-02-01 (Released:2016-10-31)
1 0 0 0 OA 社会の中のろう薬剤師 ~ろう・難聴薬剤師の役割とは~
- 著者
- 柴田 昌彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬学教育学会
- 雑誌
- 薬学教育 (ISSN:24324124)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.2020-040, 2021 (Released:2021-04-07)
- 参考文献数
- 12
ろう者・難聴者が薬剤師免許を取得する道が開かれたのは2001年のことである.免許取得者は増え続け,薬学部に入学するろう・難聴学生も続出している.これまでに薬剤師免許を取得し,社会に出たろう・難聴薬剤師の役割を理解すれば,自ずからろう・難聴薬学生を教育する意義が導き出されるだろう.筆者が考えるその役割とは,ろう・難聴者と聴者との間のコミュニケーションの課題が具体的に明らかになり,当事者の視点でその解決方法を提供することである.1つは服薬指導などにおけるろう・難聴患者–聴医療従事者間の課題で,もう1つは一緒に働くにあたってのろう・難聴薬剤師–聴医療従事者間の課題である.それらの課題や,解決に向けた活動を紹介する.薬学教育にも「文化モデル」の視点で「ろう・難聴」「日本手話」を取り入れてコミュニケーション豊かな薬剤師を輩出して頂ければ幸いである.
1 0 0 0 OA 律蔵における判定事例集(vinītaka)について
- 著者
- 李 薇
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.1018-1012, 2019-03-20 (Released:2019-09-20)
- 参考文献数
- 5
Six Vinayapiṭakas have come down to us: the Pāli Vinaya, Dharmaguptaka-vinaya (Sifen lü, 四分律), Mahīśāsaka-vinaya (Wufenlü, 五分律), Mahāsāṃghika-vinaya (Mohesengqi lü, 摩訶僧祇律), Sarvāstivāda-vinaya (Shisong lü, 十誦律) and Mūlasarvāstivāda-vinaya (根本説一切有部律).The Pāli Vinaya (Buddhist monastic law codes) is comprised of three main aspects: 1) the Vibhaṅga (analyses of the rules in the pāṭimokkhasutta), 2) the Khandhaka (corporate law or transactions of the saṅgha and so on), and 3) the Parivāra (a brief review of the Vibhaṅga and Khandhaka).The Vibhaṅgas of the four pārājika offenses of the Pāli Vinaya includes four sections, 1) nidāna (episodes that caused the rules to be made, 因縁譚), 2) sikkhāpada (the rules, 学処), 3) padabhājana (the analyses section of the sikkhāpada and offenses, 条文解釈), 4) vinītaka (the case-law pertaining to those rules, 判定事例集).In this study, I examine the vinītaka (判定事例集) of the six extant Vinayapiṭakas. The vinītaka is a part of the Vibhaṅgas in the Pāli Vinaya and found in the Khandhaka or Parivāra in the five Chinese Vinayapiṭakas. In this paper, I notice one characteristic of vinītaka: that the episode of the nidāna reappears as a brief statement in the vinītaka. This characteristic is found in the vinītaka of the four pārājika offenses in the Pāli Vinaya, and the first and fourth pārājika offenses in the Dharmaguptaka-vinaya, and the first pārājika offence in the Mahīśāsaka- and Sarvāstivāda-vinayas, but not found in the Mahāsāṃghika- and Mūlasarvāstivāda-vinayas.
1 0 0 0 OA 人工知能研究者の逆襲
- 著者
- 堀 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.5, pp.749, 2000-09-01 (Released:2020-09-29)
1 0 0 0 OA 女性史研究 : 第23集 (1988.12.1)特集「日本女性史資料(近代篇) 」
- 出版者
- 家族史研究会
特集 日本女性史資料(近代篇)クララ・ツェトキン・コロッキウムとバッハオーフェン展と 伊藤セツ女子教育 薄妙子明治民法 緒方和子治安警察法 石原通子君死にたまふこと勿れ 光永洋子堕胎罪 林葉子「青鞜」誌 高木富代子米騒動 立山ちづ子新婦人協会 犬童美子『女工哀史』 中山そみ「女工芸術」誌 林葉子「婦人戦線」誌 寺本千里国民優生法 光永洋子婦人参政権 伴栄子現行民法 卯野木盈二優生保護法 小玉稜子母子健康手帳 小柴雅子中絶・避妊 川上秀子国際婦人年・国連婦人の10年 石原通子一冊の女性史と私の読み方 富田佐保子瀬上さんの思い出 小柴雅子原始社会・女性・家族 田畑稔訳バッハオーフェンの『古代書簡』と『母権論』第二回編集III 石塚正英訳文学研究から見た「バッハオーフェン」 臼井隆一郎日本近代女性史論・第一 布村一夫
1 0 0 0 OA ボールゲームにおける状況判断の指導に関する理論的提言
- 著者
- 中川 昭
- 出版者
- Japanese Society of Sport Education
- 雑誌
- スポーツ教育学研究 (ISSN:09118845)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.39-45, 1986-11-30 (Released:2010-08-10)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 3
The purpose of this study was to make a proposition on the instruction in decision making in ball games from the theoretical standpoint. To put it concretely, the outline of contents and methods of the process-oriented instruction in it was given in this study.Firstly, a conceptual linear model of decision makig in ball games, which is consisted of four stagesselective attention to outer game situation (which means the external environment subsisting objectively), recognition of game situation (which consists of objective and subjective environmental elements), anticipation of game situation, decision on play-was presented, and the main points of instruction were discussed in each stage of the model.Secondly, the subjects of the method on field/ court, the method in room, and selecting game situations were discussed about the methodology of instruction.Resting on the basis of the proposition in this study, more improved practice and many corroborative studies on decision making in ball games should be proceeded in future.
1 0 0 0 OA 律文献からみるサンガの飢饉への対応
- 著者
- 井上 綾瀬
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.907-902, 2021-03-25 (Released:2021-09-06)
- 参考文献数
- 10
The vinayas allow special cases of “cooking and preserving food”, “utilizing leftover food”, and “collecting fruits” in case of famine. The famine exception does not apply when the famine is over. Even bhikkhu can work in times of famine in order to support their lives, according to the Vinayas. In the event of famine, the rules loosen. It was generally accepted in ancient India that there was a difference between normal and emergency times. It is common in the Vinayas and Dharma literature that, in the event of an emergency, bhikkhus or brahmins may take on the activities of someone with a different social status, while keeping their status as bhikkhu or brahmin, respectively. It can be said that the Buddhist sangha had the same character as the broader Indian society in that avoiding poverty is more important in an emergency than protecting the bhikkhu’s normally expected means of life.