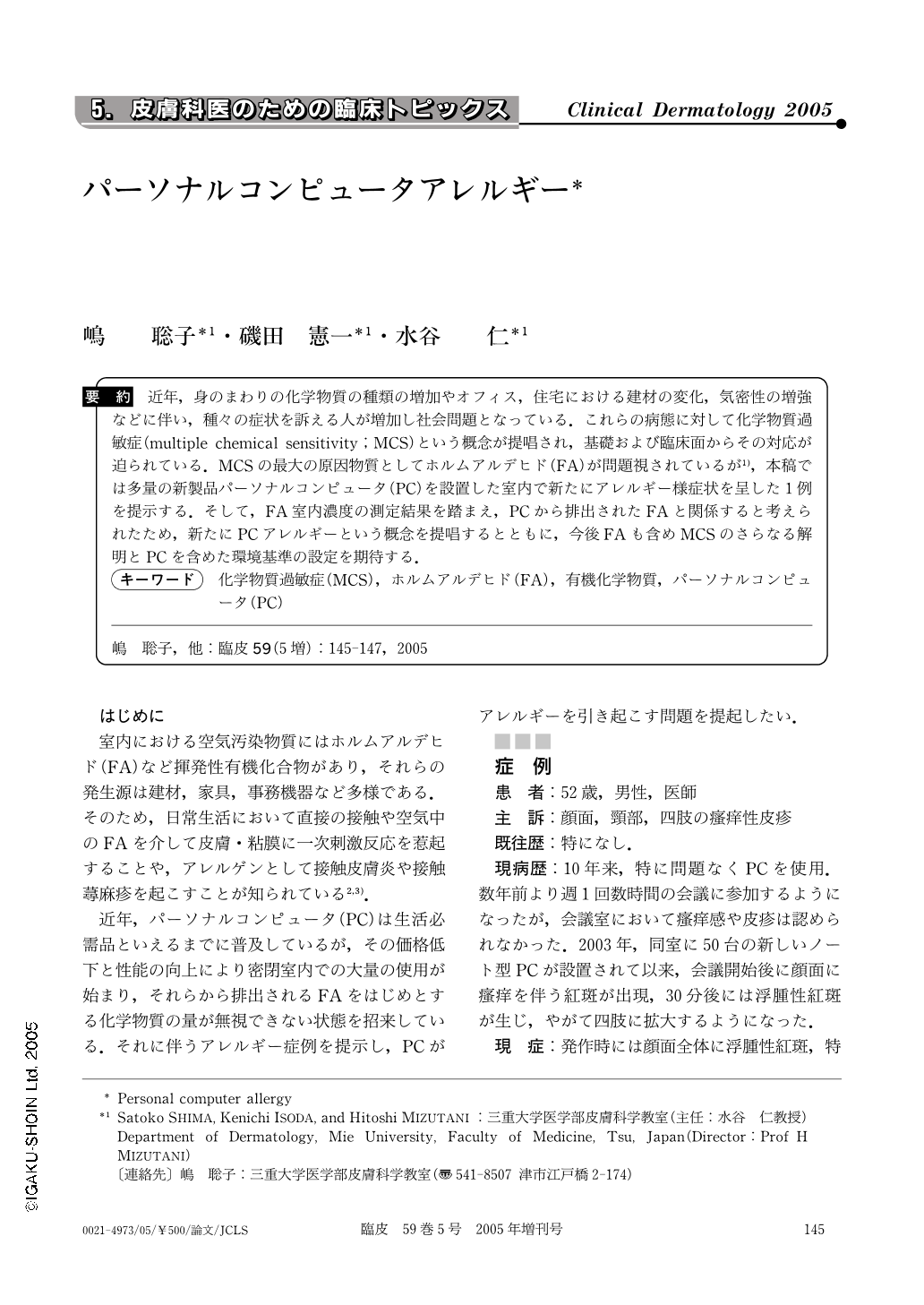1 0 0 0 IR 中世日本の西の境界領域と黒潮トライアングル研究 : 鹿児島県三島村硫黄島の調査を踏まえて
- 著者
- 市村 高男
- 出版者
- 高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科
- 雑誌
- 黒潮圏科学 (ISSN:1882823X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.174-187, 2013-03
鹿児島県三島村は、薩摩半島の南西海上に浮かぶ離島であり、竹島・硫黄島・黒島の三つの島からなる。これらの三つの島はトカラ列島とともに、中世日本の西の境界領域であった。この点に着目し、私は三つの島の文書・遺物の調査と遺跡の調査を実施した。本稿は、それらの成果を報告し、西の境界領域研究の新たな発展の基礎を固めた。また、本研究と黒潮トライアングルとの関係についても言及した。この研究によって、私は次ぎの点を明らかにした。まず第1に、三つの島の歴史的変遷を明らかにした。三つの島は、12世紀後半、13世紀末~14世紀前半、15世紀後半~16世紀後半に大きな画期があり、第3の画期が近世の島社会の出発点となった。第2に、硫黄島の三回目の変化は、島外からの新たな移住者である長浜家や岩切家らの活動によってもたらされた。長浜家は海の有力な商人であり、岩切家は硫黄採掘に関わる技術者であった。やがて長浜家は硫黄島の支配権を掌握し、君臨した。 第3に、竹島・硫黄島・黒島やトカラ列島がある海域は、多くの部分が黒潮の流れに洗われており、そこに点在する島は、航海する船の寄港地として重要な役割を果たしていた。島津氏や種子島氏らは、島の支配と商船の支配を一体的に考えていた。この海域の島々は、九州と沖縄との間の航海において、不可欠の存在であった。 第4に、この研究がフィールドとした島々や海域は、大半が黒潮トライアングルと重なっている。そこは人やモノの行き交う場であり、日本と琉球のせめぎ合いの場でもあった。それゆえ、この海域や島々の研究は、人文科学から黒潮トライアングルを考えることと深く関連する。自然科学と人文科学・社会科学との協働による研究の進展が望まれる。
1 0 0 0 明治時代の台風「6月流れ」について-2-
- 著者
- 伊集院 久吉
- 出版者
- 日本気象学会
- 雑誌
- 天気 (ISSN:05460921)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.9, 1958-09
1 0 0 0 OA 薩摩硫黄島の境界性と『平家物語』
- 著者
- 野中 哲照 ノナカ テッショウ Tessho Nonaka
- 出版者
- 鹿児島国際大学国際文化学部
- 雑誌
- 国際文化学部論集 (ISSN:13459929)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.234-212, 2012-09-30
1 0 0 0 IR 南極昭和基地第10居住棟パネル合板の経年変化と接着耐久性
- 著者
- 関口 洋嗣 田中 邦明 Hirotsugu Sekiguchi Kuniaki Tanaka
- 雑誌
- 南極資料 = Antarctic Record (ISSN:00857289)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.504-511, 2002-09
日本に持ち帰られた第10居住棟合板の耐久性を接着という観点から評価した結果と、合板の接着耐久性と並び重要である枠材と合板の接着性能について報告する。木質パネルから試験体を採取し、含水率を測定した上で、単板接着力試験と合板-枠材圧縮せん断試験を行い、接着力を測定した。その結果、室内側合板の含水率は低いため接着力は高いが、それに対して屋外側合板は高含水率化しており接着力の低下が著しかったこと、また合板と枠材の接着力は単板間接着力よりも高く、本エポキシ樹脂が適当であること、屋外面鉄板の接着仕様については今後検討を要することなどが分かった。総じて、合板の接着力低下には水分が大きく関与し、パネルの耐久性向上には、融雪水の進入対策、結露対策、外壁鋼板の防錆対策等による木材の高含水率化の防止と、接着剤の耐水性向上が必要であると思われる。
1 0 0 0 斜行型合板を用いた耐力壁の面内せん断性能
- 著者
- 河村 進 大畑 敬 村田 功二
- 出版者
- 公益社団法人 日本材料学会
- 雑誌
- 材料 (ISSN:05145163)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.280-285, 2009
- 被引用文献数
- 1 1
It is known that the shear performance of plywood depends on the grain direction of veneer sheets, and if veneer sheets are oriented 45 degree against the lateral sides, it indicates highest shear performance. Authors produced experimentally the diagonal plywood, which were laminated parallelogram veneers oriented diagonally against the lateral sides. The in-plane shear performance of the bearing wall, which joined diagonal plywood to the frame with the nail spaced 50mm to 150mm apart, was evaluated by racking test. When the nail space was shortened, load at yield point increased, but maximum load of diagonal plywood was almost equal to standard plywood. The comparable result was also obtained from the lateral nail resistance test.<br>In conjunction with this, shear strain distribution of panel was measured by digital image correlation (DIC), and approximate shear modulus of panel could be calculated from load-strain curve. Shear strain of diagonal plywood was lower than that of standard plywood. The bearing wall using diagonal plywood indicated large initial stiffness. As a result, it was concluded that bearing wall using diagonal plywood indicates higher reference shear strength. In order to increase the shear strength that is added to diagonal plywood, it is effective if the interval of nail is to some extent shorter than 150mm, which is the specification of wall index 2.5 of bearing wall using standard plywood. Shear modulus of full-sized diagonal plywood was about 4 times as much as that of standard plywood.
1 0 0 0 山古志地域の景観特性ならびに景観保全計画
- 著者
- 上野 裕治
- 出版者
- 長岡造形大学
- 雑誌
- 長岡造形大学研究紀要 (ISSN:13499033)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.巻頭1枚,1-112, 2010
ニホンスモモとウメの種間雑種'李梅'の安定生産に向けた知見を得るため,'李梅'の<i>S</i>-haplotypeおよび受粉品種について検討した.'李梅'の<i>S</i>-haplotypeを分析した結果,'李梅'の<i>S</i>-RNase遺伝子はサイモンスモモおよびウメからそれぞれ由来している可能性が高いと考えられた.サイモンスモモはニホンスモモの近縁種で,ニホンスモモと交雑和合性がある.これらのことから,'李梅'はウメだけではなくニホンスモモに対しても,<i>S</i>-haplotypeに関わらず,交雑和合性がある可能性が示唆された.実際にウメ,ニホンスモモ,アンズおよびモモ花粉を用い,'李梅'に人工受粉を行うとウメ,ニホンスモモおよびアンズ花粉では交雑和合性が確認された.特にウメ'宮口小梅',アンズ'平和'は花粉量が多く,花粉稔性が高いうえに,'李梅'と高い交雑和合性を示したので,人工受粉の花粉親として優れていると考えられた.このため,'李梅'においてはこれらの花粉を用いて人工受粉を行うことで,安定的に収量が確保できる可能性が示唆された.<br>
1 0 0 0 IR 和歌における「故郷」のディアレクティク (<特集><異郷>と<故郷>のディアレクティク)
- 著者
- 村尾 誠一 ムラオ セイイチ Murao Seiichi
- 出版者
- 東京外国語大学総合文化研究所
- 雑誌
- 総合文化研究 (Trans-Cultural Studies)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.20-32, 2006-03-07
1 0 0 0 謡曲〈胡蝶〉の構想:―「梅花に縁なき蝶」をめぐって―
- 著者
- 樹下 文隆
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.89-98, 1987
- 著者
- 棚町 祐子 表 志津子 藤川 幸未 片寄 妙子 田中 瑞穂 村住 英也 中島 志保 宮内 愛 佐伯 和子
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年看護学会
- 雑誌
- 老年看護学 (ISSN:13469665)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.92-99, 2005
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,デイケアにおける高齢脳卒中後遺症者の生き生きとした様子に注目し,高齢脳卒中後遺症者の意識から,デイケア参加の意味を明らかにすることである.デイケアを利用する高齢脳卒中後遺症者11名を対象に質的帰納的研究を行い,半構成面接と参加観察によりデータを収集し分析した結果, 3つの中核カテゴリーが抽出された.1つ目は,デイケアを利用することで<障害のある自分を否定的に捉えずにすむ>等から【不安・気兼ね・心配ごとが和らいでいる】, つ目は<リハビリの効果を実感し他の利用者と思いを分かちあい,支えあえる>等から【支えや励みを得て,リハビリを続けていくやる気を保っている】,3つ目は,デイケアへ通所することで<いつもの生活と違った雰囲気が味わえる>等から【生活に新たな喜びを加えていけている】であった.デイケアの専門職は,デイケアが生き生きとした生活を支援する場となるよう,高齢脳卒中後遺症者にとってのデイケア参加の意味に共感し,生活にも目を向けた援助を提供することが重要であると考えられた.
- 著者
- 葛西 周 KASAI Amane
- 出版者
- 名古屋大学大学院人文学研究科附属「アジアの中の日本文化」研究センター
- 雑誌
- Juncture : 超域的日本文化研究 (ISSN:18844766)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.60-72, 2018-03
本稿は、「近代日本の祝祭空間における「音楽」表象」(東京芸術大学大学院音楽研究科博士学位論文、2009)の一部に大幅な加筆修正を施したものである。追跡調査にあたり、2017年度科学研究費補助金基盤研究B「中国建国前夜のプロパガンダ・メディア表象:劇場文化と身体芸術のコラボレーション」(研究代表者:星野幸代)ならびに同若手研究B「戦前・戦中期東アジアにおける音楽ジャンル観の変遷」(研究代表者:葛西周)の援助を得た。
- 著者
- 大矢 正則
- 出版者
- カトリック社会問題研究所
- 雑誌
- 福音と社会 (ISSN:09145877)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.64-84, 2018-12
1 0 0 0 OA 注意の焦点の脳内表現:体性感覚野と聴覚野における短期可塑性
- 著者
- 井口 義信 尾崎 勇 橋本 勲
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.1-14, 2011 (Released:2017-04-12)
注意に伴う感覚皮質の反応様式の変化について、著者らの脳磁界計測の研究成果を中心にreviewした。注意レベル変化に応じて感覚入力に対する一次感覚皮質における賦活領域が変化し、聴覚皮質では音のピッチに注意するとtonotopyが明瞭化すること、また一次体性感覚皮質では、手指に注意するとsomatotopyが明瞭化することを示した。また、体性感覚に関しては、注意を向ける刺激のコントラストの違いによって二次感覚皮質の反応が増減すること、振動刺激の識別という難度の高い課題では、聴覚野が協調的に活動しうることも示した。おそらく感覚入力に関わる複雑な脳内ネットワーク間の相互信号伝達によって感覚の心象が形成されるが、中でも感覚野は実際の感覚入力を取得する場であり、その調整・加工を行う実行単位としての役割を担うので、感覚の心象表現に深く関わると思われる。
1 0 0 0 原点を考える : 安く豊かな石油時代が終わる
- 著者
- 石井 吉徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 = Journal of the Atomic Energy Society of Japan (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.193-199, 2005-03-30
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 2
<p> 昨年 (2004年) 9月9日 東京プレスセンターで日本原子力学会再処理リサイクル部会主催の講演会を開催した。前半の講演者米国原子力学会のベネデクト博士が「米国は燃料リサイクル (再処理) の研究開発を本格化すること, さらに輸送に使われる石油 (ガソリン) の1/4を原子力でまかなう計画である」と述べた。米国の方針転換の背景には, 安くて豊かな石油時代が終わることをきちんと認識しているからであろう。後半の石井吉徳氏の講演を同時通訳のイヤホンを耳に当て, しきりにうなづいていた。</p><p> その貴重な講演を文章にしていただいた。</p><p> 「40年前も, 石油資源はあと40年しか持たないといったではないか」, 「国際機関IEAでは, まだまだ大丈夫といっているではないか」, 「メタンハイドレードなど代替資源もあるではないか」との疑問にも適切に答えていただいた。</p><p> 車社会米国では石油の7割以上が輸送に使われている。日本でも石油の4割以上が輸送に使われている。車社会からわれわれはどのように脱皮していくのか。便利なガソリンの代替をどうするのか。現在の農業も大型機械や肥料など石油が支えている。天然ガスも10から20年遅れてピークを迎える。天然ガスは発電の1/3を占める。この影響も大きい。</p><p> リサイクルも熱力学から見れば, 流れが逆であり, その分エネルギーが要る。今の社会は, 安くて豊富な石油で成り立っている。われわれの生活にどのような影響があるか。どのような対策, 研究が必要か。みんなが考える問題である。本稿は皆様に考える原点を与えてくれるものと信じる。</p><p> 石油減耗への対策は, まだ世界的に解が得られていない。このような挑戦的な問題こそ, 大学, 研究機関が競って, 研究すべき課題である。</p>
1 0 0 0 歌麿の生涯と芸術
- 著者
- 菊池 貞夫
- 出版者
- 国際浮世絵学会
- 雑誌
- 浮世絵芸術 (ISSN:00415979)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.67-70, 1971
1 0 0 0 パーソナルコンピュータアレルギー
要約 近年,身のまわりの化学物質の種類の増加やオフィス,住宅における建材の変化,気密性の増強などに伴い,種々の症状を訴える人が増加し社会問題となっている.これらの病態に対して化学物質過敏症(multiple chemical sensitivity;MCS)という概念が提唱され,基礎および臨床面からその対応が迫られている.MCSの最大の原因物質としてホルムアルデヒド(FA)が問題視されているが1),本稿では多量の新製品パーソナルコンピュータ(PC)を設置した室内で新たにアレルギー様症状を呈した1例を提示する.そして,FA室内濃度の測定結果を踏まえ,PCから排出されたFAと関係すると考えられたため,新たにPCアレルギーという概念を提唱するとともに,今後FAも含めMCSのさらなる解明とPCを含めた環境基準の設定を期待する.
1 0 0 0 IR 生海苔の嗜好性と調理性
- 著者
- 三堂 徳孝
- 雑誌
- 中村学園大学薬膳科学研究所研究紀要 = Proceedings of PAMD Institute of Nakamura Gakuen University (ISSN:18829384)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.49-52, 2013-09-17
(はじめに)海苔は日本人の庶民の味を代表する海産物であるが、1食当たりの摂取量は少量で、更に食習慣の変化により食べる頻度も少なく、近年消費が低迷している。海苔の消費形態は殆んど板状の乾燥海苔であり、海苔製品は、焼き海苔や調味料で加工した味付け海苔、佃煮などで種類に乏しい。食育基本法が平成17年に制定され、地産地消が叫ばれている中、生産地においても新たな海苔製品の開発が求められている。収穫した生の海苔は、乾燥した海苔にはない風味を持ち、調理性も多様で活用範囲が広い。収穫期が12月から3月と短期間であるが、冷凍保存することによって通年利用できる。この新しい食材は海苔の消費拡大と消費者の健康増進に貢献できるものと考えられる。そこで生海苔の嗜好性と調理性について検討したので報告する。