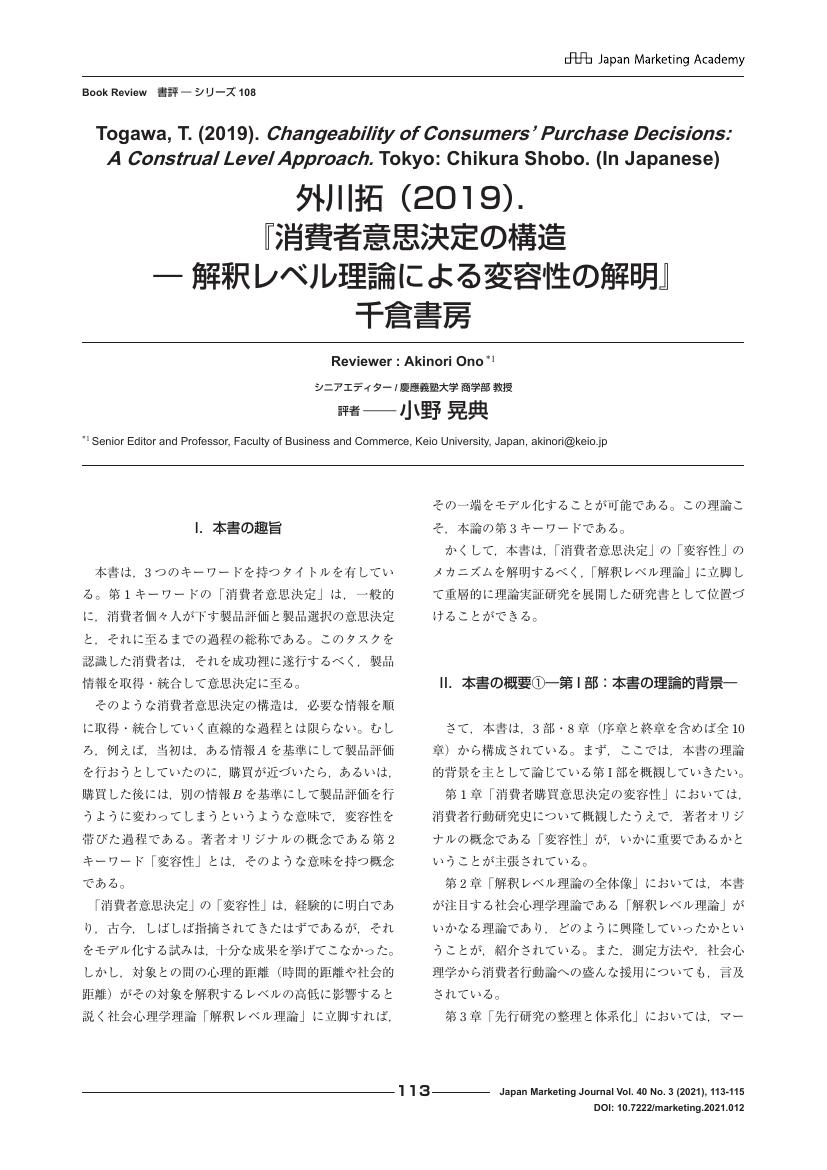- 著者
- 山之上 卓 成瀬 悠朔 尾関 孝史
- 雑誌
- 研究報告インターネットと運用技術(IOT) (ISSN:21888787)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021-IOT-54, no.1, pp.1-7, 2021-07-02
福山大学では新型コロナウィルス感染拡大防止のための健康調査が毎日行われているが,その入力のために多くの学生教職員が煩わしさを感じており,その煩わしさは健康調査入力率の低下にもつながっている.この煩わしさを低下させるため,入力の手間の大部分を省略するためのシステムを開発している.このシステムの試作について述べる.
- 著者
- シュウ テンテン Gao Weijun Qian Fanyue Li Yanxue Fukuda Hiroatsu
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会九州支部研究報告集
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.305-308, 2020-03
- 著者
- 永田 桂子
- 出版者
- 日本保育学会
- 雑誌
- 日本保育学会大会研究論文集
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.680-681, 1991-05-01
1 0 0 0 電力用金属整流器の現状
- 著者
- 酒井 善雄
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.809, pp.194-201, 1956
1 0 0 0 長野県環境保全研究所(飯綱庁舎)におけるセミの鳴き声調査
- 著者
- 栗林 正俊 大塚 孝一
- 出版者
- 長野県環境保全研究所
- 雑誌
- 長野県環境保全研究所研究報告 (ISSN:1880179X)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.55-60, 2019
長野県環境保全研究所(飯綱庁舎)において,2012~2018年に聞かれたセミの鳴き声をカレンダーに記録し,各種セミの鳴き声の聞き始めと聞き終わりについてまとめた。この結果,(1)エゾハルゼミ,アブラゼミ,エゾゼミおよびコエゾゼミ,ヒグラシは,聞き始めの日が早期化している可能性があること,(2)エゾハルゼミとアブラゼミは聞き終わりの日が早期化している可能性があること,(3)エゾゼミおよびコエゾゼミは聞き終わりの日が晩期化している可能性があること,が示された。また,2012年以前に飯綱庁舎で聞かれていなかったセミとして,ハルゼミが2014年,ツクツクボウシが2015年に初めて鳴き声が確認され,これらのセミは2018年にも鳴き声が確認された。
- 著者
- 村上 圭子
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.6, pp.2-28, 2020
本稿は、通信・放送融合時代の放送業界と放送政策の動向を中心に、メディア環境の変化を俯瞰して今後の論点を提示するシリーズの第5回である。本稿は2019年8月から2020年4月までを対象とする。本稿ではまず、新型コロナウイルスに関する放送事業者の取り組みや課題に触れたい。日々刻々と変化する状況を冷静かつ客観的にどう伝えていくか。一斉休校によって教育を受ける機会が奪われている小中学校の生徒たち向けにどのような役割が担えるか。置かれた状況が大きく異なる人々に対して、どのようなメッセージを発信していけるか。現在も状況が変化し続けているため、分析や認識は不十分であるが、状況が深刻化した4月に入ってからの動向を記録しておきたい。本稿のメインはNHKを巡る動向である。4月17日、「放送を巡る諸課題に関する検討会」の下に「公共放送の在り方に関する検討分科会」が立ち上がった。今後は、「業務」「受信料」「ガバナンス」の「三位一体改革」と共に、受信料制度の議論が本格的に行われることになるという。本稿では、4月1日にNHKの放送同時配信及び見逃し配信サービス「NHKプラス」が本格開始したのを機に、常時同時同時配信を巡る議論を、議論が開始された2015年にさかのぼって検証した。またこの半年のNHKを巡る動向を、"三位"の3点に分けて振り返った。以上の作業を通じて、今後NHKに関して重要だと思われる論点を筆者なりに提示した。
1 0 0 0 NHK経営計画の案が公表、高市総務大臣は5つの注文
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経ニューメディア = Nikkei new media (ISSN:02885026)
- 巻号頁・発行日
- no.1716, pp.2-3, 2020-08-10
公共放送 NHKは2020年8月4日、「NHK経営計画(2021-2023年度)」の案の概要を公表した。同日にNHK経営委員会が案を承認した後、NHKの前田晃伸会長が計画の案について会見で説明を行った。「(いわゆる三位一体改革に関して)次期経営計画では改革をさらにスピードアッ…
1 0 0 0 けい酸塩系表面含浸材のスケーリング抑制効果に及ぼす施工方法の影響
- 著者
- 森脇拓也 大西豊 藤井隆史 綾野克紀
- 雑誌
- コンクリート工学年次大会2021(名古屋)
- 巻号頁・発行日
- 2021-07-05
1 0 0 0 OA INNERVATION ZONES OF THE UPPER AND LOWER LIMB MUSCLES ESTIMATED BY USING MULTICHANNEL SURFACE EMG
- 著者
- KENJI SAITOU TADASHI MASUDA DAISAKU MICHIKAMI RYUHEI KOJIMA MORIHIKO OKADA
- 出版者
- Human Ergology Society
- 雑誌
- Journal of Human Ergology (ISSN:03008134)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1-2, pp.35-52, 2000-12-15 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 小野 晃典
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.113-115, 2021-01-07 (Released:2021-01-07)
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1026, pp.81-84, 2000-01-31
北海道国際航空(エア・ドゥ)は東京〜北海道間を片道1万6000円の格安料金で飛ぶ新規参入の航空会社として、98年12月20日に就航しました。当初は搭乗率が80%を超えるなど好調だったのですが、他社との競合で次第に下がっていき、苦戦を強いられるようになりました。 99年9月中間期決算では、計画の2倍に当たる約6億円の営業損失となりました。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.880, pp.93-96, 1997-03-03
銀行では戦後初めて,大蔵省から業務停止命令を受けた。子会社が過大な不動産投資に走ったことが,親銀行の首を絞めた。副頭取時代に子会社を制御できなかったことを素直に反省する。昨年11月21日,阪和銀行は大蔵省から業務停止命令を受けました。私自身としても,37年間勤めた銀行がなくなるかもしれないことは誠に残念であり,断腸の思いと言うほかはありません。
1 0 0 0 OA FM変調回路の安定性設計
- 著者
- 金本 良重
- 出版者
- 一般社団法人 品質工学会
- 雑誌
- 品質工学 (ISSN:2189633X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.5, pp.33-37, 1998-10-01 (Released:2016-06-10)
- 参考文献数
- 1
In the transmission of information, it is necessary to modulate the input signal. The frequencies of the signals for voice or music are generally low and the waves cannot be effectively transmitted remotely. For a good transmission, signals are modulated to high frequency waves. AM and FM are the modulation methods used for analog wave transmission. In the AM modulation, amplitude is changed whereas in the FM modulation,frequency is changed. Since the latter is more robust against noise, it is widely used for radios, TVs,transceivers or business radios. In the FM system modulation, voltage is used as the signal to change frequency. In this report, parameter design was conducted for the stabilization of an FM modulation circuit. In the traditional parameter design approach for electric circuits, power is used as the signal and is also measured as the output. However, it is inappropriate because the amplitude of both the input and the output are the same. In this report, a new generic function was proposed by considering frequency as the output frequency, and power was treated as noise.
1 0 0 0 OA 痛みの動物モデル-血管痛モデルについて-
- 著者
- 安藤 隆一郎 アンドウ リュウイチロウ Ando Ryuichiro
- 雑誌
- 東北薬科大学研究誌
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.33-40, 2010-12
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経インタ-ネットテクノロジ- (ISSN:13431676)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.183-187, 2000-12
障害に強いシステムを作っても,それを生かす運用がなければサービス・レベルは保てない。ポイントは2つある。1つは十分に堅固なインフラを用意すること。これはデータセンターの利用でほとんど解決する。もう1つは,問題の発生に先手を打てる監視・サポート体制を敷くこと。開発の初期段階から監視・サポートを考慮したシステムを作るのが望ましい。
- 著者
- 安島 真也 星 徹 手塚 悟
- 雑誌
- コンピュータセキュリティシンポジウム2013論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.4, pp.25-30, 2013-10-14
1 0 0 0 IR セクシュアル・ハラスメント対応における諸問題--大阪市立大学を事例として
- 著者
- 古久保 さくら
- 出版者
- 大阪市立大学
- 雑誌
- 人権問題研究 = The journal of human rights (ISSN:1346454X)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.91-113, 2007
はじめに : 2006年6月27日、大阪市立大学人権問題研究センターの研究員がキャンパス・セクシュアル・ハラスメントを事由にして停職3ヶ月という懲戒処分を受けたことは、人権問題を研究する研究組織として全国においてその独自性と先進性を誇ってきた大阪市立大学人権問題研究センターとして、断腸の思いで受け止めざるを得ないできごとであった。……
1 0 0 0 OA 大学のSD担当者養成研修における研修転移の効果と課題
- 著者
- 竹中 喜一 中井 俊樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会研究報告集 (ISSN:24363286)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.2, pp.53-58, 2021-07-03 (Released:2021-07-05)
2017年4月以降,大学では知識・技能の習得ならびに能力・資質向上をさせるための研修(スタッフ・ディベロップメント: SD)が義務化されている.組織が研修を行う目的は,職場での行動変容や業績向上である.こうした研修転移を促すためのSD担当者養成研修を設計し,その実践について研修から約3ヶ月後に実施した質問紙調査により評価した.その結果,研修中に取り組んだ組織の人材育成ビジョンやSDの企画案作成が行動変容や業績向上を促している可能性が示唆された.一方で,職場の組織文化や受講者の担当業務といった課題が研修転移の阻害要因となっていることも明らかになった.
- 著者
- 大杉 重男
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.61-70, 2005
保田与重郎の戦後最初の評論「みやらびあはれ」において、その標題になっている「みやらびあはれ」という語は、第二次世界大戦の敗北によって日本の領土から沖縄が暴力的に奪い取られたこと、引いては日本の敗戦そのものに対する保田の表象不可能な「断腸」の思いの合言葉として展開されているが、それをよりテクストに密着して解釈を進める時、この合言葉は保田の意図を超えた複数の様々な暴力の合言葉として読めて来ることを論じる。