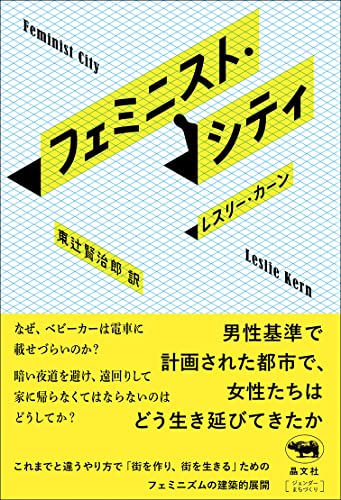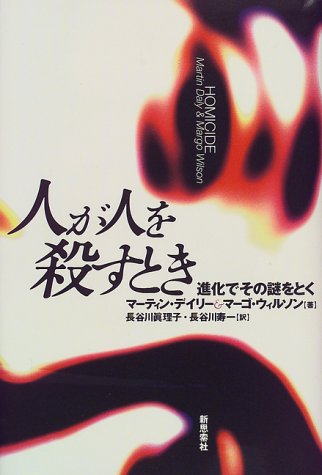1 0 0 0 OA 粒状活性炭中の有機フッ素化合物の分析
- 著者
- 竹峰 秀祐 高田 光康 山本 勝也 松村 千里 藤森 一男 渡辺 信久 中野 武 近藤 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境化学会
- 雑誌
- 環境化学 (ISSN:09172408)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.55-60, 2013 (Released:2013-09-25)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2 2
In this study, an analytical method for perfluorinated compounds (PFCs) in granular activated carbon (GAC) was investigated. The investigation of analysis was conducted by using GAC which adsorbed PFCs from artificial waste water containing PFCs of known amount. As results, it was confirmed that Accelerated solvent extraction (ASE) method using acetone as the solvent was appropriate for the extraction of PFCs in GAC.PFCs in used GAC samples, regenerated GAC samples, and a new GAC sample were analyzed by using the investigated method. The concentration of PFCs in the regenerated GAC was decreased by more than 99.9% compared with the used one. PFCs in GAC may transform and/or desorb at regeneration processes.
1 0 0 0 OA 地域メディカルコントロール協議会における救急隊の12誘導心電図記録と伝送の実態調査
- 著者
- 野々木 宏 安田 康晴 今井 寛 太田 祥一 小澤 和弘 木下 順弘 小林 誠人 高階 謙一郎 森村 尚登 山野上 敬夫 山村 仁 脇田 佳典 横田 順一朗
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.8, pp.800-805, 2019-08-15 (Released:2020-10-26)
- 参考文献数
- 15
ST上昇型急性心筋梗塞(STEMI)の発症から再灌流療法までの時間を短縮するためには,病院前12誘導心電図記録の病院への事前伝達が有効であり,ガイドライン勧告がなされている.ガイドライン勧告の実践がなされているか救急隊による12誘導心電図記録と伝送の実態を把握するため,全国地域メディカルコントロール(MC)協議会251団体へのアンケート調査を実施した.回答率は96%で救急隊による12誘導心電計を搭載しているのは82%と高率であったが,全車両に搭載しているのは28%と低率であった.12誘導心電計を搭載している196団体のうち,電話による病院への事前伝達を行っているのは88%と高率であったが,伝送しているのは27%と低率であった.本アンケート結果から,ガイドライン勧告の実践を実現するためには,12誘導心電計の搭載とともに,地域MC協議会を中心とした救急隊と病院群との連携,プロトコル作成や心電図検証が必要であり,それには救急医とともに循環器医の地域MC協議会への関与が必要であると考えられる.
1 0 0 0 OA カルシウムの神話について II
- 著者
- 山元 亜希子
- 出版者
- 帯広大谷短期大学
- 雑誌
- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.15-28, 2006-03-31 (Released:2017-06-16)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 フェミニスト・シティ
1 0 0 0 ぼくの音楽人生 : エピソードでつづる和製ジャズ・ソング史
- 著者
- 服部良一著
- 出版者
- 中央文芸社 : 日本文芸社(発売)
- 巻号頁・発行日
- 1982
1 0 0 0 OA 陰陽道祭文と修験道祭文 -牛頭天王祭文を例として-
- 著者
- 岩佐 貫三
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.317-321, 1974-12-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 銅鏡をつくる : ホルマリンによるフェーリング液の還元反応(化学実験虎の巻)
- 著者
- 嶋田 利郎 渡辺 範夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.184-185, 1989-04-20 (Released:2017-07-13)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 委託開発におけるハイブリッドアジャイルの適用効果
- 著者
- 英 繁雄 高月 裕二 東 大介
- 雑誌
- デジタルプラクティス (ISSN:21884390)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.252-259, 2016-07-15
日本では,エンタープライズ型のシステム開発は,ITサービス企業へ委託する場合が多い.欧米で多く適用されている迅速な開発手法であるアジャイルプロセスは,委託開発が主流の日本では普及しづらいのが現状である.本稿では,エンタープライズ型のシステム開発にハイブリッドアジャイルを適用し,アジャイルプロセスで採用されるいくつかのプラクティスから適用効果を評価する.適用したプラクティスは,反復,イテレーション計画,テスト駆動開発,継続的インテグレーション,コードレビュー,イテレーションレビュー,バーンダウンチャートである.
1 0 0 0 OA 非営利組織としての病院経営の方向 ──医療制度,病院価値,BSC を手掛かりに──
- 著者
- 髙橋 淑郎
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第88集 公共性と効率性のマネジメント─これからの経営学─ (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.6-15, 2018 (Released:2019-06-17)
- 被引用文献数
- 1
本稿は,わが国で非営利組織としての病院経営を,私的病院の経営を中心にして,これまでの先達の研究成果を踏まえ,わが国の医療制度の特徴を確認し,さらに先進諸国の医療における患者や医療サービス提供者の変化を明らかにした。その上で,医療における医療価値研究から病院価値研究への動きを把握し,現在および将来に向けて医療経営で,バランスト・スコアカード(BSC)およびその発展形であるSustainable BSC(SBSC)の有用性を論理的に示した。すなわち,SBSCは,持続可能性コンセプトの3つの次元すべてを,その戦略的重要度に応じて統合するBSCであることを示したことで,BSCからSBSCへの病院経営の方向を示した。これらの議論より,本稿で議論した病院価値を理解し把握した病院経営者が医師であれ,非医師であれ,払底している現状を確認し,戦略経営実践の枠組みが作れる,リーダーシップを持った人材の育成が急務であることを示した。
1 0 0 0 OA 新世代の自動車で重要な役割を果たすワイヤーハーネス
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.12, pp.769-772, 2021-12-01 (Released:2021-12-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 検体の前処理方法を変えることで菌の検出が可能となった1例
1 0 0 0 OA β遮断薬による心臓突然死の予防
- 著者
- 池田 隆徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.64-73, 2016 (Released:2016-03-25)
- 参考文献数
- 11
β遮断薬は,Na+あるいはK+チャネル遮断作用を有する狭義の抗不整脈薬に比べて,不整脈に対する作用効果は弱い.しかし,交感神経活動の緊張緩和や頻拍時の心拍数減少などの二次的な効果を有するため,不整脈治療に使用される頻度は高い.また,狭義の抗不整脈薬は強力な不整脈抑制作用を有する反面,心収縮力低下や危険性の高いほかの不整脈を惹起することがあり,この点においてもβ遮断薬は重篤な副作用の発現が比較的少なく,使用しやすい薬物といえる.さらに不整脈領域では,持続性心房細動・心房粗動のレートコントロール目的での使用頻度が最も高く,交感神経緊張が関与する心室不整脈の抑制や予防,心不全や心筋梗塞患者の心臓突然死の予防目的でも広く用いられている.β遮断薬には経口薬のみならず静注薬もあり,急性期の心室不整脈の管理においてなくてはならない薬物となっている.心室不整脈の薬物治療の中心はIII群抗不整脈薬であるが,それが無効である症例に対しては,β遮断薬が有効であることが多い.
- 著者
- 沖村 光祐 中山 友哉 吉村 崇
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.8, pp.369-376, 2021-08-01 (Released:2022-08-01)
- 参考文献数
- 29
冬季うつ病は日照時間の短い冬に,気分の落ち込みや社会性の低下などの抑うつ症状が現れる季節性の精神疾患である.欧米の高緯度地域では罹患率が人口の約10%とされ,社会問題になっているが,発症機序は不明である.うつ病は統合失調症や双極性障害に比べて遺伝率が低く,環境因子とともに多数の遺伝子が関与しているため,従来の順遺伝学や逆遺伝学を用いたアプローチには限界があった.近年,精神疾患のモデル動物としてゼブラフィッシュやメダカなどの小型魚類が注目を集めているが,メダカにケミカルゲノミクスのアプローチを適用することで,冬季のうつ様行動を制御する分子機構が明らかになってきたので紹介する.
1 0 0 0 OA ファントムセンス(VR感覚)の実態調査
- 著者
- バーチャル美少女ねむ Liudmila Bredikhina
- 出版者
- バーチャル学会運営委員会
- 雑誌
- バーチャル学会発表概要集 バーチャル学会2021 (ISSN:27583791)
- 巻号頁・発行日
- pp.29, 2021-12-17 (Released:2023-07-21)
1 0 0 0 人が人を殺すとき : 進化でその謎をとく
- 著者
- マーティン・デイリー マーゴ・ウィルソン著 長谷川眞理子 長谷川寿一訳
- 出版者
- 新思索社
- 巻号頁・発行日
- 1999
- 著者
- 吉村 理希 岩尾 洋英 金森 健彦
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会年次大会講演予稿集 2017 (ISSN:13431846)
- 巻号頁・発行日
- pp.23E-4, 2017 (Released:2020-01-23)
Fuji Television has developed the equipment “SDI-Hyper” which can be transmitted the carrier of one transponder (36MHz) or IP at high speed (960Mbps) via HD circuit. This equipment is useful in site diversity of SNG and transmission of 4K, file.
1 0 0 0 OA 理科カリキュラム内容構成論 ―誰が決定し,何を基準とするのか―
- 著者
- 磯﨑 哲夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.267-278, 2019-11-29 (Released:2019-12-20)
- 参考文献数
- 65
- 被引用文献数
- 1 1
本小論は,理科カリキュラムの内容構成論について,比較教育史的アプローチに基づき知識論を援用しながら,19世紀から現在までの3つの時代区分により,日本とイギリスを比較しながら論じた。そして,誰が学習内容を決定し,何を基準として学習内容が選定されるかについて考察した。その結果,両国の科学(理科)教育の史的展開を比較すると,まず,科学(理科)教育を完成した所与のものと見なすのではなく,社会的・歴史的産物と見なすべきことを指摘した。重要なのは,目的・目標論,別の表現をすれば,理科教育を通してどのような資質・能力を備えた人間を形成するかという前提条件のもとで,学習内容(科学(そのもの)の)知識と科学についての知識)を選択し決定するべきであり,そのためには社会や学界を十分に巻き込んだ議論を踏まえて,目標や内容等を決定する“noosphere”における議論が必要である,ということである。理科は自然科学を基盤としている教科である,という分離教科カリキュラムや学問中心カリキュラムの定義を,グローバル化の視点と現代的文脈で再解釈する必要に迫られていることを指摘した。
1 0 0 0 OA 最新の顎変形症治療 : 当院での本治療の発展とともに
- 著者
- 松下 和裕
- 出版者
- 北海道歯学会
- 雑誌
- 北海道歯学雑誌 (ISSN:09147063)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.25-32, 2018-09
昨年2017年9月2日,下顎枝矢状分割術の考案で著名なHugo Obwegeser(1920年10月21日生まれ)が96歳で亡くなった.葬儀は彼のホームタウンであるチューリッヒのシュヴェルツェンバハで9月13日に行われた.これも最新の歯学として忘れてはならない出来事である.彼が書いた書籍1)に,下顎枝矢状分割術の施行に関しとても興味深い内容が書かれているので,最初に紹介したい.その上で,当院でのこれまでの発展の歴史と最近の話題を語りたい.
1 0 0 0 OA 下肢装具のバイオメカニクス
- 著者
- 田中 惣治
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.199-203, 2022-07-01 (Released:2023-07-15)
- 参考文献数
- 7
短下肢装具が脳卒中者の歩行にどのような影響があるか,バイメカクスの観点から理解することは,短下肢装具の選定や使用に欠かすことのできない知識である.脳卒中者の歩行を対象とし,矢状面における短下肢装具の効果について解説する.また,足継手の種類,歩行のロッカー機能と短下肢装具の作用,下腿前後傾角度(Shank to Vertical Angle:SVA)に着目した評価のポイントについて述べる.さらに症例を通じて短下肢装具の使用により脳卒中者の歩容や筋活動が変化することを示す.