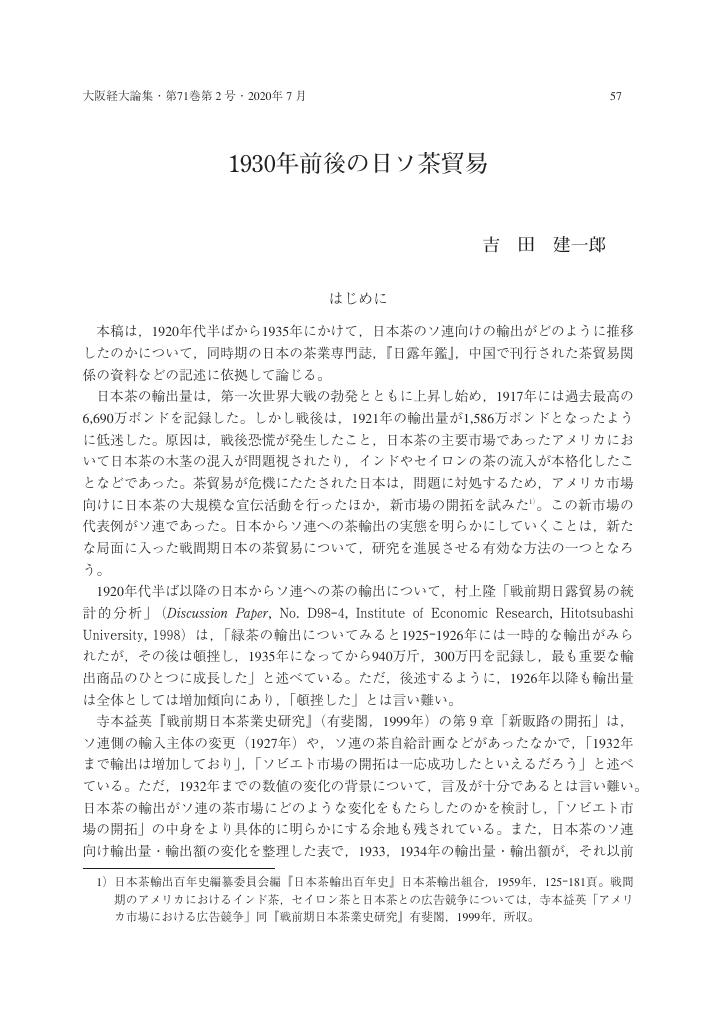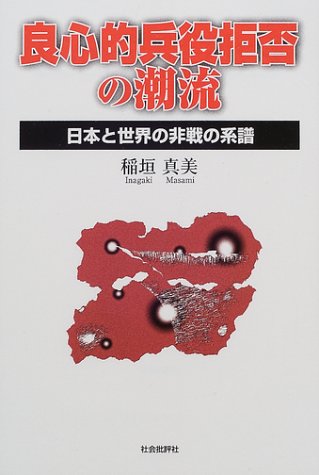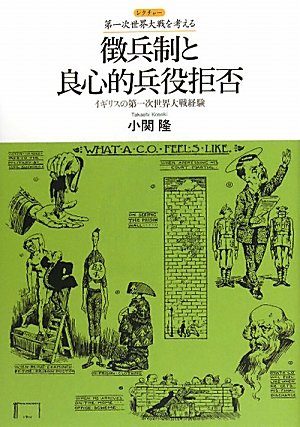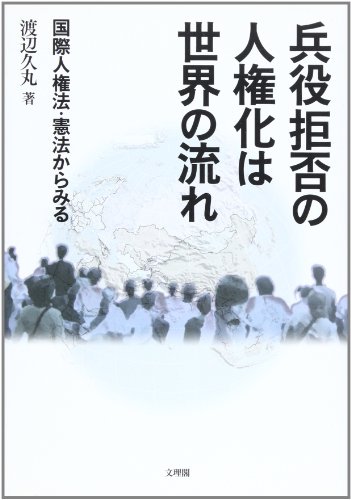- 著者
- Hironobu Mitani Kota Suzuki Junya Ako Kazuma Iekushi Renata Majewska Salsabil Touzeni Shizuya Yamashita
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.11, pp.1622-1634, 2023-11-01 (Released:2023-11-01)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 6
Aims: The study aimed to investigate low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) goal achievement rates in patients receiving LDL-C-lowering therapy using recent real-world data, following the 2017 revision of the Japan Atherosclerosis Society Guidelines for Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Diseases (JAS GL2017). Methods: Patients with documented LDL-C test results were extracted from the Medical Data Vision claims database between July 2018 and June 2021 and divided into three groups according to JAS GL2017: primary prevention high risk (Group I, LDL-C goal <120 mg/dL), secondary prevention (Group II, LDL-C goal <100 mg/dL), and secondary prevention high risk (Group III, LDL-C goal <70 mg/dL). Results: The mean LDL-C value was 108.7 mg/dL (n=125,235), 94.4 mg/dL (n=57,910), and 90.6 mg/dL (n=33,850) in Groups I, II, and III, respectively. Intensive statin monotherapy (pitavastatin, rosuvastatin, or atorvastatin) was the most frequently prescribed lipid-lowering treatment (21.6%, 30.8%, and 42.7% in Groups I, II, and III, respectively), followed by ezetimibe (2.5%, 7.1%, and 8.5% in Groups I, II, and III, respectively). LDL-C goals were achieved by 65.5%, 60.6%, and 25.4% of patients overall in Groups I, II, and III, respectively. Achievement rates were 83.9%, 75.3%, and 29.5% in patients prescribed intensive statin monotherapy and 82.3%, 86.4%, and 46.4% in those prescribed statin and ezetimibe combinations in Groups I, II, and III, respectively. In Group III, the proportion of patients with familial hypercholesterolemia prescribed statin and ezetimibe combinations achieving LDL-C goals was low (32.5%). Conclusions: The proportion of patients achieving LDL-C goals for secondary prevention in the high-risk group remains low even with statin and ezetimibe combination therapy.
1 0 0 0 OA 母体救命に特化したラピッドカー : 周産期ラピッドカーの導入
1 0 0 0 OA タイワンザメの完模式標本の再記載
- 著者
- 仲谷 一宏
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.469-473, 1983-03-10 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 6
タイワンザメProscyllium habereriは台湾・高雄から得られた成体雄1尾の標本に基づいてHilgendorf (1904) により記載された.その後, Tanaka (1912) は日本からヒョウザメCalliscyllium vemstumを記載したが, この両種の取り扱いは研究者により様々である.今回, タイワンザメの完模式標本 (ZMB16201) を調査し, ヒョウザメの原記載と直接比較する機会を得たが, 現在のところ, 両者のもっとも大きな差異は斑紋であった.しかし, タイワンザメの模式模本の体色, 斑紋は消失しつつあり, さらに原記載が簡単で図もないため, ここに詳細な完模式標本の再記載を行った。なお, タイワンザメととヨウザメの分類学的関係については将来の研究が必要である.
1 0 0 0 OA BLSと迅速な減圧が功を奏した緊張性気腹の1例
- 著者
- 爲廣 一仁 靍 知光 古賀 仁士 島 弘志 黒田 久志 田中 将也 瀧 健治
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.9, pp.734-738, 2014-09-15 (Released:2015-01-19)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 2
上部消化管内視鏡検査中に緊張性気腹から心肺停止(cardiopulmonary arrest: CPA)に陥ったが,迅速な減圧により救命できた症例を経験した。症例は63歳の男性。心窩部痛のため前医を受診した。前医で上部消化管内視鏡検査中にCPAとなり,心肺蘇生を行いながら搬入された。頸静脈怒張と著明な腹部膨満を認めた。上部消化管内視鏡検査中に生じた緊張性気腹と診断し,tube drainageを行った。腹部は平坦となり,心拍が再開し,大網充填術を行った。術後,集中治療を要したが,後遺症なく退院となった。緊張性気腹は非常に稀な病態で報告は少ない。緊急性が高いことと,減圧により病態を改善させることが可能であることを認識する必要がある。またCPAであっても,的確な一次救命救急処置(basic life support: BLS)と迅速な診断,迅速な減圧により予後良好な転帰が得られる。
1 0 0 0 OA 脳内局所組織酸素飽和度 (rSO2) の観察を契機として高度内頸動脈狭窄症を覚知した1例
- 著者
- 堀籠 啓太 伊藤 聖学 大河原 晋 相川 利子 今田 悟 宮澤 晴久 下山 博史 高雄 泰行 下山 博身 渡部 晃久 森下 義幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.77-83, 2020 (Released:2020-02-28)
- 参考文献数
- 18
症例は61歳, 男性. 糖尿病性腎症による慢性腎不全により, 週3回の血液透析 (HD) 中であり, 透析後半に頻回の血圧低下を起こしていた. 身体所見や心胸郭比, 循環血液量モニタリングからは適正な体液の状態と判断していた. 本人の同意を得たうえで, 脳内局所酸素飽和度 (rSO2) のモニタリングを行った. HD中のモニタリングでは, HD開始120分後まで緩徐に平均血圧が低下した際, 右前額部において脳内rSO2の低下が観察された. 脳内の虚血性病変を疑い, 核磁気共鳴画像を撮影したところ, 右内頸動脈の高度狭窄が確認された. 単一光子放射断層撮影では安静時の脳血流は保たれていたため, 手術には至らず, 現在も経過観察中である. HD患者の脳内rSO2のモニタリングは脳内虚血性疾患の診断に寄与する可能性がある.
1 0 0 0 OA 1930年前後の日ソ茶貿易
- 著者
- 吉田 建一郎
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.57-75, 2020 (Released:2020-08-06)
1 0 0 0 OA 累進屈折力レンズ処方後の不適切なフィッティングに関する調査
- 著者
- 有賀 義之 梶田 雅義
- 出版者
- 日本眼光学学会
- 雑誌
- 視覚の科学 (ISSN:09168273)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.66-71, 2017 (Released:2017-11-03)
- 参考文献数
- 5
【目的】累進屈折力レンズ(PAL)のフィッティング不適切例に対し, どのような調整を必要としたかを調査した。また, フィッティングの調整による不具合の改善を他覚的に評価できるか検討した。【方法】対象はPALを処方し2015年5月から1年の間に再来があった患者のうち, 不適切なフィッティングが認められた137名である。そのうちの3名については, PAL装用下のフィッティング調整前後でSpotTM Vision Screener(スポットビジョン)による測定を行い, 等価球面度数(SE)を比較した。【結果】頂点間距離の調整を要したのは84名, 遠用フィッティングポイント(FP)の調整を要したのも84名であった。そのうちの3名6眼の平均SEは調整前-0.56±0.44D, 調整後-0.33±0.47Dで有意差があった(t検定, p=0.0001)。【結論】PALの不具合を訴える場合, 頂点間距離と遠用FPを点検することが重要である。また, スポットビジョンは不適切なフィッティング症例の他覚的評価に有用であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 聖書における「愛」と「誠実」
- 著者
- 樋口 進
- 出版者
- 学校法人 夙川学院 夙川学院短期大学
- 雑誌
- 夙川学院短期大学教育実践研究紀要 (ISSN:18835996)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.13, pp.3-8, 2019 (Released:2019-10-04)
- 参考文献数
- 7
夙川学院に短期大学が設置されたのは、1965 (昭和40)年1月25日であり、同年4月20日に開学式を挙行して、教育が開始された。このとき、短大の教育理念は特には定められなかったが、戦後夙川学院が教育理念とした「キリスト教精神」は前提であったようである。しかし、礼拝とかキリスト教の授業科目を配置するということはなかった。ただ、入学式や卒業式が礼拝形式で行われ、またクリスマス行事などもあり、ここにわずかに「キリスト教精神」が生きていたと言うことができる。『九十年史』には、二代目学長の高木俊蔵の文として次のように記されている。「夙川学院は古くから宗教的情操教育を重視し、短大も創設以来この伝統を守ってきた1。」そして、短大の「教育理念」としては、1980 (昭和55)年に次のように定められた。すなわち、「愛と誠実」「清新な学識」「清楚にして優雅」である。これは、短期大学 教授の増谷くらの提案をもとにして専門委員会、教授会で検討したものということである2。『百年史』には、次のようにある3。「第一項では女性といわず、人間として基本的に求められる項目が述べられ、第二項では、教養豊かにして、専門とする学識に秀で、技能に熟達した女性が、社会の発展に寄与することを願い、短期大学が教授するものは、諸学•技術の基礎から、現代におけるその展開•応用に至ることを示唆している。そして学生が、自発的に研鑽し、探究心 を深めてくれるように願っているのである。第三項では、本学の学生が歴史と伝統に育まれた夙川学院の構成員としての自覚と誇りを持って、しかも学生らしく清楚であって、言動優雅であることを希求しているのである。」この中で、第一項の「愛と誠実」に関しては、夙川学院が戦後教育理念としたキリスト教思想を反映したものと思われる。イエス•キリストは、最も重要なこととして、「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい」ということと、「隣人を自分のように愛しなさい」ということを教えた(マタイによる福音書22:37-39、マルコによる福音書12:29-31)。また、イエス•キリストは、「正義、慈悲、誠実を最も重要なこととして行うべきだ」と教えている(マタイによる福音書23:23)。以下、聖書において「愛」と「誠実」がどのように言われているかについて検討したい。
1 0 0 0 OA 日本輸血学会40年のあゆみ その5
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血学会雑誌 (ISSN:05461448)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.150-185, 1993-03-01 (Released:2010-03-12)
1 0 0 0 OA サブカルチャーとビジネス:小劇場演劇の「商業(主義)化」についての組織的分析
- 著者
- 佐藤 郁哉
- 出版者
- 茨城大学人文学部
- 雑誌
- 茨城大学人文学部紀要. 人文学科論集 (ISSN:03886875)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.1-39, 1995-03
1 0 0 0 OA 吐血,意識障害で救急搬送された子癇の1例
- 著者
- 森 将 岸上 靖幸 伊藤 泰広 金 明 森部 真由 柴田 崇宏 稲村 達生 上野 琢史 山田 拓馬 竹田 健彦 宇野 枢 田野 翔 鈴木 徹平 小口 秀紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.182-188, 2021 (Released:2021-05-10)
- 参考文献数
- 23
症例は35歳,妊娠35週3日.吐血によるショックバイタルと意識障害の事前情報で当院に救急搬送された.消化管出血はなく,舌咬傷と口腔内出血がみられ,血圧182/130mmHg,尿蛋白定性は4+であった.胎児心拍数は70-100bpmと胎児徐脈を認めた.子癇による痙攣後の意識障害と,舌咬傷による口腔内出血,痙攣に伴う低酸素血症による胎児機能不全と診断した.ニカルジピン塩酸塩,硫酸マグネシウム投与後に母体循環動態,胎児心拍数は改善した.MRIではPRESの所見を認め,意識障害が遷延するため,緊急帝王切開を施行した.分娩後,意識障害,PRESの所見は改善し,血圧も安定し,術後11日目に退院となった.児は日齢18で退院となり,その後,発達に異常はみられていない.子癇では母体治療により児の状態改善も期待できるため,妊婦の意識障害では,常に子癇を鑑別に挙げることが重要である.また,舌咬傷による口腔内出血を吐血と誤診する可能性も念頭に置く必要がある.
1 0 0 0 良心的兵役拒否の潮流 : 日本と世界の非戦の系譜
1 0 0 0 徴兵制と良心的兵役拒否 : イギリスの第一次世界大戦経験
1 0 0 0 兵役拒否の人権化は世界の流れ : 国際人権法・憲法からみる
1 0 0 0 良心的兵役拒否の思想
1 0 0 0 OA 美の生物学的起源—比較認知科学のアプローチ
- 著者
- 渡辺 茂
- 出版者
- 日本視覚学会
- 雑誌
- VISION (ISSN:09171142)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.1-3, 2015 (Released:2018-11-29)
1 0 0 0 OA 小学校体育におけるベースボール型授業の実施状況とその課題
- 著者
- 大田 穂 小出 真奈美 岩間 圭祐 鈴木 由香 木塚 朝博
- 出版者
- 日本体育科教育学会
- 雑誌
- 体育科教育学研究 (ISSN:13428039)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.13-25, 2022-09-30 (Released:2023-03-23)
- 参考文献数
- 30
This study examined baseball-type lessons offered in physical education classes and clarified the issues that arose while implementing such lessons at the elementary school level. The participants were elementary school teachers working in T Ward, Yokohama City. We collected data using a self-administered questionnaire. Results indicated that: a) the lesson that was most frequently offered in all grades was T-ball, and b) 30% of baseball-type lessons were not implemented for classes between 3rd and 6th grades. From the systematic learning perspective, it is necessary to identify teaching materials and criteria for progressing from easy to difficult lessons in terms of skills and game-judgment. Additionally, while implementing baseball-type lessons, many novice female teachers were worried about their knowledge and skills, suggesting that they needed support. Furthermore, as many of the reference materials, videos, and new teaching materials about baseball-type lessons were not well known, improvements are needed to make these more known. In conclusion, improvements based on these results could lead to more effective and efficient implementation of baseball-type lessons in elementary school physical education.
- 著者
- 高橋 浩 南 雅代
- 出版者
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2023-04-01
水の溶存無機炭素(DIC)分析では、試料採取から分析までの期間に生物活動によりDICが変化しないように、塩化第二水銀の添加が認知されているが、水銀の錯体形成等の影響や環境負荷が大きいことが問題である。そこで、水試料のDIC変化を防ぐ処理として、塩化ベンザルコニウム(BAC)の添加とろ過を併用した手法を確立する。具体的には、ろ過実施に関するブランク検証と最適なろ紙孔径の選択、BACの添加によるブランクの低減手順の検証、複数の天然試料を用いた処理の有効性の検証を行う。本研究により水銀を使用せずに正確なDIC分析が可能となることで、分析の効率化と安全性の向上を実現し、将来にわたって大きな貢献となる。