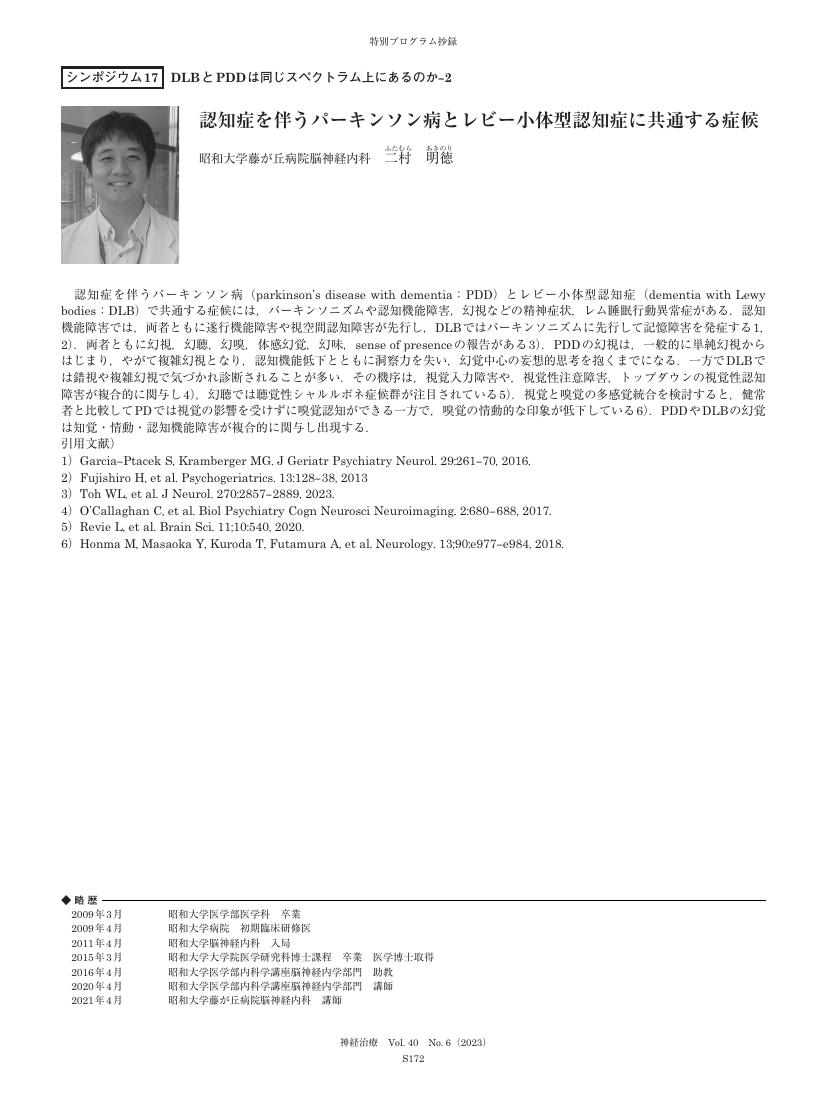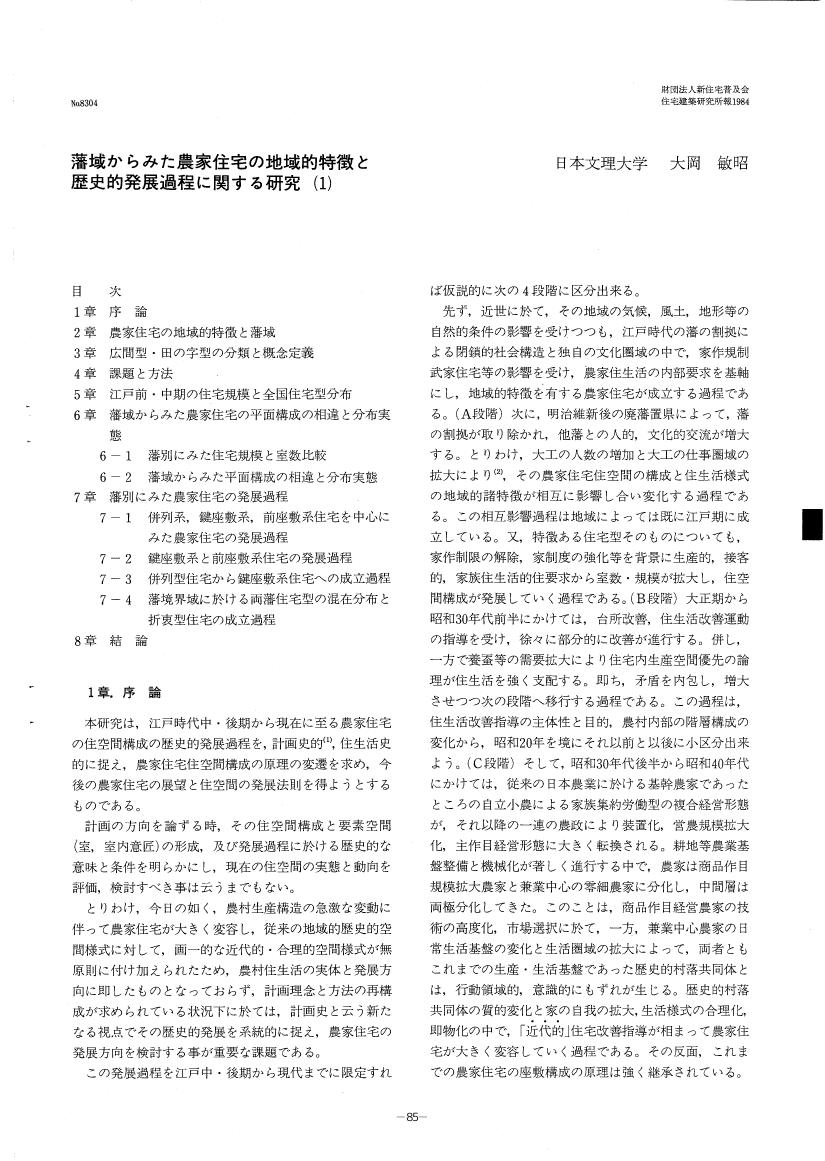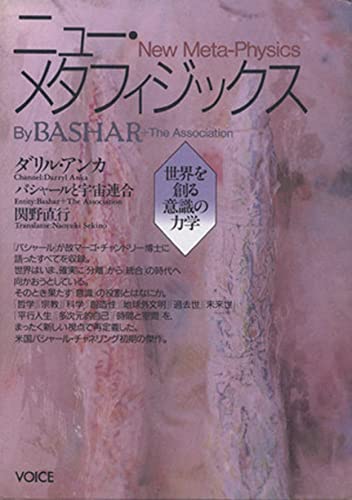1 0 0 0 OA 看取り・医療処置導入以外の事例において退院支援看護師が訪問看護導入を判断する要因
- 著者
- 菱田 一恵 藤田 淳子
- 出版者
- 学校法人 順天堂大学医療看護学部
- 雑誌
- 医療看護研究 (ISSN:13498630)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.9-18, 2023 (Released:2023-10-26)
- 参考文献数
- 12
退院支援看護師が、看取り・医療処置導入以外の事例に対して、訪問看護導入を判断する要因を明らかにすることを目的として、退院支援看護師7名に対し訪問看護の導入を判断した事例の状況と判断の過程に関する半構成的インタビューを行い、質的帰納的に分析した。その結果、看取り・医療処置導入以外の事例において、退院支援看護師が訪問看護導入を判断する要因として、【患者・家族の不安】【医療的視点での介入の必要性】【家族支援の必要性】【将来予測される病状・成長発達・療養上の課題】【疾患や患者・家族の状況に応じたタイミング】【病状変化の早期発見と適切な支援へつなぐ必要性】【患者・家族の関係や生活の把握困難】の7カテゴリーが抽出された。退院支援看護師は、療養者・家族の生活全体をとらえながら訪問看護の必要性を判断し、疾患の特徴をふまえた今後の長期的な予測の中で訪問看護導入の時期やタイミングを見極めていた。今後さらに複数の疾患を持ち療養の場を移行する患者の増加が考えられ、訪問看護導入のタイミングを考慮すべき疾患や疾患ごとの訪問看護導入のタイミングをより明確にしていく必要があることが示唆された。
1 0 0 0 OA 認知症を伴うパーキンソン病とレビー小体型認知症に共通する症候
- 著者
- 二村 明徳
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.S172, 2023 (Released:2023-10-30)
1 0 0 0 OA 拍動流灌流の生理学的意義
- 著者
- 草川 實 久保 克行
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.84-90, 1973-04-15 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 26
1 0 0 0 視覚障害者のアイデンティティをめぐる社会学的研究
- 著者
- Holger Steinbrenner Bodo Speckmann Antonio Pinto Helmut Sies
- 出版者
- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN
- 雑誌
- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.40-45, 2010 (Released:2010-12-28)
- 参考文献数
- 79
- 被引用文献数
- 127 145
The essential trace element selenium has long been considered to exhibit anti-diabetic and insulin-mimetic properties, but recent epidemiological studies indicated supranutritional selenium intake and high plasma selenium levels as possible risk factors for development of type 2 diabetes, pointing to adverse effects of selenium on carbohydrate metabolism in humans. However, increased plasma selenium levels might be both a consequence and a cause of diabetes. We summarize current evidence for an interference of selenium compounds with insulin-regulated molecular pathways, most notably the phosphoinositide-3-kinase/protein kinase B signaling cascade, which may underlie some of the pro- and anti-diabetic actions of selenium. Furthermore, we discuss reports of hyperinsulinemia, hyperglycemia and insulin resistance in mice overexpressing the selenoenzyme glutathione peroxidase 1. The peroxisomal proliferator-activated receptor gamma coactivator 1α represents a key regulator for biosynthesis of the physiological selenium transporter, selenoprotein P, as well as for hepatic gluconeogenesis. As proliferator-activated receptor gamma coactivator 1α has been shown to be up-regulated in livers of diabetic animals and to promote insulin resistance, we hypothesize that dysregulated pathways in carbohydrate metabolism and a disturbance of selenium homeostasis are linked via proliferator-activated receptor gamma coactivator 1α.
1 0 0 0 OA 肝硬変症に伴うこむら返り症状に対する分岐鎖アミノ酸の有用性
- 著者
- 後藤 紀子 飯田 和成 萩澤 良美
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.11, pp.590-599, 2001-11-25 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1 1
Child B及び一部 Child Cを含む29例の肝硬変患者に分岐鎖アルブミン製剤 (BCAA顆粒) を投与し, BCAA顆粒のこむら返り症状に対する投与効果を検討し, 投与前及び3カ月後においてアミノ酸分析を行った. 投与前においてこむら返り症状は66%に認められ, その発生回数 (0~20回/週) は血中タウリン濃度とのみ有意 (p<0.05) な逆相関関係が認められた.BCAA顆粒投与にて対象例全例の検討で体重, 総タンパク濃度, アルブミン濃度, 赤血球数に有意な上昇を認めた. こむら返り症状のある群 (19例) はBCAA顆粒投与後に有意(p<0.001) に発生頻度が低下しており, タウリン濃度の有意な上昇 (p<0.01) が認められた. また、メチオニン濃度の低下傾向 (p<0.1) を認め, タウリン合成活性化の関与が示唆された. BCAA顆粒は栄養状態の改善だけでなく, こむら返り症状の改善も望める治療法であると考えられた.
1 0 0 0 OA コロナ禍を生きるための判断力涵養教育 ― 求められる教育の姿の検討 ―
- 著者
- 楠美 順理 濱 泰一
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境教育学会
- 雑誌
- 環境教育 (ISSN:09172866)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.1_85-94, 2023-03-31 (Released:2023-04-29)
- 参考文献数
- 7
This study discusses education to foster the skills needed to select appropriate information from a large amount of complex information, and to make decisions under conditions of high uncertainty. Based on the question of whether the COVID-19 vaccination is necessary, this study focuses on discussions of the framework of education to foster judgement skills. First we examined rational judgement methods and determined the requirements for judgement education. Then we examined methods for risk education and determined the requirements for that. Finally we examined methods for critical thinking education and determined the requirements for that. Twelve requirements for the desired judgment education were listed and divided into categories based on the degree of reflection required and on who was implementing them. Briefly, A1 is what teachers do, and B1 is a requirement that can be measured at specific achievement levels. B2 is a requirement that should be met to the fullest possible extent. A sample course was designed to meet the requirements of A1 and B1, and to meet the requirements of B2 to the fullest possible extent. The course consists of three components: a “simple story” which supports vaccination based on estimated mortality risk, a “detailed story” which is more cautious in judgement and quantitative evaluation, and, lastly, the processes in which students construct their theories and refine them through discussion. While it is not easy to design a course that meets all 12 requirements, it is important to develop comprehensive skills to judge whether the vaccination is necessary. Reconfirming the importance of fostering skills such as critical thinking, judgement and expression, we created a basic framework to discuss the desired education to foster the skills needed to select appropriate information from a large amount of complex information and to make decisions under conditions of high uncertainty.
1 0 0 0 OA 民家
- 著者
- 宮澤 智士
- 出版者
- 建築史学会
- 雑誌
- 建築史学 (ISSN:02892839)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.161-171, 1984 (Released:2018-10-09)
1 0 0 0 OA 福井県の近世民家の類型
- 著者
- 宮沢 智士
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.46-51, 1963 (Released:2017-08-30)
This report forms a part of the studies on the farmhouses in Fukui-prefecture. We invastigated 34 farmhouses in various parts of Fukui prefecture. The date of farmhouses we invastigated extends from the 17th century to the 19th century. The first step to our investigation on the farmhouses is to know their original plan and constraction when they were first built. Next we tried comparing the plan and constraction in one place with them the other places. As the result of these studies we have found that the farmhouses in Fukui prefecture are grouped five types in style and form. The farmhouses that belong to first group are widely distributed in the Eehizen plains, the mountainaus district of Niu and these conected valley. The plan of these farmhouses are "Hiroma" style. The farmhouses that belong to the other four groups are distributed in the mountianaus distrct (Ohno-sanchi, Imadate-sanchi and East and West Wakasa district). The farmhouses that belong to the other four groups have their own features.
1 0 0 0 OA 近世民家が閉鎖的な間取りから開放的な間取りに変化した理由
- 著者
- 安田 徹也
- 出版者
- 建築史学会
- 雑誌
- 建築史学 (ISSN:02892839)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.133-134, 2016 (Released:2018-06-20)
1 0 0 0 OA 藩域からみた農家住宅の地域的特徴と歴史的発展過程に関する研究(1)
- 著者
- 大岡 敏昭 木村 永遠 中村 禎男 青木 正夫
- 出版者
- 一般財団法人 住総研
- 雑誌
- 住宅建築研究所報 (ISSN:02865947)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.85-111, 1985 (Released:2018-05-01)
1 0 0 0 OA 落ち葉の焼却から生成するダイオキシン類に関する考察
- 著者
- 早福 正孝 辰市 祐久 古明地 哲人 岩崎 好陽
- 出版者
- Japan Society for Atmospheric Environment
- 雑誌
- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.122-130, 2002-03-10 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
家庭用焼却炉を用いて3種の落ち葉 (ケヤキ, スダジイ, シラカシ) を焼却し, その結果を用いてダイオキシンの生成要因を考察した。葉, 焼却排ガス, 焼却灰中のダイオキシン類の濃度は, 葉の種類による大きな違いはなかった。しかしケヤキの排ガス中のダイオキシン類濃度のみは, スダジイ, シラカシに比べると高濃度であった。このケヤキの排ガス中ダイオキシン類の高濃度は, 葉中の塩素含有量に影響を受けているものと思われた。そこで, 都内の公園や街路における14種類の樹葉の塩素含有量を調査した。その結果, ケヤキの葉中の塩素含有量が最も多かった。焼却排ガス中のダイオキシン類濃度 (Y: ng-TEQ/m3N) と焼却物の塩素含有率 (X:%) の間にY=308X1.3(R2=0.9485n=12)の関係式が得られた。この式から, 塩素含有率が10倍ずつ増加すると, 焼却排ガス中のダイオキシン類濃度は約20倍ずつ増加することになる。塩素含有量の多いケヤキの葉の焼却排ガスは, 低塩素化ダイオキシン類を多く生成させた。
1 0 0 0 山陰地方のアクセント
1 0 0 0 幸福を求めて : ダルマと現代インド仏教徒
- 著者
- 龍谷大学アジア仏教文化研究センター編
- 出版者
- 龍谷大学アジア仏教文化研究センター
- 巻号頁・発行日
- 2015
1 0 0 0 OA 野口 芳子 著『グリム童話のメタファー 固定観念を覆す解釈』
- 著者
- 鶴田 涼子
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.156, pp.242-244, 2018 (Released:2019-03-31)
1 0 0 0 ニュー・メタフィジックス : 世界を創る意識の力学
- 著者
- ダリル・アンカ[著] 関野直行訳
- 出版者
- ヴォイス
- 巻号頁・発行日
- 1991
1 0 0 0 OA 栃木県那珂川町小砂地区の農村集落景観の特徴と審美的原理
- 著者
- 大澤 啓志 谷藤 圭悟
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.5, pp.605-610, 2019-03-29 (Released:2019-07-03)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1
We researched the hidden characteristics of the rural settlement landscape of Koisago District, Nakagawa Town. As a result of an investigation of twenty-two traditional residences in 2016, we recognized a sustainable land use and building arrangement based on the local conditions of the topography and the ecosystem. Furthermore, the existence of Ujigami-sama, located in the forest behind the main building, was significant. The back forest ecosystem has provided residents with ecological goods and services. It became clear that the sequence that corresponds to the topography, such as “own forest-residence- field-rice paddy-others’ forest,” is a basic pattern. Unity in diversity occurred there because of land use sequencing with living spaces where life is intertwined and farm production stands in a row at the foot of a mountain. Further, we considered the comfortableness of the settlement landscape, as an aesthetic principle, because the ecological stability of a living space combined with resident's thorough management in the rural village.
1 0 0 0 OA IgA腎症の最新治療とその背景
- 著者
- 鈴木 祐介 二瓶 義人 鈴木 仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.10, pp.2286-2292, 2021-10-10 (Released:2022-10-10)
- 参考文献数
- 17
IgA(immunoglobulin A)腎症は,世界で最も頻度の高い原発糸球体腎炎で,特に日本を含む東アジアで頻度が高い.未治療の場合,約4割が末期腎不全に至る予後不良の疾患であり,国内外を問わず本症に起因し若くして維持透析となる患者は多く,医療経済上も深刻な問題となっている.近年,糖鎖異常IgAと関連免疫複合体が本症の発症・進展のカギを握ることが証明され,その産生抑制と糸球体沈着後の炎症制御を目的とした治療薬の開発が進んでいる.なかでも,粘膜面で感作を受けた成熟IgA産生B細胞を標的とした薬剤や,糖鎖異常IgAの糸球体沈着に伴い活性化される補体古典経路及びレクチン経路を標的とした薬剤の国際治験が進行中で,その結果が期待されている.こういった複数の有望な根治治療薬の開発が進み,治療選択肢が増えれば病期・病態に応じた治療が可能となり,本症による透析移行の阻止は実現可能と考える.本稿では,これら薬剤に関する病態の背景や,現状を概説する.
1 0 0 0 OA 愛着の視点からの発達支援 愛着障害支援の立場から
- 著者
- 米澤 好史
- 出版者
- 日本発達支援学会
- 雑誌
- 発達支援学研究 (ISSN:24357626)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.59-69, 2022-03-31 (Released:2023-03-31)
本稿では、愛着障害への支援の専門家としての実践活動、実践研究から得られた経験から、発達支援において愛着の視点からの支援の重要性について提唱したい。保育、教育、福祉、医療の現場に直接、足を運びながら、発達支援にかかわり、また、発達支援者にかかわる中で、何も愛着障害の支援だけではなく、発達障害やその他の発達支援においても、発達の基盤としての愛着形成が様々な支援の土台になっていることを提唱する。そもそも愛着障害をどう捉えるべきなのか、愛着形成が発達においてどのような意味を持っているのかについて論じつつ、愛着障害についての誤解、無理解が発達支援において、より適切な支援の妨げになってすらいることについても、愛着障害と発達障害の関係を論じながら指摘する。併せて、さまざまな発達の問題、こころの問題への愛着の視点からの支援のポイント、支援のあり方について紹介する。