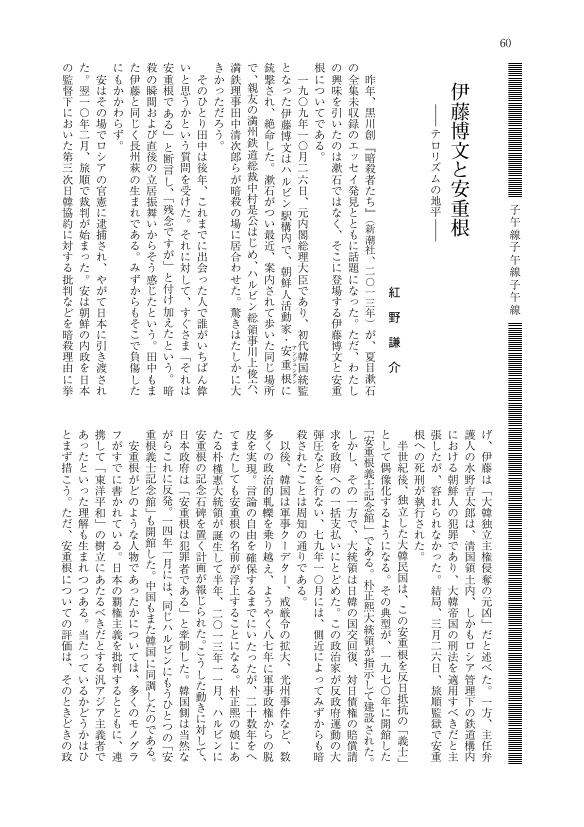- 著者
- 中林 寿文
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 夏季研究発表大会 予稿集 2023夏季研究発表大会 (ISSN:27584801)
- 巻号頁・発行日
- pp.164-168, 2023 (Released:2023-10-28)
- 参考文献数
- 19
アミューズメントゲーム機は筐体のデザイン、コントローラー、ソフトウェアの総体として構成されている。これらを保管・展示する重要性は増しているが、動態保存し試遊展示する為の保守手法は必ずしも整理されてはいない。そこで、本稿では一定量量産される工業製品である点に着目して、次世代に引き継ぐために資料の劣化を防ぐ方法と保存修復について検討する。
1 0 0 0 OA 真島正市先生と応用物理
- 著者
- 磯部 孝
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.11, pp.780-781, 1965-11-10 (Released:2009-02-09)
1 0 0 0 OA データマイニング手法の安全対策業務への導入と活用
- 著者
- 松井 和浩 飯村 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.543-547, 2014 (Released:2016-07-02)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 3
1967年に始まった市販後医薬品の副作用報告制度に基づく報告件数は増加の傾向にあり,ここ数年は企業報告の国内事例だけで年間3万件を超えている.諸外国規制当局では1998年から2000年代前半にかけて,副作用報告症例のデータベースから機械的かつ網羅的に未知の副作用候補を見つけ出すこと,すなわちシグナル検出のためのデータマイニング手法が開発・実践されていた.我が国においても,安全性監視の充実策の1つとして,予測・予防型の安全対策の必要性が高まる中,医薬品医療機器総合機構(PMDA)の第一期中期計画の中でデータマイニング手法の安全対策業務への導入検討および支援システムを開発し,2009年4月より活用している. 本稿では,データマイニング手法によるシグナル検出の概要およびPMDAにおける安全対策措置への活用事例を紹介する.
1 0 0 0 OA 伊藤博文と安重根 ――テロリズムの地平――
- 著者
- 紅野 謙介
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.10, pp.60-61, 2014-10-10 (Released:2019-11-01)
1 0 0 0 水-植物油エマルジョン燃料の精製とその物性及び燃焼特性評価
- 著者
- 松口 義人
- 出版者
- 福島工業高等専門学校
- 雑誌
- 奨励研究
- 巻号頁・発行日
- 2007
【研究目的】化石燃料の代替え品として水-植物油エマルジョン燃料をディーゼル機関で使用するために,以下の項目を調査・実験・評価し,最適なエマルジョン燃料を精製する.(1)植物油の基礎特性調査,(2)エマルジョン燃料の基本的性質の調査,(3)エマルジョン燃料の燃焼評価.【実験方法】渦流室ディーゼル機関を用いて,軽油,大豆油100%,エマルジョン燃料について,各燃料の温度による粘度変化の測定並びに燃焼実験を行った.粘度変化は音叉型の粘度計を用いて,10℃から70℃までの変化を測定した.また,燃焼実験は全負荷で行い,回転数1000〜3000rpmまでの範囲でデータを採取した.【実験結果】各燃料ともに温度が上昇するに従い粘度が低くなる傾向が見られた.特に,植物油,エマルジョン燃料は温度による粘度変化が大きく,大豆油は10℃から70℃の範囲で90〜13.7mPa・s,エマルジョン燃料で81.4〜11.9mPa・sとなり,軽油よりも温度による依存性が高い結果となった.また,若干ではあるが植物油に水を加えることで粘度が低減されたことが伺える.また、燃焼実験では,各燃料ともに回転数が増加するに従って,トルクが減少し出力が増加する傾向となった.中でも,エマルジョン燃料はトルクの減少が少なく,トルク,出力は最も高い値となった.また,低出力時ではエマルジョン燃料の燃料消費率が最も多くなったが,出力が高くなるに従い各燃料ともほぼ同等の値となった.熱効率では,軽油に比べてエマルジョン燃料の方が高い値となった。水を加えることでミクロ爆発を起こし,油滴が微粒子化され燃焼していると考えられる事から,窒素酸化物や粒子状浮遊物質を削減する効果があるものと推測できる.今後,エマルジョン燃料の実用化を実現させるためには,適正な水と植物油の混合割合の見極めとともに低い燃料温度での特性を調査していくことが必要であると考える.
1 0 0 0 OA 茶抽出液の粘度に関する研究(第1報)
- 著者
- 岡田 文雄 古谷 弘三
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.7, pp.267-273, 1965-07-15 (Released:2009-04-21)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 2
多重段浸出法で抽出液を得る場合,濃度の増加に伴って抽剤の圧力が増し,流れは低下する。これの原因のひとつに粘度の影響が考えられることから,茶種別抽出液の粘度を調査したが,その結果を要約するとつぎのごとくである。(1) 茶種別抽出液の粘度は煎茶が高く,ついで紅茶,ほうじ茶の傾向で,また濃度との関係は,高粘度における差は大きいが,希釈することによって,粘度の低下は緩慢となる。(2) 温度が粘度に及ぼす影響は,他の液体の場合と同様,低温で高く,温度が上昇するにつれて低くなり,したがって流動率は大きくなって液の流れは容易となる。また,茶種別の粘度の差異と,濃度の違いによる粘度のひらきは,温度が高くなるにつれて僅少となった。(3) 抽出時の抽剤温度の違いを,60℃と70℃で比較したが,一定の傾向はみられなかった。(4) 沈殿物は茶種によってその形態が異なり,煎茶のものが真綿状に連なったのに比べ,紅茶は同じ形でも短くきれ,ほうじ茶は断片的な形態を示した。(5) ペクチンおよび沈殿物の含有量は,ほうじ茶に多く紅茶に少なく,また両者の間にはr=0.929と1%の水準で正の相関関係が認められた。(6) 沈殿物の粘度について,抽出液を対照にその溶液を比較した。その結果,各茶種とも両者の値に差が認められず,抽出液の粘度には,この沈殿物の影響がかなり大きいものと思われた。沈殿物と粘度との関係は,沈殿物の量より茶種別によって異なる沈殿物の形態が,粘度に作用するもののようで,この点についてはさらに検討する必要がある。(7) 気泡が粘度に及ぼす影響は,気泡の混入が多くなるにつれて抽出液の粘度も急増し,流動率は低下する。また濃度は同じでも液温の低いものが気泡の影響は顕著で,粘度の増加も著しい。
1 0 0 0 OA 対人関係におけるセルフモニタリングの概念分析
- 著者
- 田中 広美
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護学教育学会
- 雑誌
- 日本看護学教育学会誌 (ISSN:09167536)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.13-23, 2018-11-01 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 43
〔目的〕対人関係におけるセルフモニタリングの概念分析を行い、定義を明確にすることを目的とする。〔方法〕Rodgersら(2000)の概念分析の手法を参考に、先行要件、属性、帰結、関連概念、定義を検討し分析した。〔結果〕30論文を分析した結果、先行要件は社会的特性、自己の内的特性の2カテゴリ、属性は観察、状況の察知、状況に対する行動の選択とコントロールの3カテゴリ、帰結は状況を見極めた行動、自己の内面的変化の2カテゴリが導き出された。〔結論〕本概念は、対人関係における自身の状況を、意図的にモニターする際の視点として有用であり、経験として蓄積し、実践知へ移行させ、看護実践の向上が可能と考える。
1 0 0 0 OA 無限自由度の正準交換関係の表現とこれに同伴する第2量子化作用素について
- 著者
- 細田 優人
- 巻号頁・発行日
- 2014-03-25
場の量子論の数学的モデルを構成する上で基礎となるものがフォック空間である。特に、ボース場のモデルを構成する上で基礎となるものはボソンフォック空間と呼ばれ、その上で働く生成・消滅作用素は重要な役割をもち、正準交換関係 (canonical commutation relations ; CCR) という特徴的な交換関係を満たす。この代数的な関係式であるCCR に着目し、これを満たすようなものを一般的に考察していくことにより、より普遍的な量子場の数学的構造が明らかとなる。
1 0 0 0 OA <論説>伊勢治田銀銅山史の研究
- 著者
- 小葉田 淳
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学文学部内)
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.153-212, 1975-03-01
個人情報保護のため削除部分あり
1 0 0 0 OA 胃全摘術後に脾動脈仮性動脈瘤を生じ大量吐血を来した1例
- 著者
- 山吉 隆友 下山 孝俊 山下 秀樹
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.10, pp.2721-2725, 1999-10-25 (Released:2009-08-24)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
症例は56歳の男性で胃小彎の4型胃癌に対し胃全摘術を施行,腹腔動脈~脾動脈周囲リンパ節に転移があり可及的な郭清を行った.術後60日目に突然の大量吐血が出現し,腹腔動脈造影で脾動脈根部に仮性動脈瘤を認め,これが再建に用いた空腸係蹄に穿破したものと考えられた.再び吐血が生じたため緊急血管造影を施行,金属コイルを用いて塞栓を行い良好な経過が得られた.定期的なCTの観察では動脈瘤はほとんど指摘できなくなっている.上部消化管癌手術後に生じる仮性動脈瘤について本邦の文献を集計し,成因,治療を中心に考察した.
1 0 0 0 OA グリコアルブミン(GA)
- 著者
- 清水 弘行
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.11, pp.2862-2867, 2010 (Released:2013-04-10)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 管楽器の空力音響解析
- 著者
- 吉永 司 横山 博史
- 出版者
- 一般社団法人 日本フルードパワーシステム学会
- 雑誌
- フルードパワーシステム (ISSN:13467719)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.170-174, 2022 (Released:2023-11-02)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 「大人のための科学実験教室(2年次)」実施報告 : 平成25年度千代田学採択事業
- 著者
- 山﨑 友紀
- 出版者
- 法政大学多摩研究報告編集委員会
- 雑誌
- 法政大学多摩研究報告 = 法政大学多摩研究報告 (ISSN:09125736)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.69-89, 2014-05-30
1 0 0 0 OA 食肉の格付けとブランド化の課題
- 著者
- 甲斐 諭
- 出版者
- 公益財団法人 生協総合研究所
- 雑誌
- 生活協同組合研究 (ISSN:09111042)
- 巻号頁・発行日
- vol.499, pp.15-21, 2017-08-05 (Released:2023-04-05)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA Amebiasis as a sexually transmitted infection: A re-emerging health problem in developed countries
- 著者
- Akira Kawashima Yasuaki Yanagawa Rieko Shimogawara Kenji Yagita Hiroyuki Gatanaga Koji Watanabe
- 出版者
- National Center for Global Health and Medicine
- 雑誌
- Global Health & Medicine (ISSN:24349186)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023.01064, (Released:2023-10-29)
- 参考文献数
- 77
Amebiasis, which is caused by Entamoeba histolytica (E. histolytica), is the second leading cause of parasite-related death worldwide. It manifests from asymptomatic carriers to severe clinical conditions, like colitis and liver abscesses. Amebiasis is commonly seen in developing countries, where water and food are easily contaminated by feces because of the poor sanitation. However, a recently challenge in many developed countries is the increase in domestic cases of invasive amebiasis as a sexually transmitted infection (STI amebiasis). In contrast to food-/waterborne transmission of E. histolytica in developing countries, transmission of STI amebiasis occurs directly through human-to-human sexual contact (e.g., men who have sex with men and people who engage in oral-anal sex); in this setting, asymptomatic infected individuals are the main reservoir of E. histolytica. The Development of screening methods for the early diagnosis of asymptomatic E. histolytica infection is the key to epidemiologic control. Moreover, delay in diagnosis of severe cases (e.g., fulminant amebiasis) leads to death even in developed countries. It is also important to increase clinical awareness of domestically transmitted STI amebiasis in the clinical settings. This review considers the changing epidemiology and clinical manifestations of STI amebiasis, and finally discusses the future strategies for the better practice.
1 0 0 0 新幹線回送線・車両センターにおけるローカル5G検証試験
- 著者
- 洞井 裕介 領木 慎一 山下 真弘 長坂 雄一 仙田 航基 坂本 洋介
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J106-B, no.8, pp.582-593, 2023-08-01
ローカル5Gは,携帯電話事業者による全国向けの5Gとは別に,5Gを企業等が自らの建物,敷地内で整備できる制度である.鉄道事業者においてローカル5Gを導入するためには,車両走行中の伝送品質等の動的変化や,敷地外へ漏れる電波の影響について,鉄道固有環境での検証が必要である.今回,新幹線回送線沿いにローカル5Gシステムを構築し,指令からの監視等,走行中の回送車両上から地上への映像伝送や,車両センターにおける保守作業にローカル5Gを活用することを念頭に試験を実施し,ローカル5Gにおける伝送品質等の動的変化,映像伝送特性,車両センター着発収容庫車両内の電波特性,敷地外電波強度に関するデータを収集・解析し,鉄道固有環境が及ぼす影響を検証した.その結果,回送車両上と地上との間で,システム仕様上の最大スループットを達成し,地上への4Kカメラ映像伝送に成功した.また,車両センター着発収容庫内の電波環境を明らかにした.更に,自己土地から最大約1 km離れた地点で,制度上調整対象区域とされる強度の電波を観測した.そして,使用環境が屋外か屋内かにかかわらず,自己土地外での電波強度確認が必要であることを明らかにした.
- 著者
- 竹村 和人 向川 均
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.1, pp.5-19, 2023 (Released:2023-02-07)
- 参考文献数
- 45
本研究では、夏季アジアジェット出口付近でロスビー波の砕波を伴うシルクロードパターンが、太平洋・日本(PJ)パターンを引き起こす割合を調査した。ここで、シルクロードパターン事例は、ユーラシア大陸上での対流圏上層の南北風の主成分分析に基づき、黄海及び日本付近が高気圧性偏差となるパターンで特徴づけられる第1、2主成分を用いて抽出した。さらに、抽出した事例を、砕波を伴う事例と伴わない事例に分類した。 砕波を伴うシルクロードパターン事例では、アジアジェット出口付近の上層での高気圧性偏差は、砕波を伴わない事例と比べて東西により広がった形状を持ち、振幅も大きい。この事例の合成図では、シルクロードパターンに伴う波列パターンがユーラシア大陸上に存在し、アジアジェット出口付近で砕波を伴っていた。砕波の発生は、砕波域でのアジアジェットの強い減速及び分流と関連する。また砕波は、上層の高渦位気塊の進入を通して、砕波域の南側で活発な対流活動を促し、PJパターンを形成する。合成図において出現する明瞭なPJパターンは、南側で低気圧性偏差、北側で高気圧性偏差を持つ双極子構造を示す。そして、砕波を伴うシルクロードパターン事例の約60~70%が、PJパターンを伴っていた。 一方、砕波を伴わないシルクロードパターン事例の合成図では、ユーラシア大陸上で波列パターンは存在するが、砕波域の南側で活発化した対流活動及びPJパターンは存在しない。そして、砕波を伴わないシルクロードパターン事例の約40~50%がPJパターンを伴っていた。したがって、砕波によって正のPJパターンの出現頻度は1.2~1.7倍に増加し、砕波はPJパターンの励起に重要な役割を果たしていることが明らかになった。
1 0 0 0 OA 抗N–methyl–D–aspartate受容体脳炎の動向
- 著者
- 亀井 聡
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.327-331, 2022 (Released:2022-11-22)
- 参考文献数
- 23
NMDA receptor encephalitis is a common autoimmune encephalitis characterized by complex neuropsychiatric features and the presence of IgG antibodies against the NR1 subunit of the NMDA receptors in the central nervous system. This encephalitis start with flu–like symptoms, followed by fairly rapid development of psychiatric symptoms, memory problems, movement disorders, seizures, coma and even changes in heart rate, blood pressure. Based on the clinical analysis of 1147 patients, although there is a difference in severity, 90% of patients presented a similar clinical course. On the other, recent researches discovered that the clinical picture is widespread and it is known to present as a psychiatric disorder (autoimmune psychosis), temporal lobe adult–onset seizure (autoimmune epilepsy), and progressive dementia (autoimmune dementia). In the treatment of this encephalitis, the development has been showed in the treatment of refractory cases (such as Tocilizumab or Bortezomib) and symptomatic epilepsy.