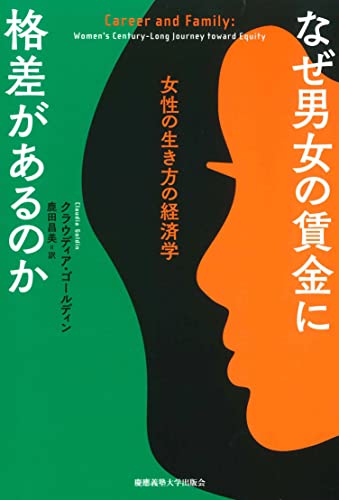- 著者
- रणजीत सिंह कूमट
- 出版者
- कम्पानी चेरिटेबल ट्रस्ट : शंकर फाउण्डेशन
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 OA Signal sequence-triage is activated by translocon obstruction sensed by an ER stress sensor IRE1α
- 著者
- Ashuei Sogawa Ryota Komori Kota Yanagitani Miku Ohfurudono Akio Tsuru Koji Kadoi Yukio Kimata Hiderou Yoshida Kenji Kohno
- 出版者
- Japan Society for Cell Biology
- 雑誌
- Cell Structure and Function (ISSN:03867196)
- 巻号頁・発行日
- pp.23072, (Released:2023-09-28)
Secretory pathway proteins are cotranslationally translocated into the endoplasmic reticulum (ER) of metazoan cells through the protein channel, translocon. Given that there are far fewer translocons than ribosomes in a cell, it is essential that secretory protein-translating ribosomes only occupy translocons transiently. Therefore, if translocons are obstructed by ribosomes stalled or slowed in translational elongation, it possibly results in deleterious consequences to cellular function. Hence, we investigated how translocon clogging by stalled ribosomes affects mammalian cells. First, we constructed ER-destined translational arrest proteins (ER-TAP) as an artificial protein that clogged the translocon in the ER membrane. Here, we show that the translocon clogging by ER-TAP expression activates triage of signal sequences (SS) in which secretory pathway proteins harboring highly efficient SS are preferentially translocated into the ER lumen. Interestingly, the translocon obstructed status specifically activates inositol requiring enzyme 1α (IRE1α) but not protein kinase R-like ER kinase (PERK). Given that the IRE1α–XBP1 pathway mainly induces the translocon components, our discovery implies that lowered availability of translocon activates IRE1α, which induces translocon itself. This results in rebalance between protein influx into the ER and the cellular translocation capacity.Keywords: endoplasmic reticulum, translocation capacity, translocon clogging, IRE1, signal sequence
1 0 0 0 OA 上直筋単独麻痺を呈した対側動眼神経核障害の一例
- 著者
- 古川 真二郎 山本 美紗 戸島 慎二 寺田 佳子 原 和之
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.91-95, 2015 (Released:2016-03-19)
- 参考文献数
- 15
【目的】神経線維が障害された場合の動眼神経麻痺では通常眼筋麻痺は障害側と同側に生じる。今回我々は左中脳梗塞により右眼上直筋麻痺を呈し、動眼神経上直筋亜核単独障害が疑われた一例を経験したので報告する。【症例】72歳、男性。仕事中に上下複視を自覚し近医受診。精査加療目的で当院神経内科を紹介受診した。頭部MRIでは左中脳内側に高信号域を認めた。発症より4日後、眼球運動精査目的で当科初診。初診時所見、両眼とも矯正視力(1.2)。遠見眼位はAPCTで右眼固視:20⊿外斜視9⊿左上斜視、左眼固視:20⊿外斜視8⊿右下斜視であった。9方向むき眼位検査及びHess赤緑眼に上転制限を認めた。複像間距離は右上方視時で最大となった。左眼の眼球運動には異常を認めなかった。瞳孔は正円同大で対光反射も迅速であった。上直筋の支配神経は中脳で交叉している事より、動眼神経上直筋亜核の障害に伴う対側上直筋麻痺であると考えた。1か月後、上下偏位は消失した。眼球運動は正常範囲内であり、全てのむき眼位で複視は消失した。【結論】対側上直筋単独麻痺を呈した動眼神経亜核障害の一例を経験した。過去に報告の少ない非常に稀な症例であったと考えられた。
1 0 0 0 OA ハリウッドにおけるスーパーヒーロー映画批判 -『複製技術時代の芸術』を踏まえて-
- 著者
- 李 夢秋
- 出版者
- 明治大学大学院
- 雑誌
- 教養デザイン研究論集 (ISSN:21856966)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.1-22, 2023-02-28
1 0 0 0 OA ピアノ打鍵動作の熟練技能:「重量奏法」の科学的検証
- 著者
- 古屋 晋一 片寄 晴弘 木下 博
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.SKL-01, pp.04, 2008-09-16 (Released:2021-08-31)
重力を利用して打鍵する「重量奏法」は、百年以上の間、ピアノ打鍵動作における熟練技能であると考えられてきた。本研究では、逆動力学計算と筋電図解析により、重量奏法が一流ピアニストのみが用いる運動技能であることを、世界で初めて実証することに成功した。
1 0 0 0 OA 「全世代型社会保障」構築への アジェンダ
- 著者
- 神野 直彦
- 出版者
- 公益財団法人 連合総合生活開発研究所
- 雑誌
- 連合総研レポートDIO (ISSN:27586030)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.1, 2023-03-01 (Released:2023-04-26)
1 0 0 0 OA 選択的表面染色法による魚類の味蕾分布の検索
- 著者
- 清原 貞夫 山下 智 鬼頭 純三
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.8, pp.1293-1297, 1984-08-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 3
A surface staining of taste buds was studied in the minnow Pseudorasbora parva, carp Cyprinus Carpio and blind cave fish Astyanax mexicanus by immersing the tissues in various kinks of staining solutions. The taste pores of buds in the lips, palatal organ and bucal cavity were found to be stained selectively with ponceau S or pontamine sky blue 6B dissolved in trichloroacetic acid solutions. In fresh material the dyes were restricted to only the taste pore regions while in fixed material they penetrated deeply into the buds as well ad into the general epithelium. This surface staining method enables a rapid location and counting of taste buds without preparing histological sections.
1 0 0 0 OA 風景画の現象学的考察
- 著者
- 佐藤 康邦
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.56, 2011 (Released:2022-12-15)
Es setzt nicht nur eine mechanistische Naturanschauung, sondern auch eine phänomenologische Naturauffassung voraus, dass man seine Umwelt als Landschaft sieht. Unter diesem Aspekt kann man die Geschichte des Landschaftsbildes betrachten. Man kann es daher als ein symbolkräftiges Ereignis in der abendländischen Ideengeschichte betrachten, dass Lorenzetti sein Landschaftsbild in Siena nur weniger Jahre später gemalt hat, nachdem Petrarca seine Bergbesteigung genossen hatte. Die Geschichte des Landschaftsbildes entsprach zuerst der Geschichte der Perspektive, dann der der naturwissenschaftlichen Weltanschauung.
1 0 0 0 OA 【投稿/レビュー】原発性線毛機能不全症候群
- 著者
- 森本 耕三 土方 美奈子 Guo Tz-Chun 宮林 亜希子 山田 博之 慶長 直人
- 出版者
- COSMIC
- 雑誌
- 呼吸臨床 (ISSN:24333778)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.6, pp.e00103, 2020 (Released:2022-10-22)
- 参考文献数
- 10
原発性線毛機能不全症候群(PCD)は主に常染色体潜性またはX連鎖性遺伝形式をとる先天性疾患の1つで,気道上皮細胞などに存在する運動性線毛や精子鞭毛の機能的障害を来し,臨床的には副鼻腔気管支症候群の特徴や不妊症,内臓逆位など呈する症候群をいう。気道クリアランスの障害により進行例では気管支拡張の進展により呼吸不全を来す。原因遺伝子はこれまでに40以上が知られており,近年新たな遺伝子異常の報告が続いているが,推測される全遺伝子異常の70%までしかカバーできていないとされている。診断には電子顕微鏡(electron microscopy:EM)検査や鼻腔NO測定など専門的な検査を必要とするため,診断が難しく,多くの患者が未診断の状態にあると考えられている。システマティックレビューから本邦ではこれまで主にEMのみを用いた診断が行われており,その解釈も欧米とは異なることが明らかとなった。われわれはPCD専門外来を開設した。これまでにびまん性汎細気管支炎でマクロライド療法不応例とされていた症例にDRC1の広範囲欠失をもつPCDが存在していることを報告した。アジア人に最適化した遺伝子パネルの開発を含め診断体制の確立により本邦の実態を明らかとし,患者支援活動に繋げることが望まれる。
1 0 0 0 なぜ男女の賃金に格差があるのか : 女性の生き方の経済学
- 著者
- クラウディア・ゴールディン著 鹿田昌美訳
- 出版者
- 慶應義塾大学出版会
- 巻号頁・発行日
- 2023
小脳の障害が自閉スペクトラム症や統合失調症の発症に関わるという多くの報告があるが、発達期小脳のシナプス刈り込みの異常とこれらの精神神経疾患との関連は不明である。本研究では、これらの精神疾患の関連遺伝子をプルキンエ細胞特異的に欠損させたマウスを対象に、発達期小脳の登上線維シナプス刈り込み、前頭前野のシナプス伝達、精神疾患関連行動を精査し、さらに、プルキンエ細胞の活動を変調してシナプス刈り込みを正常化した場合の効果を解析する。これらにより、発達期小脳の登上線維シナプス刈り込みの異常な亢進や障害が、如何にして前頭前野のシナプス機能に永続的な影響を及ぼし、精神疾患類似の行動異常を起こすのかを追及する。
1 0 0 0 OA 樹上脱渋の処理時期と脱渋果の冷蔵期間がカキ‘平核無’果実の渋もどりに及ぼす影響
- 著者
- 平 智 高林 奈美
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.11, pp.580-582, 2006-11-15 (Released:2007-09-29)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 5 3
カキ‘平核無’果実を用いて,樹上脱渋処理の時期と収穫後の脱渋果の冷蔵貯蔵期間が果実の不溶性タンニンの可溶化(渋もどり)の難易に及ぼす影響を調査するとともに,樹上脱渋果の渋もどりのしやすさを炭酸ガス脱渋果,アルコール脱渋果,干し柿およびあんぽ柿と比較した.その結果,樹上脱渋果は脱渋処理の時期が早いほど収穫時の果実は渋もどりしにくかった.また,樹上脱渋果では収穫後の冷蔵貯蔵期間が長くなるにつれてしだいに渋もどりしにくくなる傾向が認められた.この傾向は,早い時期に脱渋処理した果実より遅い時期に処理を行った果実の方が明確であった.樹上脱渋果の渋もどりのしやすさは炭酸ガス脱渋果とはほぼ同等で,アルコール脱渋果より渋もどりしにくかった.最も渋もどりしにくかったのは干し柿とあんぽ柿であった.
1 0 0 0 OA 認知行動療法の視点と実践的工夫
- 著者
- 大野 裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合病院精神医学会
- 雑誌
- 総合病院精神医学 (ISSN:09155872)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.23-28, 2016-01-15 (Released:2018-11-15)
- 参考文献数
- 6
認知行動療法の方略(スキル)は日常的に使われているストレス対処法をわかりやすくまとめたものであり,うつ病などの精神疾患の治療としてだけではなく,一般身体疾患での精神的苦痛や,さらには日常生活でのストレスへの対処法として広く用いることが可能である。そこで本稿では,認知行動療法で重視される概念化(定式化),つまり「みたて」に基づくアジェンダ設定と治療技法の選択,および治療関係を軸に,認知行動療法を総合病院精神科の診療で活用する可能性について検討した。
1 0 0 0 OA 土川五郎における「遊戯」論の展開とその歴史的意義
- 著者
- 大沼 覚子
- 出版者
- 幼児教育史学会
- 雑誌
- 幼児教育史研究 (ISSN:18815049)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.15-30, 2007-11-30 (Released:2018-03-27)
- 被引用文献数
- 1
In the Taisho period, Tsuchikawa Goro (1871-1947) criticized 'Yugi' of the Meiji Period, and proposed 'Ritsudo Yugi' (Rhythmic Play, namely Figure Marching) and 'Ritsudoteki Hyojo Yugi (Rhythmical Expressive Play, namely Singing Games). Through playing these new 'Yugi', he wanted children to experience what music and its rhythm expressed. The purpose of this paper is to reexamine the evaluation of Tsuchikawa in the previous researches and to show the historical meanings of his study on 'Yugi'. In order to achieve this goal, 1) I describe Tsuchikawa's activities and works to which have never been referred in the previous researches, 2) analyze his theories about 'Yugi', and 3) examine the relationship of Tsuchikawa to the Taisho and the beginnings of the Showa Period. As a result of this examination, several points thus become clear: First, Tsuchikawa played an important role in the process of building the concept of 'Yugi' or 'Oyugi'. That is to say, Tsuchikawa constructed new theories and created new works that opposed 'Yugi' of the Meiji Period. On the other hand, the popularization of Tsuchikawa's 'Yugi' and the confusion regarding 'Jido Buyo' (dances for children which usually use 'Doyo' as background music) reinforced the concept of 'Oyugi' as having a negative connotation. Moreover, Tsuchikawa insisted on the significance of the 'Education of Feeling', while in the Meiji Period the aim of education through 'Yugi' had inclined to gymnastics. The 'Education of Feeling' were greatly influenced by the New Education Movement and the Art Education Movement in the Taisho Period, and according to Tsuchikawa, this meant 1) a cultivation of aesthetic sentiment, 2) an experience with imagination of feelings expressed in 'Yugi', 3) an awareness of one's own body, and 4) genuinely enjoying 'Yugi'. I believe this is one of the important viewpoints to think about children's development of expression.
1 0 0 0 OA 感謝行動が日常生活に与える変化
- 著者
- 牧 久美子
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.Supplement, pp.os18, 2019 (Released:2021-01-08)
1 0 0 0 OA 水道水腐食の基礎としての水質化学
- 著者
- 小玉 俊明 藤井 哲雄
- 出版者
- Japan Society of Corrosion Engineering
- 雑誌
- 防食技術 (ISSN:00109355)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.11, pp.641-653, 1977-11-15 (Released:2009-10-30)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 9 2
Chemical factors affecting the corrosion of plumbing materials in fresh waters are reviewed in this article. Detailed discussions are given for pH, alkalinity, dissolved oxygen, anions, water treatment, and calcium carbonate equilibria.
1 0 0 0 OA 植物脂質
- 著者
- 片山 真之
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- 油化学 (ISSN:18842003)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.10, pp.695-707, 1971-10-20 (Released:2009-11-10)
- 参考文献数
- 101
1 0 0 0 OA 液体ロケットエンジン
- 著者
- 岸本 健治
- 出版者
- 日本混相流学会
- 雑誌
- 混相流 (ISSN:09142843)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.7-10, 1997-03-15 (Released:2011-02-22)
Liquid propellant rocket engine is introduced, and discussed about the technology status. As a relation with Multiphase technology, a new rocket engine development approach is introduced.
1 0 0 0 OA 大江山酒顛童子ノ岩屋
- 著者
- 高井 助太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 東京人類學會雜誌 (ISSN:18847641)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.23, pp.108a-109_1, 1888 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 OA 138. 投球時に発生する膝関節の痛みについて : 投球フォームからの一考察
- 著者
- 宮下 浩二 鵜飼 建志 宮本 三千男 小林 寛和 横江 清司
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.23 Suppl. No.2(第31回日本理学療法士学会誌 第23巻学会特別号 No.2 : 一般演題集)
- 巻号頁・発行日
- pp.138, 1996-04-20 (Released:2017-09-01)