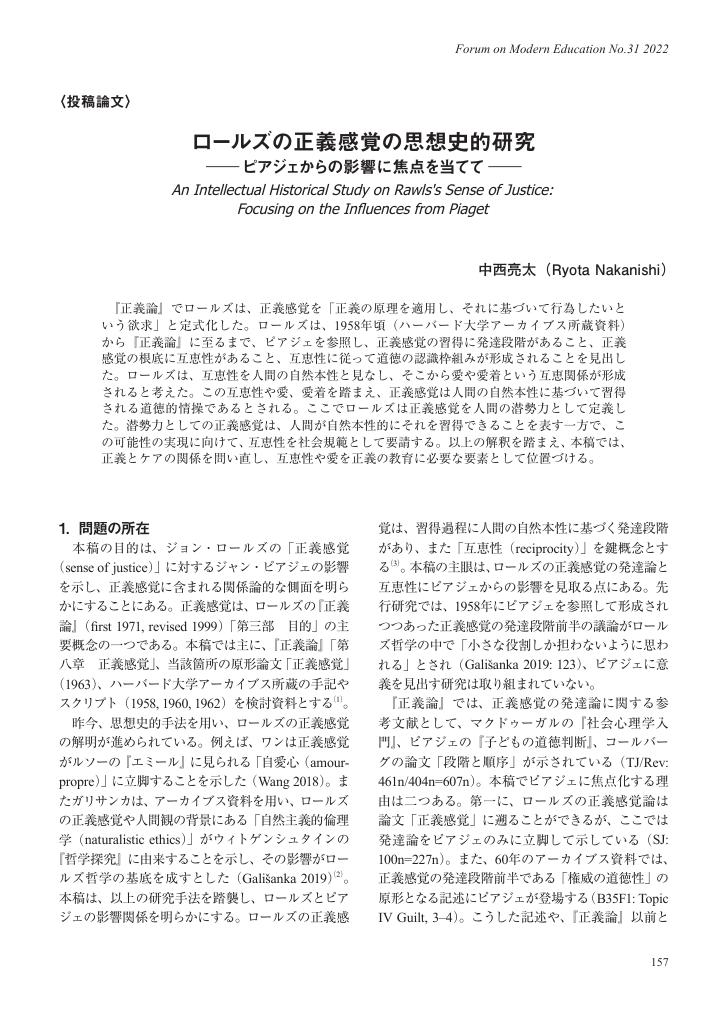1 0 0 0 OA 小学校英語における望ましい指導者についての意見と関連要因についての調査
- 著者
- 萬谷 隆一
- 出版者
- 小学校英語教育学会
- 雑誌
- 小学校英語教育学会誌 (ISSN:13489275)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.01, pp.70-81, 2021-03-20 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
本研究は,小学校英語教育における望ましい指導形態として,専科教員,担任教員,あるいはティーム・ティーチング(TT)が良いかについての教師の意識と,その意識に関連する要因を探る。北海道内の小学校教師64名に対し,質問紙調査を行い,指導者として専科教員・担任教員・TT のそれぞれがどの程度望ましいかについて評価してもらった(指導体制意見)。さらに指導体制意見と,専科・担任の立場,指導観(定着,正しい英語の習得,伝え合い,児童理解,授業規律,授業の活動構成)との関連性について分析した。分析の結果,1)専科・担任・TT のうち,担任単独の指導よりもTT がより支持されたこと,2)指導体制意見においては,専科・担任の立場で差異はみられないこと,3)担任教員に比して,専科教員が「授業規律」が重要であると答える傾向があること,4)「授業規律」を重視する教員ほど,専科教員が教えるべきではないと考える傾向があり,その傾向は特に担任教員に顕著にみられること,さらに「活動構成」が重要であると考える教員ほど,TT が望ましいと答える傾向があること,などが明らかになった。結果にもとづき,専科・担任のメリット・デメリットについての示唆を探るだけでなく,小学校英語における望ましい教師の資質や制度について考察した。
1 0 0 0 OA 雲粒の核はどのような物質なのか
- 著者
- 松本 潔
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.12-15, 2022-01-20 (Released:2023-01-01)
- 参考文献数
- 6
大気中で雲が発生するメカニズムは中学校の理科や高等学校の地学で学習するが,雲粒の核となる雲粒核や氷晶核はどのような物質なのか,どこから発生するのかなど,わかっていないことも多い。地球温暖化を打ち消す効果も指摘されている雲粒の核について,化学的特徴や発生源などを解説する。
1 0 0 0 OA 韓国出土ヒスイ勾玉の集成と流通過程に関する考古学的研究
- 著者
- 権 奇法
- 出版者
- 公益財団法人 地方自治総合研究所
- 雑誌
- 研究所資料 (ISSN:24366277)
- 巻号頁・発行日
- vol.132, no.1, pp.191-214, 2021 (Released:2023-03-01)
1 0 0 0 OA 図書館不安について
- 著者
- 三隅 健一
- 出版者
- 北海道地区大学図書館協議会
- 雑誌
- 第62回北海道地区大学図書館職員研究集会記録 (ISSN:13438026)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.21-38, 2019-08-02
- 著者
- 岸岡 智也 山下 良平
- 出版者
- 農村計画学会
- 雑誌
- 農村計画学会論文集 (ISSN:24360775)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.57-64, 2023 (Released:2023-06-25)
- 参考文献数
- 28
The purpose of this study was to examine how to coexist with black bears in Ishikawa Prefecture, where a record number of black bears appeared in the autumn of 2020, and to understand the current risk perception and coping behavior of prefectural residents, which could serve as a basis for the formation of a coexisting society. In line with the studyʼs objectives, we conducted a questionnaire survey using LINE, which has a high penetration rate, to conduct efficient sampling in rural areas where it is not easy to collect data according to regional characteristics and resident attributes. The survey was conducted in February 2021, with a sample size of 1,742 valid responses from the entire prefecture. Analysis of the obtained data showed that citizensʼ risk perception of bear encounters was increased by the occurrence of bears in their living areas and their experiences of encountering bears. Residents who had bear encounters in their living areas relied on various information sources, had higher knowledge, and took actual encounter avoidance actions when they had experienced encounters. Information communication is needed to stimulate more encounter avoidance behavior, for example, by communicating standards of real encounters.
- 著者
- 亀井 民雄 石井 英男 中山 杜人
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.10, pp.1245-1256, 1978-10-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2 2
Children with unilateral total deafness, indistinct in both etiology and time of onset, usually complain of only unilateral hearing loss. Nandate (1963) suggested terming this type of deafness “juvenile unilateral total deafness of unknown etiology”.On the other hand, our clinical experience has indicated that recurrent true vertigo develops preferentially in adolescence or early adulthood in such patients. The objective of this report was to introduce this new clinical aspect of this deafness.1. During the past 14 years, 89 patients with juvenile unilateral total deafness of unknown etiology were seen at the Gunma University Hospital. All patients conformed to the following criteria: i) Unilateral total deafness of unclear etiology and in which the onset of deafness could not be established to be other than very early in infancy; ii) Normal hearing in the other ear or, if deafness were present there also, normal hearing might be inferred to have existed in infancy; iii) Normal tympanic membranes; iv) Absence of central nervous symptoms. Of these patients, recurrent vertigo was the chief complaint of 27, or 30.3%. The age of onset of vertigo ranged from 9 to 60 years. However, in the majority of patients (19 cases: 70.4%), the onset was from 16 to 30 years. The vestibular symptoms were identical to vestibular symptoms seen in Ménière's disease.2. Among these 27 patients with recurrent vertigo of delayed onset, fluctuating sensory-neural auditory disturbances were evident in the originally non-deaf side in 3 (11.1%). These patients were diagnosed as having Ménière's disease.3. In contrast, vertigo attacks in the other 24 patients (88.9%) were never accompanied by cochlear symptoms. Such were considered to fit the delayed hydrops syndrome, a clinical entity newly postulated by Schuknecht (1976) and which is considered to occur as an aftermath of a labyrinthine injury of sufficient magnitude to destroy hearing but leaves the vestibular function intact.
- 著者
- 銅銀 一真
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.812, pp.2821-2831, 2023-10-01 (Released:2023-10-01)
- 参考文献数
- 28
This study aims to analyze “pans de verre ondulatoires” of “Couvent de La Tourette ,” designed by Iannis Xenakis under Le Corbusier, by using a novel visualization method that transforms the width into the vertical axis, and clarify the specific techniques that contribute to its musical characteristics. While previous studies have pointed out the similarity with his “stochastic method” based on mathematics, the result reveals commonalities with the polyphonic theories such as counterpoint. This result confirms that Xenakis’ musical and architectural theory based on “hors-temps” structure does not simply deny the traditional “en-temps” systems, but rather extends it.
1 0 0 0 OA アルギナーゼ1による炎症増悪とそのメカニズム
- 著者
- 安田 好文
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.362, 2017 (Released:2017-04-01)
- 参考文献数
- 3
寄生虫や花粉などに曝露されると,T細胞はTh2細胞に分化して抗原特異的にIL-5,IL-13などのTh2サイトカインを産生し,好酸球集積,杯細胞過形成,気道抵抗上昇を惹起して外来抗原を排除する.しかしその反応が過剰になると,喘息やアトピー性皮膚炎などの2型炎症の原因となる.また一方で,IL-13はマクロファージ(Mφ)を免疫抑制性のMφに分化させ.抗炎症性のIL-10やTGFβの産生を介して免疫抑制や組織修復を誘導する.このMφはさらにアルギナーゼ1(Arg1)を発現し.アルギニンの枯渇や一酸化窒素の産生抑制によっても抗炎症作用を示す.Arg1は尿素代謝に必須の酵素であり主に肝臓に発現するが,このように免疫系でも重要な役割を持つ. また上皮細胞の傷害によりIL-33などが産生されると,グループ2自然リンパ球(group 2 innate lymphoid cells:ILC2)は抗原非特異的にTh2サイトカインを大量に産生する.その特徴から.ILC2はTh2細胞とは別の2型炎症の鍵となる細胞として注目されている. 最近,ILC2がArg1を発現することが報告されたが,その意義は不明であった.本稿では,ILC2に発現するArg1の役割を明らかにしたMonticelliらの論文を紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Munder M., Br. J. Pharmacol., 158, 638-651(2009).2) Waker J. et al., Nat. Rev. Immunol., 13, 75-87(2013).3) Monticelli L. A. et al., Nat. Immunol., 17, 656-665(2016).
1 0 0 0 OA 末期認知症高齢者の肺炎に対する抗菌薬の予後の改善と苦痛緩和の効果に関する系統的レビュー
- 著者
- 平原 佐斗司 山口 泰弘 山中 崇 平川 仁尚 三浦 久幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本在宅医療連合学会
- 雑誌
- 日本在宅医療連合学会誌 (ISSN:24354007)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.60-67, 2022 (Released:2022-02-17)
- 参考文献数
- 17
目的:末期認知症高齢者の肺炎に対する抗菌薬の予後と苦痛の改善効果を検討する.方法:国内外のデータベースから検索式を用い,末期認知症の肺炎の抗菌薬治療の予後と苦痛の改善効果についての2つ の CQs を含む5つの CQs に該当する 604 論文を抽出,最終的に採用した 17 論文のうちこれらの CQ に該当する6論文を解析した.結果:末期認知症高齢者の肺炎の抗菌薬治療は予後を改善する可能性があり,とりわけ短期の予後の改善が期待できる.抗菌薬治療の予後改善効果は認知症や嚥下障害の重症度や過去の肺炎回数と関連していた.また,抗菌薬治療が肺炎による死亡前の苦痛を軽減する可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA COVID-19パンデミックとマキシミン・ルール -拡大トリアージモデルによる思考実験-
- 著者
- 徳永 純
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.21-29, 2022-09-28 (Released:2023-08-01)
- 参考文献数
- 40
COVID-19のパンデミックは、トリアージが差別に当たるかどうかという論争を引き起こした。救命措置の優先順位を決めるトリアージの理論は、帰結主義の立場から、高齢者や基礎疾患のある弱者を差別する含意なしに、救命可能性が高い患者を優先する結論を導く。ただ、既存の理論はパンデミック下における医療資源の可変性を考慮しないため、感染対策の不徹底が生む差別を隠蔽しかねない。本稿では、軽症者から重症者までの医療体制を見渡し、その整備に要する時間も考慮したトリアージについて理論モデルの構築を試みる。それにより救命数最大化を地域レベルで徹底すると、軽症から中等症については、重症化リスクの高い弱者を優先するマキシミン・ルールに基づく医療資源の拡充こそが最重要の倫理的要請であることがわかる。帰結主義の枠内で思考実験を行い、論争の着地点を探る。
1 0 0 0 OA ロールズの正義感覚の思想史的研究―ピアジェからの影響に焦点を当てて―(投稿論文)
- 著者
- 中西 亮太
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.157, 2022-09-17 (Released:2023-09-18)
1 0 0 0 パブリック・ヘルスと統治
- 著者
- 齋藤 純一
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.145-158, 2023 (Released:2023-09-23)
1 0 0 0 OA 終末期の在宅療養者に対する在宅訪問栄養食事指導の介入効果の検討
- 著者
- 中村 育子 前田 佳予子 田中 弥生 本川 佳子 水島 美保 前田 玲
- 出版者
- 一般社団法人 日本在宅医療連合学会
- 雑誌
- 日本在宅医療連合学会誌 (ISSN:24354007)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.19-27, 2023 (Released:2023-08-29)
- 参考文献数
- 18
本研究は人生の最終段階において,管理栄養士が多職種と連携して食支援を行うことは,できるだけ自分の口から食事を摂取し,最期まで食べる喜びを感じることができる等,QOL 向上に対する管理栄養士の在宅訪問栄養食事指導の介入効果と,その中で,疾患の違いによる介入効果についても検討する. 在宅訪問栄養食事指導における食支援は,管理栄養士が介護者の困りごとの相談に応じて,介護者の調理技術の向上や簡単に食事を用意できることを可能にし,介護者の食事作りの負担を軽減させ,在宅療養者の最後に食べた物は好物であったことに貢献していた.
1 0 0 0 OA 遺伝子ネットワークの数学理論に基づく細胞運命システムの制御
- 著者
- 望月 敦史
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.349-351, 2020 (Released:2020-11-28)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 脳梗塞を発症した高齢患者に対して入院早期から口腔管理を実施した症例
- 著者
- 松永 一幸 古屋 純一
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.supplement, pp.24-28, 2023-09-30 (Released:2023-10-04)
- 参考文献数
- 5
緒言:脳卒中発症後は肺炎を合併しやすく,肺炎を合併した場合は機能的予後の悪化につながるとの報告がある。一方で,脳卒中発症早期からの口腔管理は,肺炎予防に有用とされている。今回,脳梗塞を発症した高齢患者に対して,肺炎予防のために入院早期から口腔管理を実施し,口腔環境および食事摂取状況を改善した症例を経験した。 症例:83歳男性,身長147.2 cm,体重52.7 kg(BMI 24.3 kg/m2)。2021年8月に左半身の脱力感を生じ,脳梗塞と診断された。入院当日の看護師による口腔評価後,入院3日後に歯科介入した。残存歯は上顎0本,下顎6本で,左下1・2番と右下3番は顕著に動揺し,周囲歯肉から排膿があった。上顎義歯は容易に脱落し,下顎義歯は残存歯の移動により,装着不可能であった。 経過:歯科介入前は均質なペースト食を2〜4割摂取していたが,口腔衛生管理および動揺歯の抜歯後は8〜10割摂取が可能となった。さらに義歯修理後は,不均質なペースト食の10割摂取が可能となった。入院17日後に回復期病院へ転院となったため,同病院の協力歯科医院へ継続的な口腔管理を依頼した。転院後48日時点において全粥・軟菜を自力摂取し,口腔環境も維持していると報告を得ている。 考察:本症例は,脳梗塞を発症した高齢患者に対して入院早期から口腔管理を実施できたことで,口腔環境および食事摂取状況の改善につながったと考える。
1 0 0 0 OA 高校生ラグビープレイヤーにおける頚部筋力,頚部周径及び脳震盪経験との関連について
- 著者
- 森本 晃司 桜井 進一 内藤 慶 青柳 壮志 奥井 友香 加藤 大悟 遠藤 康裕 中澤 理恵 坂本 雅昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.37 Suppl. No.2 (第45回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C3O1119, 2010 (Released:2010-05-25)
【目的】ラグビーやアメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツにおいて,脳震盪などの頭・頚部の外傷は時として重大な事故を引き起こすことから,安全対策上重要な問題として取り扱われる.国際ラグビー評議会の定款では,未成年のラグビープレイヤーは脳震盪を生じた場合,3週間の練習・試合を禁止するとされており,頭・頚部の外傷は頚部筋力を向上させることで予防可能との報告もある.本研究の目的は,高校生ラグビープレイヤーにおける頚部筋力と周径の関連,脳震盪と頚部筋力の関連について検討し,脳震盪予防の一助とすることである.【方法】 対象は全国大会レベルの群馬県N高校の高校生ラグビープレイヤー69名(1年生30名,2年生18名,3年生21名)とした.評価項目は経験年数,過去8カ月間の脳震盪の有無(1年生を除く),頚部周径,頚部筋力とした.頚部周径はメジャーを使用し直立位にて第7頸椎棘突起と,喉頭隆起直下を通るように測定した.頚部筋力の測定にはアニマ社製ハンドヘルドダイナモメーターμTasMF-01を使用した.測定肢位は臥位とし,両肩と大腿部を固定した.センサーはベッドに固定用ベルトを装着した状態で額,後頭部,側頭部の各部分に当て,頚部屈曲,伸展,左右側屈の等尺性筋力を3秒間測定した.各方向3回ずつ測定し,最大値を採用した.統計学的処理にはSPSS ver.13を用い,頚部筋力と周径,経験年数の関係にはspearmanの順位相関係数を用い,各学年間の頚部筋力,周径との関係には一元配値の分散分析後,Tukeyの多重比較検定を行った.また脳震盪経験の有無と頚部筋力・周径の関係には対応のないt-検定を用い有意水準は5%とした.【説明と同意】チーム指導者並びに対象者に対し本研究の主旨及び個人情報保護についての説明を十分に行い,署名による同意を得て実施した.【結果】2,3年生計39名のうち,脳震盪経験者は28名であり非経験者は11名であった.脳震盪経験の有無で頚部筋力を比較した結果,頚部筋力,周径ともに有意差は認められなかった.頚部筋力と周径では有意な相関関係が認められた(P<0.05,R=0.52~0.65)が,経験年数と頚部筋力及び周径との間には相関関係は認められなかった.学年間の頚部筋力の比較では全項目において有意差が認められ,また,学年間の周径においても有意な差が認められた(P<0.05).多重比較検定では,頚部筋力では1年生に対して2,3年生の筋力が有意に高く(P<0.05),2年生と3年生との間に有意な差は認められなかった.頚部周径では1年生と3年生にのみ差が認められ、3年生の周径が有意に大きかった(P<0.05). 【考察】本研究における脳震盪の有無と頚部筋力の検討では,両群で有意差は認められなかった.タックル動作において,脳震盪となる場面ではタックル時に頭部が下がる,飛び込むなどのスキル的な要素や,瞬間的に頚部を安定させる筋収縮の反応などの要素も関連していると考えられる.今回の研究ではそれらの要素は検討できていないため,両群で差が見られなかったものと考える.また,各学年と頚部筋力の検討では1年生と他学年との間に有意な差が認められたが,経験年数と頚部筋力との間に相関関係は認められなかった.群馬県では中学校の部活動としてラグビー部はなく,経験者も週1回程度のクラブチームの練習に参加する程度である.このため,1年生では経験者であっても十分な頚部筋力トレーニングが行えていない可能性が考えられる.また,頚部筋力と周径ではすべての項目で相関関係が認められたことから,選手のコンディショニング管理の一つとして,筋力測定器などがない場合には,頚部周径を確認しておくことの意義が示唆された.頚部筋力は脳震盪予防のための重要な一要因であるが,今回は頚部筋力と脳震盪経験の有無とに関連は見られなかった.今後はタックル動作のスキルや,筋の反応時間なども検討することが課題である.【理学療法学研究としての意義】本研究の結果から,高校1年生と2・3年生の頚部筋力の違いが明らかとなり,新入生に対する早期からの筋力評価とトレーニングの重要性が示唆され,スポーツ障害予防のための基礎的資料となる.
1 0 0 0 平均場ゲーム理論とその数理ファイナンスへの応用
本研究では平均場ゲーム理論を用いて、多人数ゲームとしてのファイナンスモデルを考察する。具体的には、金融市場における市場参加者の相互作用を考慮し、その均衡における証券価格や投資家たちの戦略分布を記述する理論モデルを構築した上で、その理論の社会実装方法を提案することを目的とする。また、より長期的には金融市場のみならず経済全般への応用も目指している。本研究が進展すれば、投資家たちの競争・協調行動の効果を織り込みながら金融危機等を分析できるようになり、均衡における人々の状態分布を考慮に入れた効率的なリスク管理方法や投資戦略、そして投資の促進や市場の規制といった政策の方法などを提供できると期待される。
1 0 0 0 OA 腰背部の自己筋膜リリースが体幹機能におよぼす効果の検証
- 著者
- 中井 雄貴 木山 良二 川田 将之 宮﨑 宣丞
- 出版者
- 公益財団法人 石本記念デサントスポーツ科学振興財団
- 雑誌
- デサントスポーツ科学 (ISSN:02855739)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.120-127, 2022-06-20 (Released:2022-12-20)
- 参考文献数
- 18
本研究はローラーマッサージを使用した腰背部の自己筋膜リリースが体幹機能に及ぼす影響を検証することを目的とした.健常男子大学生18名を対象に,ローラーマッサージによる介入とコントロール(安静)の2条件をランダムに実施するクロスオーバー試験を実施した.介入の前後に長座体前屈,腹部体幹筋力,腰部筋・筋膜の滑走性を超音波画像診断装置にて評価した.皮下組織と多裂筋の経時的な移動速度をエコー動画分析ソフトにて算出し,両者の相関係数で滑走性を分析した.その結果,柔軟性( p=0.004),腹部体幹筋力( p=0.016),滑走性( p=0.004)すべてで介入効果に差を認めた.ローラーマッサージによる介入では,柔軟性(+ 1 .39cm, p=0.003),体幹筋力(+ 1.84kPa, p<0.001),滑走性(-0 .079, p=0.009)に有意な改善を認めた.ローラーマッサージを用いた腰背部の自己筋膜リリースが,腰部の柔軟性,腹部体幹筋出力,筋筋膜の滑走性の向上に寄与することが示唆された.
1 0 0 0 OA 1998年パプアニューギニア津波を起こした海底地すべりは地震計で検知可能か?(2)
1998年7月にパプアニューギニアにおいて発生したMw 7.0の地震の後に10mを超える津波が沿岸に押し寄せ、この津波により2,200名を超える犠牲者が出ている(Tappin et al., 2008).この津波は,地震の規模に比べて高すぎること,津波の発生が地震の発生よりも10分ほど遅れているとみられること,海底地形において地すべりを起こしたとみられる場所が確認されていることなどから,海底地すべりが発生源であるとみられている(例えば,Tappin et al., 1999; Synolakis et al., 2002).通常の地震による津波の場合には,地震計で記録される地震波が警戒の最初のトリガとなることが多い.しかし,この1998年のパプアニューギニアのような事例が発生した場合には,地震波から予測される規模の津波には備えるものの,それを超える規模の津波への警戒は通常なされない.もし,海底地すべりが地震計で捉えられるならば,この種の津波に備えることが可能となる.以前の調査(勝間田・他, 2016)に,調査対象の観測点の追加,理論波形の再検討を行ったので報告する. 海底地すべりが発生した地点から900km離れた場所にPMG観測点がある.PMG観測点の地震データをIRISより入手し,0.2秒から50秒までの様々な帯域のフィルターを施して特異な信号有無を確認したが,直前のMw 7.0の地震の後続波の振幅を超える特別な相は確認されなかった.PMG観測点において,海底地すべりに対応した相が確認できないことはSynolakis et al.(2002)によって既に指摘されている.東京大学地震研究所の海半球観測研究センターにPMGよりも更に地すべり地点に近いJAY観測点(約150km)のデータがアーカイブされている.JAY観測点のデータについても確認したが,顕著は相は確認されなかった. Watts et al. (2003)の津波発生源モデルによると,この規模の津波を発生させることができる地すべりは長さ4.5km,幅5km,厚さ760m(半楕円体)の規模のものであった.それが傾斜角12度の下で特性時間32秒の地すべりを起こしたとされる.地すべりが進行している時にはそれまで摩擦力で支えられていた地塊が加速度運動をしていると考えられる.それ以前に地塊を支えていた力が減ずるのでその分の地面に加わる力が変化したと考えられる.その力を,密度(2.15×103kg/m3)×体積(9 km3)×加速度(0.36m/s2)として見積もると7×1012Nとなる.この程度の力が作用したと仮定した場合の理論波形をTakeo (1985)により計算した.震源時間関数として数十秒程度の継続時間のものをいくつか仮定してみた.その結果,理論波形は直前の地震の後続波に比べて同程度以下の振幅にしかならず,理論波形からみても地すべりにる地震波は検知可能レベル未満であると見積もられた(図).海底地すべりによる津波の検知には,沖合い津波計のような別の手段が望まれる.謝辞IRIS及び東京大学地震研究所海半球観測研究センターに保管されていた地震記録を用いた.理論地震波形の計算にTakeo (1985)を用いた.