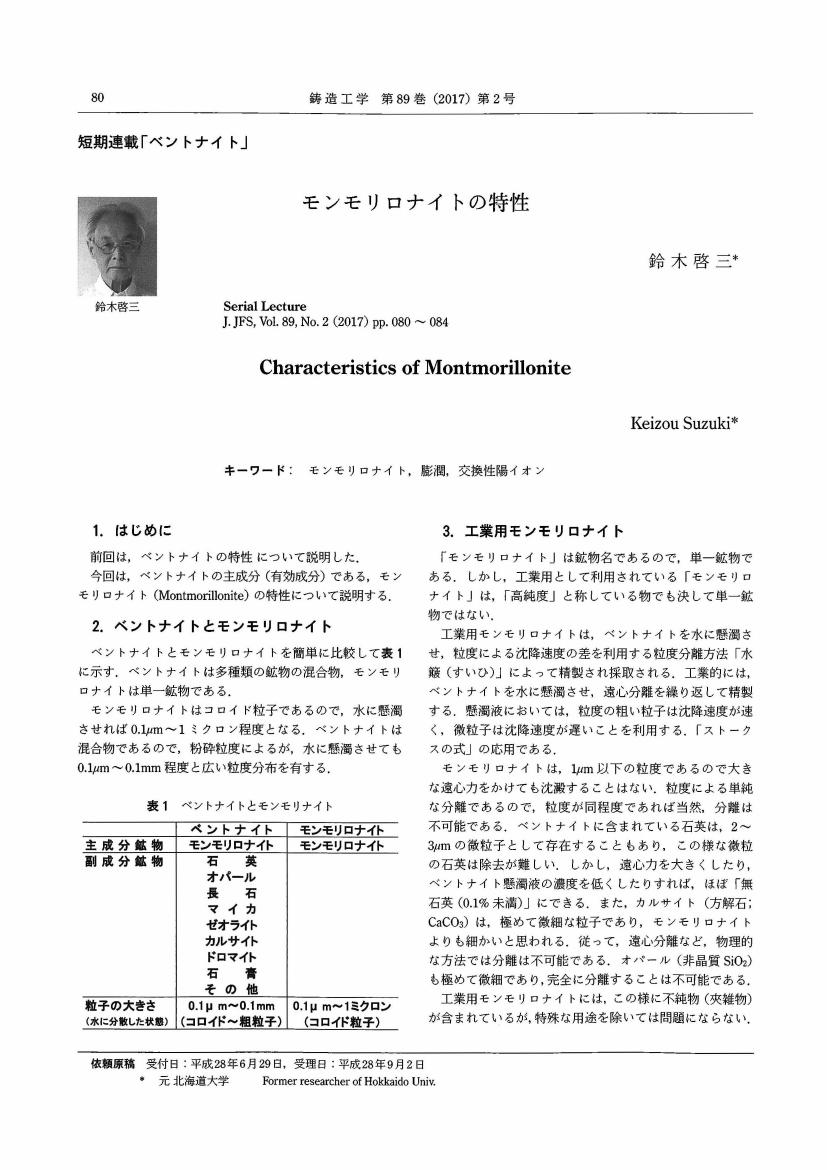1 0 0 0 OA 合理的選択理論批判の論理構造とその問題点
- 著者
- 佐藤 嘉倫
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.188-205, 1998-09-30 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2
本稿の目的は, 合理的選択理論に対する批判を分類し, それぞれの批判の論理構造を検討し, 受け入れるべき批判を明らかにすることである。 批判は次のように分類される。 (1-a) 選好の文化依存性の指摘, (1-b) プロスペクト理論, (2-a) 合理性仮定の経験的妥当性に対する批判, (2-b) 共有知識仮定に対する批判, (3-a) 経験的事象の説明可能性に対する批判, (3-b) 複数均衡の存在に対する批判, (3-c) 社会現象は行為から成り立つとは限らないという批判。これらの批判のうち, (1-a) から (2-b) までは, 合理的選択理論の仮定に関する批判である。これらの批判は, 経験科学理論に対する批判として意味がないわけではないが, 理論の説明力を無視して仮定の妥当性のみを問うならば, 生産的ではなくなる。 (3-a) の批判は, 合理的選択理論の説明力に対する批判であり, 重要である。 (3-b) の批判に対しては合理的選択理論は適切に対処できる。 (3-c) の批判は, 合理的選択理論よりも優れた説明力を持つ理論を提示していないので, 現状では受け入れるわけにはいかない。 以上の批判の検討から, (3-a) の批判に適切に対処することが, 合理的選択理論をより豊かな社会学理論にするメイン・ルートであると結論される。
1 0 0 0 OA 愛知県の水稲乾田直播栽培におけるシハロホップブチル抵抗性イヌビエ(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. crus-galli)の防除に有効な代替除草剤の検討
- 著者
- 柏木 啓佑 尾賀 俊哉 伊藤 晃
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.55-59, 2023 (Released:2023-09-30)
- 参考文献数
- 10
愛知県の水稲乾田直播栽培におけるシハロホップブチル抵抗性イヌビエに対し,有効な代替除草剤を検討した。現地圃場での試験では,ペノキススラム,ビスピリバックナトリウム塩処理で高い防除効果が得られた。また,県内各地の26地点の調査では,18地点からシハロホップブチル処理で枯死率の低いイヌビエが見いだされた。いずれの集団も上記2剤に加え,フロルピラウキシフェンベンジル処理において,枯死率が100%となった。以上より,シハロホップブチル抵抗性イヌビエは愛知県内広域に発生していること,ペノキススラム,ビスピリバックナトリウム塩,フロルピラウキシフェンベンジルが有効な代替除草剤であることが示された。
- 著者
- 姜 涌 近藤 正一 北川 啓介 張 健 若山 滋
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.516, pp.273-280, 1999-02-28 (Released:2017-02-03)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 5 5
This paper focuses to figure out the ideological trend of Chinese contemporary architects in the process of modernization and socialist transformation of traditional architectural culture by means of analyses of architects discours published in "the Architectural Journal" in the 1950-1970s, which is often called as "the Period of Chairman Mao". Refering to the method of linguistics, the keywords of discours and its frequency used in architectural papers are indexed and counted by subjects, and then be classified into several categories in accordance with the axes of "social background-architecture-culture" and "architectural ontology-methodology-artistry". Through construction and transformation investigation, it is found that architectural thoughts in that period are based on the government policy, i. e., the combination of "function, economy and beauty" in architecture, and the criterion of these is socialism ideology and political propaganda. According to the movement of focuses of architects' discours following the pressure of ideology and mass movement, this period can be divided into 6 phases.
1 0 0 0 OA 公共図書館における行政支援サービスの構築と発展:田原市図書館の事例分析
- 著者
- 德安 由希 小泉 公乃
- 出版者
- 日本図書館情報学会
- 雑誌
- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.95-111, 2022 (Released:2022-06-30)
- 参考文献数
- 61
本研究の目的は,積極的に行政支援サービスに取り組む公共図書館がどのようにサービスを構築し,発展させてきたかを解明することである。愛知県の田原市図書館を対象に,資料調査と館長,副館長,図書館員,行政職員(サービス利用経験有)への半構造化インタビューによる事例分析を行った。結果,田原市図書館では,地域課題によって図書館員と行政職員の意識と行動が互いに変化し,両者の関係性の強化を契機に従来のサービスを転換する形で行政支援サービスを構築していた。構築後も図書館員の継続的な努力によってサービスは緩やかに進展し,図書館と行政部局の連携による新たな成果の創出にまで発展していることが明らかになった。さらに,図書館と行政職員の意識や行動をサービスが変化した時期と関連づけながら,サービスに与えた影響を整理し,サービスの構築過程を4 段階別に描いた上で,行政支援サービスに関連する図書館員の専門的知識を考察した。
- 著者
- 吉城 秀治 辰巳 浩 楠田 寛人
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.646-653, 2022-10-25 (Released:2022-10-25)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
近年、SNSの普及が目覚ましく、幅広い年齢層で利用されている。そのSNSの特徴の一つとして口コミの効果の高さがあげられ、口コミが人々の行動に及ぼす影響は極めて大きい。企業においてもSNSを活用したマーケティングが進んでおり、SNSは人々の消費、ひいては回遊、来店行動に大きく影響しているものと言える。 そこで本研究では、個人属性や同伴状況を考慮した上で、中心市街地における来店行動とSNSの利用の関係を明らかにしてきた。その結果、SNSの利用、特に情報発信を伴うことによって、目的地を定めないぶらりとした来店から、目的地を定めた目的型の来店になる傾向にあり、そこで時間やお金を消費する傾向にあること等が明らかになっている。
1 0 0 0 OA 人の体型を考慮したCT診断時臓器線量の個人差を評価できるWEBシステムの開発
CT診断からの臓器線量計算を行うWebシステムWAZA-ARIにおいて、年齢と体型の個人差を考慮できるシステムに拡張したWAZA-ARI 2を開発した。未成年はフロリダ大学で開発した年齢別ファントムを用いた。成人体型の違いを計算するために、日本人の標準体型からBMIで2倍の標準偏差だけ外れるやせ型、2倍と5倍の標準偏差だけ外れる肥満型のファントムを皮下軟組織のみを変形することでファントムを構築した。また、実際の臨床で得られたCT画像をもとにボクセルファントムを構築し、臓器線量の個人差を実際の体型ごとに計算し、体型と臓器線量の関係を導いた。有効直径が体格の指数として利用できることがわかった。
1 0 0 0 OA 肘離断性骨軟骨炎に対する骨釘移植術の適応と限界
- 著者
- 村田 英明 村上 恒二 宗重 博 浜田 宣和 天野 幹三 山本 健之 生田 義和
- 出版者
- Japanese Society for Joint Diseases
- 雑誌
- 日本リウマチ・関節外科学会雑誌 (ISSN:02873214)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.273-282, 1993-12-20 (Released:2010-10-07)
- 参考文献数
- 13
To study the effectiveness of bone peg graft from the ulna for osteochondritis dissecans of the elbow joint, we analyzed 16 patients with bone peg graft who had various types of preoperative and postoperative findings. All the cases were baseball players except for one volleyball player. The onset ages ranged from 10 to 16 years (mean 11.2), and the periods from then to the operation from 5 to 72 months (mean 2.6 years) . The follow-up periods were from 12 to 29 months (mean 20 months) . Based on Minami's X-P classification, 8 cases were categorized into the stage of fragmentation and 8 into the stage of isolation. Patients were also classified with respect to the osteochondral lesion found during operation; 9 were without abrasion of the lesion or, if with it, without invasion of fibrocartilage into the lesion and were classified into Type 1. The 7 in which the osteochondral lesion was unstable due to the invasion of fibrocartilage were classified as Type 2. The results with regard to postoperative X-P were classified as excellent when the osteochondral lesion was repaired anatomically, as ‘good’ when the lesion was under repair and the osteosclerotic halo of the capitulum had disappeared, and as ‘poor’ when the halo remained. As a result, 7 Type 1 cases (78%) were excellent and 2 cases (22%) good, while one Type 2 case (14%) was excellent, 4 (57%) were good and 2 (29%) were poor. All patients were clinically not symptomatic and were satisfied with the surgery. We emphasized that bone peg graft could be indicated in all cases of osteochondral dissecans of the elbow joint and that there were difficulties in repairing osteochondral lesion in Type 2 (unstable) cases.
- 著者
- 三反畑 修
- 出版者
- 国立研究開発法人防災科学技術研究所
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2020-04-24
伊豆島弧の海底カルデラ火山では、地下浅くの高圧マグマと断層破壊が相互作用して発生すると考えられる『火山性津波地震』という特異な火山性地震が約十年間隔で発生し、大きな地震動を伴わずに数十cmの津波を引き起こしている。本研究は、地震波・津波の観測記録を基にした観測ベースの研究と、マグマと断層破壊が相互作用する現象を物理理論によって再現する理論ベースの研究によって、火山性津波地震の動力学的な発生メカニズムと、その火山活動との関連を明らかにすることを目指す。この研究によって、直接観測が困難な離島的な海底火山で繰り返す特異な現象の実態解明が期待される。
1 0 0 0 OA 浸透圧発電の現状と今後の展望
- 著者
- 眞壁 良 上山 哲郎 坂井 秀之 谷岡 明彦
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.3, pp.177-182, 2022 (Released:2023-03-16)
- 参考文献数
- 9
浸透圧発電(PRO)は,塩分濃度差によって得られる浸透水を使用する再生可能エネルギーである.メガトンスケールの海水淡水化施設に濃縮海水と下水処理水を使用したPRO 設備を導入した場合,造水の消費電力を10 %削減する能力がある.機器の汎用化によって,発電コストは10.6 円/kWh と試算した.また海水と下水処理水を利用したPRO システムの実現が重要であり,このためには新たなPRO 膜モジュールの開発が必要となる.開発するPRO 膜モジュールのA 値・B 値は,2.05×10-6 m/s/MPa・5.5×10-9 m/s の性能が求められ,このPRO 膜モジュールを使用した発電コストは,22 円/kWh と試算した.優れたPRO 膜モジュールを開発することで,世界のエネルギー供給に大きな影響を与えると期待している.
1 0 0 0 OA 文化芸術の経済評価の試み ―文化GDPの推計―
- 著者
- 藤川 清史 川村 匡
- 出版者
- 環太平洋産業連関分析学会
- 雑誌
- 産業連関 (ISSN:13419803)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.39-52, 2021 (Released:2021-09-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
近年欧米では文化芸術が成長産業の1つとみなされるようになった.日本でも「未来投資戦略2017」において,文化芸術による付加価値を拡大する方針が示された.また2017年には「文化芸術基本法」が成立するとともに「文化経済戦略」が策定された.これらが日本での文化の経済的評価の契機となり,文化庁内に「文化GDPの推計のための調査研究会議」が設置された.本報告では,UNESCOの文化GDPの推計基準を紹介するとともに,それに基づいた上記会議による日本の文化GDPの推計を紹介する.日本の文化GDPは10兆5,385億円でGDP総額の約1.9%となった.このシェアは米国や英国と比較するとやや小さい,今後は文化GDPの推計法を改善するとともに,文化雇用者や文化商品の輸出入を含めた文化サテライト勘定を推計することにしたい.
1 0 0 0 OA 北海道新産のゴハリマツモ(マツモ科)と道内におけるマツモ属の極めて稀な結実記録
1 0 0 0 OA 講座 SUT入門編No.2供給・使用表(SUT)の歴史
- 著者
- 高山 和夫
- 出版者
- 環太平洋産業連関分析学会
- 雑誌
- 産業連関 (ISSN:13419803)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.10-18, 2022 (Released:2022-09-01)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
本稿では,数次の国民経済計算体系(System of National Accounts,以下「SNA」とする.)改訂の歴史をたどりながら,SNAにおける産業連関表の位置づけについて説明する.また,1968SNA時の「U表」および「V表」を源流として,1993SNA時に供給・使用表(Supply and Use Table:以下,「SUT」とする.)が勧告された背景及び理由について,主にヨーロッパの影響に焦点を当てて,歴史的経緯について説明する. 以下では,第一に1968SNAにおける「U表」および「V表」導入の理由と背景,および1968SNAにおける産業連関表の位置付けについて述べる.第二に1993SNAにおけるSUT導入の理由・背景と,更にSNA改訂の国際的な議論の経緯を明らかにする.第三に2008SNAにおけるSUTと産業連関表の位置づけについて説明する.
1 0 0 0 OA 中国における賃金格差 ── 地域間格差と業種間格差 ──
- 著者
- 坂本 博
- 出版者
- 日本地域学会
- 雑誌
- 地域学研究 (ISSN:02876256)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.927-939, 2009 (Released:2010-04-12)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 2
This study is a statistical disparity analysis of the wages of the staff and working (Zhigong) class in China. The Chinese government strictly controlled the wage system of state owned enterprises before the reform and opening of China. However, this system is gradually being reformed and each enterprise can independently decide their own wage system. As a result, the wage disparity has expanded since the reform and opening of China. In 2006, the staff and workers (Zhigong) were 110 million people, which is about 14.6 percent of the workers and about 8.5 percent of the population of China. To understand the recent wage disparities in China, disparity was estimated with a one stage Mean Logarithm Deviation Decomposition Index and from two directions in the decomposition pattern of disparity across region and industrial sector. Several findings are presented in this paper. First, a rapid expansion of disparity occurred during the measurement period. The index was below 0.02 at the start and increased to about 0.08 at the end. Second, the main factor of disparity gradually changed from regional disparity to sector disparity. Third, the regional disparity in each sector expanded in the higher value sectors but decreased in the agriculture and industry sectors. Fourth, the tendencies in the disparity of each sector in each region differed. From these results, wage disparity is a very serious problem in China. Therefore, several difficult correspondences are required from the government to reduce various disparities in the future.JEL classification: J31, O5
1 0 0 0 OA 冬季の室内気流が知的集中に及ぼす影響
- 著者
- 伊藤 京子 古田 真也 上東 大祐 石井 裕剛 下田 宏 大林 史明 谷口 和宏
- 出版者
- ヒューマンインタフェース学会
- 雑誌
- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.235-244, 2019-05-25 (Released:2019-05-25)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
In order to improve intellectual concentration, few studies have verified the effect of indoor airflow among the thermal environment conditions, and the differences in effects have not been studied based on the season. In this study, an experiment was conducted to investigate the influence of a room airflow in winter on intellectual concentration. As a result, no significant difference of intellectual concentration was found between a condition with airflows and a condition without airflows. The thermal sensation vote showed that the airflows caused the participants to feel colder and it is the same as the results of an experiment in summer, although the intellectual concentration was not improved in winter. In addition, covariance structure analysis was carried out to analyze the effects for intellectual concentration. The participants were classified into two groups. A group improved intellectual concentration by the airflows and another group did not improve it. The former group showed that the airflows caused the comfortable feeling of the room and the latter group showed the airflows caused the feeling of coldness. It was shown that different persons like different airflows from the results. One of our future challenges is to provide each person a controllable airflow.
1 0 0 0 OA コミュニケーションとしての大衆文化(<特集>マス・コミュニケーション研究の系譜)
- 著者
- 吉見 俊哉
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- 新聞学評論 (ISSN:04886550)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.78-105, 1990-04-30 (Released:2017-10-06)
1 0 0 0 OA モンモリロナイトの特性
- 著者
- 鈴木 啓三
- 出版者
- 公益社団法人 日本鋳造工学会
- 雑誌
- 鋳造工学 (ISSN:13420429)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.80-84, 2017-02-25 (Released:2022-01-01)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 ウロコの同位体比を利用した、魚類の生活史推定手法の開発とその応用
生物の移動を把握することは、対象種を保全し資源の持続性を高める上で基礎的なデータとなる。しかし、魚類の移動履歴を推定する手法の開発は発展途上であり、空間スケールを考慮した資源保護対策を打ち出す上で大きな障害となっている。ストロンチウム同位体比(87Sr/86Sr)は水域間で値が変化することが多く、水域の値が生物体組織に直接反映されるため、対象魚が生息していた水域を推定することができる。本研究は年輪状に成長し、対象魚を殺さずとも採集できるウロコの87Sr/86Srを測定し、魚の行動履歴推定する新たな手法を開発し応用する。