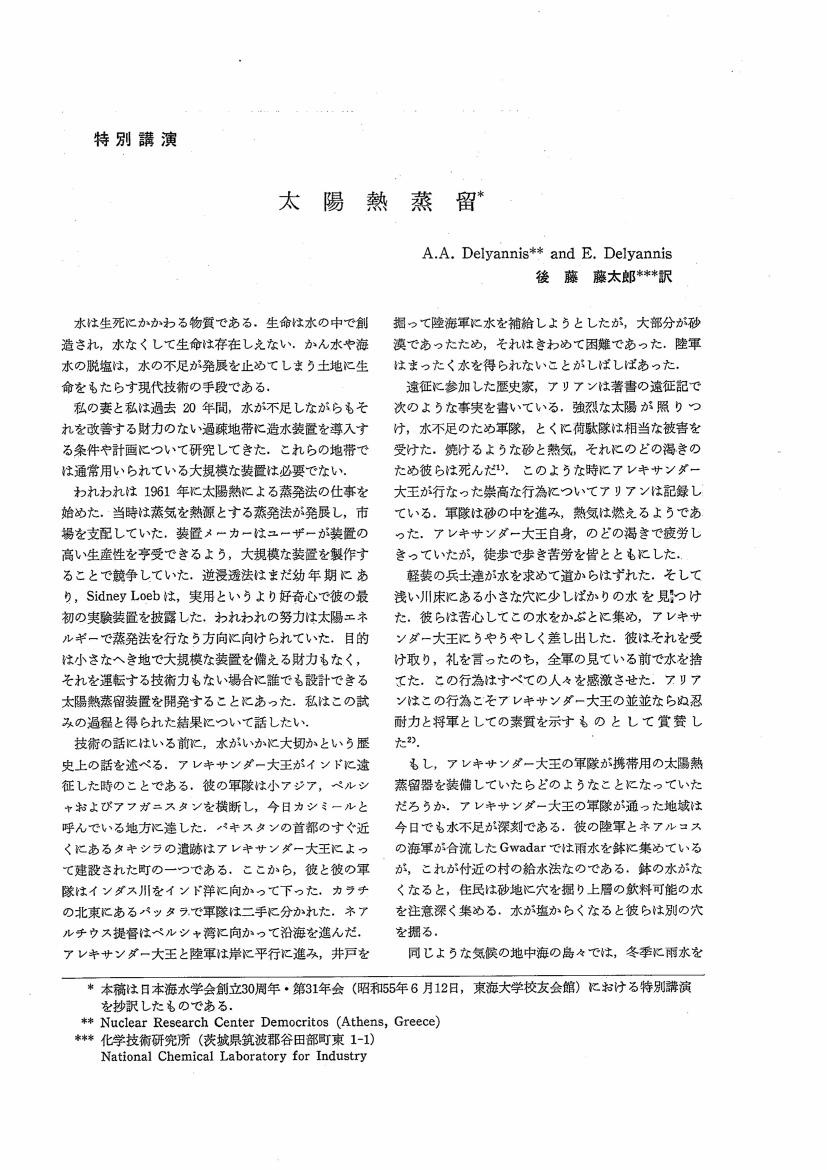- 著者
- IKESHOJI Norie
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan series B (ISSN:18834396)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.1, pp.25-37, 2023-09-30 (Released:2023-09-29)
- 参考文献数
- 25
Labour movement from East to West in the EU has been conspicuous since the enlargement of the EU in 2004, as one of the destinations in rural regions that have labour shortage problems. Research on migrating workers in the agricultural sector has accumulated over recent decades. However, there is not enough research about temporary workers in this sector in the region. Thus, this paper focuses on regional integration and issues related to the regional disparity from a case study of an agricultural sector that fulfils labour shortage by employing seasonal workers. Northern Limburg is the most prolific asparagus cultivating area due to the well-drained soil and warmer temperature. However, only a small number of farms engage solely in white asparagus production because it is challenging a temporary and intensive workforce for the short period needed for asparagus harvesting. All farmers that cooperated with interviews in this study employ seasonal workers with a supervisor system. The supervisor system works well for farm owners and seasonal workers with supervisor positions. However, the system has almost no advantage for seasonal workers without a supervisor position. Unless the wage gap between the West and the East disappears, hard work with low wages will probably persistently remain under capitalism. Therefore, researchers have to pay attention to the movement of temporary laborers who suffer the most uncertain working conditions.
1 0 0 0 橋面舗装における切削残存層の不透水性の回復手法に関する研究
- 著者
- 橋本 雅行 高橋 修 小野 秀一
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.9, pp.23-00031, 2023 (Released:2023-09-20)
- 参考文献数
- 15
橋面舗装の打換え工事において,舗装切削が既設の防水層や床版コンクリートに少なからずダメージを与える要因となっており,既設の防水層は,健全な状態であっても橋面舗装の基層と同時に再施工されるのが実状である.本研究ではこれらを課題として挙げ,防水層上の基層を薄層状態で残存させる切削工事を想定し,残存層を再利用することについて検討した.この残存層は,ひび割れなどの損傷が生じている可能性が高いものの,既設の防水層と床版コンクリートが健全であれば,新設時に近い状態まで不透水性を回復させることで,中間層として再利用できる可能性がある.このことから,残存層の不透水性の回復手法について検討し,有効性を評価した.その結果,アスファルト乳剤浸透工法は,残存層のひび割れを閉塞し,不透水性を回復できることを確認した.
- 著者
- ENDO Gen
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan series B (ISSN:18834396)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.1, pp.1-24, 2023-09-30 (Released:2023-09-29)
- 参考文献数
- 44
This study aims to revisit the claim of the “supermarket revolution theory” that modern retail formats leverage commercial standards, such as Good Agricultural Practice (GAP), to govern the production and distribution of fresh produce in developing countries. Using mangoes for export in Thailand as a case study, an empirical analysis was conducted focusing on the actual situation of GAP certification in Thailand and the role of producer organizations in mango distribution. The results revealed that the GAP certification system has not been thoroughly implemented. Even small-scale farmers who are not GAP-certified avoid this problem by organizing, and producer organizations play an important role in intermediate distribution. Conversely, large retailers and exporters also rely on the intermediate distribution function of producer organizations to source mangoes. In other words, Thailand’s mango production and distribution system, rather than being a “preferred-supplier system” led by large retailers, has a complementary relationship between the suppliers and retailers.
1 0 0 0 OA 太陽熱蒸留
- 著者
- A.A. Delyannis E. Delyannis 後藤 藤太郎
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.340-343, 1981 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 12
- 著者
- 近藤 晃
- 出版者
- 日本緑化工学会
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.144-147, 2022-08-31 (Released:2022-11-22)
- 参考文献数
- 11
スギコンテナ苗の育苗技術の構築を目的に,育苗時の潅水方法(底面給水と頭上潅水(常法))が苗木の成長,物質生産および根鉢形成に及ぼす影響について検討した。1 成長期間,両潅水法で育苗したコンテナ苗の苗高,根元径,形状比および苗木乾重(地上部,粗根,細根)には有意な差異は認められなかった。コンテナ苗の地下部は,根系が培地をしっかり包み込んだ根鉢が形成され,培地の崩落や根腐れは認められず,根鉢硬度(山中式硬度計による指標硬度)および細根率には有意な差異は認められなかった。スギコンテナ苗の育苗において,底面給水は頭上潅水と同等な育苗成績を示したことから,有効な潅水法と考えられる。
1 0 0 0 OA 両眼加重の働きと影響因子 -なぜヒトは2つの眼があるのか-
- 著者
- 若山 曉美 松本 長太 大牟禮 和代 松本 富美子 阿部 考助 田中 寛子 大鳥 利文 下村 嘉一
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.7-18, 2011 (Released:2012-02-22)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
両眼から得られた外界の視覚情報は、視覚野で統合され両眼の相互作用によって処理される。この働きについて検討することはヒトが両眼視下でどのように外界の視覚情報を処理しているかを知ることにつながる。本研究では両眼の相互作用である両眼加重に着目し、過去10年間に検討した正常成人における両眼加重の働き、さらに弱視や視野異常を伴う症例での両眼加重について述べる。 両眼加重の評価は、自動視野計Octopus 201、101、900の3種類の視野計を用い両眼刺激装置や両眼固視監視カメラを組み込むなど独自に開発して行った。また両眼からの視覚情報を収斂したことによる働きであるかは確率加重を超えているか検討した上で評価した。 両眼加重は、視標サイズ、網膜部位、認知課題による影響を受け、視標サイズは小さいほど、網膜部位では中心窩から偏心するほど、さらに認知課題では検出閾値よりも認知閾値で大きくなった。さらに閾上刺激を用いた反応時間についての検討では両眼の反応時間は単眼よりも短く、閾値で検討した両眼加重の結果と同様に視標サイズや網膜部位による影響を受けた。 以上の基礎的研究データから単眼で知覚困難な条件において両眼加重を働かせることによってより有効的に視覚情報を処理していると考える。さらに弱視や視野異常を伴う症例では明らかな両眼加重を認めず、正常成人とは異なる両眼での働きを示した。
- 著者
- Juan Luis UGARTE CABO Hideki FUKUDA Yasuyo ABE Noboru TAKAMURA Makoto OSAKI Zhaojia YE Yumiko KAWASHITA Keiko HONDA Kohei INADA Yuko KOBUKE Fumiaki SHINSHO Kiyoshi AOYAGI
- 出版者
- Nagasaki University School of Medicine
- 雑誌
- Acta Medica Nagasakiensia (ISSN:00016055)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.89-94, 2006 (Released:2006-11-22)
- 参考文献数
- 32
Good oral health is considered essential in maintaining of individual's good overall health. Information on oral problems and the behavior in visiting dentist is important for promoting oral health of the elderly. To elucidate the oral health status of the elderly in rural areas and factors affecting their oral health, we studied 147 people aged 60 years or over in a rural area of Nagasaki prefecture, Japan. We examined the dental status (dentate or edentate) and denture adaptability, and collected the information on socio-demographic variables, habits, chewing ability, visit to dentist for oral problems, self-perceived general health, and self-perceived oral health. About one-third of the subjects (47/147) had poor self-perceived oral health. Most socio-demographic variables were not associated with poor self-perceived oral health. Logistic regression analysis showed that poor chewing ability (odds ratio (OR): 3.4; 95% confidence interval (CI): 1.4-8.7), being dentate (OR: 6.6, 95% CI: 2.2-24.0), inadequate denture adaptability (OR: 3.7; 95% CI: 1.7-8.8), and no visit to dentist for oral problems (OR: 4.8; 95% CI: 1.8-14.2) were significantly associated with poor self-perceived oral health. In rural areas in Japan, adequate dental care and its good accessibility would be important for promoting the oral health in the elderly.
1 0 0 0 IR ベトナムの中の日本 : 日本のグローバリゼーションの一例・再論
- 著者
- 橋本 和孝 高橋 一得
- 出版者
- 関東学院大学[文学部]人文学会
- 雑誌
- 関東学院大学文学部紀要 (ISSN:02861216)
- 巻号頁・発行日
- no.129, pp.65-79, 2013
21世紀に入って、日本は"ベトナム・ブーム"ともいうべき現象を経験してきた。大量の日本人観光客がホーチミン市に群がる構図である。一方、日本企業はベトナムへの投資を増加させ、他方、ベトナム政府は、日本のODAや民間資金に期待している。ベトナムの大都市では、日本語学校や大学における日本語学科が増加し、日本人のためのビジネスが活発化してきた。ホーチミン市には、「リトル・ジャパン」と語るに相応しい界隈も登場した。今日では、2000年代前半にはなかった日本人会も存在し、ベトナムおよびホーチミンの日本商工会の会員数は激増を見せている。論文は、"ベトナムの中の日本"が、ベトナムの経済、社会、文化にいかなる影響を及ぼすかを探究しようとしたものであり、2005年発表した Japan in Vietnam: A Case Study of Japanese Globalization について再考したものである。
1 0 0 0 OA 大杉栄における「自己無化」言説 その特異性について
- 著者
- 鍵本 優
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.109-125, 2006-10-31 (Released:2016-03-23)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 OA 法会と和歌 ――伊勢の温子哀傷長歌への試論――
- 著者
- 吉井 祥
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.9, pp.1-11, 2018-09-10 (Released:2023-09-28)
本稿は、伊勢が中宮温子の死に関して詠歌した長歌(温子哀傷長歌)について、なぜ長歌体なのかという問題提起のもと、どのような場で詠歌され、どのような働きをしていたのかについて考察する。 まず歌の表現から、集団の代弁という機能と、追善法会を場として導き出す。また上代に見られる、人の死の際の儀礼に関わる長歌の系譜上に温子哀傷長歌も位置付けられるが、以後哀傷歌は個々の心情を詠うのが主流となることを述べる。
1 0 0 0 OA 広蔵院日辰の先師批判について
- 著者
- 田村 完爾
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.237-239, 1996-12-20 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 高アミロース米「越のかおり」で作成したライスサラダの食後血糖応答と食味評価
- 著者
- 榎 康明 前島 大輔 久保 希恵 長島 洋介
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.9, pp.339-344, 2020-09-15 (Released:2020-09-25)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
高アミロース米は食後血糖値が穏やかな機能性米としての利用が期待される一方,その米飯は硬く粘りの少ない特性を有し,普及の課題となっていた.そこで,高アミロース米「越のかおり」について,米飯としてではなくライスサラダとして摂取した場合における血糖応答と食味の評価を行い,以下の知見を得た.(1)コシヒカリと越のかおりの米飯と冷飯を調製し,RS量を測定した結果,越のかおりにおいてのみ,冷飯処理によるRS量の増加が認められた.(2)血糖応答評価では,コシヒカリ米飯と比較し,越のかおりのライスサラダにおいて,有意に低い血糖応答が認められた.(3)官能評価では,コシヒカリと越のかおりのライスサラダはともに高い評価となり,食感では,コシヒカリよりも高値傾向が認められた.
1 0 0 0 OA 船舶美学への一提言
- 著者
- 竹鼻 三雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 日本造船学会誌 (ISSN:03861597)
- 巻号頁・発行日
- vol.669, pp.137, 1985-03-25 (Released:2018-03-30)
1 0 0 0 OA カキ'松本早生富有'の平棚仕立て法における収量および果実品質
- 著者
- 林 公彦 牛島 孝策 千々和 浩幸 姫野 周二
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.346-353, 2004-07-15 (Released:2008-01-31)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 7 7
To reduce labor costs in the cultivation of Japanese persimmon which is prone to be too vigorous, a horizontal trellis training system was attempted as a practical method for lowering the tree height. The frameworks of an open center, 3.6 m high 'Matsumotowase-Fuyu' Japanese persimmon trees were altered to a horizontal frame at 1.8 m height on February 1992 by cutting back secondary scaffold branches at 1.5. to 1.6 m above ground level. The tree growth, yields and fruit quality of the altered trees were compared with the open-center free-standing trees control. One year after altering the framework, the canopy area on horizontally trellised trees expanded vigorously, compared with the control group. After pruning, the trees with altered the framework were left with twenty percent more lateral branches than the open center free-standing trees. Two years after altering, the number of shoots per canopy area was greater in the treated trees than in the control, but the number of shoots per lateral branches and mean shoot length did not significantly differ from the control group. Annual fruit yield was 300 kg/a higher in the horizontal trellis system than that of the unaltered free standing system group, and the number of fruits per canopy area exceeded 10 fruits/m2. Over 4-year period, the horizontally trellised trees produced more flowers per lateral branch than did the open center free-standing ones. Physiological fruit drop rates were lower in horizontally trellised trees than in those of the control. Fruit on the former was significantly heavier than that on the letter. The percentage of fruit weighing more than 260 g accounted for 61.2% of the total yield in horizontally trellised trees. During the period of 80 days after blossoming to harvest, fruit diameter increased significantly faster on horizontally trellised trees than that on the free standing trees. Similarly, the commencement of fruit skin coloring and harvest time was advanced in the treated trees compared with those of the control. In conclusion, by lowering tree height the horizontal trellis training system achieves the following: decreased harvest and pruning costs, increased yield and fruit weight, improved fruit quality, and advanced maturation. These advantages indicate that this system has a strong potential as a training system that will be used extensively in the near future.
1 0 0 0 OA カキ'西村早生'わい性系統樹における乾物生産と分配の特性
- 著者
- 文室 政彦
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3-4, pp.459-465, 1997 (Released:2008-05-15)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 5 4
西村早生わい性系統の果実生産力が高い原因を明らかにするために, 29年生および30年生樹を供試し,乾物生産と分配を検討した.1.強勢系統の地上部新鮮重および地下部新鮮重は, それぞれわい性系統より, 5.9倍, 5.3倍高かった. 材葉比およびT-R率は系統間に差がなかった.2.単位樹冠占有面積当たり収量は系統間に差がなかったが, 単位葉面積当たりおよび単位幹断面積当たり収量はわい性系統が強勢系統より高かった.3.着果樹の1樹当たり年間の乾物生産量は, 強勢系統がわい性系統より4.7倍高かった. 単位葉乾物重当たりおよび単位葉面積当たりの乾物生産量は系統間に差異はなかった. わい性系統は強勢系統より果実への乾物分配率が高く, 新梢および旧枝への分配率は低かった.4.適正着果樹は全摘果樹より, 1樹当たり年間の乾物生産量が強勢系統で1.3倍, わい性系統で2.2倍高く, 単位葉乾物重当たりおよび単位葉面積当たり乾物生産量は強勢系統で1.3倍, わい性系統で1.5倍高かった.以上の結果, '西村早生'わい性系統の果実生産力が強勢系統より高いのは, 葉の乾物生産力が高いのではなく, 果実への乾物分配率が高いためであることが明らかになった. また, わい性系統は葉量が顕著に少ないために樹体の全乾物生産量が低く, 加えて果実への乾物分配率が高いために新梢および旧枝への乾物分配率が低下し, 樹体をわい化させるものと考えられる.
1 0 0 0 OA OCRとLINEインターフェースによる処方箋入力業務効率化の研究
- 著者
- 小原 大智 田中 謙司 松田 悠希
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回 (2020) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.4Rin152, 2020 (Released:2020-06-19)
社会全体として自動化、IT化が求められており、機械学習技術の応用分野も広がっている。そこで本研究は、なかなか自動化、IT化が進んでいない医療分野における業務効率化を目的とし、その達成のためにOCR技術を利用した。現在、多くの薬局において処方箋の情報をパソコンへ入力する作業は手作業で行われている。そこでLINEをインターフェースとして、スマートフォンで撮影した処方箋の画像からOCRで情報を獲得するシステムを提案した。論文中で提案した前処理、テキスト処理の手法は処方箋から多くの情報を獲得することができた。我々の研究により日本語処方箋の文字認識に適した前処理・テキスト処理の手法、文字認識がしづらいフォーマットが明らかになり薬局業務の効率化に貢献するような結果が得られたと言える。
- 著者
- 千葉 槙太郎
- 出版者
- 日本西洋古典学会
- 雑誌
- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.50-63, 2020 (Released:2023-05-19)