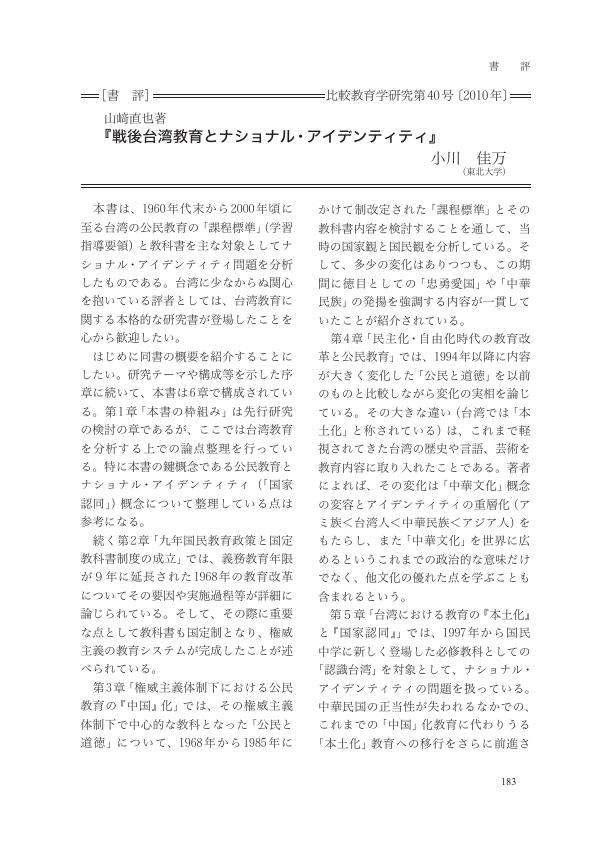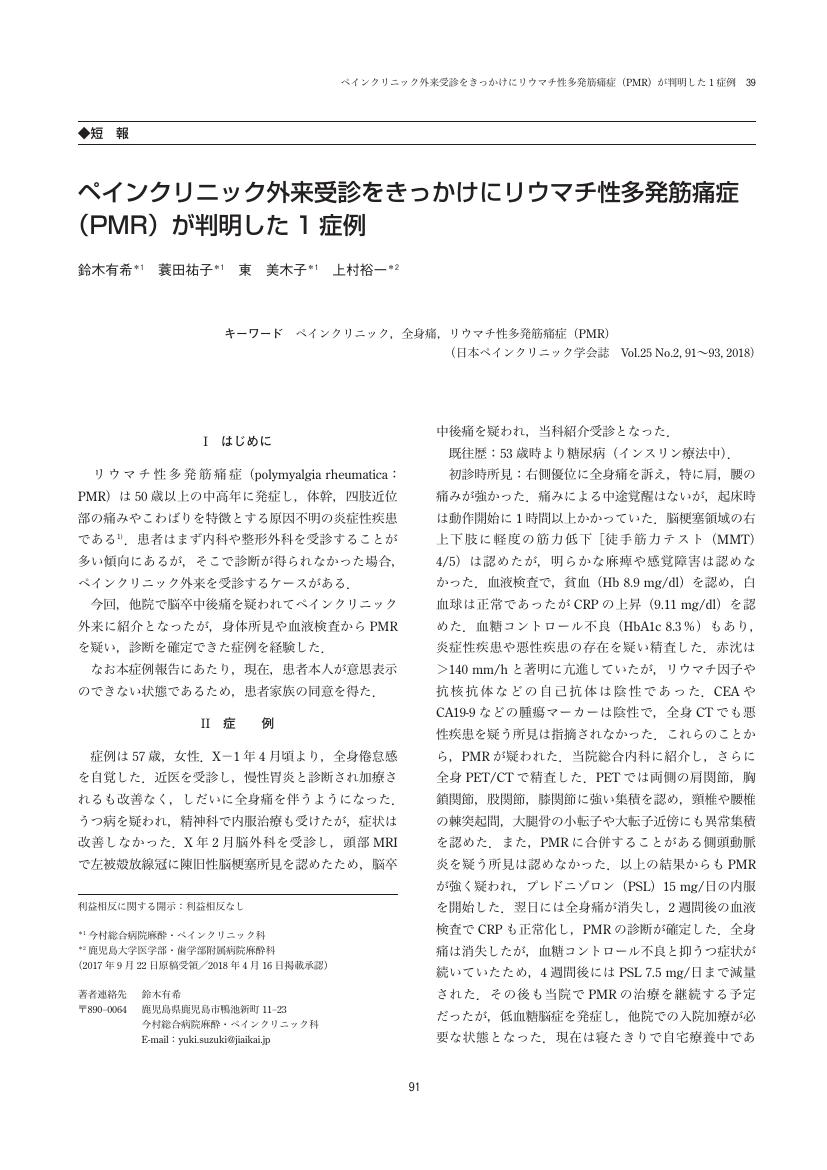- 著者
- Tomoaki Ishida Kei Kawada Kohei Jobu Tetsushi Kawazoe Naohisa Tamura Mitsuhiko Miyamura
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.460-466, 2022-04-01 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2
Bofutsushosan is a traditional Japanese Kampo medicine. In recent years, it has been reported to be effective in the treatment of lifestyle-related diseases, and its use is increasing. However, side effects from bofutsushosan administration are common, with drug-induced liver injury being the most frequently reported complication. In this study, we analyzed the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database regarding the occurrence of liver injury after bofutsushosan administration. The results showed that bofutsushosan presented a significant reporting odds ratio (ROR) signal [crude ROR 14, 95% confidence interval (CI) 12–17; p < 0.001], indicating liver injury. Furthermore, the incidents of adverse events following bofutsushosan administration, as recorded in the JADER database, were higher in women aged between 30 and 59 years. The results of logistic regression analysis in patients taking this agent showed that females in the aforementioned age range had higher odds of developing drug-induced liver injury (adjusted ROR 5.5, 95% CI 2.8–11; p < 0.001). Therefore, although bofutsushosan is a useful drug for lifestyle-related diseases, it may be necessary to refrain from its overuse, and caution should be taken during its occasional use to avoid severe adverse events.
- 著者
- Toshiaki Hirai
- 出版者
- The Keynes Society Japan
- 雑誌
- The Review of Keynesian Studies (ISSN:24356581)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.157-206, 2021 (Released:2021-11-30)
- 参考文献数
- 75
Keynes advocates his own social philosophy, “New Liberalism”, which is based on “social justice”, “economic efficiency”, and “individual liberty”. From the early 1920s to the mid-30s, he persisted in his critical stance on the “Versailles System”, which had plunged Europe into a devastating situation, first putting forward his reconstruction plan for Europe, and then engaging in activities of persuasion and criticism against many confusing pronouncements on reparations and war debt. It should be noted that these activities were based on this social philosophy and “Keynes as an economist” proceeded in tandem with them. The true value of Keynes’s “New Liberalism” lies in aiming at constructing a social organization that could achieve the best “economic efficiency” subject to “[social] justice”. Although Hobson and Hobhouse’s “New Liberalism”, which had had great influence on British society in the period 1880s-1910s, took the same side in its critical stance on Classical Liberalism, it is rather different from Keynes’s version.
1 0 0 0 OA Buerger病に対して胸腔鏡下交感神経切除術が奏功した一例
- 著者
- 高橋 剛士 福瀬 達郎 倉橋 康典 木場 崇之 高橋 鮎子 福田 正順 妻鹿 成治 板東 徹 田中 文啓 平田 敏樹 越久 仁敬 長谷川 誠紀 寺田 泰二 池 修 和田 洋巳 人見 滋樹
- 出版者
- The Japanese Association for Chest Surgery
- 雑誌
- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.5, pp.685-689, 1999-07-15 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 11
上肢に症状を呈したBuer墓er病に対して胸腔鏡下交感神経切除術が奏功した一例を経験したので報告する.症例は46歳, 男性.一日約40本, 25年の喫煙歴があった.約半年前から両上肢の指末梢側を中心として痺れ, 冷感が出現し始めた.Buerger病との診断にて星状神経節ブロック術を受けたが症状の改善は一時的で, 疼痛も増悪してきたため両側胸部交感神経節切除術を施行した。術直後より癖痛, 痺れ, 冷感の著しい改善を認め, 術後6週間を経た時点では痺れ, 冷感は全く認められず, 術前潰瘍化していた指の完全治癒を認めた.サーモグラフィーにても上肢末梢皮膚温の著明な上昇を認めた.レーザードップラー血流計を用いて指末梢側の組織間血流を計測したところ, 症状の改善とよく一致して血流の増加を認めた.このことからBuerger病における術前術後の組織間循環の評価に際してレーザードップラー血流計が有用であると考えられた.
1 0 0 0 がん診断のための呼気バイオマーカー分析法の開発
- 著者
- 手嶋 紀雄
- 出版者
- 愛知工業大学
- 雑誌
- 産学が連携した研究開発成果の展開 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 探索タイプ
- 巻号頁・発行日
- 2010
前立腺がん、乳がん等の患者の尿や呼気から健常者よりも高濃度のホルムアルデヒド(HCHO)やアセトアルデヒドが検出された報告がある。これらは揮発性があるため、呼気として排出されており、がん早期発見のための有力な呼気バイオマーカーである。そこで試料前処理を自動化する流れ分析法と分離分析が可能なキャピラリー電気泳動法(CE)を組み合わせた呼気分析のための流れ分析-CE法の開発を目的とした。今年度は、流れ分析とCEを結合するインターフェースの設計と流れ分析法によるHCHOの定量法の開発を行い、100%の目的達成には至らなかったが、今後も当初の目的を達成するため研究開発を続ける。
1 0 0 0 OA ドーピング意識に関する日本とイタリアの体育学専攻大学生の比較
- 著者
- 依田 充代 北村 薫
- 出版者
- Japan Society of Sports Industry
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.2_163-2_175, 2017 (Released:2017-04-15)
- 参考文献数
- 44
This study compares awareness about doping between Japan, which has less doping cases, and Italy, where doping is widespread, second only to that of Russia. The research sample was comprised of university physical education students. The item “opinion about doping” was divided into a doping item and a sports standards item, and the reliability of the scale was demonstrated by confirming the hypothesis model through structural equation modeling. Result 1: The Japanese group had a significantly lower value than the Italian group with regard to awareness of special doping (awareness to justify doping for the success of famous athletes and teams). Result 2: Italian students showed significantly stronger negative influences on “the spirit of fair play” and “doping awareness” than Japanese students. A stronger “spirit of fair play” significantly negatively influenced “doping awareness”. Furthermore, the Japanese students showed significantly stronger positive influences on “special doping” and “doping awareness” than Italian students. Conclusion: We can conclude the following: (1) Italian university students do not generally approve of doping but tend to approve of doping for the success of famous athletes and teams, whereas Japanese students do not; (2) in Italy, there is a tendency to not approve of general doping, reflecting a higher spirit of fair play; however, in Japan, there is only a weak relation between the spirit of fair play and doping awareness; and (3) the relation between special doping awareness on doping awareness is stronger in Japan than that in Italy.
1 0 0 0 OA 山﨑直也著『戦後台湾教育とナショナル・アイデンティティ』
- 著者
- 小川 佳万
- 出版者
- 日本比較教育学会
- 雑誌
- 比較教育学研究 (ISSN:09166785)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.40, pp.183-185, 2010 (Released:2023-07-19)
- 著者
- 前田 晃史 八田 圭司
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.533-539, 2022-06-30 (Released:2022-06-30)
- 参考文献数
- 16
本研究は,二次救急医療機関の救急外来を受診した感染症を疑う成人患者に対し,救急看護師が緊急度の高い患者を精度よく迅速に拾い上げることを目的に,SIRSの診断基準2項目以上満たすSIRS群(n=340)とqSOFAスコア2点以上のqSOFA群(n=12)および両群を満たすSq群(n=48)の緊急度・重症度などを比較した。緊急度判定時のバイタルサインは,Sq群の呼吸回数,心拍数,収縮期血圧,GCS,体温においていずれかの群に差があり,緊急度が高かった。院内死亡はSIRS群よりSq群が多く,SOFAスコア≧2点はSIRS群,qSOFA群よりSq群が多く,早期警告スコア2(NEWS 2)≧5点は,SIRS群よりqSOFA群とSq群が多かった。以上からSq群は緊急度・重症度ともに高く,全身状態を評価したうえでSq群を最優先とし,NEWS 2などの重症度の結果からSIRS群よりqSOFA群を優先することを提案する。
- 著者
- 原 葉月 水谷 元
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第65回春季研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.510-511, 2018 (Released:2018-06-21)
類似するものの中から目的の対象を選び取る際、私たちはラベルを用いることでその行為を容易にすることができる。しかしデザインを学んだ事のない人にとって、目的によって何に配慮して要素を選択すれば良いか判断することは困難である。そこで、キーホルダーを題材に差別化機能の側面を取り柄げ、人が対象をどのように識別しているか、また差別化する際の知覚情報の優位性がどのように認知に影響するかを考察した。これにより、目的に応じた要素の優位性を提示できるようなデザイン指針の作成を試み、ラベルを作成利用する際に制作者の経験不足を補うことを目的とした。
1 0 0 0 OA 自動面付システムの開発
- 著者
- 帆波 羊一
- 出版者
- 社団法人 日本印刷学会
- 雑誌
- 日本印刷学会誌 (ISSN:09143319)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.6, pp.402-403, 1993-11-30 (Released:2010-09-27)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA ヒト脾臓の構造と機能
- 著者
- 佐藤 孝 舘道 芳徳 菅野 将史 増田 友之
- 出版者
- 日本門脈圧亢進症学会
- 雑誌
- 日本門脈圧亢進症学会雑誌 (ISSN:13448447)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.344-347, 2009-12-31 (Released:2012-12-28)
- 参考文献数
- 12
脾臓は門脈系に介在する末梢最大のリンパ装置であるが,血液濾過装置としても機能している.その構造は,細網組織を骨格とする枠組みの中に白脾髄,周辺帯,赤脾髄が形成されている.ヒト脾臓では,周辺帯,赤脾髄で動脈末端は開放性に終わり,その特異な微小循環系は脾臓の持つ血液濾過・浄化作用と密接に関わっている.血管鋳型標本を用いた検討からは,部分的脾動脈塞栓術(PSE)における塞栓部位は内径1 mm 前後の脾柱動脈と考えられる.
1 0 0 0 Price Rank Prediction of a Company by Utilizing Data Mining Methods on Financial Disclosures
- 著者
- Mustafa Sami KACAR Semih YUMUSAK Halife KODAZ
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems (ISSN:09168532)
- 巻号頁・発行日
- vol.E106-D, no.9, pp.1461-1471, 2023-09-01
- 被引用文献数
- 1
The use of reports in action has grown significantly in recent decades as data has become digitized. However, traditional statistical methods no longer work due to the uncontrollable expansion and complexity of raw data. Therefore, it is crucial to clean and analyze financial data using modern machine learning methods. In this study, the quarterly reports (i.e. 10Q filings) of publicly traded companies in the United States were analyzed by utilizing data mining methods. The study used 8905 quarterly reports of companies from 2019 to 2022. The proposed approach consists of two phases with a combination of three different machine learning methods. The first two methods were used to generate a dataset from the 10Q filings with extracting new features, and the last method was used for the classification problem. Doc2Vec method in Gensim framework was used to generate vectors from textual tags in 10Q filings. The generated vectors were clustered using the K-means algorithm to combine the tags according to their semantics. By this way, 94000 tags representing different financial items were reduced to 20000 clusters consisting of these tags, making the analysis more efficient and manageable. The dataset was created with the values corresponding to the tags in the clusters. In addition, PriceRank metric was added to the dataset as a class label indicating the price strength of the companies for the next financial quarter. Thus, it is aimed to determine the effect of a company's quarterly reports on the market price of the company for the next period. Finally, a Convolutional Neural Network model was utilized for the classification problem. To evaluate the results, all stages of the proposed hybrid method were compared with other machine learning techniques. This novel approach could assist investors in examining companies collectively and inferring new, significant insights. The proposed method was compared with different approaches for creating datasets by extracting new features and classification tasks, then eventually tested with different metrics. The proposed approach performed comparatively better than the other machine learning methods to predict future price strength based on past reports with an accuracy of 84% on the created 10Q filings dataset.
- 著者
- 田口 俊夫
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.9, pp.22-00290, 2023 (Released:2023-09-20)
- 参考文献数
- 41
首都高速道路横羽線の横浜都心部への延伸部分を地下化した事案は, 一旦都市計画決定した高速道路事業を変更したものである.首都高速道路を所管する建設省と高速道路と路線で競合する市営地下鉄を所管する運輸省, そして首都高速道路公団と神奈川県に対して, 都心部再開発の軸線として大通公園を構想する横浜市が主導して 1968年から一年間に及ぶ総合的調整作業を行った.自治体が都市景観の保全という地域的価値観を掲げ, 路線的かつ構造的に競合する都市インフラ事業を総合的に調整した.地域の価値観により都市づくりを総合的に実践するため, 飛鳥田一雄市政は都市プランナー田村明を招き企画調整室を立ち上げ, 総合的調整の事務局とした.当研究の目的は, それまで詳細が不明であった高速道路地下化に関わる総合的調整過程を明らかにすることである.
- 著者
- 杉下 由行 林 邦彦 森 亨 堀口 逸子 丸井 英二
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.2, pp.127-133, 2012-03-20 (Released:2013-04-12)
- 参考文献数
- 16
【目的】我が国では,結核予防対策の一環として BCG 接種が実施されている.これは他の予防接種と同様に市町村単位で実施され,その接種体制は各自治体で異なっている.本研究の目的は,BCG 接種体制の違いによるBCG 接種率への影響を明らかにすることである.【対象と方法】対象地域は東京都多摩地区の30 市町村とした.市町村の BCG 接種体制を5 つのグループに分類し,生後6 カ月に達するまでの BCG 累積接種率をグループ間で比較した.解析は,従属変数を生後6 カ月に達するまでの BCG 接種の有無,独立変数をBCG 接種体制とし,BCG 接種体制以外の BCG 接種に関係すると考えられる市町村特性を共変量として独立変数に加え,多変量ロジスティック回帰分析を行った.因子評価はオッズ比を用い 95% 信頼区間で検定した.【結果】調整オッズ比から,5 つのグループにおいて,乳児健診併用で毎月実施の集団接種を基準とした場合,BCG 未接種者の人数は,単独(乳児健診非併用)で毎月実施の集団接種 (adj. OR : 4.01 CI : 2.24~7.11),単独で隔月実施の集団接種 (adj. OR : 15.59 CI : 10.10~24.49),個別接種 (adj. OR : 15.61 CI : 9.05~27.26),単独で隔月未満実施の集団接種 (adj. OR : 48.17 CI : 29.62~79.75) の順に多くなる傾向にあった.【結論】BCG 接種体制が BCG 累積接種率に影響していた.集団接種での乳児健診併用や高い実施頻度の確保が BCG 接種率向上に役立つと考えられた.
1 0 0 0 OA カバーロールストレッチを用いた剥がれにくいテーピング
- 著者
- 石山 修盟
- 出版者
- 一般社団法人 日本アスレティックトレーニング学会
- 雑誌
- 日本アスレティックトレーニング学会誌 (ISSN:24326623)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.27-30, 2016-03-31 (Released:2019-05-27)
1 0 0 0 OA ペインクリニック外来受診をきっかけにリウマチ性多発筋痛症(PMR)が判明した1症例
- 著者
- 鈴木 有希 蓑田 祐子 東 美木子 上村 裕一
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.91-93, 2018-06-25 (Released:2018-06-29)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 被災経験のあった地域での水害リスクと土地価格・人口の関係性分析
- 著者
- 森田 将彬 佐々木 邦明
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.9, pp.22-00194, 2023 (Released:2023-09-20)
- 参考文献数
- 20
近年,都市部の浸水や河川の氾濫,土砂災害といった被害が甚大化する事例が相次ぎ,水害へのさらなる対策強化が求められている.その一方で,国土交通省および都道府県が定める浸水想定区域において,人口や世帯数が全国的に増加している.多くの都市で,災害リスクを避け都市機能を集約させるといった,都市計画マスタープランが立案されているにもかかわらず,適切に機能していないと考えられる.そこで,近年になって浸水被害を経験した地域の地価や人口・世帯数などに着目し,水害の経験や浸水想定が及ぼした影響を,DID分析を用いて検証した.その結果,浸水被害は人口や地価に対して正の効果をもたらしており,水害の経験が必ずしも地域の人口の減少や地価の低下につながらず,増加する影響を与えていることが示された.
1 0 0 0 OA レッサーパンダの舌乳頭とその結合織芯の走査型電子顕微鏡による観察
- 著者
- 江村 正一 奥村 年彦 陳 華岳
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.37-43, 2009 (Released:2009-07-16)
- 参考文献数
- 41
レッサーパンダの舌表面を肉眼にて観察し,さらに舌乳頭およびその結合織芯を走査型電子顕微鏡で観察した.肉眼所見では,舌の先端は円く弓状を呈し,舌正中溝および舌隆起は観察されなかった.茸状乳頭は舌体に比し舌尖において密に存在した.有郭乳頭は,舌体後部において円形を呈し,V字形に並んで左右それぞれ5個観察された.葉状乳頭は観察されなかった.走査型電子顕微鏡により舌尖および舌体の糸状乳頭を観察すると,シャベル状の主乳頭とその左右から突き出た数本の針状の二次乳頭からなった.糸状乳頭の結合織芯の形態は,基部から多くの小突起がでる構造として観察され,舌尖と舌体とで異なった.すなわち,舌尖の結合織芯は舌体のやや小型であり,舌尖の中でも外側の方が内側より細く針状構造を呈した.茸状乳頭はそれら糸状乳頭の間にドーム状構造として散見され,舌体より舌尖に多かった.茸状乳頭の結合織芯は,円柱状を呈しその頂上には陥凹が存在した.有郭乳頭の表面は平坦で,乳頭は輪状郭により取り囲まれ,乳頭と輪状郭の間に輪状溝が存在した.有郭乳頭の結合織芯は,球状で表面には多数の突起が存在した.有郭乳頭の外側には,大型の円錐乳頭が見られるとともに多数の分泌腺の開口部が観察された.このような開口部は上皮を剥離するとより顕著となった.
1 0 0 0 OA 日本医療・病院管理学会(旧:日本病院管理学会)年表
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療・病院管理学会
- 雑誌
- 日本医療・病院管理学会誌 (ISSN:1882594X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.12-15, 2013 (Released:2013-04-10)
1 0 0 0 OA 日本医療・病院管理学会(旧日本病院管理学会)五十年史概要
- 著者
- 河口 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療・病院管理学会
- 雑誌
- 日本医療・病院管理学会誌 (ISSN:1882594X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.9-11, 2013 (Released:2013-04-10)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1