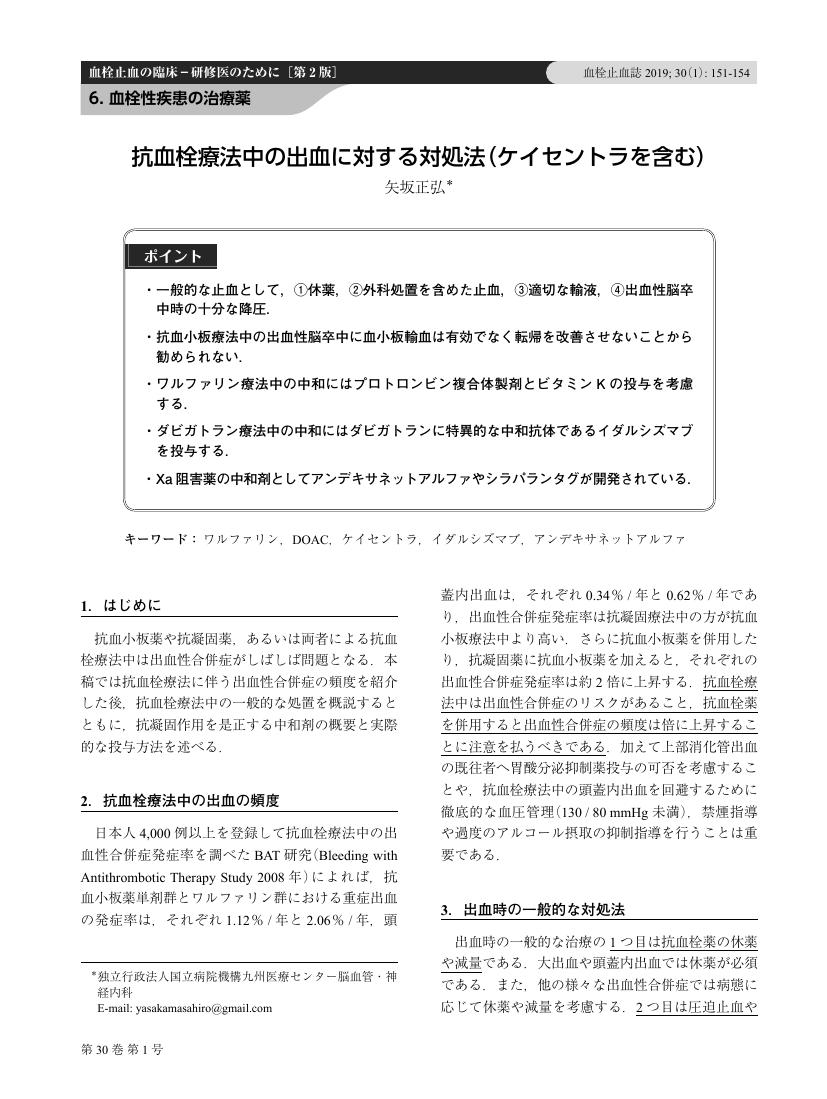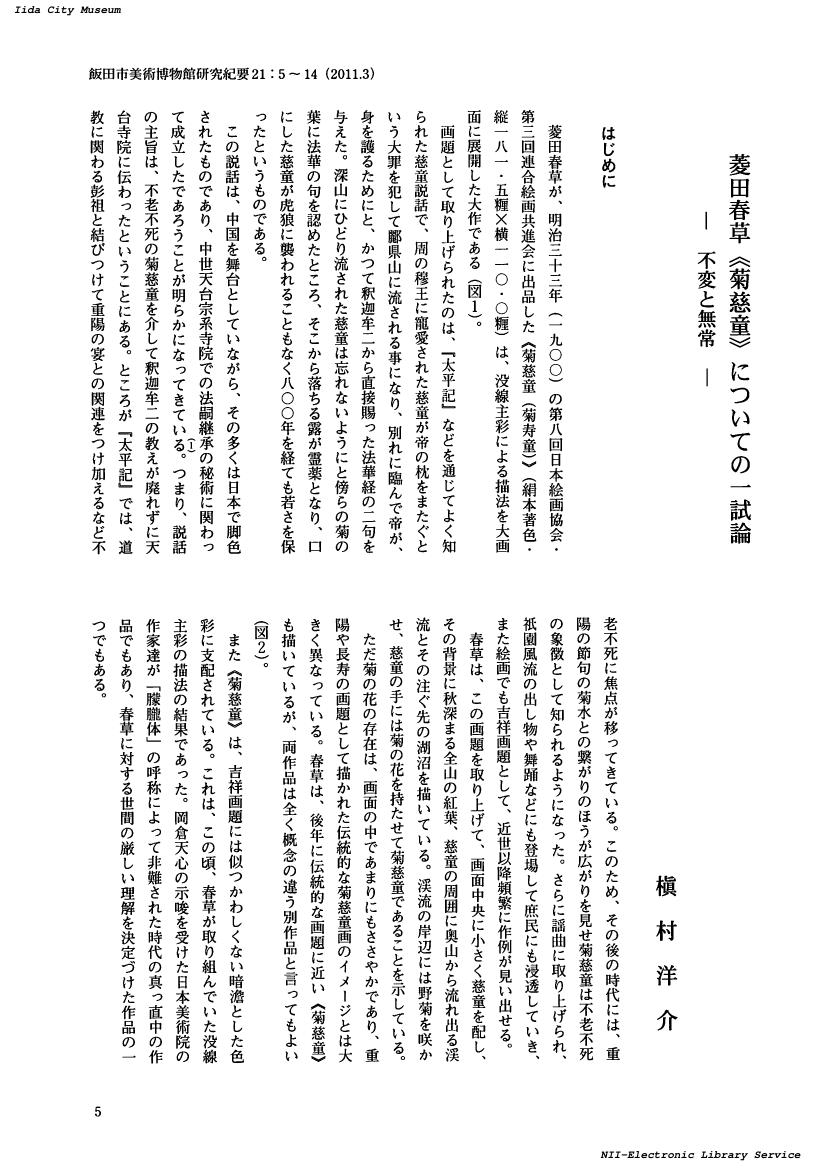- 著者
- Yu Odake Naoto Fukutani Kanako Shimoura Tappei Morino Natsuki Matsumura Niu Qian Yuki Shinohara Kohei Mukaiyama Momoko Nagai-Tanima Tomoki Aoyama
- 出版者
- Japan Society for Occupational Health
- 雑誌
- Environmental and Occupational Health Practice (ISSN:24344931)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.2020-0024-OA, 2021 (Released:2021-06-25)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
Objectives: This study aimed to examine the factors for reducing monetary loss due to presenteeism by using a tailored healthcare web-application among office workers with chronic neck pain. Methods: The study was single-arm pre-post comparison study using secondary data of 130 Japanese office workers with chronic neck pain who used a tailored healthcare web-application (web-app) over 12 weeks. This data was obtained from BackTech Inc. (Kyoto, Japan), which manages the healthcare web-app. The primary outcome measure was the monetary loss due to presenteeism based on the quality and quantity method. Secondary outcome measures were intensity of physical symptoms measured by the Visual Analog Scale, frequency of web-app use obtained from the database, and the risk of depression score assessed by the Depression and Suicide Screen. Results: Eighty-six participants were included in the complete-case analysis. Monetary loss due to presenteeism and the risk of depression reduced, while physical symptoms improved significantly (p<0.01) after using the web-app. After covariate adjustment, decrease in neck pain intensity (β=0.25, confidence interval=2.34 to 32.66) and high frequency of web-app use (β=−0.24, confidence interval=−10.29 to −0.63) were significantly associated with a reduction in monetary loss due to presenteeism. Conclusion: Neck pain intensity and frequency of web-app use may be important factors for reducing monetary loss due to presenteeism among office workers with chronic neck pain who used a tailored health care web-app.
1 0 0 0 OA 柔軟全周囲クローラ(FMT) — 無限軌道と脊椎構造を用いた新しい移動機構 —
- 著者
- 衣笠 哲也 大谷 勇太 土師 貴史 吉田 浩治 大須賀 公一 天野 久徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.107-114, 2009 (Released:2011-11-15)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 8 5
In the past decade, search type rescue robots have been focused on. Most robots took “linked mobile track” type such as snakes, so as to obtain high quality against unknown irregular surfaces. However the linked mobile track has some joints and sometimes they shut in some debris and stuck on it. In addition, many links increase total weight of robots and control complexity. In the paper, we propose a new type mobile mechanism, Flexible Mono-Tread Mobile Track (FMT) and develop a prototype called “Rescue mobile Track No.2 (RT02) WORMY”. The prototype consists of a flexible chain and a vertebrae like structure. Moreover, we investigate its performance against the irregular surfaces.
1 0 0 0 OA 政策評価における行政学理論の交錯 -再検討にむけて-
- 著者
- 山谷 清志
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本評価学会
- 雑誌
- 日本評価研究 (ISSN:13466151)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.3-14, 2023-05-31 (Released:2023-09-28)
- 参考文献数
- 45
1990年代末に日本で導入された政策評価は、総務省「政策評価に関する標準的ガイドライン」(2001年)によれば、国民に対する行政の説明責任を徹底する、国民本位の効率的で質の高い行政を実現する、国民的視点に立った成果重視の行政への転換を図る、この3つの目的を持つ。行政学はこの目的を持つ政策評価の安定的運用を考えるために行政責任論、行政管理論、NPM理論から政策評価を解釈しようとした。ただ、いずれの解釈にも難がある。ここではその行政学の取り組みの歴史を振り返り、なぜ2021年から政策評価は再検討されるようになったのか、その意味を考察したい。政策評価の再検討が実務で成功する条件を探るのが、本稿のねらいである。
1 0 0 0 OA 社会的インパクト評価の系譜 ーマネジメント支援のための評価への進化ー
- 著者
- 今田 克司
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本評価学会
- 雑誌
- 日本評価研究 (ISSN:13466151)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.27-37, 2022-09-30 (Released:2023-09-28)
- 参考文献数
- 26
近年、「社会的インパクト評価」について論じられることが増えてきた。一方で、評価研究の中で、この概念が定着しているとは言い難い。本論では、社会的インパクト評価の概念整理を試み、国内外における理論や実践の議論が、概念を成長・進化させていると論じる。具体的に取り上げるのが、2010年代中盤以降の北米(特に米国)におけるインパクト投資とインパクト測定・マネジメント(IMM)の動きと、日本国内における内閣府社会的インパクト評価ワーキンググループによる概念整理である。これらを概観し、新たに見出された社会的インパクト評価の特質として、学び・改善、マネジメント支援や意思決定のための評価の側面が強調されていることを述べる。
- 著者
- Takeshi SHIMIZU Shingo TOYOTA Motohide TAKAHARA Kazuhiro TOUHARA Tatsuya HAGIOKA Yuhei HOSHIKUMA Takamune ACHIHA Tomoaki MURAKAMI Maki KOBAYASHI Haruhiko KISHIMA
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023-0070, (Released:2023-09-23)
- 参考文献数
- 15
There have been a number of anastomosis methods of bypass techniques reported for moyamoya disease. However, there are yet no randomized controlled trials conducted on the anastomosis method. Retrograde blood flow of the superficial temporal artery (STA) may be used as one of the donor options. Here, we examined the tolerability of retrograde bypass using a distal stump of the parietal STA (dsPSTA). Anastomosis between the dsPSTA and middle cerebral artery (MCA) was performed for consecutive patients with moyamoya disease whose parietal STA was visualized to be longer than 10 cm using contrast-enhanced computed tomography preoperatively. Retrospectively, we have examined its patency and clinical outcome. Retrograde dsPSTA-MCA bypass was performed in 22 hemispheres of 17 patients. The patency of retrograde dsPSTA-MCA bypass in all 22 anastomoses could be confirmed during follow-up periods (mean: 5.5, range: 2-15 years). No recurrence of ischemic events was observed. The dsPSTA-MCA bypass using retrograde blood flow has been determined as one of the many promising anastomosis methods, and long-term patency was achieved in moyamoya disease.
1 0 0 0 OA 疾病及び関連保健問題の国際統計分類について
- 著者
- 秋山 光浩 松浦 恵子 今津 嘉宏 及川 恵美子 首藤 健治 渡辺 賢治
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.17-28, 2011 (Released:2011-07-08)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
2015年に改訂される予定のICD—11に漢方医学を含む東アジア伝統医学を導入することが検討されている。このことがどのような意義があるのかを検証するために,ICDそのものの理解が必要である。本稿ではICDの歴史・意義・問題点につき整理し,何故伝統医学を入れるに至ったかの背景について述べる。ICDは,1900年から国際的に使用されている分類で,その内容も当初の死因のための分類から疾病分類の要素を加味し,さらに,保健サービスを盛り込むなど,社会の変化に対応した分類となっている。現在のわが国での活用も,死亡統計,疾病統計など各種統計調査にとどまらず,臨床研究等幅広いものとなり,今後さらにその利用範囲は拡大するものと考えられる。一方,ICD—10と医学用語の関係や臨床における疾病分類としての使い勝手など,様々な問題が山積している。また,実際に使用している国が先進国を中心に限定されており,人口の多い,アジア地域での統計が取れていない。2015年の大改訂(ICD—10からICD—11)では,紙ベースから電子データとするとともに,東アジア伝統医学分類を盛り込むことで,アジア地域へのICDの普及促進を図る。
- 著者
- 並本 美喜雄 磯 親
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.174-185, 1957 (Released:2017-10-02)
1 0 0 0 OA (ヘ)中間子流体の状態方程式と相互作用の型(5.超高エネルギーシンポジウム報告)
- 著者
- 江沢 洋 友沢 幸男 梅沢 博臣
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.186-190, 1957 (Released:2017-10-02)
1 0 0 0 音楽療法 ―歌による発声リハビリテーション―
- 著者
- 羽石 英里
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.160-164, 2023 (Released:2023-09-28)
- 参考文献数
- 9
本稿では,発声・発話機能の改善を目的とする歌によるリハビリテーション「音楽療法ボイスプログラム(MTVP)」について解説する.この介入プログラムは,パーキンソン病患者を対象とし,歌うことの運動療法的な効果に着目したものである.歌うことが呼吸器官や体幹の筋肉をダイナミックに活用した「運動」であることは,リアルタイムMRIで確認されたプロ歌手による横隔膜の巧みなコントロールにも表れている.また,長年歌うことを習慣としてきた高齢者の発声機能が,習慣としてこなかった者に比べ高いことから,歌を継続することのメリットも推察される.MTVPは,身体のウォームアップ,呼吸・発声・構音の訓練,音読訓練,好みの曲の歌唱等を含む一連の活動からなる.音楽療法士は,歌うことに伴う心理的な影響も勘案しながら,発声・発話能力の向上を目指す.
- 著者
- Shohei Nakamura Nanami Ito Ayumi Sakurada Takatoshi Sakamoto
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.9, pp.687-694, 2023-09-01 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 43
Lactose is an excipient used extensively for bulking, diluting, and molding active pharmaceutical ingredients in tablet manufacturing. Particularly, granulated lactose (GL) intended for direct powder compression has distinct properties due to differences in manufacturing methods. It contributes to handling blended powders for tableting and tablet quality. In this study, we aimed to compare the functions of different forms of GL added as excipients during direct powder compression on the tablet properties and the effect of magnesium stearate (Mg-S) used as a lubricant on each type of GL. Different GL types obtained using different manufacturing methods (agitated granulation, GL-AG; spray-dried granulation, GL-SD; fluidized bed granulation, GL-FB) were blended with maize starch, low-substituted hydroxypropyl cellulose, and paracetamol in a V-type blender for 10 min. Mg-S was added at varying amounts (0.1, 1.0, and 2.0%) and blending times (5, 10, and 30 min) for the nine types of blended powders for tableting formulation. The powders were tableted, and the tablets were evaluated for weight and drug loading variations, tensile strength, friability, and disintegration time. When tablets with the same blending conditions were compared, the tensile strength and disintegration time were in the order of GL-FB > GL-SD > GL-AG. For each GL, we analyzed the effects of changes in the added amount of Mg-S and blending time using contour plots, evaluated the effects of blending conditions on tablet properties, and determined the target tablet properties. We investigated the optimization of the lubricant blending conditions to obtain suitable tablets.
1 0 0 0 OA 抗血栓療法中の出血に対する対処法(ケイセントラを含む)
- 著者
- 矢坂 正弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.151-154, 2019 (Released:2019-02-25)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 坂田 浩之
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.11-13, 2020-04-27 (Released:2020-04-27)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
Photographs of Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) were classified based on affect valence, and they have been used for the investigation of mental state decoding abilities depending on their valence. The present study aimed at classifying photographs of the Asian version of the RMET that can also be applied to the Japanese by affect valence, as in the original RMET. Japanese female university students were presented with 36 photographs of Asian RMET, and asked to evaluate the affect valence of each photograph. In the resulting classification of the photographs, 20 were negative, 5 were neutral, and 11 were positive.
- 著者
- Hisayoshi KUBOTA Hiroshi SUGITA
- 出版者
- Faculty of Mathematics, Kyushu University
- 雑誌
- Kyushu Journal of Mathematics (ISSN:13406116)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.391-404, 2002 (Released:2006-07-06)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 4 8
1 0 0 0 OA 自己と他者の「一体感」形成の脳メカニズム
- 著者
- 高橋 智彦 金廣 琴乃 土屋 智史 石田 哲也
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.9, pp.22-00365, 2023 (Released:2023-09-20)
- 参考文献数
- 21
本研究は,腐食環境にある既設構造物を対象として,今後の合理的な構造物の運用と維持管理を支援する解析的検討について取りまとめたものである.具体的には,供用開始から35年以上が経過した桟橋上部工を対象に,材料と構造を連成したマルチスケール統合解析を適用して,建設時からの塩害劣化進行を評価した.その際,過去に実施した劣化調査に加え,薄板モルタルによる飛来塩化物イオン量と構造物周辺の気象計測を追加実施して,概ね等価な長期評価用の作用履歴を推定した.それにより,現時点での変状を再現するとともに,複数のシナリオのもとでの塩害劣化に対する将来予測を実施した.さらに,耐荷力評価の一例として,材齢100年時に床版中央を静的に押抜く載荷解析を行い,塩害による材料劣化後の残存耐荷力評価を行った.
- 著者
- 三井 一希 戸田 真志 松葉 龍一 鈴木 克明
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.157-169, 2023-01-20 (Released:2023-02-01)
- 参考文献数
- 26
本研究では,情報端末を活用した授業の設計を支援することを目指したシステムの開発を行い,その操作性と有用性(ユーザにとって有用と捉えられるか)を検証した.システムの設計にあたっては,先行研究から現状の問題点を抽出するとともに,ユーザーニーズの調査を行って5つの機能要件を定めた.そして,機能要件を満たすシステムをスマートフォン等で動作するアプリケーションとして開発した.開発したシステムを16名の教師が評価したところ,操作性については問題点が見られなかった.また,有用性については,特徴的な機能であるSAMR モデルに基づき授業事例を段階的に示すことを含め,機能要件に定めた項目について概ね良好な評価を得た.一方で,書き込み機能や実践のアップロード機能といったユーザ参加型の機能には,抵抗を示す教師が一定数いることが示された.
1 0 0 0 OA ファジイ論理のほとんど全て(23)-含意再考-
- 著者
- 中島 信之
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第27回ファジィシステムシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.2, 2011 (Released:2012-02-15)
非古典論理において含意は非常に重要であるにもかかわらず,これまで必ずしもきちんと調べられていなかった。本発表では,一般の非古典論理および,特にファジイ論理における含意について調べる。
1 0 0 0 OA 菱田春草《菊慈童》についての一試論-不変と無常-
- 著者
- 槇村 洋介
- 出版者
- 飯田市美術博物館
- 雑誌
- 飯田市美術博物館 研究紀要 (ISSN:13412086)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.5-14, 2011 (Released:2017-09-29)
- 著者
- 杉本 達哉 杉浦 聡志 高山 雄貴
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.9, pp.23-00091, 2023 (Released:2023-09-20)
- 参考文献数
- 46
本研究では,交通混雑を考慮したFujita and Ogawa (1982)型の定量的都市経済モデルを開発する.そのために,開発したモデルにポテンシャル関数が存在することを示したうえで,その性質を利用した効率的な数値解析手法を提示した.そして,開発したモデルを使った二次元格子状空間下での解析により,本モデルが複数都心の形成を表現できることを示した.さらに,1,656地点・11.7万リンクからなる金沢都市雇用圏を対象とした,具体的な解析例を通じて,本モデルが複雑な道路ネットワークを含む計算を効率的に実施できることを明らかにした.
- 著者
- Masafumi Takafuji Masaki Ishida Satoshi Nakamura Kei Nakata Haruno Ito Takanori Kokawa Kensuke Domae Suguru Araki Shiro Nakamori Junko Ishiura Kaoru Dohi Hajime Sakuma
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2023-0018, (Released:2023-09-28)
- 参考文献数
- 37
Purpose: The purposes of this study were to compare global coronary flow reserve (CFR) between patients with idiopathic dilated cardiomyopathy (DCM) and risk-matched controls using cardiac MRI (CMR), and to evaluate the relationship between global CFR and CMR left ventricular (LV) parameters.Methods: Twenty-six patients with DCM and 26 risk-matched controls who underwent comprehensive CMR examination, including stress-rest coronary sinus flow measurement by phase contrast (PC) cine CMR were retrospectively studied. LV peak global longitudinal, radial, and circumferential strains (GLS, GRS, and GCS) were determined by feature tracking.Results: Patients with DCM had significantly lower global CFR compared with the risk-matched controls (2.87 ± 0.86 vs. 4.03 ± 1.47, P = 0.001). Among the parameters, univariate linear regression analyses revealed significant correlation of global CFR with LV end-diastolic volume index (r = –0.396, P = 0.045), LV mass index (r = –0.461, P = 0.018), GLS (r = –0.558, P = 0.003), and GRS (r = 0.392, P = 0.047). Multiple linear regression analysis revealed GLS as the only independent predictor of global CFR (standardized β = –0.558, P = 0.003).Conclusion: Global CFR was significantly impaired in patients with idiopathic DCM and independently associated with LV GLS, suggesting that microvascular dysfunction may contribute to deterioration of LV function in patients with idiopathic DCM.