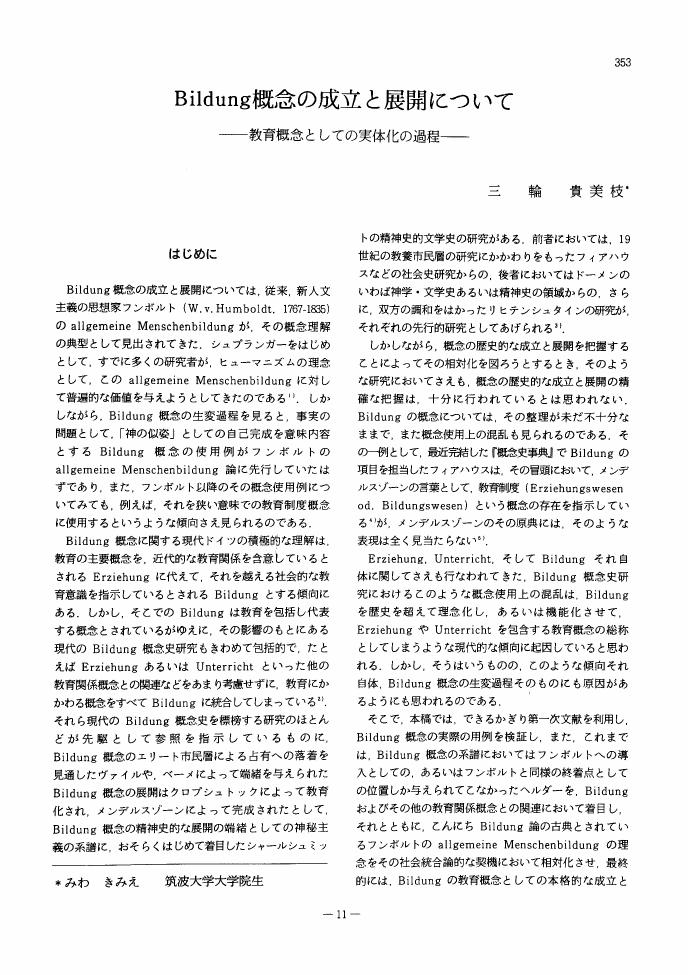1 0 0 0 OA 駅構造を組み込んだ列車遅延シミュレーションの開発
- 著者
- 小林 渉 岩倉 成志
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.5, pp.I_1067-I_1074, 2016 (Released:2016-12-23)
- 参考文献数
- 10
筆者らが開発を進めてきた遅延の発生や波及を高精度に再現する列車遅延連鎖シミュレーションシステムは,信号保安システムの改良や輸送力増強に伴うオペレーションの変更など広範な遅延対策の効果を計測することができるが,遅延対策として有効な階段やコンコース増設などの駅構造の改良の効果を計測することはできなかった.このため本研究では,駅構造の違いによって乗車位置が変化し,それが列車遅延に与える影響を予測可能にする乗車駅ホーム上の旅客の乗車位置選択モデルを構築する.ケーススタディとして階段を増設をした場合の遅延予測を行う.結果として乗車位置選択モデルは乗車分布と降車分布を概ね再現できた.シミュレーションシステムでの再現性もおおむね良好であり,また駅改良による遅延削減の例も示すことができた.
- 著者
- 中村 大輝 堀田 晃毅 西内 舞 雲財 寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- pp.45098, (Released:2022-01-21)
- 参考文献数
- 47
本研究は,社会認知的キャリア理論(Social Cognitive Career Theory, SCCT)に基づき,我が国におけるSTEMキャリア選択に影響する要因とその性差を検討した.OECDが実施したPISA2015調査の日本データを用いて,SCCTのキャリア選択モデルを追試した結果,当該モデルは日本の高校生のデータにも十分に適合することが明らかになった.多母集団同時分析の結果より,STEM職業志望への有意な影響が認められた要因としては「自己効力感」「結果期待」「興味」「社会経済文化的背景」があった.このうち,「結果期待」「興味」「社会経済文化的背景」の影響には有意な性差が見られたが,「自己効力感」の影響には性差が見られなかった.本研究の結果に基づけば,STEMキャリア選択者を増加させるためには,性別ごとに異なる介入方法が有効である可能性がある.
1 0 0 0 OA 与薬に関する訪問看護師とホームヘルパーの連携モデルの考案
- 著者
- 小枝 美由紀 大野 かおり
- 出版者
- 一般社団法人 日本在宅ケア学会
- 雑誌
- 日本在宅ケア学会誌 (ISSN:13469649)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.65-75, 2023 (Released:2023-09-26)
- 参考文献数
- 19
訪問看護師とホームヘルパーが連携しながら与薬を行うためのモデルを検討した.訪問看護ステーション管理者15名,訪問介護事業所サービス提供責任者13名にグループインタビューを実施し質的帰納的分析を行うとともに,先行研究で得られた連携の概念モデルと統合することで,連携モデルを作成した.モデルには,連携の前提となる4要素,連携の実践内容となる4要素,連携の効果となる3要素が得られた.連携の実践内容となる要素では,【情報の共有と統合】により具体的な与薬の方法が共有されたのち,【役割を分担,補完しながら共に与薬する】実践が始まり,その際,【与薬を行うための共有ツールの作成と活用】が行われる状況があった.また,連携がより上手く機能していくための基盤となるものとして【連携の基盤作り】があった.今後は,実際に現場で運用することによるモデルの有用性の検証と,更なる精錬を行う必要がある.
1 0 0 0 OA 直接法で構造を解いてみよう
- 著者
- 植草 秀裕
- 出版者
- The Crystallographic Society of Japan
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.313-323, 1996-10-31 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 1
Basic ideas and practical tips of the direct methods are presented for the beginners of crystal structure analysis.
1 0 0 0 OA Bildung 概念の成立と展開について 教育概念としての実体化の過程
- 著者
- 三輪 貴美枝
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.353-362, 1994-12-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 55
1 0 0 0 OA 「戦後教育立法と教育行政の事務配分」
- 著者
- 古野 博明
- 出版者
- 北海道大學教育學部
- 雑誌
- 北海道大學教育學部紀要 (ISSN:04410637)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.113-145, 1976-03
1 0 0 0 OA 日本産苔類研究 其二
- 著者
- 服部 新佐
- 出版者
- 公益社団法人 日本植物学会
- 雑誌
- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.685, pp.1-7, 1944 (Released:2007-06-18)
- 被引用文献数
- 2 2
7) ハシゴゴケは本邦より牧野富太郎氏に依つて採集された事の外, 其の産地等全く不明で從來何等研究者の手に觸れなかつたものであつた。幸に筆者は當博物館臘葉室所藏の苔類標本中に牧野氏が東京帝大構内池畔に採集され, STEPHANIに依つて Cheilolejeunea scalaris と鑑定された標本を見出した。之を研究するとSTEPHANIの原記相文によく一致する。恐らくは同種の co-type 標本と考へる。尚右の研究の結果本種は寧ろ Lejeunea 屬に入る可しと判斷し, 新組合を作つた。8) アカウロコゴケは本邦に廣く分布し, 相當變化に富む種類であるが, 從來其の圖がなかつたのでこゝに收録した。又アカソロヒゴケなる和名を有するが緑色が常であり (原記相文には viridis とある), 寒冷其の他の影響で赤色を帶びるに至るものである。尚 Alicularia connata HORIKAWA は本種の弱小なるものとして本種の範疇内に入る可きものである (原記載は sterilis とある)。依つて新たに異名とした。9) コバウロコゴケ (コヒシヤクゴケ) は steril の材料に依つて記載され, 花被及び苞葉等が末知であつた。依つて花被を有する標本に就き圖及び簡單な記載を與へた。同標本は吉永虎馬氏所藏, STEPHANIの鑑定にかゝはるものであるが, 内の1包は誤つて S. parxitexta と同定されて居た。本州の高山に生ずる。10) カハルクラマゴケモドキ (新稱) なる和名は産地香春岳 (豐前國) より採つた。種名は本種が結晶石灰岩上に群生する事を示す。特徴は第一に葉形を擧げねばならない。圖示する如くその腹縁の鋸齒は極めて特異である。腹葉は葉の下片と殆ど同形, 不規則に齒牙を廻らす。Porella tosana (STEPHANI) S. HATTORI, com. nov. (syn. Madotheca tosana STEPHANI in Bull. Herb. Boiss. V, 97. 1897.) に近いが以上の特徴及び葉形がより短廣なる點より區別出來る。一見殆ど黒色を呈する。11) ミドリムカデゴケ (クラマゴケモドキ) は本邦産同屬中最も大形な種の一である。葉及び腹葉に長刺を備へる點が著しい。未だ圖示したものを見ないのでこゝに略圖を附した次第である。尚本圖に使用したる標本は Spec. exam. の項に記した如くVERDOORN編 Exsiccata であるが誤つて Madotheca (=Porella) tosana STEPH. と同定してあつた。本標本を貸與せられた櫻井久一博士に厚く謝意を表する。12) ミカヅキゼニゴケ (新稱) なる和名は本種の特徴たる無性芽容器に對して與へた。廣く世界的に分布する種であるが, 我國に侵入したのは比較的近頃の樣である。こゝに侵入なる語を用ひた所以は本種が後述する如く極めて容易に識別されるものにも拘はらず, 初めて我國より報告されたのは僅か十數年前に過ぎないし, それも都市のみに限られて居るからである。筆者は東京では小石川植物園の温室及びその附近, 本郷の帝大構内或は上野の科學博物館の温室等で觀察したが, 昭和十四年八幡市高見町の新築間もない日鐵社宅に親戚を訪れた折, 未だ赤褐色の地肌を見せて居る庭園の一隅に本種とオホジヤゴケのみが生育して居るのを認めた。本種は1屬1種にして, 殆ど steril の状態に於てのみ見出されるものであるが, 筆者の見たものも總て steril であつた。然し常に葉状體上に見られる無性芽容器の三日月形に着目すれば直ちに識別出來るものである。13) オガサハラキブリツノゴケ (新稱) は小笠原に産する意であつて, 種名は本種の著しい特徴と考へられる所の葉状體下面中肋部より小球状の疣状突起を生ずる性質を指す。母島のヘゴ (Cyathea boninensis) の幹や切株上に群生する。
1 0 0 0 OA 黒体輻射のコヒーレンス
- 著者
- 岩沢 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.6, pp.424-426, 1965-06-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 19
1 0 0 0 OA 6.ミネラル
- 著者
- 能勢 健嗣
- 出版者
- 日本水産増殖学会
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4-5, pp.289-300, 1972-12-25 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 14
高等動物では通常湿重量中約3.5%, 固形物中では約10%の無機成分が含まれている。Ca, K, Na, Mg, P, S, Clの7種は主要無機元素として要求され, これらは体中総無機元素の60~80%を占めるといわれる。このほか多数の元素が微量ではあるが体中に存在しており, FeあるいはMn以下の量の少ない元素は微量元素と呼ばれている。人間および家畜, 家禽類については無機質の体内における分布, 吸取および排泄, 生理作用あるいは所要量についてかなりよく調べられているが, 魚類については従来から主として透滲圧調整の観点から研究されており, 栄養要求の側からの研究はきわめて少い。魚は水中に生育するため, 環境水と体液の滲透圧の差により, 淡水魚では常に水の浸入と塩類の喪失に, 海水魚では逆に水の喪失と塩類の浸入に曝され, つねに滲透圧の調整を行なわなければならず, その結果, 魚の無機塩の代謝は一般の陸上動物には見らない側面をもっており, 魚の無機塩に対する栄養要求の研究を困難なものにしている。今後, 魚の無機代謝の研究を発展させるためには, 滲透圧および栄養代謝の両面からの研究を並行して行なわなければならない。ここでは魚類の無機塩の経口的要求を中心に述べてみたい。
1 0 0 0 OA 帝王切開術における癒着防止剤セプラフィルム®の効果に関する検討:前方視的コホート研究
- 著者
- 信正 智輝 池田 真規子 黄 彩実 別宮 史子 白神 碧 松井 克憲 高石 侑 増田 望穂 松尾 精記 安堂 有希子 佐藤 浩 田口 奈緒 廣瀬 雅哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.282-288, 2022 (Released:2022-09-09)
- 参考文献数
- 20
[目的]セプラフィルム®の帝王切開術における癒着防止効果を前方視的に検討した. [方法]初回帝王切開術を当科で施行し,今回2回目の帝王切開術を予定している症例を対象とした.臨床背景,癒着の程度,および母児の転帰をセプラフィルム®使用群と非使用群で比較検討した. [結果]初回,2回目とも当科で帝王切開術を施行した136例から,初回帝王切開術を妊娠32週未満に実施した14例と今回の帝王切開術で術中の癒着評価記録が行われなかった4例を除く118例を解析対象とした.解析対象の118例を初回帝王切開術時セプラフィルム®使用群(46例)と非使用群(72例)で比較検討した.セプラフィルム®使用群で大網-腹壁間,あるいは子宮-大網間に2度以上の癒着を有するものは有意に少なかった.執刀-児娩出時間,総手術時間,術中出血量,臍帯動脈血pHに差は認めなかった. [結論]セプラフィルム®による大網が関連する中等度以上の癒着を抑制する効果を認めたが,母児の臨床転帰に差は認めなかった.
1 0 0 0 音声の遺伝―方法論の検討ならびに双生児音声データの収集と分析
1.問題と目的:ヒトの音声は、音源が声道で共鳴を受けた産物である。この音声が家族で近似していることは知られ、遺伝的により近い形態をとる双生児では声道が類似するために、音声がより近似すると考えられる。これまで、双生児音声を知覚的に観察した報告は数多くあるが、それを定量化して遺伝で規定される音声の諸側面を調べた研究はあまりない。そこで、本年度は、双生児の音声の音響的特性について、一卵性と二卵性双生児ペアでの近似性を調べた。2.研究対象:日本全国の多胎児サークルに文書で研究の依頼を行った。研究期間内に協力可能であったサークルの集い(青森、山梨、神奈川、福岡、宮崎)で、音声の収録を行った。対象は、幼児から学童の双生児ペア27組で、分析対象とした音声資料が収集可能であったのは、21組(一卵性MZ8組、二卵性DZ13組)であった。双生児42名(男子20名、女子22名)の年齢は、2〜12歳(平均4.52歳)であった。3.方法:音声資料は、日本語5母音の持続発声とし、音響分析プログラムMulti-Speechを用いて解析を行った。母音の中央部を切りだし、音声基本周波数Foと共鳴周波数(F1,F2,F4)を測定した。さらに、音響理論に基づいて、F4値より声道長(声帯から唇までの距離)の推定値を求めた。統計処理として、MzとDzで別々に級内相関を求めた。4.結果と考察:母音Foは、202Hz〜514Hz(平均307.6Hz)であった。級内相関係数は、Mzで0.73、Dzで0.09、であった。一方、F4(3930〜5560Hz)より推定された声道長は、10.70〜15.14cm(平均11.76cm)であった。級内相関係数は、Mzで0.86、Dzで0.34、であった。この声道長の級内相関の違いより、かなりの部分が遺伝で規定されると考えられた。5.結論と展望:双生児の音声は、その基本周波数(声の高さとほぼ一致する)と推定された声道長において、近似しており、特に声道長が遺伝でかなりが規定されることが明らかになった。これは、声道が構造上個体に付随する管腔であり、その随意的変化が小さいものであることからも、支持される。一方、声の高さは意図的かつ場面への適応的行動として変化の可能性がより高いため、遺伝の影響が明確化されなかったのであろう。
1 0 0 0 OA Multicenter Study of the Clinical Presentation of Staphylococcus lugdunensis Bacteremia in Japan
- 著者
- Yusuke Ainoda Nozomi Takeshita Ryota Hase Takahiro Mikawa Naoto Hosokawa Ichiro Kawamura Hanako Kurai Masahiro Abe Muneyoshi Kimura Hideki Araoka Takahiro Fujita Kyoichi Totsuka Kazuhisa Mezaki Noritaka Sekiya Norio Ohmagari
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.405-407, 2017 (Released:2017-07-24)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 7 7
Staphylococcus lugdunensis (SL) is a bacterium with a highly pathogenicity than most other coagulase-negative Staphylococcus spp. (CoNS). In Japan, data on this pathogen are sparse, and the current prevalence of SL bacteremia is unknown. Therefore, we investigated the prevalence of SL in blood culture specimens in a prospective multicenter study across 5 facilities. A total of 3,284 patients had positive blood cultures, and 2,478 patients had bacteremia. Among the patients with bacteremia, 7 patients (0.28%) had SL bacteremia. A total of 281 patients had CoNS bacteremia, with SL accounting for 2.49% of these cases. Of the 7 patients with SL bacteremia, 1 patient (14.3%) had infective endocarditis, and 1 patient (14.3%) died within 30 days. In this study, SL resulted in the development of bacteremia in select patients. Clinicians in Japan should be aware of the prevalence of SL and the complications of SL bacteremia.
1 0 0 0 OA Joachim Frank博士のノーベル化学賞受賞で思ったこと
- 著者
- 光岡 薫
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.106-107, 2018 (Released:2018-03-31)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- Aman B Pulungan Carine de Beaufort Amajida F Ratnasari Helena A Puteri Laura Lewis-Watts Zulfiqar A Bhutta
- 出版者
- The Japanese Society for Pediatric Endocrinology
- 雑誌
- Clinical Pediatric Endocrinology (ISSN:09185739)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.137-146, 2023 (Released:2023-06-24)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
A decade since the discovery of insulin, the increasing prevalence of type 1 diabetes mellitus (T1DM) has underscored the prevailing inequalities in the provision of essential care for T1DM worldwide. However, the details on the availability of insulin types and associated medical devices remain unclear. A cross-sectional electronic survey was distributed across a global network of pediatric societies under the umbrella of the International Pediatric Association (IPA). Access to and availability of pediatric diabetes care were investigated using standardized questions. Responses from 25 of 132 pediatric societies across six regions were included. Pediatric endocrinologists typically manage T1DM together with pediatricians or adult endocrinologists. Nonetheless, 24% of the respondents reported pediatricians to be the sole healthcare professionals. According to the respondents, the patients were either partially or completely responsible for payments of insulin (40%), A1C (24%), C-peptide (28%), and antibody testing for diagnosis (28%). Government support is generally available for insulin, but this was merely 20% for insulin pumps and 12% for continuous glucose monitors. There are considerable disparities in the access, availability, and affordability of diabetes testing, medications, and support between countries with significant out-of-pocket payments for care. Country- and region-specific improvements to national programs are necessary to achieve optimal pediatric diabetes care globally.
1 0 0 0 OA 妊娠期の過剰なリン摂取が新生児のエピゲノム変化と成長期のリン反応性に及ぼす影響
- 著者
- 多々納 詩織
- 出版者
- 島根県立大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-01
近年の慢性腎臓病患者増加の背景の一つに、食事からのリン摂取の増加がある。しかしながら、妊娠期や成長期といったライフステージにおけるリン摂取の増加が、将来の慢性腎臓病発症に及ぼす影響は不明な点が多い。さらに、妊娠期における母親の栄養状態は新生児の代謝機構に影響を与えることが知られ、妊娠期の母体のリン摂取状態が将来の慢性腎臓病の発症や進展に寄与している可能性がある。そこで本研究では、胎児期から将来の慢性腎臓病発症を予防する新しい栄養管理法の確立を目指す。
1 0 0 0 OA 官公庁情報システムにおける外注の限界と内製化の必要性
- 著者
- 岩崎 和隆
- 出版者
- 一般社団法人 情報システム学会
- 雑誌
- 情報システム学会 全国大会論文集 情報システム学会 (ISSN:24339318)
- 巻号頁・発行日
- pp.S1-A2, 2021 (Released:2023-04-01)
1 0 0 0 OA 複合冷凍菓子の水分量の違いが感性に及ぼす影響
- 著者
- 綿貫 啓一 河本 政人 岡野 洸祐 勝村 和也 加納 拓実 小林 叶昌 間島 優 小石 智也 和食 麻衣 田浦 智裕 土屋 瞳
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- pp.23-00006, (Released:2023-09-27)
- 参考文献数
- 33
There are few studies that have conducted comprehensive verification of the physiological and psychological effects of different textures of chilled confectioneries by means of biometric measurements and subjective evaluation. The effects of confectionery texture are still unclear. Therefore, this study aimed to clarify the effects of different textures on the activity of autonomic nervous system, the brain, and muscles, and emotion by simultaneously measuring changes over time in various biological information and assessing subjective evaluation given by the tasters during consumption of different types of ice cream with monaka shell with varying water content. Participants answered a subjective evaluation questionnaire and rested for 60 s, and then performed the task. The monaka ice cream consisted of 9 blocks, each of which was eaten in 20 s. Afterwards, the participants rested for 60 s and completed a subjective evaluation questionnaire. Near-infrared spectroscopy was used to measure brain activity during eating, electromyography to measure muscle activity, and electrocardiography equipment to analyze heart rate variability. Eating monaka shell with low water content significantly activated cerebral blood flow in the right hemisphere when the first and sixth blocks were eaten. A significant trend was observed in LF/HF, which is considered an index of sympathetic nerve activity. In the mastication force test, the participants chewed significantly more strongly on ice cream with a high water content monaka shell than those with a low water content. During mastication, the participants who consumed ice cream with the low water content shell tended to use slow muscles more than those who consumed ice creams with high water content shell. The questionnaire showed that both the increase in degree of emotions such as surprise and excitement and the decrease in the degree of emotions such as sadness and depression were larger when the participants consumed ice cream with a high water content shell than those with a low water content shell. The results suggest that monaka shells with a low water content induce a more relaxed state and pleasant emotions than those with a high water content.