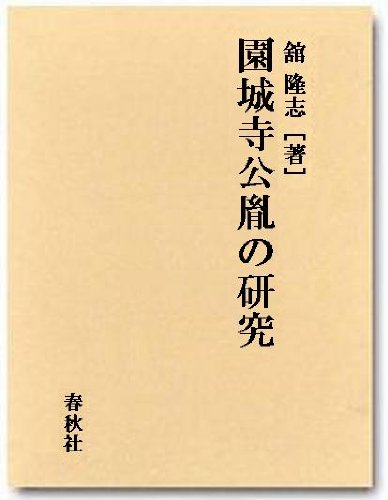1 0 0 0 OA 十六むさしの強解決
- 著者
- 田中 哲朗
- 雑誌
- ゲームプログラミングワークショップ2020論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.194-201, 2020-11-06
「十六むさし」は約400 年前から遊ばれている日本の古いボードゲームである.このゲームは,二人用の二人零和有限確定完全情報ゲームの一つであるため,ゲーム中の各局面のゲーム値を計算することができる.本研究では,標準的な「十六むさし」と2 つのバリエーションを強解決した.
1 0 0 0 OA 曹洞宗と臨済宗の五観偈の相違を考える
- 著者
- 舘 隆志
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.651-656, 2022-03-23 (Released:2022-09-09)
- 参考文献数
- 2
This study is about the differences between the Sōtō sect’s gokan no ge 五観偈 and that of the Rinzai, with considerations based on their historical transitions and how they were inherited down to the present day. The gokan no ge are the five verses recited before the meals in Zen institutions. The present study focuses on the third of the five in order to look at the differences in interpretation of the Sōtō and Rinzai sects. I focus on the basic version of the Chinese Nanshan 南山 Vinaya master 律宗 Daoxuan’s 道宣 gokan no ge. I clarify that the present day Sōtō understanding corresponds to that of Daoxuan, while the Rinzai does not.Next I have examine two works composed by medieval Rinzai monks, the Chokushu hyakujō shingi Untō-shō 勅修百丈清規雲桃抄 and the Nichiyō shingi Shōun-shō 日用清規笑雲抄, both of which convey an understanding in line with the Sōtō interpretation. The present day Rinzai sect’s interpretation first appeared in the Shoekō shingishiki 諸回向清規式, published in the early Edo period, and this was accepted by the sect thereafter. However, Muchaku Dōchū 無著道忠 of the Myōshin-ji mentioned in his Shosōrin ryakushingi 小叢林略清規 interpretations quite similar to those of the present day Sōtō. Moreover, from the situations of Edo period Sōtō, both the interpretations of Dōgen and the Nichiyō shingi Shōun-shō seem to have become mixed, with no definite interpretations for the Third Passage. At least by the end of the Edo period, there was no definitive or sectarian interpretation of this text. It was only during the Meiji period that the different sectarian interpretations came to be accepted by the Sōtō and the Rinzai, and their respective different interpretations were developed gradually.
1 0 0 0 IR 理科実験場面におけるCSCLによる相互評価に関する臨床的研究
- 著者
- 高久 道子 市川 誠一 金子 典代
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.11, pp.684-693, 2015 (Released:2015-12-09)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3
目的 愛知県に在住するスペイン語圏の南米地域出身者におけるスペイン語対応の医療機関についての情報行動の実態を把握し,その情報行動に関連する要因を明らかにする。方法 調査対象は,日本に 3 か月以上在住し愛知県に居住する,来日してから病気やケガで受診経験のある18歳以上のスペイン語圏の南米地域出身者とした。スペイン語による無記名自記式質問紙調査を2010年 4 月から 7 月に実施した。分析対象者245人(有効回答率58.9%)の情報行動を分析するにあたり,Wilsonの情報行動モデルを参考にした。東海地方にあるスペイン語対応の医療機関を探した群(以下,探索群)と探さなかった群(非探索群)を目的変数とし,回答者本人の「スペイン語対応の医療機関が必要になった経験」,「スペイン語対応の医療機関の認知」,「認知後にスペイン語対応の医療機関を受診した経験」,「情報入手先」,そして情報行動に関連すると思われる因子として基本属性,生活状況,日本語能力等との関連をみた。結果 分析対象者245人の性別内訳は,男性が106人(43.3%),女性が139人(56.7%)であった。平均年齢は39.6歳(標準偏差±11.2歳)で,国籍はペルーが84.5%を占めた。日本での在住年数は平均11.0年(±5.7年)で,愛知県での居住年数は5~9年(34.3%)が最も多かった。探索群は165人(67.3%),非探索群は80人(32.7%)であった。スペイン語対応の医療機関の探索は,病気やケガでの受診時に医療通訳など母国語対応を必要とした経験,東海地方における母国語対応の医療機関の認知,認知後に受診した経験,日本での在住年数,日本語能力,普段使用する言語と有意な関連があった。結論 スペイン語圏の南米地域出身者におけるスペイン語対応の医療機関に関する情報行動は,これまでに日本の医療機関でスペイン語通訳などの支援が必要になった経験が情報探索の動機となっていた。日本語によるコミュニケーションの困難,母国語の普段使用,短い在住年数がスペイン語対応の医療機関の情報探索に関連がみられた。スペイン語メディアを使い,家族や友人,職場の同僚といった身近な人と情報共有がなされていたと推察された一方で,自治体や公的機関発信の情報は届いているとは言えない状況にあり,医療に関する情報提供の在り方が課題として浮き彫りとなった。
1 0 0 0 OA し尿等の下水道との共同処理における施設規模の考え方
- 著者
- 渡邊 仁史 森 智志 庄司 有理
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第29回廃棄物資源循環学会研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.87, 2018 (Released:2018-12-03)
近年、し尿・浄化槽汚泥(以下、「し尿等」という。)の処理について、し尿処理施設ではなく、下水処理場において共同処理する事例が増えている。一般的にし尿処理施設は、主処理(水処理)工程の規模をもって施設規模としている事例が多いが、下水道投入を行う場合の処理フローでは、主処理工程を持たない施設が多い。し尿処理施設は、し尿等が車両収集により行われることから、搬入時における必要施設能力、施設稼働日あたりの能力、下水道へ希釈放流する場合の下水道投入量等、いくつかの考え方がある。本稿は、下水道と共同処理するし尿処理施設(し尿等投入施設)の施設規模の考え方について考察した。
1 0 0 0 OA 劇症型A群β溶連菌感染症を呈した肺炎の1例
- 著者
- 細尾 咲子 森 伸晃 松浦 友一 森 直己 山田 恵里奈 平山 美和 藤本 和志 小山田 吉孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.12, pp.2556-2562, 2015-12-10 (Released:2016-12-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
40歳,女性.実子に続く感冒様症状を主訴に来院し,急性呼吸不全と血圧低下を伴う重症肺炎の診断で入院となった.血液培養および喀痰培養からA群溶血性レンサ球菌(group A streptococci:GAS)が分離され,劇症型溶血性レンサ球菌感染症(streptococcal toxic shock syndrome:STSS)と診断した.Benzyl penicillin G(PCG)とclindamycin(CLDM)による治療を開始後,薬剤性肺障害などの有害事象が生じたため,ceftriaxone(CTRX)とlevofloxacin(LVFX)に変更し,計24日間の抗菌療法により軽快した.経過中,急性腎不全を合併し,計6回の血液透析を必要とした.GASによる市中肺炎は頻度が低く,時にSTSSを合併し致死率が高い.健常人におけるSTSSの発症機序は明らかでなく,解明が待たれる.
1 0 0 0 OA シンポジウム特集:コロナ禍以降の社会学研究・教育 特集によせて
- 著者
- 新藤 慶 品川 ひろみ
- 出版者
- 北海道社会学会
- 雑誌
- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.39-40, 2023 (Released:2023-08-01)
- 著者
- 胡 亜楠
- 出版者
- 北海道社会学会
- 雑誌
- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.19-38, 2023 (Released:2023-08-01)
- 参考文献数
- 16
パート労働者の量的な増加とともに,職務内容の高度化と責任の拡大が進み, 基幹的な労働力として活用されている。同じ企業内でも配置された部門によっ てパート労働者の責任や,正社員が担当する職務と重なる程度は異なる。それ では,正規労働者とパート労働者はどのように分業・協業しているのか。そこ で,本研究はスーパーマーケットC 社の農産,デリカ,水産の三つの部門で の正社員とパート労働との分業と協業実態を調査し,パート労働者に任される 仕事の特徴とその要因について検討を行った。結果として,部門ごとに正社員 の職務や責任の重たさが異なることによって各部門での正社員とパート労働者 の分業と協業のあり方が異なっていることが示された。正社員とパート労働者 の職務分担を技術の高低を基準として分類すると,知識と技術を必要とする水 産部門での職務分担が質的に異なる「分離型」となる。最も技術が低い農産部 門では商品・売場に関する職務が重複する「一部重複型」となっている。しか し,この技術の差はパート労働者の賃金や評価に反映されておらず,パート労 働の処遇改善を図るには雇用形態によって決められた評価方法と賃金制度を見 直す必要がある。また,調査ではベテランのパート労働者は業務内容において 契約職員に接近していることが示された。契約社員とパート労働者との働き方 や処遇上の違いを分析することがパート労働者の処遇改善を探る糸口となると 考えられる。
1 0 0 0 OA 働き方改革下の教員文化の変容 ―学校組織改革に対する学校現場の受けとめ―
- 著者
- 高島 裕美
- 出版者
- 北海道社会学会
- 雑誌
- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.1-18, 2023-05-31 (Released:2023-08-01)
- 参考文献数
- 14
本稿の課題は,教員の長時間過密労働が社会問題化するなか,ミドルリーダー の導入・配置という形で定着しつつある学校組織改革が実際の学校現場に受け とめられる過程で生じる教員たちによる意味付けを追うことをとおして,教員 文化の現在の姿を明らかにすることにある。 聞き取りの分析から示されたのは,以下の点である。 まず,ミドルリーダーである教務主任には,学校の組織編制上は管理職の補 佐としての役割が求められる。しかし,実際の役割としては,授業の「補欠」 や学級担任への寄り添い,特別な支援が必要な子どもへのサポートなど,フレ キシブルな動きやケア的役割を担うことが求められてもいることが明らかに なった。 次に,こうした役割期待に対し,調査に応じた2人の教務主任のうち1人は それを受けとめ,ケア的役割に徹することで,教員集団の関係性がハイアラー キカルにならないように工夫しつつ教務主任としての役割を負うことに成功し ていた。一方,もう1人は,教務主任という役割に含まれる権威的な性質や,個々 の教員のやり方には干渉するべきではないという自身の教員像との葛藤から, その役割を受けとめきれずにいる姿が確認された。 1990 年代後半以降急速に進行した学校組織改革は,教員の多忙をはじめと するさまざまな学校課題に機動的に取り組むために,学校組織をハイアラーキ カルに再編することが企図されているものの,実際には,いわば意図せざる結 果として,現場においては,教員文化の機能不全をカバーする役割をも担いつ つあるといえる。
1 0 0 0 電気双極子の渦状配列に起因した横型物性応答の実験的開拓
1 0 0 0 6N高純度銅を用いた低コスト・40T級強磁場発生装置の開発
- 著者
- 鈴木 政登 石山 育朗 塩田 正俊 町田 勝彦
- 出版者
- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.5, pp.585-598, 2003-10-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1 1
既存の最大酸素摂取量 (VO2max) の判定基準は軍人やスポーツ選手など十分に身体鍛錬を積んだ者を対象に設定された.しかし, 現在VO2maxは健康関連体力要素の1つとして, 幼若者から高年齢者に到るまで広く普及している.従って, それらの者に適用できるVO2max判定基準およびその臨界値が求められる.本研究では, 8~82歳までの健康男女548名を対象に, トレッドミルによる負荷漸増運動を課し任意の最大酸素摂取量 (VO2max) を実測した.任意のVO2max値を年齢回帰させ, 年齢予測VO2max値を算出し, 実測VO2max×100/年齢予測VO2maxの式から%VO2max値を求め, その度数分布図に反復切断法を適用し, VO2max基準域 (X-1.96SD~X+1.96SD, 70%~130%VO2max) を設定した.この範囲の平均値をVO2max基準値, 下位10%に相当する値を臨界値とし, いずれも実測値に変換し5歳毎の平均値として男女別に提示した.次いで, 70%~130%VO2max範囲の生理・生化学的指標 (HRmax, DPmax, RRmax, %△PVmaxおよびbLAmax) を, %VO2max値算出法に基づき%表示した.%表示された各指標の度数分布図の下位10%に相当する値を, VO2max値として採択し得る限界値 (臨界値) とし, 実測値に変換し5歳毎の平均値として男女別に提示した.最後に70%VO2max以上の領域を占めた各被験者の値をVO2maxと認定 (男性224名, 女性283名) し, 各生理・生化学的指標の臨界値を単独または組み合わせ適用によるVO2maxの採択率を調べ, さらに簡便・容易性および信頼性の観点からVO2max判定指標およびそれらの組み合わせを吟味した.その結果, 単独適用した場合の採択率が最も高いのはHRmaxであり, 男性の臨界値92.1%, 女性の値91.0%HRmaxを適用し, それぞれ92.9%および91.2%の採択率が示された.次いで, 簡便・容易で信憑性の高い組み合わせは, HRmaxとbLAmaxの両方の臨界値を同時に満たした場合で, 男性では82.6%, 女性は80.6%の採択率であった.本研究によって, 反復切断法と従来の判定基準適用によるVO2max値との間に有意差のないことが確認され, 反復切断法による性・年齢別VO2maxの基準値および臨界値が提示された.さらに, 簡便で信憑性の高いVO2max判定指標としてHRmaxおよびbLAmaxの臨界値が提示され, 性・年齢別臨界値の適用が奨められた.
1 0 0 0 OA テトリスのためのルールベースなゲーム画面認識によるデバッグAI の試作
- 著者
- 髙橋 秀太朗 服部 峻 高原 まどか
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 夏季研究発表大会 予稿集 2022 夏季研究発表大会 (ISSN:27584801)
- 巻号頁・発行日
- pp.45-48, 2022 (Released:2023-02-24)
- 参考文献数
- 2
人間のデバッガーの代わりにバグを判別可能なデバッグAI を構築するためには、プレイ動画からのバグ発見や、効率的なバグ発見のためのプレイ操作系列の自動生成など課題は多いが、ルールベースや機械学習が応用できるのではないかと考えた。そこで本稿では、テトリスゲームを題材に、人間プレイヤー操作によるバグ発生を含むプレイ動画を画像認識して、ルールベースでバグ発見するデバッグAI を試作し、その性能を検証する。
- 著者
- Hiroki UCHIKAWA Taichi KIN Satoshi KOIZUMI Katsuya SATO Tatsuya UCHIDA Yasuhiro TAKEDA Tsukasa KOIKE Satoshi KIYOFUJI Shigeo YAMASHIRO Akitake MUKASA Nobuhito SAITO
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023-0003, (Released:2023-08-23)
- 参考文献数
- 30
Rebleeding from a ruptured intracranial aneurysm has poor outcomes. Although numerous factors are associated with rebleeding, studies on computational fluid dynamics (CFD) on hemodynamic parameters associated with early rebleeding are scarce. In particular, no report of rebleeding in ultra-early phase exists. We aimed to elucidate the specific hemodynamic parameters associated with ultra-early rebleeding using CFD. In this study, the rebleeding group included patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) that rebled within 6 h from the onset. The control group included patients without rebleeding, observed for >10 h following the initial rupture. Clinical images after initial rupture and before rebleeding were used to build 3D vessel models for hemodynamic analysis focusing on the following parameters: time-averaged wall shear stress (WSS), normalized WSS, low shear area, oscillatory shear index, relative residence time, pressure loss coefficient, and aneurysmal inflow rate coefficient (AIRC). Five and 15 patients in the rebleeding and control groups, respectively, met the inclusion criteria. The World Federation of Neurosurgical Surgeons grade was significantly higher in the rebleeding group (p = 0.0088). Hemodynamic analysis showed significantly higher AIRC in the rebleeding group (p = 0.042). The other parameters were not significantly different between groups. There were no significant differences or correlations between SAH severity and AIRC. AIRC was identified as a hemodynamic parameter associated with ultra-early rebleeding of ruptured intracranial aneurysms. Thus, AIRC calculation may enable the prediction of ultra-early rebleeding.
- 著者
- Koichi Furuhashi
- 出版者
- Fujita Medical Society
- 雑誌
- Fujita Medical Journal (ISSN:21897247)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023-003, (Released:2023-08-28)
- 参考文献数
- 14
Background: The novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic has no end in sight. Currently, the emphasis is on policies aimed at easing movement restrictions and maintaining socio-economic activities. However, infection control in psychiatric hospitals has been challenging. There have been reports on the impact on mental health and outpatient/inpatient treatment environments in the field of child psychiatry. An outbreak of COVID-19 was experienced in a child and adolescent psychiatric ward, and considering that there have been few similar reports, it was deemed meaningful to accumulate such experiences.Case presentation: Three COVID-19-positive cases, all 14-year-old girls, were confirmed in a cluster among seven hospitalized patients in a child and adolescent psychiatric ward. Two patients presented symptoms of upper respiratory inflammation and one was asymptomatic. The main psychiatric diagnoses were post-traumatic stress disorder in one patient and autism spectrum disorder in the other two patients. The entire hospital ward was designated as a red zone (contaminated area), and infection control measures were adopted, such as halting group activities, wearing masks, and maintaining distance between patients. Additionally, it was necessary to use the infection control ward as it was difficult to ensure patient compliance.Conclusion: Infection control in COVID-19 clusters at child and adolescent psychiatric wards is difficult due to patient characteristics and symptoms. Restricted activities and care also result in psychobehavioral consequences, regardless of infection status. To achieve both infection control and a better treatment environment, it is necessary to make careful preparations while learning from these experiences.
- 著者
- Daijiro Suzuki Takanori Suzuki Masayuki Fujino Yumiko Asai Arisa Kojima Hidetoshi Uchida Kazuyoshi Saito Hirofumi Kusuki Yuanying Li Hiroshi Yatsuya Tsuneaki Sadanaga Tadayoshi Hata Tetsushi Yoshikawa
- 出版者
- Fujita Medical Society
- 雑誌
- Fujita Medical Journal (ISSN:21897247)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023-001, (Released:2023-08-28)
- 参考文献数
- 26
Objectives: The Gunma score is used to predict the severity of Kawasaki disease (KD), including coronary artery aneurysm (CAA) as a cardiac complication, in Japan. Additionally, the characteristic ratio of ventricular repolarization (T-peak to T-end interval to QT interval [Tp-e/QT]) on a surface electrocardiogram reflects myocardial inflammation. This study aimed to determine whether the Tp-e/QT can be used to predict CAA in children with KD.Methods: We analyzed chest surface electrocardiograms of 112 children with KD before receiving intravenous immunoglobulin therapy using available software (QTD; Fukuda Denshi, Tokyo, Japan).Results: The Tp-e/QT (lead V5) was positively correlated with the Gunma score (r=0.352, p<0.001). The Tp-e/QT was larger in patients with CAA (residual CAA at 1 month after onset) than in those without CAA (0.314±0.026 versus 0.253±0.044, p=0.003). A receiver operating characteristic curve analysis was performed to assess whether the Gunma score and Tp-e/QT could predict subsequent CAA. The area under the curve of the Gunma score was 0.719 with the cutoff set at 5 points. The area under the curve of the Tp-e/QT was 0.892 with a cutoff value of 0.299. The fit of the prediction models to the observed probability was tested by the Hosmer–Lemeshow test with calibration plots using Locally weighted scatterplot smoothing (LOESS) fit. The Gunma score (p=0.95) and Tp-e/QT (p=0.95) showed a good fit.Conclusions: The Tp-e/QT is a useful biomarker in predicting coronary aneurysm complications in KD.