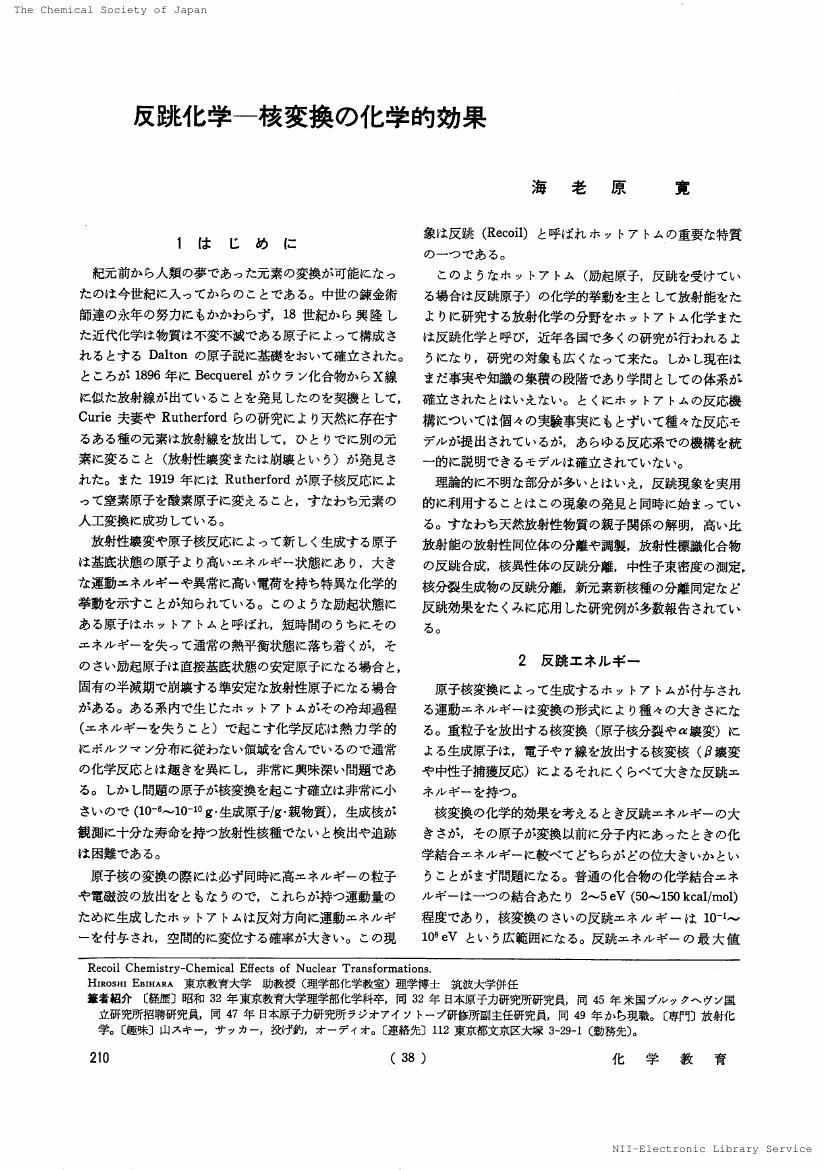1 0 0 0 OA より多くの人のためのデザイン ―アクセシブルデザインの概念と実践―
- 著者
- 佐川 賢
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.35-41, 2017 (Released:2017-02-09)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA アクセシブルデザインと国際標準化
- 著者
- 佐川 賢 倉片 憲治 横井 孝志
- 出版者
- 特定非営利活動法人 横断型基幹科学技術研究団体連合
- 雑誌
- 横幹 (ISSN:18817610)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.24-29, 2011 (Released:2016-02-26)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
“Accessible design” is an emerging design method of products, services and environments. It takes into account special requirements of older persons and persons with disabilities in the design process and, thereby, maximizes the number of their potential users. In the design process, ergonomic knowledge and human-ability/characteristic data of those target users play a crucial role. This paper reviews the development of accessible-design methods in a variety of fields such as user-interface design of consumer products and shows how ergonomic knowledge and data can be used effectively. It also focuses on relevant activities of international standardization in Technical Committee 159 “Ergonomics” of International Organization for Standardization.
1 0 0 0 OA 遺伝子工学実験講座I.プラスミドの単離・生成・分析法
- 著者
- 山口 和男
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.10, pp.552-561, 1987-10-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA 子宮頸癌の分子生物学的発生機序
- 著者
- 吉本 賢史 徳田 葵 栁沼 裕二 Masafumi Yoshimoto Aoi Tokuda Yuji Yagimuma
- 雑誌
- 熊本大学医学部保健学科紀要 (ISSN:18807151)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-13, 2016-03
本稿ではHPV感染が子宮頸癌を引き起こす分子生物学的機序について概説する。
1 0 0 0 OA 反跳化学 : 核変換の化学的効果(<特集>放射能と化学)
- 著者
- 海老原 寛
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学教育 (ISSN:24326542)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.210-216, 1975-06-20 (Released:2017-09-22)
1 0 0 0 OA 採用面接における志願者の自己呈示と非言語的行動
- 著者
- Kazumi YAMAGUCHI
- 出版者
- 経営行動科学学会
- 雑誌
- 経営行動科学 (ISSN:09145206)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.57-71, 2001-06-30 (Released:2011-01-27)
- 参考文献数
- 98
- 被引用文献数
- 2
This paper reviews literature concerning an applicant's self-presentation (ingratiation, self-promotion, exemplification) and nonverbal behaviors, e. g., eye contact, smiling behavior, and head nodding, and discusses the significance of these behaviors in job interviews. The extent to which a person engages in these nonverbal behaviors is influenced by gender, status, and personality. In the context of a job interview, these behaviors affect person perception, interpersonal attraction, and perceived job aptitude. These attributes of nonverbal behavior were associated with specific functions: there are an intimacyexpressing function of eye contact and smiling behavior, a reaction-feedback function of eye contact, an impression management function of smiling behavior, and a reinforcing function of head nodding. I propose that these nonverbal behaviors affected the interview as follows: these could be used for ingratiation, which provided a positive feeling to interviewers, self-promotion, which emphasized the competence of the applicants, or exemplification, which indicated the integrity of the applicants. Consequently, these results suggested that eye contact, smiling behavior, and head nodding by an applicant could affect the hiring decision.
1 0 0 0 OA 日本人大学生同士の雑談に見られる否定的評価の言語的表現方法に関する一考察
- 著者
- 関崎 博紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.155, pp.111-125, 2013 (Released:2017-02-17)
- 参考文献数
- 13
本研究では,日本人大学生同士の雑談の中で否定的評価として機能した発話を取り上げ,その言語的な表現方法を分析した。分析は,各発話が,評価の内容(「価値づけ」),評価の対象となる「事柄」,対象を評価する「基準」のいずれに言及したものかという観点から行い,次のことを明らかにした。「価値づけ」の表現方法には,語義として評価の意味を含んだ単語を利用する方法と比喩表現から価値づけを示唆する方法があった。また,「事柄」を表現する方法には,価値づける対象となる事柄を言語化する方法と,その事柄の結果として生じた事態を言語化する方法が見られた。価値づけの基準への言及方法には,モダリティ表現を用いた方法と基準を言語化する方法が見られた。最後に,本研究が日本語教育に示唆することについて考察した。
- 著者
- Shuang WANG Hui CHEN Lei DING He SUI Jianli DING
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems (ISSN:09168532)
- 巻号頁・発行日
- vol.E106-D, no.7, pp.1209-1218, 2023-07-01
- 被引用文献数
- 1
The issue of a low minority class identification rate caused by data imbalance in anomaly detection tasks is addressed by the proposal of a GAN-SR-based intrusion detection model for industrial control systems. First, to correct the imbalance of minority classes in the dataset, a generative adversarial network (GAN) processes the dataset to reconstruct new minority class training samples accordingly. Second, high-dimensional feature extraction is completed using stacked asymmetric depth self-encoder to address the issues of low reconstruction error and lengthy training times. After that, a random forest (RF) decision tree is built, and intrusion detection is carried out using the features that SNDAE retrieved. According to experimental validation on the UNSW-NB15, SWaT and Gas Pipeline datasets, the GAN-SR model outperforms SNDAE-SVM and SNDAE-KNN in terms of detection performance and stability.
- 著者
- Ryosuke OTSUJI Nobuhiro HATA Yusuke FUNAKOSHI Daisuke KUGA Osamu TOGAO Ryusuke HATAE Yuhei SANGATSUDA Yutaka FUJIOKA Kosuke TAKIGAWA Aki SAKO Kazufumi KIKUCHI Tadamasa YOSHITAKE Hidetaka YAMAMOTO Masahiro MIZOGUCHI Koji YOSHIMOTO
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-0351, (Released:2023-07-10)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1
We aimed to retrospectively determine the resection rate of fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) lesions to evaluate the clinical effects of supramaximal resection (SMR) on the survival of patients with glioblastoma (GBM). Thirty-three adults with newly diagnosed GBM who underwent gross total tumor resection were enrolled. The tumors were classified into cortical and deep-seated groups according to their contact with the cortical gray matter. Pre- and postoperative FLAIR and gadolinium-enhanced T1-weighted imaging tumor volumes were measured using a three-dimensional imaging volume analyzer, and the resection rate was calculated. To evaluate the association between SMR rate and outcome, we subdivided patients whose tumors were totally resected into the SMR and non-SMR groups by moving the threshold value of SMR in 10% increments from 0% and compared their overall survival (OS) change. An improvement in OS was observed when the threshold value of SMR was 30% or more. In the cortical group (n = 23), SMR (n = 8) tended to prolong OS compared with gross total resection (GTR) (n = 15), with the median OS of 69.6 and 22.1 months, respectively (p = 0.0945). Contrastingly, in the deep-seated group (n = 10), SMR (n = 4) significantly shortened OS compared with GTR (n = 6), with median OS of 10.2 and 27.9 months, respectively (p = 0.0221). SMR could help prolong OS in patients with cortical GBM when 30% or more volume reduction is achieved in FLAIR lesions, although the impact of SMR for deep-seated GBM must be validated in larger cohorts.
- 著者
- 日置 尚之 来栖 可奈 島 瑞帆 増田 絢 松本 淳
- 出版者
- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)
- 雑誌
- 神奈川自然誌資料 (ISSN:03889009)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.40, pp.1-4, 2019 (Released:2019-09-01)
Myxobolus nagaraensis (Myxozoa: Myxosporea) was first reported in 2007 in freshwater gobies (Rhinogobius sp.) from Nagara River in the Gifu Prefecture, Japan. Although freshwater gobies are common fish species found in rivers of the Kanagawa Prefecture, infection of these fishes with M. nagaraensis has not been reported. Therefore, this study surveyed for M. nagaraensis infection in freshwater gobies from Sakai River, which runs through the Kanagawa Prefecture. Freshwater gobies were captured using hand nets at different locations along the Sakai River in November 2017 and February 2018. Diseased fish displaying enlarged abdomens and nodules in the caudal peduncle were caught from 2 locations which were 20 km apart. Cysts excised from these diseased fish contained parasitic spores resembling the morphology of M. nagaraensis. DNA was extracted from the cysts and the small subunit ribosomal RNA gene was amplified (SSU rDNA). Based on homology search, the amplified partial product was 99.6% identical with M. nagaraensis SSU rDNA (Accession no. AB274267). This is the first report of M. nagaraensis infection in freshwater gobies from a river in Kanagawa. Since prevalence of the parasite and its pathogenicity to the goby populations are still unclear, continued examination of other rivers in the prefecture is crucial.
1 0 0 0 OA 滋賀県の水田地帯におけるカエル類の、 鳴き声の聞き取りによる分布調査
- 著者
- 金井 亮介
- 出版者
- 日本環境動物昆虫学会
- 雑誌
- 環動昆 (ISSN:09154698)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.121-126, 2014 (Released:2016-10-25)
1 0 0 0 OA ファミリーマートの減塩への取り組み—「こっそり減塩」の推進—
- 著者
- 木下 紀之
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.306-312, 2021-08-31 (Released:2021-09-03)
- 参考文献数
- 7
目的:株式会社ファミリーマートは,中食商品を中心に取り組んだ減塩活動が2020年の厚生労働省スマートライフプロジェクトの「健康寿命をのばそう!アワード」で厚生労働大臣最優秀賞を受賞した.本報は,その取り組み内容と今後の方向性の報告を目的とした.内容:食市場における中食比率が高まる中で,ファミリーマートでは2018年から減塩プロジェクトを立ち上げた.学協会により認定を受けたスマートミール弁当や,JSH(日本高血圧学会)減塩食品の開発導入を皮切りに,2019年9月から2020年8月までの1年間で,弁当類・麺類・総菜類などを含めて28種類の既存商品の減塩化を行った.この間の販売数量は約1億食で,減塩効果は約100 tとなった.その内の26種類は「減塩」を商品パッケージに標榜しない「こっそり減塩」とした.これは消費者の「減塩」という表現に対するネガティブなイメージを回避するだけでなく,「おいしさ」重視の考え方から「減塩を標榜できる」減塩率にはこだわらないという方針としたためである.まとめと今後の方向性:ファミリーマートでは年間50億食以上の中食商品を販売している.ただし,これまでに達成したのは1億食の減塩である.今後も既存商品の見直しをすすめ,おいしさとボリュームはそのままの「こっそり減塩」を推進し,国民の健康寿命の延伸に貢献してゆきたい.
1 0 0 0 OA 英語の疑問文とその返答の様態
- 著者
- 山田 政美
- 出版者
- 一般社団法人 日本メディア英語学会
- 雑誌
- 時事英語学研究 (ISSN:21861420)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, no.17, pp.33-40, 1978-09-01 (Released:2012-11-13)
- 参考文献数
- 36
1 0 0 0 OA Q&Aサイトにおける質問と回答の分析
- 著者
- 栗山 和子 神門 典子
- 雑誌
- 研究報告データベースシステム(DBS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009-DBS-148, no.19, pp.1-8, 2009-07-21
本稿では,Q&A サイトにおける質問と回答を分析し,質問に対して適切な回答を得るために考慮しなければいけない要素として,質問のタイプを提案する.本研究では,Q&A サイトに投稿された質問を人手で分析することにより,質問をいくつかのタイプに分類した.また,各タイプの質問を識別するために共通する特徴を抽出し,それを用いて質問を自動的にタイプ分けすることが可能かどうかを検討した.さらに,質問のタイプと質問者によって選択されたベストアンサーになんらかの関連がみられるかどうか考察した.
1 0 0 0 OA 中国産漢方薬「片仔廣」による薬剤性肺炎の1例
- 著者
- 小林 義昭 長谷川 隆志 佐藤 誠 鈴木 栄一 荒川 正昭
- 出版者
- The Japanese Respiratory Society
- 雑誌
- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.7, pp.810-815, 1996-07-25 (Released:2010-02-23)
- 参考文献数
- 17
症例は47歳の女性. 平成2 (1990) 年から慢性肝疾患の診断で某院に通院していた. 平成5年4月に肝硬変と診断され, 中国産漢方薬「片仔廣」の内服を開始したところ, 5月頃より湿性咳嗽が出現, 増悪したため, 7月当科に入院した. 両背下部に fine crackle を聴取し, 胸部X線写真で両下肺野に網状影を認めた. 血液ガス分析ではA-aDO2の軽度開大がみられ, 呼吸機能検査では拘束性障害と拡散能の低下を認めた. 薬剤性肺炎を疑って, 片仔廣を中止して無治療で経過観察したところ, 自覚症状, 画像所見, 呼吸機能のいずれも改善した. また, 白血球遊走阻止試験では, 片仔廣による遅延型過敏反応が認められた. 以上の結果から, 片仔廣による薬剤性肺炎と診断した. 本症例は, 本邦における片仔廣による薬剤性肺炎の第1例と思われる.
1 0 0 0 OA 国連ナミビア理事会の国際統治
- 著者
- 家 正治
- 出版者
- 神戸市外国語大学研究所
- 雑誌
- 神戸外大論叢 = The Kobe Gaidai Ronso : The Kobe City University Journal (ISSN:02897954)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.313-334, 1976-06-01
1 0 0 0 OA 身体化された心の文化論 文明と共進化する意識について
- 著者
- 下西 風澄
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第37回 (2023) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.2R5OS28a04, 2023 (Released:2023-07-10)
近年の認知科学を巡る哲学研究の潮流は、意識の身体性や環境との相互作用に着目している。神経生物学者のフランシスコ・ヴァレラはこうした認知哲学を「身体化された心」と呼び、認知が単なる記号的な情報処理として普遍的に機能するのではなく、それぞれの個別の歴史性を有した身体や、その有機体が行為する状況に深く依存してはじめて捉えることができるという観点に注目した。こうした認知の身体性を広く解釈すれば、認知とは、それを行う認知主体の身体的な習慣、使用する言語、活動する生態環境などの総合的な環境のなかで捉えるべき対象となる。別の言い方をすれば、意識はいわば「文明と共進化」する視座のなかから理解すべき現象でもある。 筆者は『生成と消滅の精神史』(文藝春秋、2022)にて、この「文明と共進化する意識」という観点から、古代・近世・現代の西洋における意識、夏目漱石の文学において描かれた意識を対象に論じたが、本発表では、漱石の作品における意識の描かれ方とその理論における捉え方を比較し、日本における意識の捉え方を考察する。
1 0 0 0 OA 分人型社会システムの提案 IT/AI社会における個のあり方を求めて
- 著者
- 武田 英明
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第37回 (2023) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.2Q5OS20a01, 2023 (Released:2023-07-10)
IT社会さらにAI社会と社会が発展するにつれ、人個人のあり方にも変化が求められている。本稿では伝統的な個人(individual)の概念から離れて、新たに分人(dividual)を基本とする人と社会のあり方を検討する。我々はすでにSNS等において自らの一部として参加していたり、分人的活動をしている。そこでむしろ、分人を社会の基本単位として社会を構成することで、よりIT/AI社会に適合したシステムになると考える。分人概念の歴史的経緯、分人型システムの要件、分人型システム実現への課題などをまとめる。