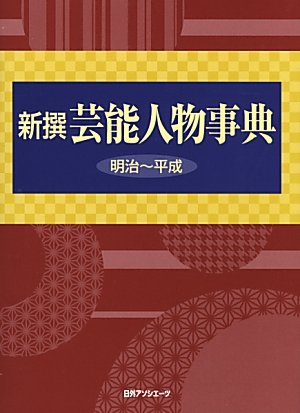1 0 0 0 OA 遺伝子組換えカイコの研究の現状と将来
- 著者
- 田村 俊樹 瀬筒 秀樹 小林 功 内野 恵郎
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.3, pp.3_155-3_159, 2006 (Released:2016-04-11)
- 参考文献数
- 30
- 著者
- Kiyohiko SAKATA Satoru KOMAKI Nobuyuki TAKESHIGE Tetsuya NEGOTO Jin KIKUCHI Sosho KAJIWARA Kimihiko ORITO Hideo NAKAMURA Masaru HIROHATA Motohiro MORIOKA
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-0142, (Released:2023-07-10)
- 参考文献数
- 54
The goal of treating patients with suprasellar meningioma is improving or preserving visual function while achieving long-term tumor control. We retrospectively examined patient and tumor characteristics and surgical and visual outcomes in 30 patients with a suprasellar meningioma who underwent resection via an endoscopic endonasal (15 patients), sub-frontal (8 patients), or anterior interhemispheric (7 patients) approach. Approach selection was based on the presence of optic canal invasion, vascular encasement, and tumor extension. Optic canal decompression and exploration were performed as key surgical procedures. Simpson grade 1 to 3 resection was achieved in 80% of cases. Among the 26 patients with pre-existing visual dysfunction, vision at discharge improved in 18 patients (69.2%), remained unchanged in six (23.1%), and deteriorated in two (7.7%). Further gradual visual recovery and/or maintenance of useful vision were also observed during follow-up. We propose an algorithm for selecting the appropriate surgical approach to a suprasellar meningioma based on preoperative radiologic tumor characteristics. The algorithm focuses on effective optic canal decompression and maximum safe resection, possibly contributing to favorable visual outcomes.
- 著者
- Walter Kolneder
- 出版者
- Lafite : Österreichischer Bundesverlag
- 巻号頁・発行日
- 1974
- 著者
- Karlheinz Essl
- 出版者
- Hans Schneider
- 巻号頁・発行日
- 1991
1 0 0 0 OA Pathogen Burden in Essential Hypertension
- 著者
- Lijuan Liu Yanbin Liu Weijun Tong Hong Ye Xianyu Zhang Wuchun Cao Yonghong Zhang
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.11, pp.1761-1764, 2007 (Released:2007-10-25)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 22 26
Background Associations between pathogens and hypertension (HT) has been reported, but few studies have focused on the relationship between aggregate pathogens and HT. The present study explored whether the risk of HT is associated with each pathogen (defined as Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniaee), Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae), Helicobacter pylori (H. pylori) and Coxsackie virus) or with aggregate pathogens in Chinese Mongolians. Methods and Results One thousand and thirty Chinese Mongolians aged 30 years or more were recruited, including 488 hypertensive and 942 normotensive subjects. Enzyme-linked immunosorbent assay was used to detect IgG antibodies for C. pneumoniaee, M. pneumoniae, H. pylori and Coxsackie virus. The seroprevalence of Coxsackie virus was significantly associated with HT (odds ratio (OR) 3.7 after adjustment for risk factors), but no significant association was found for C. pneumoniae, M. pneumoniae and H. pylori (OR 1.32, 0.75 and 1.19, respectively). The results also showed that the risk of HT was associated with the aggregate pathogens: it increased with the increasing number of pathogens, and the ORs were 1.629, 2.653, 2.129, and 5.146 for 1, 2, 3 and 4 pathogens, respectively, after controlling for risk factors. Conclusion The risk of HT is associated with Coxsackie virus and aggregate pathogen load. The mechanism(s) underlying the associations remain to be elucidated further. (Circ J 2007; 71: 1761 - 1764)
1 0 0 0 OA コメント:「若竹の園」の幼児保育史上の位置
- 著者
- 湯川 嘉津美
- 出版者
- Society for the Historical Studies of Early Childhood Education and Care in Japan
- 雑誌
- 幼児教育史研究 (ISSN:18815049)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.54-62, 2016 (Released:2017-03-29)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 韓国料理・日本料理に対する日本人・韓国人の嗜好
- 著者
- 金 廷恩 廣木 奈津 松本 仲子
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.261-270, 2014 (Released:2014-04-28)
- 参考文献数
- 5
韓国と日本は地域的な関係から, 気候風土が近似しているだけでなく, 食文化面についても, 両国は中国からの影響を受けるなど, 歴史的にも多くの関わりをもってきた。著者は, 韓国と日本の食事について, 食材, 調理法, 食嗜好, 各国の料理に対するイメージなどの点から比較してきた。本研究は, キムチ以外の料理について, 嗜好面からの検討を加えるもので, 韓国料理を日本人が試食し, 日本料理を韓国人が試食してそれぞれの受容度を官能評価によって測定した。日本人が試食した韓国料理はぜんまいのナムル, ズッキーニのジョン, プルコギ, ジャプチェなど8品目で, それぞれ韓国醤油と日本醤油で調味した。汁物は, こんぶ・かつお節, 煮干, 干しだらのだし汁を用い, それぞれ韓国味噌と日本味噌等で調味した4品目の計12品目である。韓国人が試食した日本料理は肉じゃが, すき焼, 鯛のあら煮, きんぴらごぼうなど7品目と牛丼, 親子丼などのご飯物3品目の計10品目で, いずれも韓国醤油と日本醤油で調味した。使用した醤油および味噌については, アミノ酸を分析した。官能評価は香り, 味, 旨味, 総合評価の4項目について, 5段階の評点法により評価した。パネルは, 韓国, 日本ともに女子学生の各50人である。結果は次のように要約された。日本人の韓国料理に対する評価は, 汁を除き「普通」から「良い」の間に評価され, ほぼ受容されると理解された。韓国醤油に比べて日本醤油で調味したものが高い評価であった。韓国汁に対する評価は, 食べ慣れない干しだらのだし汁を用いた汁は好まれず, 「普通」以下の評価であった。味噌については, 本味噌にくらべて韓国味噌の評価が低く, 香りが好まれなかった。日本料理に対する韓国人の評価は, 「普通」から「良い」の間に評価され, ほぼ受容されることがわかった。ご飯物は「良い」と評価され, 嗜好度が高かった。調味に使用した醤油については, ほぼ同等の評価であったが, 7品目中2品目については, 日本醤油の評価が有意に高かった。
1 0 0 0 OA 腹腔鏡下虫垂切除術を施行した虫垂結石を伴う急性虫垂炎の1例
- 著者
- 田口 大輔 上田 正射 池永 雅一 谷田 司 高 正浩 家出 清継 津田 雄二郎 中島 慎介 松山 仁 山田 晃正
- 出版者
- 日本外科系連合学会
- 雑誌
- 日本外科系連合学会誌 (ISSN:03857883)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.133-137, 2021 (Released:2022-04-30)
- 参考文献数
- 21
症例は19歳,女性.右下腹部痛のため,近医を受診し,急性虫垂炎を疑われ当科へ紹介された.腹部単純X線像で右下腹部に高吸収陰影を認め,腹部単純CTで虫垂根部より1cm末梢側虫垂内の輪状の高吸収陰影と,その末梢側虫垂の腫大を認めた.虫垂結石を伴う急性虫垂炎を疑い,腹腔鏡下虫垂切除術を施行した.切除標本内に14mm大の虫垂結石を認めた.術後経過は良好であり,術後2日目に退院した.虫垂結石を伴う急性虫垂炎は稀であり,穿孔や膿瘍形成のリスクが高く,重症化しやすいとされている.本症例は受診時の炎症は軽度であったが,虫垂結石を有すると考えられたことから早期に手術を行った.抗菌薬が発達した近年では保存的に軽快が得られる急性虫垂炎の症例も多いが,虫垂結石を伴う虫垂炎の場合は重症化のリスクが高く,積極的に手術を考慮する必要があると考えられる.
1 0 0 0 [安田雷洲欠題銅版画春画]
1 0 0 0 OA 大麦由来β-グルカンを効率的に摂取する調理法の提案
- 著者
- 古谷 彰子 三星 沙織 平尾 和子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成27年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.50, 2015 (Released:2015-08-24)
【目的】大麦種子には水溶性多糖類の(1,3)(1,4)-β-グルカン(β-グルカンと略)が胚乳部細胞壁に分布しており,血中コレステロールや血糖値,中性脂肪の低下作用,アレルギー反応を鎮め,ガンなどの腫瘍を抑える効果などが報告されている。近年,アメリカ(FFA)やフランス(EFSA)でもヘルスクレームの許可が試みられており,国際的にも注目の栄養素である。しかし,大麦は茹でる調理法(湯取り法)が主流であり,喫食時のβ-グルカンの大幅な損失が否めない。本実験では大麦を用い,その調理法を変化させてβ-グルカン含量を定量し,より美味しく損失の少ない調理法を検討した。【方法】大麦はうるち種押麦(カナリヤ 業務用,永倉精麦(株))を使用した。調理器具は炊飯器(Panasonic SR-HD103)を用い,炊き干し法と湯取り法の2種の調理法を用いた。炊き干し法の最適加水量は,順位法による官能評価により決定した。湯取り法の加熱条件は押し麦の5倍量(重量比)を加水し,物性測定を行って,炊き干し法と同様の硬さが再現できる加熱時間とした。双方のβ-グルカン量をAOAC公定法のβ-グルカン測定キット(Megazyme社)を使用して定量し比較した。物性測定は,テンシプレッサー(My BoyⅡ,㈲タケトモ電機製)を用いて1粒法による低・高圧縮測定・解析をした。【結果】加水量2倍および3倍の炊き干し法炊飯押麦飯はすべての項目で加水量1倍よりも有意に好まれた。炊き干し法では加水量の違いによるβ-グルカン量の差が見られなかったが,湯取り法では炊き干し法と比較して有意に減少し,加水量の増加に伴い減少の割合が高くなった。以上より,押麦のβ-グルカンの損失を少なくし,効率よく美味しく喫食するためは炊き干し法が効果的であった。湯取り法を使用する場合は,麦の3倍量(重量比)程度まで加水量を少なくして茹で, 炊き干し法に近似の方法で調理することにより, β-グルカンの損失を防ぐことが可能と考えられた。
1 0 0 0 OA 特徴的な平面を持つ急性期病院における看護負担感についての事例報告
- 著者
- 村川 真紀 山田 あすか
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.66, pp.841-846, 2021-06-20 (Released:2021-06-20)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 2
This case report was conducted in an acute care unit with a distinctive plan to examined the relationships between: 1) amount of nurses’ activity and nurses’ burden-feeling, and 2) plan characteristics and nursing burden. The survey consisted of a questionnaire and three-day-activity survey using a general pedometer. Results showed that the amount of activity in the nursing hall type tended to be lower than that in the middle corridor type. Furthermore, no clear relationship was found between amount of nurses’ activity and the nurses’ burden-feeling. These results suggest that nurses’ burden-feeling is an independent indicator.
1 0 0 0 新撰芸能人物事典 : 明治〜平成
- 著者
- 日外アソシエーツ編集部編
- 出版者
- 紀伊國屋書店 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2010
- 著者
- 堀田 千絵 武井 祥平 川口 潤
- 出版者
- 人間環境学研究会
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.1_21-1_26, 2007 (Released:2009-06-22)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 3 2
Recently, Anderson & Green (2001) showed that people could forget the specific memory, using the Think/No-Think paradigm. However, precise procedure of the Think/No-Think paradigm did not clearly reported in Anderson & Green's (2001) paper. Therefore, the aim of this article was to report that our modifying new type of Think/No-Think paradigm could lead to stable memory impairment effect. The new type of the Think/No-Think paradigm consisted of (1) Memorization; (2) Memorization assessment; (3) No-Think training; (4) Think/No-Think; (5) Cued recall testing. Main modified points involved in (1), (2), (3) and (4). More concretely, first, study stimuli were changed weak related pairs into the unrelated one to reduce the ceiling effect (1). Next, Memorization was assessed by participant's saying the correct response twice in succession with respect to each cue word so that the study of cue-target for each could become equal criterion (2). Also, in the No-Think training (3) and Think/No-Think phase (4), the way of presentation of the to-be-suppressed items and a number of Think/No-Think trials were changed. In the No-Think condition, participants were asked to learn the to-be-suppressed 10 cue words before main Think/No-Think phase, instead of judging the suppression or response trials by the red (suppress) or green (respond) colors. Additionally, they must continue performing the Think/No-Think task while judging whether the presented cue word was to-be-suppressed or to-be-responded one. Finally, a number of the Think/No-Think trials were reduced from 377 to 242 trials to minimize the fatigue effect on the performance of the Think/No-Think tasks. Further, the numbers of presentations of the suppression/response trials for each were 0, 4, and 12. Based upon the revision of the above four points, two experiments (N=48) were conducted. The results of both experiments showed that the final cued recall performance of the 12 suppression condition was worse than that of the baseline condition. Consequently, the new type of the Think/No-Think paradigm could successfully lead to stable memory impairment effect.
1 0 0 0 OA 顕微分光法を用いたビスマス骸晶の干渉色分析
- 著者
- 田所 利康
- 雑誌
- 2019年第80回応用物理学会秋季学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2019-07-10
- 著者
- Bo Mi Park Jina Lee Young Kyu Park Young Cheol Yang Bock Gie Jung Bong Joo Lee
- 出版者
- Japan Poultry Science Association
- 雑誌
- The Journal of Poultry Science (ISSN:13467395)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.2023016, 2023 (Released:2023-07-08)
- 参考文献数
- 38
Benefits chitosan-fermented feed additives (CFFAs) particularly in the regulation of the immune system and antimicrobial activity. Therefore, we investigated the immune-enhancing and bacterial clearance effects of CFFA (fermented by Bacillus licheniformis) on broiler chickens Salmonella Gallinarum challenge. We administered 2% or 4% CFFA evaluated its immune-enhancing effects using several immunological experiments, including examination of lysozyme activity, lymphocyte proliferation, and expression of cytokines. We also evaluated the bacterial clearance effects of CFFA against S. Gallinarum. CFFA administration markedly enhanced lysozyme activity, lymphocyte proliferation, and the expression of interleukin (IL)-2, IL-12, tumor necrosis factor alpha, and interferon gamma in the spleen. In broilers challenged with S. Gallinarum, the clinical signs of S. Gallinarum infection and the number of viable bacterial colonies in the feces and tissues decreased in both CFFA groups. Therefore, CFFAs could be good candidates for feed additive to improve nonspecific immune responses and bacterial clearance.
- 著者
- 川畑 篤史
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.2, pp.81-84, 2013 (Released:2013-02-08)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 6 8
がん化学療法の副作用として生じる神経障害性疼痛は,患者のQOL低下を招くだけでなく,化学療法の中止の原因にもなりうるので,その対策は急務である.神経障害性疼痛薬物療法の第一選択薬とされているプレガバリンは,高電位活性化型Ca2+チャネルのα2δサブユニットを標的とした薬物であるが,プレガバリンが作用しないT型(低電位活性化型)Ca2+チャネルのうちCav3.2が神経障害性疼痛の病態に関与することが明らかとなり,T型Ca2+チャネル阻害薬が神経障害性疼痛の治療に応用できる可能性が示唆されている.Cav3.2は,内因性気体メディエーターである硫化水素やL-システインによって直接活性化され,またプロスタグランジンE2によりプロテインキナーゼA依存的に活性化されるほか,生体内のZn2+やビタミンCによって機能が抑制される.本稿では,Cav3.2 T型Ca2+チャネルの分子機能調節機構を概説し,特にがん化学療法に伴う神経障害性疼痛の治療標的分子としての可能性について述べる.
1 0 0 0 OA 精神疾患に対するrTMS 治療
- 著者
- 鵜飼 聡
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.199-205, 2011 (Released:2017-02-16)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
これまでに多様な精神疾患・病態を対象に反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)治療の臨床研究が報告されているが,その対象はうつ病に対するものが圧倒的に多く,その他,統合失調症の言語性幻聴と陽性・陰性症状,強迫性障害についてはメタ解析が報告されている。うつ病に対して,rTMS は,電気けいれん療法との比較では有効性・即効性の面で及ばないものの非侵襲的で忍容性が格段に高く,薬物との比較では遜色のないレベルの有益性があるとの報告もある。米国食品医薬品局は2008年にうつ病に対して適応に厳しい条件を付けたうえでrTMSを認可しており,今後の症例数の増加,臨床研究の発展が期待される。統合失調症の幻聴に対しては比較的良好な成績が示されているが,陽性・陰性症状および強迫性障害に対しては有益性が示されていない。外傷後ストレス障害については複数の二重盲検試験が報告されているが,現状ではメタ解析が可能なレベルの報告はない。
1 0 0 0 OA 生理用品の受容によるケガレ観の変容 パプアニューギニア・アベラム社会の事例から
- 著者
- 新本 万里子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第47回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.1, 2013 (Released:2013-05-27)
生理用品(ナプキンなど西洋起源の経血処置の道具)の受容による月経のケガレ観の変容を、パプアニューギニア・アベラム社会を事例に明らかにすることを目的とする。月経小屋があった当時、作物の栽培に危険な月経中の女性は可視化されていた。生理用品の受容によって、月経は、女性個人のものとなった。月経が作物の栽培に危険なものであるという感覚が希薄化し、当該社会の月経のケガレ観は変容していると考えられる。
1 0 0 0 OA アインシュタイン理論とディラック理論の融合
- 著者
- 中西 襄
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.131-134, 1979-12-20 (Released:2017-10-02)
一般相対論とディラックの電子論の自然な融合が重力場の量子化によってはじめて達成された。この数学的な事情を面倒な計算を一切抜きにして説明する。