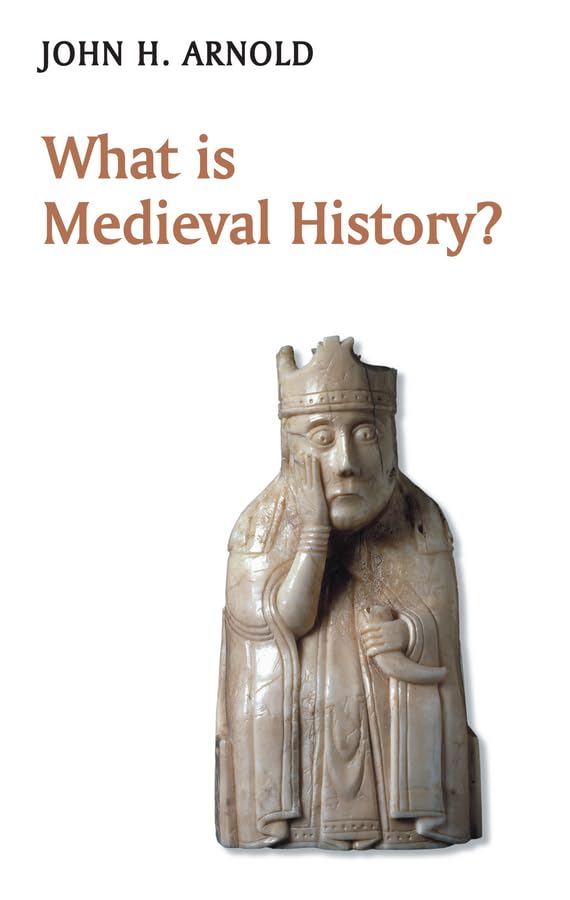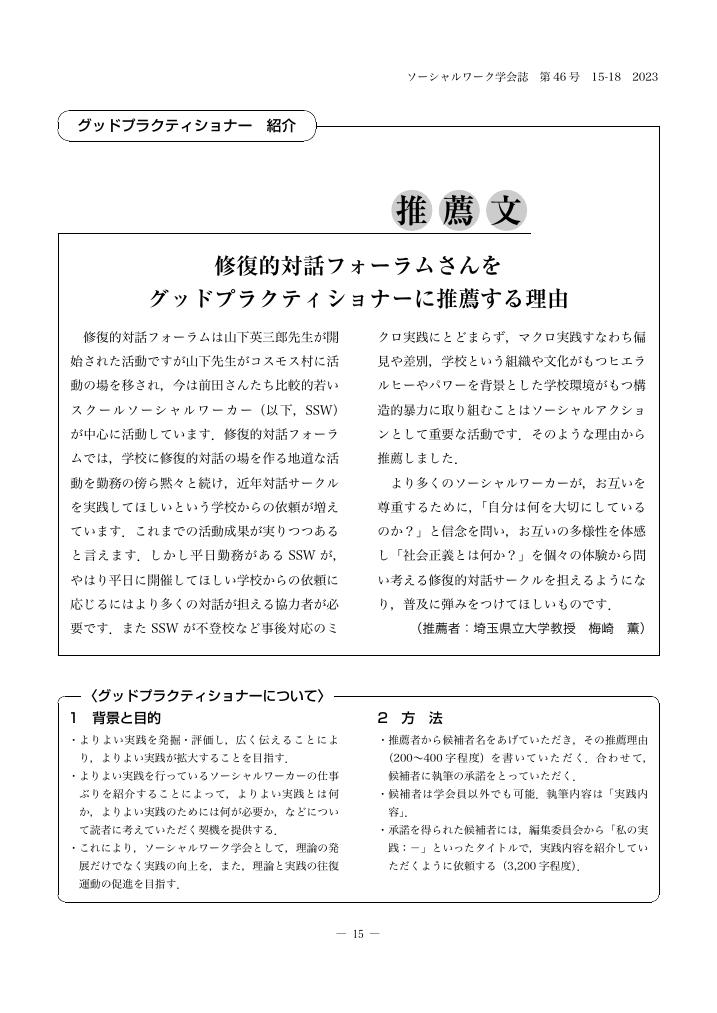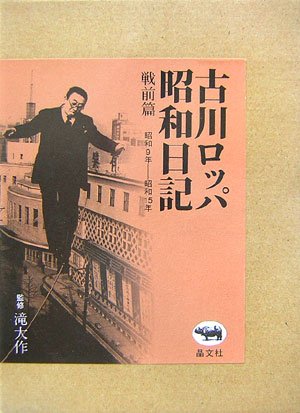1 0 0 0 音声資料の諸側面を一体化したデータベース構築に関する研究
1.ボツワナでの実地調査によって採集したグイクエ=ブッシュマンの言語(グイ語)の記述資料(フィールドノート)を音韻分析した。その結果、この言語の音素目録、および語彙的語根ならびに機能語の音素配列、声調の体系、さらに主な動詞形態音韻論的現象を明らかにした。2.上記の分析に基づき、この言語の約2500項目の基礎語彙についての情報をカード型データベースに入力した。(1)表記法は音素表記を原則とする簡略音声表記を用いた。(2)表記のための特殊記号を含むグイ語専用フォントを一組作成した。(3)様々な音韻的条件からの検索を可能とするソ-トフィールドを、音素配列分析、声調分析の結果をもとに作成した。(4)語彙の形態論的、意味論的および民族学的な情報を入力した。(意味的・民族学的情報の入力に先立ち調査地を同じくする人類学者との意見交換、情報交換をおこなった。)3.録音資料(アナログテープ及びDATによる記録)を編集し、その一部を音響分析した。さらにこの音響資料をカード型データベースに画像データとして入力した。(ただしこの作業は現在も進行中である。)4.調音器官の図版(上顎と舌の断面図)を作成し、画像ファイルとして入力した。5.言語調査がまだ初期段階である現時点では、資料が非常に流動的であるため、枠組みを変更しやすいカード型データベースを用いているが、録音、画像、文字という異質な資料を統合的に扱うには、リレーショナルデータベースのほうが好都合である。将来的にはリレーショナルデータベースに移行する予定である。また、現在用いているパソコンの処理能力では検索に時間がかかり過ぎる。データベースの公開には高速マシンが必要である。
1 0 0 0 グイ語子音の音響音声学的研究
本研究は、ボツワナ共和国のカラハリ地域でブッシュマンの1グループによって話されている、グイ語(中部コイサン語族)が有する極めて複雑な子音組織の理解のために、この組織を特徴付ける4つのクリック種、13種類のクリック伴音、4つの“軟口蓋化"歯茎閉鎖音([tx,tx',tsx、tsx'])、またこれらの音韻分析に直接関連する口蓋垂摩擦音と軟口蓋側面破察放出音の音響的特徴を、CSL-Computerized Speech Labを用いて分析した。その結果は、これまで私が行ってきた伝統的な主観的音声観察に主に基づく記述を大筋では支持し、それに音声的詳細に関する新たな事実を付加するものであった。細かい点では再考や修正に有益であった(たとえば破擦的放出伴音における喉頭の調節に関する推測に関して)。本研究の結果の一部として、すでに、Nakagawa,H.(1998)Unnatural Palatalization in Gui and Gana?Quellen zur Khoisan-Forschung 15,245-263で非クリック子音に関する議論を、また中川裕(1998)「コサイン諸語のクリック子音の記述的枠組み」『音声研究』ではクリック子音の記述に関する議論を、さらにNakagawa,H(1998)A cluster analysis of clicks and their accompaniments,Linguisitics and Phonetics 98(Sept.1998,Ohaio State University)ではクリック子音および“軟口蓋化"歯茎閉鎖音の新子音クラスター解釈の可能性を、それぞれ報告した。本研究の結果の主要部分にあたる子音組織全体の詳細な記述は現在進めているところである。そこでは、クリック子音と非クリック子音とを統一的に記述し分類するのに妥当な弁別特徴に関しても議論をする予定である。
1 0 0 0 言語崩壊時における構造変化の動態的研究
前年度までに蓄積してきた、コイサン諸語コエ語族ガナ語群の統語論、音韻論、声調論の資料を総合し、それらの重要な側面を記述した。また、日本国内のコイサン研究者を訪問して、ガナ語群グイ語の語彙に関する情報交換や討議を行い、その結果(とくに意味記述に関する情報と討議結果)を、構築進行中のグイ語語彙データベースに組み入れた。さらに、この語彙データベースの意味記述の重要な部分を英訳し、英語による公開の準備に着手した。以上に加えて、研究協力者をナイジェリアとウガンダに派遣し、以下(1)(2)のような調査研究を行った。(1)ナイジェリア北部に分布するチャド語系少数民族語であるブラ語の記述調査:主にブラ語の名詞形態論の解明を目的とした調査を行い、特に可譲渡/不可譲渡性がこの言語における名詞分類の根幹を成すこと、また屈折的な形態論を持つ多くのチャド諸語に対し、この言語が主に膠着的な手法で語形成を行い、さらに語形成の方法として重複が重要な機能を果たしていることなどを説明する論文を作成した;またブラ語の語彙調査も継続して行い、音声の録音資料などを収集した。(2)ウガンダのにおける言語使用と言語態度についての調査:首都カンパラの7つの地域およびウガンダ東部のトロロ・ディストリクトのブタレジャで社会言語学的調査を行った。その結果、各調査地点でのリンガフランカ(ガンダ語)と民族語の使用についての諸側面が明らかになり、また、それらの言語に対する言語態度(とくに重要なのはリンガフランカヘの反対意識と民族語保持意識)の実態が明らかになった。
1 0 0 0 OA 乳がんのリスクと予防 ―疫学的観点から―
- 著者
- 津金 昌一郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本乳癌検診学会
- 雑誌
- 日本乳癌検診学会誌 (ISSN:09180729)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.4-15, 2010-03-30 (Released:2011-04-15)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
米国では乳がん死亡の減少が見られ,乳がん検診の重要性が示唆されているが,最近の統計データでは,罹患率の減少も観察されている。これは,乳がんリスクとなるホルモン補充療法の利用減少の影響と考えられている。日本では乳がん罹患,死亡ともに増加している。欧米との違いは,閉経後の乳がんが比較的少ないことだが,米国に移住した日本人の間では閉経後も増加が見られる。初潮・閉経・出産など女性の生殖要因が大きいが,疫学データからは生活習慣との関わりも考えられる。国際的な評価では,閉経前後にかかわらず飲酒は乳がんのリスク要因であり,授乳は予防要因である。肥満に関しては,閉経後の確実な乳がんのリスクだが逆に閉経前の乳がんをほぼ確実に予防する。また,運動が閉経後の乳がんの予防をするのはほぼ確実であるが,閉経前に関しては可能性を示唆するにとどまる。肥満の乳がんへの影響は,極端な肥満の少ない日本人では小さいと考えられる。飲酒については,ほとんど毎日飲む女性の割合は少ないものの,やはりリスクであるということが示されつつある。身体活動の乳がん予防効果を示す日本人の研究はほとんどないが,全般的な健康には良いと言えよう。イソフラボン摂取については,大豆製品をよくとる日本人では,特に閉経後の乳がんを予防してきた可能性が示される。また,受動喫煙と乳がんとの関連を示す研究があるが,特に閉経前では,受動喫煙だけでなく喫煙もやはりリスクである可能性がある。
1 0 0 0 OA 濃尾平野の旧砂丘
- 著者
- 西沢 邦和
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.4, pp.222-226, 1978-08-25 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 平松 真輝
1 0 0 0 What is medieval history?
- 著者
- John H. Arnold
- 出版者
- Polity
- 巻号頁・発行日
- 2008
1 0 0 0 OA 石原深予 著『尾崎翠の詩と病理』
- 著者
- 中川 成美
- 出版者
- 昭和文学会
- 雑誌
- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.216-218, 2016 (Released:2022-11-19)
1 0 0 0 OA 学校に対話文化を定着させるために -学校でのRJサークルを通して-
- 著者
- 前田 奈緒
- 出版者
- 日本ソーシャルワーク学会
- 雑誌
- ソーシャルワーク学会誌 (ISSN:18843654)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.15-18, 2023 (Released:2023-06-27)
1 0 0 0 OA 脳脊髄液産生と自律神経
- 著者
- 田村 直俊
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.105-109, 2022 (Released:2022-04-23)
- 参考文献数
- 32
Schaltenbrand(1936,53))は,脳脊髄液(CSF)が脈絡叢由来の液体と血管周囲腔由来の液体の混合物であること(二元産生説),CSF減少症が自律神経の異常によるCSF産生低下で生じることを記述した.Edvinssonら(1972,73)は,脈絡叢におけるadrenaline作動性とcholine作動性の二重神経支配を確認した.Pappenheimerら(1962)はトレーサーを加えた液体でCSF腔を灌流して,トレーサーのクリアランスからCSF産生量を算出する方法を考案し,Haywood(1976),Lindvallら(1978)は本法を用いて,交感神経刺激でCSF産生が低下することを示唆した.しかし,本法はCSFの産生部位が脈絡叢だけであるという誤った前提(一元産生説)によっていることが指摘されたので,1980年代以降,CSF産生の自律神経制御を検討した報告はない.
1 0 0 0 OA 歩行時における足圧中心軌跡と距骨下関節の可動性の関係
- 著者
- 江戸 優裕 西江 謙一郎 根本 伸洋 中村 大介
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.169-172, 2018 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 18
〔目的〕歩行時の足圧中心軌跡と距骨下関節の関係を明らかにすることとした.〔対象と方法〕対象は健常成人10名とした.足圧分布測定器を用いて至適速度での裸足歩行時の後・中・前足部における足圧中心位置を捉えた.そして,距骨下関節に関わる10項目の理学所見との関係を分析した.〔結果〕足圧中心は後足部から中足部までは足底やや外側を通り,前足部では内側に抜けていく軌跡を描いた.また,足圧中心が後足部と前足部レベルで外方を通過するほど,距骨下関節回内可動性が小さいことがわかった.〔結語〕距骨下関節回外筋の習慣的な活動が,歩行時の足圧中心軌跡の外方化と距骨下関節回内可動性の減少を招くことが示唆された.
- 著者
- Junho Chae Jun-Gi Lee Jun-Ho Lee Sam-Kyu Kim
- 出版者
- Arachnological Society of Japan
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.29-37, 2023-06-20 (Released:2023-07-01)
A poorly known nursery web spider species, Dolomedes nigrimaculatus (Araneae: Pisauridae), is redescribed on the basis of Korean specimens, with a new junior synonym, Dolomedes jirisanensis which has been treated wrongly as a nomen nudum. Dolomedes nigrimaculatus is considered a sister species of D. zatsun from Okinawa Island, Japan, which have several morphological characteristics in common. Detailed description and remarks on the synonymy and intraspecific variation in its body coloration and shape of copulatory organs of D. nigrimaculatus are provided, with a key to all Korean Dolomedes species.
1 0 0 0 OA Comparative analysis of endophyte diversity of Dendrobium officinale lived on rock and tree
- 著者
- Xiaolan Li Huan Hu Qunli Ren Miao Wang Yimei Du Yuqi He Qian Wang
- 出版者
- Japanese Society for Plant Biotechnology
- 雑誌
- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.145-155, 2023-06-25 (Released:2023-06-25)
- 参考文献数
- 70
Dendrobium officinale usually lives on rock or tree, but their endophyte diversity has not yet been fully revealed? In this study, high-throughput sequencing technology was used to investigate the endophyte diversity of the roots of D. officinale lived on tree (Group 1–3, arboreal type) and rock (Group 4, lithophytic type). The results showed that their composition of endophytic fungi and bacteria were similar at phylum level, while their relative abundance were different. Their taxa composition and abundance of endophytes differed significantly among groups at the genus level. Alpha diversity of endophytic fungi of lithophytic type was higher than those from arboreal type, while there was no advantage in endophytic bacteria. Beta diversity revealed that the endophytic fungi tended to cluster in each group, but the endophytic bacteria were dispersed among the groups. LEfSe analysis found that the numbers of predicted endophyte biomarkers of lithophytic type were more than arboreal types at genus level, and the biomarkers varied among groups. Microbial network analysis revealed similarities and differences in the taxa composition and abundance of shared and special endophytes in each group. These results suggested that the root endophytes of lithophytic and arboreal D. officinale differed in diversity.
- 著者
- Hiroyuki Katsuoka Naoya Hamabe Chiemi Kato Susumu Hisamatsu Fujio Baba Motohiro Taneishi Toshiyuki Sasaki
- 出版者
- Japanese Society for Plant Biotechnology
- 雑誌
- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.135-143, 2023-06-25 (Released:2023-06-25)
- 参考文献数
- 34
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. and Rhodanthemum gayanum (Coss. & Durieu) B. H. Wilcox, K. Bremer & Humphries are capable of hybridization. To expand flower color variation in this intergeneric hybrid group, we performed crosses using A. frutescens as the seed parent and R. hosmariense (Ball) B. H. Wilcox, K. Bremer & Humphries, R. catananche (Ball) B. H. Wilcox, K. Bremer & Humphries as the pollen parent. One plantlet was obtained from each cross between the white to pale pink-flowered A. frutescens and white-flowered R. hosmariense, and from a cross between the pink-flowered A. frutescens and cream to pale yellow-flowered R. catananche, via ovule culture. The cross with R. hosmariense produced an individual with white to pale pink ray florets, and the cross with R. catananche produced an individual with red ray florets. The flower and leaf shape of the progenies was intermediate between the parents, and other morphological traits were also characterized in the same manner. Morphological observations and a cleaved amplified polymorphic sequence marker-based determination, using the internal transcribed spacer region as a target for amplification and the restriction enzyme Afl II, revealed that both individuals are hybrids between A. frutescens and R. hosmariense, R. catananche. To the best of our knowledge, this is the first study to report that crossbreeding between A. frutescens (seed parent) and R. hosmariense, R. catananche (pollen parent) is possible. Moreover, further development of Argyranthemum breeding, especially that of a series of hybrid cultivars with different flower colors, is expected.
1 0 0 0 OA 身体的万華鏡:鑑賞者と鏡作品の位置に応じて反射像が変化する万華鏡型作品の提案
- 著者
- 中津 正樹 藤木 淳
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.121-130, 2023 (Released:2023-06-30)
- 参考文献数
- 24
This research proposes a mirror work in which reflected image changes by inducing the viewer to move their body, even though the work itself and the entity that generates the image are stationary. The change in reflected image is triggered by the position of the viewer, which encourages the viewer to continuously move their body. This is intended to create an active and sustained viewing experience. The questionnaire conducted at the time of the exhibition confirmed the descriptions of the viewing of the artworks that involved physical movement during viewing. In addition, the behavioral observation of the viewers confirmed that they moved their bodies several times. This indicates that this proposal has achieved its goal of promoting an active and sustained viewing experience.
1 0 0 0 OA リウマチ・膠原病とHLA
- 著者
- 土屋 尚之 川﨑 綾 岡 笑美 古川 宏
- 出版者
- 日本組織適合性学会
- 雑誌
- 日本組織適合性学会誌 (ISSN:21869995)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.74-83, 2015 (Released:2015-08-11)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 4
1973年の強直性脊椎炎とHLA-B27の関連の発見以来,40年以上にわたり,HLA遺伝子群は,リウマチ・膠原病において最も確立した病因的因子であり続けている。これまで,多くの関連研究や分子機構を探る研究が積み重ねられ,その時代の先端的解析法を駆使して,多くの知見が明らかになるとともに,それ以上の新たな疑問が産み出されてきた。本稿では,代表的なリウマチ性疾患・膠原病および類縁疾患について,日本人集団を中心に関連研究の成果をまとめるとともに,リウマチ性疾患に関するHLA研究の最近の進歩について概説する。
1 0 0 0 OA 励起子ポラリトンの量子凝縮 (解説)
- 著者
- 山本 喜久 宇都宮 聖子
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.96-107, 2012-02-05 (Released:2019-10-19)
- 参考文献数
- 56
量子井戸にトラップされた励起子とプレーナマイクロ共振器に閉じ込められた光子が強結合を起こして生成される励起子ポラリトンは,その質量がアルカリ原子に比べて約10桁,励起子に比べて約4桁も軽いため,極めて高温・低密度で量子凝縮相を実現できる.一方,励起子ポラリトンは,数ピコ秒から数十ピコ秒という短い寿命を持つため,超流動液体ヘリウムやアルカリ原子ボーズアインシュタイン凝縮体(BEC)が熱平衡下の量子凝縮相を示すのに対し,非平衡開放系での量子凝縮を発現する.本稿では,急速に発展しているこの新しい量子凝縮相の研究をレビューする.特に,同じ非平衡系でありながら巨視的コヒーレンスを実現しているレーザー相転移との違い,2次元系に特有なBerezinskii-Kosterlitz-Thouless(BKT)相転移の実験的証拠,音波的な励起スペクトラム,高次軌道関数での量子凝縮,などに焦点を当てて解説する.
- 著者
- Haruka Mizuno Takahiro Ueno Hiroshi Takasaki
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.5, pp.340-345, 2023 (Released:2023-05-01)
- 参考文献数
- 25
[Purpose] This study aimed to determine whether certain research activities improve the attitude of rehabilitation professionals towards evidence-based practice and its implementation in Japan. [Participants and Methods] We included physical, occupational, and speech therapists currently working in clinical settings. We employed hierarchical multiple regression analyses to assess the attitude of rehabilitation professionals towards evidence-based practice and research activities. Scores of the five dimensions of the Health Sciences-Evidence Based Practice questionnaire were considered the dependent variables. The five dimensions were as follows: Dimension 1, attitude towards evidence-based practice; Dimensions 2–4, evidence-based practice implementation; and Dimension 5, work environment related to evidence-based practice barriers–facilitators. The four sociodemographic variables (gender, academic degree, clinical experience, and the number of therapists at work) were initially included, following which self-reported research achievements were supplemented as independent variables (the number of case studies, literature reviews, cross-sectional studies, and longitudinal studies). [Results] We analyzed data from 167 participants. In addition to sociodemographic variables, the research achievements that statistically increased F-values of the modeling were case study achievements in Dimensions 2–3, cross-sectional study achievements in Dimensions 2 and 4, and longitudinal study achievements in Dimension 5. [Conclusion] Case studies and cross-sectional studies could improve evidence-based practice implementation among rehabilitation professionals in Japan.