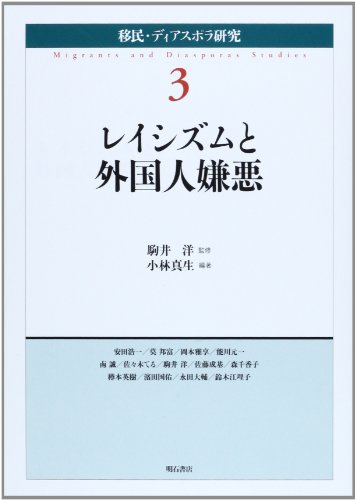- 著者
- 新井 直人 中山 雅之 新井 郷史 川﨑 樹里 花輪 幸太郎 黒崎 史朗 渡邊 真弥 間藤 尚子 坂東 政司 萩原 弘一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会
- 雑誌
- 気管支学 (ISSN:02872137)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.221-225, 2023-05-25 (Released:2023-06-13)
- 参考文献数
- 15
背景.肺末梢病変を呈する放線菌症は,気管支鏡検査で確定診断することが難しく,肺癌や肺結核との鑑別目的に外科的肺切除を必要とすることが少なくない.症例.47歳男性.咳嗽・血痰を主訴に受診した.胸部CTで右肺S1末梢に限局した浸潤影を認め,内部に気管支の拡張像を伴っていた.気管支鏡検査でガイドシース併用気管支腔内超音波断層法を用いて,病変から生検を複数回行い,嫌気培養の結果Actinomyces graevenitziiによる肺放線菌症と診断した.呼吸不全なく,6カ月間のアモキシシリン内服治療で陰影はわずかな瘢痕を残して消退し,その後再燃なく経過した.結論.内部に気管支拡張像を伴う肺末梢病変の鑑別に肺放線菌症が挙げられる.起因菌分離のための気管支鏡検査を施行する場合,病変内部で生検を複数回行い,さらに検体を嫌気培養に提出することが重要である.
1 0 0 0 OA 「昭和の大合併」研究の動向と「平成の大合併」研究の課題
- 著者
- 新藤 慶
- 出版者
- 地域社会学会
- 雑誌
- 地域社会学会年報 (ISSN:21893918)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.91-108, 2005-05-14 (Released:2021-05-07)
- 参考文献数
- 25
1 0 0 0 レイシズムと外国人嫌悪
1 0 0 0 西説醫範提綱釋義 3巻
- 著者
- 榛齋宇田川先生譯述 諏訪俊筆記
- 出版者
- 河内屋儀助 : 河内屋太助
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 OA 青年期後期から成人期にわたる親の老いの認知と親の老いに対する態度との関係
- 著者
- 池田 幸恭
- 出版者
- 日本青年心理学会
- 雑誌
- 青年心理学研究 (ISSN:09153349)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.67-86, 2023-04-20 (Released:2023-05-13)
- 参考文献数
- 48
This study aimed to clarify the relations between awareness of and attitude toward parental aging from late adolescence to early adulthood in Japan. An online survey was conducted with 800 participants aged 20-39 years, and the data were analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis. Awareness of “decline in parents’ activity” and “parents’ psychological maturation” were extracted for awareness of parental aging. Four attitudes toward parental aging were extracted: “caring about aging parents,” “sadness about parental aging,” “anxiety over parents’ old age,” and “generativity evoked by parental aging.” Structural equation modeling revealed that awareness of decline in parents’ activity was positively associated with sadness about paternal aging as well as anxiety over parents’ old age. Awareness of parents’ psychological maturation was positively associated with generativity evoked by parental aging. Additionally, awareness of parents’ psychological maturation was positively associated with caring about aging parents, except for women in their 20s and 30s regarding their fathers and mothers, respectively. These associations differed according to the type of parent-child relationship and the child’s age group.
1 0 0 0 OA 大気中の微量金属成分の密度分布
- 著者
- 杉前 昭好
- 出版者
- Japan Society for Atmospheric Environment
- 雑誌
- 大気汚染学会誌 (ISSN:03867064)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.5, pp.416-424, 1983-10-20 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
重液分離法とICP発光分析法の組み合せにより, 各種大気試料中の金属成分の密度分布の測定を実施した。測定対象試料はピル空調フィルター付着粉じん, Hi-volによる浮遊粉じん試料, Low-volによる大気浮遊粒子状物質試料, アンダーセン・サソプラーによる粒径別分級捕集試料, 降下ばいじんなどであり, 空調フィルター付着粉じんについては, Zn, Pb, Cd, Cr, Mn, Fe, V, Cuの8成分, その他の試料については, Zn, Fe, Mn, Cuの4成分の密度分布を測定した。各試料について, 特徴的な密度分布パターンが得られ, 降下ばいじん中の金属成分の密度分布曲線には密度2.7g/cm3と3.3g/cm3以上の位置にピークがあるのに対し, 浮遊粉じん中の金属成分は金属化合物であるとは考えにくいような低比重であることが判明した。また試料捕集面への空気取り込み流量の差が密度分布パターンに影響を及ぼしており, 空気吸引流量の大きい場合には, 高密度成分の比率が増加の傾向を示した。密度分布曲線には, 金属成分間でも差異があり, Znで代表される人為発生源からの寄与の大きな元素は低密度であり, 自然発生源からの寄与率の高いFeなどは比較的高密度成分の比率が高くなる傾向があった。またアンダーセン・サンプラーにより, 空気力学的粒径に応じて分級捕集した粉じん中の金属成分の密度分布には相互にかなりの差異があり, 微小 (粗大) 粒子捕集ステージには低 (高) 密度粒子が分級捕集されていることも確認された。
1 0 0 0 OA 韓国における大型店の立地動向 出店規制に注目して
- 著者
- 駒木 伸比古
- 出版者
- 地理空間学会
- 雑誌
- 地理空間 (ISSN:18829872)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.222-235, 2018 (Released:2018-04-13)
本稿は,韓国において現在みられるような「割引店」を主とした大型店が業態として確立した背景を把握するとともに,立地状況を明らかにすることを目的とした。その際に,韓国における政策転換に伴う小売業に関する制度の変化との関わりにも注目した。そして韓国における流通業,特に大型店に関する規制の変遷を整理するとともに,韓国における大型店が業態としてどのように成立,成長してきたのかを検討した。さらに,地図化することで,現在立地している大型店の出店時期や規模について考察した。その結果,(1)大型店に関する流通規制の方向性が2010年前後に大きく変化したこと,(2)流通規制の変化に伴い,1990 年代にソウル大都市圏や広域市などに限定されていた大型店の立地が,2000年代に入り地方の小都市にまで全国展開していったものの,2010年代になると出店数が急激に減少し,立地も大都市圏付近に回帰しつつあること,の2 点が明らかとなった。
1 0 0 0 OA 在宅強化型介護老人保健施設に関する文献検討 ─在宅復帰率の向上に向けた取り組みと課題─
- 著者
- 佐伯 恭子 鳥田 美紀代 杉本 知子 上野 佳代
- 出版者
- 千葉県立保健医療大学
- 雑誌
- 千葉県立保健医療大学紀要 (ISSN:18849326)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1_43-1_49, 2016-03-29 (Released:2019-07-31)
- 参考文献数
- 35
平成24年度の介護報酬改定では在宅強化型の基本報酬が創設され,介護老人保健施設(以下,老健)から在宅に戻る流れが推進されているが,算定を取得している施設は少ない.そこで,在宅強化型の算定を取得した老健でおこなわれている実際の取り組みと,現状における課題を明らかにすることを目的に文献検討をおこなった. 文献検索は,医学中央雑誌Web版などを用いておこなった.文献は2012年以降のものとし,検索のキーワードは「介護老人保健施設」「在宅強化型」「在宅復帰」「在宅療養支援」とした.その結果,在宅強化型老健に関する文献は32件が抽出された. 在宅強化型老健における在宅復帰率向上に向けた実際の取り組みは,〈入所前や入所時点で入所目的を明確化〉,〈リハビリテーションの重視〉,〈在宅介護が可能かもしれないと思えるための家族支援〉など,現状における課題は,《ベッド稼働率の低下》や《入退所が増えることによる業務負担増加》などであった. 在宅強化型老健で在宅復帰率を向上させるためには,利用者個々に対する在宅復帰のための具体的な目標を利用者や家族とともに設定し,その目標に向かって多職種協働でかかわることが重要であると考えられた.
- 著者
- 平生 尚之 稲葉 綾乃 井澤 信三
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.147-158, 2018-09-30 (Released:2019-04-05)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
本研究では、自閉症スペクトラム障害特性(以下、ASD)を背景とするひきこもり状態にある人の家族を対象とし、ASDに特化したCRAFTプログラムによる介入を実施した。本プログラムは、個別セッションと集団セッションの併用型とし、対象者は本人相談につながりにくい9家族12名の親であった。本介入の結果、ひきこもり行動チェックリストの得点が改善され、本人10名中6名が相談につながり、別の1名はアルバイトを開始した。また、家族の心理的ストレス反応(SRS-18)の低減も認められた。本介入では、ひきこもり状態にある本人がASD特性のなかでも受け身型で、なおかつ対人不安の強いタイプに効果的であった。一方で、参加した親のなかでパートナーにもASD特性が疑われる場合は、精神健康度(GHQ-28)が介入後に低減したが、フォローアップ時には再上昇が認められた。
1 0 0 0 OA 『華厳経』の世界成就とホーキングの宇宙論
- 著者
- 陳 永裕(本覚)
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.1110-1102, 2012-03-20 (Released:2017-09-01)
- 著者
- Gabriel Téllez
- 雑誌
- STATPHYS28
- 巻号頁・発行日
- 2023-06-23
1 0 0 0 OA 擬似極配置法によるPIDコントローラ調整法
- 著者
- 志水 清孝 本城 仰太 山口 毅
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.8, pp.686-693, 2002-08-31 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 4
In this paper, a new tuning method for PID control is proposed. We set the controlled system to be a controllable and observable SISO system. In the first half, we consider optimal servo problems by 2 methods. For each method, the optimal state feedback rule is obtained by the theory of optimal regulator, and the optimal poles of this closed-loop system are calculated. In the second half, we consider the problem that the poles of closed-loop system by PID control are approximated to the optimal poles as much as possible. This technique is called quasi pole placement. The problem becomes a nonlinear planning problem with some equality constraints, and solved by exterior penalty function method. Finally, the simulation results for the 5 order system are reported, and the effectiveness of this technique is demonstrated.
- 著者
- 蒲谷 槙介
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.507-517, 2013 (Released:2015-12-20)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2
近年,アタッチメントの世代間伝達の枠組みの中で,母親がいかに乳児のネガティブ情動を共感的に映し出すかという調律的応答を重視する立場が台頭しつつある。本稿では,前言語期の乳児とその母親を対象とした相互作用場面の観察を実施し,母親が実際にどのような調律的応答を行うのかを検証した。回帰分析の結果,内的作業モデルが安定傾向の母親は乳児のネガティブ情動表出に対し「笑顔を伴った心境言及」を行いやすい一方,不安定傾向の母親は心境言及を行わない,もしくは心境言及を含まない応答をしやすいことが明らかとなった。また,気質的にむずかりやすい乳児と,内的作業モデルのうち回避の側面が強い母親の組合せでは,「笑顔を伴った心境言及」が特に生起しにくいことが明らかとなった。この応答はこれまでの理論的枠組みでは見逃されてきた調律的応答の一種と考えられ,子どもの社会情緒的発達を促進する一つの要因として今後着目すべきものである。
1 0 0 0 OA 著作権の刑事罰・刑事手続が表現者に与える萎縮効果の研究
1 0 0 0 OA 1 戦場のLGBT ——戦時性暴力の被害と国連安全保障理事会における対立
- 著者
- 上野 友也
- 出版者
- 日本平和学会
- 雑誌
- 平和研究 (ISSN:24361054)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.1-21, 2023-03-31 (Released:2023-03-25)
- 参考文献数
- 27
国連安全保障理事会は、LGBTに対する戦時性暴力についてどのような議論を展開し、どのように対立してきたのであろうか。それにはどのような展望があるのか。それを明らかにするのが、本稿の目的である。LGBTに対する暴力と差別の問題は、大国間・地域間対立が先鋭化しているテーマの一つでもある。欧米諸国、ラテンアメリカ諸国、イスラエルは、LGBTの権利の擁護に積極的である一方、ロシア、中国、アラブ諸国、アフリカ諸国、アジア諸国の多くがLGBTの権利の擁護に消極的あるいは否定的な立場をとっている。両者の対立は、国連安全保障理事会においても繰り広げられている。国連安全保障理事会は、「女性・平和・安全保障」のアジェンダを構築したが、LGBTの権利の擁護を目的としていない。しかし、このアジェンダに関する国連安全保障理事会の決議、議長声明、議事録を分析することで、国連安全保障理事会がLGBTに対する戦時性暴力に対して一致した行動がとれない状況にある一方、国連LGBTIコア・グループに所属している理事国が戦時性暴力からのLGBTの保護に積極的な発言をしていることがわかるであろう。現在のところ、国連安全保障理事会において、戦時性暴力からのLGBTの保護に積極的な国家と、消極的あるいは否定的な立場の国家は拮抗しており、多くの理事国の賛同を得て決議や議長声明を採択することが困難であることに変わりはない。
1 0 0 0 OA 広域の消費者購買データに基づくオリーブオイル購買の傾向分析と地域実店舗への適用
- 著者
- 坂井 明日香 丸橋 弘明 羽室 行信 笹嶋 宗彦 加藤 直樹 宇野 毅明
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.WI2-I_1-12, 2021-01-01 (Released:2021-01-01)
- 参考文献数
- 12
Recently, data-driven sales management is widely recognized and sales at the real super-market is not the exception. For designing such strategies, first of all, we have to analyze consumers’ behavior. However, such an analysis is difficult, especially for the managers of the real shops, since they only have customers’ data of their own shops. Generally, the customers buy things not only from the managers’ shops but also other shops. The goal of this research is to develop a general method to transfer sales promotion strategy, derived from analysis on wide area, to local real shop. The authors analyzed such consumers’ characteristics who buy olive oils in Kansai region. For the analysis, we used QPR(Quick Purchase Report system, developed and managed by MACROMILL, Inc). Firstly, we divided the consumers on the QPR into five clusters, according to the simultaneous buying pattern. Then, we analyzed each of the clusters and found some emerging patterns of the purchasing behavior. Observing the patterns, we designed a marketing strategy for the real shop in Hyogo prefecture belonging Kansai district. Finally, we carried out an experiment at the shop to evaluate whether the strategy promotes the sales of the olive oil or not for six weeks. The result of the experiment showed that the marketing strategy is effective in one view. At the same time, we learned many lessons from the research, especially difficulty of the evaluation at the real shop.
1 0 0 0 OA 学び続ける教師は幸せか? コーリングの媒介効果に着目して
- 著者
- 村上 祐介
- 出版者
- 日本トランスパーソナル心理学/精神医学会
- 雑誌
- トランスパーソナル心理学/精神医学 (ISSN:13454501)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.16-26, 2021 (Released:2022-10-29)
本研究の目的は,学校教員の学び続ける態度と,人生満足度の関連における,コーリングの媒介効果を検討 することであった。インターネット調査を実施し,318名の学校教員がアンケートに回答した。最終的に,234 名(平均年齢 = 46.68歳,男性155名,女性79名)を対象とした媒介分析を行った結果,コーリングの媒介効果が確認された。すなわち,自主的に職務の改善に取り 組む学び続ける教師は,人生満足度が高いが,その関係性は,コーリングによって媒介されることが示された。本研究の限界と今後の展望が議論された。
1 0 0 0 OA 「英米特殊関係」とイギリスの第一回EEC加盟申請, 1955-61年
- 著者
- 小川 浩之
- 出版者
- 日本EU学会
- 雑誌
- 日本EU学会年報 (ISSN:18843123)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.25, pp.139-173,285, 2005-09-30 (Released:2010-05-21)
The British Government under Harold Macmillan made its first application to join the European Economic Community (EEC) in August 1961. This application marked not only a significant turning point of Britain's post-war external policy, but also a very beginning of the enlargement process of the European Integration (“from the Six to the Twenty-five”).In the existing studies, it has often been pointed out that the British Government's consideration about its “special relationship” with the United States, particularly its recognition that the new John F. Kennedy Administration (inaugurated in January 1961) supported the EEC and Britain's entry into it more vigorously than the previous Dwight D. Eisenhower Administration, was one of the factors which facilitated the first application. However, this article, which is based on both British and American governmental records, claims that America's strong support for the European Integration of the Six and its relative coolness towards British initiative such as the European Free Trade Area (FTA) plan (the so-called Plan G) and the European Free Trade Association (EFTA) were largely consistent throughout the Eisenhower and Kennedy Administrations. The British Government tried hard to persuade the Americans into adopting more pro-British and pro-FTA/EFTA attitudes, but those efforts turned out to be mostly abortive. Consequently, the consistency (rather than change, as often pointed out in many existing studies) of the American attitudes facilitated Britain's policy change towards its first application to the EEC.In the diplomatic sphere, Britain's first application to the EEC can be understood as a measure to maintain and strengthen its “special relationship” with the United States, by becoming a member and a “stabilising force” in the EEC. In the trade sphere, Britain's first application can be understood as a measure to secure an equal access to the EEC market, which was expected to be an alternative to the huge but still protective American market but (if Britain remained outside) be surrounded by relatively high common external tariffs. Therefore, it can be pointed out that Britain's first attempt to join the EEC was a primarily defensive effort to avoid the danger of being sandwiched by the United States and the EEC and seriously losing the basis of its international influence and economic power.
1 0 0 0 OA 強化プラスチックスの破壊機構 静的および疲労強度について
- 著者
- 藤井 太一
- 出版者
- 公益社団法人 日本材料学会
- 雑誌
- 材料 (ISSN:05145163)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.163, pp.257-267, 1967-04-15 (Released:2009-06-03)
- 被引用文献数
- 1 1