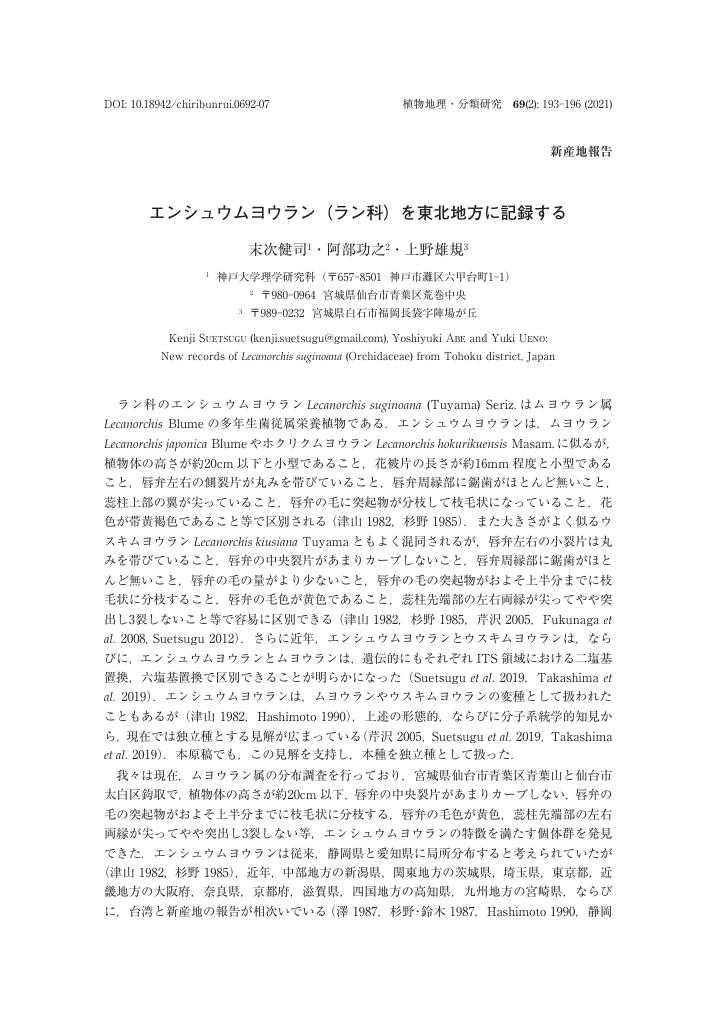- 著者
- 西平 崇人 鈴木 圭輔 竹川 英宏 中村 利生 岩崎 晶夫 平田 幸一
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.10, pp.819-823, 2014-10-01 (Released:2014-10-24)
- 参考文献数
- 17
症例は45歳男性である.後頭部痛と吐き気の後,左方向への傾きが出現した.神経学的には左へのtruncal lateropulsion以外に異常はなかった.頭部MRIでは左延髄下部外側に急性期梗塞をみとめ,臨床・画像所見から左椎骨動脈解離による機序が考えられた.第6病日に右第10胸髄以下の温痛覚障害,左顔面発汗低下,左縮瞳が出現し,頭部MRIでは梗塞巣が拡大していた.脊髄小脳路の障害によりtruncal lateropulsionが,外側脊髄視床路の最外側部の障害により胸髄以下の温痛覚障害が出現したと推察された.本症例は延髄外側の臨床症状と障害部位との関連を理解する上において貴重な症例と考えられた.
1 0 0 0 OA Body lateropulsionを主訴とした脳梗塞5症例の臨床像の検討
- 著者
- 松田 雅純 鎌田 幸子 大川 聡 菅原 正伯 大西 洋英
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.195-199, 2013-05-20 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 17
要旨:Body lateropulsionは,一側に体が不随意に倒れてしまう症候のことをいう.今回我々は,body lateropulsionを主訴とした脳梗塞の5症例について後ろ向きに検討した.5例とも当科には原因不明の失調症として紹介された.症状としては,Horner症候群,顔面,手,足の感覚障害を伴う例もみられた.急性期では画像診断に難渋する例が多くみられた.5例とも初回のMRI検査では病巣を検出できなかった.病巣をMRI検査で検出できたのは平均6.4日目(中央値8日)であった.責任病巣としては前脊髄小脳路またはascending graviceptive pathwayが責任病巣と考えられた.急性発症の体が傾くという訴えの際には,詳細な診察を行い発症初期のMRI拡散強調像で病変を指摘することができなくても脳血管障害の可能性を常に念頭に置き診療に当たることが重要であると思われた.
1 0 0 0 OA ワーク・ライフ・バランス意識が組織市民行動に与える影響に関する研究 M社のケース
- 著者
- 加納 郁也
- 出版者
- 日本情報経営学会
- 雑誌
- 日本情報経営学会誌 (ISSN:18822614)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.32-44, 2019 (Released:2020-09-23)
- 参考文献数
- 19
The purpose of this paper is to research the effect of Work-life Balance on organizational citizenship behaviors (OCB). Previous research on work-life balance (hereinafter referred to as “WLB”) has mainly focused on the aspect of life, giving rise to the problem that only institutional factors and operational factors related to the introduction of WLB measures were considered the leading factors. The results of this study indicate that WLB is a positive influence of OCB.
1 0 0 0 OA 身体性知能の実現に向けたソフトロボティクスの設計原理
- 著者
- 飯田 史也 新山 龍馬 國吉 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.10, pp.791-797, 2019-10-10 (Released:2019-10-25)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 塚野 慧星
- 出版者
- 日本特別活動学会
- 雑誌
- 日本特別活動学会紀要 (ISSN:13437151)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.39-47, 2023-03-31 (Released:2023-04-13)
- 参考文献数
- 22
本稿では、近代の哲学者であるカントの多元主義を手がかりに、児童生徒が互いのよさや可能性を発揮することのできる集団活動のあり方を実現するため、集団活動を「冷ます」ことの意義を論じている。活動が盛り上がるなかで熱を帯びる集団活動を適度に抑制することを指すこの実践は、児童生徒が自他について冷静に反省を行うための機会を用意し、互いのよさや可能性を発揮しやすい環境を整えるものである。同実践は、特別活動研究一般において目指されているような、児童生徒の相互作用を豊かにするものとは別なる方向において、集団活動のより良いあり方を実現するための第一歩となりうるものである。
- 著者
- Masakuni Matsuoka Kohei Danzuka
- 出版者
- The Society of Chemical Engineers, Japan
- 雑誌
- JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN (ISSN:00219592)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.393-399, 2009-06-20 (Released:2009-06-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 6
To demonstrate the effect of mechanochemical processing on solid-state recrystallization, four inorganic salts of NaCl, KCl, NaBr and KBr were selected on the basis of a literature survey and crystallographic data, and their binary mixtures were ground with a planetary ball mill. X-ray powder diffraction patterns of the ground particles were analyzed, showing either formation of solid solutions and exchange reactions as well as no changes occurring due to grinding. The binary systems of NaCl–NaBr and KCl–KBr resulted in the formation of complete solid solutions, while the NaBr–KCl system exhibited the exchange reaction so that the final XRD patterns were exactly the same as those of NaCl–KBr. Additional experiments with salt mixtures containing NaBr and KCl showed the occurrence of the exchange reactions and simultaneous formation of solid solutions. From these observations, mechanochemical processing was found to be effective to cause several types of solid-state recrystallization at the atomic level.
- 著者
- Duck Y. Hwang Yong M. Kim Dong H. Shin
- 出版者
- The Japan Institute of Metals and Materials
- 雑誌
- MATERIALS TRANSACTIONS (ISSN:13459678)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.671-678, 2009-03-01 (Released:2009-02-25)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 39 47
Plasma Electrolyte Oxidation (PEO) behavior of AZ91 Mg alloy was investigated in the electrolytes with/without potassium fluoride. Growth rate of coating thickness in the electrolyte containing potassium fluoride (Bath B) was much higher than that in the electrolyte without potassium fluoride (Bath A). The oxide layer formed on AZ91 Mg alloy in electrolyte with potassium fluoride and sodium silicate consisted of MgO, MgF2 and Mg2SiO4. Corrosion current density of oxide layer coated from the electrolyte with potassium fluoride was much lower than that of oxide layer coated from the electrolyte without potassium fluoride. From the result of EIS analysis, it was known that inner barrier layer in the oxide layer coated from the electrolyte with potassium fluoride had a good influence of the corrosion resistance of Mg alloy. The corrosion resistance curves of Bath B were similar to the thickness curves, indicating that the thickness of the oxide layer played an important role in corrosion resistance of AZ91 Mg alloy. The oxide layer in the Bath B containing potassium fluoride was found to be a compact barrier-type passive film in presence of fluoride ions. The existence of the dense MgO and MgF2 in the barrier layer had a favorable effect on the corrosion resistance of the AZ91 Mg alloy formed from Bath B by PEO process.
1 0 0 0 人と共に変化するAI倫理のための共同デザインワークショップ
- 著者
- 中尾 悠里
- 雑誌
- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)
- 巻号頁・発行日
- 2023-04-06
1 0 0 0 OA 長崎方言におけるタイとバイの意味論的差違
- 著者
- 前田 昭彦
- 雑誌
- 長崎大学留学生センター紀要 (ISSN:13486810)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.83-103, 1999-06-30
1 0 0 0 OA 学校(と地域)における虐待予防と介入
- 著者
- 数井 みゆき
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.208-217, 2011-03-30 (Released:2011-11-25)
- 参考文献数
- 57
被虐待児の特徴として, 情動調節がうまくいかないことや社会的な関係で不利益を受けやすいこと, また, 学力の低下や常習的な学校のさぼり, 暴力行為や犯罪などへの加担など, 学業や学校生活の問題だけではなく人生そのものが破壊されてしまうこともある。また, 早期に通告されて, 親からの分離という措置によって里親家庭や児童養護施設に移ることが, 学力の低下をもたらし, 学校適応を阻害することも報告されている。すでに北米では, 学校(や地域)で予防教育が 1970 年代から多数行われているが, 被虐待児の家庭背景は多くの場合, 片親家庭で貧困や人種問題, 地域の危険性など複雑である。そのため, 子どもや家庭, 学校を含む包括的な介入の実践が行われてきた。特に, 1991 年から準備が始まり, 現在も追跡が行われているカナダ, オンタリオ州政府の全面援助と協力による地域全体のつながりの構築を含むプロジェクトは不利な条件にいる子どもの発達に対して大きな効力を生み出している。子どものいる家族だけではなく, 様々な立場にある近隣住民を引き込みながら行った予防的介入プロジェクトから, 学ぶことは非常に大きい。対症療法では, 子どもは救われないのである。
- 著者
- 近藤 龍彰
- 出版者
- 心理科学研究会
- 雑誌
- 心理科学 (ISSN:03883299)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.45-56, 2021 (Released:2022-05-11)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA オペラント学習と強化
- 著者
- 池上 司郎 川村 浩
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.337-358, 1981 (Released:2019-07-24)
1 0 0 0 OA イギリスの国民性--イギリス学序論
- 著者
- 武井. 邦夫
- 雑誌
- 茨城大学地域総合研究所年報
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.9-22, 1982
1 0 0 0 OA パンデミック下でのマスク着用促進ポスターの研究
- 著者
- 鈴木 清史
- 出版者
- 静岡大学人文社会科学部アジア研究センター
- 雑誌
- アジア研究 = Asian Studies
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.3-19, 2023-03
- 著者
- 米村 みゆき
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.8, pp.63-72, 1995-08-10 (Released:2017-08-01)
宮沢賢治『どんぐりと山猫』の別當はこれまで"周縁人物"として扱われてきた。その背景には別當がこれまでの賢治像に位置づけることが難しい存在であること、逆に別當を隠蔽化したところに賢治神話は成立してきた。本稿はテクストを大正後期の時代状況と対話させ、別當は教育が孕む重要な問題を浮き彫りにする人物であることを指摘する。それは学歴と階層の対応であり、講義録、夜学の記述のうちに当時の農村青年の「学校」への希望と諦めが見える。
1 0 0 0 OA エンシュウムヨウラン(ラン科)を東北地方に記録する
- 著者
- 合田 哲雄
- 出版者
- 日本教育制度学会
- 雑誌
- 教育制度学研究 (ISSN:2189759X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.27, pp.2-23, 2020 (Released:2022-10-07)
1 0 0 0 OA 動物園展示動物における感染症の特徴とその対策
- 著者
- 宇根 有美
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.117-123, 2014-12-22 (Released:2018-05-04)
- 参考文献数
- 19
感染症対策に関連する動物園の特性として,動物園という管理された環境下では,感染症の発見,その発生状況,病原体保有状況などが把握しやすく,感染症対策も立てやすいといった点があげられる。その一方で,生息地域や生態も異なる多種多様の動物が飼育されており,自然界では起こりえない動物種の間接的・直接的接触が,病原体に新たな宿主を提供することになったり,動物種による病原体への感受性の差が感染症の流行に結びついたりすることがある。また,飼育環境も,必ずしも自然界における生息環境を忠実に反映しているわけではなく,不適切な飼育環境が感染症発生の要因になることがある。そして,往々にして個体密度が高くなり,病原体の伝播および大量暴露を容易にし,流行のスピードを加速することもある。さらに,汚染された飼料などによる感染症の発生も起こり得る。ここでは,動物園における「感染症」について,いくつかの事例を提示して紹介する。