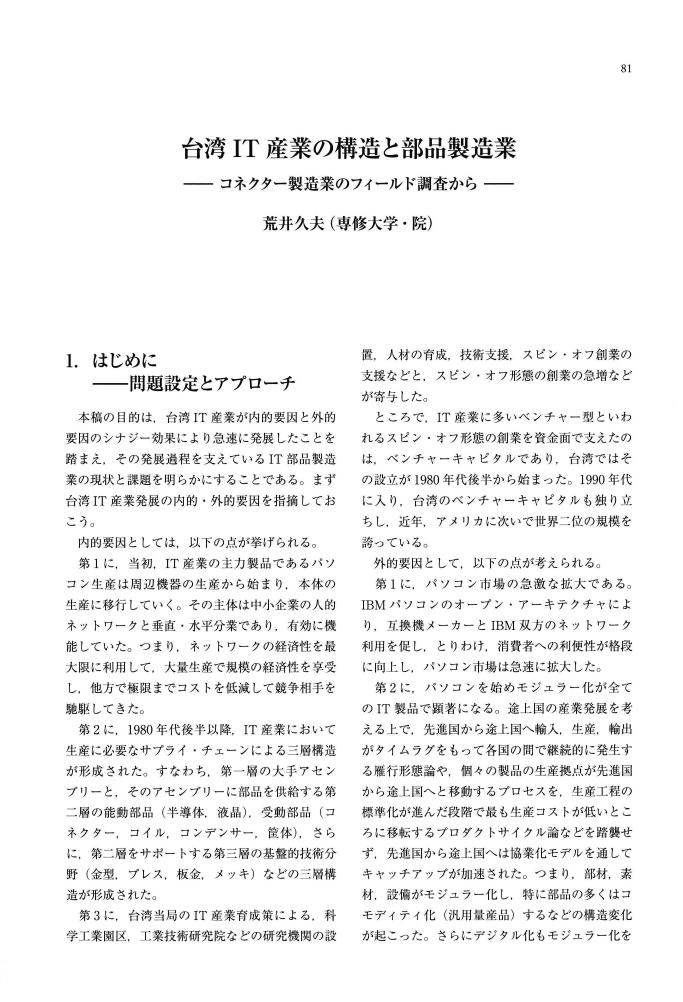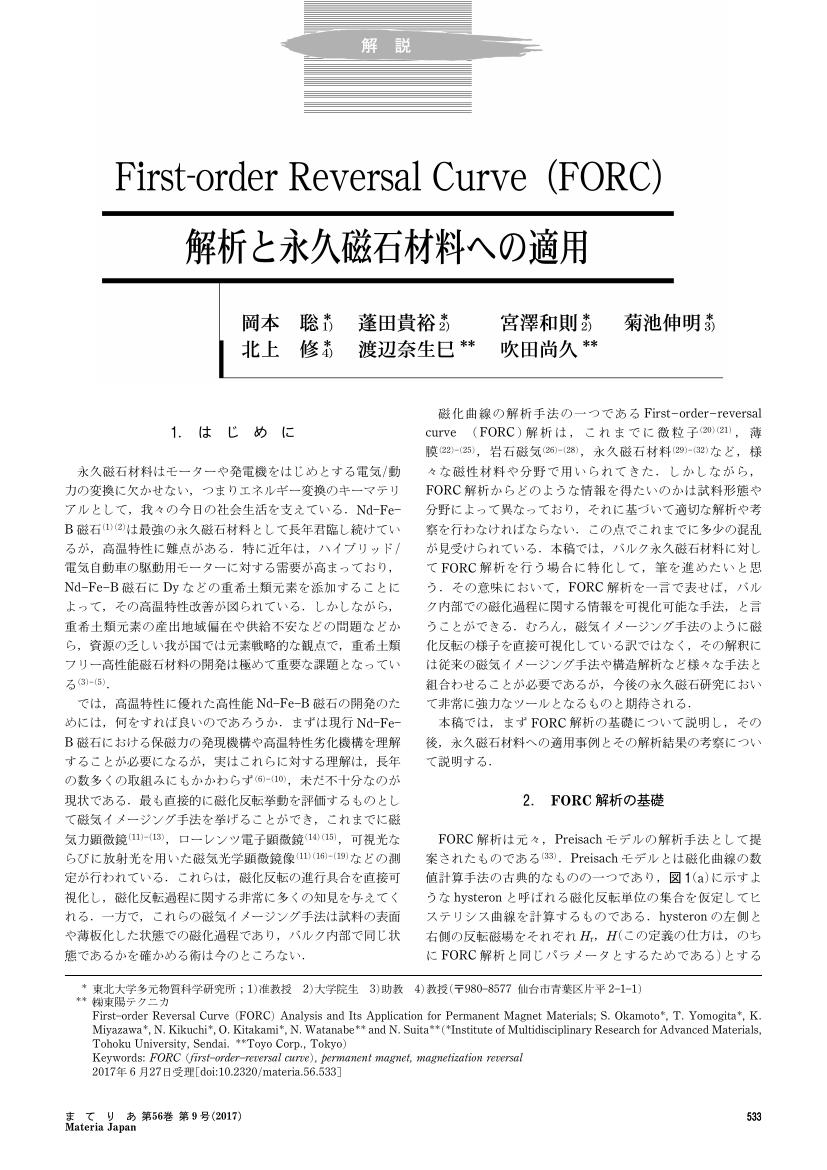1 0 0 0 OA イメージの鮮明性に関する研究(Ⅰ)
- 著者
- 上杉喬 鈴木賢男
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 生活科学研究 = Bulletin of Living Science (ISSN:02852454)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.47-59, 2001-03-01
1 0 0 0 OA キノロン系抗菌薬の基礎
- 著者
- 満山 順一
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.4, pp.287-293, 2007 (Released:2007-10-12)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
キノロン系抗菌薬(以下,キノロン)は各科領域における感染症治療薬として不可欠な薬剤である.ノルフロキサシン(NFLX)以降に登場したいわゆるニューキノロンは,それまでのナリジクス酸やピペミド酸などのオールドキノロンに比べ,抗菌スペクトル,体内動態や代謝安定性が大幅に改善し,適応菌種および適応症が飛躍的に拡大した.当初,経口剤だけであった剤型は,その後,注射薬,点眼・点耳薬,さらには皮膚外用薬へと拡大している.NFLX以外の薬剤も小児科領域への適応拡大が勘案されており,現在も多くの化合物が前臨床ならびに臨床試験のステージにある.世界的なキノロンの使用頻度の増加と共にキノロン耐性菌も増加し,臨床的に大きな問題となっているが,最近はPharmacokinetics/Pharmacodynamics(PK/PD)による解析が進み,有効性だけでなく耐性菌の抑制も議論されるようになってきている.
1 0 0 0 OA ニューラルネットワークによる地域分類法
- 著者
- 青木 義次 永井 明子 大佛 俊泰
- 出版者
- Geographic Information Systems Association
- 雑誌
- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.11-21, 1993-03-25 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 2
It is a fundamental process of urban planning to determine the planning area or to divide the area into the zones in which the tendency on urban activities at each place is similar to others. The area dividing process can be formulated as a minimization problem of the sum of the generalized distance. This problem can be numerically solved by using Hopfiled Network which is a basic model of neural network theory.Applying the proposed method to the actual urban lattice data, we can obtain divided zones.
- 著者
- 野平 慎二
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 教育科学編 (ISSN:18845142)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.59-67, 2021-03-01
- 著者
- 今村 彰生
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.115-125, 2018 (Released:2018-07-23)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2
琵琶湖淀川水系および三方五湖の固有種であり絶滅危惧種であるハスについて、2011年3月~ 2016年11月にかけて生息調査を行った。2014 年に発表した175 地点に、190 地点を新たに調査した。本研究では北西岸の調査地を重点的に増やし、これによって、ハスの生息が確認できた地点を前報の58 から135 地点に増やすことができた。また、北西部(北湖)にはハスの生息地点が多数存在することが判明した。前報と同様に、説明変数を底質、水路形状、水路の護岸の有無、水路の樹木の有無、ヨシ帯の有無、季節(春、夏、秋)とした一般化線形混合モデル解析を実施した。その結果、ハスの在/ 不在に正の影響を与える要因として、砂質の湖底の重要性が示され、礫質についても重要であることが新たに示された。これら365 地点のうち、332 地点についてハスの成魚と未成魚を区別して記録した。成魚と未成魚がいずれも在の地点が17、成魚のみの地点が41、未成魚のみの地点が65、いずれも不在の地点が209であった。成魚と未成魚の在/ 不在を応答変数行列として、上記の水路形状、水路の護岸の有無、水路の樹木の有無、ヨシ帯の有無を説明変数にPERMANOVA 解析を実施したところ、底質と護岸が有意な影響を与えていることが示された。琵琶湖西岸でのハスの在/ 不在を示した地図に、一般化線形混合モデル解析から得られたハスの生息確率予測値を、色分けして図示したところ、北湖と南湖における生息地の現状の差が明瞭に示され、本研究で新たに調査した北西部にハスの生息地が多数あり、未検出の調査地点にも生息確率が高い地点が複数あった。一方南湖では生息確率の高い地点が極めて少なく、本研究での検出地点以外でのハスの生息の見込みは少ないことが示された。本研究で得られた砂底、礫底の重要性を踏まえ、北湖に砂浜が相対的に多く残存していることも合わせて考えると、今後の砂浜の維持や河川からの砂の供給の重要性についても注目する必要がある。
1 0 0 0 OA 薄層クロマトグラフィーにおけるドラーゲンドルフ試液調製法の違いによる検出感度への影響
- 著者
- 桑山 健次 辻川 健治 宮口 一 金森 達之 岩田 祐子 井上 博之 岸 徹 角田 紀子
- 出版者
- 日本法科学技術学会
- 雑誌
- 日本法科学技術学会誌 (ISSN:18801323)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.127-133, 2005 (Released:2007-07-03)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
The effects of the various preparation procedures of the Dragendorff reagent on sensitivity for thin layer chromatography (TLC) were examined. The sensitivity to various compounds was different depending on the preparation procedures of the Dragendorff reagent. The reagent with the highest sensitivity to most of the compounds tested was the one prepared with bismuth subnitrate and concentrated hydrochloric acid. However, color spots were disappeared relatively in a short time after the reagent was sprayed on the compounds. The reagent with the second highest sensitivity was the one prepared with precipitation of Bi(OH)3 from bismuth subnitrate, although the procedure was complicated and time-consuming. Consequently, to simplify the preparation procedure of the reagent, we modified it to the procedure without precipitation of Bi(OH)3 from bismuth subnitrate. The reagent was also prepared from commercially-manufactured Bi(OH)3 or BiI3. The modified Dragendorff reagents showed almost the same sensitivity to most of the compounds tested as the one prepared with precipitation of Bi(OH)3 from bismuth subnitrate, and would be useful for practical TLC analysis.
1 0 0 0 OA オリゴ糖の特性と生理効果
- 著者
- 菅原 正義
- 出版者
- 財団法人 日本ビフィズス菌センター
- 雑誌
- ビフィズス (ISSN:09142509)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1-12, 1993 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 51
1 0 0 0 OA 台湾IT産業の構造と部品製造業 コネクター製造業のフィールド調査から
- 著者
- 荒井 久夫
- 出版者
- アジア経営学会
- 雑誌
- アジア経営研究 (ISSN:24242284)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.81-90, 2009 (Released:2019-01-01)
- 参考文献数
- 16
心筋トロポニンは急性心筋梗塞などの心筋障害の指標として利用されている。わずかなトロポニン濃度の変化は軽微な心筋障害の反映と推測されるが、変化の機序や要因は明らかではなく、未解明のトロポニン調整機構に関連している可能性がある。本研究では健常人におけるトロポニンI、T 濃度、および関連する動脈硬化指標や血液学的指標などを測定し、さらにトロポニン発現を調節するnon-coding RNAに着目してエピゲノム因子の探索を行う。候補となる指標の有用性を検証しつつ、最終的にはトロポニン検出の意義解明を目指す。本研究の成果は心疾患の早期発見や治療に結びつき、医療費削減と健康寿命延伸への貢献が期待される。
1 0 0 0 OA EVALUATING POSITIVE EFFECTS OF LEISURE FROM A LIFE-COURSE PERSPECTIVE: A LITERATURE REVIEW
- 著者
- Yuta TAKIGUCHI Mariko KIKUTANI Mie MATSUI
- 出版者
- Psychologia Editorial Office
- 雑誌
- PSYCHOLOGIA (ISSN:00332852)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-B027, (Released:2023-04-21)
- 参考文献数
- 125
- 被引用文献数
- 1
This article discusses the psychological impact of leisure across a lifetime using a life-course perspective, which assumes that people’s experiences at earlier life stages shape their following developmental trajectories. Since leisure activities are part of one’s lifestyle, adopting this perspective to leisure research is invaluable. By reviewing a variety of research, the article discusses 1) the progress of psychological leisure research and the impact of leisure on subjective well-being and cognitive functioning, 2) transitions in leisure and their relationship from a life-course perspective, and 3) the benefits related to the accumulation of leisure activities across the lifespan. The present review concludes that positive psychological achievement (e.g., self-worth, affirmation, and self-realization) and cognitive foundation (e.g., high levels of basic cognitive skills) shaped through leisure participation in early life stages help overcome challenges in later stages (i.e., successfully adapt to psychological vulnerability and cognitive decline in old age).
- 著者
- 池亀 彩
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION FOR SOUTH ASIAN STUDIES
- 雑誌
- 南アジア研究 (ISSN:09155643)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.15, pp.142-164, 2003-10-31 (Released:2011-03-16)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 OA オーヒンレック写本と十字軍
- 著者
- 酒見 紀成
- 出版者
- 広島工業大学
- 雑誌
- 広島工業大学紀要. 研究編 (ISSN:13469975)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.37-42, 2014-02
My impression of the forty-four works included in the Auchinleck manuscript is that the medieval period was the period of the Crusades in the literal sense of the word. So I searched the manuscript for the keyword “Saracen,” spelled Sar(r)asin, Sar(r)azin, or Sar(r)aʒ in, and found it in fourteen works. This figure is significant because in this manuscript seventeen items out of forty-four are religious texts. Next, in each item I inspected the context in which the Crusades are referred to. Finally, Turville-Petre's opinion, expressed in his England the Nation: Language, Literature, and National identity 1290-1340 (1996), that this manuscript was ordered by the Beauchaump family is presented in a favorable light.
- 著者
- 西川 朋美 青木 由香
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.177, pp.47-61, 2020-12-25 (Released:2022-12-26)
- 参考文献数
- 26
本稿では,日本生まれ・育ちで日本語を第二言語とする (JSL) 小学4~6年生 (n=122),及び同学年の日本語モノリンガル (Mono)(n=427) を対象に,格助詞「が」「を」「に」「で」の産出をイラスト付の記述式テストを用いて調べた。テストは,各格助詞の複数の用法や語順交替アイテムなどが含まれ,計73アイテムである。分散分析の結果,合計点において,JSLとMonoの間に差が見られた。また,合計点が最下層に位置づけられる子どもの割合は,JSLはMonoの2~5倍であった。詳細に目を向けると,JSLとMonoの得点差が顕著に見られるのは,名詞がいずれも有情物の場合の主格「が」と対格「を」・与格「に」の語順交替のアイテム群であった。これらのアイテムは,JSL・Mono両方にとって難易度が上がるが,特にJSLのつまずきが大きいことが分かった。
1 0 0 0 OA 1.粘膜面におけるバリア機能と免疫恒常性の維持に果たすM細胞の役割
- 著者
- 石原 成美 小林 伸英 長谷 耕二
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.171-178, 2018 (Released:2018-05-17)
- 参考文献数
- 34
1 0 0 0 OA 二酸化炭素の鉛直プロファイルを現地観測するドローンシステムの試作開発と飛行試験
- 著者
- 間所 洋和 井上 誠 永吉 武志 千葉 崇 芳賀 ゆうみ 木口 倫 佐藤 和人
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.37-44, 2020 (Released:2020-02-15)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1 1
This paper presents a novel drone system used for in-situ measurement of carbon dioxide (CO2), which is one of greenhouse gases. To obtain a vertical profile of atmospheric CO2 concentration, a Non-Dispersive Infrared (NDIR) analyzer was equipped on an off-the-shelf industrial drone. We designed and assembled an original mount which consists of carbon plates, hollow aluminum pipes, and resinous adapters created using a 3D printer. We obtained vertical CO2 profiles up to the 500m level through a flight test of five different dates after getting the flight permissions at an altitude of more than 150m above the ground and Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. It is shown that CO2 concentration generally increases with altitude, though the feature of CO2 profiles varies with observation dates. Based on the five profiles from September 2017 to January 2018, we revealed a seasonality of CO2 concentration over Akita. We suggest that this system is useful for in-situ CO2 measurement and enables to conduct frequent and easy observations.