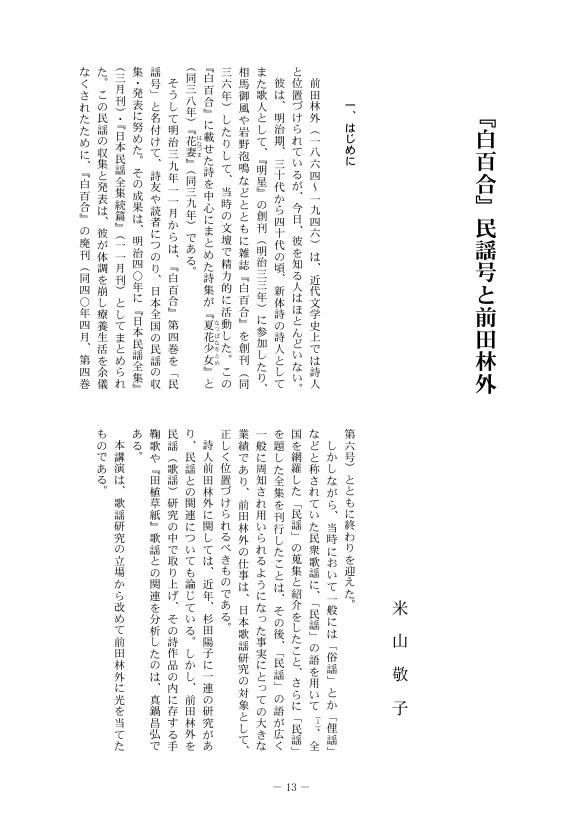1 0 0 0 OA 〈講演〉『白百合』民謡号と前田林外
- 著者
- 米山 敬子
- 出版者
- 日本歌謡学会
- 雑誌
- 日本歌謡研究 (ISSN:03873218)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.13-20, 2019-12-31 (Released:2021-03-31)
1 0 0 0 OA 婚姻状態・子どもの有無別にみた社会関係資本のニーズと格差
- 著者
- 喜多 加実代
- 出版者
- 福岡教育大学
- 雑誌
- 福岡教育大学紀要. 第二分冊, 社会科編 = Bulletin of University of Teacher Education Fukuoka. Part II, Social sciences (ISSN:02863227)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.17-27, 2022-03-10
1 0 0 0 OA 安楽死とその背景についての覚書
- 著者
- 金 永晃
- 出版者
- Research Society of Buddhism and Cultural Heritage
- 雑誌
- 佛教文化学会紀要 (ISSN:09196943)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.10, pp.l48-l58, 2001-10-10 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 死をめぐる自己決定について : 尊厳死と安楽死と
- 著者
- 五十子 敬子
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.94-99, 1998-09-07 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 40
19世紀後半に英国で、安楽死法に関する問題提起がなされた。日本でもすでに1882年(明治15年)に安楽死法の可否をめぐる議論が提起されている。本論文はそうした新資料の紹介を始めとして、死をめぐる自己決定について、各国の歴史的展開および現況を概観するものである。現代、安楽死論は、尊厳死論に移行する形で広くとりあげられるようになった。そこで本稿では、(1)尊厳死にかかわる問題(2)安楽死法の是非(3)今後の課題と提言に分け、(1)では現代医療が生み出した尊厳死への対応について外国と日本を比較する。(2)では外国の現状を紹介し、日本の判例、学説を検討し、安楽死法の是非を考察する。(3)では今後の日本における意思表示のあり方について提言することとする。
1 0 0 0 OA オーストラリアにおける自発的幇助自死の法制化の進展と法制度の特徴
- 著者
- 南 貴子 Takako Minami
- 出版者
- 香川県立保健医療大学
- 雑誌
- 香川県立保健医療大学雑誌 = Journal of Kagawa Prefectural University of Health Sciences (ISSN:18841872)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.19-27, 2022-03-18
オーストラリアでは,2017 年にビクトリア州で安楽死を認める「自発的幇助自死法(Voluntary Assisted Dying Act )」が成立した.2019 年には,西オーストラリア州において,さらに2021 年には,タスマニア州と南オーストラリア州においても同様の法律が成立した.それらの法律(以下VAD法と総称する)では,各州に住む18 歳以上で,意思決定能力があり,耐え難い苦痛を抱える,余命の限られた末期患者に対して,自ら命を絶つために医師に致死薬を要請する権利が認められる. 1995 年には,オーストラリア・北部準州において,世界で初めて「医師による患者の積極的安楽死並びに自殺幇助」を認めるRights of the Terminally Ill Act 1995 (NT)(ROTTIA )が制定された.しかし,ROTTIA を無効にする連邦法Euthanasia Laws Act 1997 (Cth) の成立によって,施行後9 か月でその効力を失った.その後,多くの安楽死法案が各州の議会に提出されたが,議会を通過しなかった.ROTTIA の無効後,20 年を経てビクトリア州でVAD 法が成立した. ビクトリア州では,患者本人による致死薬の自己投与を原則とすること,意思決定能力を持っていること,医師から自発的幇助自死(VAD)についての話を始めるのを禁じることなど,厳しい制限が設けられた.本稿では,オーストラリアの4 州で成立したVAD法の特徴を比較分析し,VAD の法制化の進展と法制化に伴う課題を明らかにする. In Australia, the state of Victoria passed the Voluntary Assisted Dying Act (“VAD Act ”) in 2017, which allows terminally ill patients to avail of physician-assisted death using a lethal substance. Victoria’s enactment of the law was followed by the passage of similar laws in states of Western Australia in 2019, and Tasmania and South Australia in 2021. According to each state’s VAD legislation, if one has decision-making capacity regarding VAD and is suffering intolerably from an advanced and progressive medical condition expected to cause death within the prescribed timeframe, residents 18 years and older are allowed the right to access VAD. In 1995, the Northern Territory of Australia was the first in the world to legislate the Rights of the Terminally Ill Act 1995 (NT) “( ROTTIA”), which allows physician-assisted voluntary euthanasia or assisted suicide. However, it was in effect only for nine months until the Commonwealth’s enactment of the Euthanasia Laws Act 1997 (Cth) nullified the territory’s legislation on VAD. After two decades and numerous unsuccessful attempts by each state to pass the VAD legislation since the invalidation of ROTTIA , Victoria finally passed its VAD Act . Victoria’s VAD Act establishes rigorous safeguards, including the requirement of patient’s selfadministration of the lethal substance by default, sound decision-making capacity as the eligibility criteria, and prohibition of medical practitioners from initiating discussion about VAD with their patients. This paper clarifies the legislative progress and the issues surrounding VAD legislation in Australia through a comparative analysis of the characteristics of VAD legal systems in the four Australian states.
1 0 0 0 OA ナチス「安楽死」計画への道程 ―法史的・思想史的一考察―
- 著者
- 佐野 誠
- 出版者
- 浜松医科大学
- 雑誌
- 浜松医科大学紀要. 一般教育 (ISSN:09140174)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-34, 1998-03-30
In der folgenden Arbeit handelt es sich um eine Betrachtung der "Euthanasieaktion"der NSDAP und ihrer rechts- und geistesgeschichtlichen Hintergründe. Euthanasie leitet sich von dem griechischen Begriff euthanatos, d.h. dem schönen Tod her. Die NSDAP verstand jedoch unter "Euthanasie" die "Vernichtung lebensunwerten Lebens". Im Namen des "Gnadentodes" haben Hitler und seine Helfer in den Jahren 1939-1945 die schwer beeinträchtigten Geisteskranken und die behinderten Kinder getötet. Insgesamt 125, 000 Menschen sind durch die "Euthanasieaktion" ermordet worden, darunter 100,000 Bewohner von Heil- und Pflegeanstalten, 20,000 Anstaltsinsassen in den besetzten Gebieten Polens und der Sowjetunion und 5, 000 behinderte Kinder. In der vorliegenden Abhandlung wird versucht, das Wesen der "Euthanasieaktion"und den Einfluß der Rassenhygiene, der Erblichkeitslehre und der Wirtschaftskrise nach dem ersten Weltkrieg auf die "Euthanasieaktion"zu erklären.
1 0 0 0 OA 「死ぬ権利」はフィクションか : 安楽死の是非をめぐって
- 著者
- 鎌田 学
- 出版者
- 弘前学院大学文学部
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:13479709)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.12-18, 2004-03-25
1 0 0 0 OA 「生きる権利」と「死ぬ権利」は背中合わせか?
- 著者
- 秋葉 峻介
- 出版者
- 武蔵野大学通信教育部
- 雑誌
- 人間学研究論集 = Bulletin of human studies (ISSN:21867267)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.63-73, 2021-03-10
1 0 0 0 OA 幼児期におけるルール取得の2つの水準
- 著者
- 石川 由香里
- 出版者
- 活水女子大学
- 雑誌
- 活水論文集 = Kwassui Bulletin (ISSN:24348015)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.143-155, 2021-03-31
- 著者
- 柴田 勝二
- 出版者
- 山口大学
- 雑誌
- 山口国文 (ISSN:03867447)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.6-17, 1992
1 0 0 0 OA プレギャバリン・ガバペンチンの本当の作用機序
成熟ラットから後根付き脊髄スライスを作成し、脊髄後角細胞からホールセルパッチクランプ記録を行った。そして、後根の電気刺激で誘発される単シナプス性興奮性シナプス後電流に対するプレガバリンやガバペンチンの作用を検証した。これらの薬物は単シナプス性興奮性シナプス後電流の大きさを減少させなかった。これらの結果から、プレガバリンやガバペンチンは臨床濃度において一次求心性線維終末からのグルタミン酸放出に影響しないことが明らかとなり、これらの薬物の鎮痛作用は従来言われていたような一次求心性線維終末の電位依存性カルシウムチャネルの抑制によるシナプス前抑制ではないことがわかった。
1 0 0 0 強磁場による化学反応制御
本研究の目的は、(1)先に見いだした有機光化学反応に対する10Tクラスの強磁場効果の機構の解明、(2)さらに強磁場による新しい化学反応制御の可能性を模索することにある。(1)では、フェナントレン(Phen)とジメチルアニリン(DMA)をメチレン鎖で連結した連結化合物(Phen-(CH_2)_<10>-DMA)のエキサイプレックスケイ光の強磁場効果をナノ秒レーザー分光法により研究し、2T以上の磁場ではΔg機構による磁場効果が起こることが解明された。またアントラキノン(AQ)にメチレン側鎖をもつ誘導体(AQ-CO_2-(CH_2)_<n-1>-CH_3)のミセル中の光半により生成するラジカル対の強磁場降下のメチレン鎖長依存性、ミセルの種類の依存性をレーザー閃光法により検討したところ、δg機構による磁場効果が強磁場中で起こることが解明された。(2)では、金属銅と硝酸銀水溶液などの金属と水溶液系の酸化還元反応により生成する金属樹に対する強磁場効果を検討した。銅棒(5Φ X 250mm)と硝酸銀水溶液からの銀樹の生成反応(Cu+2Ag^+→Cu^<2+>+2Ag↓)では、金属樹の生成が磁場勾配により顕著な影響を受ける。すなわち強磁場中では銀樹がほとんど生成せず磁場の弱い箇所で主に生成することが明らかになった。この新しい磁場効果は、常磁性イオンである銅のイオンが勾配磁場効果により磁場に引き寄せられるためであることが解明された。また、反磁性結晶の成長が磁場配向するという新しい現象を見いだした。以上の研究から、「強磁場反応化学」というべき新分野の開拓の端緒を得ることができた。
1 0 0 0 OA いわゆる“磁石石”中の強磁性鉱物の磁気特性
- 著者
- 大川 真紀雄 下田 健士朗 浦谷 勇貴
- 出版者
- 一般社団法人日本鉱物科学会
- 雑誌
- 日本鉱物科学会年会講演要旨集 日本鉱物科学会 2014年年会
- 巻号頁・発行日
- pp.49, 2014 (Released:2019-03-20)
強い磁性を帯びた岩石として知られる、山口県萩市「須佐高山の磁石石」(斑レイ岩)、島根県益田市「松島の磁石石」(石英斑岩)、和歌山県紀の川市「龍門山の磁石岩」(蛇紋岩)の試料を採取し、SQUID磁束計を用いて岩石中に含まれる強磁性鉱物の磁気特性の評価を行った。須佐高山の磁石石中の強磁性鉱物はチタノマグネタイトで、イルメナイトラメラが析出している。龍門山の磁石岩中の強磁性鉱物はクロム鉄鉱-ヘルシン石系列の固溶体でラメラ状の磁鉄鉱が認められる。松島の磁石石にはチタン鉄鉱のみが認められ、磁鉄鉱(系列)は見つからなかった。本研究で得られた磁石石中の磁性鉱物の持つ磁気特性は天然磁石のそれには及ばない値であった。
細胞から動物に至るまで自然界において,ひいては人間社会においても,生物の個体同士が互いに影響を及ぼし合った(相互作用した)結果として,その集団に秩序ある振る舞いが自発的に形成される現象(自己組織化現象)は様々に見られる.このような自己組織化現象は多様であるが,そこに通底する原理や法則を探究するため,相互作用する粒子集団の数理モデルであるSwarm oscillatorモデル(SOモデル)を解析する.SOモデルは,単一のモデルながら多様な空間的なパターンが生じることが判っている.よってSOモデルの詳細な解析により,自己組織化現象に潜む一般的な原理が見いだされることを期待している.
1 0 0 0 太宰治「水仙」論 : 「僕」というナルキッソスの悲劇
- 著者
- 鈴木 杏花
- 出版者
- 明治大学大学院
- 雑誌
- 文学研究論集 (ISSN:13409174)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.111-122, 2015
1 0 0 0 OA 強磁場中の有機化学
- 著者
- 谷本 能文 藤原 好恒
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.413-422, 1995-05-01 (Released:2009-11-16)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 17 18
Effects of high magnetic field (<14 T) on the primary process of organic photochemical reactions and related phenomena are reviewed. With increasing a magnetic field, lifetimes of triplet radical pairs in micellar solution and triplet biradicals in homogeneous solution increase significantly, reach their maximum values at ca. 2 T, and then decrease gradually up to 14 T. These results are interpreted in terms of the radical pair mechanism. The effects at low field are attributable to the reduction of spin transitions due to the isotropic and anisotropic hyperfine interaction. The inversion of the lifetime is attributable to the enhancement of spin relaxation induced by the anisotropic g-value.
1 0 0 0 OA 靭帯修復に対する変動電磁場の効果
- 著者
- 林 永昌 西村 亮平 野崎 一敏 佐々木 伸雄 廉沢 剛 後藤 直彰 伊達 宗宏 竹内 啓
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.1017-1022, 1992-10-15 (Released:2008-02-15)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 25 30
膝蓋靭帯欠損を作製したウサギに対し, 磁場強度0(対照群), 2, 10および50Gauss(G)の変動電磁場刺激を連日6時間行い, 各群に対し1週ごとに4週後まで肉眼的観察, 病理組織学的検索および力学的強度試験を行った. その結果, 欠損作製2週後における肉眼および病理組織学所見では, 対照群および2G, 10G群で, 靭帯欠損部が依然陥没していたのに対し, 50G群では出血, 壊死像はすでに消失し, 他群に比べ走行性のより一致した膝原線維が増加した. この傾向はその後も持続し, 50G群で最も早期の修復像が認められた. 一方, 引張り強度試験では, すべての刺激群で, 対照群よりいずれの週も高値を示し, かつ50Gが最も高値を示した. 以上の結果から, 50Gの変動電磁場刺激は靭帯の修復機転の少なくとも初期段階に対し, 組織学的, 力学的な促進効果を示すことが示された.
1 0 0 0 OA 上古漢語の音韻体系
- 著者
- 小倉 肇
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1981, no.79, pp.33-69, 1981-03-31 (Released:2011-02-18)
- 参考文献数
- 62
From the phonemic point of view, the author attempts to review the reconstructions of Archaic Chinese sound system by B. Karlgren, Tung T'ungho (董同和). He modifies their reconstructions and presents his phonemic interpretation of the initials and the finals in Archaic Chinese. To summarize the conculusion of his interpretation, the phonemic system of Archaic Chinese is as follows.1) Initial consonants:p-p′-b-m-t-t′-d-n-l-ç-j-ts-ts′-dz-s-z-k-k′-g-η-x-γ-2) Medials:-φ-(zero)-r-u-3) Vowels:(i)(u)e e Aa a4) Final consonants:-m-p-b-n-t-d -r-D-k-g-uη-uk-ug