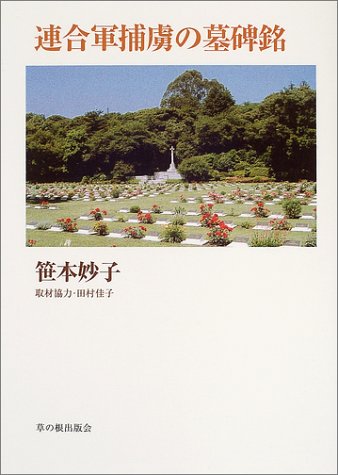1 0 0 0 OA マダイの品種改良に関する研究
- 著者
- 家戸 敬太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.3, pp.140-143, 2022-05-15 (Released:2022-05-21)
- 参考文献数
- 18
1 0 0 0 俘虜情報局・俘虜取扱の記録
1 0 0 0 OA 食品の加熱調理によるアスコルビン酸由来メイラード反応生成物の健康への影響
- 著者
- 三宅 紀子 酒井 清子 曽根 保子 伊坂 亜友美 鈴木 恵美子 倉田 忠男
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成25年度(一社)日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.75, 2013 (Released:2013-08-23)
【目的】アスコルビン酸(ASA)は調理過程において容易に酸化、加水分解されてジケトグロン酸(DKG)になる。ASA酸化生成物は反応性が高いジカルボニル構造を有することから、タンパク質とのメイラード反応が懸念される。近年このメイラード反応が生体内においても進行し、様々な疾病に関わることが報告され、飲食物由来のメイラード反応生成物の健康への影響についても関心が向けられるようになった。本研究ではASA酸化生成物と食品タンパク質との反応生成物の生体への影響について検討を行った。【方法】食品の加熱調理のモデル系として、ASA、DKG(50mM)とカゼイン(10mg/ml)との反応をリン酸緩衝液(0.1M、pH6)中、70℃で一定時間行い、ジカルボニル化合物の生成をHPLC法により定量した。また、反応生成物の高分子画分を用いて、ヒト腸管上皮モデル細胞Caco-2について増殖への影響をMTT法により、AGEレセプター(RAGE)のmRNA発現をリアルタイムRT-PCR法により調べた。【結果】DKGとカゼインとの加熱反応の過程において、数種のジカルボニル化合物の生成が確認され、その中でグリオキサール(GO)量は反応初期において高く、反応時間15分以降GO量が著しく減少した。DKGとカゼインとのメイラード反応生成物(DKG-Casein)の培養細胞への影響を調べたところ、GOおよびMGの場合よりも低濃度での細胞増殖抑制が示された。さらにCaco-2のRAGEのmRNA発現は、DKG-Casein処理により、カゼイン処理の約1.4倍に有意に上昇した。よって、食品中のASA由来メイラード反応生成物が生体に影響を与える可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 不連続変形法(DDA)による石積み擁壁の安定性に関する研究
- 著者
- 西山 哲 大西 有三 大津 宏康 西村 浩史 梁川 俊晃 亀村 勝美 関 文夫 池谷 清次
- 出版者
- 公益社団法人 地盤工学会
- 雑誌
- 地盤工学研究発表会 発表講演集 第38回地盤工学研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.1631-1632, 2003-03-05 (Released:2005-06-15)
石積み擁壁の安定性を不連続変形法(DDA)を用いて解析し,安定な構造となるためのメカニズムおよび盛土荷重に対する耐力や地震時での挙動を考察するためのデータを提供する.本研究は,特に空積み工法によって築かれた石積み擁壁を対象にし,従来の解析手法による安定性解析の困難さを示すと共に,当困難を克服するために開発された不連続変形法を紹介し,さらに当擁壁の各種地盤条件下ので安定性や地震時の挙動に関する解析結果を報告する.これにより,景観と環境に配慮し,人と地球の共生を図るための構造物としての石積み擁壁について考察する.
- 著者
- 中島 和歌子
- 出版者
- 北海道教育大学国語国文学会・札幌
- 雑誌
- 札幌国語研究 (ISSN:13426869)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.21-52, 2005
1 0 0 0 OA ウイスキーの香り
- 著者
- 増田 正裕 杉林 勝男
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.6, pp.480-484, 1980-06-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 69
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 第一回万国道徳教育会議における日本政府参加の経緯と影響関係
- 著者
- 平田 諭治
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.97-110, 1991-10-01 (Released:2017-06-01)
- 著者
- Shimpei Kato Ryo Kurokawa Fumio Suzuki Shiori Amemiya Takahiro Shinozaki Daiki Takanezawa Ryutaro Kohashi Osamu Abe
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2022-0099, (Released:2023-03-29)
- 参考文献数
- 70
Purpose: Burning mouth syndrome (BMS) is defined by a burning sensation or pain in the tongue or other oral sites despite the presence of normal mucosa on inspection. Both psychiatric and neuroimaging investigations have examined BMS; however, there have been no analyses using the neurite orientation dispersion and density imaging (NODDI) model, which provides detailed information of intra- and extracellular microstructures. Therefore, we performed voxel-wise analyses using both NODDI and diffusion tensor imaging (DTI) models and compared the results to better comprehend the pathology of BMS.Methods: Fourteen patients with BMS and 11 age- and sex-matched healthy control subjects were prospectively scanned using a 3T-MRI machine using 2-shell diffusion imaging. Diffusion tensor metrics (fractional anisotropy [FA], mean diffusivity [MD], axial diffusivity [AD], and radial diffusivity [RD]) and neurite orientation and dispersion index metrics (intracellular volume fraction [ICVF], isotropic volume fraction [ISO], and orientation dispersion index [ODI]) were retrieved from diffusion MRI data. These data were analyzed using tract-based spatial statistics (TBSS) and gray matter-based spatial statistics (GBSS).Results: TBSS analysis showed that patients with BMS had significantly higher FA and ICVF and lower MD and RD than the healthy control subjects (family-wise error [FWE] corrected P < 0.05). Changes in ICVF, MD, and RD were observed in widespread white matter areas. Fairly small areas with different FA were included. GBSS analysis showed that patients with BMS had significantly higher ISO and lower MD and RD than the healthy control subjects (FWE-corrected P < 0.05), mainly limited to the amygdala.Conclusion: The increased ICVF in the BMS group may represent myelination and/or astrocytic hypertrophy, and microstructural changes in the amygdala in GBSS analysis indicate the emotional-affective profile of BMS.
- 著者
- Kengo Kiso Takahiro Tsuboyama Hiromitsu Onishi Kazuya Ogawa Atsushi Nakamoto Mitsuaki Tatsumi Takashi Ota Hideyuki Fukui Keigo Yano Toru Honda Shinji Kakemoto Yoshihiro Koyama Hiroyuki Tarewaki Noriyuki Tomiyama
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2022-0111, (Released:2023-03-29)
- 参考文献数
- 25
Purpose: To compare the effects of deep learning reconstruction (DLR) on respiratory-triggered T2-weighted MRI of the liver between single-shot fast spin-echo (SSFSE) and fast spin-echo (FSE) sequences.Methods: Respiratory-triggered fat-suppressed liver T2-weighted MRI was obtained with the FSE and SSFSE sequences at the same spatial resolution in 55 patients. Conventional reconstruction (CR) and DLR were applied to each sequence, and the SNR and liver-to-lesion contrast were measured on FSE-CR, FSE-DLR, SSFSE-CR, and SSFSE-DLR images. Image quality was independently assessed by three radiologists. The results of the qualitative and quantitative analyses were compared among the four types of images using repeated-measures analysis of variance or Friedman’s test for normally and non-normally distributed data, respectively, and a visual grading characteristics (VGC) analysis was performed to evaluate the image quality improvement by DLR on the FSE and SSFSE sequences.Results: The liver SNR was lowest on SSFSE-CR and highest on FSE-DLR and SSFSE-DLR (P < 0.01). The liver-to-lesion contrast did not differ significantly among the four types of images. Qualitatively, noise scores were worst on SSFSE-CR but best on SSFSE-DLR because DLR significantly reduced noise (P < 0.01). In contrast, artifact scores were worst both on FSE-CR and FSE-DLR (P < 0.01) because DLR did not reduce the artifacts. Lesion conspicuity was significantly improved by DLR compared with CR in the SSFSE (P < 0.01) but not in FSE sequences for all readers. Overall image quality was significantly improved by DLR compared with CR for all readers in the SSFSE (P < 0.01) but only one reader in the FSE (P < 0.01). The mean area under the VGC curve values for the FSE-DLR and SSFSE-DLR sequences were 0.65 and 0.94, respectively.Conclusion: In liver T2-weighted MRI, DLR produced more marked improvements in image quality in SSFSE than in FSE.
- 著者
- 柳沼 孝一郎
- 出版者
- ラテン・アメリカ政経学会
- 雑誌
- ラテン・アメリカ論集 (ISSN:0286004X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.15-31, 1999 (Released:2022-09-17)
- 著者
- 大槻 順朗 乾 隆帝 野田 洋二 皆川 朋子 一柳 英隆
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.22-00112, 2023 (Released:2023-03-20)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2
海・河川域双方を生息場とする通し回遊魚3種(カマキリ,シマウキゴリ,スミウキゴリ)を対象に,海・河川水温を加味した気候変動による影響を評価した.1980年代~2010年代の水温の公共観測値を1級水系ごとに整理し,沿岸・河川河口域の月別の平均値と変動勾配を得た.水温を含む生息環境条件を説明変数とし,生息有無を評価するモデルを構築し,変数の重要度を比較した.また,構築したモデルで将来の想定水温での生息可能性を評価した.その結果,カマキリ,スミウキゴリでは2月海水温,シマウキゴリでは4月河川水温が生息確率へ最も強く影響する水温に抽出された.水温の変動勾配は海域(+1.29℃/100yrs)よりも河川河口域(+3.93℃/100yrs)で大きく,将来の想定水温では3種ともに河川水温上昇による制限がより強いことが示唆された.
1 0 0 0 機械学習を活用したエンジン吸排気系のモデリングと制御
- 著者
- 平田 光男
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.131-139, 2023-03-10 (Released:2023-03-21)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 11-Jodo-10-undecynoic acid の抗白癬作用について
- 著者
- 上野 明 松崎 悦子 百木 克夫 斉藤 伍作 酒井 純雄
- 出版者
- The Japanese Society for Medical Mycology
- 雑誌
- 真菌と真菌症 (ISSN:05830516)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.109-114, 1965-06-20 (Released:2009-12-18)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 1
11-jodo-10-undecynoic acid (K-4172) was synthesised in our laboratory from 10-undecynoic acid reacting with iodine in presence of alkaline hydroxide. Fungistatic and bacteriostatic activities of K-4172 were examined. It showed significant antifungal activities, especially against Trichophytons and Crytococcus neoformans, but it had weak antibacterial activities.In in vivo test by experimental trichophytosis on guineapigs, it showed also significant therapeutic activities at the concentration of 0.5% in alcohol solution. It is very interest that in the in vivo test 0.5% tincture of K-4172 was more effective when it was applied in combination with 10% of 2, 4, 6-tribromophenyl caproate.Interperitoneal and oral LD50 of K-4172 dissolved in olive oil were 132 and 225mg/Kg respectively and intraperitoneal LD50 of its sodium salt was 134mg/Kg. Chronic toxicity test of K-4172 on mice and rat showed both almost no side effect when it was admidistrated intraperitoneally and orally. The authers persume from these data that K-4172 is safely available for treatment of human trichophytosis.
1 0 0 0 OA 腰仙移行椎の形態的特徴と上位椎間への影響
- 著者
- 角田 信昭
- 出版者
- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.809-812, 1988-04-25 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 12
The relationship between the abnormalities of the posterior elements and anterior elements in lumbosacral transitional vertebrae, and then the relationship between disc degeneration and lumbosacral transitional vertebrae were investigated. The modified Jinnaka's classification for the abnormalities of posterior elements and the modified igh's classification for the abnormalities of anterior elements were employed for this purpose. Of 597 patients with low back pain, 82 patients (14%) presented the posterior abnormalities and 90 patients (15%) presented the anterior abnormalities. Ninety% of type I of posterior abnormalities showed normal disc in anterior, whereas only 4% of type II-IV showed normal disc. Ninety-four% of type III of posterior abnormalities had type I and type II (and III) of anterior abnormalities which were thought typical fixed transitional vertebrae. It presents a greater than normal incidence of the disc degeneration, especially posterior slip at the level of just above the lumbo-sacral transitional vertebrae.
1 0 0 0 OA 特許出願意思決定支援のための発明評価
- 著者
- 加藤 浩一郎 石井 和克 須川 成利
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.105-112, 2006 (Released:2006-06-01)
- 参考文献数
- 8
本研究は,特許出願を行うかどうかを判断するための発明評価とその項目について,調査・研究を行い,発明の内容(分野)や企業,特許戦略等にかかわらず各社共通となる評価項目とその重要性を明らかにする。また,本研究は,この結果に基づいて,発明評価をできるだけ共通的かつ客観的に行うためには具体的にどのようにすればよいかを検討する。
1 0 0 0 OA 新生涯学習制度と当院で展開する卒後教育との融合
- 著者
- 深江 航也 高原 剛 石渡 正浩
- 出版者
- 一般社団法人 千葉県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法の科学と研究 (ISSN:18849032)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.14_21-14_25, 2023-03-24 (Released:2023-03-24)
- 参考文献数
- 4
本稿では,理学療法士の卒前教育と新生涯学習制度と当院での教育システムを融合した取り組みと,今後の展望をまとめた。近年,卒前教育の違いや,コロナ禍の影響で十分な臨床実習を経験できていないことなどで新入職員の能力はスタッフ間で様々であり,十分な指導や手助けが必要な新入職員が多いのが現状である。その為,当院では独自の患者レベル分け,チェックリストを用いながら個々のスタッフの成長スピードに合わせた教育システムを展開している。課題として,On the Job Training(以下OJT)を中心とした教育システムを導入しているが指導者を担う経験者数が少なく,一人の指導者に負担が多くかかる現状に陥っている。多くのスタッフに一定水準の卒後教育を提供し,安全に理学療法を提供することができる能力を担保するために当院の教育システムと新生涯学習制度の融合は必要であると考える。
1 0 0 0 OA 南方熊楠が夢や幻の探求を通じて目指していたこと ―アイスバーグモデルを参照にしながら―
- 著者
- 唐澤 太輔
- 出版者
- 東洋大学国際哲学研究センター(「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ)事務局
- 雑誌
- 「エコ・フィロソフィ」研究 = Eco-Philosophy (ISSN:18846904)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.39-55, 2019-03
1 0 0 0 OA 理学療法士養成教育へVR(Virtual Reality)を導入した具体例の紹介
- 著者
- 山下 喬之 横山 尚宏 川元 大輔
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.517-521, 2022 (Released:2022-10-20)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
〔医学・医療系教育とVR〕近年,Virtual Reality(VR)の教育実践が盛んに行われ始め,効果検証も始まりつつあるが,理学療法教育分野での報告は少ない.〔先端技術教育と理学療法教育へのVR導入〕Information and Communication Technology(ICT)を活用した教育は,コロナ禍以降の進化も必要であり,VRは理学療法士養成教育においても業界の様々な課題を解決に導ける可能性を秘めている.〔開発と課題〕カメラとパソコン,通信環境のみで,仮想現実空間における臨床疑似体験を可能とする教材を開発した.導入コスト,映像編集・加工のスキル,通信環境や新しい教育方法に対する慣れに関する課題が挙げられた.〔実践案〕VRの導入を現実的にする提案を,既存のサービスを活用した教材配信,学習者既有のデジタル端末で視聴できる教材の制作と,簡易ゴーグルを使った方略の工夫としてまとめた.