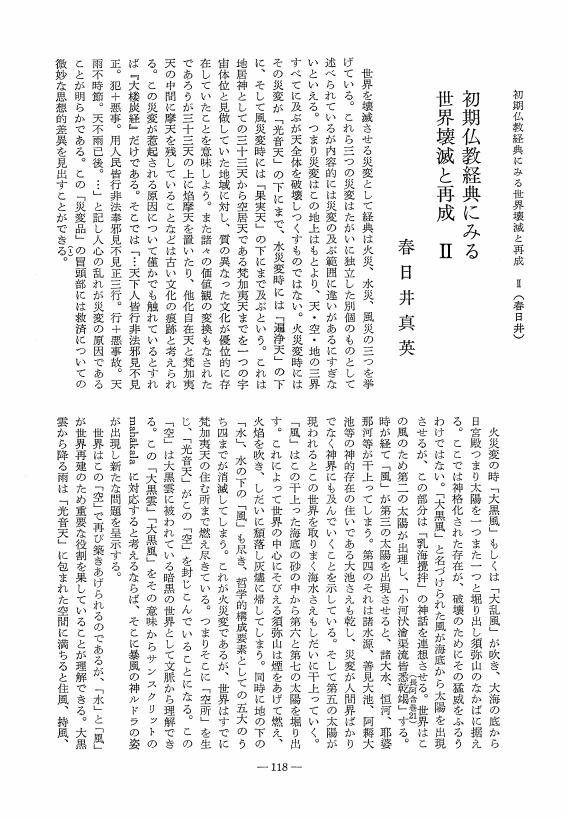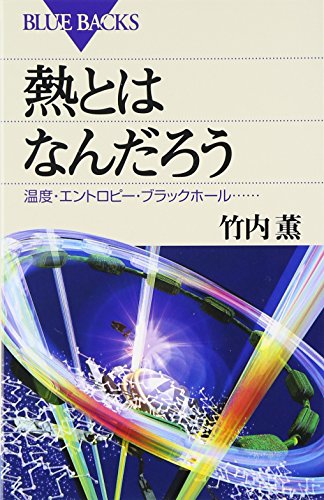- 著者
- 鈴木 慈子 古瀬 みどり
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.79-87, 2023 (Released:2023-03-29)
- 参考文献数
- 38
【目的】看護師の患者・家族とのコミュニケーションにおける曖昧さへの態度および感情対処傾向と終末期ケアへの態度との関連を明らかにする.【方法】一般病棟勤務の実務経験3年以上の看護師を対象にWEBによる自記式アンケート調査を行った.【結果】239名を分析対象とした.看護師の曖昧さへの態度得点は〈曖昧さへの統制〉〈曖昧さへの享受〉が高く,感情対処傾向は〈両感情調整対処〉が最も高かった.〈死にゆく患者へのケアの前向きさ〉と最も関連がみとめられたのは〈曖昧さへの享受〉であり,〈患者・家族を中心とするケアの認識〉と最も関連がみとめられたのは〈両感情調整対処〉だった.【結論】一般病棟に勤務する看護師の終末期ケアへの態度を高めるには,患者・家族とのコミュニケーションにおける曖昧さを肯定的にとらえ関与する態度を育み,また患者と自己の両方の感情にバランスよく対処する力を育むことの必要性が示唆された.
1 0 0 0 OA 初期仏教経典にみる世界壊滅と再成 II
- 著者
- 春日井 真英
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.118-119, 1982-12-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA ケアの倫理と社会政策 ―日本の障害者政策への示唆―
- 著者
- 鈴木 知花
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.93-104, 2021-03-30 (Released:2023-03-30)
- 参考文献数
- 35
本論文は,公私二元論によってその社会性・政治性を否定され私的領域にのみ適用可能だとされてきたケアの倫理を,公的領域における社会福祉ひいては社会福祉政策の理念を基礎づけるものとして位置づける。代表的ケア論者たちの視点から,ケアの倫理を基盤とした社会福祉政策のあり様を理念的に探究することによって,近年の日本の障害者政策がいかにリベラリズム(正義の倫理)によって特徴づけられてきたのかを明らかにする。特に障害者自立支援法とその改正法である障害者総合支援法の根底にあるのは,リベラリズムが前提とする「強い」個人像である。 本論文はリベラリズムに代わるオルタナティヴとしてケアの倫理の視座から社会福祉のあり様を見つめることによって,人間一般が種として脆弱性を内包し,相互依存的なケアの関係性の中で生きるものであることを基調とする社会福祉政策が要請されることを提起する。
1 0 0 0 OA 檜稚苗の表裏に關する一考察
- 著者
- 東 巽
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 林學會雑誌 (ISSN:21858187)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.284-293, 1934-04-10 (Released:2009-02-13)
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 OA 平和を希求し,武力に抵抗した文学青年考察 : 尹東柱,小林多喜二,鶴彬,槇村浩を中心に
- 著者
- 李修京
- 出版者
- 東京学芸大学学術情報委員会
- 雑誌
- 東京学芸大学紀要. 人文社会科学系. I (ISSN:18804314)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.99-115, 2010-01
1 0 0 0 OA 構成主義と学習環境デザイン : 大学ゼミの活動から見える拡張的な学び
- 著者
- 久保田 賢一
- 出版者
- 関西大学
- 雑誌
- 情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 (ISSN:1341156X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.3-14, 2021-01-30
本稿は,最終講義の内容をもとに,構成主義と学習環境デザインの概要について紹介をする.従来の学校教育では,個人に焦点を当て,知識やスキルを個人に蓄積することをめざすが,構成主義の学習では,個人ではなく,まわりとの関係性に焦点を当て,人や人工物との関わりのなかで,学ぶことを重視している.具体例として,アフリカの仕立屋の活動を取り上げ,徒弟が仕立屋という実践コミュニティに参加し,周辺的な仕事から次第に十全的な活動をになうようになり,一人前の仕立屋として成長していく過程を紹介する.また,活動理論は関係論的な観点から,学習者が一つの活動システムから越境して,他の活動システムとの交流を通して,発達していくプロセスを紹介する.大学のゼミにおいても,異質な活動システムとの交流が学生の学びに大きく影響していること明らかにした.構成主義の学習では,⑴主体的な知識構成,⑵状況に埋め込まれた学習,⑶異質な人との相互作用,⑷道具の活用の4つのガイドラインを提案している.
- 著者
- 三池 忠
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.121-124, 2021 (Released:2021-01-20)
1 0 0 0 クラゲ廃棄物から抽出した新規ムチン生産の企業化
- 著者
- 丑田 公規
- 出版者
- 独立行政法人理化学研究所
- 雑誌
- 産学が連携した研究開発成果の展開 研究成果展開事業 平成20年度までに募集を終了した事業 独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出推進
- 巻号頁・発行日
- 2006
しばしば大量発生するエチゼンクラゲなどは現状では、発電所や各種工場、漁業関係者に多大な除去作業負担を強いるだけの全く無価値の廃棄物である。本研究開発では、これらエチゼンクラゲなどの各種クラゲを収集して、破砕・減量化/抽出・精製の工程作業を経て有効成分を単離して、食品添加物、生分解性プラスチック、化粧品材料をはじめ、胃腸薬、点眼薬、粘液などの医療品原料として広い用途が期待されるムチンの新規な生産法を開発する。廃棄物の除去作業負担を軽減するなど環境保全に寄与するほか、天然物由来の安全な高付加価値製品の創出が期待される。
1 0 0 0 OA EDTAの重金属中毒に対する効果
- 出版者
- 金沢大学十全医学会
- 雑誌
- 金沢大学十全医学会雑誌 (ISSN:00227226)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.1476-1486, 1955-08-20
1 0 0 0 想起への希求--谷崎潤一郎『春琴抄』論
- 著者
- 林 貴裕
- 出版者
- 早稲田大学大学院教育学研究科千葉・金井・石原研究室
- 雑誌
- 近代文学 第二次 研究と資料
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.131-145, 2011-03
- 著者
- Pramod DHAKAL Akiko HIRAMA Yasuo NAMBO Takehiro HARADA Fumio SATO Kentaro NAGAOKA Gen WATANABE Kazuyoshi TAYA
- 出版者
- The Society for Reproduction and Development
- 雑誌
- Journal of Reproduction and Development (ISSN:09168818)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.522-530, 2012 (Released:2012-11-01)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 21 17
The present study was conducted to elucidate the profile of circulating gonadotropins and gonadal hormones from birth to puberty and relationship between gonadal seasonality and hormonal secretion in both sexes of Thoroughbred horses. Spring-born colts (n=6) and fillies (n=9) were blood sampled weekly from jugular vein from birth to 60 weeks of age. Circulating FSH, LH, prolactin, testosterone, progesterone, estradiol-17β, and immunoreactive (ir)-inhibin were measured by radioimmunoassay. In both sexes, the steroid hormones levels were remarkably high at birth, rapidly dropped within a week and remained at the lower levels until the start of second spring after birth. Ir-inhibin was also high during the birth, remaining lowest during winter and again increasing towards the second summer. There was an increase in FSH concentration in foals during the first summer months after birth and in the next summer, the FSH concentration along with that of LH increased significantly. The seasonal increase in circulating prolactin was remarkable even in the first year, and no differences were noted between the two summers. These results clearly demonstrated that the hypothalamo-pituitary axis is already responsive to changes in photoperiod and secrete prolactin similar to adult horses, but pituitary gonadotrophs for FSH and LH secretion is less sensitive. When the values of these hormones in the second breeding season after birth were compared with adult values of the respective sex in the breeding season, no significant differences were observed, indicating that spring-born fillies and colts have already attained the stage of puberty at the second breeding season after birth.
- 著者
- 中野 逸雄 ナカノ イツオ Nakano Itsuo
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 待兼山論叢. 美学篇 (ISSN:03874818)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.1-23, 2011-12-26
1 0 0 0 OA <講義ノート>情報処理の熱力学 (第59回物性若手夏の学校 : 集中ゼミ)
- 著者
- 沙川 貴大
- 出版者
- 物性研究・電子版 編集委員会
- 雑誌
- 物性研究・電子版
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.1-16, 2015-02
情報理論と熱力学を融合した理論, 情報熱力学について入門的な解説を行う. とくに, 測定やフィードバックなどの情報処理過程への, 熱力学第二法則や非平衡関係式の一般化について議論する. また, 情報熱力学の一つの帰結として, いわゆるマクスウェルのデーモンのパラドックスがどう解決されるかも議論する
1 0 0 0 熱とはなんだろう : 温度・エントロピー・ブラックホール……
1 0 0 0 OA 乳幼児期の難聴児における補聴器機能と装用状況に関する検討
- 著者
- 中市 真理子 廣田 栄子 綿貫 敬介 成沢 良幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.209-215, 2014-06-30 (Released:2014-11-06)
- 参考文献数
- 6
要旨: 本研究では, 全国の乳幼児補聴器適合施設に対し, 補聴器装用・機能の状況と, 補聴器選択に関して調査した。乳幼児に適合されている補聴器型は, 耳かけ型が最も多く, ベビー型の使用数は低かった。乳幼児の補聴器機能では, ボリューム固定, ハウリング抑制, 雑音低減, ワイヤレス, 指向性の順で使用されていた。常用や装用を妨げる原因にハウリング, 補聴器を嫌がる, 耳から外れやすいがあり, 補聴器の故障原因は, 汗が多かった。乳幼児の補聴器選択において, 経済的負担軽減 (障害者自立支援法: 現障害者総合支援法対応), 耳介にあった形状, ハウリング抑制機能, 装着のしやすさ, 防水性能が重視されていることが確認された。補聴器適合担当者は, 補聴器の日常使用の利便性の向上と, 発達への対応における保護者負担の軽減への要望が高かった。また, 早期難聴診断や補聴・支援に関する社会啓発と, 診断機関と療育・教育機関の情報共有の指摘も高かった。
1 0 0 0 OA 15~97歳日本人男女1006名における体肢筋量と筋量分布
- 著者
- 山田 陽介 木村 みさか 中村 榮太郎 増尾 善久 小田 伸午
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.461-472, 2007-10-01 (Released:2007-11-22)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 17 12
Although skeletal muscle mass decreases with aging, its decrease rate may differ among parts of the body. There have been few studies examining the differences in the muscle mass decrease rate between proximal and distal parts of the limbs or between the left and right legs in a large population. Bioelectrical impedance (BI) index, calculated as the ratio of the square of segment length to impedance, is linearly correlated with the muscle mass calculated by MRI (r=0.902-0.976, p<0.05, Miyatani et al., 2001) in the limb segments. The purpose of this study was to examine differences in the decrease rate of muscle mass between the proximal and distal parts of the limbs and between the upper and lower limbs in healthy Japanese. The BI index was measured in the bilateral thighs, lower legs, upper arms, and forearms of 1006 healthy Japanese men and women (aged 15-97 years). While the BI index decreased with aging in all examined parts of the body, the decrease rate was larger in the lower limb than in the upper limb, and in the thigh than in the lower leg. The percentage of people who showed a difference of more than 10 % in the BI index between the left and right lower limbs was significantly higher in the elderly than in young subjects. These differences in the decrease rate of muscle mass between limbs may be associated with decreases in physical functions in the elderly.
1 0 0 0 西ドイツにおける農地一子相続制度の研究
1 0 0 0 OA 目標設定したウォーキング介入が高齢者に及ぼす心理的影響
- 著者
- 白石 卓也 千村 洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.285-290, 2016-07-31 (Released:2016-09-24)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 1
ウォーキングに関しては高齢者においても健康増進につながる目標値が明らかとなっているが,高齢者は加齢に伴う身体機能の低下や基礎疾患等の理由のため目標を達成できない場合がある。しかし,目標達成有無における高齢者の心理機能への影響を報告した研究はほとんどない。今回,高齢者を対象に,歩数と活動量を指標として目標設定したウォーキングによる運動介入を行ない,その介入が高齢者にどのような心理機能の変化を及ぼしたのか検討した。対象は,平成27年7月から24週間継続してウォーキングによる運動介入をうけた高齢者14名(男性5名,女性9名)とした。1日平均歩数8,000歩かつ1日平均中強度活動時間20分という目標を設定し,運動介入を行なった。運動介入前と介入後24週目に心理機能の評価を行ない,その変化を比較検討した。さらに,設定した目標を達成できた群(達成群)8名および達成できなかった群(未達成群)6名に分け,さらに比較検討した。その結果,全対象者,達成群および未達成群の心理機能に介入前後で有意な変化はなかったものの,達成群では心理機能は向上する傾向があり,未達成群では主観的健康感および生活満足度は低下し,うつ評価は悪化する傾向があった。目標設定した運動介入は,目標達成できれば心理機能は向上しうるが,目標達成できなければ心理機能の低下を引き起こし健康増進の阻害因子となりうる可能性が示唆された。
- 著者
- 古賀 雄二 茂呂 悦子 有田 孝 小幡 祐司 川島 孝太 雀地 洋平 古厩 智美 藤野 智子
- 出版者
- 日本クリティカルケア看護学会
- 雑誌
- 日本クリティカルケア看護学会誌 (ISSN:18808913)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.47-56, 2018-03-01 (Released:2018-06-02)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 1
適切な診療報酬請求を行う上で,せん妄患者の明確化は不可欠である.平成28年度診療報酬改定後のせん妄評価およびせん妄ケアの現状調査を行うことを研究目的として,「急性期に密度の高い医療を必要とする状態」の患者を多くケアするクリティカルケア看護専門団体(急性・重症患者看護専門看護師,集中ケア認定看護師,救急看護認定看護師)の全会員を対象に,平成28年度診療報酬改定後のせん妄評価・ケアの現状を調査した.Web式無記名式質問紙調査を行い,単純集計と質的記述的分析を行った.対象者数1,798人,回答率9.6%,有効回答率100%であった.周術期全体で継続的に妥当性・信頼性のあるせん妄評価は行われていなかった.診療報酬請求の適切性の向上のために,せん妄評価ツールの導入に加えて,ツール評価精度の維持が重要であり,学会等を通じた教育支援を行う必要がある.また,看護必要度を通した医療経済的・政策的なせん妄評価定着への支援は,多職種連携・チーム間連携が進むせん妄ケアの共通言語化を促し,患者ケアを推進する可能性がある.
1 0 0 0 OA <論説>京都府における国会開設運動の展開 : 私擬憲法案「大日本国憲法」の成立と沢辺正修
- 著者
- 飯塚 一幸
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.2, pp.359-387, 2009-03-31
「大日本国憲法」は、国会期成同盟第二回大会前に作成された数少ない私擬憲法案であるが、関係史料が限られていて、作成者の確定、作成の経緯など、基本的な点がはっきりしていなかった。ところが稲葉家文書から発見された新史料により、一八八○年九月における筑前共愛会の和田操の宮津遊説が契機となり、同会の憲法草案の影響の下、天橋義塾社長沢辺正修が一気に書き上げたことが判明した。その後「大日本国憲法」は、丹後選出府会議員らの討議により若干の修正を加えられ印刷・配布されていった。「大日本国憲法」作成と沢辺の国会期成同盟第二回大会参加は、筑前共愛会側から言えば、同会の遊説活動の顕著な成功例である。いち早く起草した憲法草案を携え国会期成同盟第二回大会に臨み主導権を握ろうとした筑前共愛会は、九州の外に同志を得たのである。こうして沢辺正修ら京都府民権派と筑前共愛会は、坂野潤治の言う「在地民権右派」の中核を形作っていく。