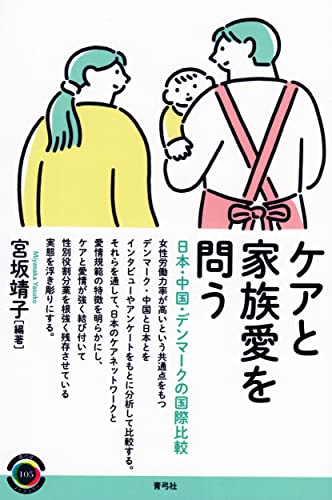- 著者
- 佐々木 加奈子
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.1-14, 2018 (Released:2018-05-19)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
東日本大震災後に開始された地域情報のアーカイブ活動には,以前から複数の問題が指摘されてきた。これに加えて,近年,多くの震災アーカイブが「あの時,どう避難したのか」という被災上の教訓の伝達に焦点を当てすぎており,その土地に生きた人々の多元的なライフストーリーが省略されているとする指摘が現れた。先行研究の分析は,しかしながら,多元的なライフストーリーの生成プロセスの理論化がまだ十分ではない。佐々木(2016)では,福島県双葉郡浪江町民に焦点をあてて多元的なライフストーリーの生成を実際に試みており,「協働」の場を設定することで,その中での相互行為の中から多元的なライフストーリーが語られうることを実証的に示している。しかし,なぜその結果が得られるのか等は明らかにされていない。本論文では,行為を演技として捉えるゴフマンの演劇論的アプローチの役割概念を用いて,その仕組みを明らかにした。協働の場では,多層的なオーディエンス構造とオーディエンス・パフォーマー間の親密な関係性によって,チームパフォーマンスが促された。その際,参加者たちは自由に自身の役割を見出すことができ,メディアが設定する避難者像から距離を取ることができ,これにより新たな語りの発現に至った。
1 0 0 0 OA 染色法によるヨコバイ類の加害部位 (口針挿入部位) の検出方法
- 著者
- 内藤 篤
- 出版者
- 関東東山病害虫研究会
- 雑誌
- 関東東山病害虫研究会年報 (ISSN:03888258)
- 巻号頁・発行日
- vol.1963, no.10, pp.44, 1963-12-10 (Released:2010-03-12)
1 0 0 0 OA 検診で発見された境界病変
- 著者
- 小石 彩 岩瀬 拓士 堀井 理絵 秋山 太
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本乳癌検診学会
- 雑誌
- 日本乳癌検診学会誌 (ISSN:09180729)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.342-345, 2015 (Released:2018-06-15)
- 参考文献数
- 26
乳癌検診で発見される病変のうち,悪性の可能性が否定できない病変に対しては穿刺による組織生検がしばしば行われる。しかし,その病理結果においても良悪性の鑑別が困難な症例をときに経験する。そのような場合に,臨床医がどのように対応すべきか明らかにすることを目的として,当院における検診後の鑑別困難症例を抽出し,病理学的所見で分類,その転帰を調べた。 2006年1年間に当院病理で針生検の診断を行った952件のうち,良悪性の鑑別が困難と診断された病変の数は30病変,そのうち検診で発見されたものは23病変であった。検体が少ない,あるいは変性しているため,確定診断が困難であったもの2例と良性病変内にDCIS が入り込んでいた1例を除外した20例(2.1%)が境界病変に相当した。その20例を病理学的に分類し,その転帰をカルテ上で調査した。境界病変のうちFEA(flat epithelial atypia)に相当する平坦型病変8例からは2例,ADH(atypical ductal hyperplasia)に相当する過形成型病変7例からは4例が後に癌と診断された。いずれもDCISか微小浸潤癌だった。境界病変からのちに癌の診断にいたる症例は確かに存在するが,慎重な経過観察をして,マンモグラフィや超音波検査で変化が出現したときに再生検すれば,早期癌の状態で診断できると思われた。
1 0 0 0 日本社会論および国際社会論からみた広島についての総合的研究
- 著者
- 広島大学総合科学部 [編]
- 出版者
- 広島大学総合科学部
- 巻号頁・発行日
- 1989
1 0 0 0 OA 浜松中納言物語を読む(前編) : 散逸首巻・巻一・巻二・巻三
- 著者
- 島内 景二
- 出版者
- 電気通信大学
- 雑誌
- 電気通信大学紀要 = Bulletin of the University of Electro-Communications (ISSN:09150935)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.395-439, 1988-12
1 0 0 0 OA 浜松中納言物語を読む(後編) : 巻四・巻五
- 著者
- 島内 景二
- 出版者
- 電気通信大学
- 雑誌
- 電気通信大学紀要 = Bulletin of the University of Electro-Communications (ISSN:09150935)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.217-250, 1989-06
1 0 0 0 OA 5p-N-3 非常に薄い膜における超伝導転移とV-I特性
- 著者
- 青峰 隆文
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 年会予稿集 28.3 (ISSN:24331155)
- 巻号頁・発行日
- pp.228, 1973-04-03 (Released:2018-03-26)
1 0 0 0 ケアと家族愛を問う : 日本・中国・デンマークの国際比較
1 0 0 0 OA 脳神経外科領域における術後脳静脈梗塞―合併症回避のためにすべきこと―
- 著者
- 中瀬 裕之 田村 健太郎 玉置 亮 竹島 靖浩 乾 登史孝 三宅 仁 堀内 薫 榊 寿右
- 出版者
- 日本静脈学会
- 雑誌
- 静脈学 (ISSN:09157395)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.157-161, 2007 (Released:2022-07-09)
- 参考文献数
- 20
当科における術後脳静脈梗塞の症例から,術後脳静脈梗塞の臨床的特徴を検討し,合併症(術後静脈梗塞)を回避するために注意すべきことについて述べる.脳外科手術中の脳静脈損傷により術後静脈梗塞を起こした自験例8症例(全手術中の0.3%),男性3例,女性5例(平均58.1歳)を対象とした.二次性静脈血栓の進展により緩徐に症状が発現してくる群(n=5)と急激に脳静脈灌流障害を起こしてくる群(n=3)の2群に分類できた.症状の発現が旱いものほど重篤な症状がみられた.外科的療法を要したものが2例,保存的に対処できたものが6例である.予後は良好が6例,軽度障害を残したものが2例であった.術後脳静脈梗塞を少なくするためには,(1)術前に静脈解剖を考慮し,重要な静脈を避けた手術アプローチの選択,(2)静脈を損傷しない手術法の工夫, (3)脳静脈損傷時の対処や術後管理など,できるかぎり静脈を温存し合併症を早期に予測し予防する努力が必要である.
- 著者
- Mei Matsuzaki Tomohiro Sasanami
- 出版者
- Japan Poultry Science Association
- 雑誌
- The Journal of Poultry Science (ISSN:13467395)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.1-7, 2022 (Released:2022-01-25)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 4
Sperm drastically change their flagellar movement in response to the surrounding physical and chemical environment. Testicular sperm are immotile; however, they gain the competence to initiate motility during passage through the male reproductive tract. Once ejaculated, the sperm are activated and promptly initiate motility. Unlike mammals, ejaculated sperm in birds are stored in specialized tubular invaginations referred to as sperm storage tubules (SSTs), located between the vagina and uterus, before fertilization. The resident sperm in the SSTs are in a quiescent state and then re-activated after release from the SSTs. It is thought that avian sperm can undergo motility change from quiescent to active state twice; however, the molecular mechanism underlying sperm motility regulation is poorly understood. In this short review, we summarize the current understanding of sperm motility regulation in male and female bird reproductive tracts. We also describe signal transduction, which regulates sperm motility, mainly derived from in vitro studies.
1 0 0 0 OA 人文学的アーバニズムとしての中心市街地再生
- 著者
- 武者 忠彦
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.337-351, 2020-12-30 (Released:2021-12-30)
- 参考文献数
- 51
地方都市における中心市街地の再生は長年の政策課題であるが,行政主導の計画や事業の多くが機能不全に陥る一方で,近年は小規模で漸進的に都市を改良していく「計画的ではない再生」の動きが注目されている.こうした変化を「工学的アーバニズム」から「人文学的アーバニズム」へのシフトとして解釈することが本稿の目的である.工学的アーバニズムとは,都市は予測・制御が可能なものであるという認識の下で,全国標準化された計画や事業を集権的な行政システムによって進めるという考え方や手法のことである.それを可能にしたのは,近代都市像の社会的共有と都市化という時代背景であった.これによって,中心市街地再生は近代化,活性化,集約化というテーマで政策的に進められてきたが,工学的アーバニズムの限界が明らかになった現在では,都市形成のメカニズムの複雑さを前提に,個々の主体が試行錯誤しながら漸進的に都市を改良し,結果的に都市の文脈が形成されていくという人文学的アーバニズムの重要性が高まっている.現在の地方都市が直面する「都市のスポンジ化」も,人文学的アーバニズムとして読み解くことで,都市形態学的な説明よりも深い洞察が得られることが期待される.そうしたアプローチは「中心市街地再生の人文学」を構想することにもつながるだろう.
- 著者
- Hanaka ISHII Masanori YAMAJI Haruki NATSUKAWA Tomohiro ICHINOSE
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- ORNITHOLOGICAL SCIENCE (ISSN:13470558)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.227-234, 2022 (Released:2022-08-13)
- 参考文献数
- 39
The Daurian Redstart Phoenicurus auroreus has expanded its breeding distribution in recent years and now breeds in Japan, previously only part of its wintering range. We analyzed the breeding habitat selection of the population at the nest and territory scale in the Kirigamine Highlands, Nagano, Central Japan. At the nesting scale, the birds chose buildings frequently occupied by humans, while at the territory scale, they avoided sites in larger built-up areas. Our findings demonstrate that the breeding habitat selection of Daurian Redstart is influenced by environmental factors at both nest and territory scales.
1 0 0 0 OA 男女別にみた認知症高齢者の病前性格とBPSDの関連
- 著者
- 野末 波輝 薬袋 淳子 成 順月
- 出版者
- 社会福祉法人 認知症介護研究・研修東京センター
- 雑誌
- 認知症ケア研究誌 (ISSN:24334995)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.1-11, 2020 (Released:2020-06-10)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
【目的】認知症高齢者の病前性格とBPSDとの関連を男女別に明らかにする。【方法】病院に入院、または施設に入所しているBPSDを有する認知症高齢者と、そのキーパーソン216名を対象に、質問紙調査を実施した。BPSD12項目は担当の職員または認知症認定看護師に記入を依頼し、当事者の病前性格は日本語版Ten Item Personality Inventoryを用いて外向性、協調性、勤勉性、神経症傾向、開放性の5つに分類し、キーパーソンから回答を得た。男女別に属性とBPSD12項目との関連をカイ二乗検定で調べ、病前性格とBPSD12項目との関連はスピアマン相関係数を算出し調べた。BPSDの有無を従属変数とし、単変量解析でp<0.1の変数を独立変数として多重ロジスティック回帰分析を行った。【結果】認知症高齢者121名に関する回答が得られた(回収率56%)。多重ロジスティック回帰分析の結果、男性では外向性傾向の性格はうつ(OR=0.54:95%CI 0.36-0.81)や不安(0.75:0.57-0.97)になりにくく、勤勉性傾向の性格は、うつ(0.73:0.53-0.97)になりくいが、脱抑制(1.88:1.32-2.67)を起こしやすく、協調性傾向の性格は食異常(1.60:1.17-2.12)、神経症傾向は易刺激性(1.47:1.10-1.97)を起こしやすく、開放性傾向の性格はうつになりにくかった(0.45:0.21-0.95)。女性では、外向性傾向の性格は易刺激性(1.27:1.06-1.52)、協調性傾向の性格はアパシー (1.68:1.24-2.26)と食異常(1.49:1.15-1.92)を起こしやすく、神経症傾向の性格は易刺激性(1.26:1.03-1.53)、勤勉性の性格は脱抑制(1.39:1.10-1.76)を起こしやすかった。【結論】男女別における病前性格とBPSDの関連が示唆され、BPSDの各症状に対する予防的取り組みや対処方法など検討できると考える。
1 0 0 0 OA 犬の歩行評価に活かす相分け概念の導入とその応用
1 0 0 0 OA 根菜収穫機構に関する研究 (第1報)
- 著者
- 古谷 正
- 出版者
- The Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers
- 雑誌
- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.587-592, 1980 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 17
根菜の収穫作業は, 人力手作業を主体とする重労働にたよっており, 機械化技術の開発が望まれている。収穫の機械化研究は, 一方ではトレンチャーやサブソイラなど既存の機械利用の多目的化により, 他方では欧米諸国で開発された根菜収穫機の改良研究という方向で検討が進められている。収穫の機械化がいづれの方向で進むにせよ, まず, 根菜収穫の基礎事項として根菜の物理性を明らかにしておく必要がある。本報では, 根菜の物理性を明らかにするとともに, わが国の農業事情下でも適応した小型でしかも構造的に単純な根菜収穫機構を開発し, 収穫機の作物に対する適応性を解析した。第1報では根菜の物理性に基づく問題を提起し, 第2報では平行した2枚の矩形板により根菜を周囲の土ごと収穫する根菜収穫機構について解析, 第3報では小型円板による根菜収穫の模型実験について解析, 第4報では試作した新しい根菜収穫機の性能を解析した結果を報告する。
1 0 0 0 OA ABS車輪速センサーケーブルへのグロメット一体成形技術の適用
1 0 0 0 OA 坂口安吾初期短篇小説についての考察 : 不安定な身体をめぐって
- 著者
- 大原 祐治 Yuji Ohara
- 出版者
- 学習院大学文学部国語国文学会
- 雑誌
- 学習院大学国語国文学会誌 (ISSN:02864436)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.78-88, 1996-03-15