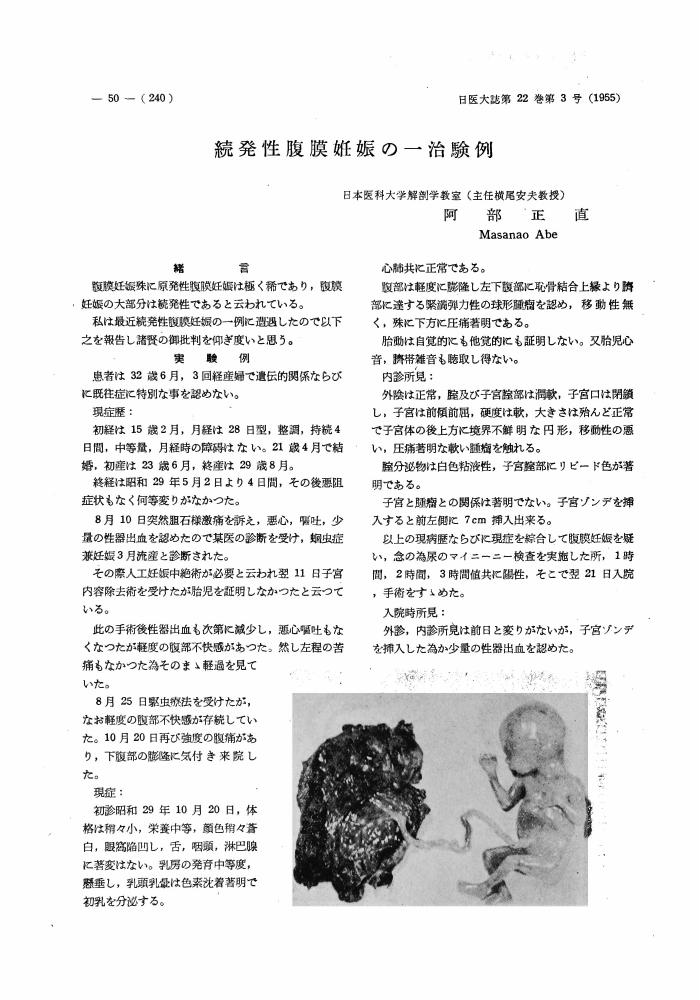1 0 0 0 OA 続発性腹膜妊娠の一治験例
- 著者
- 阿部 正直
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.240-242, 1955-03-15 (Released:2010-10-14)
1 0 0 0 OA シロアリの生活と水
- 著者
- 神原 広平
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1, pp.1_011-1_013, 2012 (Released:2014-05-15)
- 参考文献数
- 14
- 著者
- Takayuki NOZAKI Motohiko ISAKA
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE Transactions on Communications (ISSN:09168516)
- 巻号頁・発行日
- vol.E105.B, no.8, pp.894-905, 2022-08-01 (Released:2022-08-01)
- 参考文献数
- 88
- 被引用文献数
- 2
Low-density parity-check (LDPC) codes are widely used in communication systems for their high error-correcting performance. This survey introduces the elements of LDPC codes: decoding algorithms, code construction, encoding algorithms, and several classes of LDPC codes.
1 0 0 0 大川市誌
- 著者
- 大川市誌編集委員会 編
- 出版者
- 大川市
- 巻号頁・発行日
- 1977
1 0 0 0 OA 井上準之助論叢
- 著者
- 井上準之助論叢編纂会 編
- 出版者
- 井上準之助論叢編纂会
- 巻号頁・発行日
- vol.一, 1935
1 0 0 0 OA [論説] 大日本帝国下における競馬 --前田長吉を事例に--
- 著者
- 高橋 一友
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科 社会システム研究刊行会
- 雑誌
- 社会システム研究
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.1-17, 2021-03-17
1 0 0 0 OA CLPを用いたナース・スケジューリング問題における実用解の効率的探索
- 著者
- 西川 理規 松井 藤五郎 大和田 勇人
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第23回 (2009)
- 巻号頁・発行日
- pp.2H32, 2009 (Released:2018-07-30)
近年、看護の質と生活の質の両方のバランスの取れた勤務表を作成することを目指したナース・スケジューリングの研究が多くされているが、数多い解から現場で利用出来る解を見つけることは難しい。そこで本研究では、制約論理プログラミングを用いて、各ナースの出来る仕事やスキルなどの情報を定義し、それらを制約として探索戦略に組み込むことにより、対象となる現場に応じた実用的な勤務表を効率的に作成することを可能にした。
1 0 0 0 OA 口コミの効果を通じてみる霊場の脱聖地化と広域化 ――富山県「穴の谷霊場」を事例に――
- 著者
- 鈴木 晃志郎 島田 章代 伊藤 修一
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.50-65, 2018-06-28 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 35
対象者が未知の財やサービス,製品にアクセスするときに依拠するのがいわゆる口コミ(WoM)である。観光行動もサービスを選択・消費する消費行動の一つであり,リピート率の向上や顧客満足度の上昇に及ぼすWoMの効果に注目した分析の対象となりうる。そこで本研究は富山県の湧水池「穴の谷霊場」をとりあげ,来訪者の特性を分析するとともに,入込客数の維持にWoMがもたらす効果を調査した。半構造化インタビューを交えたアンケート調査により来訪者86人の類型化を行いその動機を分析したところ,病気治療,健康維持,味の良さでカテゴリー化される一方,当初の霊場としての場所性はその影響力を大きく失っていた。また来訪者の76%が信頼のおける肉親や知人からのWoM情報を最初の来訪のきっかけに挙げ,WoM研究の知見を裏付けた。開祖が世を去って40年,穴の谷は宗教的な聖地としてよりも,霊水を求める一種の自然信仰に支えられた観光地へと変容を遂げており,WoM効果は観光客数の維持に少なからず貢献していると考えられる。
1 0 0 0 OA ラットの末梢神経再生に及ぼす鍼通電刺激の影響
- 著者
- 井上 基浩
- 出版者
- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.391-406, 2003-08-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 4 5
This study was undertaken to examine the effects of electro-acupuncture with direct current on peripheral nerve regeneration. Fifty-five 7 month old male rats were used in the present study. Sciatic nerve of each rat was crushed at the thigh, then the subject were divided into four groups as Cathode distal group (n=15), Anode distal group (n=14), Sham group (n=13), and Control group (n=13) . In the Cathode distal group, an insulated acupuncture needle which was inserted at lcm distal to the injured site was used as cathodal electrode, while a needle inserted at lcm proximal to the lesion was used as anodal electrode. In the Anode distal group, the needle at lcm distal and pro. ximal to the lesion were used as the anodal and the cathodal electrodes respectively. In the Sham group, no electrical stimulation were given to the insulated needle inserted at the same site as the aforementioned groups. In the Control group, no operation was given after crush injury. Regeneration of the sciatic nerve were evaluated with the number and the latency of the evoked EMG recorded at 12 sites in the foot, the behavioral test score (BTS) at 1, 2, 3, and 4 week after crush injury, weight ratio of the tibialis anterior and morphological study at 4 weeks after crush injury. Every kind of evaluation indicated that regeneration of the peripheral nerve was faster in the Cathode distal group than those in the other group. In the Anode distal group, the number of the evoked EMG and BTS were significantly lower than those in the Control group with tendency of longer latency and lesser muscle weight ratio. We suggested that electro-acupuncture with cathode distal orientation accelerated regeneration of the peripheral nerve after crush injury, while anode distal orientation delayed the regeneration. The electro-acupuncture with cathode distal orientation might be one of the useful treatment having advantage to perform deeper insertion with minimal invasion.
1 0 0 0 OA 現代朝鮮語の補助動詞 -(a/e) noh- : [V1 + PUT]研究
- 著者
- 黒島 規史
- 出版者
- 神田外語大学韓国語学会
- 雑誌
- 韓国語学年報 (ISSN:18831141)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.113-138, 2018-04
1 0 0 0 OA 太田川下流平野における人為的影響の検討 ―上流部でのたたら製鉄に注目して―
- 著者
- 松本 誠子 久保 純子 貞方 昇
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2021年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.128, 2021 (Released:2021-03-29)
1.研究目的 本発表は、典型的なデルタとして取り上げられてきた太田川デルタの形成・成立には、上流域における往時の砂鉄採取による廃土が大きく関与した、とみなす調査結果の第一報である。近年における発表者らによる太田川上流の調査(貞方ほか2020、印刷中)を通して、これまで看過されてきた太田川の上流域でも、中世に遡る広範かつ大規模な「たたら製鉄」に伴う砂鉄採取跡地が確認された。発表者らは、さらに、そこから排出された大量の廃土が同川の下流平野・デルタ形成に何らかの影響を与えたものとみて、とりわけ同地における完新世堆積物中の「最上部陸成層」に着目し、その堆積物の諸特性や平野微地形の特徴を調査した。その結果、以下に記すような上流域の砂鉄採取と整合する幾つかの明瞭な証拠を得た。 平地に乏しい我が国にあって、デルタは主要な生活の舞台である一方、洪水や高潮などの災害も多く発生するため、防災の観点を含めてこれまで数多くの研究業績が蓄積されてきた。従来「最上部陸成層」は、後氷期海面高頂期以降の海面微変動や堆積物供給の多寡に呼応して形成されてきたとされるが、最新期における人間活動の影響も少なからず関与したものと思われる。本発表は、デルタ形成・成立における人為関与地形形成の役割を評価することに的を絞り、その調査成果の一部を紹介するものである。2.研究方法・データ 本研究では、米軍大縮尺空中写真判読を中心とした一連の微地形調査や、既存ボーリング資料の検討、表層堆積物の各種分析に加え、歴史時代を含めた短い時間スケールの地形形成の経緯をより明らかにするため、洪水史等の歴史資料の検討も行った。分析対象とした試料は、広島城西の広島市中央公園(「デルタ」:人為関与前)、広島大学霞キャンパス(干拓地)の試掘露頭ほか、「デルタ」内の数地点(深度0.5m、1m)で採取した表層堆積物および現河床の堆積物から得た。堆積物は粒度分析、砕屑粒子組成分析とともに鉄滓粒の存否を確認し、12点の炭化物についてAMS14C年代測定を行った。3.結果と考察 太田川下流域は、広島市安佐南区八木の高瀬堰以南にまとまった沖積平野を形成し、大きくは広島市西区の大芝水門付近までの幅2km前後の「下流平野」とそれ以南に広がる「デルタ」(いわゆる広島デルタ)に二分される。微地形判読によれば、太田川は「下流平野」で扇状地をほとんどつくらず、氾濫原上の旧蛇行河道に沿ういわゆる「自然堤防」の発達は弱い。また、「デルタ」のうち自然堆積域として分類できるのは大芝から白神社付近までの狭い範囲(径4km)に限られ、他の多くは近世以降の干拓地および埋立地である。さらに、干拓地内に延びる河道沿いには連続的に微高地が形成されている等の特徴をもつ。既存ボーリング資料および掘削現場の露頭観察によって「最上部陸成層」とみなされた各採取堆積物試料中における花崗岩類起源の砂粒の割合は80%以上と非常に高く、それより下位の試料(上部砂層以下)の組成では、平野の直上流側に分布する付加体起源の砂粒の割合が高いことが示された。現段階の採取試料で見る限り、「最上部陸成層」中の炭化物の年代は13世紀から18世紀という極めて新しい年代値(中世から近世)を示した。また、「下流平野」に属する安佐南区緑井の自然堤防状微高地からは、砂鉄製錬滓由来の鉄滓粒が見出され、「デルタ」の各試料からは鉄錆片(鍛造鉄器片)を含む幾つかの鍛冶関連物質粒が認められた。 これらの年代や人工物質の存在は、太田川上流部でのたたら製鉄やそれに伴う砂鉄採取が行われていた時期とも重なることから、花崗岩類起源の割合が高い堆積物は、当時の砂鉄採取によって廃出された土砂の影響をかなり受けたものと見ることができよう。歴史資料によれば、広島藩により1628年に太田川流域の砂鉄採取は禁止されたが、同川下流では引き続き過大な土砂流出・堆積が継続するとともに洪水被害が頻発し、「デルタ」では河道の固定(堤防強化)や「川浚え」と呼ばれた河道からの砂排除が行われるようになったという。こうした人為的営為も「デルタ」の微地形特徴に寄与したとみられる。4.まとめ 太田川下流の「デルタ」(広島デルタ)は教科書などで典型的なデルタとして扱われてきたが、自然堆積範囲は狭く、干拓地を含めて「最上部陸成層」の形成には、たたら製鉄に伴う砂鉄採取による廃土が大きく関与したものとみられる。また「デルタ」上の各河道に沿う微高地は、主に近世に二次的な地形改変を受けつつ形成されたものである。 本発表では微高地そのものと対応する堆積物の分析は行えなかったことや、「デルタ」の堆積物からは直接に砂鉄製錬に由来する鉄滓粒の確認はできなかったが、今後分析試料数を増やして「最上部陸成層」の意義づけや人為関与地形形成の実態把握を進めたい。
1 0 0 0 OA 地域在住高齢者における「楽しさ」の因子構造について
- 著者
- 矢嶋 昌英 浅川 康吉 山口 晴保
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.95-99, 2011 (Released:2011-03-31)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 3 2
〔目的〕高齢者の「楽しさ」を構成する因子を明らかにすることを目的とした。〔対象〕群馬県前橋市敷島及び吉岡町老人福祉センターの利用者165名とした。〔方法〕独自に作成した調査票を用い,性別,年齢,「楽しみ」の有無,「楽しい理由」について個別面接により聴取した。「楽しみ」の有無を尋ね,「有る」と回答された方には,その内容および「楽しい理由」を聴取した。「楽しい理由」はTaxonomy of Human Goals(人間が持つ目標の分類)を参照し,「はい」と「いいえ」の2件法で回答を得た。「楽しい理由」としてあげられた項目について探索的因子分析を行い,「楽しさ」を構成する項目を抽出した。〔結果〕楽しみがある人は159名(96.4%)であった。主な内容はカラオケ,センターに来ること,会話,温泉,手芸であった。「楽しい理由」として抽出されたのは3因子11項目であった。それぞれ,第1因子は探究・理解・知的創造性・熟達・課題創造性であり「認知-課題」,第2因子は個性・自己決定・優越であり「自己主張的社会関係」,第3因子は平穏・幸福・身体的健康であり「情動」と命名した。なお,11項目のCronbach α係数は0.73であった。〔結語〕地域在住高齢者の「楽しさ」は,「認知-課題」,「自己主張的社会関係」,「情動」の3因子構造を示し,抽出された11項目で評価できることが示唆された。
1 0 0 0 OA 性格特性を表現するエージェントジェスチャの生成
- 著者
- 中野 有紀子 大山 真央 二瓶 芙巳雄 東中 竜一郎 石井 亮
- 出版者
- ヒューマンインタフェース学会
- 雑誌
- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.153-164, 2021-05-25 (Released:2021-05-25)
- 参考文献数
- 40
In this study, first, we analyze the relationship between personality traits and the expressivity of hand gestures in dyad interaction. Second, based on the analysis results, we propose a method for agents’ gesture generation that can express their personality traits. Our user study reveals that expected personality traits can be perceived from the agent’s animation generated by our proposed method. Especially for extroversion and emotional instability, agent gestures generated based on our method successfully gave the expected impression to the human subjects.
1 0 0 0 OA 自宅での仮想キャラクタによる能動的情報提供が許容されるタイミングの検討
- 著者
- 藤江 律也 仲澤 悠太 徐 建鋒 小森田 賢史 内藤 整 藤田 欣也
- 出版者
- ヒューマンインタフェース学会
- 雑誌
- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.135-144, 2021-05-25 (Released:2021-05-25)
- 参考文献数
- 34
Making smart speakers proactive might benefit users by delivering unconscious but useful information. However, depending on the timing and manner of the delivery, proactive deliveries pose a risk in disturbing user’s ongoing activity. Thus, we hypothesized that the times of activity-transition are appropriate for information delivery. In this study, we prototyped a system that estimates activity-transitions based the user’s body motion using a depth camera, and actively provide Internet news through a voice of virtual character. We then conducted a set of experiments in everyday-living scenario at the homes of five university students living alone. The result demonstrated that the times after transfer are generally appropriate. In contrast, the change of the user’s face direction, i.e. supposed gaze-target transition, occurred more frequently but included more inappropriate cases. Elimination of the error-detections such as body posture change while looking at smartphone is needed to detect activity-transitions more appropriately.
- 著者
- 橋本 義郎 ハシモト ヨシロウ Yoshiro Hashimoto
- 雑誌
- 国際研究論叢 : 大阪国際大学紀要 = OIU journal of international studies
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.9-23, 2007-03-31
Almost all of schools and universities in Sweden, both public and private, chargestudents little or no educational fees. As a condition of receiving financial support from the national government, they may receive only small sums from students forthe purchase of learning materials for individual use and are not allowed to chargefor tuition. In addition to this indirect support, there is a direct financial supportsystem for helping students at various educational levels, including university. Thearticle introduces this system, focusing on its function of supporting students, anddiscusses its characteristics. There seems to be a shared value-system, transcending political standpoints, which helps people accept the idea of usingpublic funds to meet ordinary human needs such as financial support for students.
1 0 0 0 OA 椎骨動脈解離性動脈瘤の治療
- 著者
- 恩田 英明 谷川 達也 竹下 幹彦 荒井 孝司 川俣 貴一 氏家 弘 井沢 正博 加川 瑞夫 高倉 公朋
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中の外科学会
- 雑誌
- 脳卒中の外科 (ISSN:09145508)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.293-299, 1994-07-30 (Released:2012-10-29)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 20 16
The authors present 33 patients with dissecting aneurysm of the intracranial vertebral artery, of whom subarachnoid hemorrhage developed in 26 patients and cerebral ischemia in 7 patients. Sixteen patients were surgically treated and 17 were conservatively treated. In this series, recurrent hemorrhage occured in 9 (35%) of 26 patients who presented with subarachnoid hemorrhage within 2 weeks after the initial ictus. The outcome of the cases with recurrent hemorrhage was very poor-7 of these 9 patients died. Therefore, surgical intervention during the acute stage is required to avoid the early rerupture. Comparative study with surgical and conservative treatment for dissecting aneurysms of the vertebral artery indicated that the outcome of patients with surgical treatment was much better than with conservative treatment. In surgical procedures, proximal clip-occlusion of the vertebral artery at the site distal to the PICA (DTP) was performed in 5 cases, at proximal to the PICA (PTP) in 4, trapping of the vertebral artery with dissecting aneurysm in 2, coating in 3, and proximal occlusion of the vertebral artery with detachable balloon in 2 patients. Postoperatively, transient lower cranial nerve palsy or cerebellar signs developed in 2 cases with trapping, in 1 with PTP and permanent hemiparesis due to thromboembolism at the top of the basilar artery in 1 with balloon-occlusion of the vertebral artery. In spite of surgical intervention, rerupture occured postoperatively in 1 case with coating and in 1 with DTP. Trapping procedure is most reliable to prevent rerupture of dissecting aneurysm, but it is difficult to expose the distal part of the vertebral artery beyond the aneurysm for trapping. Although proximal clip-occlusion is not completely satisfactory for prevention of rebleeding, it is simple as a method and useful for dissecting aneurysm of the vertebral artery.