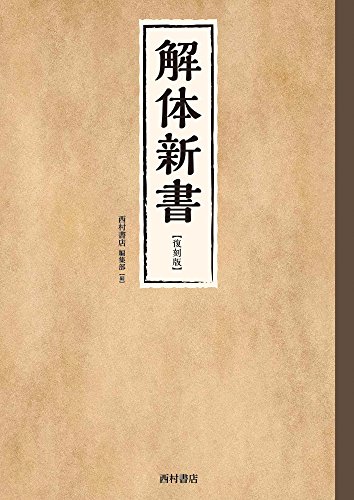- 著者
- 河原 典史 Kawahara Norifumi
- 出版者
- 神奈川大学 国際常民文化研究機構
- 雑誌
- 国際常民文化研究叢書1 -漁場利用の比較研究-=International Center for Folk Culture Studies Monographs 1 -Comparative Research on Fishing Ground Use-
- 巻号頁・発行日
- pp.173-184, 2013-03-01
第二次世界大戦以前、カナダ西岸における塩ニシン製造業は、日本人漁業者による独占的な産業として重要であった。本稿は、1920 年頃のカナダ・バンクーバー島西岸におけるニシン漁業の漁場利用を考察したものである。分析にあたって、1919 年に農商務省から発行された『加奈陀太平洋岸鰊・大鮃漁業調査報告』を活用した。この報告書には、解説文とともに様々な実測図が掲載され、漁場利用が理解されやすい。また、有力な塩ニシン製造業者の一つである嘉祥家が所蔵する古写真の読解と、当時のニシン漁に携わった日系二世へのインタビュー調査も実施した。 この漁業に関わる漁船は、ニシン群を漁獲する2 隻の網船のほか、曳船・手船・スカウ(Scow・無動力の平底船)から構成されていた。網船やスカウを曳行する曳船には船長(漁撈長)と機関長のほか、漁場利用に大きく関与する2 人の沖船頭が乗船した。そして、前日に準備された漁具を積んだ2 隻の網船には、25 人ずつが分乗した。つまり、二隻曳巾着網漁業は、55 名程度で操業されていたのである。 曳船に載った沖合船頭の2 名は、海上を見渡せる船首に位置してニシン群を追った。その方法について、昼間には海上に浮上してくるニシンを空中から狙うカモメの動向や、魚群が映る海水の色、さらに海中のニシンが発する気泡にまで気が払われた。それに対し、視覚に頼れない夜間ではニシン群の発する水音が手掛かりとなった。 魚群を発見すると曳船に乗っていた漁業者は手船に乗り移り、網船の位置取りの指示をした。それを受けた2 隻の網船には、役割毎に17 名がそれぞれの漁船に分乗し、魚群を取り囲んだ。そして、推進機関を用いて網締めが開始されると、スカウに移った漁業者は2 人1 組となり、たも網を利用してニシンを掬い入れた。この作業には日本人だけではなく、ユーゴスラビア系移民も関わっていたようである。
1 0 0 0 IR 憲法訴訟と違憲審査基準-3-
- 著者
- 藤井 俊夫
- 出版者
- 千葉大学教育学部
- 雑誌
- 千葉大学教育学部研究紀要 (ISSN:05776856)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.p131-151, 1983-12
1 0 0 0 解体新書
- 著者
- [クルムス著] [杉田玄白 前野良沢訳] [中川淳庵校] [石川玄常参] [桂川甫周閲] 西村書店編集部編
- 出版者
- 西村書店東京出版編集部
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 IR 助動詞CANの特異性
- 著者
- 小野 浩司
- 出版者
- 佐賀大学文化教育学部
- 雑誌
- 研究論文集 / 佐賀大学文化教育学部 (ISSN:13428705)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.1-7, 1998-12
- 著者
- 新井 哲夫
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.15-33, 2019 (Released:2020-04-28)
- 参考文献数
- 56
本研究の目的は,欧米視察旅行(以下,欧米旅行)が久保貞次郎の批評家としてのキャリア形成に与えた影響と欧米旅行実現に至った背景を明らかにすることである。研究は,貞次郎が戦前・戦中に執筆した雑誌記事,同時期における貞次郎の実生活上の経験に関わる文献,戦後の回想記等を対象に文献研究法によって行った。その結果,欧米旅行が貞次郎の美術及び児童美術の批評家としてのキャリア形成に決定的影響を与えたこと,欧米旅行に至る背景については,エスペラント運動の経験と婚家の経済的支援が必須の前提条件となり,社会教育研究生の経験が自らの将来像を見直す機会を与え,それが大学院進学に繋がり,大学院時代に参加した日米学生会議における北米体験が欧米旅行実現の直接的な動因となったことを実証的に明らかにした。
1 0 0 0 在日外国人のスギ花粉症実態調査
- 著者
- 石井 彩子 宇田川 友克 柳 清 今井 透
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.279-283, 2003
スギ花粉症の患者は年々増加傾向で, 現在では国民の10%以上が罹患しており, スギ花粉症は日本人の国民病といわれている。その影響は, 在日外国人にも及んでいる模様で, 花粉症症状を訴えて来院する外国人も年々増加傾向にあると考えられる。その実態を調査するため, 平成14年1月から4月までの期間に鼻汁, 鼻閉, くしゃみ等のアレルギー症状を主訴に聖路加国際病院耳鼻咽喉科を受診した在日外国人患者38人のうち, 血清スギ特異的IgE抗体測定にてスギ花粉症が確認された20人 (男性 : 12人女性8人) を対象にアンケート調査を施行した。来日後発症までの期間は平均約4年であった。在日外国人のスギ花粉症に対する認知度は低い傾向にあり, スギ花粉情報の提供も含めた啓蒙活動が必要であると考えられた。
研究2年目においては、「みんなのうた」初代チーフ・プロデューサーであった故後藤田純生氏に更に焦点を当て、国会図書館、後藤田氏遺族自宅での資料調査や論文執筆・学会発表を行った。また、申請書に記載していた六つの研究課題のうち、以下の二つの課題について掘り下げることができた。⑤「ゼッキーノ・ドーロ」の調査「みんなのうた」の楽曲には、1959年に始まったイタリアの児童音楽祭「ゼッキーノ・ドーロ」の入賞歌曲を原曲とするものが複数存在する。後藤田氏の資料より、後藤田氏が「ゼッキーノ・ドーロ」の楽曲を「みんなのうた」に輸入した経緯を検討し、また商業主義の強かった「ゼッキーノ・ドーロ」の楽曲が「みんなのうた」に入ることにより、その後のポピュラー路線につながる契機となったことを導き出した。⑥学校教育における楽曲使用の調査この課題については、まず保育現場や小学校で使用されている楽曲の実態を検討した。また「NHK番組アーカイブス学術利用トライアル」にも参加し、「ポピュラー性」をキーワードとして、特集番組等における「みんなのうた」各楽曲の使用頻度について調査を行い、各楽曲の認知度について分析を行った。また、5月3日に東京・晴海区民館で初期「みんなのうた」の関係者(当時のディレクター、演奏者、ファン会会員等)を招いての研究座談会を行った。これによって、1960年代の「みんなのうた」の制作背景や、当時の番組の受容についての情報を得ることができた。更に、9月17日に国際シンポジウム「近代の音と声のアーカイブズ」を熊本大学音楽学講座と共同開催した。そこで報告「戦後のNHK児童番組の資料保存についての現状と『みんなのうた』写真資料の発見」を行い、映像が失われてしまった1962年度版「大きな古時計」について、後藤田氏の資料よりセル画の写真資料を発掘したことと、再現映像を作成していることについての発表を行った。
- 著者
- 新山王 政和 小瀬木 崇
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学教職キャリアセンター紀要 The journal of the Teaching Career Center (ISSN:24238929)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.113-121, 2019-03-31
一連の研究では、偶然性に依拠したり機器に頼って音符並べをしたりする「音楽づくり(創作)」ではなく、まず自らが表したいイメージを定め、そのイメージに向かってICレコーダーと鍵盤ハーモニカを用いながら音楽づくりを創意工夫する活動を模索している。そのうち南山大学附属小学校で試行した河田愛子教諭による研究授業は、愛知教育大学研究報告第68輯に於いて報告する。(1)そして本報告では春日井市立勝川小学校で試行した小瀬木崇教諭による研究授業について報告するが、注目したい点は「旋律をつくる→"合いの手"に合うように旋律を手直しする」という二段階で試行錯誤を深めさせたことである。研究授業の計画に先立ち、実践協力者には次の5つの条件を提示し、これを考慮してもらった。①音楽づくり(創作)の活動は、音楽の諸要素と曲想との関係を感じ取る鑑賞と組み合わせて行う。②ICレコーダーを用いて振り返ることで、思考を伴った試行錯誤を積み重ねながら音楽づくりを深める。③2人組のペア学習、さらにペア2組で聴き直しながら対話的な活動や学び合いを深めていく。④ICレコーダーの有用性と効果的な活用方法、教師による声掛けやアドバイスの効果を検証する。⑤児童自らが音を出す楽器を使用し、並べた音符をPCやタブレットに演奏させる方法は用いない。試行実践の結果、音楽づくりの活動に於いても、音楽の"よさ"に気付き自分なりの"解"を追究するためにICレコーダーが有効なツールになり得ることがわかった。しかしその効果は教師による働きかけを伴うことで発揮され、子供に持たせるだけでは十分な効果を得られないことも確認した。
1 0 0 0 楽観性・悲観性および心拍数の反応性と回復性の関連
- 著者
- 本多 麻子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.2D-089-2D-089, 2017
1 0 0 0 産婦人科領域の漢方治療
- 著者
- 岡村 麻子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.234-239, 2020
女性のライフステージは、小児期・思春期・成熟期・更年期・老年期に区分される。いずれの領域、ライフステージにおいても漢方治療は単独でも西洋医学との併用でも役に立ち、なくれはならない治療法である。新しい命を生み出す本能を備えているのが女性であるが、その底力を支える治療方法であり、少子高齢化対策の一助となり得る。漢方治療の恩恵を得て一人でも多くの女性が笑顔で元気に世の中を明るく照らす存在になってほしい。
1 0 0 0 オンライン調査における努力の最小限化が回答行動に及ぼす影響
<p>This study investigated the influence of satisficing on response behavior in online surveys. We compared online response data to psychological scales and logical thinking tasks conducted by an online survey company and a crowd sourcing service. In previous studies, satisficing was found to be more likely to occur among online survey monitors than among crowd sourcing service contributors. Results of the present study replicated it and showed that satisficing in terms of inattentively reading items significantly damages the integrity of psychological scales. On the other hand, it was also found that the influence of satisficing in terms of inattentively reading instructions carefully can be reduced by raising respondents' awareness. Those conducting online surveys should discuss taking active measures to minimize satisficing. </p>
1 0 0 0 OA 兎ノ解剖案内 : 前々號ノ續キ
1 0 0 0 OA 兎ノ解剖案内(二一頁ノ續キ)
1 0 0 0 ロングストロ-ク空気ばねによる鉄道車両用車体傾斜制御
1 0 0 0 IR 空気圧制御による鉄道車両の乗り心地向上
1 0 0 0 IR 日本占領を問い直す : ジェンダーと地域からの視点
- 著者
- 三宅 千晶
- 出版者
- 朝陽会 ; 1953-
- 雑誌
- 時の法令 (ISSN:04934067)
- 巻号頁・発行日
- no.2117, pp.53-60, 2021-03-15