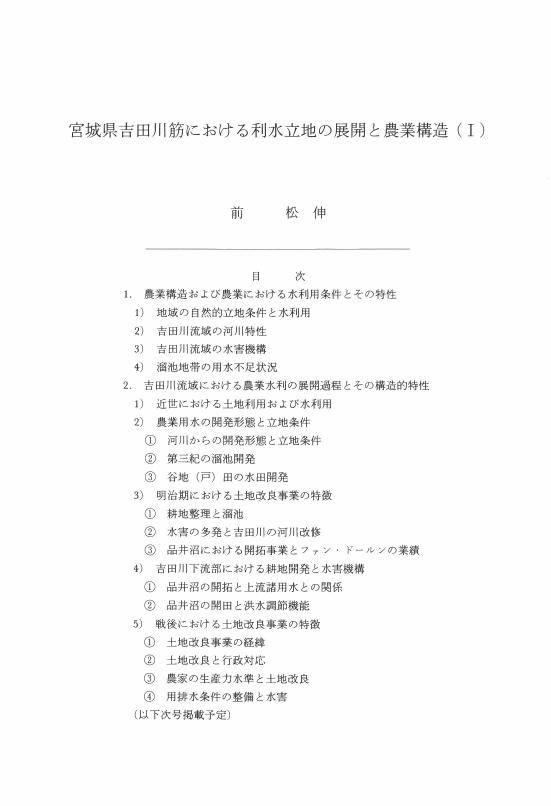1 0 0 0 OA てんかんをもつ児と水泳 養護教諭に対するアンケート調査より
- 著者
- 西河 美希 市山 高志 林 隆 古川 漸
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.15-19, 1998-01-01 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 9
山口県下の小中学校, 養護学校の養護教諭391名を対象とし, てんかん児の水泳を中心とした学校生活の対応について, アンケート調査を行った.対象人数391名中, 回答人数278名で, 回収率71%だった.82.7%の養護教諭がてんかん児を経験していたが, 学校行事の中で水泳を制限するという回答が全体の24.5%にみられた.また, 医師から制限不要の指示がでた場合でも, 20%以上の養護教諭が何らかの制限をするという回答だった.これらの結果より学校現場の中で医学的知識に詳しいと予測される養護教諭でも, てんかんに対する知識で不適切と思われる考え方が根強く残っていることがわかった.今後, 養護教諭に対するてんかんの正しい知識の普及が望まれる.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ものづくり (ISSN:13492772)
- 巻号頁・発行日
- no.743, pp.57-59, 2016-08
体操競技で選手が繰り出す技は、ますます高度に、かつ複雑になっている。例えばリオ五輪代表の1人、白井健三選手の「ゆか」の新技「シライ3」は、わずか約1秒の間に、後方伸身宙返りを2回、同時にひねりを3回実行する1)、*1。採点に当たる審判員は、このよ…
1 0 0 0 ノモンハン会会員名簿
- 出版者
- ノモンハン会
- 巻号頁・発行日
- 1993
- 著者
- 事柴 壮武 浦辺 幸夫 前田 慶明 篠原 博 山本 圭彦 藤井 絵里 森山 信彰
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2014
【はじめに,目的】膝前十字靭帯(anterior cruciate ligament;ACL)損傷はストップやジャンプ着地動作,サイドステップカッティング(sidestep cutting;SSC)動作で多く発生している。一般的に"Knee-in & Toe-out"という下肢アライメントの組み合わせが,マルアライメントの代表的なものとしてあげられる。SSC動作の筋活動について,Xieら(2012)はストップ期において大腿四頭筋に対するハムストリングの比(H/Q比)は,側方移動期よりも低値を示したとしている。また,ACL損傷のリスクである膝関節の過度の外反を制動するためには,大腿四頭筋とハムストリングの同時収縮をタイミングよく行う必要がある。よって,ACL損傷のメカニズムや予防を考慮すると,筋活動量だけでなく筋活動のタイミングを検討することは重要であると考える。SSCは足部運動との関連が示されており,足部の外側接地(Dempseyら,2009)や後足部での接地(Cortesら,2012)がACL損傷のリスクになるとされている。しかし,足部の方向(Toe-out)とSSCの関連を調べたものはみあたらない。本研究は,Toe-outでのSSCが膝関節運動学,筋活動様式に及ぼす影響を検討することを目的とした。仮説は,Toe-outでのSSCはNeutralと比較して膝関節外反角度が大きく,H/Q比が低いとし,さらに筋電位ピーク到達時間が遅延するとした。【方法】対象は下肢に整形外科的疾患の既往がない,健常な女性バスケットボール選手6名(年齢20.0±1.4歳,身長158.0±3.5cm,体重49.3±5.3kg,競技歴9.3±5.3年)とした。対象は5m離れた地点から最大努力速度で助走し,軸脚の左脚で踏み切り,右90°方向へSSCを行った。その際,着地条件として足部Neutral(条件N)と足部Toe-out(条件TO)の2条件を設定し,3試行ずつ実施した。なお,反射マーカーを対象の左下肢8ヶ所に貼付し,ハイスピードカメラ(フォーアシスト社)5台を用い,サンプリング周波数200HzでSSCを撮影した。撮影した映像を動作解析ソフト(Ditect社)に取り込み,DLT法で各マーカーの3次元座標を求め,膝関節屈曲,外反角度を算出した。本研究ではSSCを足部接地から膝関節最大屈曲位までのストップ期,膝関節最大屈曲位から足部離地までの側方移動期の2期に分割し,各期の膝関節最大外反角度を分析に用いた。筋活動の記録には表面筋電図(追坂電子機器社)を用いた。被験筋は外側広筋(VL),内側広筋(VM),大腿二頭筋(BF),半膜様筋(SM)とした。筋電図は生波形からRMS(root mean square)に変換して解析した。本研究ではVLとVMの活動量の平均値を大腿四頭筋の活動量,BFとSMの活動量の平均値をハムストリングの活動量とした。Initial contact(IC)を基準(0)とし,筋電波形の振幅がピークに達する時間をピーク到達時間と規定した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は,広島大学大学院保健学研究科心身機能生活制御科学講座倫理委員会の承認を得て実施した(承認番号1327,1335)。対象に本研究の趣旨を十分に説明し,書面にて同意を得た。【結果】膝関節最大外反角度はストップ期の条件Nで7.0±3.8°,条件TOで8.8±5.5°であった。側方移動期の条件Nで4.6±3.9°,条件TOで7.9±5.4°であり,条件TOで有意に高値を示した(p<0.05)。H/Q比はストップ期の条件Nで0.33±0.08,条件TOで0.33±0.13であった。側方移動期の条件Nで0.67±0.22,条件TOで0.48±0.12であり,条件TOで有意に低値を示した(p<0.05)。各筋のピーク到達時間は,条件NでVMは119.9±49.1msec,VLは114.3±49.6msec,SMは102.1±76.1msec,BFは175.4±79.5msecであった。条件TOでVMは145.2±26.2msec,VLは151.9±24.8msec,SMは88.6±62.6msec,BFは194.1±58.8msecであった。条件TOでVMのピーク到達時間が有意に遅延していた(p<0.05)。【考察】本研究の結果より,Toe-outでのSSCはNeutralと比較して,側方移動期の膝外反角度が高値となり,H/Q比が低値を示した。膝関節外反角度が大きく,H/Q比が低いことは大腿四頭筋優位となりACL損傷のリスクが高いことを示している。さらに,VMのピーク到達時間の遅延を認めた。また,有意差はなかったもののSMのみピーク到達時間がNeutralよりも早期であった。VMは内側ハムストリング(SM)と協同して内側機構の支持に働き,膝関節の安定性に関与している(Myerら,2005)。したがって,内側安定機構であるSMとVMのピーク到達時間のずれは,過度の膝関節外反の制動を困難にしていることが考えられる。【理学療法学研究としての意義】Toe-outでのSSCが膝関節運動学,筋活動様式に与える影響を明らかにすることは,ACL損傷メカニズムを解明する一助になるだけでなく,スポーツ現場やリハビリテーション場面において,ACL損傷の予防につながると考える。
1 0 0 0 OA 戸隠神社奥社社叢林に生育するスギの遺伝的多様性と遺伝的特性
- 著者
- 木村 恵 中村 千賀 林部 直樹 小山 泰弘 津村 義彦
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.173-181, 2013-06-01 (Released:2013-07-25)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 6 4
多面的機能が注目される社叢林の保護と管理を行うには, その成立要因を理解する必要がある。本研究では長野県戸隠神社奥社参道のスギ並木を対象に林分構造と遺伝的多様性・特性を調べた。二山型を示す直径階分布から多くの個体は限られた時期の植林によって成立しており, 現在の樹高成長量は低く今後は補植が必要になると考えられた。核マイクロサテライトマーカー8遺伝子座での遺伝解析から多くのクローンが検出され, 挿し木による植林の可能性が示された。また奥社参道における遺伝的多様性の指数は天然林と同程度だが, 遺伝距離に基づく主座標分析では天然林とは異なる特異な遺伝的特性を示した。さらに周囲の社叢林のスギ, 在来挿し木品種クマスギを加えた解析では血縁関係 (親子, 兄弟) が検出された。天然林との特異な遺伝的関係も検出され, 限られた母樹からの苗木による創始者効果の可能性が示された。現在の遺伝的多様性・特性を維持するには, 挿し木や血縁関係にある幹の重複を避けて母樹を選定し, 苗木を生産することが有効である。また信仰的な理由で挿し木されたと考えられる個体もみられており, 戸隠神社の歴史を反映するこれらの遺伝子型の保存も重要である。
1 0 0 0 OA 物理未修学生に配慮した力学の授業開発
- 著者
- 石川 洋
- 出版者
- 東北大学高度教養教育・学生支援機構
- 雑誌
- 東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要 = BULLETIN OF THE INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION TOHOKU UNIVERSITY (ISSN:21895945)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.419-424, 2021-03
1 0 0 0 OA 宮城県吉田川筋における利水立地の展開と農業構造(Ⅰ)
- 著者
- 前 松伸
- 出版者
- 一般社団法人 日本治山治水協会
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.6, pp.48-86, 1991-02-01 (Released:2019-08-13)
- 著者
- 福田 栄紀
- 出版者
- 日本草地学会
- 雑誌
- 日本草地学会誌 (ISSN:04475933)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.1-11, 2015-04-15 (Released:2015-06-25)
- 参考文献数
- 41
寒地型牧草のための肥培樹,庇陰樹としてのマメ科先駆樹種ネムノキの特性を評価するため,ネムノキがオーチャードグラス(Og)の生育に及ぼす影響を調べた。ネムノキの孤立木とOgが同所的に生育する3か所において,ベルトトランセクト法によりOgの草丈,収量を測定し,樹冠内外で飼料成分含量を比較した。草丈,乾物収量はネムノキの樹幹に近づくにつれ漸次高くなった。樹冠内が高い成分は,2番草におけるCP,DE,OCC+Oaであり,これら蛋白質・可消化エネルギー関連成分は番草を問わず樹冠内が高い傾向にあった。樹冠外が高い成分は,2番草におけるObであり,また番草を問わず繊維性成分は樹冠外が高い傾向にあった。TDN収量,CP収量は,1番草において樹冠内の方が樹冠外より高かった。収量特性における樹冠内外差は1番草においてより顕著であり,一方栄養特性における内外差は2番草でより顕著であった。これらの結果はOgの生育に影響を及ぼす主要環境要因がネムノキ樹冠内において一様ではなく,樹幹に近づくにつれて漸次好適になること,およびネムノキは夏が暑い日本でOgのための肥培樹,庇陰樹として機能しうることを示唆する。
1 0 0 0 IR 金沢美術工芸大学所蔵「架鷹図屏風」の絵画材料、絵画技術の調査研究
- 著者
- 佐藤 一郎
- 出版者
- 金沢美術工芸大学
- 雑誌
- 金沢美術工芸大学紀要 = Bulletin of Kanazawa College of Art (ISSN:09146164)
- 巻号頁・発行日
- no.63, pp.123-131, 2019
1 0 0 0 OA 「傷痍軍人」考―大島渚監督「忘れられた皇軍」を通して―
- 著者
- 溝口 元
- 出版者
- 立正大学社会福祉研究所
- 雑誌
- 立正大学社会福祉研究所年報 (ISSN:13449532)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.53-63, 2016-03-31
- 著者
- 飛ヶ谷 潤一郎
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.588, pp.211-216, 2005
- 参考文献数
- 9
Firmitas (strength), one of the famous Vitruvian triad, can be imagined as a magnificent building structure, such as the dome of the Pantheon, which is based on the high technologies of the Roman Architecture. It is, however, important to note that the word firmitas is mostly found in his Book II, where architectural materials are explained. This paper intends to examine Vitruvian firmitas from the viewpoint of material "strength" or "durability", and to trace its changes in encyclopedic works of Antiquity and the early Middle Ages, such as Plinius' Natural History and Isidore's Etymology. Isidore substituted constructio for the Vitruvian firmitas, but the word merely meant "consrtuction."
1 0 0 0 OA 高野山スギ特別母樹林
- 著者
- 木村 恵
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 森林科学 (ISSN:09171908)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.32-33, 2012-10-01 (Released:2017-07-07)
1 0 0 0 OA ミシェル・フーコーにおける言語と自由の問題
- 著者
- 柴田 秀樹
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会関西支部
- 雑誌
- 関西フランス語フランス文学 (ISSN:24331864)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.27-38, 2016-05-25 (Released:2018-08-08)
Le problème de la langue et de la liberté chez Michel Foucault Dans ses dernières années, Foucault a souligné l’importance politique de la pratique de la liberté. Le «gouvernement», le «souci de soi» ou la «parrêsia», qui signifie la «liberté de parler» en grec, toutes ces notions foucaldiennnes ont sa source dans cet intérêt à la pratique de la liberté. Nous pourrons éclaicir la caractéristique de cette liberté par comparaison avec celle de Isaiah Berlin. Berlin a distingué deux aspects de la liberté, c’est-àdire la liberté positive et la liberté négative. Et il a attaché beaucoup de prix à cette dernière. Au contraire, Foucault a apprécié la liberté positive, pour sa possibilité de créer les nouvelles relations humaines, sexuelles ou politiques. Dans cette pratique de la liberté foucaldienne, particulièrement dans l’acte de la parrêsia, la brutalité de la liberté positive,contre laquelle Berlin a poussé un cri d’alarme, est modérée par le respect envers la réciprocité et l’autonomie mutuelle entre deux sujets qui parlent librement. Et on pourra dire que cette pratique est rendue possible par l’intermédiation de la langue. Chez Foucault, la langue et la liberté sont s’unissent donc intimement.
1 0 0 0 IR 教員養成課程におけるピアノ実技教材の考察 : ギロック作品の導入と効果
- 著者
- 松井 裕樹 松永 洋介 マツイ ヒロキ マツナガ ヨウスケ MATSUI Hiroki MATSUNAGA Yousuke
- 出版者
- 岐阜大学教育学部
- 雑誌
- 岐阜大学教育学部研究報告. 人文科学 = Annual report of the Faculty of Education, Gifu University. 岐阜大学教育学部 編 (ISSN:02865556)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.69-79, 2017
1 0 0 0 スマートウォッチを用いた参加型降水センシングシステム
- 著者
- 沖原 周佑 本木 悠介 中澤 仁 大越 匡 陳 寅
- 雑誌
- 研究報告ユビキタスコンピューティングシステム(UBI) (ISSN:21888698)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021-UBI-70, no.3, pp.1-8, 2021-05-27
気象情報は多くの人々の生活に影響を与えるもので,人間社会の経済活動や,個人の生活に欠かせない一種のインフラとしての側面を持つ.既存の降雨情報の取得において,情報の粒度,リアルタイム性,測定機器の構造に課題がある.本研究ではスマートウォッチを用いた参加型降水センシングシステムを提案する.このシステムにより,これらの課題を解決し,信頼性と精度のある気象情報を共有することを目的とする.このシステムは設備の整備コストなしに,人が傘をさすという行為のなかに極めて自然に埋め込むことができる.本論文ではこのシステムの実現に向けて,傘への降水の衝撃をスマートウォッチで計測し,降水の程度を分類することは可能なのかを検証した.検証の結果,適切なデータの処理を施すことで,より正確に分類可能であることが明らかとなった.
- 著者
- MORODA Yukie TSUBOKI Kazuhisa SATOH Shinsuke NAKAGAWA Katsuhiro USHIO Tomoo SHIMIZU Shingo
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-038, (Released:2021-03-16)
- 被引用文献数
- 3
A phased array weather radar (PAWR) can complete one volume scan in 30 seconds, thus enabling us to obtain high spatiotemporal resolution echo intensities and wind fields of storms. Using its rapid scanning capability, we investigated the evolution of a convective storm in detail. To describe evolution of convective storms, we used the following definitions. The precipitation cell is defined as a three-dimensionally contiguous region of 40 dBZ or greater. The precipitation core is defined by a threshold of positive deviation greater than 7 dBZ, which is a difference from the average reflectivity during the mature stage of the cell. An updraft core is defined as an updraft region of 1 m s−1 or stronger at a height of 2 km. An isolated convective storm was observed by two PAWRs on 7 August 2015 in the Kinki District, western Japan. The storm was judged as a single cell, according to the above definition. We identified nine precipitation cores and five updraft cores within 49 minutes in the mature stage of the cell. A long-lasting updraft core and its branches moved southwestward or southeastward. Around these updraft cores, the precipitation cores were generated successively. The updraft core with the longest duration lasted 73.5 minutes; in contrast, the lifetimes of precipitation cores were from 4.5 to 14.5 minutes. The precipitation cell was maintained by the successive generations of updraft cores which lifted humid air associated with a low-level southwesterly inflow. The total amounts of water vapor inflow supplied by all the identified updraft cores were proportional to the volumes of the precipitation cell, with a correlation coefficient of 0.75. Thus, the extremely high spatiotemporal resolution of the PAWR observations provides us with new evidence that an isolated convective storm can be formed by multiple precipitation cores and updraft cores.
- 著者
- YAMADA Yoshinori
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-036, (Released:2021-03-12)
This paper presents an efficient, practical post-processing algorithm for the quality control of dual-pulse repetition frequency (dual-PRF) Doppler velocity data observed in Plan Position Indicator (PPI) mode. Quality control refers to the enhancement of the quality of the Doppler velocities through the re-assignment of an appropriate Nyquist interval number to an erroneous velocity datum and the elimination of unreliable data. The proposed algorithm relies on the local continuity of velocity data, as do most of the preexisting algorithms. Its uniqueness, however, lies both in the preparation of more reliable reference velocity data and its applicability to PPI data at higher elevation angles. The performance of the proposed algorithm is highlighted by its application to observed data from C- and X-band Doppler radars. This algorithm is practical, efficient, and not time consuming. It may be of great help in the derivation of accurate wind information from dual-PRF Doppler velocities.
1 0 0 0 再発を繰り返す難治性聴神経鞘腫に対する手術戦略
- 著者
- 野中 洋一 佐々木 裕亮 田中 将大 角 真佐武 小林 達弥
- 出版者
- 日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.5, pp.376-383, 2017
- 著者
- CUI Ye RUAN Zheng WEI Ming LI Feng GE Runsheng HUANG Yong
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-032, (Released:2021-01-21)
- 被引用文献数
- 1
This study applied the C-band vertically pointing radar with frequency-modulation continuous-wave technology to obtain the continuous observation data of four shallow and two deep snow events during the winter of 2015-2016 in the midlatitudes of China. Generating cells (GCs) were found near the echo tops in every event. The ice particle number concentration (N), ice water content (IWC), and median mass diameter (Dm) retrieved from radar Doppler spectra were used to analyze the microphysical properties in the snow clouds. The clouds were divided into upper GC and lower stratiform (St) regions according to their vertical structure. The fall streaks (FSs) associated with GCs were embedded in the St regions. In the GC regions, the N values in shallow events were smaller compared with deep events, while Dm and IWC were larger. In the St regions, N decreased compared with the GC regions, while the Dm and IWC increased, implying the existence of aggregation and deposition growth. The growth of particle size and mass mainly occurred in the St regions. The increases of N were usually observed near −5°C accompanied by bimodal Doppler spectra, which might be caused by ice multiplication. The average ratios of the median N, Dm, and IWC inside GCs to those outside GCs are 2, 1.3, and 2.5 respectively for shallow events, with 1.7, 1.2, and 2.3 respectively for deep events. These values were basically the same as those for the FSs, implying the importance of GCs to the enhanced ice growth subsequently found in FSs. The larger values of N, Dm, and IWC inside GCs could be related to the upward air motions inside GCs. The first Ze–IWC relationship suitable for snow clouds in the midlatitudes of China was also established.