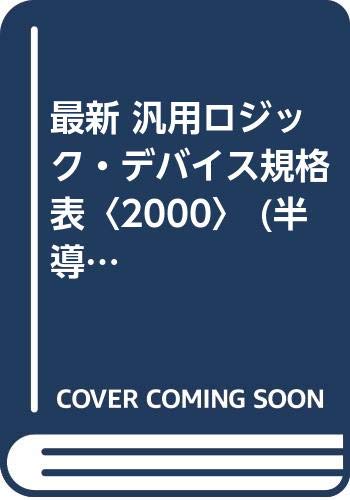1 0 0 0 IR 犯罪被害者等の被害後の実態と支援に関する一考察 ― インターネットによる実態調査 ―
- 著者
- 藤原 幸子
- 出版者
- 学校法人順正学園 九州保健福祉大学大学院社会福祉学研究科
- 雑誌
- 最新社会福祉学研究 (ISSN:18809545)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.33-40, 2021-03-31
本研究は,犯罪被害者等に対するインターネット調査を通じて,被害後の実態,二次被害の実態,被害後に必要な支援等を明らかにすることである.調査は,犯罪の被害にあったことのある200名の男女を対象に実施した.犯罪被害者等の半数以上の者が心身の被害を訴え,身体的心理的影響が生活機能の低下をもたらしていることから心理面だけでなく生活面の支援の拡充が求められる.犯罪被害者等は,複数の人や機関等から二次被害を受けた人も多く,社会,専門機関,被害者に対する啓発を行っていく必要がある.事件後に必要な支援は,事件直後は様々な手続き等の支援への要望が多く,時間が経過するにつれて精神的なケアの要望が多くなる.犯罪被害者等が被害から回復するためには,時に長い時間を要し,犯罪被害者等のニーズは変化する.そのため,ソーシャルワーカーは長期的に支援するという犯罪被害者等の視点に立った支援が求められる.
- 著者
- 大貝 健二
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.309-323, 2012-12-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 1
経済のグローバル化や,少子高齢化の進行に伴い,国内地域経済の疲弊が進んでいる.そのなかで農商工連携,6次産業化など地域資源を活用した地域経済の活性化を目指す取り組みが展開されてきている.本稿で取り上げる北海道・十勝地域は,国内最大の小麦生産地であるが,その大部分は国内消費地へと移出されていることから,地域内で生産,加工,消費の連関は希薄であった.しかし,近年は,農業生産者,中小企業者などの地域の経済主体により,十勝で生産された小麦を地域内で加工し消費する,地域内経済循環を構築する取り組みが広まりつつある,同時に,十勝地域では,「農」や「食」をキーワードに,地域資源を活用した地域産業振興策が積極的に展開されている.そこで,本稿では,地域の経済主体による経済循環を構築する取り組みを明らかにするとともに,地方自治体による地域産業振興施策の展開にも注目している.
- 著者
- 是澤 優子 Koresawa Yuko コレサワ ユウコ
- 出版者
- 東京家政大学
- 雑誌
- 東京家政大学研究紀要 1 人文社会科学 (ISSN:03851206)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.79-88, 1999
1 0 0 0 OA 関節可動域測定における傾斜計の同時的妥当性と再現性
- 著者
- 重島 晃史 坂上 昇
- 出版者
- 高知リハビリテーション学院
- 雑誌
- 高知リハビリテーション学院紀要 = Journal of Kochi Rehabilitation Institute (ISSN:13455648)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.39-46, 2006-03-31
傾斜計は土木建築分野で用いられる角度計であるが,測定面に傾斜計を乗せるだけで容易にその傾斜角度を測定できるので,ROM測定としての応用が考えられる.本研究の目的は,2種の傾斜計の同時的妥当性および再現性を検討することである.対象者は本学院の男子学生12名(平均19.75±0.75歳)で,本研究の主旨の理解と同意を得た.測定器具には,SAKAI社製東大型角度計(以下,角度計),(株)新潟精機製傾斜計(以下,傾斜計),および傾斜計に鉄製の棒を取り付けた傾斜計(以下,軸付き傾斜計)の3種を用いた.傾斜計は移動肢の体表に密着させ測定し,軸付き傾斜計は鉄製の棒を移動軸に合わせることで可動域を測定した.手順は,まず本学院理学療法学科2年生(以下,PTS)に角度計を使用させ,左右の股屈曲,SLR,膝窩角,足背屈を測定し,同様の手順で軸付き傾斜計,傾斜計の順で行った後,経験年数6年目の理学療法士(以下,RPT)においても同様の測定方法および測定部位で行った.再現性の検討には数日の間隔(平均4.5±4.58日)を置き,再度同様の被検者,手順で測定を行った.統計解析では両傾斜計の同時的妥当性をPearsonの相関係数,再現性をPearsonの相関係数および級内相関係数,各測定方法間の差を分散分析・多重比較にて検討した.傾斜計および軸付き傾斜計の同時的妥当性はPTS,RPTともに強い相関を示し,再現性はPTSで股屈曲を除き良好,RPTではすべての測定部位で強い再現性を示した.また,測定方法間ではRPTの軸付き傾斜計で差を示した(p<0.05).本研究において傾斜計はROM測定の器具としての可能性を示した.また,軸付き傾斜計では測定姿勢や器具の当て方を考慮する必要があると考えられた.傾斜計はホームセンターで購入できる安価な物であり,軽量で片手でも扱いやすいので臨床や地域でも有効であることが示唆された.
1 0 0 0 共有知問題のラカン的解釈
- 著者
- 樫村 愛子
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.3-18,184, 1998
The discussions about the "common knowledge" which criticize the code model haven't ever explained with the real process of the communication. So I want to explain it by examining the game theory's approach which tries to explain the connection between the micro and macro phase and elaborating this approach by the Lacanian analytical logic.<br> Lacan presents that the real communication depends on the emergent knowledges which others give. This idea presupposes that the subject is ambiguous with his knowledges and that he doesn't know himself (his unconsciousness). So he should depend on the other and accept the emergent knowledges. Lacan points out that this process is governed by "the logic of precipitousness", which is discovered by the treatments of the neurotics. The neurotics can't accept the ambiguousness of their knowledges and they adhere to the determinable. For example, ordinary man is convinced that he loves somebody in the ambiguousness, but the neurotics can't do it and so they can't love anybody.<br> This phenomenon also makes clear the universal condition of the knowledge. The knowledges are always based on this process through which we accept emergent knowledges in the ambiguousness. The axiom about the "common knowledge" by the game theory has the possibility that describes this process mathematically and the connection with the micro and macro phase, though in fact at the actual level of the mathematics it is difficult.
1 0 0 0 OA ながさきの治山
- 出版者
- 長崎県山地災害対策室
- 巻号頁・発行日
- 1995
1 0 0 0 大学生のメンタルヘルス(<特集>現代の若者のメンタルヘルス)
- 著者
- 三宅 典恵 岡本 百合
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.12, pp.1360-1366, 2015
大学生は思春期の自己同一性の問題が出現する時期であり,メンタルヘルス問題を生じやすい.特に新入生は,入学後の環境変化も大きいことから,新生活への悩みを抱え,不安やうつ傾向の高さが指摘されている.メンタルヘルス問題を抱えると,学生生活への影響も大きく,不登校やひきこもりのリスク要因となるため,早期発見や治療が重要である.そうした中で,大学内の保健管理センターを利用する学生も増加の一途である.メンタルヘルス相談に訪れた学生の精神科診断ではうつ病や不安症が多く,摂食障害や発達障害の相談も増加している.本稿では,大学生に多くみられる精神疾患,その早期発見や治療,支援に向けての取り組みについて述べる.
1 0 0 0 OA 母子間における嗅覚シグナル
- 著者
- 刀川 夏詩子
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.279-281, 2015-07-25 (Released:2019-02-20)
- 参考文献数
- 18
1 0 0 0 OA 実践現場における発達研究の役割 実践的研究者と研究的実践者を目指して
- 著者
- 無藤 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.407-416, 2013 (Released:2015-12-20)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 3
本論文は,発達心理学が実践現場に役立つ可能性を,保育を例として検討する。特に,その問題を,研究が実践にどう役立つのかというより大きな問題の一部としてとらえる。発達心理学を含めた研究の進展が,実践と研究の関連を変えてきている。その中で,エビデンスベーストのアプローチがその新たな関連を作り出した。また,実践研究の積み上げを工夫する必要がある。実践を対象とする研究として,実践者自身によるものと,実践者と研究者の協働によるアクションリサーチ,そして研究者が実践を観察し分析するものが分けられた。さらに,関連する研究として,子ども研究全般,カリキュラムや指導法に示唆を与える研究,社会的問題に取り組む研究,エビデンスを提供する研究,理論枠組みを変える基礎研究,政策へ示唆を与える研究などに分けて,各々の特質を検討した。実践現場から研究を立ち上げることが重要だと指摘した。最後に,研究的実践者と実践的研究者の育成を目指すことが提言された。
1 0 0 0 OA 日本画の手法を用いたコンピューターグラフィックスによる森林風景の再現
- 著者
- 吉岡 太郎 熊谷 洋一 斎藤 馨
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.265-270, 1993-03-31 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
コンピューターテクノロジーの進歩によって, 豊富な情報を可視化することが可能になり, 現在では, 非常に美しいフォトリアリスティックな森林風景を再現することもできる。しかしそれらは, 「そこにあるもの」を基本とし「そこに見えるもの」について考えられているものではない。最近の脳生理学の研究によって, 視覚情報は脳の中で (ニューロンレベルでも) 再構成され, それによって変化しているということが明らかにされている。したがつて, これからのCGは, 豊富な情報を分かりやすい形に再構成するという点も考慮する必要がある。本研究は, 日本画の手法を応用し, 我々が「見ている」形に視覚情報を再構成するという新たな試みである
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経バイト (ISSN:02896508)
- 巻号頁・発行日
- no.217, pp.92-99, 2001-06
Linuxでファイアウォールを実現するための実践に入ろう。ここまで述べてきたように,Linuxではパケット・フィルタリングやIPマスカレードの機能をカーネルに実装している。この設定にipchainsというプログラムを用いる注9)。ここでは,まず前半でipchainsの使い方を説明する。後半では実際の利用環境を想定し,そのそれぞれについて設定方法を紹介する注10)。
- 著者
- TAKAHASHI JUNICHI GYOBA JIRO
- 出版者
- 東北大学文学研究科心理学研究室
- 雑誌
- Tohoku psychologica folia (ISSN:00408743)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, pp.26-32, 2021-03-26
1 0 0 0 Linuxで作る社内サーバー(4)運用ツールをそろえる
- 著者
- 緒方 俊輔
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コミュニケ-ション (ISSN:09107215)
- 巻号頁・発行日
- no.304, pp.156-161, 1999-10-18
今回は,Linuxサーバーを運用するためのソフトの設定方法と使い方を説明します。セキュリティ確保のためのIPマスカレード機能,アクセス制御ソフト「tcp_wrappers」や,各種運用管理ツールを取り上げます。(本文中→マークの用語は欄外で解説) Linuxで構築した業務サーバーでは,運用のためのソフトを豊富に入手できます。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経network (ISSN:1345482X)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.54-57, 2002-09
攻略編に入る前に,アドレス変換の基本であるNATとIPマスカレードのしくみをじっくりと確認しておこう。 NATとIPマスカレードを同一視して語られることもあるが,技術的に見ると少し違う。この準備編では,アドレス変換のカラクリを解き明かし,NATとIPマスカレードの違いを確認していこう。 アドレス変換は,IPアドレスの体系が違うネットワーク同士をつなぐ。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経network (ISSN:1345482X)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.58-65, 2002-09
NATやIPマスカレードによって,LANとインターネットがつながり,Webアクセスや電子メールの送受信などは何の問題もなく使えるようになる。ところが,インターネットと直接つなぐとキチンと動くのに,アドレス変換が介在するとうまく通信できなくなってしまうアプリケーションもある。このような「アドレス変換問題」は,ブロードバンド・ルーターを使う最大の足かせにもなっている。
1 0 0 0 最新汎用ロジック・デバイス規格表
- 著者
- 猪飼國夫 相田泰志 デザインウェーブ編著
- 出版者
- CQ出版
- 巻号頁・発行日
- 2000
1 0 0 0 OA 琵琶湖全域で導入された産卵期のホンモロコ自主禁漁
- 著者
- 比較文化史研究会 [編]
- 出版者
- 比較文化史研究会
- 巻号頁・発行日
- 1999
1 0 0 0 IR フランスのNATO統合軍事機構離脱とドゴールの同盟政策
- 著者
- 山本 健太郎
- 出版者
- 関西学院大学法政学会
- 雑誌
- 法と政治 (ISSN:02880709)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.192-106, 2009-04