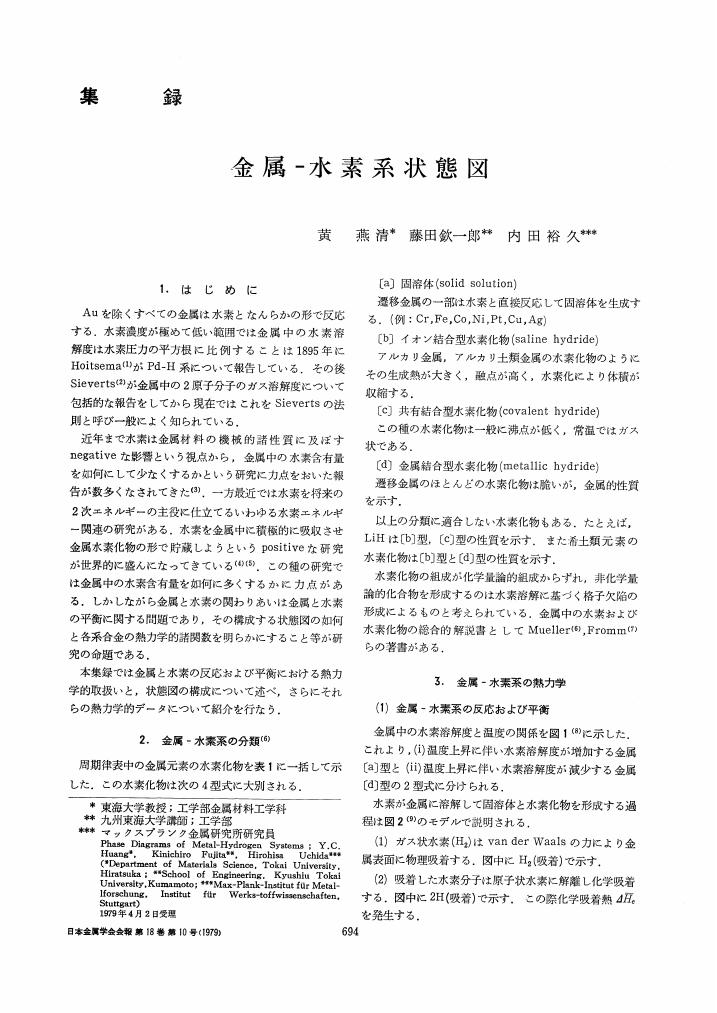1 0 0 0 OA 金属-水素系状態図
- 著者
- 黄 燕清 藤田 欽一郎 内田 裕久
- 出版者
- 社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会会報 (ISSN:00214426)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.10, pp.694-703, 1979-10-20 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 15 16
- 著者
- George P. Richardson
- 出版者
- University of Pennsylvania Press
- 巻号頁・発行日
- 1991
1 0 0 0 OA 精神科看護師の自尊感情の関連要因 ―患者に対する陰性感情経験を視野に入れた検討―
- 著者
- 松浦 利江子 鈴木 英子
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.319-328, 2017 (Released:2018-02-07)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2 2
目的:精神科看護師の自尊感情の関連要因を患者に対する陰性感情経験も視野に入れて明らかにし,看護師支援策を検討する.方法:9私立精神科病院に勤務する看護師737名を対象に質問紙調査を実施した.有効回答数は365名(49.5%)であった.調査内容は,基本的属性,職場環境要因,心理的健康,自尊感情尺度(Rosenberg, 1965;山本ら,1982)とし,自尊感情尺度合計得点を従属変数とした重回帰分析を行った.結果:重回帰分析の結果,自由度調整済み決定係数は0.44であった.自尊感情尺度合計得点と有意な関連が認められた要因は,環境制御力,患者に対する陰性感情経験への嫌悪度,既婚,職位が主任,コーピング行動は当事者と話し合う手法をとる,最長勤務領域が外科系病棟,であった.結論:患者に対する陰性感情への嫌悪感が過度にならない支援,患者を取り巻く精神科看護師も含めた人的・物的環境を制御する能力としての患者支援技術修得への支援,問題の当事者と話し合う対処方法修得への支援の重要性が示唆された.
1 0 0 0 IR 『日本十進分類法』新訂10版をめぐって (特集 分類新時代)
- 著者
- 藤倉 恵一
- 出版者
- 日本図書館協会
- 雑誌
- 現代の図書館 (ISSN:00166332)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.217-223, 2010-12
1 0 0 0 OA HDL, LDLコレステロールに対するγ-oryzanol (Hi-Z) の効果について
- 著者
- 岩崎 勤 松下 哲 折茂 肇 白木 正孝 萬木 信人 加藤 洋一 高橋 龍太郎 蔵本 築 村上 元孝 野間 昭夫 岡部 紘明
- 出版者
- 一般社団法人 日本動脈硬化学会
- 雑誌
- 動脈硬化 (ISSN:03862682)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.87-91, 1981-04-01 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
Effects of γ-oryzanol on the serum HDL, LDL and total cholesterol (ch) and Triglyceride were studied in 17 cases whose age was 47 years old to 82 years old (mean age was 71.2 years old). Three hundred mg/day of γ-oryzanol was given for 4 months.Serum HDL-ch was 50.0±2.3 (m±SE) mg/dl before γ-oryzanol and 53.7mg/dl 3 months later but HDL-ch which was below 50mg/dl before treatment increased significantly (p<0.01) from 43.3mg/dl to 50.4mg/dl 2 months later. HDL-ch below 45mg/dl increased significantly (p<0.01) from 41.3mg/dl (mean) to 50.0mg/dl (mean) 2 months later. LDL-ch decreased significantly (p<0.01) from 158.8mg/dl to 134.8mg/dl after γ-oryzanol. HDL-ch×10/LDL-ch showed significant changes (p<0.01) (from 3.26 to 4.14) 2 months later. Total-ch did not change and between 203mg/dl and 208mg/dl. Triglyceride did not show significant changes.It is suggested that γ-oryzanol alters the metabolism of HDL-ch and LDL-ch and increases serum low HDL-ch.
- 著者
- 星野 勇馬 中村 肇
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.8, 2006
- 著者
- 小川 伸彦
- 出版者
- 奈良女子大学文学部
- 雑誌
- 奈良女子大学文学部研究教育年報 (ISSN:13499882)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.15-32, 2013
1 0 0 0 OA 小曽根乾堂
- 著者
- 泉 賢司
- 出版者
- 國士舘大學武道徳育研究所
- 雑誌
- 國士舘大學武徳紀要 (ISSN:1346194X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, 1989-11
1 0 0 0 OA アリの種内及び種間の勢力関係について
- 著者
- 常木 勝次 安達 之彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.166-171, 1957-12-31 (Released:2017-04-08)
- 被引用文献数
- 3
A horizontal, well sun-shiny area of 16×20 sq. m. in the precincts of a temple, deeply surrounded by trees and shrubs, inhabited by four species of ants-Camponotus herculeanus japonicus MAYR (abbreviated to C), Formica fusca japonica MOTSCHULSKY (abbr. to F), Aphae-nogaster famelica SMITH (abbr. to A) and Tetramorium caespitum jacoti WHEELER (abbr. to T)-was adopted as the observation ground. It was sectioned into a net of 2 m (partly 1 m)meshes and was baited at all corners of the meshes with such small insects as house flies and the like. All the baits were numbered by means of a tiny label respectively which was attached with a silk thread, in order to make clear their original positions even when they were carried afar by the ant. They were always replaced by another new ones as soon as dragged off. Observations were made as to the species and the nest of the ant by which the bait was found and transported. Also every event occurred during the transportation was recorded in detail. The investigation was conducted during 8-10 o'clock a.m. every day from Aug. 3 to 26,1956. The records thus obtained were put in order on a sheet of section paper per species (Figs. 2,4 and 5) and the foraging range of each nest population, its size, form and distribution, as well as its intra-and interspecific relations were investigated. Also the social order among the species concerned could be elucidated through the observation of their behaviour during forage and bait transportation. The results can be summarized as follows : 1) Habitat segregation and territoriality can be observed, as a rule, among nest populations of the same species (Fig. 2,4 and 5). Such relations, however, could not be confirmed, as a rule, between populations of different species, although there can be admitted some tendency towards such a segregation between A and T, A and F and C and A. 2) Foraging distance is greatest in F, next to it in C and much less in A and T, the last mentioned two being nearly equal to each other in the range of their foraging. (Fig. 3). 3) Social order among the species concluded from the observation of the behaviour at the time when they met with one another is A=T>C>F. While the ratio of the total number of the baits carried away by each species is C>T>F>A. However, when the dimension of the ants is taken into consideration, it comes to be efficiently T>F>C>A. Possibly this is the practical scale of the population prosperity among them.
1 0 0 0 OA フーコーにおける権力論の転換 : 1976 年 講義の位置づけ
- 著者
- 北田 了介 Ryosuke Kitada
- 雑誌
- 関西学院経済学研究 (ISSN:02876914)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.81-108, 2013
1 0 0 0 OA 統一企業のチャネル政策を取り巻く台湾流通構造の特質 -日本との比較を通じて
- 著者
- 鍾 淑玲
- 出版者
- 立命館大学経営学会
- 雑誌
- 立命館経営学 = 立命館経営学 (ISSN:04852206)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.101-129, 2002-05
1 0 0 0 モバイルアドホックネットワークにおける位置推定手法の提案
- 著者
- 林国興 岩井祐太 西山裕之
- 雑誌
- 第73回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.1, pp.283-284, 2011-03-02
近年,携帯端末の高機能化,無線通信の向上などに伴い,これを用いた様々なサービスが普及しており,中でも,位置情報サービスにおいては,携帯電話へのGPS搭載義務化を受けより一層注目を集めている.しかしながら,屋内環境においてはGPSの取得が困難であるため,アクセスポイントや発信機といったインフラを利用した位置推定を行うシステムが多く提案されている一方,設置や初期設定などからユーザが容易に利用できるとは言い難い.本研究では,インフラを利用することなく,携帯端末によるアドホックネットワークを形成することにより相対的な位置を推定する手法を提案する.また,位置推定精度の評価実験を行い,システムの有効性を示す.
1 0 0 0 書評 岡崎正継著『中古中世語論攷』
- 著者
- 橋本 行洋
- 出版者
- 日本語学会 ; 2005-
- 雑誌
- 日本語の研究 = Studies in the Japanese language (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.27-34, 2021-04
1 0 0 0 OA 1970年代生まれはなぜ結婚しないのか?
- 著者
- 豊田 哲也
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2020年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.163, 2020 (Released:2020-03-30)
日本社会で進行する少子化の主因は未婚率の上昇にある。また,東京大都市圏では地方圏より出生率が低く,人口の一極集中が少子化を加速させている。若い世代は女性の社会進出の結果「結婚を選択しなくなった」のか,男性の経済力低下のため「結婚できなくなった」のか。本研究の目的は,地域格差と世代格差の視点から,都道府県別に推定した所得と未婚率の地域分析により,この二つの仮説を検証することにある。対象とするコーホートは就職氷河期(1993〜2004年)に大学卒業期を迎えた1970年代生まれの世代である。彼らが35〜39歳時点(2010年と2015年)における未婚率を目的変数とし,所得水準と就業環境を説明変数とする二通りのモデルで重回帰分析(MLS)をおこなった。使用するデータは国勢調査の人口と就業構造基本調査の年収である。地域による性比の偏りや都市化の程度をコントロールした上で,男の所得が低いまたは女の所得が高いほど両者の未婚率が高い傾向があり,二つの仮説はいずれも支持される。特に,就職氷河期における非正規雇用の拡大は男の所得水準低下をもたらし未婚率の上昇に寄与したと考えられるが,女の就業継続可能性に関する変数が未婚率に及ぼす影響は十分確認できなかった。
1 0 0 0 講演 量刑をめぐる理論と実務
- 著者
- 井田 良
- 出版者
- 司法研修所
- 雑誌
- 司法研修所論集 (ISSN:13425080)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.2, pp.203-238, 2005-03
1 0 0 0 OA セル生産ラインにおける作業者の標準外動作検知システムの開発
- 著者
- 西田 一貴 音田 浩臣
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.149-155, 2020-05-15 (Released:2020-08-15)
- 参考文献数
- 8
In this paper, we propose a method to detect workers’ nonstandard motion in cell production lines. Our method consists of three features: (1) sensing motion of a person, (2) measuring the time of motion by using Dynamic Time Warping and (3) analysis of the motion time. We applied the method to a prototype cell production line in our factory and verified its effectiveness. In an interview with Industrial Engineer, we have confirmed that our system has the potential to reduce the time taken for discovering nonstandard motion from 10 hours to 2.5 hours. From the above, we conclude that our method can enhance the efficiency of cell production line improvement.
1 0 0 0 IR 全国高校野球選手権大会の教育学
- 著者
- 古田 栄作
- 出版者
- 大手前女子大学
- 雑誌
- 大手前女子大学論集 (ISSN:02859785)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.71-119, 1997
1 0 0 0 OA 社会環境によるプロシューマーの定義と活動動機の変化
- 著者
- 鴇田 彩夏
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.74-82, 2020-09-29 (Released:2020-09-29)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 1
Toffler(1980)によって提案されたプロシューマーの概念と活動は,情報技術や社会環境の変化によって拡大してきた。本稿の目的は,能動的な消費者として定義されているプロシューマーに関する研究をレビューすることによって,生産技術や社会的環境とともに変化するプロシューマーの定義と彼らの活動動機を明らかにすることである。プロシューマーの概念はさまざまな分野で応用され,類似した概念も複数存在する。これらの類似概念は活動の能動性の高さや他者へのモノ・サービスの提供という点で相違がある。これらの定義を活動の能動性と製品・サービスの消費主体という2つの軸で分類した上で,近年の社会環境に対応するためにプロシューマーの生産と利用にとどまらず,他者への提供も含めるべきであると指摘する。さらに,彼らの活動動機として,個人的動機と社会的動機に加えて,経済的動機についても考察する。最後に,これらを踏まえた上で今後の研究課題を提示する。
1 0 0 0 OA ナラ類集団枯損が発生したコナラ二次林における17年間のナラ類の生残と枯死
- 著者
- 西川 祥子 久保 満佐子 尾崎 嘉信
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.1, pp.1-6, 2020-02-01 (Released:2020-04-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 3
コナラ林におけるナラ枯れの進行過程とナラ類およびクリ(以下,ナラ類としてまとめる)の動態を明らかにするため,島根大学三瓶演習林の1 haのコナラ林で2001年から2018年の17年間のナラ類の生残および枯死,胸高直径の変化を調べた。ナラ枯れが確認された2012年から2014年の各年は枯死個体の分布も調べた。その結果,ナラ枯れ発生前は,ナラ類の小径木が枯死するものの胸高断面積合計は増加し,ナラ枯れの発生に伴い減少に転じた。ナラ枯れ発生初期の2012年と2013年はナラ枯れにより直径に関係なく枯死し,ナラ枯れが蔓延した2014年は小径木で枯死しやすく,ナラ枯れは谷で発生しやすかった。2013年と2014年は各1年でナラ枯れ発生前の5年分に近い本数が枯死した。2001年に426本あったナラ類は2018年に212本になり,ナラ枯れによる枯死率が18.1%,その他の要因による枯死率が32.2%と17年間ではナラ枯れによる枯死木の方が少なかった。しかしナラ枯れによって,短期間で枯死木が増加することに加え,大径木も枯死することで森林構造が大きく変化すると考えられた。
1 0 0 0 OA 山形県におけるナラ枯れ被害林分での森林構造と枯死木の動態
- 著者
- 斉藤 正一 柴田 銃江
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.5, pp.223-228, 2012-10-01 (Released:2012-11-22)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 13 15
ナラ枯れ被害を受けやすい森林特性や, 被害林再生の見込み, ナラ枯れが農山村の生活基盤に及ぼす影響を検討するため, 山形県において, ナラ林のタイプや被害程度の異なる林分の森林構造や, 被害木の分解過程などを調べた。ナラ枯れが始まってから10年内には, ほとんどのミズナラ林冠木は枯死したが, コナラ林冠木は少なくとも4割程度が生存した。激害ミズナラ林の林冠層植被率は28%だったが, 激害コナラ林では47%だった。さらに, コナラ林の亜高木層には少数ながら高木性樹種もみられた。そのため, ミズナラ林では高木層を欠く状態が長く続くが, コナラ林ではある程度の林冠修復が期待できる。しかし, 実生稚樹による天然更新は, ユキツバキを主とする常緑広葉樹が低木層を占有し続けるため, どちらのナラ林タイプでも困難だろう。また, ナラ枯れ枯死木の多くが5年ほどで倒伏したことから, 被害激化地域では, 倒木による電線切断や道路閉鎖などのライフラインの障害が数年内に頻繁に発生することが危惧される。