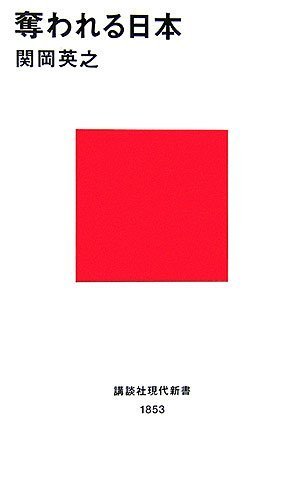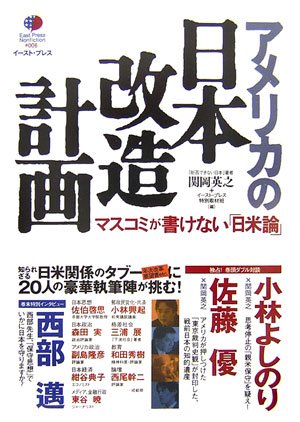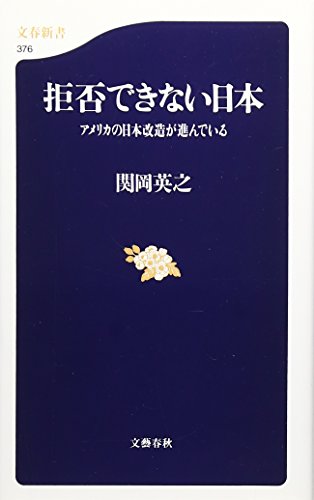1 0 0 0 OA ミョウガの生理生態的特性の解明並びに新作型開発に関する研究
- 著者
- 前田 幸二
- 巻号頁・発行日
- no.497, 1993
- 著者
- 佐伯 亮太 藤田 武彦 笹倉 みなみ 中村 義弘
- 出版者
- 一般財団法人 住総研
- 雑誌
- 住総研研究論文集・実践研究報告集 (ISSN:2433801X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.203-212, 2018
「団地の空室活用によるコミュニティづくりと団地再生の実践」1970 年代に建設された民間所有の5階建て階段室型団地(農住団地)の空室をシェアスペースに転用(DIY リノベーション)し活用することで,地域コミュニティづくり,団地住人の居住環境の改善,団地の入居率改善をねらった実践である。実践にあたっては,建物所有者,住人,外部協力者でのチームを立ち上げた。2017年10月現在,シェアスペースでは日常的に地域住民,団地住人が参加できるイベントが開催され,また団地の入居率も改善されるなど,一定の成果を見せている。本実践活動は,今後,急増することが予想される同様の建物の活用方法を模索するためのケーススタディである。
- 著者
- 藤川 祐輔
- 出版者
- 中村学園大学
- 雑誌
- 流通科学研究 (ISSN:13469614)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.43-56, 2004-10-01
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア = Nikkei architecture (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.1146, pp.70-74, 2019-06-27
付帯施設の建て替えで印象を一新。築21年の社宅が、街に開いた分譲マンションに生まれ変わった。里山の自然を切り取ったような緑化屋根と、日中は地域に開放されるシェアスペースが、住人と街をつなぐ。
- 著者
- 上野 雄一 椎葉 太一
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 年次大会講演論文集 2007.7 (ISSN:24331325)
- 巻号頁・発行日
- pp.65-66, 2007-09-07 (Released:2017-08-01)
This paper deals with a driving stability analysis method of a kart considering an elastic deformation of the kart frame. The stiffness matrix of the kart frame was calculated with the finite element method, and the vertical load of each tire simulation was analyzed with this stiffness matrix. In addition, the vertical load distribution was examined with tests to validate the stiffness matrix, and it was confirmed that the experimental results agree with simulation results. Furthermore, the driving stability was evaluated with simulations, and it was observed that the elastic deformation of the kart frame effects on the steering characteristic.
- 著者
- 武藤 徹一郎 小西 富夫 上谷 潤二郎 杉原 健一 久保田 芳郎 安達 実樹 阿川 千一郎 斉藤 幸夫 森岡 恭彦 沢田 俊夫
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.492-499, 1983
教室におけるCrohn病17例の経験を報告し,最近の外科的治療方針の動向について文献的考察を行った.手術は9例に行われ,残る8例はいずれも経静脈栄養によって管理することができた.9例中6例には吻合術が可能であった,痔瘻は8例に合併していたが,7例は通常痔瘻と性状が変わらず,lay openにて治癒した.<BR>欧米ではCrohn病に対する外科的治療として,小範囲切除を行う一派と広範囲切除を行う一派とがあり,主として前者には英米の専門家が,後者にはスカンジナビア,ドイツの専門家が属している.広範囲切除派は術中の凍結切片標本の検索により,病変の取り残しを防ぐことを主張している.これら欧米のCrohn病に対する外科治療方針の現況を紹介し,われわれの方針についても述べた.
1 0 0 0 OA 中小企業の為替デリバティブ問題と投資家保護に関する考察
- 著者
- 島 義夫
- 雑誌
- 論叢:玉川大学経営学部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.18, pp.15-32, 2012-07-31
大手銀行が中心となって中小企業向けに販売した為替デリバティブの巨額損失に関する紛争が裁判やADR(Alternative Dispute Resolution裁判外紛争処理手続き)に持ち込まれる例が急増している。これらの為替デリバティブ商品は、円安期間に「円安ヘッジ」目的で販売され、2008年リーマンショックを契機とする急激な円高で巨額損失が発生している。現在も、1万社を超す中小企業が、本業の黒字が為替損失で相殺され資金繰りにも困窮している。そして、その含み損により債務超過状態や倒産に陥る企業も少なくない。この問題は、その規模の大きさからして日本経済の観点からも無視できない。 この問題の争点としては、銀行の顧客適合性原則違反や説明義務違反などだけでは不十分である。「円安ヘッジ」として販売された当該商品は円安ヘッジ性に乏しく、複数のプット・オプション売りを含む「長期の為替投機商品」である。しかも、オプション売りの利益を銀行が確保したことで、当該商品は「ハイリスク・ローリターン」という経済的に不合理な商品になっており商品内容そのものが問題である。また、銀行の「優越的地位の濫用」の有無も今後裁判などで解明される必要があろう。 銀行による為替デリバティブの積極販売は、金融当局からの『金融再生プログラム』や「業務改善命令」などにより大手銀行経営が強力なプレッシャーを受けた時期と一致している。銀行の収益改善策の多くは成功しなかったが、結果的に中小企業へのデリバティブ販売手数料収入は銀行収益に貢献した。この問題を通じて、リテール投資家保護の在り方も再考が求められている。ADRの運用には中立性や専門性が必要だ。また、中途半端なADRよりも、個別の事情を勘案して公平な裁定ができる裁判の活用が求められており、そのためにも裁判のハードルを下げる努力が必要である。
- 著者
- 安倉 良二
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.3-20, 2016
本研究は,大店立地法に基づく大型店の出店調整について,奈良県と京都府にまたがる平城・相楽ニュータウンにある近鉄京都線高の原駅前を事例に,出店経緯と住民の対応に着目しながら考察した.大型店出店の背景として,空き地の有効活用を進めたい建物設置者と,大型店の出店規制緩和を契機に地域市場で優位に立とうとする小売業者の思惑が一致したことがあげられる.他方,生活環境の悪化を懸念する一部の住民は,運用主体である京都府に出店届出の内容に関する意見書を提出する形で出店調整に介入した.これに対して京都府は,大型店の建物設置者に対して出店届出の内容に関する改善を求める意見を出した.それをふまえて,建物設置者と小売業者は一部の住民との間で大型店の出店に向けた協議を重ねた.大店立地法に基づく大型店の出店調整は旧大店法とは異なり,出店自体を抑制するものではない.こうした制約下で運用主体から出店届出の内容に改善を求める意見が出されたことは,住宅地における大型店の出店に際して店舗に近接する住民の生活環境への慎重な配慮が不可欠であることを示す.
- 著者
- HIRANO Emiko
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室
- 雑誌
- Slavistika : 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室年報
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.207-222, 2012-03-08
1 0 0 0 OA 急性肺損傷(ALI),急性呼吸促迫症候群(ARDS)の病態と診療
- 著者
- 藤島 清太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.10, pp.819-827, 2010-10-15 (Released:2010-12-04)
- 参考文献数
- 40
急性肺損傷(ALI),急性呼吸促迫(窮迫)症候群(ARDS)は,種々の原因や基礎疾患に続発して急性に発症し,その原因が心不全,腎不全,血管内水分過剰のみでは説明できない肺水腫の総称である。病理学的にはびまん性肺胞障害(DAD)を呈し,病態生理学的には,肺胞領域を中心とした好中球主体の急性炎症と,肺胞上皮細胞,血管内皮細胞の傷害,および肺微小血管透過性の亢進を認める。本症候群の診断においては,Bernardらによるアメリカ胸部疾患学会とヨーロッパ集中治療医学会の合意会議(American European Consensus Conference; AECC)の定義が標準的であるが,その他にもMurrayらの拡大定義などが用いられる。これらの臨床的診断基準は比較的簡便で,とくにAECCのものは診断感度が高いが,特異度は十分に高くなく,類似病態の除外に留意を要する。すなわち,静水圧性肺水腫,各種呼吸器感染症,好酸球性肺炎(AEP),びまん性肺胞出血(DAH),特発性器質化肺炎(COP, BOOP),剥離性間質性肺炎(DIP),過敏性肺臓炎(HP),膠原病肺,リンパ脈管筋腫症(LAM),肺血栓塞栓症(PE),悪性腫瘍,急性拒絶反応,薬剤性肺障害などとの鑑別が必要である。鑑別診断を行う上で肺生検が最も正確と思われるが,現実的な選択枝とはなり難く,これに代わる実用的な検査手段として気管支肺胞洗浄(BAL)が重要である。ALI/ARDSの基礎・原因傷病としては,直接傷害として有毒物質の吸入,細菌性肺炎などの重症呼吸器感染症,誤嚥性肺炎,脂肪塞栓症候群(FES),肺挫傷など,また間接障害として敗血症を含む重症感染症など様々なものがある。したがって,これらに続発して発症するALI/ARDSの病態も多様であり,基礎・原因傷病ごとに最適な治療法が異なる可能性がある。
1 0 0 0 OA 江戸時代文献「うつろ船の蛮女」に描かれている「宇宙文字」の正体
- 著者
- 皆神 龍太郎
- 雑誌
- 文化科学研究 = cultural sciences
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.(1)-(8), 2014-03-15
1 0 0 0 アメリカの日本改造計画 : マスコミが書けない「日米論」
- 著者
- 関岡英之 イースト・プレス特別取材班編
- 出版者
- イースト・プレス
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 拒否できない日本 : アメリカの日本改造が進んでいる
- 著者
- ENNAHACHI Zakaria
- 出版者
- 立命館アジア太平洋大学
- 巻号頁・発行日
- 2019-03-31
1 0 0 0 IR 豊臣期宇喜多氏の構造的特質
- 著者
- 森脇 崇文 Moriwaki Takafumi モリワキ タカフミ
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 待兼山論叢 (ISSN:03874818)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.27-52, 2012
1 0 0 0 IR 訪問客と共に作るイベント・コンベンション : ドイツのConnichiを通して
- 著者
- 金 兌娟 Kim Teyon キム テヨン
- 出版者
- 大阪大学大学院言語文化研究科
- 雑誌
- 言語文化共同研究プロジェクト
- 巻号頁・発行日
- no.2017, pp.33-42, 2018-05-30
表象と文化 (15)
- 著者
- 渡辺 千花 Watanabe Chika ワタナベ チカ
- 出版者
- 「宗教と社会貢献」研究会
- 雑誌
- 宗教と社会貢献 (ISSN:21856869)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.23-48, 2011-10
近年、多くの社会科学者の間では国際支援を行うNGOはネオリベラリズムの統治制度を促進していると批判されてきた。本稿ではネオリベラリズムへの批判では完全に説明できない活動の例として神道系新宗教から生まれた財団法人オイスカを紹介する。特に(1)オイスカと政府関係者の歴史的関係、(2)オイスカの研修活動を主体と客体の相互関係性にもとづいた主体形成の一例として考察する。この視点は宗教とNGOの関連を追究することによって可能であり、ネオリベラリズムの枠を越えたNGO研究の新たな視座を提示する試みである。
- 著者
- 要木 香苗
- 出版者
- 公益社団法人 日本航海学会
- 雑誌
- 日本航海学会誌 NAVIGATION (ISSN:09199985)
- 巻号頁・発行日
- vol.180, 2012
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 国内における外国人犯罪と法的課題 ー 多文化共生社会実現に向けた意識調査からの考察 ー
- 著者
- 大重 史朗
- 雑誌
- 中央学院大学法学論叢 = The Chuo-Gakuin University review of Faculty of Law (ISSN:09164022)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.119-137, 2017-09-20