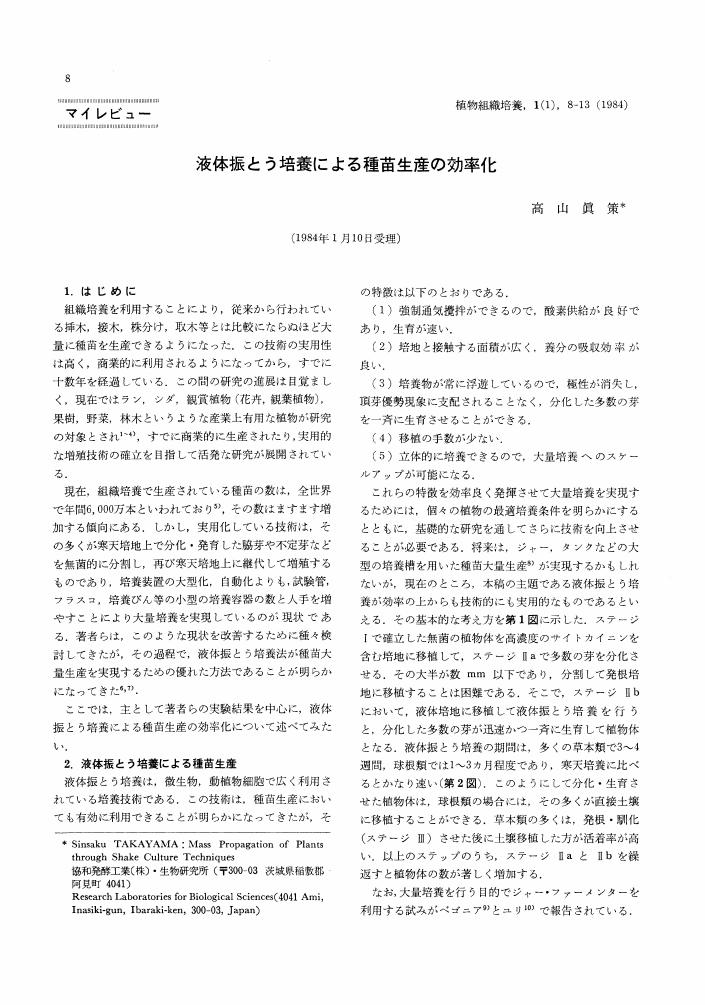1 0 0 0 OA 神経性食思不振症を発症し心房粗動を合併した成人先天性心疾患の1例
- 著者
- 櫻井 史紀 岩島 覚 早野 聡 佐藤 慶介 芳本 潤
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.181-187, 2020-02-15 (Released:2021-04-22)
- 参考文献数
- 23
成人先天性心疾患に神経性食指不振症を合併し経過中に心房粗動(atrial flutter;AFL)を発症した19歳女性を経験した.症例は生後に心雑音に気づかれventricular septal defect(VSD perimenbranous type),pulmonic stenosis(PS, valvular and subvalvular stenosis)と診断.3歳3カ月時に人工心肺管理下にVSD閉鎖術,右室流出路形成術施行.術後経過は良好であったが,16歳頃より神経性食思不振症(anorexia nervosa;AN)と診断され,その頃より動悸を自覚,入浴後に突然動悸が持続し救急外来受診,AFLが疑われたが,不整脈治療準備中に自然頓挫し動悸の症状も消失した.不整脈発症前の心臓MRI検査で右房右心系の拡大とpulmonary regurgitation fraction 39.8%を認め,ANの治療が長期に及ぶ可能性があったため心臓電気生理学検査を施行,三尖弁輪を反時計方向に旋回する頻拍が誘発されAFLと診断,アブレーション療法施行.その後の経過は良好であった.成人先天性心疾患症例では経年的に不整脈を合併するリスクがあるがAN等,不整脈を合併しやすい病態を合併した場合,さらに不整脈発症のリスクが高まる可能性があるため注意深い観察が必要と思われた.
1 0 0 0 時事・プロジェクト ゆいレールの契約解除問題で和解成立
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経コンストラクション = Nikkei construction (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.738, 2020-06-22
沖縄都市モノレール(那覇市)が運営する「ゆいレール」の駅舎関連工事の契約解除を巡り、建設会社が発注者の沖縄県を訴えた裁判で、2020年4月に和解が成立していたことが分かった。工期延長に関するトラブルで、県が契約を解除していた。 県は契約解除の手…
- 著者
- 轟木 靖子
- 出版者
- 香川大学教育学部
- 雑誌
- 香川大学教育学部研究報告 第Ⅰ部 = Memoirs of the Faculty of Education, Kagawa University. Part I (ISSN:04549309)
- 巻号頁・発行日
- no.151, pp.47-56, 2019-03-31
1 0 0 0 IR 福岡市方言の文末詞「バイ」「タイ」の福岡部若年層における使用実態と代替形式について
- 著者
- 髙山 彩
- 出版者
- 熊本女子大学国文談話会
- 雑誌
- 國文研究 (ISSN:09148345)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.126-59, 2016-08
1 0 0 0 OA 静岡県特種産物調査
- 著者
- 静岡県農会事務所 編
- 出版者
- 静岡県農会事務所
- 巻号頁・発行日
- vol.続, 1915
- 著者
- 片山 綾 佐伯 大輔
- 出版者
- 大阪市立大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 人文研究 : 大阪市立大学大学院文学研究科紀要 = Studies in the humanities : Bulletin of the Graduate School of Literature and Human Sciences, Osaka City University (ISSN:04913329)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.129-142, 2020
「将来のために禁煙して健康な身体を手に入れるか、目の前の煙草を吸うか」といった、将来の目標達成と目先の快楽のどちらを選択するかの問題は、心理学の様々な分野において、セルフ・コントロールの問題として扱われてきた。本稿では、遅延される大きな利得を選択することをセルフ・コントロール、即時に得られる小さな利得を選択することを衝動性と定義し、これまで行われてきたセルフ・コントロール研究を概観する。まず、心理学におけるセルフ・コントロール研究の先駆けである満足の遅延パラダイムに基づいた基礎研究とその応用可能性、さらにそれに関連したセルフ・コントロールの強度モデルについてその概要を説明し、問題点を指摘する。次に、その問題点を解消するために、セルフ・コントロールを行動分析学の観点から扱う意義について考察し、これまで行動分析学で行われてきたセルフ・コントロールに関する基礎研究とその課題について整理する。最後に、それらの課題を踏まえて片山・佐伯(2018)によって新しく提案されたパラダイムを紹介し、基礎研究と応用研究の両方の側面から、今後の展望を述べる。
1 0 0 0 OA 東アフリカにおける新規商品作物導入過程の地域農学的研究
1 0 0 0 IR 介護の社会化論と介護の歴史認識再考
- 著者
- 三富 紀敬
- 出版者
- 立命館大学経済学会
- 雑誌
- 立命館経済学 (ISSN:02880180)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.986-996, 2011-03
- 著者
- 井上 智宏 林 英治
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会学術講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.521-522, 2012
自動演奏ピアノで用いるデータは楽譜上の音符全てを表現したものであり、編集に多くの時間を必要とする。そこで、「同一演奏者では、音符の並びが類似するフレーズではその演奏表現も類似する」という研究結果を用いて、効率的な編集支援システムの開発を行った。本システムでは編集済みの楽曲上で未編集のフレーズと類似したフレーズを探索し、発見されたフレーズの表現をもとに未編集のフレーズを推論する。
1 0 0 0 OA シャルル・フーリエと階級調和の方策:「資本」の分配を中心に
- 著者
- 大塚 昇三
- 出版者
- 北海道大学經濟學部
- 雑誌
- 經濟學研究 (ISSN:04516265)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.101-113, 1987-09
1 0 0 0 北アルプス槍ヶ岳をめぐる登山観光地域の変容
- 著者
- 猪股 泰広
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, 2015
<b>1.はじめに<br></b> 近年,富士山の世界文化遺産登録や国民の祝日としての「山の日」制定など,山岳地域への関心が高まっている.観光対象としての山岳地域は,自然・文化の多様性や非日常性といった多くの魅力を有する一方で,人間活動の影響に対して実に脆弱である(Nepal and Chipeniuk 2005).人間による利用が進むこと,およびそれに伴い必要となる保全施策が進むことで,本来的に山岳地域が有する魅力を享受できなくなる,すなわち利用体験の破壊が生じるため(八巻 2008),利用目的や環境に応じた地域づくりが必要とされている.これについて,レクリエーション機会多様性(ROS)概念を用いた検討は多数なされているが,あくまで現況の指標に基づくものであり,地域的文脈はあまり考慮されていない.そこで本研究では,近代登山発祥以降の観光利用の進展が顕著な北アルプス槍ヶ岳周辺地域を対象に,山小屋の機能や周辺環境の変化に着目することで,登山観光地域の変容過程を明らかにし,今後の地域づくりの指針を得ることを目的とする.<br><b>2.対象地域<br></b> 槍ヶ岳(標高3180 m)は,長野県,岐阜県の境界に位置する北アルプス南部・槍穂高連峰の主要ピークである.東側に連なる常念山脈の存在や梓川沿いの地形の急峻さにより,近代登山発祥(1900年頃)以前は信仰登山目的などで僅かな人が立入るのみであった.1916年に営林署による島々~徳本峠,明神~槍ヶ岳の登山道が整備されて以降,要衝における山小屋開業とともに,槍ヶ岳周辺地域は登山観光地としての性格を表し始めた.槍穂高連峰や常念山脈は一帯が国有林であり,また中部山岳国立公園に指定されている.<br><b>3.登山の大衆化と地域の変容<br></b> 1920年前後,槍ヶ岳をめぐる登山道整備の進展に伴い山小屋の開業が相次いだ.当時は登山者の宿泊・休憩だけでなく,より高所にある山小屋への物資補給のための歩(ぼっ)荷(か)の中継施設としての機能を担う山小屋が多かった.1927年の釜トンネル開通,1929年のバス運行開始により,登山の起点が上高地に移ると,小屋の収容能力を超えるほどの登山者が訪れるようになった.高度経済成長を迎える頃には,収容人数増を目的とした小屋の増築が進んだことと,物資運搬手段としてのヘリコプター導入により,歩荷では不可能であった重い建材や新鮮な食料の供給が可能になったことが,設備充実や美味しい食事の提供をもたらし,登山者の利用体験の向上につながり,登山の大衆化を推し進めた. <br> 1970年代になると環境問題が顕在化し,1975年には国立公園で初となる上高地マイカー規制が実施された.こうしたことによる登山停滞期を経て,1990年頃から中高年,とくにレートビギナー層による登山が卓越するようになった.これを受けて,定員数百人の大規模な山小屋では,調理用コンベクションオーブンやビールサーバーを導入するなど,更なるサービスの向上を図っていた.一方で,増加する登山者の環境影響やそれに伴う利用体験の悪化を最小限に抑えるため,無放流水洗トイレの導入や官民連携での登山道整備の取り組みなどが行われている.今後の登山者の質的変化により,地域に求められるものも変化するであろう.
1 0 0 0 OA 液体振とう培養による種苗生産の効率化
- 著者
- 高山 眞策
- 出版者
- Japanese Society for Plant Cell and Molecular Biology
- 雑誌
- 植物組織培養 (ISSN:02895773)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.8-13, 1984 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 100
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- Yoshinori Abe Keisuke Meguriya Takahisa Matsuzaki Teruki Sugiyama Hiroshi Y. Yoshikawa Miyo Terao Morita Masatsugu Toyota
- 出版者
- Japanese Society for Plant Biotechnology
- 雑誌
- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.405-415, 2020-12-25 (Released:2020-12-25)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1 7
Intracellular sedimentation of highly dense, starch-filled amyloplasts toward the gravity vector is likely a key initial step for gravity sensing in plants. However, recent live-cell imaging technology revealed that most amyloplasts continuously exhibit dynamic, saltatory movements in the endodermal cells of Arabidopsis stems. These complicated movements led to questions about what type of amyloplast movement triggers gravity sensing. Here we show that a confocal microscope equipped with optical tweezers can be a powerful tool to trap and manipulate amyloplasts noninvasively, while simultaneously observing cellular responses such as vacuolar dynamics in living cells. A near-infrared (λ=1064 nm) laser that was focused into the endodermal cells at 1 mW of laser power attracted and captured amyloplasts at the laser focus. The optical force exerted on the amyloplasts was theoretically estimated to be up to 1 pN. Interestingly, endosomes and trans-Golgi network were trapped at 30 mW but not at 1 mW, which is probably due to lower refractive indices of these organelles than that of the amyloplasts. Because amyloplasts are in close proximity to vacuolar membranes in endodermal cells, their physical interaction could be visualized in real time. The vacuolar membranes drastically stretched and deformed in response to the manipulated movements of amyloplasts by optical tweezers. Our new method provides deep insights into the biophysical properties of plant organelles in vivo and opens a new avenue for studying gravity-sensing mechanisms in plants.
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経ビジネス = Nikkei business (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.2026, pp.42-45, 2020-01-27
「彼のおかげでウィンドウズ中心主義のアプローチから離れることができた」。米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏がこう称賛する人物がいる。サティア・ナデラ氏。同社のCEO(最高経営責任者)を務める。
1 0 0 0 OA 日系作家ヒサエ・ヤマモトの短編に描かれた他者としての記憶
- 著者
- 飯田 深雪
- 出版者
- 神奈川県立国際言語文化アカデミア
- 雑誌
- 神奈川県立国際言語文化アカデミア紀要 (ISSN:21867348)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.29-38, 2018 (Released:2018-04-10)
- 著者
- Kaori Matsuyama Naoki Sunagawa Kiyohiko Igarashi
- 出版者
- Japanese Society for Plant Biotechnology
- 雑誌
- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.397-403, 2020-12-25 (Released:2020-12-25)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1 4
The study of Carbohydrate-Active enZymes (CAZymes) associated with plant cell wall metabolism is important for elucidating the developmental mechanisms of plants and also for the utilization of plants as a biomass resource. The use of recombinant proteins is common in this context, but heterologous expression of plant proteins is particularly difficult, in part because the presence of many cysteine residues promotes denaturation, aggregation and/or protein misfolding. In this study, we evaluated two phenotypes of methylotrophic yeast Pichia pastoris as expression hosts for expansin from peach (Prunus persica (L.) Batsch, PpEXP1), which is one of the most challenging targets for heterologous expression. cDNAs encoding wild-type expansin (PpEXP1_WT) and a mutant in which all cysteine residues were replaced with serine (PpEXP1_CS) were each inserted into expression vectors, and the protein expression levels were compared. The total amount of secreted protein in PpEXP1_WT culture was approximately twice that of PpEXP1_CS. However, the amounts of recombinant expansin were 0.58 and 4.3 mg l−1, corresponding to 0.18% and 2.37% of total expressed protein, respectively. This 13-fold increase in production of the mutant in P. pastoris indicates that the replacement of cysteine residues stabilizes recombinant PpEXP1.
1 0 0 0 OA 食糧生産と応用物理
- 著者
- 高辻 正基
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.8, pp.909-913, 1999-08-10 (Released:2009-02-05)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
異常気象,土地浸食などの環境問題や人口増大の影響で, 21世紀前半以降の人類の食糧問題が懸念されている.従来の土地利用型農業だけでは,特に日本の食糧を支えきれない可能性がある.そこで,植物工場のような超集約的食糧生産技術の実用化が期待される.応用物理的技術の応用として,発光ダイオードやレーザーダイオードを植物栽培用の光源として利用する可能性について論じる.
1 0 0 0 ネット検索の達人(2)人の名前からさまざまな情報を知る
- 著者
- 大内 範行
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.462, pp.147-150, 2004-07-19
営業先の社長を検索する/役に立つGoogleの紹介文/画像検索で人物の顔を知る/同姓同名の名前の場合は/自分や子供の名前で検索/子供の名前はGoogleで/ビル・ゲイツ氏が次に狙うのは検索市場/
- 著者
- 西 和彦 東 昌樹
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経ビジネス = Nikkei business (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.2030, pp.86-89, 2020-02-24
米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏とともに、日本のパソコン産業の黎明期を支えた。だが、マイクロソフトからも自身が創業したアスキーからも追われ、教育の道へ。コンピューター産業の育成に、"オタク"が集う大学の設立構想を描く。