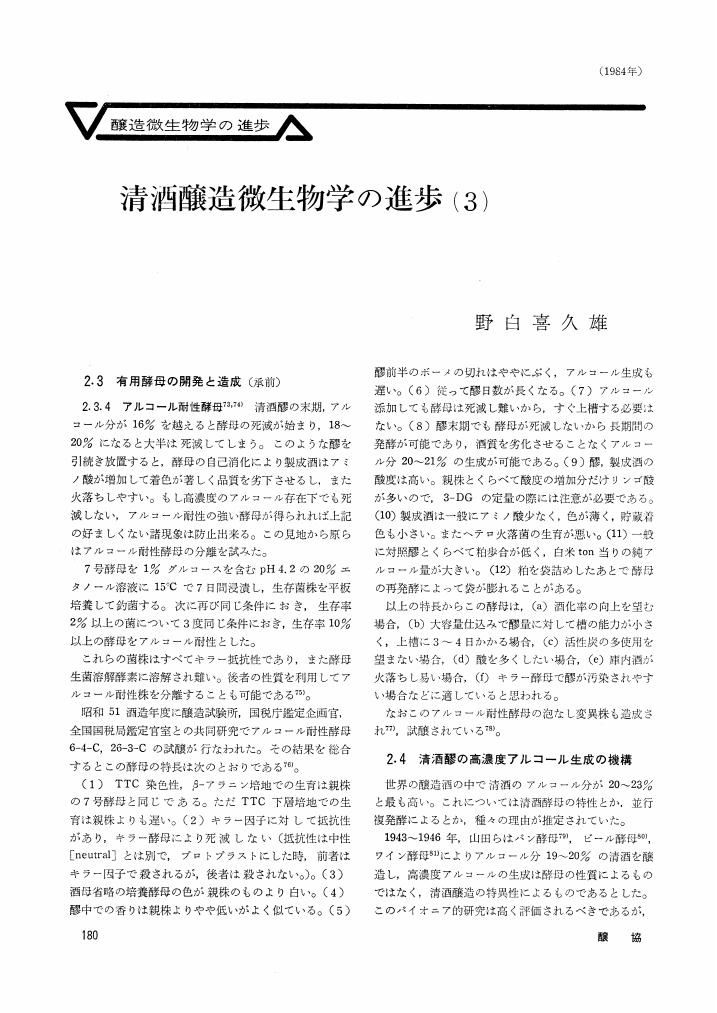1 0 0 0 OA 宥和情報が生理的喚起および報復攻撃におよぼす効果
- 著者
- 大平 英樹
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.95-104, 1989-02-20 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2 2
本研究では, 宥和情報による責任性についての評定が生理的喚起と報復攻撃の強度決定におよぼす効果について検討した。宥和情報の提示時期 (攻撃前, 攻撃後) と宥和晴報の程度 (中程度, 高程度) が独立変数として操作され, さらに宥和情報を与えない統制群を加えて5つの実験群が設けられた。被験者は教師一生徒パラダイムの第1試行において実験協力者から強い攻撃を受け, 第2試行において報復の機会が与えられた。本研究において得られた主な結果は以下のとおりである。1. 攻撃を受けることにより各群被験者の生理的喚起の上昇がみられたが, 宥和情報を攻撃前に提示された群では上昇の程度が他の群に比べて低かった。2. 直接的攻撃と間接的攻撃という2つの相異なったタイプの報復攻撃がみられた。3. 直接的攻撃では, 宥和情報の程度が高い場合は提示時期にかかわらず攻撃低減の効果がみられたが, 中くらいの程度の場合は攻撃前に提示したときにのみ攻撃低減の効果があった。ここでは, 生理的喚起と攻撃者の責任の評定の両方が報復攻撃の規定因となっていることが示唆された。4. 間接的攻撃では, 報復攻撃の強度は宥和情報が攻撃前に提示された場合にのみ低減され, 宥和情報の程度は効果を持たなかった。ここでは, 生理的喚起が報復攻撃の重要な規定因なっていることが示唆された。
1 0 0 0 OA ボッカッチョIl Filostratoにおける動詞活用について
- 著者
- 西村 政人 ニシムラ マサヒト Masahito Nishimura
- 雑誌
- 雲雀野 = The Lark Hill
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.11-26, 2008
Boccaccio's Il Filostrato is essential for studying Chaucer's Troilus and Criseyde. However, while reading this work, it was apparent that there are many verbs whose conjugations are different from those in contemporary Italian. The purpose of this paper is to clarify the conjugations of the verbs used in Il Filostrato. First, the present author discusses the overall features of the Italian verbs that appear in this work from both morphologic and syntactic viewpoints. Second, the author deals with the verbs, avere and essere, and makes their special conjugations clear. Part of the conclusions in this paper are stated below. 1. Il Filostrato is a poetic work. Therefore, poetic rules affect the conjugations of the Italian verbs. 2. Boccaccio uses special conjugations if verbs are placed at the end of the line. 3. Different conjugations of avere and essere can be observed in the future, imperfect, past historic, present subjunctive and present conditional tenses.
1 0 0 0 IR 中学生における仲間関係の発達と受容感およびネット利用との関連
- 著者
- 中島 浩子 関山 徹
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要 (ISSN:09175865)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.203-215, 2016
1 0 0 0 IR 日本の精神保健福祉施策の展開とリカバリーに関する一考察
- 著者
- 中條 大輔 ナカジョウ ダイスケ Daisuke Nakajyo
- 出版者
- 鹿児島国際大学大学院
- 雑誌
- 鹿児島国際大学大学院学術論集 (ISSN:18838987)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.19-33, 2016-11
It is hard to say that the notion of recovery is still entrenched in Japan when we think of the current state of Japan's psychiatric care and average length of stay, which is projected especially with reference to the case of dependents of special provisions for psychiatric and private hospitalization. Consider a historical overview of Japan's mental health and welfare measures. From the "Accommodation of the Home of Psychiatric Patients," "Psychiatric Patients' Custody Law," and "Mental Hospital Law" to the modern "Law Related to Mental Health and Welfare of the Person with Mental Disorder," and the post-war "Mental Hygiene Law," mental health and welfare measures that focus on isolation and hospitalization of the psychiatric patient continue to be mandatorily implemented. Thus, the main determiner for recovery continues to be the nation, indicating that the norm of subjectivity, as determined by the user in the treatment, has not existed for a long time. Indeed, this is the greatest factor inhibiting the users' recovery. In the future, we must seek more reflective concepts for recovery in mental health and welfare measures.
- 著者
- 大塚 俊弘
- 出版者
- 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所
- 雑誌
- 精神保健研究 = Journal of mental health : official journal of the National Institute of Mental Health, NCNP, Japan (ISSN:0915065X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.64, pp.63-66, 2018
1 0 0 0 アンチスティグマ活動-当事者の声を発信する意義-
1 0 0 0 スティグマと社会福祉 : 我が国の公的扶助をめぐって
- 著者
- 西尾 祐吾
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.1-23, 1988
Firstly, I tried to describe to the implications of discussing "stigma" in Japan, today explicating the meaning of the term "stigma". Then I outlined tke contents of "Stigma and Social Welfore" by P. Spicker, 1984, Croom Helm, in which the relation between stigma and social welfare has been dealt with systematically and preponderantly for the first time. Lastly, focusing on public assistance, I discussed the various phenomena of stigma seen in the present practices of social welfare in our country.
1 0 0 0 OA 清酒醸造微生物学の進歩 (3)
- 著者
- 野白 喜久雄
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.180-184, 1984-03-15 (Released:2011-11-29)
- 参考文献数
- 41
- 著者
- 伊東 俊夫 中山 志郎
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.445-449, 1998-01-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 3
症例は64歳, 女性。平成7年10月より胸部, 下肢に点状出血斑が出現したため受診。ITPと診断し, ツムラ加味帰脾湯を投与したが, 血小板数の増加を認めないために入院。入院時血小板数は4.3万/μl。プレドニゾロン50mg/日の投与を開始したところ, 血小板数は20.0万/μlまで増加した。しかし, プレドニゾロンの漸減後は4.4万/μlまで低下した。そのために加味帰脾湯を併用で再投与したところ, 血小板数は最高27.1万/μlまで増加した。現在, プレドニゾロン8mg/日と加味帰脾湯の併用で外来通院中であるが, 血小板数は約10万/μlで, 経過良好である。本症例は加味帰脾湯単独投与では効果がみられなかったが, 副腎皮質ホルモン剤の減量後の再発時に再投与して血小板数の著しい増加を認めた点が興味深い症例である。今後, 副腎皮質ホルモン剤の減量の時に加味帰脾湯を併用することは再発を予防するために有意義であろうと結論した。
1 0 0 0 OA 青年期における友人との活動と友人に対する感情の発達的変化
- 著者
- 榎本 淳子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.180-190, 1999-06-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 27 14
本研究は, 青年期の友人関係の発達的な変化を明らかにすることが目的である。青年期の友人関係を友人との「活動的側面」と友人に対する「感情的側面」の2側面から捉え, これらの関連とそれぞれの発達的な変化を質問紙を用いて検討した。対象者は中学生 (326名), 高校生 (335名), 大学生 (247名) の計 908名であった。因子分析の結果, 活動的側面については4因子 (「相互理解活動」, 「親密確認活動」, 「共有活動」, 「閉鎖的活動」) が見いだされた。発達的変化としては, 男子は友人と遊ぶ関係の「共有活動」からお互いを尊重する「相互理解活動」へと変化し, 女子は友人との類似性に重点をおいた「親密確認活動」から他者を入れない絆を持つ「閉鎖的活動」へと変化し, その後「相互理解活動」へ変化した。感情的側面については, 因子分析から5因子 (「信頼・安定」, 「不安・懸念」, 「独立」, 「ライバル意識」, 「葛藤」) が見出された。また, 発達的変化は, あまり見られなかった。2側面の関連については, どの活動的側面も感情的側面の「信頼・安定」と関連しており, 親しい友人とは信頼し安定した感情で友人関係を築いていることがわかった。また, 活動的側面の「親密確認活動」は主に感情的側面の「不安・懸念」と関連しており, 「相互理解活動」は「独立」と関連していた。
1 0 0 0 OA 離婚後の親子の面会交流に関する研究
1 0 0 0 IR 大地震の発生と地体構造との関係〔英文〕
- 著者
- 茂木 清夫
- 出版者
- 東京大学地震研究所
- 雑誌
- 東京大学地震研究所彙報 (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.429-451, 1969-06
The tectonic relief on the focal regions of great shallow earthquakes in the circum-Pacific belt and its surrounding regions is discussed in relation to the generation mechanism of great earthquakes. In Part I, relationship between the tectonic relief and the occurrence of the great ・earthquake (namely the great fracture) is discussed according to aftershock locations. The result shows that a great fracture suddenly occurs in a unit area or its complex which is bounded by structural discontinuities, such as faults, ridges and trenches. In a sequential occurrence of great earthquakes, a subsequent great fracture propagates from the margin of the adjacent fractured area. In Part II, the "tectonic features of the focal regions of the great shallow earthquakes are discussed in their broader aspects. According to the result, most great earthquakes occur in the tectonically limited regions, characterized mainly by topographical depression: About 64 percent of great earthquakes continuously occurred in ocean-facing slopes of deep sea trenches, about 26 percent occurred in local depressions, such as troughs and ends of trenches, and some singular places in tectonic structures, and only about 8 percent occurred in other tectonic areas. These results seem to give some important information on the earthquake generation mechanism.|大地震の起こり方の特徴についてこれまでいくつかの調査を行なってきたが,本報告では,地体構造,とくに長期の地殻変動のあらわれとみられる変動地形(断層や海溝)との関係について述べる.第I部では,大地震のときの大規模破壊の過程を反映しているとみられる余震の起こり方と構造との関係を述べ,第II部では,このような大地震の起こる場所の地体構造上の特徴を論ずる.今回の調査は,太平洋地域及びその周辺に限られている.次にその結果を要約する.第I部 大地震の余震と地体構造 アリューシャン,チリ,日本の大地震の余震の起こり方は,震源域の断層や海溝の分布と密接な関係を示し,次のような過程が推定される.即ち,大地震の際の大規模破壊は,既存の構造上の不連続線で境された単一若しくは複合ブロックで起こり,このブロックは海溝の陸側斜面にあって海溝にまたがらない.一つのブロックの破壊につづいて隣接ブロックの破壊が起こる場合が多く,その際破壊は既破壊ブロック寄りから進行する.第II部 浅い大地震の震源域の地体構造上の特徴 この様な大地震(又は大規模破壊)の起こり方を地体構造との関連の上からみると,約64%の大きい地震が大海溝の陸側斜面に連続的に分布し(Type A),約26%が小規模海溝の末端や局所的高まりなどに起こり(Type B),その他の地域に起こったもの(Type C)は僅かに10%にすぎない.即ち,大地震のほとんどは,Type A及びBに属するもので,その発生地域は極めて限定され,凹地形という共通の特微が指摘される.南米の北部チリ海溝及び伊豆・マリアナ海溝では例外的に浅い大地震が少ないが,ここではそれを補うように深い地震活動が活発である.以上,大地震の震源域は,大局的にも,局部的にも,地体構造と密接な関連を示し,これが大地震の発生機構を研究する上の重要な手掛りとなると思われる.
1 0 0 0 OA タグラグビーにおけるルール設定による主観的評価の検証 : ボールの争奪と継続
- 著者
- 廣瀬 文彦 早坂 一成 齊藤 武利
- 出版者
- 白鴎大学教育学部
- 雑誌
- 白鴎大学教育学部論集 = Hakuoh Journal of the Faculty of Education (ISSN:18824145)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.179-191, 2020-11-30
1 0 0 0 OA ハイテクベンチャーの企業存続におけるリスク要因分析~営業を主軸とした概念モデル構築~
- 著者
- 永富 靖章
- 巻号頁・発行日
- pp.3-55, 2017-03
- 著者
- 甘利 俊一
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.198-200, 2003-09-25 (Released:2017-04-08)
1 0 0 0 OA 慢性腎不全時におけるリンのコントロールの重要性 1.総論
- 著者
- 星 史雄
- 出版者
- 動物臨床医学会
- 雑誌
- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.101-105, 2015-09-30 (Released:2016-09-30)
1 0 0 0 OA 脳における生成とクオリア(<特集>知の起源)
- 著者
- 茂木 健一郎
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.385-391, 2003-07-01 (Released:2020-09-29)
1 0 0 0 OA E・ラクラウにおける主体概念の転回とラディカル・デモクラシー
- 著者
- 山本 圭
- 出版者
- 日本社会学理論学会
- 雑誌
- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.86-98, 2009 (Released:2020-03-09)
ラディカル・デモクラシーという現代民主主義理論のー潮流には、それ自体の内部においても多様なパースペクティブが存在しており、そのなかでも本稿が焦点を当てるのは、エルネスト・ラクラウの政治理論である。ラクラウの政治理論はこれまで、今日のアカデミズムへの甚大な影響にも関わらず、主題的に論じられることはあまりなかった。したがって本稿の目的は、ラクラウの提示した民主主義理論の可能性を検証するためにも、彼がどのように自身の政治理論を醸成させていったかを明らかにすることである。そこで手掛かりとなるのが「主体」の概念である。つまり『ヘゲモニーと社会主義戦略』において主体は、構造内部の「主体位置」と考えられていたが、後に精神分析理論からの批判を取り入れることにより、それを「欠如の主体」と捉えるようになったのである。そしてこの主体概念をめぐる転回が、ラクラウ政治理論を脱構築との接合や普遍/個別概念の再考などの新しい展開へと促したことを示すことにしたい。最後にこの「欠如の主体」の導入が、ラクラウの民主主義理論をどのように深化させたのかを議論し、ラクラウが提唱するラディカル・デモクラシーが何たるかを明らかにする。
1 0 0 0 OA アール・ヌーヴォーの服飾表現について
- 著者
- 飯塚 弘子
- 出版者
- 文化女子大学研究紀要編集委員会
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:02868059)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.53-66, 1988-01-31