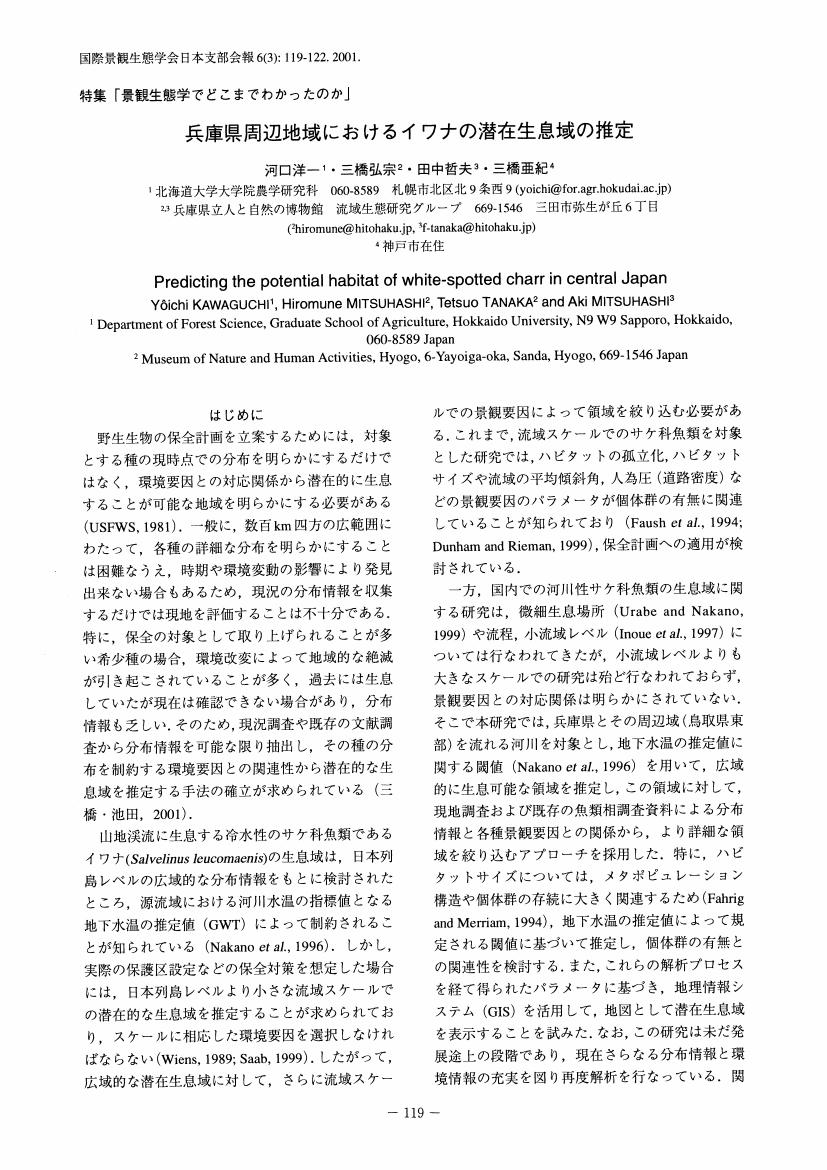1 0 0 0 OA プレゼンテーションにおけるスライド評価と発表評価の一致率
- 著者
- 山下 祐一郎
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.Suppl., pp.5-8, 2021-02-20 (Released:2021-03-08)
- 参考文献数
- 4
本研究では,プレゼンテーション評価の効率化を実現するため,プレゼンテーションにおけるスライド評価と発表評価の一致率を分析した.スライド評価は,プレゼンテーションスライドのみを評価することである.また,発表評価はスライドを使用した口頭発表に対する評価である.本研究の評価では,アンケート形式のルーブリックを用いて,ピアレビューを実施している.そして,例えば,わかりやすさの評価は「わかりやすい」と「わかりにくい」の二極の傾向に分けて一致率を求めた.このように,傾向に分けた場合の一致率は,わかりやすさ,面白さ,タイトルの適切さ,論理構成,目的の説明,情報収集の項目で90%以上を示していた.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.813, pp.36-39, 2006-01-09
構造計算書の偽造問題が、刑事事件にまで発展した。事件の全容を解明するカギは、経営コンサルタントの総合経営研究所(以下、総研)が果たした役割分担にある。12月14日の証人喚問で示された資料を本誌は入手。資料には、コストダウンにこだわる総研が、設計者に対して鉄筋減らしを推奨していた実態が示されていた。 偽造の発覚から約1カ月を経て、ついに捜査のメスが入った。
- 著者
- 近藤 有美
- 出版者
- 名古屋外国語大学
- 雑誌
- 名古屋外国語大学論集 = Bulletin of Nagoya University of Foreign Studies (ISSN:24334332)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.105-130, 2021-02
1 0 0 0 OA 大学生のグローバル人材としての能力をどう測るか―『REFERENCE FRAMEWORK OF COMPETENCES FOR DEMOCRATIC CULTURE』を用いた予備調査―
- 著者
- 宮本 真有 近藤 行人 櫻井 省吾 近藤 有美
- 出版者
- 名古屋外国語大学
- 雑誌
- 名古屋外国語大学論集 = Bulletin of Nagoya University of Foreign Studies (ISSN:24334332)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.271-284, 2021-02
- 著者
- 佐伯 徹
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュータ = Nikkei computer (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.985, pp.84-87, 2019-03-07
第3回ITプロジェクトの失敗原因を究明しようとすると「犯人捜し」に陥りがちだ。そうした事態を避け、真因にたどり着くために「成功曼荼羅図」の活用を勧める。参加メンバーが議論しつつ、5つのステップで原因究明を進めていく。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ニューメディア (ISSN:02885026)
- 巻号頁・発行日
- no.1634, 2018-11-19
通信政策、携帯電話<ローミング、シェアリング自体に問題はない> 2018年11月1日にKDDIと楽天は、決済、物流、通信ネットワーク分野において、両社の保有するさまざまなアセットを相互利用し、それぞれの事業領域におけるサービス競争力を一層強化することを発…
- 著者
- 佐伯 徹
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュータ = Nikkei computer (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.981, pp.96-98, 2019-01-10
ここで事件の真相や報告書の内容の是非を問うつもりはない。筆者が問題にしたいのは、何らかの事件やトラブルが起こった際にすぐ犯人を捜し、特定したらそれで幕引きにする風潮である。冒頭の事件に限らず、日本の企業や組織でよく見られる光景ではないだろ…
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.813, pp.40-43, 2006-01-09
「11階建てのホテルを6カ月で施工できる」—。木村建設の成長の原動力となっていたのが、低コスト、短工期を売り物にした大型型枠工法だ。しかし、総研の指導で海外から導入したこの工法で過度にコスト削減を図ったことが、構造計算書の偽造を生み出した要因となったとの見方もある。
1 0 0 0 看護記録における不適切表現の実態調査
- 著者
- 津嘉山 みどり 大城 江利加
- 出版者
- 日本看護協会出版会
- 雑誌
- 日本看護学会論文集 看護総合 (ISSN:1347815X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.472-474, 2006
1 0 0 0 作文添削システムの開発
本稿の目的は,作文の添削システムを開発することである.作文の添削には多大の労力と時間を必要とする.形式的な間違いを指摘したり,訂正するだけでも,教師の負担は大きい.文章を書く能力の未発達な生徒は,作文上でいくつかの基本的な「誤り」をおかす.その誤りには,明白な「間違い表現」と,「不適切表現」とがある.教師は添削の過程で,前者の誤りは訂正し,後者の誤りは指摘した上で,書き換えを促すか,訂正案を示す.本稿で述べる作文添削システム,TENSAKUは,この教師の役目を果たすものである.
- 著者
- 高杉 能婦子
- 出版者
- 日本看護協会出版会
- 雑誌
- 看護 (ISSN:00228362)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.14, pp.100-103, 2001-11
- 著者
- Tomonori Unno
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.495-498, 2015 (Released:2015-09-10)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 7
Maple syrups are prepared by thermally concentrating maple sap. Based on their clarity, density and characteristic taste, they are divided into 5 grades: extralight, light, medium, amber and dark. This study aimed to evaluate differences in antioxidant activities among grades by the hydrophilic oxygen radical absorbance capacity (H-ORAC) method. The results demonstrated that H-ORAC values varied widely depending on the degree of brown coloration; darker-colored maple syrups showed stronger antioxidant activity. The darker-colored grades of maple syrup also contained more reducing sugars (fructose and glucose) than the lighter-colored ones; however, the grade had little impact on the content of free amino nitrogen in the syrup samples. The present study suggests that the brown pigments (melanoidins) produced by condensation of amines and reducing groups may contribute significantly to the antioxidant activity of maple syrups.
1 0 0 0 アンケートを併用した隔離試験によるウマの不安傾向の評価
- 著者
- 桃沢 幸秀 寺田 節 佐藤 文夫 菊水 健史 武内 ゆかり 楠瀬 良 森 裕司
- 出版者
- 社団法人日本獣医学会
- 雑誌
- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.9, pp.945-950, 2007-09-25
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1 18
ウマの不安傾向を理解することは、騎乗者にとっても獣医師にとっても重要である。本研究では、被験馬をよく知る管理者が気質評価アンケートに回答することで得られた不安傾向スコアと、行動実験から得られた結果とを比較し、不安傾向と関連が深い行動指標を探索した。各馬を新奇環境に導入後、ビニール紐を介して壁に繋留し、管理者が傍にいる状態で2分間観察したのち管理者が離れウマ単独の状態で更に2分間観察した。その結果、単独にされることで多くの観察データが変化したが、アンケート調査により不安傾向が高いと評価された個体ほど、心拍反応が高くビニール紐切断までの潜時は短かった。こうした傾向はメスでより顕著に観察された。以上のことから、新奇環境に単独でおかれた際の心拍数と切断潜時は不安傾向の指標として有効であることが示された。また行動実験と気質評価を組み合わせることで、他の気質項目についてもより信頼性の高い評価を行える可能性が示された。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュータ = Nikkei computer (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.982, pp.84-87, 2019-01-24
他にもIT業界の不正が相次ぎ発覚した。NECは3月、子会社のNECエンジニアリング(現NECプラットフォームズ)における不正を明らかにした。2002年から2005年にかけて部長級の社員が売上高を計363億円、営業利益を計93億円それぞれ水増ししていた。
- 著者
- Tomomi TAKANO Haruna WATANABE Tomoyoshi DOKI Hajime KUSUHARA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-0703, (Released:2021-03-11)
- 被引用文献数
- 1
Feline noroviruses (FNoVs) are potential clinical pathogens in cats. To perform an epidemiological study of FNoV infection, it is necessary to develop a simple and effective method for virus detection. We investigated whether a commercial human NoV quantitative RT-PCR kit for the detection of human NoVs used in medical practice can be applied for FNoV detection. This kit was capable of detecting the FNoV gene regardless of the genogroup (GIV and GVI) in experimental and field samples. Based on the above findings, it is possible to detect FNoVs using human NoV tests. The relationship between FNoV infection and gastroenteritis in cats may be clarified by applying these methods to an epidemiological survey of FNoVs.
- 著者
- Makoto AKIYOSHI Masaharu HISASUE Sakurako NEO Masami AKIYOSHI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-0566, (Released:2021-03-11)
- 被引用文献数
- 1
This report describes the cases of two Miniature Dachshunds who were suspected to have immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) and were treated with immunosuppressive therapy. However, progression of anemia, increases in C-reactive protein (CRP) and total-bilirubin (T-Bil) levels, splenomegaly, transition to nonregenerative anemia, and thrombocytopenia occurred after the treatment. Splenectomy and bone-marrow aspirations were performed subsequently. Both dogs were diagnosed with hemophagocytic syndrome (HPS) associated with IMHA. Unfortunately, they died 9 and 6 days later. These findings indicate that some cases of refractory IMHA have the pathogenicity of HPS. HPS should be included as a differential diagnosis of refractory IMHA concurrent with thrombocytopenia. Continuously elevated CRP and T-Bil levels may be helpful indicators in the detection of HPS associated with IMHA.
1 0 0 0 OA 声と色から読み解く歴史文書学 : イランのモンゴル帝国期命令文書から
- 著者
- 四日市 康博 ヨッカイチ ヤスヒロ Yasuhiro Yokkaichi
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.1-13, 2020-03
1 0 0 0 OA 主体的・対話的で深い学びを実現するための理科授業デザイン試論とその実践
- 著者
- 野原 博人 和田 一郎 森本 信也
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.293-309, 2018-03-19 (Released:2018-04-06)
- 参考文献数
- 17
本研究では, Engeström, Y.による「拡張的学習(Expansive Learning)」を理科授業デザインの視点として援用し, 主体的・対話的で深い学びを通した子どもの科学概念構築に関わる変化の様態について, 形成的アセスメントの要素とその関連性を視点として分析した。その内実と関連づけた上で, 主体的・対話的で深い学びの評価について, Sawyer, R.K.による「深い理解」を規準とした。科学概念の構築を図るための「道具」の変換過程をⅠ〜Ⅴと措定し, 小学校第4学年の水の温まり方についての授業デザインの分析を行った。分析した結果, 以下の諸点が明らかとなった。(1)「拡張的学習による理科授業デザイン」が具現されていくことで, 知識としての「道具」が主体的・対話的で深い学びによって構築されていった。(2)主体的・対話的で深い学びによって構築された知識としての「道具」は, Ⅰ〜Ⅴの段階を通して, 「深い理解」の具現化として, 質的変換が図られた。(3)「深い学び」と「学習における主体性・協働性」は表裏一体化して機能する。
1 0 0 0 三浦雅博先生に聞く
- 著者
- 巻田 修一
- 出版者
- 日本眼光学学会
- 雑誌
- 視覚の科学 (ISSN:09168273)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.42-43, 2020
<p>この度,東京医科大学茨城医療センター病院眼科教授の三浦雅博先生にインタビューをさせていただきたいと思います。三浦先生は眼科イメージング装置の臨床研究に携わってこられました。学生時代の話から,現在の研究に関わっていかれた経緯,光工学やエンジニアとの共同研究にまつわるお話をお伺いしました。</p>
1 0 0 0 OA 兵庫県周辺地域におけるイワナの潜在生息域の推定
- 著者
- 河口 洋一 三橋 弘宗 田中 哲夫 三橋 亜紀
- 出版者
- 日本景観生態学会
- 雑誌
- 国際景観生態学会日本支部会報 (ISSN:1345532X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.119-122, 2001-12-30 (Released:2011-07-05)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1