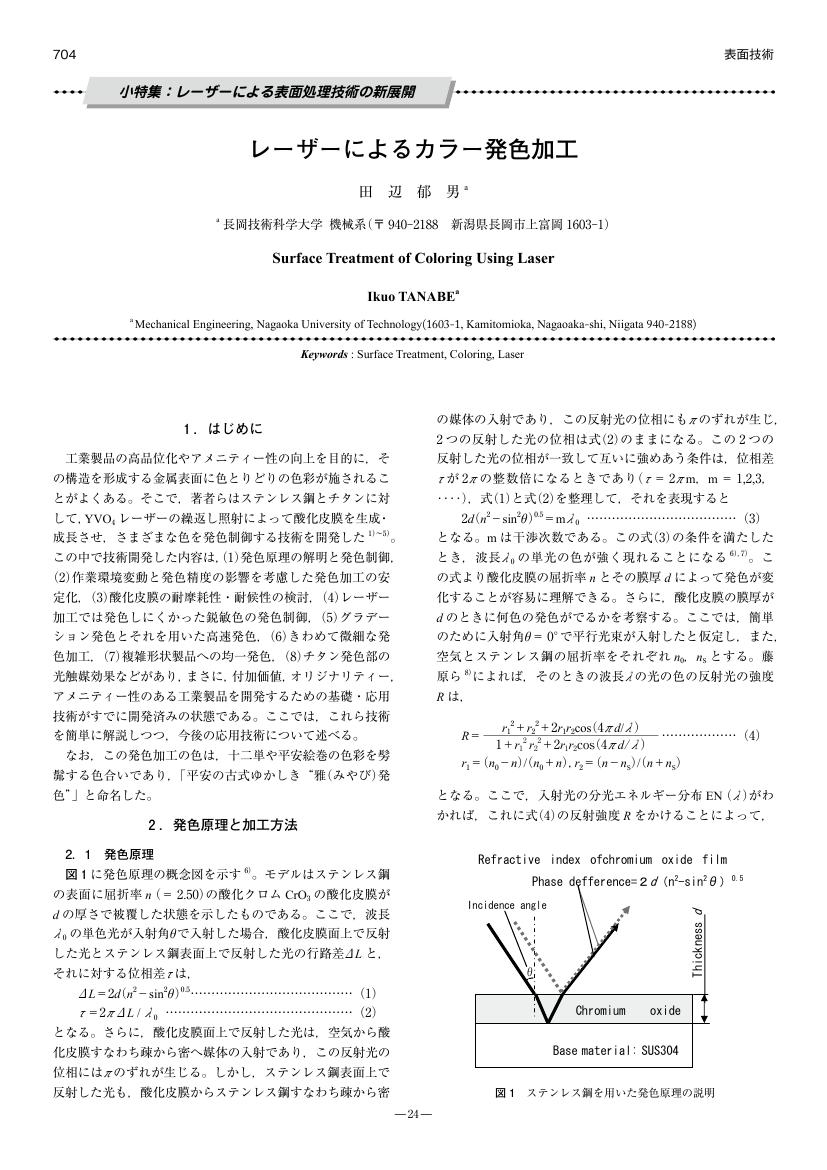1 0 0 0 OA レーザーによるカラー発色加工
- 著者
- 田辺 郁男
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.11, pp.704, 2009-11-01 (Released:2010-05-28)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 都市近郊に局所的に残存する森林植生について-埼玉県朝霞市の例-
- 著者
- 浅見 和弘
- 出版者
- 公益財団法人 地球環境戦略研究機関 国際生態学センター
- 雑誌
- 生態環境研究 (ISSN:13404776)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, 1996
1 0 0 0 IR 国立歴史民俗博物館所蔵『顕広王記』承安四年・安元二年・安元三年・治承二年巻
- 著者
- 高橋 昌明 樋口 健太郎
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.153, pp.417-444, 2009-12
1 0 0 0 ハンドスピナー部品を誤飲した学童の2症例
- 著者
- 鈴木 淳志 桑島 成子 松寺 翔太郎 土岡 丘 楫 靖
- 出版者
- 日本小児放射線学会
- 雑誌
- 日本小児放射線学会雑誌 (ISSN:09188487)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.137-141, 2020
<p>ハンドスピナーは主に学童を対象とした玩具で,2017年頃から世界的に普及している.普及に伴い部品の誤飲が報告され,問題になっている.今回2例を経験したので報告する.</p><p>1例目は7歳女児,既往にTurner症候群をもつ.ハンドスピナー部品誤飲を母が目撃し来院.無症状かつ腹部単純X線写真で異物は胃内のため経過観察とした.しかし異物は1か月以上胃に停留したため,内視鏡的摘出施行となった.2例目は7歳男児,生来健康.ハンドスピナー部品のボタン電池のようなものを誤飲した後から腹痛を訴えたため来院.腹部単純X線写真で異物が小腸内であることを確認し,来院時症状軽快していたため経過観察した.</p><p>小児の異物誤飲は低年齢が好発で,多くは経過観察で対処可能であるが,ハンドスピナー部品誤飲は好発年齢が高く,内視鏡的摘出を要する率が高いとされている.病歴聴取より診断は比較的容易だが,長期停滞やボタン電池が含まれるため注意を要する.</p>
1 0 0 0 島根県の地産地消促進活動 島根県産大根を使用した大根麺の開発
【目的】<br><br>島根県の食料自給率は65%と中・四国地方の中で一番高く、全国でも12番目に高い自給率を示す。その理由として、島根県では平成15年にしまね地産池消推進協議会が策定した考え方を基に、広報誌やパンフレットによる啓発活動等を行っている。それにより県民の地産池消に対する理解が広がり、地産池消の取り組みが拡大していたことが理由とされている。そこで、より地産池消へ向けての活動を向上させるため、島根県での生産量が安定しているが、消費量の少ない食材として大根をピックアップする。地元の人が興味を持ち、親しみを持ってもらえるような食品開発を目的とした。<br><br>【方法】<br><br>島根県産の大根を使用し、細長くスライスしたものに片栗粉をまぶして油で揚げ、あんをかけた皿うどん風の大根麺作りを実施した。本学学生に試食をしてもらった後、味や食感、麺として活用したいと思うか、価格設定などの項目についてのアンケートに協力してもらった。<br><br>【結果】<br><br>アンケート結果によると、「珍しくて美味しかった」、「色々な料理に活用できそう」、といった総合的に良い評価を得ることができた。今後、価格設定や、パッケージ、栄養価など商品としてのビジョンを詳しく決め、広める必要がある。まずは、本学学生による給食運営管理実習を利用し地域の方や外部の方に、大根麺の存在を知ってもらい、実際に食べてもらうことで農林水産省の地産地消推進計画の4つある推進の柱の「知る」「味わう」「伝える」を実施する。残りの柱である「伸ばす」という点は、給食センターや道の駅などでの販売や提供を行い、大根麺の生産や流通体制を作ることによって、地産池消活動の協力・食料自給率の向上につながると考える。
1 0 0 0 OA 穢土の往生(四)
- 著者
- 越部 良一
- 出版者
- 宗教法人 真宗大谷派 親鸞仏教センター
- 雑誌
- 現代と親鸞 (ISSN:13474316)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.38, 2015 (Released:2018-04-04)
- 著者
- 千賀 則史 SENGA Norifumi
- 出版者
- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科
- 雑誌
- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 心理発達科学 (ISSN:13461729)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.21-33, 2016-12-28
The purpose of this study is to explore the diversity and possibility of psychological support in the field of child welfare by taking up the practice at a child guidance center and a child welfare institution as a subject for discussion. Since a clinical psychology in Japan has developed centering on psychoanalytic therapy, the primary emphasis is on individual psychotherapy in a room, which focuses on the internal world. However, in order to solve child maltreatment it is necessary to have the idea of improving daily life and the environment of children and parents by creating a social network because children are immature and strongly influenced by the external environment. Therefore, it is required for a child welfare psychologist, as a member of the multidisciplinary team, to go out of a room to approach not only the internal world but also the external world. The greatest characteristic of the support system at a child guidance center is a multidisciplinary team approach. The assessment and planning of all cases of a child guidance center are carried out collaboratively by the council system, in which a psychologist is expected to play a role in psychological assessment. Since child maltreatment became a social problem, a child guidance center has been asked to actively intervene in the family suspected of child maltreatment for the purpose of child protection. As a result, the workers at a child guidance center in Japan sought for a new approach, until safety oriented child protection frameworks such as Signs of Safety Approach (SoSA) and Partnering for Safety (PFS) were introduced from foreign countries. In the field of child welfare institutions, psychological support is provided in daily life instead of in a room. It is essential for a psychologist to approach not only an individual child by play therapy but also the environment surrounding a child by consultation for the care workers. A psychologist in a child welfare institution is expected to promote a therapeutic function of network support by bringing the perspective of clinical psychology. It is necessary for a child welfare psychologist to take an integrative approach based on daily life, which deals with both the internal and the external world because child maltreatment occurs when the bio-psycho-social multidimensional factors are complexly intertwined. With the diversity of clinical psychology increasing in this way, unique and innovative approaches such as Holonical Therapy and Open Dialogue have been established as a possibility of new types of psychological support. Although there are already many good practices in the field of child welfare, there are few academic theses which collect such clinical wisdom. It is an urgent task to construct the psychological support model which is effective in the field of child welfare.
1 0 0 0 ソマチット研究の歴史と将来--古代超微小生命体の謎
- 著者
- 福村 一郎
- 出版者
- サトルエネルギー学会
- 雑誌
- サトルエネルギー学会誌 (ISSN:13424963)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.26, pp.3-8, 2009
- 著者
- 谷 卓生
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.6, pp.96-99, 2018
1 0 0 0 現代の艦載兵器(第2回)対空ミサイル(その2)日米以外の西側諸国
1 0 0 0 IR 冨澤成實先生
- 著者
- 吉田 悦志
- 出版者
- 明治大学政治経済学部
- 雑誌
- 政経フォーラム
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.76-78, 2002-03-20
- 著者
- 山本 健 藤本 佳則 中久喜 輝夫
- 出版者
- FFIジャーナル編集委員会
- 雑誌
- 食品・食品添加物研究誌 (ISSN:09199772)
- 巻号頁・発行日
- vol.211, no.10, pp.847-853, 2006
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 米の食味の評価方法
- 著者
- 竹生 新治郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.17-22, 1970-02-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 4
1 0 0 0 OA 2型糖尿病における生態学的経時的評価法を用いた心理行動的アプローチの最適化
- 著者
- 齋藤 順一 熊野 宏昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第83回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.L-018, 2019-09-11 (Released:2020-09-26)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- Kohno Katsuyuki
- 出版者
- Springer-Verlag Tokyo
- 雑誌
- Researches on population ecology (ISSN:00345466)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.11-16, 1997-06
- 参考文献数
- 15
- 著者
- 洪 ジョンウン
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.3-16, 2015-06-25 (Released:2017-09-22)
本稿は、1960年代において在日朝鮮人女性が「女性同盟」の活動を通じて獲得した民族アイデンティティの特徴について考察することを目的とする。北朝鮮を支持する「朝鮮総連」の傘下団体である「女性同盟」は、戦後、最も古い歴史を持つ在日朝鮮人女性団体である。北朝鮮への帰国運動が始まったばかりの1960年代初頭、大阪では「女性同盟」の活動家によって朝鮮学校に「オモニ会」が発足され、公的領域においてもオモニ役割が遂行されるようになった。北朝鮮の影響を受けて1962年に開かれた「オモニ大会」ではオモニとしての役割が公式に強調され、北朝鮮の「革命的オモニ言説」が総連系在日朝鮮人社会に広がる契機となった。「女性同盟」は「康盤石女史を見習う運動」を行い、金日成の母である康盤石を理想化した。康盤石は自ら革命家になるよりも、革命家の子どもを育てることに重点を置く女性像であったため、「女性同盟」の活動家にとって良妻賢母主義を批判的に克服することは難しかった。一方、多様な女性闘士が登場する『回想記』シリーズを用いた学習では、自ら革命の闘士となった女性像を探り出す転覆的読み方の試みが行われ、新たな遂行性の可能性を見せた。1960年代総連系在日朝鮮人の民族運動はジェンダー化されていたため、それに参加した女性主体は、オモニ役割の遂行によって、単なる民族アイデンティティではなく、オモニというジェンダー化された民族アイデンティティを遂行的に構築・再構築したといえる。
1 0 0 0 OA 徳川・豊臣大阪夏御陣
- 著者
- 佐藤 惟
- 出版者
- 福祉社会学会
- 雑誌
- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.169-191, 2017-05-31 (Released:2019-06-20)
- 参考文献数
- 37
本稿の目的は,近年社会科学の分野で注目を集める「希望」の概念を社会福祉領域に適用することが,「ニーズ」をめぐる議論に与える影響を探ることである.本稿では特に,「ニーズ」や「デマンド」,「希望」に関する議論と,介護保険制度導入前後の時期に出された行政文書から,高齢者福祉領域における政策理念の転換を分析した.その結果,1990 年代前半まで「ニーズ」と「デマンド」の相違に関する議論が主流であったのが,2000 年前後からは,「ニーズ」と「希望」の関係への言及が増えていた.介護保険制度の導入に当たっては,高齢者の「希望」に基づき「その人らしい生活」を送ることが,「尊厳の保持」につながることが述べられ,それまでの「ニーズ」とは別の視点が現れていた. 「デマンド」に比べて「希望」は,自己決定の土台となる概念でもあり,介護保険制度が掲げる「自立支援」や「尊厳の保持」と親和性の高いものである.ミクロ実践の場では,「信頼関係構築」のためにも,「希望」の把握が欠かせない.一方で,本当に支援が必要な社会的マイノリティの存在を見逃さないためにも,マクロ政策においては「希望」とは別の基準による議論が必要であり,「社会的判断に基づくニーズ」を語ることがあくまで重要な意味を持つ.「希望」の概念を導入することで,「ニーズ」が指し示す範囲は客観的ニーズとしてのあり方に収束し,その輪郭が明確になってくる.
1 0 0 0 OA 漢魏律目考
- 著者
- 陶安 あんど
- 出版者
- Japan Legal History Association
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.52, pp.81-116,en7, 2003-03-30 (Released:2009-11-16)
- 被引用文献数
- 1 1
This thesis constitutes a part of a larger investigation into the history of Law Codification in traditional China. As former research puts tremendous emphasis on proper nouns which are supposed to be chapter headings of Law Codes and takes them as proof for the existence of already lost ancient law codes in case of absence of other direct evidence, in this thesis a reconsideration of those proper nouns will be conducted.The reconsideration first starts with the chapters of the Wei-Lü, which is the first Chinese Law Code for which we have still access to contemporary source material on the compilation process, viz. an excerpt of the preamble. Because of difficulties in interpreting this source there is an old controversy about which of the embedded proper nouns constitute the eighteen chapters of the Code, the number of which is specified in the preamble. This thesis will show that those difficulties stem from the inappropriate import of hypotheses on chaptering from non-contemporary sources (mostly from the Tang) and that these difficulties can be avoided easily by focusing on inherent formal features of the preamble. Next, a reconsideration of the chapters of Han-Lü based on the Wei-Lü preamble will give proof that former knowledge of Han -Lü chapters was misled by later sources, too. The Han-Lü chapters will be reconstructed newly by our insights on the reading of the Wei-Lü preamble, which constitutes the oldest available source on chapters of the Han- Lü as well as on the Wei-Lü, despite of general scholarly negligence of this fact.Finally, an investigation is conducted into the transmission process of Jin-Lü to the Tang, in reply to misleading endeavours of former scholars to extract collateral evidence for particular Wei-Lü chapters from chapters of the Jin-Lü, which is supposed to have been preserved as an original text at least until the Northern Song. It will be shown that the preservation theory is based merely on requotations in encyclopaedias of the Northern Song of quotations of commentaries to the Jin-Lü in encyclopaedias of the Tang. The Jin-Lü Law code itself was scattered and lost during the turbulences at the beginning of the Period of North and South Dynasties. The commentaries, on the other hand, are products of scholarly work on contemporary and recollected ancient legal materials throughout the North and South Period. Partly, they contain private compilations of Law codes of dynasties which, as a well-known fact, never compiled any Law Code.Founded on the results of this inquiry, the author urges for more textual criticism when handling non-contemporary sources which are supposed to contain components of lost ancient Law Codes.