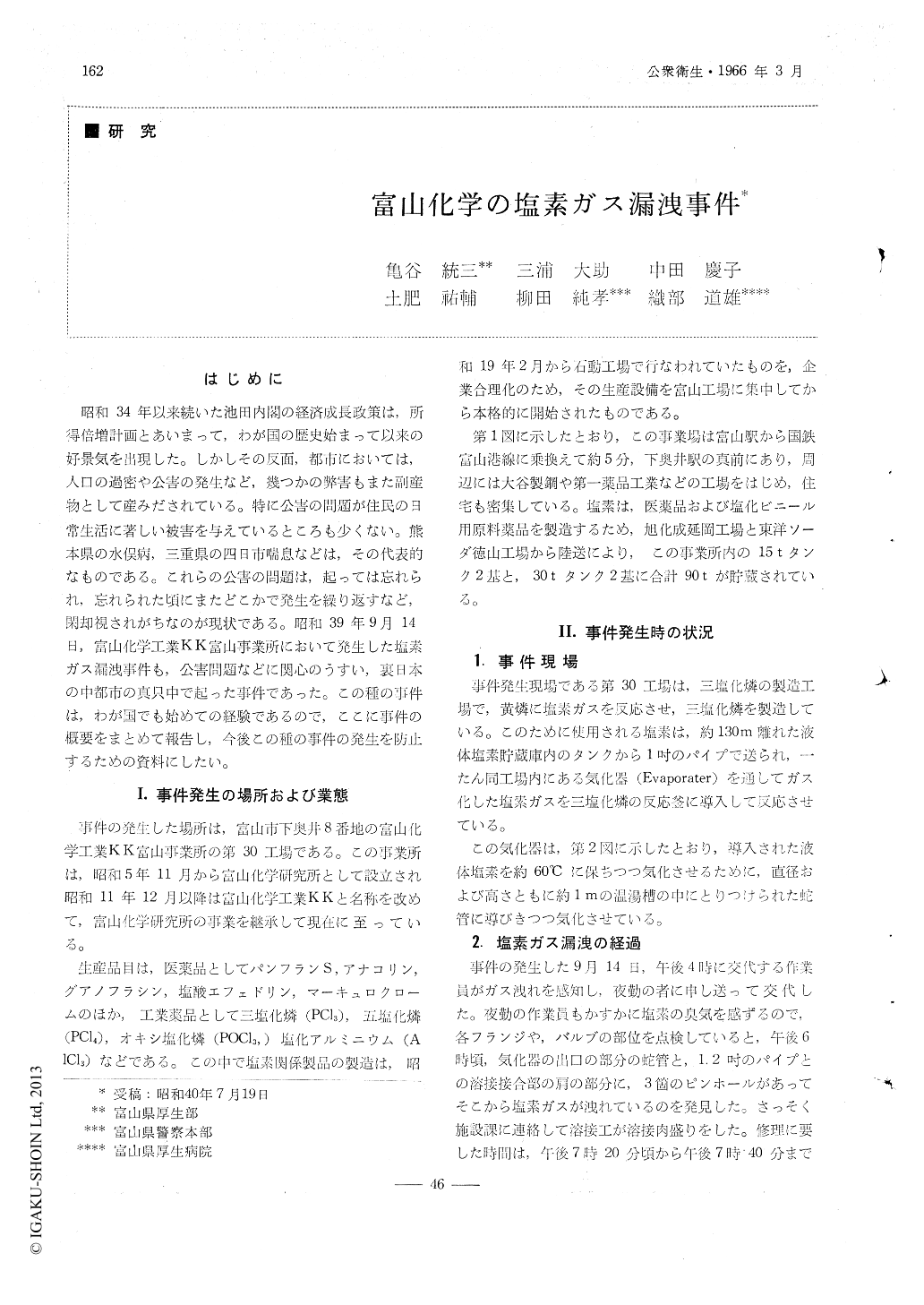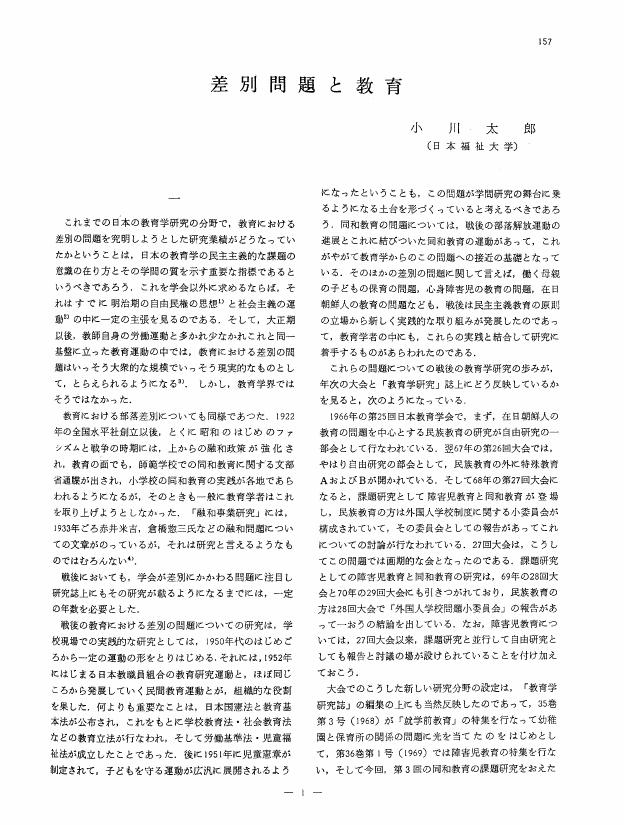1 0 0 0 OA 安部川鉄橋上汽車進行ノ光景 / 静岡名所
- 出版者
- 《東京堂書店》
- 著者
- Taiji Noguchi Fumi Kondo Takeshi Nishiyama Takahiro Otani Hiroko Nakagawa-Senda Miki Watanabe Nahomi Imaeda Chiho Goto Akihiro Hosono Kiyoshi Shibata Hiroyuki Kamishima Akane Nogimura Kenji Nagaya Tamaki Yamada Sadao Suzuki
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20200343, (Released:2020-10-17)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
Background: Marital transitions are associated with adverse health events, such as mortality and cardiovascular disease. Since marital transitions (e.g., becoming widowed) are unavoidable life events, it is necessary to identify modifiable intermediate outcomes. Thus, we examined the association between marital transitions and vegetable intake among middle-aged and older Japanese adults.Methods: This longitudinal study included Japanese adults aged 40–79 years who received an annual health checkup between 2007 and 2011 (baseline) and five years later (follow-up). Marital transitions were classified as whether and what type of transition occurred during the five-year period and comprised five groups: consistently married, married to widowed, married to divorced, not married to married, and remained not married. Changes in total vegetable, green and yellow vegetable, and light-colored vegetable intake from baseline to follow-up were calculated using the Food Frequency Questionnaire.Results: Data from 4813 participants were analyzed (mean age: 59.4 years; 44.1% women). Regarding marital transitions, 3,960 participants were classified as “consistently married,” 135 as “married to widowed,” 40 as “married to divorced,” 60 as “not married to married,” and 529 as “remained not married.” Multivariable linear regression analysis revealed that compared to consistently married, married to widowed was inversely associated with the change in total vegetable intake (β = -16.64, SE = 7.68, p = 0.030) and light-colored vegetable intake (β = -11.46, SE = 4.33, p = 0.008).Conclusion: Our findings suggest that being widowed could result in a reduced intake of vegetables. Hence, dietary counseling according to marital situation is necessary.
1 0 0 0 OA 地方公務員法第34条の「秘密」とは何か
1 0 0 0 OA シエナ大学
- 著者
- 佐々木 智也
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.44-45, 2020-09-30 (Released:2020-10-17)
1 0 0 0 OA 宗教的ニューカマーと地域社会 : 外来宗教はホスト社会といかなる関係を構築するのか(宗教の創りだす絆-信仰による交わりの意義と可能性-,公開シンポジウム,<特集>第七十回学術大会紀要)
- 著者
- 三木 英
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.4, pp.879-904, 2012-03-30 (Released:2017-07-14)
現代日本では外国籍の住民が増え、それに伴って日本人に馴染み薄い宗教の施設も増加することになっている。ブラジル福音王義キリスト教やイスラームがその宗教の代表であるが、それらの現状は日系人やムスリムだけが集う、孤立した信仰共同体にとどまっている。それら共同体に日本人信者は僅かしかおらず、教会やモスクの所在する地域の住民が、それらに出入りすることはない。とはいえ宗教的なニューカマーもホスト社会に無関心であるかといえば、そうではない。彼らは日本人・日本社会に向け活動し、メッセージを発信しているのである。その働き掛けは現時では一方的なもので、多くの日本人はその現実に気づいてはいない。しかし現代日本が多文化共生をその課題とする限り、日本人がニューカマーによる活動・メッセージを認識することは必要であろう。宗教的なニューカマーは国内に増加している。彼らと日本人との間の協働関係構築の可能性は、探究するに値しよう。
1 0 0 0 OA スーパーオーディオ
- 著者
- 海老塚 伸一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.12, pp.1588-1592, 2001-12-01 (Released:2011-08-17)
現在のディジタルオーディオの流れは多岐にわたり, 各ポジションでより精緻な進化を遂げている.データ圧縮とクオリティの共存技術 (AAC), 伝送レートを押さえ明瞭な音声信号を扱う技術 (MPEG-4) 等が上げられるが, もう一つの大きな流れは「より精細な原音の再生」を目指したダイレクトストリームディジタル (DSD) 技術である.本稿では, これまでのディジタルオーディオに付随する概念を大きく超えた高ダイナミックレンジ (120dB), 広範な周波数特性 (100kHz) を有する音声信号再生が可能となる「スーパーオーディオCD (SACD) 」を例に, 権利保護iを含む各種構成技術について解説する.また, コンテンツ制作の技法を具体的に解説しながら, 本技術の今後の可能性について述べる.
1 0 0 0 富山化学の塩素ガス漏洩事件
はじめに 昭和34年以来続いた池田内閣の経済成長政策は,所得倍増計画とあいまって,わが国の歴史始まって以来の好景気を出現した。しかしその反面,都市においては,入口の過密や公害の発生など,幾つかの弊害もまた副産物として産みだされている。特に公害の問題が住民の日常生活に著しい被害を与えているところも少くない。熊本県の水俣病,三重県の四日市喘息などは,その代表的なものである。これらの公害の問題は,起っては忘れられ,忘れられた頃にまたどこかで発生を繰り返すなど,閑却視されがちなのが現状である。昭和39年9月14日,富山化学工業KK富山事業所において発生した塩素ガス漏洩事件も,公害問題などに関心のうすい,裏日本の中都市の真只中で起った事件であった。この種の事件は,わが国でも始めての経験であるので,ここに事件の概要をまとめて報告し,今後この種の事件の発生を防止するための資料にしたい。
- 著者
- 新井 竜治
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.2_11-2_20, 2013-07-31 (Released:2013-09-30)
- 参考文献数
- 41
昭和戦前期の東京地区百貨店における新作家具展示会に出品された洋家具には、アール・デコ調、近代合理主義モダン、國風家具、様式家具、ペザント家具(農民家具)等、多様な家具スタイルが混在していた。またその家具設計者の中には戦前期・戦後期を通して活躍した人々がいた。一方、終戦直後期から高度経済成長期の東京地区百貨店の新作家具展示会では、一部に戦前の延長としての多様な家具スタイルが見られたが、全体として簡素なユティリティー家具、近代合理主義モダンの家具が比較的多く見られた。そして小住宅向け・アパート向けの簡素な量産家具が全盛になった。この百貨店専属工場で開発された新作家具の展示会は、1950 年代末頃から、家具製造業・販売業における位置が相対的に低下し始めた。代わりに欧米輸入家具展・官展・家具組合展・木製家具メーカーの個展等が百貨店各店において盛大に開催されるようになっていった。
- 著者
- 太田 敏一 松野 泉 石田 祐
- 出版者
- 日本安全教育学会
- 雑誌
- 安全教育学研究 = The Japanese journal of safety education (ISSN:13465171)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.3-9, 2015-09
1 0 0 0 OA 各種低級脂肪酸の活性炭への吸着挙動およびその温度特性
- 著者
- 塩盛 弘一郎 馬場 由成 河野 恵宣 羽野 忠
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学論文集 (ISSN:0386216X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.453-458, 1994-05-15 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 11
283-323Kで, 活性炭に対する酢酸, プロピオン酸, クロトン酸, シュウ酸, コハク酸, イタコン酸, マレイン酸, 乳酸, クエン酸の吸着平衡を広い濃度範囲で測定した.脂肪酸の吸着量は温度と共に減少した.吸着挙動は, 低濃度域ではLangmuir型単分子吸着式, 高濃度までの広い濃度域ではB.E.T.型多分子層吸着式で説明された.B.E.T.式中の相対濃度として, 脂肪酸の液体状態における純物質濃度に対する平衡濃度の割合を用いて, 全濃度域での吸着平衡結果を説明することができた.単分子層および多分子層吸着平衡定数は温度が高くなると減少し, 脂肪酸の疎水性と相関される傾向を示した.
1 0 0 0 OA 硫酸銅低濃度液中におけるキンギョとコイの生存と成長
- 著者
- 尾崎 久雄 上松 和夫 田中 幸二
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.166-172, 1970-12-25 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 11
Subacute and chronic intoxication of copper sulphate on goldfish and carp were tested under lower concentrations than those in usual cases of TLm test in 24 or 48 hours.The effects were measured, in tanks containing the water of 48 or 50l with 5 fish of similar size placed as one experiment lot, referring to the maximum and minimum periods of survival (days), the growth in length and weight of body, the condition factor and amount of food consumed. The temperature of the water was kept at 23±1°C, and pH value at 5.7±0.1 during the test extending the maximum of 30 days.Also, seven kinds of copper compounds were examined on the survival (in hours) of carp.The tests revealed, among others, that the concentrations which permitted the survival of more than 30 days were 0.17 ppm for goldfish, and 0.08 for carp in the maximum and that the growth showed lowering at 0.08 ppm for goldfish and 0.024 for carp in the minimum.The amount of food consumed decreased to 70% at the concentration of 0.008 ppm in carp against 100% at 0ppm, though the fish survived more than 30 days in apparent healthy condition at this low concentration.The decrease of intake of food by carp was believed to have resulted from the toxic effects of copper sulphate on the mucous epithelia and on the enzymes in the digestive tract as usually observed in mammals.Discussion was made from the results of the present study and from literature referring to the so-called safety concentrations of copper compounds, which are often applied for the extermination of parasitic animals and plants to fish.The concentrations of copper sulphate used for such purposes range from 500 to 0.04 ppm.The safety level has been often calculated from the TLm in 24 or 48 hours. However, the results gained in the present study will indicate that the allowance on the safety concentration of copper sulphate of fish should be made on the basis of the bioassay tests aimed to the seeking of the concentrations which effect subacute or chronic intoxication rather than on usual TLm test in shorter periods as above mentioned.
1 0 0 0 OA 27a-D-1 卵白のゲル→ガラス様転移における時間分解観察
- 著者
- 金谷 晴一 石田 謙司 吉田 郵司 原 一広 岡部 弘高 松重 和美 澤岻 英正
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 秋の分科会予稿集 1992.3 (ISSN:2433118X)
- 巻号頁・発行日
- pp.567, 1992-09-14 (Released:2018-03-22)
1 0 0 0 OA 評価の時代のエコとエゴ
- 著者
- 菊池 雅史
- 出版者
- 日本建築仕上学会
- 雑誌
- Finex (ISSN:09156224)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.56, pp.28-29, 1998 (Released:2020-06-23)
1 0 0 0 OA 差別問題と教育
- 著者
- 小川 太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.157-163, 1971-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 14
- 著者
- 勝田 春子
- 出版者
- 文化女子大学研究紀要編集委員会
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:02868059)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.103-113, 1991-01-31
第2報に引き続き,今回の「箸」の考察は,明治から昭和までを見た。新しい時代が外国との関わりをどのように受け止めながら変化してきたか見てきた。以下その概要について述べてみたいと思う。毎年,慣例行事として, 8月4日に東京山王日枝神社1)で、「ハシの日」と称し,日頃使用した箸に礼をこめて焼き,供養している。この行事は箸に関心のある人々が多数集って感謝するという「箸供用祭」2)である。近年,食生活の多様化がみられるが,日本人の食事と箸は切り離すことが不可能な食事用具の一つである。箸は単純な二本の棒状のものであるが,食事用として,又食事以外の使い方として長い年月にわたって使用されてきた。どのような経過をたどってきたのか詳細は,第一報・第二報を参照していただきたい。箸については,古今東西,多くの研究がなされているが,今後, 「箸」に関する研究をすすめていくうえで,歴史的変遷はその出発点となる。これまで弥生時代から江戸時代までの約1600年の考察が出来たが,江戸時代の後半に町人文化とともに,工芸的,機能的な箸が,塗箸や引裂箸となってあらわれ,独自の展開をみせてきた。竹の引裂箸は,割箸を生み,好まれる条件をもって,急速に発達し,今日の外食産業になくてはならないものであり,一方では,外食産業をささえる要因でもある。西洋文化の影響とともに余りにもめまぐるしく動く現代に,食生活も大きな変化をみせている。箸はどのように変り,展開されていくのか考察を続けた。
1 0 0 0 OA Semiochemicals containing lepidopteran sex pheromones: Wonderland for a natural product chemist
- 著者
- Tetsu Ando Masanobu Yamamoto
- 出版者
- Pesticide Science Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- pp.D20-046, (Released:2020-10-15)
- 参考文献数
- 99
- 被引用文献数
- 16
Since the first identification of bombykol, sex pheromones of about 700 moth species have been elucidated. Additionally, field evaluations of synthetic pheromones and their related compounds have revealed the male attraction of another 1,300 species. These pheromones and attractants are listed on the web-sites, “Pheromone Database, Part I.” Pheromone components are classified according to their chemical structures into two major groups (Types I and II) and miscellaneous. Based on our previous review published in 2004, studies reported during the last two decades are highlighted here to provide information on the structure characteristics of newly identified pheromones, current techniques for structure determination, new enantioselective syntheses of methyl-branched pheromones, and the progress of biosynthetic research. Besides the moth sex pheromones, various pheromones and allomones from many arthropod species have been uncovered. These semiochemicals are being collected in the “Pheromone Database, Part II.” The chemical diversity provides a wonderland for natural product chemists.
1 0 0 0 和辻風土論と梅棹生態学
- 著者
- 鵜木 奎治郎
- 出版者
- 大正大学
- 雑誌
- 比較思想研究 (ISSN:02862379)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.58-68, 1976-12
1 0 0 0 OA 生活習慣病の予防・改善を目指した時間栄養学の可能性
- 著者
- 大石 勝隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会
- 雑誌
- 日本糖尿病教育・看護学会誌 (ISSN:13428497)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.51-55, 2020-03-31 (Released:2020-09-15)
- 参考文献数
- 27