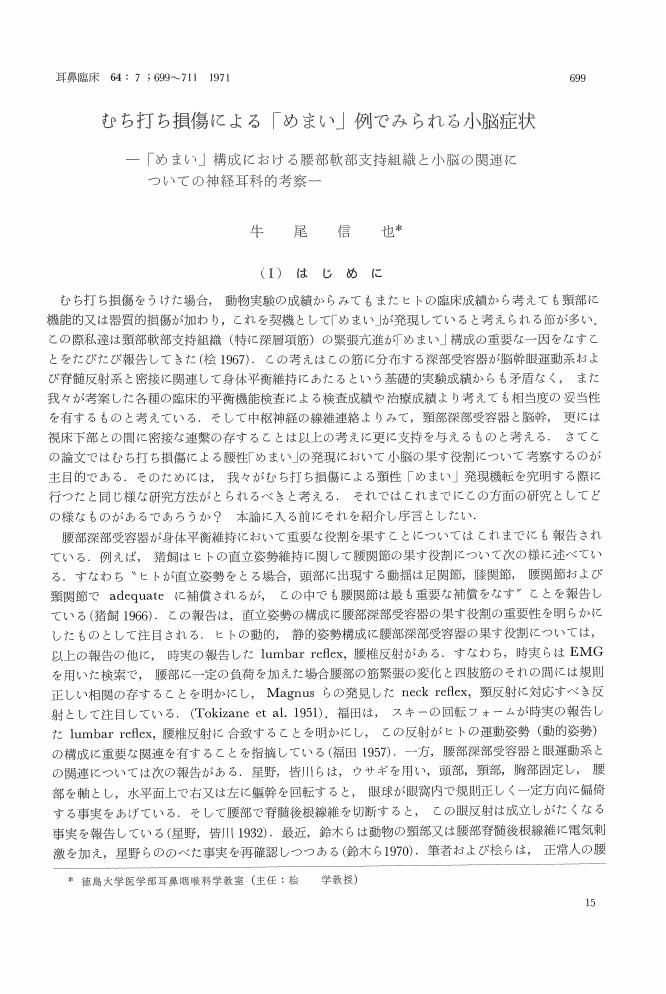- 著者
- Satoshi Maekawa Makoto Niizawa Masaru Harada
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.9, pp.1133-1139, 2020-05-01 (Released:2020-05-01)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 4
Objective Intragastric balloon (IGB) therapy is a low-invasion treatment for obesity. Recently, a low-carbohydrate diet has shown effectiveness for encouraging weight loss, but whether or not a low-carbohydrate diet improves the efficacy of IGB therapy remains unclear. Therefore, we examined the effectiveness of a low-carbohydrate diet compared with a calorie-restricted diet in combination with IGB therapy. Methods A prospective study was conducted on 51 patients who had undergone IGB therapy from October 2012 to December 2017. Overall, 31 of the 51 patients were included in this study (12-month assessment after IGB placement). These 31 cases consisted of 18 IGB plus low-carbohydrate diet and 13 IGB plus calorie-restricted diet. We compared the two groups with respect to body weight loss as outcomes. Results At 12 months after IGB placement, the body weight was significantly lower than that observed at baseline in both the IGB plus low-carbohydrate diet group (baseline 101.9±25.8 kg, 12 months 88.2±21.9 kg) (p<0.0001) and the IGB plus calorie-restricted diet group (baseline 103.5±17.0 kg, 12 months 89.1±6.2 kg) (p<0.005). The percentage of excess weight loss in the IGB plus low-carbohydrate diet group was slightly higher than that in the IGB plus calorie-restricted diet group, but there was no significant difference between the 2 groups at 12 months after IGB placement (IGB plus low-carbohydrate 49.9±60.0%, IGB plus calorie-restricted diet 33.1±27.0%). Conclusion Our study demonstrated that both a low-carbohydrate diet and a calorie-restricted diet were effective interventions for weight reduction in combination with IGB therapy.
1 0 0 0 OA マルチモーダル深層学習を用いた画像とテキストの意味理解に基づく整合性判定
- 著者
- 鈴木 莉子 小西 幹人 池田 順哉 林 大地 深井 颯 菅原 優 町井 湧介 山浦 佑介
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.3Q5GS901, 2020 (Released:2020-06-19)
ドキュメントに含まれる画像はテキストの内容理解を助ける役割を持つが、画像とテキストの間に整合性が無い場合は、読み手の理解を妨げる恐れがある。ドキュメント作成時の人的ミスやデータの改ざん等により、画像に対してテキストの意味が部分的に変わってしまう場合は、作成者が矛盾点に気付きにくいため、意図せずドキュメントの品質を落としてしまう可能性もある。本研究では、マルチモーダル深層学習を用いて、画像とテキストの整合性判定を行い、画像の物体領域とテキストの単語の関連性を学習するCross Attentionにより、画像とテキストの矛盾点を可視化するモデルを構築する。画像とキャプションが対になったデータセットを元に、キャプションの意味を部分的に変更したデータセットを作成し、提案モデルの有効性を検証すると共に、Cross Attentionにより可視化される画像とテキストの対応関係について考察する。
1 0 0 0 IR 19世紀の西洋の病院指針の比較による長崎小島養生所に関する計画史的研究
- 著者
- 深澤 恵 安武 敦子 山下 龍
- 出版者
- 長崎大学大学院工学研究科
- 雑誌
- 長崎大学大学院工学研究科研究報告 (ISSN:18805574)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.94, pp.95-101, 2020-01
We restored the drawings of Nagasaki Yojosho from previous studies, old photographs, and excavated materials. In addition, by comparing with a western hospital manual and guideline, which are "HANDLEIDING TOT DE KENNIS DER BURGERLIJKEEN MILITAIRE BOUWKUNST" and "Notes on hospitals", we examined whether Nagasaki Yojosho was influenced by them. By restoring drawings, the situation at that time became clear, that is high probability that Pompe referenced when he planned Nagasaki yojosho. They don't all match, because he had created its plan in consideration of the given site.
- 著者
- 小田 寛 大野 道也 大橋 宏重 渡辺 佐知郎 横山 仁美 荒木 肇 澤田 重樹 伊藤 裕康
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.9, pp.1231-1236, 2000
慢性透析患者では心血管系合併症, とくに虚血性心疾患 (IHD) の発症頻度が高い. 今回, 血液透析 (HD) 患者と持続性自己管理腹膜透析 (CAPD) 患者の凝固, 線溶系の各因子を測定し, IHDとの関連性について検討した.<br>平均年齢48.5歳の健常者20名 (男性9名, 女性11名), 平均年齢52.7歳のHD患者20名 (男性8名, 女性12名), 平均年齢47.8歳のCAPD患者30名 (男性18名, 女性12名) を対象とした. 平均透析期間は45.2か月と43.8か月で, 基礎疾患はいずれも慢性糸球体腎炎である. 凝固系因子として第XII因子活性, 第VII因子活性, フィブリノーゲン, トロンビン・アンチトロンビンIII複合体 (TAT) を, 線溶系因子としてプラスミノーゲンアクチベーターインヒビター1 (PAI-1), α<sub>2</sub>プラスミンインヒビター・プラスミン複合体 (PICテスト), Dダイマーを測定した. またIHDは, (1) 心筋梗塞, 狭心症の有無, (2) 無症候性心筋虚血は運動負荷, 薬物負荷後のタリウム心筋シンチグラフィーの所見から診断した. 以下の成績が得られた.<br>(1) 健常者に比較して透析患者の第VII因子活性, TAT, フィブリノーゲンは高値を示し, 凝固亢進状態にあった. またHDに比較してCAPD患者の第VII因子活性とフィブリノーゲンはさらに上昇していた. (2) 透析患者のPIC, Dダイマーは高値を示し, 線溶亢進状態にあった. なおHDとCAPD患者の間に線溶系因子に有意差は認められなかった. (3) IHDを有する透析患者の第VII因子活性, フィブリノーゲンは上昇していた. この傾向はCAPD患者でより顕著であった.<br>以上より, 透析患者の凝固・線溶系は亢進状態にあり, この傾向はCAPD患者で顕著であった. なかでも第VII因子とフィブリノーゲンはIHD発症の危険因子であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 失語症者の自動車運転再開支援リハビリテーション
- 著者
- 佐藤 卓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.149-154, 2018-06-30 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 8
自動車運転は現代生活において欠かすことのできないものである。高次脳機能障害者が社会復帰する場合, 自動車運転再開について適切な評価が必要である。運転に関する概念モデルとして Michon (1985) 及び渡邉 (2016) があるが, それに対応する高次脳機能として, 視空間認知, 視覚認知, 聴覚認知, 注意機能 (持続, 選択, 配分) , 遂行機能, 処理速度, 作業記憶, そして言語機能が挙げられる。運転評価は, オフロード評価として神経心理学的評価及びドライビングシミュレーター評価と, オンロード評価として自動車教習所での実車評価がある。自験例において, 神経心理学的評価について失語群 60 例 (運転再開可能群 44 例, 再開見送り群 16 例) と非失語群 84 例 (運転再開可能群 64 例, 再開見送り群 20 例) の 2 群で比較検討した。非失語群は, MMSE, 記号探し, 数唱, 語音整列で失語群よりも有意な結果であり, 失語群では負荷が多い可能性が示された。失語群を Goodglass ら (1971) のBoston diagnostic aphasia examination により重症度分類し比較検討すると, 区分 1-3 の群よりも区分 4 及び区分 5 の 2 群が運転再開可能群の割合が高く, MMSE, TMT-A 及び B, 数唱で有意に高い結果であった。言語処理の負荷がこれらの課題において不利となる可能性が考えられ, それは運転にも同様に不利に作用する可能性が示唆された。
1 0 0 0 IR ソクラテス的対話の生成と宗教的基礎
- 著者
- 箕浦 恵了
- 出版者
- 大谷学会
- 雑誌
- 大谷大學研究年報 = THE ANNUAL REPORT OF RESEARCHES OF OTANI UNIVERSITY (ISSN:02896982)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.1-40, 1995-03-30
1 0 0 0 OA むち打ち損傷による「めまい」例でみられる小脳症状
- 著者
- 森上 誠 行定 健治 田島 賢一 佐藤 暢昭 杉崎 順平 宇野 滋 山田 敏元
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.517-524, 2010
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
多岐にわたる各種の歯科処置が歯科医師の治療時間のなかでどの程度の割合を占めているのかについて,3ヵ月間にわたる調査を虎の門病院歯科において行った.通常行われる歯科処置について,初診診査,歯周処置,歯内処置,レジン修復,インレー修復,脱離修復物・補綴物の再装着,クラウン補綴,ブリッジ補綴,義歯補綴,インプラント処置,口腔外科処置,顎関節症処置,漂白,その他の14カテゴリーに分類し,さらにこれらを全50項目に細分化した.11名の歯科医師が診療を行いながら,その処置時間をストップウォッチで計測した(単位:分).調査期間終了後,各種の歯科処置に要した時間および患者数を集計し,これに基づき処置内容別の患者1人当たりの平均処置時間を算出した.また,平均処置時間とそれぞれに対応する保険診療報酬との関係を処置内容別に比較・検討するために,保険点数を平均処置時間で除した値(Point/Time ratio,以下,P/T ratio)を算出した.カテゴリー別の処置時間は,歯周処置が29,556分(28.7%),歯内処置が9,274分(9.0%),レジンおよびインレー修復処置が16,083分(15.6%)であり,歯科保存学領域の処置は全体の53.3%を占めた.処置内容別では,スケーリングが21,677分で全体の21.0%を占め,すべての処置内容のなかで最も多くの処置時間を占めることが明らかとなった.次いでレジン修復の13,019分(12.6%),初診診査の9,312分(9.0%),歯周疾患処置の4,276分(4.1%),義歯調整の3,938分(3.8%),クラウン失活歯支台歯形成+印象採得+咬合採得の3,930分(3.8%),根管貼薬の3,725分(3.6%)という順になった.また,すべての歯科処置のなかでP/T ratioの高い処置は,硬質レジン前装ブリッジ装着(218.8),総義歯装着(171.6),床副子(ナイトガード)装着(170.1)であり,P/T ratioの低い処置は,クラウンメタルコア高洞形成+印象採得(1.3),ブリッジメタルコア窩洞形成+印象採得(2支台歯:1.6),硬質レジン前装ブリッジ試適(1.8),根管貼薬(単根:1.9)であった.P/T ratioは,診療時間に対する歯科処置のコストパフォーマンスを考慮する際の指標になるものと思われた.
1 0 0 0 OA 新刊紹介
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.103-105, 2015-05-25 (Released:2015-07-23)
1 0 0 0 OA 口唇裂口蓋裂者の自己の意味づけの特徴
- 著者
- 松本 学
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.234-242, 2009-09-10 (Released:2017-07-27)
- 被引用文献数
- 3
本研究の目的は,口唇裂口蓋裂(Cleft lip and/or palate;CLP)を有する人々について,各発達期における自己の意味づけの特徴とその変化を明らかにすることである。CLPは,先天的可視的変形の代表的疾患であり,機能障害の他に裂による可視的変形を有している。このため,発達早期から成人期に至るまで継続した治療を必要とする。T大学歯学部付属病院に口腔管理治療のため来院した成人期CLP者14名(男性6名,女性8名,平均年齢25.4歳,両側性口唇口蓋裂5名,片側性口唇口蓋裂9名)に対して,同病院外来にて児童期から成人期までのCLPに関する経験についての回想的語りによるライフストーリーインタビューを行った。その結果,彼らの自己の意味づけ特徴として【「傷」がある自己の意味づけ】,【自己理解に影響する要因の意味づけ】,【対処】の3つの概念が生成された。この特徴の各発達期における変化を見ると,児童期前期の<機能障害・可視的変形への気付き>から児童期中期から後期の<他者との違いの理解>,思春期の<低い自己評価>,青年期後期から成人期の<CLPをもった私の理解>へと変化していた。今後の課題として,本研究の知見に基づき,CLP者の自己の個別発達の検討および,発達的支援の構築が急務であると考えられた。
1 0 0 0 IR 和算以前における分数・小数理解 (数学史の研究 研究集会報告集)
- 著者
- 岡山 茂彦 田村 三郎
- 出版者
- 京都大学数理解析研究所
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- no.1317, pp.108-113, 2003-05
1 0 0 0 OA 山梨における文庫活動 : 浅川玲子と一坪図書館
- 著者
- 伊東 久実
- 出版者
- 身延山大学東洋文化研究所
- 雑誌
- 東洋文化研究所 所報 = Journal, Research Institute of Eastern Culture (ISSN:13426605)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.21-42L, 2008-04-01
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1917年11月13日, 1917-11-13
1 0 0 0 OA 術後肺がん患者の退院時から術後6カ月までの身体的不快症状の実態
- 著者
- 板東 孝枝 雄西 智恵美 今井 芳枝
- 出版者
- 一般社団法人 日本がん看護学会
- 雑誌
- 日本がん看護学会誌 (ISSN:09146423)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.18-28, 2015-12-25 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 34
要 旨 本研究の目的は,肺がん手術後の身体的不快症状の実態とそれらが生活に及ぼす影響について,退院時から術後6 カ月までの経時的推移を明らかにすることである.術後肺がん患者41 名(平均年齢67.0 歳)を対象とし,自記記入式質問紙法と診療録からデータ収集を行った.分析の結果,肺がん手術後6 カ月を経過しても約6 割の患者が2 つ以上の不快症状を抱えていた.創部に関連する不快症状は,退院時は創部表面の訴えが最も多く,術後1 カ月以降は創部内部の訴えへと変化した.創部以外の不快症状は,術後1 カ月以降では半数以上の患者に術後の息苦しさが出現しており,経時的変化はみられなかったが,術式や喫煙経験により日常生活への影響の程度に関連がみられた.また術後1 カ月が経過しても,術後術側急性肩部不快症状が約17%の患者に存在し,術後6 カ月が経過しても約半数の患者に咳嗽が出現していた.以上より,患者へ術後出現する可能性のある不快症状の回復過程やその機序に関する情報提供を行い,患者自身に不快症状に対するセルフモニタリングの実施を促し,自らの症状に対する認識を深めることで,セルフケア支援へと繋げる必要がある.今後は,患者の不快症状体験を加味した周手術期肺がん看護プログラム開発の必要性が示唆された.
- 著者
- 加納 善明 藪見 崇生
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.4, pp.255-264, 2020-04-01 (Released:2020-04-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4
This paper presents the design studies of a multi-layer interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) with a radially oriented arc-shaped hot-deformed magnet for automotive traction drives. Specifically, by using the IPMSM on a 2010 Prius as a benchmark, we designed an IPM rotor geometry that simultaneously achieves a 20% improvement in both the maximum power and constant output power line with high efficiency while maintaining maximum torque. A prototype of the designed three-layer IPMSM was manufactured and evaluated. The results of the tests conducted on the prototype are reported and discussed in this paper.
1 0 0 0 OA 日本のセダンの全高の変遷と影響因子の関係
- 著者
- 林 孝一 御園 秀一 渡邉 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.2_1-2_8, 2014-09-30 (Released:2014-10-25)
- 参考文献数
- 9
日本の代表的なセダンの全高の推移において'80年代半ばに減少から増加に転じ、更に'90年代後半から2000年初頭にかけ100mm近くも急増する特異性を指摘した。その因子を抽出し、将来の自動車デザインのための知見を得ることを目標とした。全高の変化の様子から、1954年から2012年までの期間を4つに分け考察を行った。その結果、道路環境の変化、スポーツカーや帽子着用等の流行すたり、車自体の構造変化、プレス技術の進化、ユーザーの車への要求の変化、石油高騰と環境問題の悪化、エコカー減税や補助金政策の影響など、時代による各因子の影響で全高は特異な変遷を示したことが推定された。特に新たな快適性の提案をしたプリウスの影響が最も大きかった。一方、全高/全長というプロポーションの値で見ると、時代変化には左右されにくい、人が受容し得るセダンとしての領域、更には各車格毎の領域が存在する可能性が見えてきた。この領域の中央値を高級セダン、小型セダン、大衆セダン毎に導出した。
1 0 0 0 OA 埼玉県小松鉱山から産するバナジウムを主成分とする鉱物
- 著者
- 山田 隆 滝沢 実
- 出版者
- 一般社団法人日本鉱物科学会
- 雑誌
- 日本鉱物科学会年会講演要旨集 日本鉱物科学会 2007年度年会
- 巻号頁・発行日
- pp.199, 2007 (Released:2008-09-02)
埼玉県小松鉱山は変成層状マンガン鉱床であり、これまでにバナジウムを含む鉱物として、フィアネル石やヴォレライネン石の産出が知られる。今回、新たにアンセルメ石とフランシスカン石が見つかった。アンセルメ石はときにフィアネル石と共存し、低品位鉱石中の割れ目に沿って暗赤色~橙赤色、ガラス~樹脂光沢の最長2mm程の柱状結晶として産する。化学組成は、Mn1.04V1.98O6/3.17H2O、格子常数(単斜晶系)は、a=1.316, b=1.011, c=0.698(nm), β=111.6deg.。 フランシスカン石は低品位鉱石中の割れ目を充填する黒色不透明脂肪光沢の鉱物。断口は不規則、条痕は暗褐色。化学組成は、Mn6.2(V0.5W0.02□0.48)Si1.8[O10.2(OH)4.5]。格子常数(六方晶系)はa=0.8150, c=0.4804(nm)。