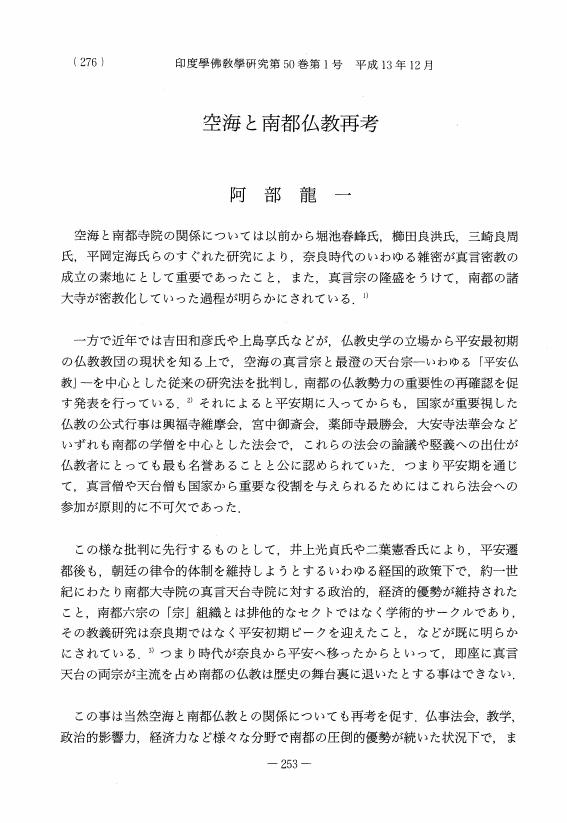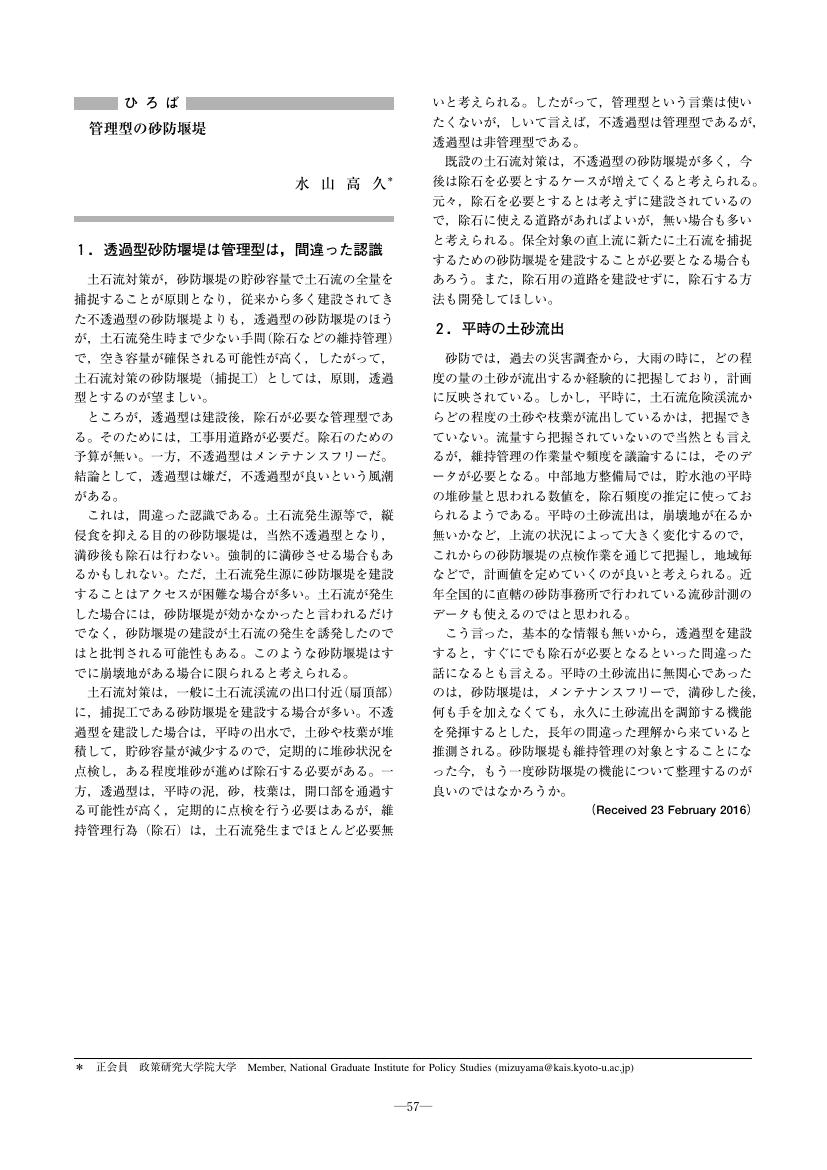1 0 0 0 IR テクニカル詳細 高齢化時代の資産運用手法 キャッシュフロー管理と機能的アプローチ
- 著者
- 加藤 康之
- 出版者
- Kyoto University (京都大学)
- 巻号頁・発行日
- 2016
元資料の権利情報 : 学位規則第9条第2項により要約公開
- 著者
- 荒牧 央
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.2-37, 2019
NHKは1973年から5年ごとに「日本人の意識」調査を行い、同じ質問・同じ方法で調査を繰り返すことによって、社会や経済、政治、生活など、人びとの幅広い意識を長期的に追跡している。その最新の調査結果から、結婚観、婚前交渉、女性の職業、女の子の教育など、家庭・男女関係についての結果を紹介する。家庭・男女関係は、「日本人の意識」調査の中で最も変化の大きい領域である。その変化の特徴として以下のようなことがあげられる。①全体として、男女の平等や個人の自由を認める方向へ意識が変化している。②増えるものは増え続け、減るものは減り続けるというように、同じ方向に変化している項目が多い。③世代交代によって変化している質問もあれば、時代の影響を大きく受けている質問もある。家庭・男女関係についての考え方は45年間で大きく変わったが、2000年頃からは変化が小さくなった質問も見られる。
1 0 0 0 パーソナル・デジタルツインの獲得・記述・認証
1 0 0 0 OA 空海と南都仏教再考
- 著者
- 阿部 龍一
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.253-249, 2001-12-20 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 粉末活性炭素添加による酵母の増殖促進及び香気成分の高濃度生成
- 著者
- 福田 典雄 平松 幹雄 産本 弘之 福崎 智司
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.8, pp.641-645, 1995-08-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 17
液化発酵において, 粉末活性炭素を添加することにより, 酵母の増殖が促進され香気成分生成縫が増加する現象の要囚について検討した。静置発酵において, 槽の高さ方向における溶存酸素 (DO), 溶存炭酸ガス (DCO2) および酵母濃度の分布を経時的に側定した。粉末炭による酸素の持ち込み量は相対的に少量であり, また, 添加, 無添加醪における, DO濃度の経時変化に差異は認められなかったことから, DOは粉末炭添加効果の重要な因子ではないと考えられた。一方, DCO2濃度には明確な差異が認められ, 炭酸ガスの生成が活発な発酵中期 (3~7日) を通して, 粉末炭添加醪の方が常に低い値を示した, 髪た, 無添加醪では, 槽の下部ほどDCO2濃度が高くなる濃度分布が明確に見られた。粉末炭添加醪における, 発酵中期の酵母の濃度分布は, 槽全体にほぼ均一であり分散性に優れていた。これに対して, 無添加醪では, 槽の下部に酵母が沈降する傾向が見られた。これは, 活発な炭酸ガスの発生に伴う発酵液の流動性に起因していると考えられた。全酵母数当たりの酢酸インアミル生成量は, 粉末炭添加によって約2.5倍増加した。以上の結果から, 粉末炭添加による酵母の増殖促進ならびに酢酸インアミル生成量の増加の重要な要因はDCO2濃度であることが確かめられた。
- 著者
- Yu-Hua Chen Chin-fen Chang
- 出版者
- Japan Society of Family Sociology
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.189-199, 2017-10-31 (Released:2018-11-08)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
The study of intergenerational transmission of gender role attitudes (GRA) connects those about parenting mechanism of children's value, socialization, challenges of feminism and gender studies to patriarchy. Previous studies of the transmission of GRA between generations focused on the effects of socialization and symbolic interaction on the formation of GRA of children. Attitudes may change with children's own life-course events, such as entering labor market or starting family formation. The current paper studies if socialization at home remains significant predictor of children's GRA and if their life experiences play an important role in their early adulthood. Findings of analyzing panel data from the Taiwan Youth Project show that children are more egalitarian than their parents, female are more so than male, and children in adulthood are more so than in their youth. Parents have strong effects on shaping children's GRA, especially between mother and daughter. The results seem to support the exposure perspective. However, marriage makes adult children more conservative, especially for married men. The results seem to indicate more the acceptance of the reality by married couple than the backlash of egalitarian attitudes. The self-interested perspective is better to explain the changes of GRA in early adulthood of respondents.
1 0 0 0 OA 「昔話における異界観」-日欧の昔話AT480を比較して-
- 著者
- 細谷 瑞枝 Hosoya Mizue 茨城キリスト教大学
- 雑誌
- 茨城キリスト教大学紀要. I, 人文科学 = Journal of Ibaraki Christian University. I, Humanities (ISSN:13426362)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.137-151, 2009-01-01
Zum Marchentyp AT480 gehoren die japanischen Marchen Jizo Jodo (Elysium des Schutzgottes), Nezumi Jodo (Elysium der Mäuse) und Kurihiroi (Kastanien Sammeln). In dieser Abhandlung werden sie mit den europäischen Märchen AT480 wie KHM 24 „Frau Holle" und anderenachtzehnMärchenausverschiedenenSprachgebietenverglichen,umzu^nveranschaulichen, wie man sich die unirdische Welt vorstellt und wie man damit umgeht. In den europäischen Märchen gelangt die Hauptfigur zwangsweise in die unirdische Welt, und das unirdische Wesen, das meistens allein, aber auch mit Apfelbaum, Backofen, Kuh u.a. zusammen hervortritt, pruft, wie gut oder bose die Haupt- und Nebenfigur sind. Das unirdische Wesen belohnt die Hauptfigur fur ihre Tugend wie Freundlichkeit und Bescheidenheit und bestraft die Nebenfigur für ihre Unfreundlickeit und Habgier. In diesem Sinne gilt die irdische Moral auch in der unirdischen Welt. Dagegen geht die Hauptfigur der japanischen Marchen freiwillig oder sogar eingeladen in die unirdische Welt, in der sie mit zwei unirdischen Wesen, einem Jizo (Schutzgott) und Oni (Teufel) begegnet. Zwar ist der Jizo gut und der Oni bose, wie die Hauptfigur ein guter Alter und die Nebenfigur ein boser Alter ist. Aber wenn man es genauer betarachtet, ist das Gute und Bose nicht so leicht zu unterscheiden. Aus Dankbarkeit für das Essen, das der Jizo ohne Erlaubnis der Hauptfigur gegessen hat, berät der gute Jizo der Hauptfigur, den Onis Geld zu stehlen. Die Nebenfigur, die neidisch die Hauptfigur nachahmt, erleidet einen miserablen Misserfolg, manchmal den Tod. In diesen japanischen Märchen wird das Verhalten der Figuren nicht getestet und der Grund, warum die Hauptfigur belohnt und die Nebenfigur bestraft wird, ist nicht überzeugend, und die unirdische Welt und deren Verlauf ist trotzdem mit Respekt zu akzeptieren.
1 0 0 0 OA <論文>大衆版運命愛としての選択輪廻観
- 著者
- 熊田 一雄
- 出版者
- 愛知学院大学
- 雑誌
- 愛知学院大学文学部紀要 (ISSN:02858940)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.230-222, 1996
1 0 0 0 OA 霊魂の行方 : 仏教と日本人との霊魂観
- 著者
- 梶村 昇
- 出版者
- 亜細亜大学
- 雑誌
- アジア研究所紀要 (ISSN:03850439)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.1-21, 1992
1 0 0 0 OA 現代における「生まれ変わり」思想の諸相(第七部会,<特集>第72回学術大会紀要)
- 著者
- 竹倉 史人
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究. 別冊 (ISSN:21883858)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.318-319, 2014-03-30
1 0 0 0 OA ⾼知県⼟佐清⽔⽖⽩海岸海底で発⾒された石柱の歴史⾃然災害指標としての意義
- 著者
- 濱田 洋平 谷川 亘 山本 裕二 浦本 豪一郎 村山 雅史 廣瀬 丈洋 多田井 修 田中 幸記 尾嵜 大真 米田 穣 徳山 英一
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
⾼知県⼟佐清⽔市⽖⽩海岸付近の海底(水深5-10m)には、数十基の大型の石柱(長さ1m)が横たわっている。しかし、石柱が人工的に作られたものなのか、自然の岩石ブロックなのか、そしてその起源ついては不明である。石柱が確認された爪白地区は、昔から南海トラフ地震による津波と台⾵・⼤⾬による⽔害に幾度も襲われているため、海底の石柱には自然災害の痕跡が残されている可能性がある。また、⾼知県各地の沿岸部には684年の⽩鳳地震で⼀夜にして沈んだとされる村(⿊田郡)の伝承が伝わっており、石柱と「黒田郡」との関係性にも期待がもたれる。そこで本研究では、石柱の幾何学的特性と岩石物理鉱物学的な特性を測定し、起源の推定につながる可能性の高い近傍の岩石および石造物についても同じ特性を測定した。各特性の類似性を評価し、海底石柱の起源の推定を行った。一連の分析の結果、海底の石柱は三崎層群竜串層(中新統)を起源とし、現在は閉鎖している三崎地区の採石場から採取、加工され、爪白地区で石段や家の基礎などの石造物として利用された可能性が高いことがわかった。さらに、爪白地区で利用されていた石柱は1707年の宝永地震による津波により海岸まで流された可能性が高いことがわかった。本研究は、破壊分析(間隙率・密度・XRD)と非破壊分析(X線CT・pXRF・帯磁率測定)の両手法を用いて実施している。将来における水中考古遺物の保存を念頭に置いた場合、水中における非破壊分析手法の確立が喫緊の課題となる。本研究ではX線CT画像解析による石柱の表面形状の特徴とpXRFによる元素濃度比の測定結果を用いたPCA解析が起源特定に大きな貢献をしたが、水中でも室内分析と同様の精度でデータを取得する必要がある。一方で、石柱が水中に水没したプロセスを知る上での重要な手がかりとなる年代評価については手法と精度に問題点があることがわかった。本研究の一部は高銀地域経済振興財団の助成金により実施された。
- 著者
- 村山 雅史 谷川 亘 井尻 暁 星野 辰彦 廣瀬 丈洋 富士原 敏也 北田 数也 捫垣 勝哉 徳山 英一 浦本 豪一郎 新井 和乃 近藤 康生 山本 裕二 黒田郡 調査隊チーム一同
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
黒田郡遺構調査の目的で,高知県浦ノ内湾の最奥部(水深10m)から採取した堆積物コアを解析した。当時の海洋環境や生物相の変遷履歴も復元することもおこなった。高知県土佐湾の中央部に位置する浦ノ内湾は,横浪半島の北側に面し,東西に細長く,12kmも湾入する沈降性の湾として知られている。高知大学調査船「ねぷちゅーん」を用いて、バイブロコアリングによって4mの堆積物コアが採取された。採取地点は,周囲からの河川の影響はないため,本コア試料は,湾内の詳細な環境変動を記録していると考えられる。採取されたコア試料は,X線CT撮影,MSCL解析後,半割をおこない肉眼記載や頻出する貝の採取,同定をおこなった。 堆積物の岩相は,olive色のsity clayであり,全体的に多くの貝殻片を含む。コア上部付近は,黒っぽい色を呈し強い硫化水素臭がした。また,コア下部に葉理の発達したイベント堆積物が認められ,その成因について今後検証する予定である。
1 0 0 0 OA 黒田郡伝承の謎にせまる高知県沿岸部海底調査:概要紹介
日本各地には巨大災害により沿岸部の集落や構造物が水没した記録や伝承が残されている。例えば1498年の明応東海地震による浜名湖南部集落の水没、天正13年の地震に伴う長浜市琵琶湖湖岸集落の水没、磐梯山の噴火に伴う檜原宿の水没が挙げられる。高知県内でも684年に発生した白鳳南海地震により集落が水没した伝承が残されており、その集落は「黒田郡」という名称で市民に知れ渡っている。この黒田郡伝承を明らかにするために、過去に幾度にもわたり調査が実施されてきた。しかし、調査記録が不明瞭な点が多く、黒田郡の謎にどこまで迫れたのかわからない。そこで2013年から高知大学と海洋研究開発機構が中心となって、黒田郡の調査が始まった。2019年までに高知県内沿岸部の6地点(南国市十市、野見湾、浦ノ内湾、興津、爪白、柏島)の調査を実施してきた。残念ながらこれまでのところ黒田郡の痕跡を示す証拠は得られていない。一方、本研究は海底の人工物と構造物を自然災害の記録を残す物証として見立てた地球科学的な分析アプローチであるため、これまでの発想にない発見が得られつつある。そこで本発表では、研究成果が出つつある3地点(野見湾・爪白・柏島)について調査概要を紹介する。須崎市野見湾の南部に位置する戸島は弥生時代の遺跡があり、島北東部海底で井戸を見たという報告が昔から寄せられている。そのため、野見湾は高知県内でも黒田郡の有力候補地として知られている。本研究では、海底地形調査により戸島北東部において縦横200m幅にわたる台地を確認することができた。海底台地は非常に平坦で、海食台の可能性をうかがわせることから、海食台の形成過程から地震性沈降史を評価できる可能性がある。一方、土佐清水市爪白海岸海底には人工的に加工された跡が残る石柱が多く横たわっている。本研究により、この石柱は近郊の爪白地区で石段や家の基礎として古くから使用されていた石造物であることがわかった。さらに、石柱が陸上から海底に運搬されたプロセスに南海地震津波と水害が関与している可能性があることがわかった。幡多郡柏島の北部に石堤を想定させる巨石が積まれた壁状構造物が海底にあることが知られている。野中兼山が整備した陸上の堤(兼山堤)とほぼ並行に位置しているため、兼山堤との関連性もうかがわせる。しかし、年代同定と鉱物分析からこの構造物は自然でできたビーチロックである可能性が高いことがわかった。ビーチロックは潮間帯で形成されるため、ビーチロックの年代分析から沈降履歴を評価できる可能性がある。本研究は、水中構造物と水中遺物を対象にした調査が、地震や水害などの歴史自然災害の履歴の評価につなげられる可能性を示唆している。本研究の一部は高銀地域経済振興財団の助成金により実施された。参考文献谷川亘ほか、2016、黒田郡水没伝承と海底遺構調査から歴史南海地震を紐解く:レビューと今後の展望、歴史地震、31、17-26
1 0 0 0 OA ツガ・コメツガとマツタケ菌との共生関係
- 著者
- 竹内 嘉江
- 出版者
- 日本菌学会
- 雑誌
- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第55回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.80, 2011 (Released:2012-02-23)
ツガ・コメツガとマツタケ菌との共生関係 竹内嘉江1)・松下範久2)・(1)長野県林総セ・2)東大院農) symbiosis relation between tsuga sieboldii ,t.diversifolia and tricholoma matsutake by y.takeuchi,n.matsushita.(1)nagano pref.for.res.ins.;2)the univ.of tokyo) マツタケ菌が,ツガ・コメツガの根に共生するのかを明らかにするために,野外のマツタケのシロに苗木を植栽して,マツタケの菌根が形成されるのかを調査した.長野県下伊那郡松川町のマツタケが発生する59~66年生アカマツ林において,林内に植栽した31年生ツガと,マツタケのシロ前線に植栽した6年生コメツガ幼木の根を採集し,実体顕微鏡下で観察した.その結果,両樹種ともに,アカマツのマツタケ菌根と形態的に類似した菌根が観察された.これらの菌根からDNAを抽出し,菌類のrDNA-ITS領域の塩基配列を決定した.得られた塩基配列をDNAデータベース登録配列と比較した結果,両樹種の菌根から得られた配列は,マツタケの登録配列と99%以上一致した.これらの結果から,人工植栽したマツ科ツガ属の2樹種ともに,自然条件下でマツタケ菌が菌根を形成することが実証された.このことによりマツノザイセンチュウによるアカマツ被害の多い地域では,ツガ・コメツガを植栽することによりマツタケのシロを保持できる可能性のあることが明らかになった.
1 0 0 0 OA マットレスの幅が睡眠に及ぼす影響
- 著者
- 木暮 貴政 白川 修一郎
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.147-151, 2007-08-25 (Released:2017-07-28)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3
To evaluate the effects of mattress size on sleep feelings estimated by standardized OSA sleep inventory MA version and sleep quality measured by actigraph, eighteen healthy subjects (8 males, 10 females), aged 61-65, were recorded, sleeping in their homes for 15 consecutive nights under two crossover designed conditions from Friday. A subject slept for 7 consecutive nights (4 adaptation nights and 3 nights for analysis) on a 78cm wide mattress first and then for 8 consecutive nights (4 adaptation nights, 3 nights for analysis and excluded last night) on a 100cm wide mattress. The results showed the sleep on a 100cm mattress indicated better sleep quality and feelings.
1 0 0 0 IR 言語音のピッチ変化に対する自閉症スペクトラム児の知覚過程
- 著者
- 諸橋 茜 谷口 清
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 人間科学研究 = Bulletin of Human Science (ISSN:03882152)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.187-197, 2017-03-01
In order to clarify how children with autism spectrum disorder (ASD) process speech, the current study recorded event-related potentials (ERPs) during active and passive oddball tasks and this study examined how information is processed in the brains of those children. The latency of P1s ("s" means the response to a shift in pitch) at Cz to a shift in the auditory pitch of the vowel /e/ changed significantly in children with ASD depending on the magnitude of the shift. Children with ASD had a briefer latency with a 6% shift in pitch which typically developed (TD) children did not. The latency of P1s was significantly briefer during the active task than during the passive task in TD children but not in children with ASD. These results suggest the possibility that children with ASD have a system of bottom-up processing of dominant sounds and that they have difficulty with top-down processing when perceiving sound.本研究では,自閉症スペクトラム(以下ASD)児の聴覚特性を明らかにするために,受動および能動オドボール課題の下でERPを記録し,彼らの脳の情報処理過程を検討した。母音/e/の音高変化に対するCzのP1s潜時 (ここで"s"は音高変化への応答であることを示す) は,ASD児においては3%変化よりも6%変化で短縮するというように音高変化の程度によって有意に変化した。TD児ではそのようなことはなかった。他方,同じP1s潜時はTD児では受動課題よりも能動課題で有意に短かった。しかしASD児ではそれが見られなかった。これらの結果はASD児がボトムアップ優位な音処理システムを持っており,聴知覚におけるトップダウンプロセスに困難を持つ可能性があることを示唆する
1 0 0 0 OA 屎尿中における結核菌の生存期間
- 著者
- 大沼 丈男
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.9, pp.674-679, 1955 (Released:2011-10-19)
- 参考文献数
- 7
In order to study the term of existence of tubercle bacilli in excrements, the author coducted model experiments on 51 materials, by means of Kudo's culture method. Tubercle bacilli which were put in the excrements lost their living power gradually, the number of the bacilli decreased as times went off and finally they disappeared entirely. The experiments were conducted at room temperatures of different seasons. The term of existence of the bacilli in the experiments which started in December was of 231 days at the maximum, the one started in March was of 136 days at the maximum, the one in May was of 72 days at the maximum, and the one in August was of 167 days at the maximum. Therefore, it was found that by seasons there were differences in the term of existence and the bacilli seemed to have the tendency to live longer in cold weather, whereas they seemed to exist for a shorter period in hot weather. The author does not intend to say that the results of his experiments give directly the data for the longevity of tubercle bacilli in patients' sputa that appear in the excrements of receptacle, however, it may be considered as one of the basic facts, through which the longevity of the bacilli can be infered.
1 0 0 0 IR 世紀転換期の装飾と「近代性」をめぐる問題 : ヨーロッパ文化論の視座から
1 0 0 0 OA 管理型の砂防堰堤
- 著者
- 水山 高久
- 出版者
- 公益社団法人 砂防学会
- 雑誌
- 砂防学会誌 (ISSN:02868385)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.57, 2016-05-15 (Released:2017-09-29)
1 0 0 0 OA 慢性骨髄性白血病治療薬ダサチニブにより誘発された出血性大腸炎の1例
- 著者
- 宮澤 正樹 清島 淳 中井 亮太郎 小村 卓也 丸川 洋平 加賀谷 尚史 太田 肇 鵜浦 雅志
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.10, pp.2176-2181, 2016 (Released:2016-10-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
74歳男性.慢性骨髄性白血病に対してダサチニブを内服中.血便を契機に施行した大腸内視鏡検査にて横行結腸から直腸にかけて多発し,滲出物の付着と出血を伴うアフタ様びらんを認めた.病理組織学的には表面に炎症性滲出物の付着する陰窩炎であった.感染症を念頭に置いて抗菌薬の投与を行ったが改善せず,ダサチニブによる出血性大腸炎を疑い投与を中止したところ,血便の消失と内視鏡所見の改善を認めた.第2世代チロシンキナーゼ阻害薬であるダサチニブによる消化管出血の報告は散見されるが,ダサチニブ中止前後の内視鏡所見の変化を観察し得た症例は貴重であると考えられた.