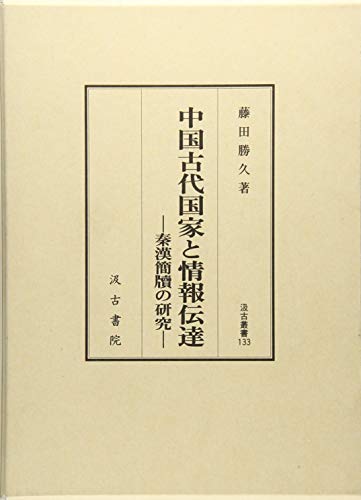1 0 0 0 OA ホタル類の光コミュニケーションと夜間照明
- 著者
- 大場 信義
- 出版者
- 日本環境動物昆虫学会
- 雑誌
- 環動昆 (ISSN:09154698)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.67-76, 2002 (Released:2016-08-05)
1 0 0 0 OA 単極モーターの動作原理
- 著者
- 中川 雅仁
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.141-144, 2007-06-19 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
単極モーターの動作原理について,理論的な考察及び計算を行った。特に,単極モーターの反作用は磁石に働くという誤解を解き,その上に立った解釈を与えた。すなわち,磁石(と流れる電流)の磁場により単極モーターの金属板部分に回転軸まわりの力のモーメントが働き,それによって回転するが,磁石には,金属板や導線に流れる電流からの力のモーメントは働かない。導線部分には金属板部分に働く回転軸まわりの力のモーメントと,大きさは同じで向きが反対の回転軸まわりの力のモーメントが働く。
1 0 0 0 中国古代国家と情報伝達 : 秦漢簡牘の研究
1 0 0 0 OA 姿勢の違いが頭頸部屈曲テスト時の頸長筋筋厚に及ぼす影響
- 著者
- 宮田 信彦 小串 直也 中岡 伶弥 中川 佳久 羽崎 完
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.H2-53_2, 2019 (Released:2019-08-20)
【はじめに、目的】頸長筋(以下:LC)は頸椎椎体の前・側面を走行する頸部屈曲筋として知られ,頸椎の過度な前弯を防ぐ働きがあるとされている。Jullらが頭頸部屈曲テスト(以下:CCFT)を報告して以来,CCFTはLCの評価,治療として広く用いられている。CCFTは従来,背臥位にて行われる方法であるが,日常生活において,ヒトは重力に抗して頭頸部を正中位に保持し,立位もしくは座位をとることが多い。そこで我々は座位にてCCFTを行わせ,LC筋厚が安静時よりも有意に増大することを報告した。しかし,背臥位と座位のCCFTを直接比較はしていない。そこで本研究は,CCFTを背臥位・座位の2条件で実施し,姿勢の違いが LC筋厚に及ぼす影響を確認することを目的とした。【方法】対象は頸部に既往のない健常男子大学生とし,背臥位群9名,座位群16名とした。測定肢位はそれぞれ,膝を屈曲した背臥位,壁面に肩甲骨,仙骨後面が接した椅座位とした。頭部位置は背臥位で床と平行,座位で壁面と平行とした。後頭隆起下の頸部背側にスタビライザー(chattanooga 社製)を置いた。強度はスタビライザーの圧センサーの目盛りが指し示す22~28mmHgの範囲を2mmHgずつ,それぞれ10秒間保持させた。その間のLC,頸椎椎体前面,総頸動脈,胸鎖乳突筋を超音波画像診断装置(日立メディコ社製)にて描出した。プローブ(10MHz,リニア型)は甲状軟骨より 2cm 右・外・下方かつ水平面上で内側に20°傾けた位置とし,頸部長軸と平行にあてた。測定によって得られた画像から画像解析ソフト Image J を用い,LC筋厚を測定した。その後,安静時のLC筋厚を基準としたCCFT時のLC筋厚の増減を安静時比として表した。統計学的手法は,姿勢と強度の2要因における対応のない二元配置分散分析およびBonferroniの多重比較検定にて,背臥位と座位のLC筋厚の安静時比を比較した。【結果】LC筋厚の平均値は安静時(背臥位1.14±0.11cm,座位0.82±0.16cm)となった。安静時比はそれぞれ22mmHg時(背臥位112.8±9.6%,座位113.4±10.8%),24mmHg時(背臥位111.3±9.5%,座位115.7±13.2%),26mmHg時(背臥位117.2±12.0%,座位115.2±13.1%),28mmHg時(背臥位120.8±13.2%,座位113.4±11.9%)となった。二元配置分散分析の結果,姿勢,強度を要因としたLC筋厚の安静時比に有意な主効果および交互作用は認めなかった。【結論(考察も含む)】我々は先行研究においてLC筋厚が座位でのCCFTによって安静時よりも有意に増大したことを報告している。また,一瀬らはLC筋厚が背臥位でのCCFTによって安静時よりも有意に増大したことを報告している。今回の結果で背臥位,座位といった姿勢の違いがLC筋厚の安静時比に有意な影響を与えなかったことから,座位のCCFTにおいても背臥位と同様の効果が期待できると考える。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は大阪電気通信大学における生体を対象とする研究および教育に関する倫理委員会の承認を受けた研究の一部であり,被験者の同意のもと実施した(承認番号:生倫認14-007号)。また被験者には研究中であっても不利益を受けることなく,同意を撤回することができることを説明した。情報の安全管理は個人情報や測定データは匿名化し,被験者の同意なく第三者提供しないよう研究従事者すべてに周知徹底した。
1 0 0 0 健常成人における股関節屈曲・伸展時の大転子移動について
- 著者
- 対馬 栄輝 石田 水里
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.A3P3160, 2009
<B>【目的】</B>股関節副運動の障害を把握するために,股関節屈曲(股屈曲)・伸展(股伸展)時の大転子の動きを触知・観察する方法が考案されている(Sahrmann,2005).異常のない者では股屈曲時に大転子は比較的一定の位置に保たれ,股屈曲で後方へのすべりが起こらないと大転子は前方(腹側)に移動するといわれる.この検査法は簡便であり,臨床的にも有用だと考える.しかし実際,健常者では股屈曲・伸展によって大転子は動かないのか,動くとすればどの程度動くのかを明確にしたい.そこで健常成人を対象に,他動的な股屈曲・伸展における大転子の動きを測定した.また下肢伸展挙上(SLR)の角度や,大腿骨前捻角評価としてのクレイグテストとの関連も検討した.<BR><B>【対象と方法】</B>対象は健常成人6名(男性3名,女性3名)とした.平均年齢は20.8±0.4歳,平均BMIは20.8±3.4であった.検者は股屈曲・伸展を行う者,非測定下肢と骨盤を固定する者,大転子の位置を触知する者の3名とした.検者と被検者には事前に研究目的,内容に関する説明を十分に行い,同意を得た上で参加してもらった.測定肢は左下肢とした.被検者を平坦なベッドに背臥位とさせ,股関節中間位での大転子位置を触知し,円形のシールを貼ってマークした.次に背臥位で(1)股屈曲45°のSLR,(2)膝関節屈曲位(下腿が床と平行な状態)とした股屈曲45°と(3)腹臥位において股伸展10°としたときの,それぞれ大転子の位置を円形シールでマークした.各運動は他動運動とし,股関節回旋が起こらないように注意した.被検者の左側矢状面に対して垂直に設置したデジタルカメラ(Panasonic社製DMC-LZ5)で,マークした股関節周囲部を撮影した.撮影像をもとに画像計測ソフト(PLocate V1.0k)にて,股関節中間位に対するSLR・股屈曲・股伸展時の大転子移動距離を計測した.その他,被検者の他動的最大SLR角度の測定,クレイグテストも行った.<BR><B>【結果】</B>SLRの大転子移動距離は後方(背側)に平均1.6cm(範囲-1.3~3.8cm),股屈曲では後方に1.1cm(-1.5~1.6cm),伸展時は前方(腹側)に0.4cm(0.0~0.8cm)移動した.各大転子移動距離とSLR角度との相関はr=-0.512~0.206で有意ではなかった.クレイグテストとは股屈曲時の大転子移動距離のみがr=-0.967で有意(p<0.01)となった.<BR><B>【考察】</B>SLRと股屈曲では,ほとんどの者で大転子が後方に移動したが,このことは前捻角の影響から予想していた.股伸展は小さい可動範囲のために,移動量も少なかったのだろう.しかしクレイグテストで得た前捻角の大きい者ほど,股屈曲において大転子が大きく前方に移動する矛盾が生じた.前捻角の大きい者は大腿骨アライメントが最初から内旋位となっている可能性がある.また,後方すべりが生じ難いのかもしれない.この点については今後さらに追究する必要がある.
- 著者
- 力丸 祥子
- 出版者
- 日本比較法研究所
- 雑誌
- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.1-36[含 フランス語文要旨], 2007
1 0 0 0 OA テキスト解釈の視点に基づく適合性判定の分析:文章理解理論と関連性理論を用いて
- 著者
- 小田切 夕子
- 出版者
- 筑波大学 (University of Tsukuba)
- 巻号頁・発行日
- 2017
2017
- 著者
- 中村 亨 坂野 雄二
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.9, pp.934-938, 2017 (Released:2017-09-01)
- 参考文献数
- 2
2015年12月より実施されたストレスチェック制度の中で臨床心理士や産業カウンセラーなどの心理職の担う役割は限定的であるものの, 実務を行うにあたって, ストレスチェックにおいて高ストレスと判定された労働者に対する医師による面接指導に先立つ情報聴取を目的とした面接を, 心理職が行うことが考えられる. このため, 心理職は, 医師面接の位置づけを含むストレスチェック制度やストレスチェックの際に用いられる検査について学ぶとともに, 個人情報の保護を考慮した面接の進め方を身につける必要がある.本ワークショップではストレスチェック制度と標準項目となっている職業性ストレス簡易調査票について概説するとともに, 医師による面接指導前の情報聴取を目的とした面接のポイントを整理した.
1 0 0 0 10代の母親から出生した児81例の臨床像と養育状況
1 0 0 0 OA イワシ類稚仔魚の冷蔵保存中の自己消化
- 著者
- 保 聖子 藤田 聡 緒方 由美 木村 郁夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.103-110, 2018 (Released:2018-01-19)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
シラス(イワシ類稚仔魚)の冷蔵保存中に発生する自己消化について,魚体プロテアーゼ活性の経時変化やプロテアーゼの種類および漁獲時の魚体にかかる圧の影響を測定した。モデル試験で魚体に圧力を加えると冷蔵保存中の自己消化が促進した。また,冷蔵保存中には保存温度に依存してプロテアーゼ活性の上昇がみられ,その原因としてセリンプロテアーゼ(主にキモトリプシン)の酵素活性値が高くなることをプロテアーゼ阻害スペクトルから明らかにした。卵白はシラス魚体溶解の原因プロテアーゼに対して強い阻害効果を示した。
1 0 0 0 OA ウォルター・スコットとロシア・ロマン主義文学
- 著者
- 金沢 美知子
- 出版者
- 北海道大学スラブ研究センター
- 雑誌
- スラヴ研究 (ISSN:05626579)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.1-19, 1989
1 0 0 0 OA 層流制御技術について
- 著者
- 石田 洋治
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.356, pp.475-485, 1983-09-05 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 層流制御技術の現状と課題
- 著者
- 吉田 憲司 石田 洋治 野口 正芳
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.554, pp.148-155, 2000-03-05 (Released:2019-04-11)
- 参考文献数
- 26
1 0 0 0 OA ラッツェルとブラーシュに関する地理教育論的考察
- 著者
- 山口 幸男
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2007年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.5, 2007 (Released:2007-04-29)
「自然と人間との関係」というテーマは、地理教育・地理学習の最も重要な目標であり内容の1つである。戦前には環境決定論(自然決定論)的な考え方がみられたが、戦後においては環境決定論の非科学性が批判されるとともに、環境可能論(可能論)が中心的・主流的な考え方となった。環境決定論を代表する地理学者はラッツェルであり、環境可能論を代表するのがブラーシュといわれている。そのため、「環境決定論=ラッツェル=悪」、「環境可能論=ブラーシュ=善」という図式が地理教育界において強く浸透した。環境決定論批判、ラッツェル批判を一貫して主張したのは飯塚浩二で、飯塚の著作を通じて環境決定論批判、ラッツェル批判が地理学・地理教育界に広まっていった。したがって、多くの地理教師のラッツェル理解は飯塚の論じたラッツェルの理解であって、ラッツェル自身の著作に基づくものではない。そのような中、最近、由比濱(2006)によって、ラッツェルの主著『人類地理学』(第一巻1882、第二巻1891、古今書院)の訳書が刊行され、ラッツェル地理学の正確な姿を論じる基盤が整った。一方、ブラーシュの『人文地理学原理』(1922)は既に飯塚によって翻訳されている(1940,岩波文庫)。こうして、ラッツェルとブラーシュという近代地理学史上の2巨人の主著の訳書が出揃い、地理教師各自が自らの眼で両著を考察することができるようになった。
1 0 0 0 OA タマゴが先かニワトリが先か : 神の証明から環境決定論まで
- 著者
- 橋本 順光
- 出版者
- 横浜国立大学教育人間科学部
- 雑誌
- 横浜国立大学教育人間科学部紀要. II, 人文科学 = Journal of the Faculty of Education and Human Sciences, Yokohama National University. The humanities (ISSN:1344462X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.1-11, 2008-02-28
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1900年08月13日, 1900-08-13
1 0 0 0 OA 霊長類における互恵的利他行動
- 著者
- 室山 泰之
- 出版者
- Primate Society of Japan
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.165-178, 1998 (Released:2009-09-07)
- 参考文献数
- 55
This paper reviews recent studies of reciprocal altruistic behaviours in non-human primates. Although altruistic behaviours such as alliances in agonistic interactions and social grooming are explained by the theories of kin selection or reciprocal altruism, evidence of reciprocity is scarce. Recent development of methods, however, may allow us to investigate reciprocity in quantitative and systematic ways. Model-based comparison of matrices of social interactions in a group are a powerful tool to investigate reciprocity at group level. Sequential analyses of social interactions reveal how monkeys do decision-making during the interactions with different partners in terms of reciprocity. Some computer simulations may give us an insight into false reciprocity in the case that human observers may assume the existence of reciprocity. It is also discussed whether reciprocal altruism could develop into true altruism which is reported exclusively in humans.
1 0 0 0 OA 五十町歩以上ノ耕地ヲ所有スル大地主ニ関スル調査
1 0 0 0 OA 二粒径構成河床における反砂堆と礫集合体形成に関する一考察
- 著者
- 溝口 敦子 土屋 幸宏 森 勇輔
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集A2(応用力学) (ISSN:21854661)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.I_549-I_556, 2016 (Released:2017-01-29)
- 参考文献数
- 10
山地河道の階段状河床形状,Step-poolの定義は研究者によって異なり,形成過程等を踏まえた整理が必要と考える.通常のStep-poolは大礫がStepを形成し形状を決めるものであり,長谷川らは横断方向に列をなして礫が集積し落差が少ないTransverse ribsをStep-poolとは区別し定義している.著者らは状況によっては礫の集合体が瀬淵構造またはStep-poolになると考え,まずTransverse ribesに近い状況での礫の集合体形成過程の検討,砂の流出後の表層状態の確認を行う.特に,山地河道における礫の集積形成過程を明確にするため,実験で反砂堆と礫の集合体の形成について調べた.まず,礫の集合体形成には遡上反砂堆がかかわる実験例ともに,進行方向で礫の集積の仕方が異なることを示した.そのうえで,砂礫の比率を変えた河床を用いて遡上反砂堆の形成実験を土砂供給をしながら行うことにした.実験では特に各粒径の流送形態がどのように変化するなどを詳細に調べ,混合率によって砂が流出した後の礫の集合体の形成状況が異なることなどを明らかにした.
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1898年03月28日, 1898-03-28