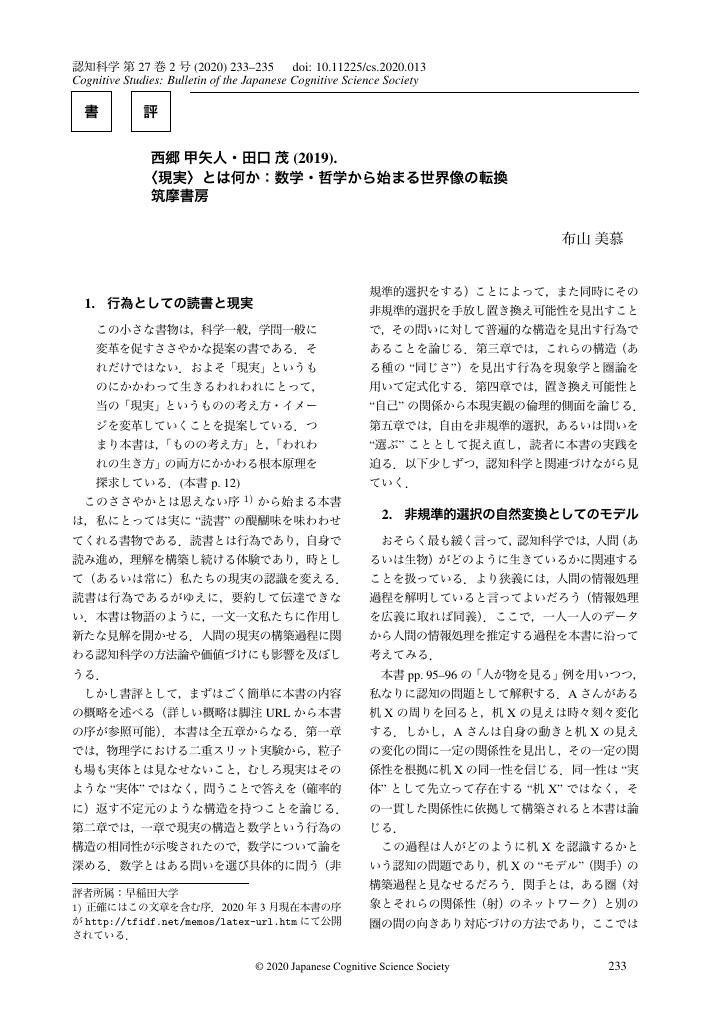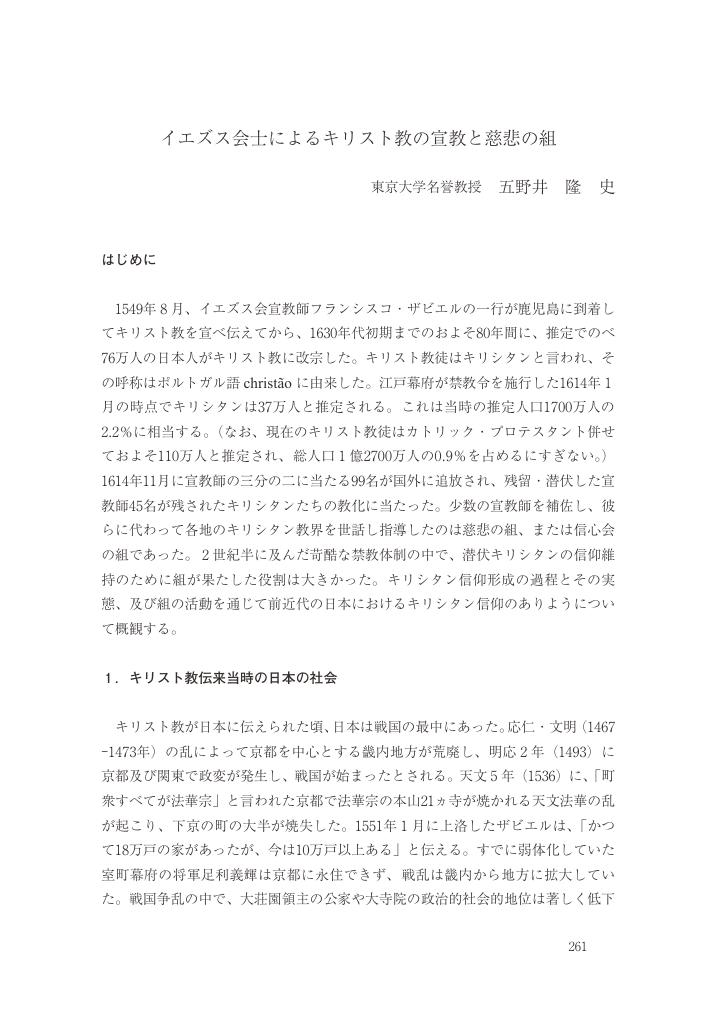3 0 0 0 OA 生物コーナー
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.306-308, 1998-05-25 (Released:2009-05-25)
3 0 0 0 OA 鍼治療と両側性気胸
- 著者
- 山下 仁 形井 秀一
- 出版者
- 社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.142-148, 2004-05-01 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 41
鍼治療後に両側性気胸を起こしたとされる症例報告文献について、臨床鍼灸学の立場から概説した。解剖所見が示されている論文から、鍼灸臨床において肺または胸膜まで鍼が到達する例が予想以上に存在しており、その中の一部が気胸を発症し、さらにその中の少数例が重篤な症状に陥ることが示唆された。文献検索では国内外で23例の両側性気胸の症例が見出された。我々はこれらの症例から教訓を学ぶだけでなく、その背景にある教育内容の再検討やフェイルセーフの発想の導入についても考えるべきである。
3 0 0 0 OA 名古屋市における雨水中のトリチウム濃度
- 著者
- 茶谷 邦男 加賀 美忠明 浜村 憲克
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.9, pp.636-639, 1977-09-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 12
3 0 0 0 OA 低ESRと高ESRコンデンサの組み合わせ使用による電源インピーダンスの低減手法
- 著者
- 山長 功 佐藤 高史
- 出版者
- 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
- 雑誌
- エレクトロニクス実装学術講演大会講演論文集 第26回エレクトロニクス実装学術講演大会
- 巻号頁・発行日
- pp.94-97, 2012 (Released:2014-07-17)
電源インピーダンスの反共振は、EMIや電源電圧変動を引き起こし、LSIの性能や安定性を悪化させる。近年、電源電圧変動の許容値が低下しており、反共振の抑制は電源設計における重要な課題となっている。そこで、本論文では、低ESRと高ESRコンデンサを組み合わせた効果的な反共振抑制手法を提案する。2種類のコンデンサを組み合わせることで、それぞれを単体で使う場合のデメリットを改善し、高帯域に電源インピーダンスを低減することを実験により示す。
3 0 0 0 OA 胎生期ストレス刺激が惹起するストレス脆弱性と脳内5-HT神経機能異常
- 著者
- 宮川 和也 齋藤 淳美 宮岸 寛子 武田 弘太郎 辻 稔 武田 弘志
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.147, no.4, pp.212-218, 2016 (Released:2016-04-09)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 1
脳機能の発達過程において,最も外界から影響を受けやすい時期は胎生期であり,この時期に過剰なストレス刺激に曝露されることにより,中枢神経の発達や成長後の情動性の異常が惹起される可能性が考えられる.実際,妊娠期に母体が過度のストレス刺激に曝露されることにより,子の成長後のストレス反応に異常が生じるという臨床報告がなされている.本稿ではまず,胎生期ストレス研究について,臨床的側面と実験動物を用いた基礎研究の両面から概説する.また,近年著者らは,胎生期ストレスが惹起する子のストレス脆弱性の病態生理の解明に加え,その治療法の提案を期した薬理学的研究を行っている.その結果,行動学的検討において,妊娠期に強度のストレス刺激に曝露された親マウスから生まれた子マウスでは,成長後の一般情動行動の低下,不安感受性の増強およびストレス適応形成の障害が認められた.また,生化学的検討の結果,その発症機構の基盤として,脳内5-HT神経系の器質的あるいは機能的障害が関係している可能性が示唆された.さらに,胎生期ストレス刺激により惹起される情動障害に対する抑肝散の幼少期投与の効果について検討した結果,胎生期ストレス刺激により誘発される不安感受性の亢進は,抑肝散を生後3週齢から6週齢にかけて処置することにより改善した.本稿では,これらの著者らの研究成果を交え,胎生期におけるストレス刺激が子の精神機能障害を誘発する科学的根拠をまとめるとともに,子の安全かつ有効な薬物療法について議論する.
3 0 0 0 心揺さぶる音楽花火 ~伝統を彩る現代技術~
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.6, pp.507-511, 2019-06-05 (Released:2019-06-05)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- Yasuko K. Bando
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-21-0174, (Released:2021-04-08)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 広田照幸著『大学論を組み替える──新たな議論のために』 (名古屋大学出版会、2019年)
- 著者
- 間篠 剛留
- 出版者
- 日本大学教育学会
- 雑誌
- 教育學雑誌 (ISSN:02884038)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.53-56, 2021-03-25 (Released:2021-04-09)
- 参考文献数
- 5
3 0 0 0 OA 12. ツマキチョウの蛹休眠の性質(一般講演,日本鱗翅学会第43回大会・講演要旨)
- 著者
- 石井 実
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- やどりが (ISSN:0513417X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.171, pp.51, 1997-11-01 (Released:2017-08-19)
3 0 0 0 OA 猫用3種混合生ワクチン中からのRD114ウイルスの検出とその試行的安全性評価
- 著者
- 成嶋 理恵 笛吹 達史 小川 孝 嶋崎 智章
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.630-633, 2010-08-20 (Released:2016-09-07)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 5 5
猫内在性レトロウイルス(RD114ウイルス)はすべての猫の体細胞と生殖細胞内に内在化していることから,猫由来培養細胞を用いて製造される猫用混合生ワクチンに混入することが懸念される. 最近,Miyazawaらはいくつかの猫用弱毒生ワクチンにRD114ウイルスが混入していることを報告した[Journal of Virology]. そこで,国内既承認ワクチンにおけるその混入状況をLacZ マーカーレスキュー法によって調査した結果,供試ワクチン(4製剤,計30製品)の30%から感染性RD114ウイルスが検出された. 今回の報告はわれわれがワクチン中に感染性RD114ウイルスが存在することを実証したものである. これまでRD114ウイルスの猫に対する病原性およびRD114ウイルスの混入する当該ワクチンの接種による副作用については,いまだ明確ではない. また,同一のワクチンが製造販売されている欧米においても特段の規制措置は講じられていないことから,われわれは,現段階ではこれらのワクチンに対して緊急的な措置を講じる必要はないと結論付け,今後とも有用情報収集に努めることとした.
3 0 0 0 OA 人造寶石の製造法附寶石僞和品(二)
- 著者
- 小山 一郎 平岡 勇三
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.346, pp.276-296, 1922-07-20 (Released:2008-04-11)
- 著者
- 諏訪 きぬ
- 出版者
- 一般社団法人 日本保育学会
- 雑誌
- 保育学研究 (ISSN:13409808)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.46-56, 2017 (Released:2018-03-16)
- 参考文献数
- 15
子どもの生活に対する家庭の役割は押しなべて脆弱化し,社会的な支援が必要不可欠となっている。学童期の子どもの場合も例外ではない。小学校における学習・遊び・生活(学校給食)による子どもの生活権・発達権保障の役割は大きいし,放課後の学童の生活を学童保育によって守られている子どもも100万人を超えている。ここでは学童保育の運営に着手して日の浅い学童保育のフィールドワークとアンケート調査を通して,学童保育がどう家庭・学校・地域と連携しようとしているか,事例的にその実態を明らかにする。
3 0 0 0 OA 訓練法を立案する立場からみた流暢性の諸問題
- 著者
- 伊澤 幸洋 小嶋 知幸
- 出版者
- 日本神経心理学会
- 雑誌
- 神経心理学 (ISSN:09111085)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.16-28, 2018-03-25 (Released:2018-04-28)
- 参考文献数
- 19
まず,失語症候学における流暢/非流暢のdichotomyの源流に遡って,その概念成立の歴史的経緯を確認し,続いてBoston学派の諸家を中心に考案された「流暢性尺度」をめぐるいくつかの問題を論じた.また,流暢/非流暢の問題に関連する言語学からのコミットメントであるJakobson(1963)による選択/結合についても触れた.さらに,症例を提示しつつ,「流暢性尺度プロフィール」での評定と実際の障害構造の推定の間で齟齬をきたす事例を通していくつかの問題を提起した.最後に,失語学における流暢/非流暢のdichotomyが成立した歴史的意義は十分に理解しつつも,今日的視点に立つと,とりわけ訓練法立案という立場からみた場合,流暢/非流暢を参照枠として失語を捉えるアプローチはそろそろ収束すべき時期に来ているのではないかと述べた.
3 0 0 0 東海発電所の安全審査をめぐる論争 : 原子力災害を中心に
- 著者
- 横田 陽子
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.293, pp.1-17, 2020 (Released:2021-01-24)
This paper examines controversy during the safety examination of the first commercial nuclear power plant (NPP) in Japan, the Tokai Nuclear Power Plant, focusing on the issue of major accidents. Politicians, bureaucrats, business leaders, and engineers generally pushed for the plantʼs construction, while scientists̶mainly physicists̶opposed it. At the time, nuclear power technology was a rapidly growing field, with the knowledge of its safety yet to be established. The controversy revolved around four key issues: 1) how to develop NPP technology; 2) how to mitigate the risk of a major accident; 3) how to estimate the potential effects of such an accident on people; and 4) how to determine the "safety" of NPPs. In addressing these issues, scientists consistently upheld the three basic principles on nuclear research and development in Japan, namely democracy, independence, and public disclosure, emphasizing the importance of free discussion and rigorous scientific standards. By contrast, advocates of power plants opposed such an approach and supported the approval of the construction plan on the basis of administrative procedures. In this way, the knowledge on reactor and radiation safety offered by scientists was intentionally and politically disregarded.
- 著者
- Kunihiro OGATA Tomoki MITA Takeshi SHIMIZU Nobuya YAMASAKI
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE Transactions on Information and Systems (ISSN:09168532)
- 巻号頁・発行日
- vol.E98.D, no.11, pp.1916-1922, 2015-11-01 (Released:2015-11-01)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 5
Some unilateral lower-limb amputees, have through continued exertion, increase the foot reaction force of the sound leg. The asymmetric gait with a prosthetic leg may thus negatively affect the musculoskeletal health of the leg on the healthy side. Therefore, it is important for these amputees to learn how to adjust the balance of each foot load in training. The aim of this study is to develop a training support system visualizing floor-reaction forces using a color-depth sensor. The pose of the entire body of the amputee is measured by the depth sensor, and the floor reaction force is estimated based on Zero Moment Point (ZMP), which is calculated using the center of mass of the amputee. Evaluation experiments of the proposed method were performed and they confirmed the effectiveness of the estimation method and the training with the visualization of reaction force.
- 著者
- 布山 美慕
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.233-235, 2020-06-01 (Released:2020-06-15)
- 参考文献数
- 1
3 0 0 0 OA 55B. 韓国,独火山島の岩石学(日本火山学会1986年度春季大会)
- 著者
- 金 允圭 吉田 武義 李 大声
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山.第2集 (ISSN:24330590)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.144-145, 1986-07-01 (Released:2018-02-13)
3 0 0 0 OA イエズス会士によるキリスト教の宣教と慈悲の組
- 著者
- 五野井 隆史
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.Special_Issue, pp.261-272, 2018-04-11 (Released:2018-05-23)
3 0 0 0 OA 東京都新宿区南元町遺跡から出土した布袋に入った江戸時代の茶
- 著者
- 鈴木 三男 小林 和貴 吉川 純子 佐々木 由香 能城 修一
- 出版者
- 日本植生史学会
- 雑誌
- 植生史研究 (ISSN:0915003X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.79-85, 2017 (Released:2021-03-17)
A cloth bag of the early modern Edo period (the latter half of the 18th century) was excavated from the road remains of the Minamimotomachi site, Shinjuku, Tokyo. This bag contained stems and leaves of plants. The material of the cloth bag was anatomically identified as fibers of the hemp (Cannabis sativa L.). From the plant morphological and anatomical studies, the contents of the bag were identified as stems and leaves of the tea plant (Camellia sinensis (L.) Kuntze). These results agree well with the description in the historical literature that, during the Edo period, commoners drank tea by boiling tea leaves in hemp bags in a pot.
3 0 0 0 OA 特異な震源分布を示す甑海峡北部の地震活動
- 著者
- 八木原 寛 角田 寿喜 後藤 和彦 清水 洋
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.53-61, 1994-06-14 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 30
On January 30, 1992, a shallow earthquake of magnitude 4.9 followed by about 300 aftershocks occurred in a northern area of the Koshiki channel, north-western Kagoshima Prefecture. We located seismic events observed at two stations of NOEV (Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes) and four stations of SEVO (Shimabara Earthquake and Volcano Observatory), using Joint hypocenter determination (JHD). Hypocenters of the mainshock and its aftershocks were nearly vertically distributed at depths from 5km to 13km in a small area.Initial motions at the seismic stations of NOEV, SEVO and FMO (Fukuoka Meteorological Observatory) suggest a focal mechanism of strike slip fault type with a T-axis of NNW-SSE direction: the mechanism is very similar to those reported for the earthquakes in and around the area. The nodal plane striking in NE-SW agrees with trends of the fault system in the channel and the other WNW-ESE plane is parallel to the earthquake alignment along Amakusanada-Izumi-Kakuto areas. Hypocenters of the event and aftershocks nearly vertically distributing are, however, not consistent with any of the planes.In March of 1991, about 10 months before the M 4.9 event, an earthquake swarm (Mmax 2.9) occurred at depths around 5km almost within the same epicentral area. Namely, two different types of earthquake sequence occurred at different depths in the same area: the swarm occupied a shallower zone than the focal zone of the M 4.9 event. Although some volcanic process may be inferred from hypocenters vertically aligning, it is probably difficult to explain the fact that the earthquake swarm at shallow depths occurred about 10 months before the M 4.9 event at a deeper depth without accompanying any notable foreshocks.