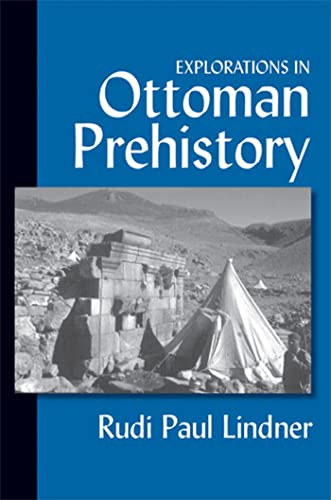- 著者
- Rudi Paul Lindner
- 出版者
- University of Michigan Press
- 巻号頁・発行日
- 2007
- 著者
- 宮本 正尊
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.855-845, 1965-03-31 (Released:2010-03-09)
7 0 0 0 IR 「伝統医学」の受容基盤をめぐって
- 著者
- 森口 眞衣
- 出版者
- 北海道大学宗教学インド哲学講座
- 雑誌
- 北大宗教学年報 (ISSN:24343617)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.26-35, 2018-08-31
7 0 0 0 OA アカデミア発DDS技術の起業化・事業化の課題
- 著者
- 黒田 俊一
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.251-258, 2017-09-25 (Released:2017-12-25)
- 参考文献数
- 5
2001年に経済産業省より「大学発ベンチャー1000社計画」が発表され、2004年末には約1,000社、2005年末には約1,500社が設立された。そのなかには、創薬系ベンチャーが大きなグループを形成し、DDS技術に特化したベンチャーも数多く存在したが、現在まで存続するものは少なく、存続していても創薬事業を放棄していることが多い。また、2011年以降、大学発ベンチャー設立が再燃しているが、IT系ベンチャーが主であり、DDS技術を含めた創薬系ベンチャーは少ないままである。本稿では、筆者らが2002年に設立したDDS技術をコアとする創薬系ベンチャーの現在までの経緯を概説し、アカデミア発創薬系ベンチャー(特にDDS技術系)の起業化・事業化の課題を指摘した後、今後の発展につながる提言を行いたい。
7 0 0 0 人力飛行機における離陸滑走時の必要パワーの計測
- 著者
- 吉川 俊明 坂本 慎介 堀 琴乃 楠本 寛 山本 康 服部 高資 佐多 宏太
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会論文集 = Journal of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences (ISSN:13446460)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.655, pp.391-395, 2008-08-05
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
In this paper, we propose the method for the measurement of required power and the adjustment of optimum gear ratio in take-off ground running. To get the values of required power and speed, we measured torque of the left side and the right side of pedals, RPM of pedals, and speed of the cockpit frame. In order to improve the take-off speed, some drums were applied, and the optimum gear ratio of the front drum to the rear drum was determined.
- 著者
- 岡部 貴美子 牧野 俊一
- 出版者
- 日本ダニ学会
- 雑誌
- 日本ダニ学会誌 (ISSN:09181067)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.73-84, 2002-11-25
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3 15
日本産キムネクマバチの成虫は雌雄共に、後体部第1節及び中胸部翅基部後方にアカリナリウムをもっていることが確認された。中胸部のアカリナリウムの開口部は、雌よりも雄の方が大きかった。後体部のアカリナリウムは、X. latipesなどで記録されている著しく陥入した空洞ではなく、細長い溝であった。キムネクマバチからは、クマバチコナダニ、コガタノクマバチコナダニ、ヒメクマバチカザリコナダニの3種の第二若虫が採集された。このうちクマバチコナダニとコガタノクマバチコナダニの個体数が圧倒的に多かった。3種のダニは、労働寄生あるいは寄主の巣の中のゴミを摂食する腐食者と考えられた。クマバチコナダニはそのほとんどが中胸部の毛に定着していたが、クマバチコナダニより体が小さなコガタノクマバチコナダニはアカリナリウム内や翅の基部に多かった。これはおそらくクマバチコナダニは体サイズが大きくアカリナリウムに入れないが、寄主の毛をつかめるためと思われた。更に、ハチとダニの相互作用の観点から、Xylocopa属のアカリナリウムの特徴について考察した。
7 0 0 0 OA 宮廷儀礼としてのノウルーズ : 16世紀後半サファヴィー朝宮廷とムガル朝宮廷の比較から
- 著者
- 後藤 裕加子 Yukako Goto
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.94-110, 2005-09-25
7 0 0 0 IR ルーヴル、オルセー、ポンピドゥーになぜ日本画がないのか?
- 著者
- 杉本 昌裕 斉藤 幸義
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学文学部紀要 (ISSN:13481444)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.A63-A81, 2016-03-25
7 0 0 0 IR 安倍晋三の『戦後レジームからの脱却』 : 文化と伝統の視点から
- 著者
- 東郷 和彦 Kazuhiko TOGO 京都産業大学世界問題研究所
- 出版者
- 京都産業大学世界問題研究所
- 雑誌
- 京都産業大学世界問題研究所紀要 = The bulletin of the Institute for World Affairs, Kyoto Sangyo University (ISSN:03885410)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.3-12, 2015-03
7 0 0 0 IR サルトルは日本でどのように受容されたか : その黎明期を中心として
- 著者
- 増田 靖彦
- 出版者
- 学習院大学
- 雑誌
- 人文 (ISSN:18817920)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.81-101, 2007
サルトルが日本に受容されるに当たっては、いくつかの困難が存在した。彼の多様な執筆活動に対応しきれない日本のアカデミズムの構造や、第二次世界大戦という世界の特殊な状況などがそれに当たる。 そうした困難を克服しつつ、サルトルの受容はまず作品の素描や翻訳から始まった。その蓄積はやがて、サルトルの作品を総体として論じる試みとなって現れる。その嚆矢となったのが、サルトルをフッサール現象学に基づいた自我の問題提起として読解する研究であり、自己と他者の関係を基礎付ける人間学として読解する研究であり、今日の人類が抱える思想的課題と格闘する文学者として読解する研究であった。これらの研究はいずれも、サルトルの思想家としての側面に焦点を当てていることが特徴的である。 しかし、サルトルの作品における形式及び内容の変化と、行動する知識人というイメージの流布とによって、そうした研究動向にも転換の時期が訪れる。日本におけるサルトルの受容はもっぱら実存主義者サルトルを前面に押し出すようになっていくのである。This paper tries to clarify how Sartre's thoughts came to be known and studied in Japan. At the time they were introduced into Japan, there were two main difficulties: the subdivided organization of special studies in Japanese academia and the grave situation of the world during World War II. The introduction of Sartre into Japan began with the sketch or translation of his works. These efforts easily made it possible to treat the works of Sartre as a whole. An assortment of studies appeared such as those which discussed his thoughts on the problematic of ego based on Husserlian phenomenology, those which concidered his thoughts as an anthropology founded on the relationship between the self and the other, and those which considered him to be a man of letters tackling every kind of task important for the modern human. Each one of these studies focused on the thinker in its own characteristic way. However, as Sartre altered the form and content of his works, and was held in high reputation as the intellectual who acts, the studies on Sartre gradually began to move in another direction. They came to project Sartre as an existentialist in the foreground of their interpretations.
7 0 0 0 異性装と御釜(<特集>中世における「聖なるもの」)
- 著者
- 西山 克
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.46-56, 1996
禅僧大極の日記『碧山日録』応仁二年一一月一九日条には、釜鳴りを鎮める作法-釜鳴法-が書き記されている。なかで興味深いのは、異性装によるトランス・ジェンダーにより釡鳴りが鎮まるとする法である。なぜ、異性装により釜鳴りが鎮まるのか。またこの釜鳴法が、現代日本の下位文化において語られるオカマという隠語と、どのように関わるのか。日本中世の女装者である持者の存在をも視野におさめながら、聖なるオカマを論じ、インドの両性具有者ヒジュラを遠望してみたい。
7 0 0 0 超並列V言語とそのマルチスレッド実行方式の概要
V言語はデータフロー向き関数型言語validを拡張したもので,依存関係のないものは全て並行動作することを前提とした言語である.計算の進行する頂序を規定するのは依存関係だけである.依存関係を持つものの間で頻繁な同期が必要となるが,データフロー同期方式により同期は暗黙のうちに行なわれ,プログラマが明示的に同期を指定する必要はない.ある計算に必要な値がまだ求まっていない場合は,その値が決まるまで実行が中断し,値が求まった時点で自動的に同期がとられ計算が再開する.V言語では,自律して並列に動作するプロセスとしてagentインスタンスを生成し,並列オブジェクト指向風の計算を行なうことができる.agentインスタンスはカプセル化された内部状態を持ち,お互いの間でストリームを通じてデータをやり取りしながら計算を進める.インスタンス間の同期もデータフロー同期方式によって行なわれる.送信側では通信路に次々にデータを流し,受信側では通信路の出口からデータを読みとって計算を進める.データが到着していなければ読みとり側のプロセスは待たされ,データが到着すると待ちが解かれ処理が進む(メッセージ駆動orデータ駆動).ストリームの要素をメッセージとみなせば並列オブジェクト指向と考えることが出来るが,処理内容がメッセージだけで決定するなら,Validの枠組での関数呼び出しで済む.ここでagentを導入したのは,並行に動作し内部状態を持ったプロセスと,それらの間の自由度の高い通信を容易に記述することが目的である.出来る限り関数性を保持するため,agentの内部で状態を保持するためには,再帰で明示的に状態をフィードバックする.本稿ではagentを中心にV言語の特徴とその処理系,並列実行モデルの概略について述べる.V言語プログラムは命令レベルの細並列処理も可能だが,ここでは種々の並列計算機上での実現を意識したマルチスレッド並列実行モデルについて述べる.
7 0 0 0 IR 幕末の上海貿易
- 著者
- 本庄 榮治郎
- 出版者
- 京都帝國大學經濟學會
- 雑誌
- 經濟論叢 (ISSN:00130273)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.780-789, 1938-05-01
7 0 0 0 IR 日本のイラク戦争支持の問題点(2)
- 著者
- 野崎 久和
- 出版者
- 北海学園大学
- 雑誌
- 季刊北海学園大学経済論集 (ISSN:03857263)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.49-76, 2010-03-25
7 0 0 0 OA <研究論文>日米開戦60周年と記者桐生悠々
- 著者
- 壱岐 一郎
- 出版者
- 沖縄大学
- 雑誌
- 沖縄大学人文学部紀要 (ISSN:13458523)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-12, 2002-03-31
21世紀,最初の年は米中枢多発テロ,炭疽菌テロで米国が揺らいだ。日本政府は英国に次ぐ武力報復協力を示した。「報復」ムードの中で1941年9月に急死した,ジャーナリスト桐生悠々(1873-1941)を回顧することは無駄ではなかろう。大阪,東京,長野,名古屋などで記者活動をした桐生は信濃毎日新聞主筆として関東防空大演習を嗤う」を書き,退社に追い込まれ,60代の8年間,半月刊の個人誌『他山の石』を発行し続けたが,日米開戦3か月前,「廃刊の辞」を記した。「この超畜生道に堕落しつつある地球の表面より消え失せることを歓迎致し居り候うも,唯小生が理想したる戦後の一大軍粛(ママ)を見ることなくして早くもこの世を去ることは如何にも残念至極に候う」(一部,現代読みに訂正)と記した。九・一一事件の直後,米大統領は「西部劇」そして「十字軍」のように進撃をと口走った。低劣な台詞は「畜生道の地球」が決して軍縮の道を歩いていないことを示す。
- 著者
- 平山 勉
- 雑誌
- 東洋文化研究 (ISSN:13449850)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.67-104, 2016-03-01
The purpose of this paper is to clarify the relationship between the middle management of the South Manchuria Railway Company (SMR) and the employees association, Mantetsu-Shain-kai, in order to better understand the characteristics of SMR’s in-house bulletin known as Kyowa. Why focus on middle management instead of upper management officials? The main reason is that the highest ranking company officials―the president and vice president―tended to be hired from outside the company and had rather short terms of office. Moreover, only a few of these people actually stayed for the duration of these relatively short terms. But middle level directors who were promoted internally often had careers of more than ten years either as department heads or chief managers of each section. That is the reason why we must analyze SMR’s middle management. On the other hand, those officers at the headquarters of Mantetsu-Shain-kai were selected in a democratic way. These officials were the chief secretary, the permanent secretary and the chief of section. Most of these people were SMR’s middle management officers at the same time, or would become chief managers of sections later on. Mantetsu-Shain-kai was a facility for the training of SMR’s middle management. According to the account settlement of Mantetsu-Shain-kai, ‘membership fees’ and ‘revenue from publication’ occupied most of the revenue, and ‘publication expenses’ accounted for most of the expenditure. Most ‘publication expenses’ were used to publish Kyowa. The main activity of the headquarters’ officers of Mantetsu-Shain-kai was to declare their own views in Kyowa in order to manage SMR as the key member. Understanding Kyowa is important in order to properly analyze the economic system in China in 1930-40s.
- 著者
- 水島 豪太 野口 佳裕 西尾 綾子 喜多村 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.583-584, 2011 (Released:2013-12-05)
7 0 0 0 教育学部所属大学生のICT活用指導力の実態と関連要因
- 著者
- 竹野 英敏 谷田 親彦 紅林 秀治 上野 耕史
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.147-155, 2011
本研究では,教員養成課程におけるICT活用指導力の組織的な向上を図るための基礎的知見を得ることを目的とした.ICT活用指導力の18項目と,PCやインターネットの使用経験や形態を質問項目とした調査を実施し,教育学部に所属する1219名の大学生から有効回答を得ることができた.その結果,教育学部生のICT活用指導力は,授業の展開・評価,態度の涵養及び校務処理に関する面において低調であることが示された.また,ICT活用指導力の向上には,PCに対する興味・関心,自由に利活用できるPCの所有,様々な目的や方法によるPCの利用・活用などの要因が結びついていると推察された.さらに,ICT活用指導力には,メールや表計算などのPC使用形態や,HP作成などのインターネット使用形態が影響しているのではないかと考えられ,これらの学習活動や利用形態を経験させることによってICT活用指導力の充実を図ることができるのではないかと思われた.
7 0 0 0 IR 江戸後期から明治初期の絞り染め : 江戸の浮世絵,京の古裂
- 著者
- 上田 香
- 出版者
- 意匠学会
- 雑誌
- デザイン理論 (ISSN:09101578)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, pp.74-75, 2019-01-21
大会研究発表要旨第60回大会 2018年8月8日~9日 同志社大学