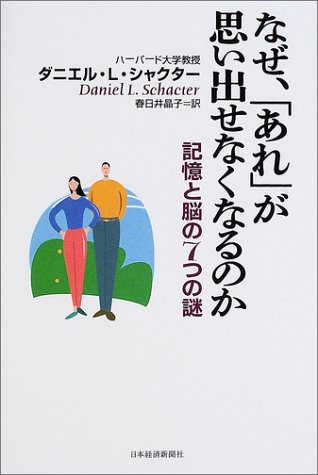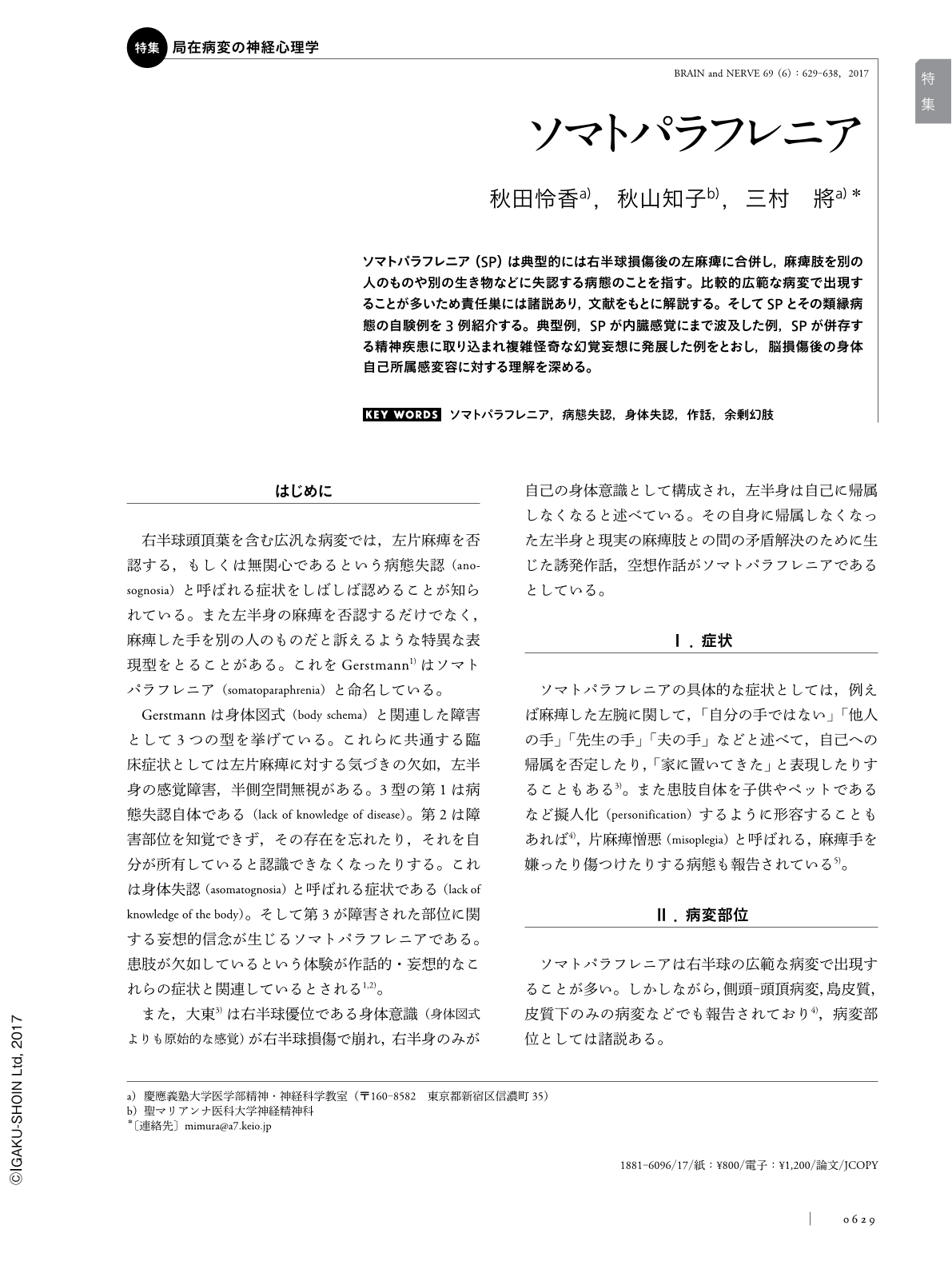1 0 0 0 OA トラックドライバーの過労に影響する働き方と休み方の横断的検討
- 著者
- 松元 俊 久保 智英 井澤 修平 池田 大樹 高橋 正也 甲田 茂樹
- 出版者
- 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所
- 雑誌
- 労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)
- 巻号頁・発行日
- pp.JOSH-2019-0021-GE, (Released:2019-12-06)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
本研究は,脳・心臓疾患による過労死の多発職種であるトラックドライバーにおいて,労災認定要件であ る過重負荷と過労の関連について質問紙調査を行った.1911人の男性トラックドライバーから,属性,健康状態, 過重負荷(労働条件:運行形態,時間外労働時間,夜間・早朝勤務回数,休息条件:睡眠取得状況,休日数),疲労感に関する回答を得た.運行形態別には,地場夜間・早朝運行で他運行に比して一か月間の時間外労働が 101時間を超す割合が多く,深夜・早朝勤務回数が多く,勤務日の睡眠時間が短く,1日の疲労を持ち越す割合 が多かった.長距離運行では地場昼間運行に比して夜勤・早朝勤務回数が多く,休日数が少なかったものの, 睡眠時間は勤務日も休日も長く,過労トラックドライバーの割合は変わらなかった.過労状態は,1日の疲労の持ち越しに対して勤務日と休日の5時間未満の睡眠との間に関連が見られた.週の疲労の持ち越しに対しては,一か月間の101時間以上の時間外労働,休日の7時間未満の睡眠,4日未満の休日の影響が見られた。運行形態間で労働・休息条件が異なること,また1日と週の過労に関連する労働・休息条件が異なること,過労に影響 を与えたのは主に睡眠時間と休日数の休息条件であったことから,トラックドライバーの過労対策には運行形態にあわせた休日配置と睡眠管理の重要性が示唆された.
1 0 0 0 OA ハピネストレーニングプログラムが主観的幸福感の変容に及ぼす効果
- 著者
- 根建 由美子 田上 不二夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.177-184, 1995-06-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 2
Bradburn (1969) indicated that psychopathology focuses too exclusively on the negative affect and psychologists ignore the positive aspects of life. The purpose of the present study was to compare the effects of the psychotherapy in order to increase well-being on subjective well-being modification with one of the psychotherapy so that anxiety would decrease. In the group on increasing well-being, happiness training program (Fordyce, 1977) was used. In the group on decreasing anxiety, the general cognitive behavior therapy was used. The result was obtained for the effects of the cognitive behavior therapy which could increase subjective well-being and could decrease anxiety. But the effects of the happiness training program were not significant.
1 0 0 0 OA 家畜人工授精の現况
- 著者
- 西川 義正
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.5, pp.233-238, 1965-05-25 (Released:2009-05-25)
1 0 0 0 OA 韓国のヘルスツーリズムにおける健康・美容認識に関する研究
- 著者
- 李 彰美
- 出版者
- RIKKYO UNIVERSITY(立教大学)
- 巻号頁・発行日
- 2014-09-19
観光学研究科観光学専攻
1 0 0 0 OA [B16] 学術論文出版からみる研究データへのDOI付与とその粒度の考え方の課題
- 著者
- 尾鷲 瑞穂
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.171-174, 2019-03-15 (Released:2019-06-01)
- 参考文献数
- 5
オープンサイエンスの潮流が広がる中、研究データの公開とその方法についても関心が高まっている。科学研究の学術論文投稿時には、その研究を通して生産された研究データの公開が求められ、メタデータと併せて永続的固有識別子であるDOI(Digital Object Identifier)をその研究データに付与することが求められるようになってきている。その際には、データの再利用や引用のしやすさを考慮した上で、その粒度やメタデータへの記載にも留意する必要がある。しかし、その考え方は、分野によっても相違があり、統一した方法があるわけではない。今回は、気象観測データや環境モニタリングなど、先に集積的なデータが公開されており、それを解析して研究を行うようなケースと、社会調査や疫学調査など、データ集計の経過途中で論文が出版されるケースを取り上げ、学術論文の出版を見据えた研究データへのDOI付与の考え方の必要性を報告する。
1 0 0 0 木材を曲げる(化学への招待)
- 著者
- 則元 京
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.170-174, 1991
- 被引用文献数
- 1
木材は, 軽くて強いけれども, 比較的脆い材料であるとの印象をもつ者は, カットに示すような曲げ木を見ると, 驚くかもしれない。また同時に, どのようにすればこのように木材を曲げられるのか, 木材の微細構造はどのようになっていて, 曲げるとどのような構造の変化が起こるのか, この変形は永久的なものなのか, など多くの疑問がわいてくるかもしれない。本稿では, 細胞壁の微細構造と関連づけて, 木材の軟化, 曲げ変形とその固定, 変形の回復の仕組みを説明し, 曲げやすい木材と曲げにくい木材の構造上の違いに触れ, 最後に, 家庭用電子レンジを使って木材を曲げる方法について紹介する。
1 0 0 0 なぜ、「あれ」が思い出せなくなるのか : 記憶と脳の7つの謎
- 著者
- ダニエル・L・シャクター著 春日井晶子訳
- 出版者
- 日本経済新聞社
- 巻号頁・発行日
- 2002
- 出版者
- 防衛弘済会
- 雑誌
- セキュリタリアン (ISSN:09182306)
- 巻号頁・発行日
- no.524, pp.54-55, 2002-07
1 0 0 0 OA 能の身体 : その時代的変遷
- 著者
- 石井 倫子
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号 第47回(1996) (ISSN:24330183)
- 巻号頁・発行日
- pp.73, 1996-08-25 (Released:2017-08-25)
1 0 0 0 ソマトパラフレニア
- 著者
- 秋田 怜香 秋山 知子 三村 將
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.6, pp.629-638, 2017-06-01
ソマトパラフレニア(SP)は典型的には右半球損傷後の左麻痺に合併し,麻痺肢を別の人のものや別の生き物などに失認する病態のことを指す。比較的広範な病変で出現することが多いため責任巣には諸説あり,文献をもとに解説する。そしてSPとその類縁病態の自験例を3例紹介する。典型例,SPが内臓感覚にまで波及した例,SPが併存する精神疾患に取り込まれ複雑怪奇な幻覚妄想に発展した例をとおし,脳損傷後の身体自己所属感変容に対する理解を深める。
優れた殺菌/抗菌効果を発揮する銀粒子は,粒子径の微小化に伴い,その抗菌活性を飛躍的に向上させることから,既に直径10~100 nmのナノマテリアル(NM),1~10 nmのサブナノマテリアル(sNM)としての応用が急速に進展している。従って,銀微小粒子の安全性担保に向け,物性-動態-安全性の詳細な連関解析によるナノ安全科学研究が急務となっている。特に近年,NMが生体蛋白質と相互作用し,NMを核とした蛋白質の層構造(プロテインコロナ)が形成されることが報告され,NMの動態・安全性を制御する可能性が示されつつある。しかし,粒子径や表面性状といった物性が,プロテインコロナの形成におよぼす影響は未だ不明な点が多い。特にsNMは,当研究室が昨年の本会で報告したように,分子ともNMとも異なる動態・生体影響を示すことから,粒子径の違いがプロテインコロナの形成に影響を与えた可能性が疑われる。そこで,本検討では,物性-プロテインコロナ形成-生体影響の連関解析の第一歩として,粒子径の異なる銀粒子を用いて,血清存在/非存在下における細胞傷害性を比較解析した。ヒト肺胞癌細胞株(A549細胞)に,直径20 nm未満のナノ銀(nAg),直径1 nm未満のサブナノ銀(snAg)を血清存在/非存在下で添加し,細胞傷害性を比較した。その結果,nAgは血清非存在下で高い細胞傷害性を示すものの,血清の添加によって細胞傷害性の低下が認められた。一方で,snAgは血清の有無に関わらず,ほぼ同等の細胞傷害性を示すことが明らかとなった。以上の結果から,sNMの生体影響に対する血清蛋白質の寄与は少ないことが示唆された。今後は,プロテインコロナの観点から,細胞内取り込み効率を含めた解析を進め,本現象のメカニズム解明を図ると共に,本現象が認められるNM/sNMの粒子径の閾値を探索していく予定である。
- 著者
- 横井 龍雄 首藤 洋志 池田 賢一 中田 伸生 土山 聡宏 大村 孝仁 峯 洋二 高島 和希
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.5, pp.244-252, 2016 (Released:2016-04-30)
- 参考文献数
- 38
Dual Phase (DP) steel is used in automotive body parts for weight saving and crashworthiness, however there is an issue of DP steel in low stretch flange ability evaluated by hole expanding tests. In order to improve stretch flange ability of DP steel, it is important to estimate the damage of punching quantitatively and to clarify the change of microstructure before and after punching because the hole expansion ratio is decided in the ductility remained after pre-strain equivalent to punching. Therefore we tried to measure the damage of punching by unique techniques of Electron Backscatter Diffraction (EBSD), nano-indentation and micro-tensile testing and to observe fracture surface by Scanning Transmission Electron Microscope (STEM). Average EBSD-Kernel Average Misorientation (KAM) value and pre-strain damage have strong correlation, thus average KAM value can become the index of the damage. The nanohardness and tensile strength using micrometer-sized specimens increased with increasing average KAM value in the ferritic phase as approaching the punching edge. A shear type fracture occurred without necking in the specimen cut out in the area of the edge. The ultrafine-grained ferritic microstructure was observed in the sample cut out in the same area with STEM. It seems that the ductility loss of the punched DP steel was probably attributed to localized strain into the ultrafine-grained ferritic microstructure.
1 0 0 0 忘れられる権利に配慮した生体認証:爪を用いたマイクロ生体認証
- 著者
- 杉本 元輝 藤田 真浩 眞野 勇人 大木 哲史 西垣 正勝
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.12, pp.2095-2105, 2019-12-15
近年,プライバシ保護の観点から「忘れられる権利」の必要性が度々議論されている.本権利はEUの一般データ保護規則に「消去権」として記載されたこともあり,世界的に注目を集めており,生体認証の分野においてもこの「消去権」への配慮が求められる.その一実現形態としてテンプレートを乱数でマスクするキャンセラブル生体認証(テンプレート保護技術)が存在する.しかしこの方式では,登録された電子的な生体情報を保護することは可能であるが,登録時や認証時に提示される物理的な生体情報の漏洩まで保護することは不可能である.本論文では,物理的な生体情報に対して「消去権」に配慮した生体認証を実現するため,人間の微細生体部位を用いたマイクロ生体認証システムを爪へと応用した生体認証システムを構築した.ユーザ実験を通じて有用性を検証した結果,本システムが物理的な生体情報に対してテンプレート保護技術に準じた安全性を提供できる可能性が示された.