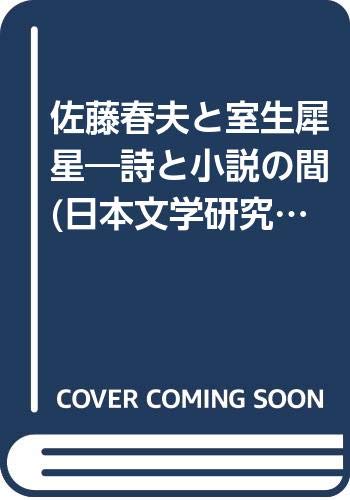1 0 0 0 OA 3.医薬品開発におけるリアルワールドデータ活用への期待 ―製薬企業の視点より―
- 著者
- 東郷 香苗 川松 真也 木口 亮 今井 康彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬剤疫学会
- 雑誌
- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.19-30, 2019-03-31 (Released:2019-05-17)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 1 3
医薬品開発におけるエビデンス創出はこれまで臨床試験に偏っていたが,そのアプローチにはもっと選択肢があるべきであり,リアルワールドデータ (RWD) がその役割を果たすことが期待される.ICH GCP リノベーションでも,多様な試験デザインとデータソースの選択肢を持つこと,患者に画期的な新薬を早く提供するために早期承認申請をサポートすることが挙げられている.本邦においても,条件付き早期承認制度や改正GPSP 省令で医療情報データベースや患者レジストリ等の活用が可能であることが明記された.本稿では,医薬品開発における RWD の活用として,① 承認申請データへの活用, ②臨床試験計画および患者リクルートメントへの活用,③ Electronic Health Record をデータソースとした臨床試験データの収集,④ 臨床試験の評価や診断への活用,⑤ 開発戦略,薬価・アクセス戦略への活用についてまとめる.それぞれの活用場面で課題があり,インフラと規制環境の整備が望まれるものの,それを待つことなく医薬品開発の現場でRWD の活用が進むことに期待したい.
- 著者
- Masato TAKEUCHI
- 出版者
- The Imaging Society of Japan
- 雑誌
- 日本画像学会誌 (ISSN:13444425)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.633-643, 2019-12-10 (Released:2019-12-10)
- 参考文献数
- 38
The near infrared (NIR) spectroscopy has been applied to analyze the catalyst and adsorbent surfaces. Since H2O molecules were hardly stabilized on the SiO2 surface, the hydrogen bond networks of H2O cluster on the SiO2 surfaces was almost similar to liquid phase H2O. In contrast, H2O molecules were largely stabilized on the TiO2 or Al2O3 surfaces. Thus, the H2O clusters on the TiO2 or Al2O3 surfaces had more complicated hydrogen bond networks as compared to liquid phase H2O. We have further discussed the correlation between the hydrophilic/hydrophobic properties and the surface wettability. Then, the NIR measurements for the SiO2 and cellulose adsorbents grafted with organic functional groups clearly showed the typical absorption bands due to NH2, CH3, and CH2 groups. The alkyl or aminopropyl grafted SiO2 adsorbed drastically smaller amounts of H2O molecules as compared to the pristine SiO2. While the alkyl grafted cellulose showed still hydrophilic surface character because the pristine cellulose was highly hydrophilic. Finally, the NIR spectroscopy enabled the simultaneous analyses of NH3, NH4+ and H2O adsorbed on zeolite surfaces.
1 0 0 0 OA 上総層群国本層中の更新世前期-中期境界付近に発達するシルト岩層の層相と堆積環境(予察)
- 著者
- 風岡 修 亀山 瞬 森崎 正昭 香川 淳 吉田 剛 荻津 達 西田 尚央 岡田 誠 菅沼 悠介 会田 信行 熊井 久雄 楡井 久
- 出版者
- The Geological Society of Japan
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.325, 2014 (Released:2015-03-16)
1 0 0 0 OA 標識したカワウのコロニーからの長距離移動
- 著者
- 福田 道雄
- 出版者
- 日本鳥類標識協会
- 雑誌
- 日本鳥類標識協会誌 (ISSN:09144307)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.5-10, 1994 (Released:2015-08-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
東京都上野公園不忍池のコロニーに住むカワウの,日常的な行動範囲はコロニーから30~40km以内とみられる。この範囲を越える50km以上離れた地点で,7羽のカラーリングを装着したカワウが観察確認または回収された。それらが出生コロニーから消失したのは2~11カ月齢であった。関東地域に生息するカワウは定住していたが,幼鳥がより遠方まで移動するという3種のウ類についての報告と同じ傾向を示していた。不忍池コロニーのカワウは,100km以内の移動は短期的な放浪で,出生コロニーに帰還することも多く,200km以上の移動は分散で,他のコロニーに住み着いてしまうことが多いと考えられる。これらのことには,不忍池の200km以内に,個体の行き来のあるコロニーが無いという立地条件が大きく影響していた。さらに,不忍池のように定住したカワウでも、生息地域内での羽数の増加やコロニーや塒が複数化することで,移動・分散しやすくなるとみられた。
1 0 0 0 佐藤春夫と室生犀星 : 詩と小説の間
- 著者
- 佐久間保明 大橋毅彦編
- 出版者
- 有精堂出版
- 巻号頁・発行日
- 1992
1 0 0 0 OA パーソナリティ特性をどうイメージするか
- 著者
- 酒井 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.63-74, 2019-03-30 (Released:2019-09-09)
- 参考文献数
- 45
パーソナリティ特性を,単純な「数直線」ではなく「多面体」として捉え,多面性・多様性を含んだものと考える立場から,2017年7月から2018年6月までの1年間に『教育心理学研究』に掲載された論文,および,日本教育心理学会第60回総会における発表やシンポジウムを中心に,いくつかのパーソナリティ研究を取り上げ,(a)特性の多面性を意識した研究,(b)尺度項目の多様性を意識した研究,(c)個人内の構造を意識した研究,に大別して論評した。さらに,「パーソナリティ特性にマイナス極が存在するか」という問題についても論じた。
- 著者
- 角山 栄
- 出版者
- 文芸春秋
- 雑誌
- 諸君 (ISSN:09173005)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.6, pp.34-50, 2002-05
1 0 0 0 OA 相模湾西部沿岸におけるマナマコの分布と産卵期
- 著者
- 片山 俊之 木下 淳司
- 出版者
- 神奈川県水産技術センター
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.17-24, 2013 (Released:2014-02-07)
1 0 0 0 OA 山口県瀬戸内海東部平生町地先のマナマコの産卵期について
- 著者
- 村田 実 松野 進
- 出版者
- 山口県水産研究センター
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.53-58, 2010 (Released:2014-08-18)
- 著者
- Mitsukuri,K.
- 出版者
- 日本動物学会
- 雑誌
- 日本動物学彙報
- 巻号頁・発行日
- vol.1, 1897
1 0 0 0 OA 稚ナマコ(アカナマコ)飼育における付着珪藻以外の餌料の比較
- 著者
- 江口 勝久
- 出版者
- 佐賀県玄海水産振興センター
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.5-9, 2015 (Released:2016-01-20)
稚ナマコ飼育工程における付着珪藻と併用効果の高い餌料を明らかにすることを目的とした餌料試験を実施した。当センターの飼育方法に依った着底直後~15日程度までの餌料としては,用いた3種(浮遊珪藻,海藻粉末,付着珪藻粉末)の餌料の中で,浮遊珪藻が適すると考えられた。また,着底後15日以降の餌料としては,海藻粉末のマコンブ粉末が適すると考えられた。今後,マコンブ粉末を主体とし,他の成分の添加等を検討し,稚ナマコ用配合餌料の改良を行っていく予定である。
1 0 0 0 OA 北海道北部宗谷周辺海域に棲息するマナマコの重量と消化管の季節変動
- 著者
- 中島 幹二 合田 浩朗
- 出版者
- 北海道立総合研究機構水産研究本部
- 巻号頁・発行日
- no.87, pp.71-79, 2015 (Released:2015-06-24)
北海道宗谷周辺海域から得られたマナマコを用いて,体重や消化管長の季節変動を調べた。体重に対する内臓重の割合は,10月に最低値を示した。体重に対する腸長の割合も同様に10月に最低値を示し,この時期に内臓のリセット(内臓を新しくする)が行われていることを示唆した。殻重に対するその乾燥重量の割合は,夏季に最低値を示した後,8~9月の間に急激な上昇が認められ,秋季に最高値となった。このことは夏季から秋季にかけて体壁構成成分量の大きな減少があることを意味している。これらより,本種は,1年の中で内臓や体壁構成成分量の劇的な変動を毎年繰り返しながら成長していることが明らかとなった。
1 0 0 0 OA 水槽内でのマナマコの摂餌行動におよぼす砂粒の影響
- 著者
- 木原 稔 田本 淳一 星 貴敬
- 出版者
- 水産総合研究センター
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.39-43, 2009 (Released:2011-07-26)
マナマコへの給餌方法の検討を目的に、ワカメ粉末、ワカメ粉末と砂粒、および砂粒を水槽底面に散布し、マナマコに70日間給餌した。その結果、砂粒+ワカメ粉末区では糞塊が高い頻度で確認でき、生残率も高く(73%)、体重も実験開始時に比べ2.2倍に増加した。砂粒区では糞塊は確認できず、ワカメ粉末区では糞塊は確認できたものの、飼育開始後30日目での生残率は2区ともに20%以下であった。以上より、ナマコには微粒子の栄養物質に併せて砂粒を投与することで、給餌効果を高められると考えられた。
- 著者
- Mitsukuri K.
- 出版者
- 日本動物学会
- 雑誌
- 日本動物学彙報
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.31-42, 1897
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 箸の使い勝手について箸の持ち方 (その2)
- 著者
- 向井 由紀子 橋本 慶子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.8, pp.622-627, 1981-09-20 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
1) 伝統的なA型の持ち方は, 対象物がこわれやすい場合や, 2種の試料を交互に運ぶような複雑な作業の場合に, 失敗が少なく作業能率もよいこと, また焼魚の肉をわけるなどのように箸もひらいて用いる場合も鉛筆式の持ち方であるB型よりも早くできることがわかった.2) 自然に箸を持った位置とひらく作業後の箸を持った位置をみると, A型では指先の移動が少なかった.このことよりB型は作業時に箸を持ちかえるのに対し, A型はそのようなごとが少なく安定した持ち方といえるのではないかと考えられた.3) 箸先をひらく作業では測定筋のうちで背側骨間筋の筋活動度が大きく箸先をひらいて用いる場合の特徴と思われた.4) 伝統的な箸の持ち方では鉛筆式の持ち方に比べて短母指外転筋の活動度が大きいが, これは第一指で一方の箸を固定すると同時にもう一方の箸を動かすためと考えられ, 伝統的な持ち方の特徴であると思われた.
1 0 0 0 OA 建築構造物とコンクリート
- 著者
- 世良 耕作
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.7, pp.51-57, 1990-07-01 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 神楽継承用教材としての立体視CGの評価
- 著者
- 佐藤 克美 海賀 孝明 渡部 信一
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.Suppl., pp.145-148, 2011-12-20 (Released:2016-08-08)
- 参考文献数
- 4
神楽継承用教材として立体視CGにどれほど効果があるかを明らかにするため,フレームシーケンシャル方式の3D眼鏡を採用したプロジェクタ用およびパララックスバリア方式を採用した裸眼立体視モニター用の2方式の立体視CGを評価した.予備調査として高校生に立体視CGを視聴してもらったところ,3D眼鏡をかけた立体視の方がよいとの回答が多く,没入感やリアリティーの高さが教育に役立つと考えれた.また神楽の師匠と弟子たちに調査をしたところ全員が裸眼立体視がよいと答えた.明るく,はっきりしていることがその理由だった.立体視CGは複雑で理解が難しいものに対して学習者の理解を助ける役目が期待されていると思われた.
1 0 0 0 IR 映画『食人族』とモンテーニュの食人言説
- 著者
- 高岸 敦夫
- 出版者
- 関西大学フランス語フランス文学会
- 雑誌
- 仏語仏文学 (ISSN:02880067)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.165-179, 2011
伊藤誠宏教授退職記念号