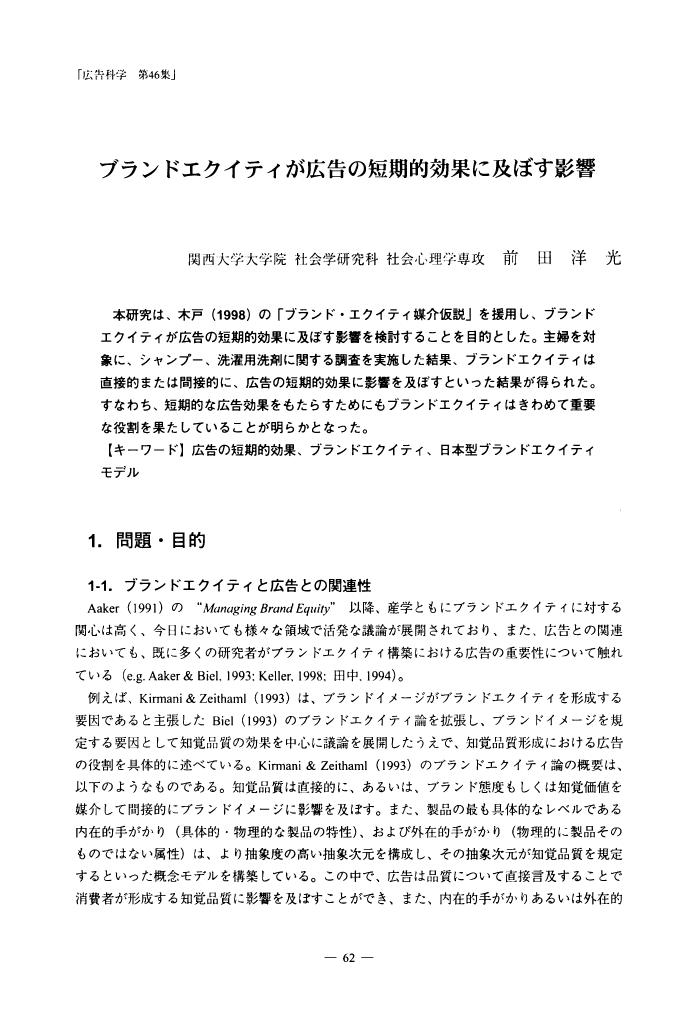- 著者
- 塩原 直美
- 出版者
- 茨城県立医療大学
- 雑誌
- 茨城県立医療大学紀要 (ISSN:13420038)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.139-143, 2003-03
精神科における長期入院患者には, 精神症状を呈する知的障害者のいることがある。報告する症例は32歳で統合失調症の症状として時折, 不穏・興奮状態を呈し, 対人行動において適切な行動がとれない知的障害を有する女性であった。当該長期入院患者に対し適応の援助として遊び的な手芸活動と園芸, レクリエーションの集団活動を作業療法介入とした。その結果, 症例は行動随伴性の制御により, 衝動的な行為が改善し退院に至った。しかし, 数年後に再入院をした。本症例に対する作業療法の経験は, 統合失調症に知的障害をあわせもつ場合には, より詳細な評価と治療プログラムの継続ならびに社会資源の活用が必要であることを示唆するものである。
- 著者
- 菅原 裕文 樋口 諒
- 出版者
- 金沢大学国際文化資源学研究センター
- 雑誌
- 金沢大学文化資源学研究 = Kanazawa cultural resource studies (ISSN:2186053X)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.57,59-65, 2019-03
1 0 0 0 OA スポーツの競技特性要因と二分法的思考との関連
- 著者
- 上野 雄己 三枝 高大 小塩 真司
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- Journal of Health Psychology Research (ISSN:21898790)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.35-44, 2017-08-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 60
Correlations between factors characteristic of competitive sports (athletic events and competitive levels) and dichotomous thinking were investigated. A questionnaire survey was conducted with university students in university athletic clubs (N=200, 67 men and 133 women, mean age=19.5, SD=1.2). The results indicated the following. (1) Dichotomous Thinking Inventory (DTI, Oshio, 2009) is appropriate for use with athletes. (2) Athletes in general use more dichotomous thinking, compared to average Japanese university students. (3) No significant differences in DTI scores were observed between individual and group events, although the possibility of a hierarchical structure consisting of micro (individual athletes)–macro (athletic group: athletic event) was suggested. (4) DTI score of male athletes tended to be higher in the high-competitive, compared to the low-competitive group. These results indicate that dichotomous thinking, which could be maladaptive, might have adaptive functions in sports.
1 0 0 0 IR グスタフ・シュモラーの重商主義論
- 著者
- 田村 信一
- 出版者
- 北星学園大学
- 雑誌
- 北星学園大学経済学部北星論集 = The Faculty of Economics, Hokusei Review (ISSN:02893398)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.71-101, 1986-03
1 0 0 0 OA 家庭お伽文庫
- 著者
- 吉岡向陽, 高野斑山 編
- 出版者
- 春陽堂
- 巻号頁・発行日
- vol.第一篇, 1912
- 著者
- 山内 香奈
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第46回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.425, 2004-09-10 (Released:2017-03-30)
1 0 0 0 OA ブランドエクイティが広告の短期的効果に及ぼす影響
- 著者
- 前田 洋光
- 出版者
- 日本広告学会
- 雑誌
- 広告科学 (ISSN:13436597)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.62-75, 2005 (Released:2017-10-25)
1 0 0 0 OA 広告認知と店頭配荷による販売への影響
- 著者
- 竹内 淑恵
- 出版者
- 日本消費者行動研究学会
- 雑誌
- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1-2, pp.19-33, 2005-03-31 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 衛藤 涼太
- 出版者
- Japan Society of Sports Industry
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.1_123-1_125, 2018 (Released:2018-02-09)
1 0 0 0 OA テトラサイクリンによる稚ナマコ囲食道骨の標識
- 著者
- 松野 進
- 出版者
- 山口県水産研究センター
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.65-71, 2002 (Released:2011-03-05)
稚ナマコへのテトラサイクリン(TC)による標識方法を検討した結果、TCを餌料に約10%添加して約2週間経口投与することにより、またはTC濃度100ppmで4日間、浸漬投与で囲食道骨が最も安定して標識されることが分かった。標識した稚ナマコを海域に放流し、追跡調査を行った結果、161日後に標識の確認ができ、従来、唯一有効とされてきた焼き印標識より約2ヶ月間有効期間が長かった。ナマコが約125mm程度に成長して標識部位に新たな骨組織が厚く被った場合には囲食道骨の直接検鏡によるTC標識の識別は困難となるため、有効期間は成長状況にもよるが、半年間と推察された。放流から161日後にTC標識が確認できた再捕個体群の可食部からは、細菌に対して活性を有するTC系抗生物質は検出されなかった。
1 0 0 0 マナマコの資源生物学的研究
- 著者
- 熊本 哲也
- 出版者
- 岩手県立大学高等教育推進センター
- 雑誌
- Liberal arts = リベラル・アーツ (ISSN:18816746)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.101-114, 2016
Le Voyage à Tokyo d'Ozu est un film célèbre qui évoque la destruction progressive des liens parent-enfant au sein des membres d'une même famille dans les années 1950. Il est vrai que dans ce film on voit partout des éléments montrant une coupure entre les vieux parents et leurs descendants. Ceci peut peut-être s'expliquer par la divergence d'appréciation sur le temps vécu ; les moments réitératifs et stagnants chez les parents âgés, en opposition au temps irréversible qui s'écoule sans arrêt du point de vue de leurs enfants. Ces deux groupes générationnels habitent très loin l'un de l'autre et mènent des vies très différentes entre vie traditionnelle à la campagne et vie moderne à Tokyo ; ils vivent et ressentent le cours du temps bien différemment. Or, dans le film d'Ozu, certaines scènes signalent l'heure exacte : il y a, par exemple, celle du tout début du film dans laquelle Shukichi précise l'horaire exact du passage du train à Osaka. En réalité, ce train n'existait pas d'après l'emploi du temps de cette époque. On trouve aussi une autre scène qui dévoile une conversation intime entre Tomi et Noriko, discussion qui commence tout juste à minuit. Ces heures ne sont pas choisies par hasard mais presque par nécessité dans la mesure où le Voyage à Tokyo peut se découler sur un temps répétitif et stagnant, tout en évoquant aussi une histoire de la mort qui symbolise l'irréversibilité de la vie. Noriko jouée par feue Setsuko Hara, veuve du deuxième fils des vieux parents, se trouve du côté de Shukichi et de Tomi, parce qu'elle est aussi une femme qui vit dans des moments figés. Mais à la fin du film, la montre héritée par Shukichi - quoi de mieux pour symboliser le temps ? - permettra de "redémarrer" la vie de Noriko dans le train qui la ramène à Tokyo.
1 0 0 0 OA 理科教育における「問いの設定」の学習内容の構成
- 著者
- 内ノ倉 真吾 廣 直哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.41-46, 2017-12-02 (Released:2018-07-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
科学の内容的・手続き的な知識,メタ科学的な知識に着目して,アメリカの科学スダンダ ード・カリキュラム・教科書における問いの設定の学習内容の構成を調査した。科学スタンダードでは,第一に,小学校から高校段階にかけて,問いの設定に関する手続き的・メタ科学的な知識の習得が図られるように構成されていた。第二に,問いの設定に関する学習内容としての手続き的・メタ科学的な知識は,問いの種類,問いの条件,議論に係わる問いの3 つに分類しうるものとなっていた。 一方,教科書や補助教材では,第一に,科学的な問いの重要性や具体的な事例が中心的な内容であった。第二に,科学的な問いの定義が提示されている場合,観察や情報の収集で答えられるのが科学的な問いとされ,科学的には答えられない問いの性質や具体例も併せて提示されていた。第三に,特定の事物・事象に即して問いを立てるという学習場面の設定は,ほとんど見られず,実際の授業での指導に委ねられていると推察されるのであった。
1 0 0 0 OA 中学生による科学的に探究可能な問いの判断と生成の実際
- 著者
- 廣 直哉 内ノ倉 真吾
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.49-52, 2017-11-18 (Released:2018-07-01)
- 参考文献数
- 14
中学校と大学生への質問紙調査を基にして,与えられた事物・事象の探究可能性の判断と生成する問いの特性を探った。第一に、大学生は,一部の問題を除いて,適切に探究可能性を判断できていたのに対して,中学生は,倫理的な判断や個人的な好みに係わる問題が科学的に探究可能な問題ではないと判断できていたものの,それ以外の事物・事象について適切に判断できていなかった。第二に,中学生と大学生ともに,探究可能であると判断できた場合は,適切な問いの生成もできている傾向が見られた。しかしながら,大学生が生成する問いには,事物・事象の原因や理由を問う疑問や,対照実験を意図した疑問が見られるのに対して,中学生が生成する問いには,与えられた事物・現象をそのまま利用した疑問が多く,問いの生成に違いが見られた。
1 0 0 0 OA 科学的リテラシーに必要な認識に関する知識をどのように評価するか
- 著者
- 塩瀬 隆之 後藤 崇志 加納 圭
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会年会論文集 42 (ISSN:21863628)
- 巻号頁・発行日
- pp.61-62, 2018 (Released:2019-06-14)
- 参考文献数
- 5
本稿は,科学的リテラシーに必要な「認識に関する知識」を評価するために、どのような項目が必要かを特定するため、PISA 型の過去問について回答理由まで掘り下げた追加設問への回答傾向から偽陽性、偽陰性の傾向を分類、どのような項目候補が想定されるか、調査結果について概説する。
1 0 0 0 OA NICTサイエンスクラウドセキュアWebアプリケーション開発協力手法
- 著者
- 渡邉 英伸 上野 宣 村田 健史
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.291-296, 2014-10-06 (Released:2014-12-31)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 1
科学データのオープン化に対する取り組みが進められる中で,Web アプリケーションの脆弱性は避けて通れない問題である.NICTサイエンスクラウドでも,Web アプリケーションの公開を希望するクラウド利用者の技術的スキルや専門知識を問わず,高水準のセキュアなWeb アプリケーションの開発が可能な仕組みや体制が要求されるようになった.本論文では,一般競争入札方式を想定し,NICTサイエンスクラウド利用者のWeb アプリケーション開発の技術的スキルや専門知識が乏しい場合においても,セキュアなWeb アプリケーションを開発するための開発協力手法を提案する.
1 0 0 0 気象がナラ枯れ(ブナ科樹木萎凋病)に及ぼす影響に関する初歩的研究
<p>カシノナガキクイムシの穿入に伴うナラ枯れ被害が1980年代以降に拡大している.被害拡大要因として気象条件も指摘されているが,統計解析に基づいた仮説はない.そこで,舞鶴市と京都市で実施された被害量調査の結果を基に,ナラ枯れ被害量の増減と気象条件との関係を単回帰分析で解析した.その結果,両地域ともで,厳冬期(1~2月)の最高気温が高いほど被害が助長される傾向が認められた.また,京都市では春期の降水量が多いほど被害が助長される傾向が認められた.さらに,舞鶴市では,6~7月の間の最低気温が20℃以上の日数が多いほど被害が助長される傾向が認められた.ただし,通説化している夏期の高温・少雨が被害を助長することを支持する明確な結果は得られなかった.</p>