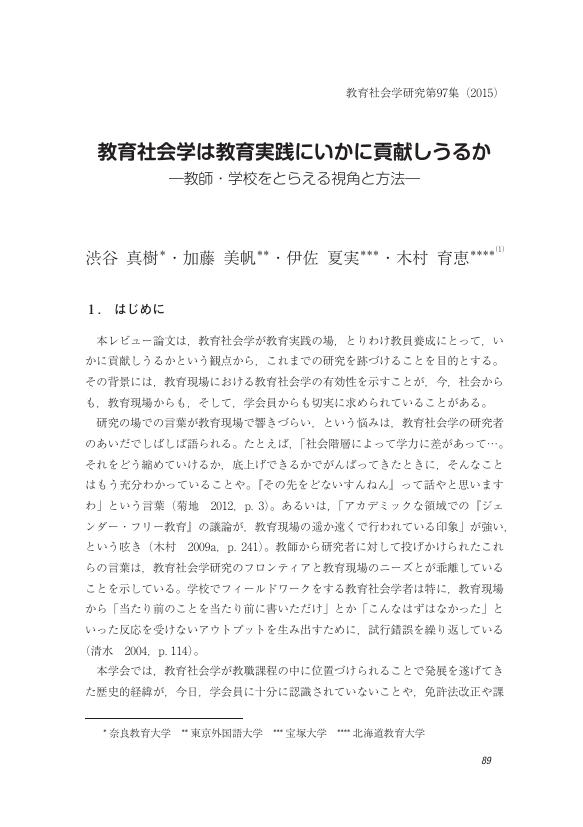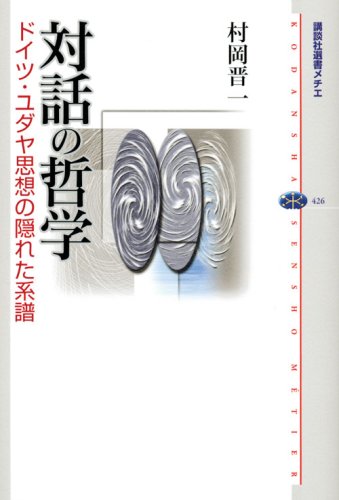1 0 0 0 OA 都市研究における消費への着目と流通システム研究の再構築
- 著者
- 土屋 純
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2010年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.140, 2010 (Released:2010-11-22)
本発表では「商品」の持つ意味に着目し,都市研究と流通システム研究との新たな融合を試みたいと考える.比較的古くから存在する商品であり,近年では流通チャネルの多様化が進んでいる「化粧品」に着目していきたい. 流通システム研究における「商品」の取り扱い 地理学における流通システムに着目した都市研究は,(1)都市空間における商業の集積・分布パターンを検討した研究,(2)商品フローに着目した流通システム研究,(3)都市社会と消費との関係に着目した研究,の3つに大別できると考える.流通システムを取り扱っている以上,商品について少なからず考察が行われていると考えられるが,では3つの分野ではどのように「商品」を取り扱ってきたのであろうか. まず,(1)の分野では,商品への着目は概して少なかったといえよう.ベリーの中心地研究を引用しつつ,店舗の集積や分布状況について検討し,商業と都市構造との関係について検討してきた. (2)の分野では,商品のフローに着目し,主にチェーンストアなどを題材として,地理的に広がる市場に対してどのように商品が配送されているのか,配送コストに着目して分析してきた.その際の商品の取り扱いは,大量販売としての商品の「量」,配送コストなどの「コスト面」への着目である.こうした研究では,流通システムの経営的,経済的仕組みを解明することに主眼が置かれていることから,流通の最終段階である「消費」に対する考察が十分に行われていなかった.その結果,商品の質的側面について検討してこなかったといえよう. 都市研究における消費への着目 では,(3)の分野では商品はどのように取り扱っているのであろうか.注目したいのは,アメリカの諸都市におけるジェントリフィケーション研究における消費への着目である. 例えば,Smith(1996)は,スターバックスコーヒーに着目し,ジェントリフィケーションとの関わりを検討するために,スターバックスにおける店舗デザイン,商品開発,サービスを考察している.(1)都市のインナーシティにおける再開発地域という環境が,1990年代中頃までにスターバックスの営業戦略を形作り,(2)シアトル系コーヒーという商品文化がチェーン展開によって様々な地域に展開していったこと,を指摘している.ジェントリフィケーション研究では,新中間層の消費に着目して,新たな食文化を題材として場所の意味について考察しているのである. 他にも(3)の分野では,ショッピングセンターの建造環境や,グローバルな商品連鎖と消費,など様々な側面に着目した研究が行われており,欧米諸国の都市社会を舞台に議論が進んでいる. 化粧品流通から日本の都市を捉える 本発表では,日本における化粧品の流通システムについて検討し,都市空間,消費との関わりについて捉えることを試みる.欧米のように日本の都市社会でも階層分化が進行し,消費が多様化していると考えられるが,(1)化粧品流通はどのように進化しているのか,(2)都市空間の中でどのように再編成されているのか,の2点ついて検討できればと考える. 化粧品とは,基礎化粧品とメークアップ化粧品といった顔につけるものから,ボディ用商品など多岐にわたる.化粧品の流通システムは,百貨店のインショップでのメーカーの直接販売だけでなく,コンビニやドラッグストアでの大量販売も行われ,近年ではインターネットやテレビなどの通信販売も発展している.また,@コスメなどインターネットの書き込みサイトも登場し,新たな社会ネットワークも発達している. 参考文献 Michael, D. Smith. 1996. The empire filters back: consumption, production, and the politics of Starbucks coffee. Urban Geography 17: 502-525.
1 0 0 0 OA 1990年代以降の教員養成カリキュラムの変容
- 著者
- 佐久間 亜紀
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, pp.97-112, 2010-06-30 (Released:2017-04-21)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
本稿では,90年代以降の教員養成カリキュラムの変容とその問題点を,高等教育全体の改革動向に位置づけて整理した。先行研究において,教員養成論と高等教育論は乖離しがちであり,近年の高等教育改革が教員養成カリキュラムに及ぼした影響は,充分に検討されてこなかった。 高等教育全体に市場原理を導入する90年代以降の改革は,教員養成大学・学部と教育委員会の「連携」を「融合」ともいえる状態にまで至らしめ,大学教育の質を向上させるという本来の意図とは裏腹に,教員養成カリキュラムの「矮小化」や「非学間化」を進行させていた。また,90年代にいったんは規制緩和に向かった教免法の改革は,00年代以降「再統制化」の傾向を強め,教員養成カリキュラムの「規格化」を進行させていた。そして教員養成大学・学部は,学生の成長を支援し教員を「養成」する機関から,国や地方自治体の求める規格や要望にあわせて教員を「供給」する機関へと変質しつつあった。これらの変化から,改革の意図とは裏腹に,輩出される教員の「質」が低下している可能性を指摘した。 最後に,大学とは何かという共通理解が失われた高等教育界の現状を踏まえれば,先行研究の鍵語とされてきた「大学における教員養成」「開放制」という二語では,もはや近年の教員養成の変容を捉えきれなくなっていることを指摘した。その上で,今後の教員養成研究は,高等教育論に充分根ざしつつ探究される必要があることを論じた。
1 0 0 0 OA 教職を支援する教育社会学は可能か?
- 著者
- 加野 芳正
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, pp.158-163, 2017-07-28 (Released:2019-03-08)
1 0 0 0 OA 教育社会学は教育実践にいかに貢献しうるか
1 0 0 0 OA <寄稿論文>近世後期大阪菊屋町の人口と乳幼児死亡 (佐々木陽一郎先生退官記念号)
- 著者
- 速水 融
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 千葉大学経済研究 (ISSN:09127216)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.353-387, 1998-12-02
The urban mortality rate was generally higher than the rural rate in pre-modern society. This resulted from the population influx from rural to urban areas, giving the empirical evidence to the "urban graveyard theory."Since Tokugaya period saw a heavy i佐々木陽一郎先生退官記念号Collected Papers on the Occasion of the Retirement of Professor Yoichiro Sasaki
1 0 0 0 OA 10 立位・片脚立位時の下肢筋活動と足部回内可動域の関係 : 表面筋電図による検討
- 著者
- 西守 隆 中島 敏貴 西埜植 祐介 森 清子 矢田 敦子 大工谷 新一 西口 悟 鈴木 俊明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.26 Suppl. No.1(第34回日本理学療法士学会 第26巻学会特別号)
- 巻号頁・発行日
- pp.5, 1999-05-23 (Released:2017-09-22)
1 0 0 0 OA 雪室をビルトインした住宅における空調性能試験その4
- 著者
- 上村 靖司 宝地戸 謙介 伊藤 親臣
- 出版者
- 公益社団法人 日本雪氷学会/日本雪工学会
- 雑誌
- 雪氷研究大会講演要旨集 雪氷研究大会(2009・札幌) (ISSN:18830870)
- 巻号頁・発行日
- pp.122, 2009 (Released:2009-12-10)
1 0 0 0 OA 実測による天井放射パネル冷暖房システムの性能評価
- 著者
- 李 栄玲 大岡 龍三 W. OLESEN Bjarne
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.705-708, 2013-09-01 (Released:2014-02-07)
- 参考文献数
- 6
天井放射パネル冷暖房は,放射により人体を直接暖める,あるいは冷やすものであり,搬送動力や空調ファン動力を削減することができる.また不要なドラフトを避け,快適性も向上することが期待されている.本研究では,天井放射パネルのエネルギー利用効率に着目し,その基本性能を明らかにするため,実測を行う.熱フラックスの計測値とISO 11855-2の理論式の計算結果がよく一致し,計測値の精度を確認できた.送水温度35 ºC・40 ºCの場合,総括熱伝達率U1 は約3.7 W/(m2 ºC)であり,熱利用比率は60%~65%であり,水から放射パネル表面の熱伝達率は9 W/(m2 ºC)であった.室内空間の温度差は1.5 ºC以内であったため,快適な温熱環境を形成していると判断される.
1 0 0 0 対話の哲学 : ドイツ・ユダヤ思想の隠れた系譜
1 0 0 0 OA 影響の論理 : レオナルドオの光と暗の系譜
- 著者
- 植田 寿蔵
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.1-12, 1959-09-30 (Released:2017-05-22)
Differentiation expects unification. If two things can be differentiated each other, it is because each of them has its proper basic structure meaning. Meaning must be its meaning forever. A meaning, which assumes the form of one thing, must necessarily assume another form. Following after this logic, there are innumerable things that are unified into one meaning. The fact of influence in the art history is brought into existence under this circumstances. The existence of one thing expects that of another thing. There is basically the sequence of time in this connection. When a painter, secing the work of another painter, learns his style, it is said that there is a fact of influence. In this case two conditions must be satisfied. First, to confirm from records that be saw the work of his predecessor. Second, to recognize that his predecessor's style is transmitted to his painting. It shows the influenced style but is quite different one, unless it is merely a copy. It is newly created one as well as inherited. This means a progress of the sight which has appeared in the form of the artistic style of the predecessor's work. This is the logic of influence.
1 0 0 0 OA 航空郵便の利用について
- 著者
- Fumio WATANABE Yuri TANIOKA Emi MIYAMOTO Tomoyuki FUJITA Hiroyuki TAKENAKA Yoshihisa NAKANO
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.183-186, 2007 (Released:2008-01-10)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 15 19
Vitamin B12 content (98.8±5.6 μg/100 g dry weight) of an edible cyanobacterium, Nostoc commune (Ishikurage) was determined by the Lactobacillus delbrueckii ATCC 7830 microbiological method. Bioautography with vitamin B12-dependent Escherichia coli 215 indicated that N. commune contained two (main and minor) corrinoid-compounds. These corrinoid-compounds were purified to homogeneity from the dried algal cells and characterized. The main and minor purified corrinoid-compounds were identified as pseudovitamin B12 and vitamin B12, respectively, on the basis of silica gel 60 TLC, C18 reversed-phase HPLC, 1H NMR spectroscopy, and UV-visible spectroscopy. These results suggest that the bacterial cells are not suitable for use as a vitamin B12 source, especially in vegetarians.
- 著者
- 濱田 麻矢
- 出版者
- 愛知大学現代中国学会
- 雑誌
- 中国21 (ISSN:13428241)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.207-222, 2015-08
1 0 0 0 OA 北京で語られるアメリカ像 ─宗璞の一九四九年、イーユン・リーの一九八九年─
- 著者
- 濱田 麻矢
- 出版者
- 愛知大学現代中国学会
- 雑誌
- 中国21 = China 21 (ISSN:13428241)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.207-222, 2015-08-20
1 0 0 0 ナルシシズムとマゾヒズム--大衆文化と男性性
- 著者
- 國友 万裕
- 出版者
- 京都外国語大学
- 雑誌
- 京都外国語大学研究論叢 (ISSN:03899152)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.15-27, 2003
1 0 0 0 OA 可視的変形者に対する一般人の評価と認識―写真刺激を用いて―
- 著者
- 深谷 悦子 岩滿 優美
- 出版者
- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター
- 雑誌
- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)
- 巻号頁・発行日
- pp.2018002, (Released:2019-01-18)
- 参考文献数
- 42
Objective: This study aimed to assess how the general public perceives and evaluates people with visible differences.Methods: This study targeted 153 university and graduate students. These students were shown four photographs, and were asked to anonymously answer an originally-developed questionnaire which included items on perception and evaluation of people with visible differences. After excluding questionnaires with missing values, we analyzed data from a total of 127 participants. Results and Discussion: High evaluation scores were obtained for five items, including “readily catching the eyes of others” and “being surprised when running into them.” This reflects difficulties experienced by people with visible differences. There were significant sex-differences in five items, including “being in a disadvantageous position when it comes to marriage” and “difficult to have a loving relationship with someone”; suggesting men evaluated people with visible differences more negatively than women. When assessing how participants perceived the reasons underlying the visible differences in free descriptions, the rate of correct answers differed by the specific reason. In particular, for port-wine stain, even in the perception group are had a low rate. These findings highlight the importance of educating the general public so that they would have accurate knowledge regarding visible differences.
1 0 0 0 人間行動遺伝学と教育
- 著者
- 安藤 寿康
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.p96-107, 1992-03
- 被引用文献数
- 1
The present paper reviews the methodology and findings of recent human behavioral genetics in relation to education. Under "interactionism", genetic factors in human development and education have been minimized or treated as taboo. Genetic effect is, however, mainly additive and, heritabilities of IQ and various personality traits are considered to be about 50% in adulthood. Further more, concerning IQ, genetic effects tend to increase from infancy to childhood because of genotype-environment correlation. Recent behavioral genetics are also focusing on environmental effects and the concepts of shared / nonshared environment have been introduced. These findings suggest that genetic factors, are not only related to learning and development but also an important role in the making of one's individuality. Finally, the educational implications of human behavioral genetics are making the topic for a discussion.
1 0 0 0 OA ノンリニア編集におけるリアルタイムテロップ機能“iTake”の開発
- 著者
- 大松 浩一郎
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.J2-J8, 2018-01-01 (Released:2017-12-21)
- 参考文献数
- 1
リニア編集のように映像を止めることなくテロップ付け(またはスーパー)する仕組みを,ノンリニア編集上に実現した.テレビ朝日は 2015年に報道設備がテープからファイルベースのシステムになり,編集面では本格的にノンリニア編集システムを取り入れた.しかし編集マンによると,映像編集は便利になる一方で,テロップ付けは逆に作業が大きな負担になるとのことだった.理由の一つはテロップ付けの際,映像の再生・停止を頻繁に繰り返すため,リニア編集よりもテロップ付けに時間がかかるためだった.もう一つはリニア編集で使っているディレクター用のスーパーボタンがなく編集マンがテロップ付け操作をすべて代行しなければならないためだった.今回の開発により,それら弱点を克服し,ノンリニア編集でのテロップ付けにかかる時間は旧来の半分になった.ノンリニア編集の圧倒的な利便性に加え,リニア編集の弱点であったテロップ付け機能が補強され,両者の長所を併せ持った編集システムが実現できた.