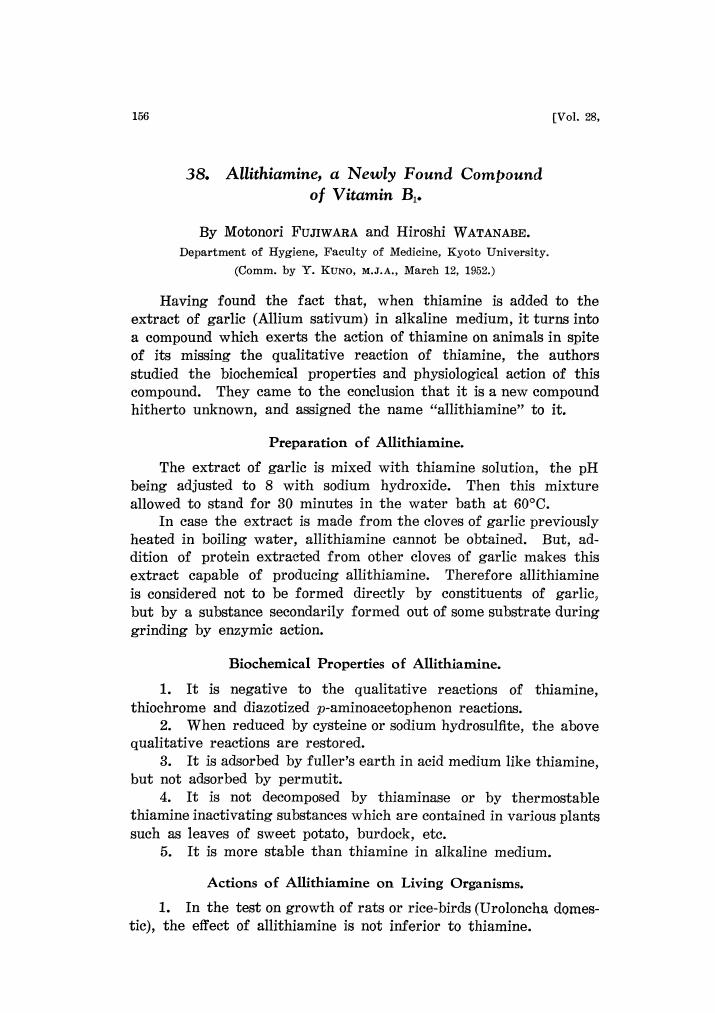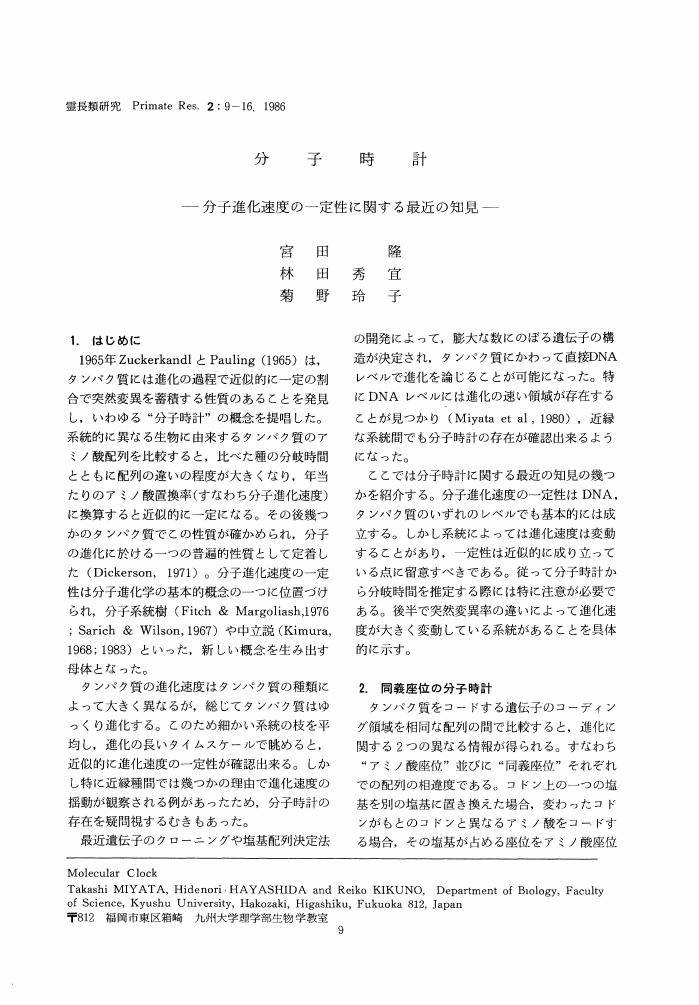- 著者
- Tomomi HARA Tatsuki TSUJIMORI Kennet E. FLORES Jun–Ichi KIMURA
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.6, pp.296-301, 2019 (Released:2020-01-22)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 2
Lawsonite, jadeite, and glaucophane are iconic minerals within a Pacheco Pass metagraywacke of the Franciscan Complex, California. Those minerals and the associated quartz form the distinctive very low–temperature and high–pressure metamorphic lawsonite–jadeite–glaucophane assemblage, which is diagnostic of ‘cold’ oceanic subduction zones. In this paper, we evaluate the ability of lawsonite geochemistry to trace protoliths with in–situ trace element and Sr–Pb isotope analyses in lawsonite from the Pacheco Pass blueschist–facies metagraywacke, a classical example of trench–fill sediments in subduction zones. Initial Sr isotope ratios are relatively high (87Sr/86Sr = 0.7071–0.7074), and initial Pb isotope ratios are 206Pb/204Pb = 18.74–19.66, 207Pb/204Pb = 15.58–15.70, and 208Pb/204Pb = 38.41–39.34, which range from a MORB trend to a cluster on the EMII component. These geochemical signatures suggest the protolith of the metagraywacke mainly contained material derived from continental volcaniclastic rocks and quartzofeldspathic sediments. There is also a possibility that the protolith contains plume–related oceanic island basalt that reached or intruded into the fore–arc sedimentary sequence of California. Considering the maximum depositional age of the metagraywacke at ~ 102 Ma, the subduction of the Farallon Plate beneath the continental crust of the North American Plate might have carried alkali basalt with OIB–like isotopic signatures to the Franciscan trench. Our study proves the advantage of in–situ lawsonite Sr–Pb isotope analyses to characterize protoliths of metamorphic rocks. The results would manifest that the Sr–Pb isotopic signature of Ca–Al silicate minerals, such as lawsonite, and possibly epidote and pumpellyite, in various types of metamorphic/metasomatic rocks, would be an effective tool for investigating convergent margins.
- 著者
- Chinatsu YAMADA Tatsuki TSUJIMORI Qing CHANG Jun–Ichi KIMURA
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.6, pp.290-295, 2019 (Released:2020-01-22)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 6
The antigorite–grade serpentinite and Late Paleozoic high–pressure schists are main components of a serpentinite–matrix mélange in the Itoigawa–Omi area, Hida–Gaien Belt, Japan. Based on the petrologic characteristics of the high–pressure schists, the mélange is divided into two units, namely an ‘eclogitic unit’ and a ‘non–eclogitic unit’. Our preliminary in–situ boron isotope analyses of five serpentinites using a laser–ablation multiple–collector inductively–coupled–plasma mass spectrometry (LA–MC–ICPMS) found a systematic difference of boron isotopic trends among the two units in the same mélange. The ‘eclogitic unit’ serpentinites from Yunotani and Kotagi–gawa are characterized by lower δ11B value (mostly lower than +10‰), whereas the non–eclogitic unit serpentinite from Omi–gawa is higher than +10‰. Although the δ11B value of <0‰ was not measured from the eclogitic unit serpentinites, the relatively low δ11B values of <+10‰ might have recorded the signature of fluids released from deep subducted dehydrating slab. In contrast, the non–eclogitic unit serpentinite might have been affected by fluids released from shallower portion. Our new data confirmed the potential sensitivity of the boron isotope signature of serpentinites reflecting variation of high–pressure metamorphism.
3 0 0 0 OA フューチャー・デザイン
- 著者
- 西條 辰義
- 出版者
- 環境経済・政策学会
- 雑誌
- 環境経済・政策研究 (ISSN:18823742)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.29-42, 2018-09-28 (Released:2018-10-27)
- 参考文献数
- 57
持続可能な自然と社会を将来世代に引き継ぐために,どのような社会制度をデザインすればよいのかを課題とするのが「フューチャー・デザイン」である.その手法の1つである「仮想将来世代」を中心に,理論的背景,ラボラトリ実験やフィールド実験の結果および幾つかの自治体との実践の様子を展望する.
3 0 0 0 OA ダイオキシン類・ポリ塩化ビフェニル曝露と糖尿病との関連
- 著者
- 上村 浩一
- 出版者
- 一般社団法人日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.363-374, 2012 (Released:2012-06-26)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 8 10
Persistent organic pollutants (POPs) are a group of chemical substances that have the common properties of resistance to biodegradation, wide-range transportation, high lipophilicity, bioaccumulation in fat, and biomagnification in the food chain. POPs are persistent in the environment worldwide and have potential adverse impacts on human health and the environment. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), and polychlorinated biphenyls (PCBs) are well known chemicals that are considered as POPs. The association between high-level exposure to dioxins and type 2 diabetes among U.S. Air Force veterans who had been exposed to Agent Orange contaminated with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) during the Vietnam War was reported in the late 1990s. This association has been supported by similar epidemiologic studies, whose subjects were exposed to high doses of dioxins in their places of work involving phenoxyacid herbicide production and spraying, and in the industrial accident in Seveso, Italy. Recently, low-level exposure to dioxins and PCBs has been reported to be linked to type 2 diabetes. Cross-sectional studies in the U.S. general population and Japanese general population showed that body burden levels of some dioxins and PCBs were strongly associated with the prevalence of type 2 diabetes. Very recently, following these cross-sectional studies, several prospective studies have suggested that low-level exposure to some PCBs predicted the future risk of type 2 diabetes in the general population. Environmental exposure to some dioxins and PCBs, which mainly accumulate in adipose tissue, may play a role in the development of type 2 diabetes.
3 0 0 0 OA 慢性心不全患者に対する患者教育は心不全増悪による再入院率を低下させる
- 著者
- 中島 宏樹 大川 保昭 久保 寛紀 水野 翔太 三宅 真一 浅井 徹 杉浦 剛志 志水 清和 柴田 哲男
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0741, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに,目的】慢性心不全患者は年々増加しており,再入院率が高いことが問題となっている。これまでに退院前患者教育が慢性心不全患者の再入院率を低下させることが報告されているが,わが国において患者教育を実践している医療機関は限られ,長期的なフォローアップを行う体制をもつ医療機関はほとんどない。さらに,患者教育プログラムに運動指導が含まれていないことが多い。今回,我々は心不全患者に対する運動指導を含めた患者教育が退院後1年以内の再入院率減少に有効であるか検討した。【方法】心不全増悪で入院した心不全患者73名(平均年齢70.5±9.6歳)を対象とし,当院で患者教育を導入する前の対照群36名と導入後の患者教育群37名との退院後1年間での再入院率を比較した。除外基準は,認知症(改訂長谷川式簡易知能評価スケール<20),6分間歩行距離<100 m,過去の心不全入院歴≧3回,慢性閉塞性肺疾患を合併する症例,入院中あるいは退院後に心臓外科手術を受けた症例,中枢神経疾患や骨関節疾患による運動制限がある症例とした。患者教育は理学療法士と看護師により実施し,患者教育には,心不全の病態と増悪因子・増悪時の対処法,体重管理,運動指導,塩分・水分制限,過活動制限,感染予防,栄養,服薬管理および血圧測定について当院で作成した資料を用いて行った。なお,患者教育群は入院中に通常のリハビリテーションプログラムに加え,計5-6単位の個別教育を実施した。退院後1年間,当院に再入院することなく,外来診察がないために経過が確認できない症例については自宅に電話して他院への再入院の有無などの状況を確認した。統計解析は,ベースライン時の各因子の2群間の比較に対応のないt検定またはMann-Whitney U検定を用いた。また,再入院率は,退院日を起点としてKaplan-Meier法を用いて算出し,有意差検定にはlog-rank検定を用いた。統計学的有意水準は5%未満とした。統計ソフトウェアにはEZR(ver. 1.11)を用いた。【倫理的配慮】本研究は一宮市立市民病院倫理委員会の承認を得て行った(承認番号:9)。対象者には事前に書面および口頭にて研究の目的や内容の説明を行い,書面での承諾を得た。【結果】心不全増悪による再入院率は患者教育群で5名(13.5%),対照群では12名(33.3%)であった。ベースライン時の年齢,Body Mass Index,心不全増悪による入院回数,左室駆出率,脳性ナトリウム利尿ペプチド値,推算糸球体濾過量および6分間歩行距離の評価項目において2群間で有意差は認めなかった。心不全増悪による再入院率は患者教育群と対照群との間に有意差が認められた(log-rank test,P<0.05)。【考察】退院前の患者教育が心不全増悪による1年以内の再入院率を有意に低下させた。患者教育群は教育を実施しなかった対照群と比較し,再入院率が19.8%低下した。心不全患者は心不全増悪の要因として,塩分・水分制限の不徹底や過活動,治療薬の不徹底,感染などの予防可能な因子が上位を占め,心筋虚血や不整脈といった医学的要因よりも多いことが知られている。過活動の制限に関しては,嫌気性代謝閾値(AT)を超えての運動・活動の持続がダブルプロダクトの上昇による心負荷となり心不全増悪の要因となるが,運動耐容能の低下した症例では日常生活活動で容易にAT強度を超えるため,過活動となる機会が多いことが予想される。先行研究において報告されている心不全増悪による再入院に影響を及ぼす因子にはベースライン時で有意差を認めなかったことから,運動指導を含めた患者教育により患者自身が体重管理や過活動の制限,塩分・水分制限,服薬の遵守,感染予防などを実施できたことが再入院率の低下に影響したと考えられる。【理学療法学研究としての意義】心不全患者自身による管理能力が再入院予防において重要であることが示唆されているが,多職種による患者教育を実践している医療機関は少ないのが現状である。一方で,理学療法士が心不全患者に関わる場面は,今後さらに増加することが予想され,心不全管理に関する一般的事項を患者自身およびその家族に指導することは心不全増悪による再入院率を低下させ,さらにQOLを改善する可能性を有している。理学療法士はその一翼を担っており,本研究の結果から理学療法士の立場から患者教育を実践することが再入院率低下に有効であると示唆された。
3 0 0 0 OA スポーツにおけるアミノ酸の使用法とその効果
- 著者
- 鈴木 良雄
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.95-99, 2011-04-30 (Released:2014-11-21)
- 参考文献数
- 39
スポーツにおいてサプリメントとして利用されているアミノ酸のうち, 分岐鎖アミノ酸 (Branched-chain amino acid;BCAA) とグルタミンについて, ヒトで観察されている効果とそのメカニズムについて最近の知見を紹介する. BCAAは, 比較的大量に摂取した場合に, 遅発性筋痛を軽減し, そのメカニズムとしてロイシンによるmTORを介したタンパク代謝の調節があると考えられている. グルタミンは, 術後感染性合併症低下させたり, 運動後の免疫抑制を軽減したりするが, そのメカニズムは当初考えられていた血漿グルタミン濃度の維持による免疫細胞の機能維持ではなく, HSPを介した身体ストレスの軽減であると考えられるようになってきている. グルタミンには, 運動後のグリコーゲンの回復を促進する作用も報告されているほか, 安定なグルタミン素材である小麦グルテン加水分解物 (Wheat Gluten Hydrolysate;WGH) により運動中の血漿グルタミン濃度を維持すると持久運動が可能になる可能性も示唆されている. またWGHには遅発性筋痛を軽減する効果のあることも報告されている.
3 0 0 0 OA 日本の現世哺乳類の起源を考える
- 著者
- 長谷川 善和
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.233-247, 2012 (Released:2013-02-06)
- 参考文献数
- 39
3 0 0 0 母指示指切断に対する切断示指を用いた母指再建の 1 例
- 著者
- 小山田 基子 大安 剛裕 伊藤 綾美
- 出版者
- 日本マイクロサージャリー学会
- 雑誌
- 日本マイクロサージャリー学会会誌 (ISSN:09164936)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.25-28, 2018 (Released:2018-03-23)
- 参考文献数
- 14
In cases of multiple finger amputation, replantation of all amputated fingers may not be possible depending on the condition of the amputated fingers. Therefore, other reconstructive procedures should be considered, such as ectopic replantation, which is an important treatment option, especially when the thumb is one of the amputated fingers. We report the case of a 22-year-old man with complete amputation of his left thumb and index finger. The thumb amputation level was distal of the carpometacarpal joint and the amputated thumb was crushed too severely to perform replantation. We ectopically replanted the amputated index finger to the thumb stump at the anatomical position because the amputated index finger was less damaged. Good results were obtained in terms of both function and appearance.
3 0 0 0 OA 敗血症時のAutophagyと栄養管理
- 著者
- 渡邉 栄三
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.287-292, 2019-12-15 (Released:2020-01-15)
- 参考文献数
- 28
Autophagyは, 細胞の自己成分をlysosomeに運び込み分解する機構であり, 必ずしも細胞死を意味するわけではない. 飢餓応答としての栄養供給という働き以外にも, 不要なオルガネラの分解, 病原微生物の排除, 腫瘍抑制などの役割も確認されており, むしろ生命維持に必須のシステムである. そして敗血症病態下での重要臓器 (肝, 腎, 脾臓の免疫担当細胞など) においては, 発症早期には一過性にautophagyは亢進するものの, その後停滞傾向に向かうことが判明してきており, 臓器保護的な役割を担っている. 一方, 敗血症時の骨格筋では, autophagy過活性が筋萎縮を惹起することも報告され, 臓器やその構成細胞によっては諸刃の剣である. 敗血症とautophagyの関与の解明と, autophagyの生体でのモニタリング手法の確立が, 敗血症時のautophagy動態の制御を企図した栄養管理実現へのポイントである.
- 著者
- Motonori FUJIWARA Hiroshi WATANABE
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- Proceedings of the Japan Academy (ISSN:00214280)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.156-158, 1952 (Released:2006-09-12)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 3 18
3 0 0 0 OA アリチアミンの発見
- 著者
- 藤原 元典
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.857-862, 1953 (Released:2017-12-20)
3 0 0 0 OA アーチ高率の違いによる内外側方向における足圧中心位置の検討
- 著者
- 三秋 泰一 加藤 逸平
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.409-412, 2007 (Released:2007-08-18)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3 4
本研究の目的は,足アーチ高率と内外側方向における足圧中心位置の関係を検討することであった。20名の健常女性の足アーチ高率を測定し,足アーチ高率が11%以下の低い群(4名),11~15%の中等度群(8名),15%以上の高い群(8名)の3群に分け,それぞれの内外側方向における足圧中心位置を比較した。足アーチ高率は低い群で10.7±0.2%,中等度群で11.8±0.5%,高い群で16.7±1.2%であり,足アーチ高率は,低い群および中等度に比較して高い群が有意に高かった。内外側方向における足圧中心位置は,低い群および中等度群が高い群と比較して有意に内側へ偏移していた。これらの結果は,扁平足の評価において内外側方向における足圧中心位置が一指標となりえることが示唆され,足底板を作製する際,この足アーチ高率は,足底板の高さを決める指標に使用できると思われた。
3 0 0 0 OA 昆虫の行動を制御するホルモンの研究の最近の動向
- 著者
- 永田 晋治
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.168-176, 2013-03-01 (Released:2014-03-01)
- 参考文献数
- 60
昆虫が,環境に適応し,正確に成長し,そして繁殖するためには,各成長段階においてライフイベントに関わる行動が規定されている必要がある.つまり,脱皮,摂食行動,生殖行動,社会行動などは,生命や種の維持のための重要なメカニズムなのである.現在,昆虫の内分泌学的な行動制御の仕組みが明らかになりつつある.ここでは,これまでに明らかにされた昆虫の行動を制御する一連のホルモンと,その作用のメカニズムを脱皮,摂食行動,生殖行動をメインに簡単に紹介した.
3 0 0 0 OA 化粧品に用いられる特殊機能粉末
- 著者
- 佐藤 文孝
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.9, pp.397-403, 2006-09-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2
3 0 0 0 OA 神経回路の自発活動パターンとその機能的役割
- 著者
- 田渕 理史 並木 重宏
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.100-111, 2019-08-06 (Released:2019-08-26)
- 参考文献数
- 128
脳は内発的に情報を生み出すことで自身の構造を創り上げることが出来るだけでなく,情報表現のために機能状態を自身で創り換えることも出来るシステムである。 最近の研究から,“神経細胞の自発活動パターン”が,この過程において重要な役割を担っている可能性が示唆されている。 しかしながら,自発神経活動パターンがどのような分子機構によって形成され,どのような情報を伝達しているのか,さらに神経回路の設計指針としてどのように使われているのかなど,まだよく分かっていないことが多い。本総説では,発達期神経系において観察される自発神経活動パターンの時間構造と,それらの形成を担っている分子機構に関して,筆者ら自身の研究も含めた最近の動向を紹介する。 さらに,神経系の発生ないし生後発達の過程において脳の神経回路の基本構造を創り上げる時だけでなく,成熟した脳がより最適化された情報表現を行うために神経回路の機能状態を創り換える時においても,特異的な時間構造パターンを有する自発神経活動が神経機能の再構築のために使われている可能性を議論したい。また,自発神経活動の時間構造の機能的意義の理解に向けた将来発展的な方法論の開発の必要性についても考察したい。
3 0 0 0 OA 東京都区内における路上生活者支援施策の現状と課題
- 著者
- 窪田 亜矢
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.39.3, pp.607-612, 2004-10-25 (Released:2017-08-02)
- 参考文献数
- 20
2002年ホームレス自立支援法が成立した。自治体に実施計画が義務づけられるなか、東京都では自立構築システムのもとで緊急一時保護センターや自立支援センターなどが設けられた。センターの立地やデザイン、内容についてはまだお問題はあるし、ここまでの施策は就労を前提としていることがしばしば指摘されてきた。しかし民間借り上げ住宅も検討され、多様な選択肢が用意され初めている。新宿区では NPOや自治体のみならず地域住民や路上生活者自身が加わる検討協議会も立ち上げられた。事態は進展しつつある。今後は、予防まで含めた総合的な取り組みを進めること、路上生活者自身の主体的な取り組みの支援、居住の権利に基づきながら問題を政治化していくことが必要だ。
3 0 0 0 OA ベタメタゾン点鼻液長期使用にて,医原性Cushing症候群を来たした1例
- 著者
- 小野田 教高 須田 俊宏 木野 紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.12, pp.2513-2517, 2018-12-10 (Released:2019-12-10)
- 参考文献数
- 8
72歳,男性.軽微な打撲で上肢に皮下出血を来たし,赤ら顔,満月様顔貌を認め,Cushing症候群が疑われた.3年前より,ベタメタゾン含有製剤を点鼻で継続使用していたことから,外因性ステロイドが原因であることが判明した.被疑薬剤を中止,ヒドロコルチゾンの補充漸減療法にて症状は軽快した.副腎皮質ホルモン製剤は,投与経路にかかわらず,内因性の視床下部―下垂体―副腎系を抑制し得ることを認識する必要がある.
3 0 0 0 OA 座談会
- 著者
- 大久保 利道
- 出版者
- 北日本病害虫研究会
- 雑誌
- 北日本病害虫研究会報 (ISSN:0368623X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.49, pp.167-169, 1998-11-30 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 8
北海道の札幌においてハマナスのゴールからハマナスメトゲコブタマバチ (Diplolepis fukudae) を確認した。ゴール内には複数の育房がみられ, 出現した蜂の性比は雌に偏っていた。タマバチの寄生蜂としてオナガコバチ, カタビロコバチ, ヒメバチそれぞれ1種が認められたが, 主体はオナガコバチGlypymrerus stigm (Fabricius) であった。
3 0 0 0 OA 分子時計
- 著者
- 宮田 隆 林田 秀宜 菊野 玲子
- 出版者
- Primate Society of Japan
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.9-16, 1986 (Released:2009-09-07)
- 参考文献数
- 21