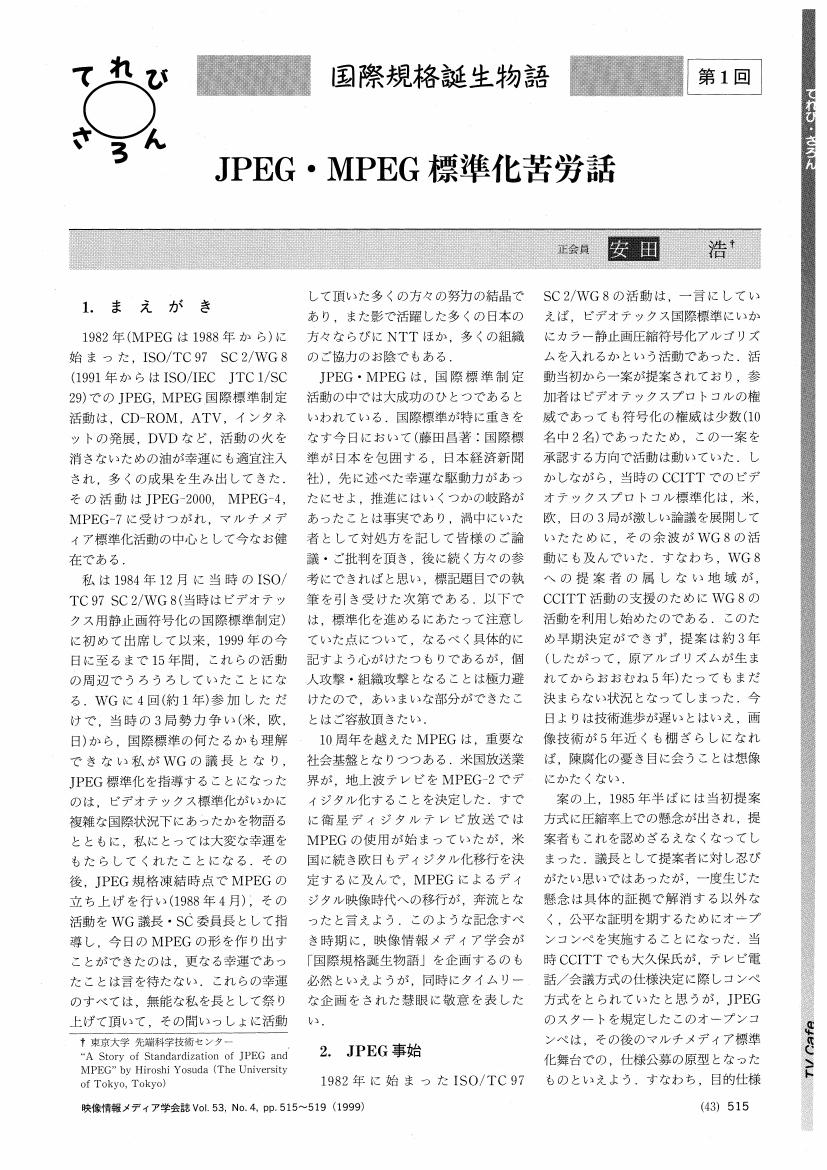3 0 0 0 OA 雜録
- 出版者
- 公益社団法人 日本植物学会
- 雑誌
- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.374, pp.49-55, 1918 (Released:2013-05-14)
3 0 0 0 リン栄養枯渇条件下での根圏糸状菌による植物生長促進
- 著者
- 晝間 敬 西條 雄介
- 出版者
- 日本植物病理学会
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.78-84, 2018 (Released:2018-06-05)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 1
Phosphorus is one of three macronutrients limiting plant growth in natural soils. For efficient phosphate uptake from soil, plants get help from root-associated fungi such as arbuscular mycorrhizal fungi and the root endophyte Colletotrichum tofieldiae. Plants have also developed a phosphate starvation response (PSR) system that senses phosphate starvation and increases phosphate uptake. In this review, we discuss how these two root-associated beneficial fungi contribute to plant growth in phosphate-starvation conditions. We also discuss how the plant PSR system regulates beneficial fungi via the regulation of tryptophan-derived secondary metabolites of the plant.
- 著者
- Michihiro Satoh Takahisa Murakami Kei Asayama Takuo Hirose Masahiro Kikuya Ryusuke Inoue Megumi Tsubota-Utsugi Keiko Murakami Ayako Matsuda Azusa Hara Taku Obara Ryo Kawasaki Kyoko Nomura Hirohito Metoki Koichi Node Yutaka Imai Takayoshi Ohkubo
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-17-1227, (Released:2018-06-09)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 6
Background:N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) has been used for risk stratification in heart failure or acute coronary syndrome, but the beyond 5-year predictive value of NT-proBNP for stroke remains an unsettled issue in Asian patients. The aim of the present study was to clarify this point.Methods and Results:We followed 1,198 participants (33.4% men; mean age, 60.5±11.1 years old) in the Japanese general population for a median of 13.0 years. A first stroke occurred in 93 participants. Referencing previous reports, we stratified participants according to NT-proBNP 30.0, 55.0, and 125.0 pg/mL. Using the NT-proBNP <30.0 pg/mL group as a reference, adjusted HR for stroke (95% CI) in the NT-proBNP 30.0–54.9-pg/mL, 55.0–124.9-pg/mL, and ≥125.0-pg/mL groups were 1.92 (0.94–3.94), 1.77 (0.85–3.66), and 1.99 (0.86–4.61), respectively. With the maximum follow-up period set at 5 years, the hazard ratio of the NT-proBNP≥125.0-pg/mL group compared with the <30.0-pg/mL group increased significantly (HR, 4.51; 95% CI: 1.03–19.85). On extension of the maximum follow-up period, however, the association between NT-proBNP and stroke risk weakened.Conclusions:NT-proBNP was significantly associated with an elevated stroke risk. Given, however, that the predictive power decreased with the number of years after NT-proBNP measurement, NT-proBNP should be re-evaluated periodically in Asian patients.
3 0 0 0 OA JPEG・MPEG標準化苦労話
- 著者
- 安田 浩
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.515-519, 1999-04-20 (Released:2011-03-14)
3 0 0 0 OA 国際会議開催報告
- 著者
- 小川 一人
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.207-208, 2018-01-01 (Released:2018-01-01)
3 0 0 0 OA ノリおよびその他の海藻中に放射性ルテニウムの存在について
- 著者
- 敦賀 花人
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.372-378, 1962-03-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 2
3 0 0 0 OA 公立文化施設の公共性をめぐって
- 著者
- 曽田 修司
- 出版者
- Japan Association for Cultural Economics
- 雑誌
- 文化経済学 (ISSN:13441442)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.47-55, 2007-03-31 (Released:2009-12-08)
- 参考文献数
- 31
公立文化施設は、従来アートの愛好家だけを対象としがちであり、公共財としてのアートという認識は一般的ではなかった。近年、ワークショップやアウトリーチなどの手法により、非愛好家に対してもアートの価値を目に見える形で提示する機会が増加している。これは、非愛好家を含む地域住民が地域文化形成への参加の保証を得ることにつながり、公立文化施設をめぐる異なる立場間の対立に「対話の可能性」をもたらすものと考えられる。
- 著者
- 湯浅 有希子
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集 第63回(2012) (ISSN:24241946)
- 巻号頁・発行日
- pp.83, 2012-08-22 (Released:2017-04-06)
3 0 0 0 OA 岡山県東部,超丹波帯ペルム系上月層中のデボン紀チャート層
- 著者
- 竹村 静夫 竹村 厚司 植野 輝 菅森 義晃 古谷 裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.2, pp.117-125, 2018-02-15 (Released:2018-05-30)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 2
中~後期ペルム紀に形成されたと考えられる超丹波帯上月層は,その一部にデボン紀のチャート層を含むことが判明した.このチャート層は玄武岩類とともに産し,磁鉄鉱の濃集層を頻繁に挟在する.磁鉄鉱濃集層を含むチャートからは,放散虫化石Holoeciscus foremanaeなどが産出し,その年代は後期デボン紀Fammenian期である.これは中国地方から産する化石として最も古い年代であるとともに,日本列島の付加体中に含まれる異地性岩体としては,東北地方の根田茂帯のチャートとならんで最も古いことを示す.
3 0 0 0 OA 開散麻痺が疑われた内斜視に対するプリズム治療
- 著者
- 今井 小百合 高崎 裕子 三浦 由紀子 渡辺 好政
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.145-151, 2004-07-31 (Released:2009-10-29)
- 参考文献数
- 7
目的:開散麻痺は中枢神経系の器質的病変によるものとされているが、単独でおこることも多く、臨床上同様な症状を示す他の疾患と鑑別することは難しい。治療は複視の解消を目的に行われる。我々視能訓練士は臨床上プリズムを使用する頻度は高い。そこで開散麻痺が疑われた内斜視症例に対し行ったプリズム治療について報告する。対象及び方法:対象は過去5年間に開散麻痺様の内斜視を示した初診時年齢39歳から83歳の6例。内科および神経学的検査を行った後、眼位、眼球運動、両眼視機能、融像幅の検査をプリズムあるいは大型弱視鏡、Hess Chartプロジェクタを用いて行った。プリズム度数は遠見時の両眼性複視が解消する最小のものを求めた。最終来院時にはプリズム眼鏡装用による日常生活での自覚的な改善について調査した。結果:開散麻痺が疑われた遠見内斜視により自覚する両眼性複視を解消するためにプリズム治療を行った結果、4例ではプリズムは不要あるいは減少となった。プリズム眼鏡装用により、複視は全例で解消され日常生活の自覚症状は改善された。結論:前駆症状に頭痛があった2例は、早期にプリズム治療を開始できたこともあり遠見内斜視による両眼性複視は解決した。プリズム使用前には、事前の十分な説明と患者の要望に沿った装用練習が必要である。これらを行うことで高齢者でもプリズム眼鏡装用が可能となった。プリズムは日常生活の自覚症状を改善し、複視を解消する選択肢の1つであると確認できた。
3 0 0 0 OA 頭部伝達関数の模擬によるヘッドホン再生音像の定位
- 著者
- 川浦 淳一 鈴木 陽一 浅野 太 曽根 敏夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.10, pp.756-766, 1989-10-01 (Released:2017-06-02)
- 被引用文献数
- 3
本論文では、ヘッドホン再生によってラウドスピーカ再生時の音場を模擬する手法について述べる。ヘッドホン再生条件と、ラウドスピーカ再生条件の比較から、頭部が静止している状態の静的な頭部伝達関数と、聴取者が頭部を動かすことによって生じる頭部伝達関数の動的な変化の2点について、ディジタル信号処理などの手法により補償を行った。静的な頭部伝達だけの補償によって、ヘッドホン再生によっても、頭外の水平面内任意方向への音像定位が実現できたが、正面付近のラウドスピーカを模擬した場合には前後の誤判定が増加する、頭内定位が起き易いなどの問題が生じた。静的な頭部伝達関数に加えて、伝達関数の動的な変化を模擬すると、前後の誤判定が減少し、頭内定位も減少するなど、より自然な音像定位が実現された。また、頭部回転に伴う動的な音源位置情報は、静的な伝達関数からの音源位置情報に比べて、少なくとも同程度の重みを持つものであることが示唆された。
3 0 0 0 OA 集会報告 2017年度 人工知能学会全国大会(第31回, JSAI 2017)
- 著者
- 清田 陽司
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.5, pp.350-353, 2017-08-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 3
3 0 0 0 OA 社会的不確実性のもとでの信頼とコミットメント
- 著者
- 山岸 俊男 渡部 幹 林 直保子 高橋 伸幸 山岸 みどり
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.206-216, 1996-03-30 (Released:2016-12-04)
- 被引用文献数
- 2
An experiment was conducted to test three hypotheses concerning effects of social uncertainty and general trust on commitment formation, hypotheses derived from Yamagishi & Yamagishi's (1994) theory of trust. First two hypotheses were supported, while the last one was not. First, increasing social uncertainty facilitated commitment formation. Second, low general trusters formed mutually committed relations more often than did high trusters. Finally, the prediction that the effect of general trust on commitment formation would be stronger in the high uncertainty condition than in the low uncertainty condition was not supported. Theoretical implications of these findings for the theory of trust advanced by Yamagishi and his associates are discussed.
3 0 0 0 OA 一般的信頼と依存度選択型囚人のジレンマ
- 著者
- 垣内 理希 山岸 俊男
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.212-221, 1997-03-31 (Released:2016-12-06)
This study examined the development of trusting relationships as investments in relation-specific assets. A new experimental game called "the dilemma of variable interdependency" was created based on iterated prisoner's dilemma game, in which subjects faced a choice of increasing or decreasing the level of dependency in addition to the usual choice between cooperation and defection. Results of the experiment confirmed the hypothesis that high-trusters (those who have a strong belief in human benevolence) would take a risk of making themselves vulnerable to exploitative behavior of the partner more strongly than low-trusters. This resulted in formation of mutually highly dependent relationships among high-trusters. It was further demonstrated that the subjects' levels of trust affect their cooperation levels when they were given an option to choose the level of dependence but not in the ordinary two-person, iterated PD.
3 0 0 0 OA 非固定的関係における信頼 : シグナルとしての信頼行動
- 著者
- 真島 理恵 山岸 俊男 松田 昌史
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.175-183, 2004-03-15 (Released:2017-01-13)
The purpose of this study was to examine the role of trust in relationships between temporary partners. In this study, we predicted that trust would play a "signaling" role in promoting mutual cooperation, even in relationships with unfixed or temporary partners. To examine this prediction, we conducted an experiment using two different games. We used the repeated PD/D (prisoner's dilemma with choice of dependence) game, which can measure trusting behavior independently from cooperation. Also, we used the ordinary PD game in which there is no option for trust. Seventy participants were assigned to either the PD/D condition or the ordinary PD condition. In both conditions, players interacted with a randomly matched partner in each trial. The results reveal that the cooperation rate in the PD/D game was significantly higher than that in the PD game. Such a finding indicates that trust serves as a signal of the player's intention, which in turn, promotes mutual cooperation. However, in a similar experiment in which players interacted with the same partner, Matsuda & Yamagishi (2001) found a much lower cooperation rate in the PD/D condition than what was found in this experiment. Therefore, we conclude that the role of trust in non-fixed relationships has only a limited effect for promoting mutual cooperation.
3 0 0 0 OA 2次的ジレンマ問題に対する集団応報戦略の効果 : コンピュータ・シミュレーション研究
- 著者
- 寺井 滋 山岸 俊男 渡部 幹
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.94-103, 2003-12-15 (Released:2017-01-13)
Using computer simulations, this study examined whether mutual cooperation can occur in social dilemmas characterized by the absence of a central authority. In the absence of a central authority, provision of a sanctioning system that administers selective incentives-a well referred solution to social dilemmas-constitutes a second-order social dilemma. The purpose of this study was to examine whether the generalized tit-for-tat (TFT) strategy, which is an extended version of tit-for-tat that is applied in n-person games, can help solve the second-order social dilemma. The results of computer simulations indicated that the second-order social dilemma could be resolved when group members adopt the Generalized TFT. Furthermore, it was demonstrated that the Generalized TFT strategy could survive and prosper in a population originally dominated by "probabilistic actors."
- 著者
- 丹羽 隆 篠田 康孝 鈴木 昭夫 大森 智史 太田 浩敏 深尾 亜由美 安田 満 北市 清幸 松浦 克彦 杉山 正 村上 啓雄 伊藤 善規
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.273-281, 2012-05-10 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1 15
Antimicrobial resistance in hospitals is increasingly becoming a major problem worldwide, thus appropriate use of antimicrobial agents should be promoted. Since August 2009, our hospital has established a review system for checking prescriptions in all patients receiving antimicrobial injections according to the intervention and feedback of antimicrobial stewardship (AMS) guideline. The antimicrobial use density (AUD), duration of administration, length of hospital stay, and antimicrobial resistance in a year were compared before and after starting the intervention into AMS. Suggestions made by members of the infection control team (ICT) to the prescribers were for the major part the choice and dose elevation of antimicrobials. Most of the proposals (91%) were accepted by the prescribers. Although AUD was not changed after AMS intervention, the proportion of prolonged antimicrobial use (over 2 weeks) was significantly reduced from 5.2% to 4.1% (p=0.007), which led to the saving of costs for antibiotics (4.48 million yen/ year). The incidence of MRSA tended to decrease after AMS intervention (p=0.074). The median length of hospital stay was ultimately shortened by 1.0 day (p=0.0005), which led to an estimated saving of medical costs by 520 million yen/year. We consider that our intervention profoundly affects this cost saving. These findings suggest that the extensive intervention into AMS is effective in reducing the frequency of inappropriate use of antimicrobials, suppressing the occurrence of antimicrobial resistance, and saving medical expenses.
3 0 0 0 OA 電子ジャーナル : 神話と真実
- 著者
- ウッドワード ヘーゼル ローランド フィトン マックナイト クリフ メドゥズ ジャック プリチェット キャロライン 尾城 孝一 細川 真紀 手塚 敬子 砂押 久雄
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.303-311, 1998-05-01 (Released:2017-05-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
電子ジャーナルに対するエンド・ユーザの反応の調査を目的としたCafe Jusプロジェクトのこれまでの調査結果について考察を加えた。電子ジャーナルへのアクセス, 雑誌の利用方法, ヒューマン・ファクター, 財政的問題, さらには, 電子出版の環境下における, 図書館員, 雑誌取次業者, 出版社のこれからの役割についても論じた。
3 0 0 0 OA 『情報管理』誌SGML編集システム
- 著者
- 森田 歌子 石黒 裕康 千葉 吉一
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.6, pp.445-459, 1998 (Released:2001-04-01)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 4 4
科学技術振興事業団では1996年3月にJICST―DTDおよびSGML文書作成プロトタイプシステムを開発した。また,『情報管理』誌では編集・印刷における作業量の軽減,期間短縮,経費節減と同時に,データの一元的利用,電子ジャーナル・全文DBの同時進行を目的として,『情報管理』誌SGML編集システムを開発した。本稿では,SGML文書処理システムの概要を紹介し,『情報管理』誌SGML編集システム開発のポイント,システムの機能,編集作業の流れ,編集・印刷工程の変化について述べる。
3 0 0 0 OA OCLCの電子ジャーナル (<特集>電子ジャーナルとネットパブリッシング)
- 著者
- 長塚 隆
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.7, pp.404-409, 1996-07-01 (Released:2017-05-25)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 2
インターネットなどの通信ネットワークを通じて提供される科学雑誌,電子ジャーナルが急速に増加している。OCLC (Online Computer Library Center)は, 1992年10月に,電子ジャーナルのオンラインサービスであるElectronic Journals Onlineを開始した。Electronic Journals Online はOCLCが開発した専用の通信・検索ソフトGuidonと汎用のWWWブラウザーで、近々予定のものを含め12タイトル(複数の対応印刷物を持つものがあるので印刷物では50タイトル)が利用できる。印刷体のない最初の本格的な電子ジャーナルである臨床医学分野の科学雑誌The Online Journal of Current Clinical Trials (OJCCT)の構成の特徴と,専用の通信・検索ソフトGuidonでの利用方法について説明した。さらに,専用の通信・検索ソフトGuidonと汎用のWWWブラウザーでの検索や文献の表示機能などについて比較したところ,現状では文献の表示機能などGuidonのほうが優れている点が多いといえる。