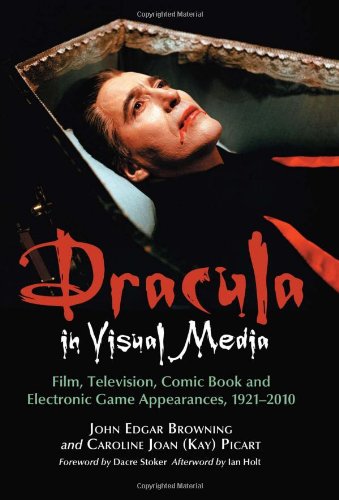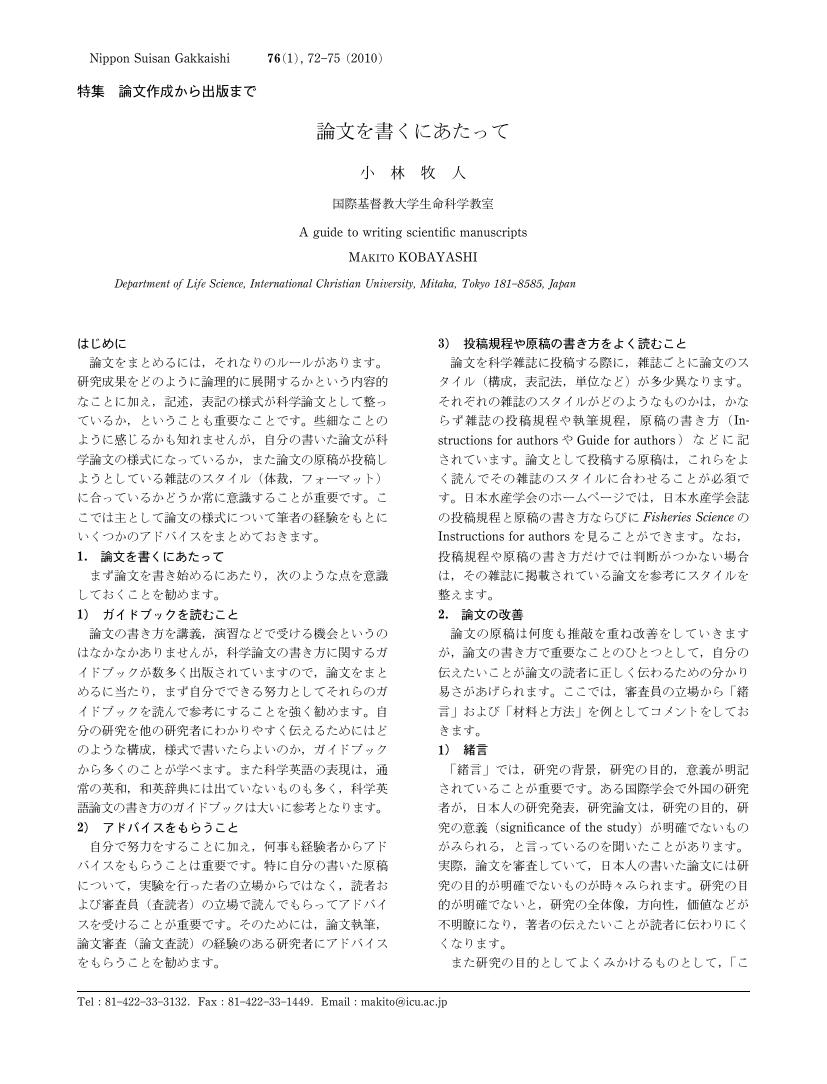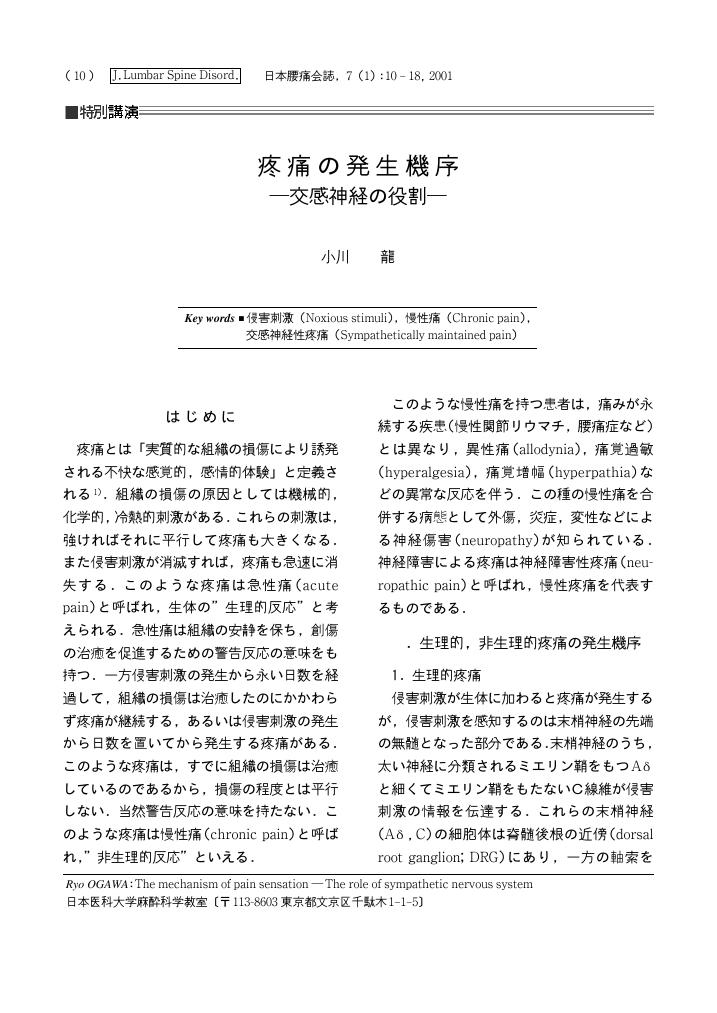6 0 0 0 IR 日本におけるミュージックビデオの展開 : テレビメディアの共起と別離
- 著者
- 塚田 修一
- 出版者
- 相模女子大学
- 雑誌
- メディア情報研究 : Journal of information and medelia studies (ISSN:21888019)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.21-32, 2021-03
6 0 0 0 OA 通知発出により現場は変わったか?問題は何か?
- 著者
- 河野 太郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本レーザー医学会
- 雑誌
- 日本レーザー医学会誌 (ISSN:02886200)
- 巻号頁・発行日
- pp.jslsm-40_0064, (Released:2019-12-14)
- 参考文献数
- 1
現在の皮膚科形成外科領域のレーザー治療における未承認機器の占める割合は少なくない.デバイスラグが問題の一つであるが,中にはFDAでの許認可のみならず,CEマークさえ取得していない機器が臨床研究を経ることなく使用されている現状がある.医学的に正しい機器が早期に承認されることは望ましいことであるが,本邦のように,科学的根拠の乏しい機器でも医師の裁量権で使用可能となっている現状に問題がないとは言い切れない.医師の倫理観のみでなく,美容領域のガイドラインの作成,合併症や事故情報の集積等学会ができることを粛々と進める必要がある.
6 0 0 0 OA オスマン朝下レバノン山地特別県における宗派別土地調査と地域支配の再編
- 著者
- 田中 雅人
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho (ISSN:03869067)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.4, pp.01-032, 2021-03-15
In 1861, the Ottoman Government established a special district in Mount Lebanon, which embodied the principle of proportionate-sectarian representation as opposed to the conventional mode of rule by the local Druze lords. However, the details of the complex process of reintegrating the autonomous local ruler into the new regime remain uncertain, and need to be closely reexamined. Overdue discussion of the sectarian land survey of 1862 to 1869 thus offers excellent insights into this question. The communal conflict of 1841–60, being the crucial background for the new administration in Mount Lebanon, broke out as the tension between the local Druze lords and the Maronite clergy-led peasants peaked following a proclamation to abolish tax-farming in the Ottoman State. The debates of the representatives of the Ottoman Government and the Five European Powers who interfered in the conflict reveals that they saw the establishing of a new order in Mount Lebanon as entailing the separation of the Druze and Maronite sects. To achieve this, the Government and the European Powers deemed the individualization of land ownership as a prerequisite since they understood that the existing unequal share of land revenue between the two sects was the main reason for the unrest. Analysis of the locally preserved land records of the sectarian mixed village in the Shūf sub-district shows that although the calculation and assessment of the land revenue relied on native methods, every land plot and its revenues in the village are listed by sect (Druze, Maronite, and Greek-Catholic), and are recorded under the names of the proprietors. However, the fact that the land tax remained to be collected in each village en bloc indicates the incomplete individualization of property rights. Nevertheless, the unification of tax collection to each village signifies that they became independent administrative units, and it was a pragmatic measure to retract the hereditary rights of powerful local lords as tax-farmers. This point is particularly evident in the successive failures of the earlier efforts of land surveys in the 1840s, which attempted to register each property individually. Therefore, by designating each village a sole collector of the land tax, and allocating the burden by sect, the sectarian land survey dismantled the established rule of the local lords under the tax-farming system and envisaged an independent sectarian entity in return for taxation. It was at this point that even the Druze notables, who had claimed their ancestral right during the conflict of 1841–60, readily applied sectarian language to their political discourse.
6 0 0 0 西洋古典学におけるジェンダー研究--その歴史と展望(2)
- 著者
- 西村 賀子
- 出版者
- 和歌山県立医科大学保健看護学部
- 雑誌
- 和歌山県立医科大学保健看護学部紀要 (ISSN:18801366)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.1-8, 2008
6 0 0 0 OA 北伊豆地震 (1930年) による丹那トンネル内地震断層出現状況記録
- 著者
- 櫻井 孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用地質学会
- 雑誌
- 応用地質 (ISSN:02867737)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.6, pp.540-544, 1999-02-10 (Released:2010-02-23)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 5
6 0 0 0 OA 科学哲学の現代的課題
- 著者
- 横山 輝雄
- 出版者
- 科学・技術研究会
- 雑誌
- 科学・技術研究 (ISSN:21864942)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.5-14, 2018 (Released:2018-07-05)
「科学哲学」という日本語は、一般には「科学についての哲学的考察」として「科学とは何か」「科学の意義」などを論ずるものと思われているが、実際には英語のphilosophy of science にあたる狭く限定されたものであり、そうした問題を扱わない。「科学哲学」に一般に期待されている内容は、科学史、科学社会学、科学技術社会論などの「科学論」(science studies)と呼ばれている分野で議論されてきた。それらの成果を概括して「科学と技術」「科学と倫理」「科学と宗教」などの問題を扱う科学哲学が現在求められている。
6 0 0 0 OA 新規性ポテンシャルと単語分散表現モデルに基づく特許情報からの設計概念生成
- 著者
- 橘 智也 正田 浩暉 Aiza Syamimi Binti Abd Rani 野間口 大 岡本 和也 藤田 喜久雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-00222, (Released:2022-01-07)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
Generating novel design concepts in the conceptual design phase is a cornerstone for producing innovative products. This paper proposes a method to support the generation of new design concepts from patent documents. The proposed method is based on the theory of novelty potential that the combination of abstract concepts leads to the generation of the novel design concept and that the distance between the combined abstract concepts correlates to the possibility of generating it. This research adopts the distributed word representation model of word2vec to extract abstract concepts from patent documents and to measure the concept distance. The two matrices are introduced to visualize the relationships of the extracted abstract concepts; the novelty potential matrix which shows the value of the novelty potential between the abstract concepts, and the void matrix which shows the numbers of existing patents of the abstract concepts. They help a designer to identify the combinations of abstract concepts that are high novelty potential and no existing patent. This paper demonstrates a case study of generating novel ideas of sports business with blockchain using the proposed method. The results show its uniqueness and effectiveness.
6 0 0 0 OA 入試区分による入学後の学業成績の優劣の検証
- 著者
- 池田 文人
- 出版者
- 国立大学入学者選抜研究連絡協議会
- 雑誌
- 大学入試研究ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.95-99, 2009
AO入学者の学力不足を理由に,AO入試の撤廃を含む見直しが各大学ではじまった。本研究では,北海道大学が2005年度から導入したGrade Point Average(GPA) を用いて,2005年度入学者を対象に,AO入学者の学業成績が,一般選抜による入学者に比べて劣るかどうかを検証した。この結果,AO入学者の学業成績は他の入学者に比べて劣っているという確証は得られなかった。今後は,2005年度より前の学業成績を含め,より多くのデータを対象に分析を行って統計的な精度を高める必要がある。また,AO入学者が本来その入試によって求められている資質や適性を評価できる指標を開発する一方で,GPAに基づく学力の分析を継続し,資質や適性が発揮されるまでの学業の支援体制を検討していく必要がある。
6 0 0 0 IR 小幡甚三郎のアメリカ留学 : 福澤研究センター所蔵資料紹介
- 著者
- 西澤 直子
- 出版者
- 慶應義塾福澤研究センター
- 雑誌
- 近代日本研究 (ISSN:09114181)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.143-163, 1997
資料一 はじめに二 小幡甚三郎関係資料の詳細と成立経緯三 小幡甚三郎の履歴四 アメリカ留学五 おわりに : 小幡兄弟への期待
6 0 0 0 OA 高松都市圏における地方鉄道経営再建に関する事例研究†
- 著者
- 浅見 均 小美野 智紀
- 出版者
- 日本地域学会
- 雑誌
- 地域学研究 (ISSN:02876256)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.225-237, 2015 (Released:2016-02-25)
- 参考文献数
- 23
Railways, including local railways, serve as a form of public transport, and public transport is a constituent element of social infrastructure that helps support the lives of passengers. While it can be said that railways exist for the sake of their passengers, the converse is not true. Sound railway management cannot be readily sustained without a considerable number of passengers. With Japan now facing a downturn in total population, ensuring a sufficient pool of potential passengers within station territories has become a significant business challenge for local railway lines in particular. Ensuring sufficient populations within station territories is a nearly impossible task for a railway business, necessitating some form of outside assistance. Following the abolition of supply-demand adjustment regulations in 2000, recent years have seen an increasing number of local railway companies undergo transfers of management, making case studies on management revitalization of local railway companies of substantial social importance. This case study focuses on management revitalization of the Takamatsu-Kotohira Electric Railroad (Kotoden) in the Takamatsu urban area by employing the following analysis techniques: 1) Factor analysis of Kotoden’s successful management revitalization and comparisons with the findings of case studies on the Kishigawa Line 2) Detailed GIS (Geographic Information System) based analysis of changes in the populations of station territories along Kotoden lines 3) Analysis of the relationships between Kotoden’s successful management revitalization and urban planning 4) Comparative analysis with other urban areas The authors are convinced that the findings of this case study offer valuable information on successful management revitalization of local railways, given that success in this instance can be attributed to the fact that Kotoden’s management revitalization was authorized in recognition of its value as a public transport provider in the context of urban planning for the Takamatsu urban area. This case study was also able to show the utility and importance of analyzing population changes in station territories using GIS (100 m mesh population data). This research further demonstrated that tripartite management by local governments along the Kotoden railway lines, residents living along these lines (passengers), and the railway company itself are all major factors in the success of the management revitalization undertaken by this local railway company.JEL Classifications:O18, R14, R42
6 0 0 0 OA 津波による大気ラム波の励起についての理論的考察
- 著者
- 中島 健介
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2018年大会
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-14
はじめに大規模な津波は大気Lamb波を励起することが知られており(Arai et al 2011; Mikumo et al 2008 など), グローバルな微気圧計観測網から海面変位を推定することも行われている. 過去のその様な手法において, 津波の波源域での圧力偏差 p は津波に伴う海面鉛直速度 w を用いて p=ρ c w (cは音速)と与えられている. この関係は, 通常の音波を想定しており, 内部重力波, 重力の影響を強く受ける音波, そして Lamb 波の場合の適切さには疑問がある.実際, Watada (2009)は等温大気について, 下面境界に鉛直速度を与えて圧力応答を波数・周波数空間において調べ, 音波, 内部重力波,Lamb 波の分散関係に対応して顕著な違いがあることを示した. 対応して実空間での応答の調査が望まれるが, 過去には現実的な断層運 動を想定した計算が行われており(たとえば泉宮・長岡,1994) 理論的な理解には必ずしも繋がっていない. そこで本研究では理想的な状況を想定して津波による大気波動の励起を調べる.考察する系と数値モデル線形化した水平鉛直2次元の等温大気の方程式を,下面に与える鉛直流により駆動し, 応答を調べる.計算領域は, 水平2000km, 鉛直 100km であり,上端 20km はスポンジ層とする. 下端の鉛直流は2種類のものを想定する. 第一は, 時間空間的にガウス分布のパルスであり, 地震断層変位に対応する海面盛り上がりを想定する. 時定数は, 通常の地震から津波地震までを想定して 10秒から300秒までのパラメタ実験を行なう. 第二は, 水平にガウス分布の海面変位を左右に動かすものであり, 津波の水平伝播を想定する. 伝播速度は, 典型的な水深における津波伝播速度を想定して25m/sから 300m/s の範囲でパラメタ実験を行う. 方程式の離散化には spmodel(竹広ほか2013)を用いた.結果海面の盛り上がりで生じる圧力偏差は音速で水平に伝わるLamb波によって支配されるが, その波形は, 海面盛り上がりの時定数にほとんどよらないことがわかった. 振幅は, 海面の盛り上がりに対応して大気が static に鉛直変位することを想定して見積もることができる(詳細は当日)。伝播する津波から生じる応答としては、津波とともに伝わる強制波動(通常は内部重力波)に加えて, 音速で水平に伝わるLamb波が生じることがわかった. この成分の振幅は概ね津波伝播速度の2乗に比例し, 典型的なパラメタでは, 海面盛り上がりによる成分の半分程度の大きさとなる.理論的考察以上の結果は、鉛直流擾乱を持たない Lamb 波が大気下端での鉛直運動で励起されることを示す。このような必ずしも自明でない結果について、当日、理論的議論を行う。参考文献Arai et al (2011): Geophys. Res. Lett. doi:10.1029/2011GL049146Mikumo et al (2008): J. Geophys. Res. doi:10.1029/2008JB005710Watada(2009): J. Fluid. Mech. doi:10.1017/S0022112009005953泉宮・長岡(1994): 海岸工学論文集, Vol.41, p.241.
6 0 0 0 OA 論文を書くにあたって
- 著者
- 小林 牧人
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.72-75, 2010 (Released:2010-05-13)
6 0 0 0 OA 疼痛の発生機序─交感神経の役割─
- 著者
- 小川 龍
- 出版者
- 日本腰痛学会
- 雑誌
- 日本腰痛学会雑誌 (ISSN:13459074)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.10-18, 2001 (Released:2008-07-10)
- 参考文献数
- 6
6 0 0 0 OA 占領初期のPHWの児童福祉政策構想 : 厚生省児童局の設置過程を通して
- 著者
- 岩永 公成
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.1-10, 2002-03-31 (Released:2018-07-20)
これまで,占領期児童福祉政策に深く関与したPHW(公衆衛生福祉局,GHQ)の政策構想は不分明なままであった。そこで,本稿は,厚生省児童局の設置過程を手がかりに,PHWの政策構想の解明を課題として設定した。検討の結果,次の2点が明らかになった。第1に,PHWは「児童保護活動を行ううえで,最も障害なのは日本人の児童問題に対する無関心である」とみなしていた。したがって,占領初期,PHWは「関心を喚起し,重要性を認識させること」に腐心した。通達の作成や児童局設置の推進,女性局長の提案などは,その証左である。第2に,PHWは浮浪児問題に関与し始めた頃から,「対象児童の一般化」と「関係機関の連携」という重要な政策理念を有していた。これらの政策理念は,児童局に普通児童を対象とする企画課が設置されたこと,学校保健問題にかかわる連絡調整委員会が設置されたことからわかるように,厚生省児童局の設置により一応結実した。