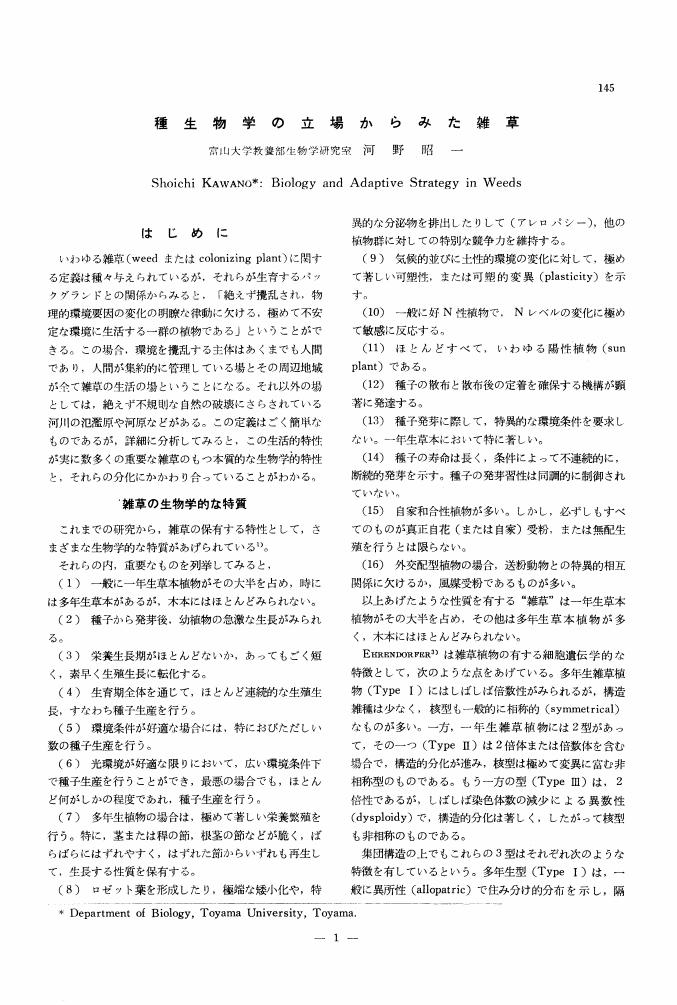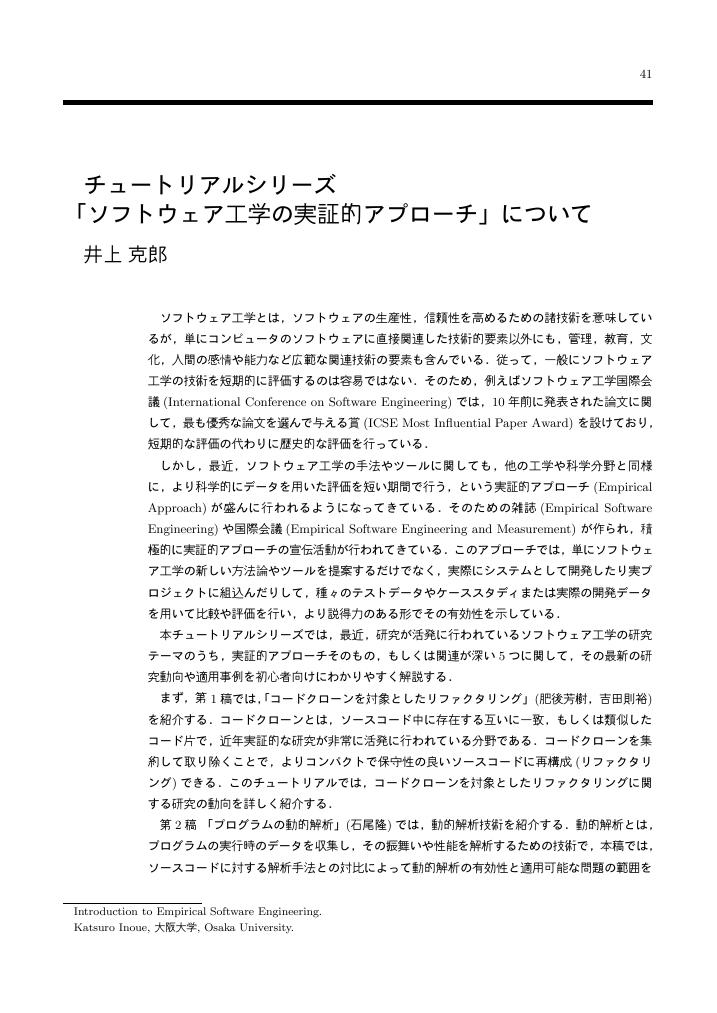3 0 0 0 OA 頭痛
- 著者
- 稲福 徹也
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.43-46, 2013 (Released:2013-05-02)
- 参考文献数
- 6
要 旨 頭痛診療において初めて経験する頭痛については, 生命に危険が及ぶくも膜下出血と細菌性髄膜炎を見逃さず適切なタイミングで専門医へ紹介することが大事である. 一方同じような頭痛を繰り返す慢性頭痛については, 日常生活に支障をきたす片頭痛をきちんと診断して適切にマネージメントすることが大事である. いずれの場合も頭痛の診断には病歴聴取が最も重要であることは言うまでもない.
3 0 0 0 OA 入浴習慣と要介護認定者数に関する5年間の前向きコホート研究
- 著者
- 日本温泉気候物理医学会温泉療法医会
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.3, pp.200-206, 2011 (Released:2012-12-07)
- 参考文献数
- 6
- 著者
- Akihito Konishi Yasukazu Hirao Kouzou Matsumoto Hiroyuki Kurata Takashi Kubo
- 出版者
- The Chemical Society of Japan
- 雑誌
- Chemistry Letters (ISSN:03667022)
- 巻号頁・発行日
- pp.130153, (Released:2013-05-18)
- 被引用文献数
- 52
The improved Scholl reaction allows for the direct cyclization of anthracene oligomers to give bisanthene, teranthene, and quarteranthene. Furthermore, a variety of π-expanded bisanthenes are obtained by the Diels–Alder cycloaddition of bisanthene with several arynes. These reactions would allow us to synthesize various size- and shape-controlled polyperiacenes.
3 0 0 0 OA 種生物学の立場からみた雑草
3 0 0 0 OA オイルショック後の日本における少年の殺人発生率と完全失業率の長期的関連とその構造変化
- 著者
- 遊間 義一 金澤 雄一郎 遊間 千秋
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.149-168, 2012 (Released:2013-03-18)
- 参考文献数
- 39
本研究は,遊間・金澤・遊間(2010)に2年分のデータを追加して1974年から2008年までの,日本全国で起きた少年による殺人事件の発生率に対する完全失業率の効果及びその構造変化の有無を共和分回帰及び誤差修正モデルを用いて検証したものである.その結果,遊間・金澤・遊間では,見いだせなかった構造変化が,年長少年(18・19歳)において確認された.つまり,年長少年においては,完全失業率が上昇(下降)すれば殺人発生率も上昇(下降)するという正の関係が認められ,この効果の強さは調査期間を通じて変化がなかったものの,殺人発生率は2000年を境に急激に減少する傾向が認められた.他方,中間少年(16・17歳)では,遊間・金澤・遊間とほぼ同様の結果が得られており,完全失業率と殺人発生率との間に正の関係が認められたが,構造変化は見いだせなかった.年長少年の急激な減少について,1998年以降急増した自殺率や1990年代後半からの犯罪や少年非行への厳罰化傾向との関連から考察した.
3 0 0 0 OA 非虚血性拡張型心筋症に対する新しい左室縮小形成術(Overlapping法)の麻酔経験
- 著者
- 高橋 栄美 硲 光司 新谷 知久 本間 英司 深田 靖久 松居 喜郎
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.7, pp.257-262, 2004 (Released:2005-05-27)
- 参考文献数
- 11
心不全末期の拡張心に対する新しい左室縮小形成術(Overlapping cardiac volume reduction operation ; OLCVR, 松居法)10症例の麻酔を経験した. 低濃度のセボフルランと静脈麻酔で行った. 体外循環離脱時には経食道心エコーで左室壁運動や容積の変化を観察しながら, 適切な前負荷を保つことと後負荷の軽減に重点を置き, カテコラミンおよび血管拡張薬の使用法に留意することが重要である.
3 0 0 0 OA 意味ベクトルによる画像検索
- 著者
- 田中 理恵子 芥子 育雄 池内 洋
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.579-585, 1994-10-01 (Released:2008-05-30)
- 参考文献数
- 7
従来のキーワード検索では, キーワードを思い出せないと検索できない, 検索結果を順位付けすることができないなどの問題があった。これらの問題を解決し, キーワード1個からでも連想検索ができる検索手法として意味ベクトルによる連想検索技術を開発中である。この技術を画像検索へ応用した画像データベースを試作した。風景写真など約170枚の画像と, それぞれに付与した説明文からなる画像データベースを構築し, 意味ベクトルを用いた検索を行ったところ, 素人によって数語程度の説明文をつけただけでも, かなりの検索ができることがわかった。
- 著者
- Celik Ozlem Buyuktas Deram Sevinc Mustafa Tascilar Koray Demirkesen Cuyan Tasan Ertugrul
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.18, pp.1973-1976, 2011 (Released:2011-09-15)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 6 8
Propylthiouracil (PTU) is an antithyroid drug which is known to cause drug-induced vasculitis. PTU is implicated in 80-90% of cases of anti-neutrophil cytoplasm circulating antibody (ANCA)-associated vasculitis caused by anti-thyroid drugs which induce ANCA production. Sweet's syndrome is characterized by fever, leucocytosis, neutrophilia and the sudden onset of painful skin lesions. The pathology of the disease is still unclear. Cytokine dysregulation including interleukin-6 and endogenous granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) are thought to play a role in the pathogenesis of Sweet's syndrome. PTU and G-CSF are known to cause Sweet's syndrome and other neutrophilic dermatosis. The presence of ANCA can have a diagnostic value in Sweet's syndrome. Systemic corticosteroids are the first-line therapy for both diseases. Here we report a female patient with Graves' disease who developed ANCA and Sweet's syndrome after using PTU and G-CSF.
- 著者
- Kuzuhara Shigeki
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.11, pp.968-971, 2009 (Released:2009-12-28)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 2
The first medical society of Japanese neurologists and psychiatrists was founded in 1902, but psychiatrists gradually dominated in number. New "Japanese Society of Neurology" (JSN) was founded in 1960. The number of members was only 643 in 1960, while it rose up to 8,555 in 2009, including regular, junior, senior and associate members. JSN contributed much to solve the causes and treatment of the medicosocial and iatrogenic diseases such as Minamata disease and SMON (subacute myelopticoneuropathy) at its early period. In undergraduate education at medical school, neurology is one of the core subjects in the curriculum, and almost all the 80 medical schools have at least one faculty neurologist. The Board of neurology of JSN was started in 1975, as the third earliest of the Japanese Medical Associations. It takes at least 6 years' clinical training after graduating from the medical school to take the neurology Board examinations. By 2009, 4,000 members passed the Board examinations. In 2002 JSN published evidence-based "Treatment Guidelines 2002" of 6 diseases: Parkinson's disease, stroke, chronic headache, dementia and ALS. As to the international issues, JSN hosted the 12th World Congress of Neurology in 1981, and international activities markedly increased after that. The first informal meeting with JSN and Korean Neurological Association (KNA) was held at the 48th JSN Annual Meeting in Nagoya in May 2007. In May 2008 the KNA-JSN 1st Joint symposium was held at the 49th Annual Meeting of JSN in Yokohama on "International comparison of neurological disorders: focusing on spinocerebellar atrophies (SCA) and epilepsies". In May 2009, KNA-JNS 2nd Joint Symposium was held at the 50th JSN Annual Meeting in Sendai, inviting a speaker from Taiwan Neurological Society, on the subject "History and Education of Neurology in Japan, Korea and Taiwan". In this symposium, a strategy to make up the Northeast Asian Neurological Association was discussed.
3 0 0 0 2種のM成分を伴えるリンパ肉腫の1例
- 著者
- 浜中 保三 前田 省吾 赤岩 道夫 岸川 央 沢江 義郎 冨永 喜久男
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.8, pp.898-903, 1974 (Released:2008-10-31)
- 参考文献数
- 8
A 29 years old male patient of Lymphosarcoma with two kinds of M-Components has been described.The patient had been admitted to Shin Kokura Hospital because of lymphadenopathy of cervical, axillar and inguinal area. Biopsy of the cervical lymph node has revealed the histological finding of Lymphosarcoma.During the course of therapy with corticosteroid hormone and cyclophosphamide, two kinds of M-components had appeared in the patient's serum, and had been identified as IgG·κ and IgM·κ by immunoelectrophoresis.Serum concentration of the patient's immunoglobulin had increased three times for IgG and approximately ten times for IgM by antibody agar plate method.In ultracentrifugal analysis, however, there had been no increase of 19S component although 7S component had shown remarkable increase.The dyscrepancy between immunological measurement and ultracentrifugal analysis has been explained by the appearance of IgM with smaller molecular size than usual 19S-IgM. After clinical course of some thirty days the IgM concentration had come down to normal range accompanying the disappearance of monoclonal IgM in immunoelectrophoresis.The mechanism of the appearance of the two kinds of M-components, one of which was transient, has been discussed.
3 0 0 0 OA 日本海沖合漁場におけるイカ釣り漁業用青色 LED 漁灯の性能評価
- 著者
- 四方 崇文 山下 邦治 白田 光司 町田 洋一
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.6, pp.1104-1111, 2012 (Released:2012-11-28)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 4 7
調査船に LED 灯を装備してスルメイカを対象にしたイカ釣り操業を行った。メタルハライド(MH)灯 78 灯による操業を基準に比較したところ,LED 灯単用操業では漁獲量は大きく減少したが,LED 灯 216 灯と MH 灯 24 灯の併用操業では漁獲量の減少が小さく,漁灯点灯のための燃油消費は大幅に減少した。以上より,両灯を併用することで漁獲量をある程度維持しつつ燃油節減できることが分かった。MH 灯に比べて LED 灯は船体近くの限られた範囲にのみ光を放射しており,配光の違いが漁獲性能を左右すると考えられた。
- 著者
- Florian Quadt André Düsterhus Heinke Höck Michael Lautenschlager Andreas V. Hense Andreas N. Hense Martin Dames
- 出版者
- CODATA
- 雑誌
- Data Science Journal (ISSN:16831470)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.89-109, 2012 (Released:2012-11-09)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 4
In a research project funded by the German Research Foundation, meteorologists, data publication experts, and computer scientists optimised the publication process of meteorological data and developed software that supports metadata review. The project group placed particular emphasis on scientific and technical quality assurance of primary data and metadata. At the end, the software automatically registers a Digital Object Identifier at DataCite. The software has been successfully integrated into the infrastructure of the World Data Center for Climate, but a key objective was to make the results applicable to data publication processes in other sciences as well.
3 0 0 0 OA 淡路島北部における活断層の活動度の再評価
- 著者
- 吾妻 崇
- 出版者
- 日本第四紀学会
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.29-42, 1997-02-28 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 2
淡路島北部の活断層について,空中写真(縮尺約1/10,000)の判読に基づき,変位地形の記載および活動度の再評価を行った.写真判読の結果,釜口断層と蟇浦断層を新たに認め,各断層において低断層崖や水系の屈曲がみられることを明らかにした.また,当地域の活断層を3つの断層系(淡路島東縁断層系・西縁断層系・横断断層系)に分類した.楠本断層と野田尾断層では,山麓線より平野側に低断層崖が存在する.1995年以前には野島断層に沿ってそのような低断層崖はみられず,1995年以前の活動(約2,000年前)により形成された低断層崖は侵食され消失したと考えられる.断層の活動度は,断層を横切る水系の屈曲量(D,単位m)と断層よりも上流の長さ(L,単位m)を楠本・東浦・野田尾・釜口・野島断層について調べ,関係式D=aL(松田,1975)のaの値から評価した.その結果,東縁断層系では楠本断層よりも東浦断層の方が活動度が大きいこと,西縁の野島断層の活動度は東浦断層に匹敵することが明らかになった.今回新たに認められた釜口断層bは逆向き低断層崖と考えられ,東側の海底には逆断層の存在が推定される.淡路島横断断層系では,横ずれ変位地形は認められず,西縁断層系の隆起側花崗岩類ブロックの移動に関係した逆断層的な変形が段丘面にみられる.
3 0 0 0 OA 緩和ケア病棟に対する認識調査―入院患者とその家族の視点の検討
- 著者
- 黒田 佑次郎 岩満 優美 轟 慶子 石黒 理加 延藤 麻子 松原 芽衣 岡崎 賀美 山田 祐司 宮岡 等
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.306-313, 2012 (Released:2012-03-02)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
【目的】緩和ケア病棟(以下, PCU)入院中の患者とその家族を対象に, 入院前後のPCUに対する認識と印象の変化を質的に検討した. 【方法】PCUの入院患者5名と家族9名に半構造化面接を実施し, 要約的内容分析を行った. 【結果】入院前の印象は, 患者では“想像がつかない”など「特に印象がない」を含む2カテゴリー, 家族では“最期を迎えるところ”や“穏やかに過ごす場所”など「PCUの環境」を含む5カテゴリーが得られた. 入院後の印象は, 患者では“心のケアが重要”など「PCUでのケア」を含む3カテゴリー, 家族では“個室でプライベートがある”など「PCUの環境」を含む7カテゴリーが得られた. 【結論】PCU入転院に際し, 家族は“安心が得られる”と“最期を迎えるところ”という気持ちが併存していることが示された. また, 入転院前に比し入転院後は, 患者と家族ともにPCUに対して好意的な印象をもっている可能性が示唆された.
3 0 0 0 OA わが国における赤米栽培の歴史と最近の研究情勢
- 著者
- 猪谷 富雄 小川 正巳
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物学会紀事 (ISSN:00111848)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.137-147, 2004 (Released:2004-09-29)
- 参考文献数
- 110
- 被引用文献数
- 14 26
赤米とは, 糠層にタンニン系赤色色素を持つイネの種類であり, わが国においては日本型とインド型の2種の赤米が栽培されてきた. 日本型の赤米は古くから日本に渡来し, 7~8世紀には全国各地で栽培されたことが平城京跡などから出土する木簡から推測されている. 14~15世紀には中国からインド型の赤米もわが国へ渡来し, 「大唐米」などと呼ばれ, 近世に至るまでかなりの規模で栽培されていた. 早熟で不良環境や病害虫に強い大唐米は, 最盛期の江戸時代には関東から北陸地方以西において広く栽培され, 特に低湿地や新たに開発された新田などに適していた. 明治時代に入るとこれらの赤米は徐々に駆除され, わが国の水田から姿を消す道を辿った. 例外として, 日本型の赤米の一部が神聖視され, 神社の神田などで連綿と栽培されてきたもの, 雑草化して栽培品種に混生してきたものなどがある. 約20年前から, 赤米は小規模ながら栽培が復活し, 日本各地で歴史や環境を考える教育や地域起こしの素材として利用されている. また, 赤米は抗酸化活性を持つポリフェノールを含む機能性食品としても注目されている. わが国における赤米栽培の歴史と赤米を取り巻く最近の研究状況などについて, 以下の順に概要を述べる. (1)赤米を含む有色米の定義と分類, (2)赤米の赤色系色素, (3)赤米の栽培の歴史, (4)残存した赤米, (5)赤米など有色米が有する新機能, (6)赤米の育種などに関する最近の情勢.
3 0 0 0 OA 「日本各地域におけるシカ管理の現状」,千葉県におけるニホンジカの保護管理の現状
3 0 0 0 OA チュートリアルシリーズ「ソフトウェア工学の実証的アプローチ」について
- 著者
- 井上 克郎
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.4_41-4_42, 2011-10-25 (Released:2011-12-25)
3 0 0 0 OA 日本語版リーディングスパンテストにおける方略利用の個人差
- 著者
- 遠藤 香織 苧阪 満里子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.6, pp.554-559, 2012 (Released:2012-08-18)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 4 7
Working memory is a system for processing and storing information. The Reading Span Test (RST), developed by Daneman and Carpenter (1980), is well-known for assessing individual difference in working memory. In the present investigation, we used the Japanese version of the RST (Osaka, 2002) and analyzed individual differences in strategy use from the viewpoint of strategy type (rehearsal, chaining, word-image, scene-image, and initial letter) and frequency of use (used in almost all trials, in half the trials, or not used). Data from the participants (N = 132) were assigned to groups according to the scores, for the total number of words correctly recalled and the proportion correct. The results showed that the frequency of word-image strategy use differed significantly between high-scoring subjects (HSS) and low-scoring subjects (LSS). HSS mainly used word-image and chaining strategies, while LSS used rehearsal and chaining strategies. This indicates that HSS used both verbal and visual strategies, whereas LSS relied only on verbal strategies. The use of the word-image is important for effective retention of words in memory.
3 0 0 0 OA ドーピング防止薬剤師がそなえる薬理学的知識
- 著者
- 笠師 久美子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.137, no.2, pp.65-67, 2011 (Released:2011-02-10)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2
本来,スポーツは健全な心身のもとに競技が行われるべきであるが,薬物等の誤用や濫用による「ドーピング」が社会問題にまで発展している.これは一部の作為的な行為によるものばかりではなく,医薬品やドーピングに関する知識不足による使用も多く含み,結果的に同様の制裁を受けるのが現状となっている.2007年にドーピング防止ガイドラインが文部科学省により策定され,薬剤師も積極的にドーピング防止活動に努めることが明記された.ドーピング撲滅のために薬剤師が介入できる事項としては,薬に関する教育や相談応需,医薬品情報の提供,禁止物質の治療目的使用に係る除外措置(TUE)に関する支援などがあげられる.薬剤師の職務である適正な薬物療法と安全性の担保は,スポーツにおいても求められるところである.そのためには,従来薬剤師が医薬品として理解している「薬物」に加え,ドーピング効果を期待する「薬物」としての情報が求められる.
3 0 0 0 OA 薬剤師のためのドーピング防止リファレンス
- 著者
- 笠師 久美子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.12, pp.1475-1481, 2009 (Released:2009-12-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2 5
In recent years, appropriate medication and guarantees of safety are being sought not only by medical circles but also by the world of sport. Under normal circumstances, sport should be wholesome in both mind and body, but “doping” by the misuse and abuse of drugs and such is developing into a social issue. This is not just a result of the deliberate behavior of a certain number of people; many cases include use due to a lack of knowledge of drugs and doping, although eventually the sanctions received are the same. Doping tends to be perceived as the problem of just a section of elite athletes, but since the introduction of doping control at the National Athletic Meet 2003, anti-doping measures continue to be a problem close at hand. In 2004, the World Anti-Doping Code came into effect and subsequently not just the world of sport but various national governments became deeply involved with anti-doping. Anti-doping guidelines in Japan were formulated by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in 2007, stipulating that doctors and pharmacists should be proactive in anti-doping activities. With the aim of eradicating doping, it was deemed that pharmacists can intervene by providing support regarding such issues as drug enlightenment, consultation; the supply of drug information; database production; and therapeutic use exemption. It can be considered that pharmacists can sufficiently use their knowledge and experience gained in these fields, and that such knowledge could lead to more appropriate drug use in sport.